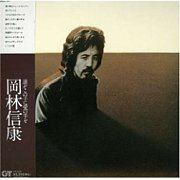伝説の人である。かつて“フォークの神様”と呼ばれたこともあった。しかし、話をうかがっていると、“神格化”されたところなど微塵も感じられないし、感じさせもしない。むしろ強さや弱さを包み隠さず、あけっぴろげに見せてしまえる無邪気な、あまりにも人間くさいたたずまいが随所に見え隠れする。
そんな岡林信康の60年代後半から70年代前半にかけての初期作品が、ディスクユニオンの富士レーベルから8月以降、次々と復刻され、若い世代の間で俄かに岡林信康ブームが起こりつつある。11月24日には、第2弾発売を記念したインストア・ライヴもタワーレコード渋谷店で行なわれるなど、周辺がなにやら騒がしくなってきた。
ああいうロックの編成でライヴをやったのは25年ぶりぐらい。僕はステージ・ネームはないし、本名で歌ってきたけど、生まれて初めて演じたんよ。エレキ・ギターで歌ってたころの自分をね。こういう歌い方があんのやね、っていう楽しさを初めて知った感じ。芸名で歌っている人っていうのは、ステージに出たときに別人になるのかな。それが、ちょっと分かったような気がした。客がどう思ったか知りませんが。でもステージではときどき本人に戻ったりしてましたね。喋っているうちに。演じきれないというか。それはテレやろうね。本名で歌ってたということでずっとやってきたから、そこにすっと戻ってしまうんとちゃうかな。これ芝居だよって、客に言いたくなってくる。何かね、客観的に見ている自分がいるね。ちょっとやり過ぎとちゃうかと思うと、茶化したくなる。
おどけてみせたり、他人を煙に巻いたりするような印象が、岡林信康にはどことなくある。それは、テレ隠しがもたらすものかもしれないし、自分をどこか斜め後方から見ているからこそ生まれるものなのかもしれない。
岡林信康っていうのは、どういう生き物なんだろう、っていう興味やね。自分の中から次に何が出てくるんだろう、っていう。最初、弾き語りでスタートして、まさかロックをやれるとは思ってなかった。でも、そういう作品が書けたら面白いなと思って、それでのめり込んで。そのあと村に住むと演歌好きになってしまったり。すると演歌的なものが書けてきて、演歌って面白いなと。だから、自分の中に何が詰まっているのかなと興味をもってここまで来たのだけれど、周りは、突然変わっていくので戸惑ったと思う。でも、それは止められないし、僕自身が意図してやってることでもないから。歌に引きずられているような感じだね。
68年に「山谷ブルース」でデビュー後、数々の曲が放送禁止になるなど話題もふりまきながら、一気にスターダムに。しかし岡林自身は、本来の自分と世間のイメージとのギャップに耐えきれず、一時蒸発。71年からの5年間、岐阜と京都の山村に引きこもってしまう。
ずっと俺は犠牲者だと思っていた。被害者っていうか。理解されないままの。でも、やる音がそんなにころころ変わったら、俺が聴き手ならヤジを飛ばしていたかも。いや、ひょっとして、俺が加害者だったのかも分からないな。聴き手に対する配慮が欠けていたのかな。でも、自分の中ではギターの弾き語りではもう何も出てこないというのは分かっていたから、そこには留まれなかったね。そのまま、学生服着て「高校三年生」を歌ってりゃ良かったんですよ。でも、それはできない。
歌が自分の表現手段だと思っていた時期があるんですよ。“歌は俺の道具”だと。でも、あるときから、“歌の道具が俺”だと思うようになった。俺は、歌に道具として使われている。そういう感覚になってくる。そしたら、もうそれに従うって。ロックやったり、演歌やったり、いまはエンヤトットやってるけど、岡林は落ち着きのない男やな、って自分では思うんだけど、それは、よく考えたら歌の道具になってるんだと。そういう感覚になったのは、もう15年とか20年ぐらい前とちゃうかな。歌いだして10年ぐらいしてからとちゃうかね。
友達がね、那須で牧場をやってるんですよ。正月、みんな休んでいるときに、牛舎の掃除をして餌を運ぶと、牛はそこで寝てる。それを見たときに、俺は牛に飼われているんだって思ったと。牛を飼っているんじゃなくて。そういう感覚ね。歌に遊ばれているなって。それからは、もう無駄な抵抗はしない。でも、それは幸せもあるし不幸もあるね。というのは、だんだん客は離れていくし、レコード出してくれる会社もなくなるし、だから、犠牲者だ、被害者だという意識はつねにあった。
岡林は、穏やかな表情を浮かべながらも淡々と話す。とはいえ、被害者意識が吹っ切れたのは、ごく最近のことだという。あるきっかけがあって、と言うが、ここでもまた岡林ならではの名調子が聞けた。
恨みが消えたのは、極めて最近。小室哲哉くんからですよ。というのは、彼は歌を作って歌うことがひとつの喜びで達成感だったのに、たくさん売れるということが喜びにすり替わっていったんですよ。歌自体が手段になってしまった。最初は“歌、できた”っていう達成感や喜びがあったのに、それがねじ曲がっていったと思うんです。歌を、お金を得る道具にしてしまったんやね。でも、彼は不幸ではなかったと僕は思う。達成感や喜びはあったんだから。そういう意味で、苦労して歌を作って、“わあ、こんな歌できた”っていうその喜びがあるんだから、受ける受けないは人の自由。結果は問わないと自分でも完全に吹っ切れたのは、小室哲哉先生事件。つい昨日のことです。
もともと牧師の息子として滋賀県近江八幡市に生まれたが、自らのキリスト教への信仰に疑問を感じたことが、フォークに目覚めたきっかけになったという。
小さいころからギターをいじっていたとか、歌手になりたいとか、一度も思ったことはなかった。たまたま、こうなってしまった。だから、しょっちゅうやめたいなと思っていた。そのたんびに、違うジャンルの音楽に出会って、またのめり込んで……。そんなに好きかどうか分からないのだけれど、それでずーっときてる。結局、これからもそういうカタチで行くんとちゃうかな。
ちょうど学校やめてぶらぶらして山谷に行ったりしてるときに、高石ともやという人のコンサートを観て、彼の音楽を聴いて、面白いなって思った。自分で歌つくって歌って、音楽学校も出てないのにそんなことしていいのか、って。すごいショックで、じゃあ俺も作って歌おうって、ギターなんかいじったことないのに思ったんです。そのときに。すーって、スイッチが入ったんやね。作詞とか作曲なんて、そんなことは専門の教育を受けた人以外やってはいかんと思ってたから。40年前は自作自演なんてなかったよ。歌は作詞家がいて作曲家がいてできるもんだ。だから、素人が作詞作曲なんて、できないと思っていた。それが、高石がへたなギターでぐちゅぐちゅやって、自分で作った歌ですってやってるから、こんなのありかって。当時は俺の心が荒んでいるから、流行ってるやつの歌聴いてもピンとこないのね。腹立つばっかりで。何が幸せなんだ、このやろうって。でも高石は暗くてひねくれた歌もあったからいいかなって。
まあ、ほかにやることもないから、牧師になろうと思って、そのために神学部に行ったりしてたんやけど、途中でやめた。人生の最大目標が消えたんやから、真空状態のパニック。そこで俺も歌つくって歌いたいというのは、かなり強力なものがあったんでしょうね。どうしても歌手になろうなんて思ったことはないけれど、俺もやりたい、これはやれるってスイッチがガシャって入ったね。だから、そういう意味ではすごい幸運な出会いだったんだね。
その後ボブ・ディランに影響を受け、はっぴいえんどがバックをつとめたセカンド・アルバム『見るまえに跳べ』を70年に発表、以後、転がるままに波乱万丈な半生を歩んできた。
僕は牧師の息子に生まれて良かったといまは思ってるんですよ。音楽的な意味でいえば、賛美歌で育ったということは大きいからね。演歌も聴けたし、ロックもあったし、浪曲もあったし、音楽性を豊かにしてくれたというので、いまは良かったと思ってる。長い間悩みましたけどね。ロックをやりだしたときも、はっぴいえんどというバンドと出会ったし、演歌やったら美空ひばりさんとも出会ったし。運が良かったのかな。
岡林はその後、さきほど話に少し出てきた、日本の民謡リズムに西洋のロックの要素を取り入れたエンヤトットスタイルを“発明”するのである。
そもそもエンヤトットを作ろうと思ったのは25年ほど前だけど、イギリスに行ったときに、向こうの有名なロック・ミュージシャンから“お前たち俺らの真似ばかりで日本人のロック聴かせろ”って侮蔑的に言われて、こいつらギャフンと言わせたろと思って始めたことなんだ。エンヤトット・スタイルは、誰もやっていないから、これはカタチのないものを初めから作ろうというものやから、おもろいし、喜びが大きい。
育ったのは田舎の教会だったけれど、夏の盆踊りとか、土着のそういうものにはなかなか入れなかった。みんな酒飲んでウワーってやってるところに牧師の息子が行くわけには……と、自己規制してたんです。それが、小学校2年生のときに、思わず踊ったわけですよ。そうしたら、この陶酔感は何なんだって。賛美歌とは違うけど、本当はこっちなんじゃないかなって。それをずっと長い間また押し込めていたのだけど、40歳ぐらいになったときに、あれが日本のロック・ミュージックじゃないかなって思った。西洋のロックと何が違うんだっていうと、リズムですよ。それで、日本のリズムをいろいろ勉強して、それをベースにした。メロディ・ラインは西洋でいいから、リズムを作り出すと。リズムが命だと。歌詞は、だからすごくくだらなくてもいい。というのは、体が動いて踊るということを邪魔できないし。って言うて、まったくデタラメでもダメなんです。そこが面白いところ。“月が出た出た、月が出た”なんて面白いやろ。くだらないけど面白い。そんな歌詞に変わってきた。
うちの親父も新潟の百姓上がりの牧師なんですよ。だから、おそらく無理して牧師やってたんですよ。彼の中に、盆踊りに対する思いはあったんだと思う。親父は農村から脱出して西洋化をめざして牧師になって、俺はそこで学習して、それからまた盆踊りに向かっていって、だから二代かかっているのよ。二代かけて、別に捨てなくていいものがたくさんあったということ。親父は明治の最後の年に生まれてる。だから、明治維新を、私たち親子で克服してるんで、テーマは大きい。悪いけど普通の人が盆踊りしたら、田子作音頭になりますよ。ちっともかっこ良くならない。俺がやるからっていう自信はある。俺がやるからロック・ミュージックになる。まあ、ボブ・ディランみたいに、踊れないロックンローラーもいるけどね。
と、話はエンヤトットからボブ・ディランへと流れていく。
エンヤトットをやるまでは、ボブ・ディランにのめり込んだこともあったね。でも、ディランを聴いてたらキリがない。すごい魅力があって引き込まれて、我をなくしてしまう。だから、聴くのはやめようと。俺は自分のオリジナルの日本のロックを作ろうと思ったとき、この人とは縁を切らなきゃいけないと思ったんです。ある時期すごくディランを崇めていて、レコーディングのときでも、ディランのこのフレーズを弾けとか、そこまでいってしまった。それが、エンヤトットを創り出すころには、あえて耳を塞いだ。僕は僕の道に行きたいと。でも、好きですよ。いまのボブ・ディランは、全然聴いていないから分からないけど。『ノー・ディレクション・ホーム』っていうのは観たんですよ。面白かった。俺と同じ目に遭うとるなって。俺と一緒だなって。ブーイング受けて俺は田舎に引っ込んでしまったんやけど、彼は交通事故にあって引っ込んだんだよね。あの映画観て、ディランはこういうことをやってきたんやろうな、と思うとおりやった。ディランが決してちゃんと語らない、というところも分かるね。
ボブ・ディラン以外では、レイ・チャールズやザ・バンドもかなり聴いたね。いまのJ-POPとかの音楽は全然聴いていない。俺にしか興味ない。生活の中であえて聴かない。聴きたくないのやろうね。俺の家はテレビがなかった。おそらく生まれた町で、一番最後にテレビが入ったのが俺の家だと思う。だから、世の中で何が流行っていようが、何をしようが情報がないことに対して何の不安もない。何にも関係ない。だから、レコードなどもほとんど持っていないし、他のミュージシャンであえて誰が好きだとか言われたら、ジャズの山下洋輔さんとか、あの人のピアノが面白いなとか、とりあえず聴いていたら元気が出るなって、そんなレベルやけど。だから、普段は浪曲のCD聴いたり、古い民謡聴いたり……。まあ資料みたいなもんやけど。あとディランの映画を観てからは、ちょっとディランも聴いたり。もうボブ・ディランを聴いても大丈夫だという自信もついたんやろうね。
岡林は農村での生活の中で演歌に傾倒、美空ひばりとの交流を通じ、美空ひばりに「月の夜汽車」などの作品を提供。75年には、岡林本人も演歌路線のアルバム『うつし絵』をコロムビアより発表する。そのころの美空ひばりとのエピソードは、才能とは自分を信じることができることだと言ったジョン・レノンを思い起こさせるものでもあった。
昔ね、美空ひばりさんと喋っていて、“歌ってなんなんだ”っていう話になって、俺はうんこだって言ったんです。“俺のうんこ”だけど、でも俺にはうんこを作る力はない。でも、うんこは出てくるもんだって。喩えが汚いって美空ひばりさんは怒ってたけど。歌にはそういう力があるわけですよ。だから、そういうものを信じるということやね。親父が牧師だったから宗教的かもしれんし、ひとつ間違うとオカルトとかになるから、あまり言わないけれど。どんなことも楽しく受け止めて、この人生を一枚の絵を描くように楽しいものとして創造していく力は誰にでも備わっている。それを信じる。内なるエネルギーを。誰もが歌手になれたはずやし、俺はそのスイッチを押してしまったんやね。俺はカメラマンになれたかもしれんですよ、そのスイッチを押せば。ただ、カメラマンになる必要がなかった。歌手にならなあかんかった。それでスイッチを押した。それを信じる。
過去を否定も肯定もせずに受け入れた結果、現在どこに自分がいるのかがわかる。そんな岡林のフラットな姿勢は、人に生きる力を与えるものだと思うが、さて、では岡林自身は、今後どんな夢を自分に託しているのだろうか。
今はいろんなところでライヴをやりたい。400〜500人ぐらいのホールがベストやな。田舎に引っ込んだから、音楽業界とのつながりが何もないし、向こうも連絡がとりにくいんだろうけど、コンサートをたくさんやりたい。歌ってるときがやっと楽しくなってきたんですよ。海外、たとえばニューヨークのハーレムの黒人教会でやりたいね。シアトルではやったけれど、黒人も白人も1曲目からワアーって踊ったし、それはエンヤトットのリズムの力やね。でも日本のリズムの中で、あの人たちは違うところにポイントを置いて自分のリズムで捉えているんだ。それが面白い。小さな教会でいいから、いくつか回ってライヴをしたいね。カーネギー・ホールに日本の駐在員ばかり集めて“カーネギー・ホールでやりました”なんて大嘘こいて、アホやないかと思うもんね。場所が外国だけで、客は日本人ばかり。そんなんじゃなくて、ハーレム黒人教会なんかでやりたい。
もうひとつ、生まれ故郷が滋賀県の近江八幡というところで、城下町で風情の残った町並みとか、きれいなお壕があるんだけど、観光地としては中途半端。貧乏で金もない。そこを文化観光都市にしたい。観光ってのは決して悪いことではないと思う。いいのもに触れさせてあげるのだから。お金は何千億いるけどね。隣町が安土だから、安土城も復元したい。これ、歌以外でバカ言え、というんならの話やで。
言葉が次から次へと飛び出してくる。それを聞いているだけでも、やっぱりシンガー・ソングライターだなあと思ってしまうわけだが、今年、デビュー40周年を迎えた岡林自身は、破天荒にも見えるこれまでの足取りについてどんなふうに思っているのだろうか。
俺のこんな人生、そうそう誰も送れないだろうなって。これはもうけとちゃうかなって。俺は諦めたのか——諦めたという言い方も悪いけど、もういいやって。人の心はコントロールできないし、してはいけないし、何を聴こうが、聴き手の自由だから。やっぱり弾き語りが最高という人もいるしね。どの時期を好きになろうが勝手や。その人たちの自由や。
新興宗教であるまいしね。どの時期の俺を好きになれとか、俺の方を向けなんていうほうがおかしい。客がいなけりゃコンサートはないから、もうちょっとコンサートやらしてくれや、っていうくらいで。諦めっていうのは、俺の生き方が招いたことは、俺が責任とるっていうこと。これがいやなら、俺はこういうことをしなけりゃよかった。全部俺が招いたことだから、俺が責任とる。さあ、殺せって。思うのはそんなことかな。だから、重苦しいところから、どんどん楽になってきてる。歌ってるのは楽しいな。やっぱり俺の一番いいところが出てるのやろうな、と思う。声も昔より出てる。不思議なんよ。何もしてないのに。重しが外れてきてるからだろうね。自分で自分を狭いところに閉じ込めていたのを、自分で開けて、身軽になったと思うね。
最後に、岡林信康に影響を受けた日本の多くの若手ミュージシャンが、“岡林さんのようなことをしたい“とか”岡林さんみたいに生きてみたい”と言ったら?
と訊いてみたら、こんな答えがかえってきた。
おやめなさい。不幸になるよ。
あっ。
これもきっとテレからくる言葉だ。
そんな岡林信康の60年代後半から70年代前半にかけての初期作品が、ディスクユニオンの富士レーベルから8月以降、次々と復刻され、若い世代の間で俄かに岡林信康ブームが起こりつつある。11月24日には、第2弾発売を記念したインストア・ライヴもタワーレコード渋谷店で行なわれるなど、周辺がなにやら騒がしくなってきた。
ああいうロックの編成でライヴをやったのは25年ぶりぐらい。僕はステージ・ネームはないし、本名で歌ってきたけど、生まれて初めて演じたんよ。エレキ・ギターで歌ってたころの自分をね。こういう歌い方があんのやね、っていう楽しさを初めて知った感じ。芸名で歌っている人っていうのは、ステージに出たときに別人になるのかな。それが、ちょっと分かったような気がした。客がどう思ったか知りませんが。でもステージではときどき本人に戻ったりしてましたね。喋っているうちに。演じきれないというか。それはテレやろうね。本名で歌ってたということでずっとやってきたから、そこにすっと戻ってしまうんとちゃうかな。これ芝居だよって、客に言いたくなってくる。何かね、客観的に見ている自分がいるね。ちょっとやり過ぎとちゃうかと思うと、茶化したくなる。
おどけてみせたり、他人を煙に巻いたりするような印象が、岡林信康にはどことなくある。それは、テレ隠しがもたらすものかもしれないし、自分をどこか斜め後方から見ているからこそ生まれるものなのかもしれない。
岡林信康っていうのは、どういう生き物なんだろう、っていう興味やね。自分の中から次に何が出てくるんだろう、っていう。最初、弾き語りでスタートして、まさかロックをやれるとは思ってなかった。でも、そういう作品が書けたら面白いなと思って、それでのめり込んで。そのあと村に住むと演歌好きになってしまったり。すると演歌的なものが書けてきて、演歌って面白いなと。だから、自分の中に何が詰まっているのかなと興味をもってここまで来たのだけれど、周りは、突然変わっていくので戸惑ったと思う。でも、それは止められないし、僕自身が意図してやってることでもないから。歌に引きずられているような感じだね。
68年に「山谷ブルース」でデビュー後、数々の曲が放送禁止になるなど話題もふりまきながら、一気にスターダムに。しかし岡林自身は、本来の自分と世間のイメージとのギャップに耐えきれず、一時蒸発。71年からの5年間、岐阜と京都の山村に引きこもってしまう。
ずっと俺は犠牲者だと思っていた。被害者っていうか。理解されないままの。でも、やる音がそんなにころころ変わったら、俺が聴き手ならヤジを飛ばしていたかも。いや、ひょっとして、俺が加害者だったのかも分からないな。聴き手に対する配慮が欠けていたのかな。でも、自分の中ではギターの弾き語りではもう何も出てこないというのは分かっていたから、そこには留まれなかったね。そのまま、学生服着て「高校三年生」を歌ってりゃ良かったんですよ。でも、それはできない。
歌が自分の表現手段だと思っていた時期があるんですよ。“歌は俺の道具”だと。でも、あるときから、“歌の道具が俺”だと思うようになった。俺は、歌に道具として使われている。そういう感覚になってくる。そしたら、もうそれに従うって。ロックやったり、演歌やったり、いまはエンヤトットやってるけど、岡林は落ち着きのない男やな、って自分では思うんだけど、それは、よく考えたら歌の道具になってるんだと。そういう感覚になったのは、もう15年とか20年ぐらい前とちゃうかな。歌いだして10年ぐらいしてからとちゃうかね。
友達がね、那須で牧場をやってるんですよ。正月、みんな休んでいるときに、牛舎の掃除をして餌を運ぶと、牛はそこで寝てる。それを見たときに、俺は牛に飼われているんだって思ったと。牛を飼っているんじゃなくて。そういう感覚ね。歌に遊ばれているなって。それからは、もう無駄な抵抗はしない。でも、それは幸せもあるし不幸もあるね。というのは、だんだん客は離れていくし、レコード出してくれる会社もなくなるし、だから、犠牲者だ、被害者だという意識はつねにあった。
岡林は、穏やかな表情を浮かべながらも淡々と話す。とはいえ、被害者意識が吹っ切れたのは、ごく最近のことだという。あるきっかけがあって、と言うが、ここでもまた岡林ならではの名調子が聞けた。
恨みが消えたのは、極めて最近。小室哲哉くんからですよ。というのは、彼は歌を作って歌うことがひとつの喜びで達成感だったのに、たくさん売れるということが喜びにすり替わっていったんですよ。歌自体が手段になってしまった。最初は“歌、できた”っていう達成感や喜びがあったのに、それがねじ曲がっていったと思うんです。歌を、お金を得る道具にしてしまったんやね。でも、彼は不幸ではなかったと僕は思う。達成感や喜びはあったんだから。そういう意味で、苦労して歌を作って、“わあ、こんな歌できた”っていうその喜びがあるんだから、受ける受けないは人の自由。結果は問わないと自分でも完全に吹っ切れたのは、小室哲哉先生事件。つい昨日のことです。
もともと牧師の息子として滋賀県近江八幡市に生まれたが、自らのキリスト教への信仰に疑問を感じたことが、フォークに目覚めたきっかけになったという。
小さいころからギターをいじっていたとか、歌手になりたいとか、一度も思ったことはなかった。たまたま、こうなってしまった。だから、しょっちゅうやめたいなと思っていた。そのたんびに、違うジャンルの音楽に出会って、またのめり込んで……。そんなに好きかどうか分からないのだけれど、それでずーっときてる。結局、これからもそういうカタチで行くんとちゃうかな。
ちょうど学校やめてぶらぶらして山谷に行ったりしてるときに、高石ともやという人のコンサートを観て、彼の音楽を聴いて、面白いなって思った。自分で歌つくって歌って、音楽学校も出てないのにそんなことしていいのか、って。すごいショックで、じゃあ俺も作って歌おうって、ギターなんかいじったことないのに思ったんです。そのときに。すーって、スイッチが入ったんやね。作詞とか作曲なんて、そんなことは専門の教育を受けた人以外やってはいかんと思ってたから。40年前は自作自演なんてなかったよ。歌は作詞家がいて作曲家がいてできるもんだ。だから、素人が作詞作曲なんて、できないと思っていた。それが、高石がへたなギターでぐちゅぐちゅやって、自分で作った歌ですってやってるから、こんなのありかって。当時は俺の心が荒んでいるから、流行ってるやつの歌聴いてもピンとこないのね。腹立つばっかりで。何が幸せなんだ、このやろうって。でも高石は暗くてひねくれた歌もあったからいいかなって。
まあ、ほかにやることもないから、牧師になろうと思って、そのために神学部に行ったりしてたんやけど、途中でやめた。人生の最大目標が消えたんやから、真空状態のパニック。そこで俺も歌つくって歌いたいというのは、かなり強力なものがあったんでしょうね。どうしても歌手になろうなんて思ったことはないけれど、俺もやりたい、これはやれるってスイッチがガシャって入ったね。だから、そういう意味ではすごい幸運な出会いだったんだね。
その後ボブ・ディランに影響を受け、はっぴいえんどがバックをつとめたセカンド・アルバム『見るまえに跳べ』を70年に発表、以後、転がるままに波乱万丈な半生を歩んできた。
僕は牧師の息子に生まれて良かったといまは思ってるんですよ。音楽的な意味でいえば、賛美歌で育ったということは大きいからね。演歌も聴けたし、ロックもあったし、浪曲もあったし、音楽性を豊かにしてくれたというので、いまは良かったと思ってる。長い間悩みましたけどね。ロックをやりだしたときも、はっぴいえんどというバンドと出会ったし、演歌やったら美空ひばりさんとも出会ったし。運が良かったのかな。
岡林はその後、さきほど話に少し出てきた、日本の民謡リズムに西洋のロックの要素を取り入れたエンヤトットスタイルを“発明”するのである。
そもそもエンヤトットを作ろうと思ったのは25年ほど前だけど、イギリスに行ったときに、向こうの有名なロック・ミュージシャンから“お前たち俺らの真似ばかりで日本人のロック聴かせろ”って侮蔑的に言われて、こいつらギャフンと言わせたろと思って始めたことなんだ。エンヤトット・スタイルは、誰もやっていないから、これはカタチのないものを初めから作ろうというものやから、おもろいし、喜びが大きい。
育ったのは田舎の教会だったけれど、夏の盆踊りとか、土着のそういうものにはなかなか入れなかった。みんな酒飲んでウワーってやってるところに牧師の息子が行くわけには……と、自己規制してたんです。それが、小学校2年生のときに、思わず踊ったわけですよ。そうしたら、この陶酔感は何なんだって。賛美歌とは違うけど、本当はこっちなんじゃないかなって。それをずっと長い間また押し込めていたのだけど、40歳ぐらいになったときに、あれが日本のロック・ミュージックじゃないかなって思った。西洋のロックと何が違うんだっていうと、リズムですよ。それで、日本のリズムをいろいろ勉強して、それをベースにした。メロディ・ラインは西洋でいいから、リズムを作り出すと。リズムが命だと。歌詞は、だからすごくくだらなくてもいい。というのは、体が動いて踊るということを邪魔できないし。って言うて、まったくデタラメでもダメなんです。そこが面白いところ。“月が出た出た、月が出た”なんて面白いやろ。くだらないけど面白い。そんな歌詞に変わってきた。
うちの親父も新潟の百姓上がりの牧師なんですよ。だから、おそらく無理して牧師やってたんですよ。彼の中に、盆踊りに対する思いはあったんだと思う。親父は農村から脱出して西洋化をめざして牧師になって、俺はそこで学習して、それからまた盆踊りに向かっていって、だから二代かかっているのよ。二代かけて、別に捨てなくていいものがたくさんあったということ。親父は明治の最後の年に生まれてる。だから、明治維新を、私たち親子で克服してるんで、テーマは大きい。悪いけど普通の人が盆踊りしたら、田子作音頭になりますよ。ちっともかっこ良くならない。俺がやるからっていう自信はある。俺がやるからロック・ミュージックになる。まあ、ボブ・ディランみたいに、踊れないロックンローラーもいるけどね。
と、話はエンヤトットからボブ・ディランへと流れていく。
エンヤトットをやるまでは、ボブ・ディランにのめり込んだこともあったね。でも、ディランを聴いてたらキリがない。すごい魅力があって引き込まれて、我をなくしてしまう。だから、聴くのはやめようと。俺は自分のオリジナルの日本のロックを作ろうと思ったとき、この人とは縁を切らなきゃいけないと思ったんです。ある時期すごくディランを崇めていて、レコーディングのときでも、ディランのこのフレーズを弾けとか、そこまでいってしまった。それが、エンヤトットを創り出すころには、あえて耳を塞いだ。僕は僕の道に行きたいと。でも、好きですよ。いまのボブ・ディランは、全然聴いていないから分からないけど。『ノー・ディレクション・ホーム』っていうのは観たんですよ。面白かった。俺と同じ目に遭うとるなって。俺と一緒だなって。ブーイング受けて俺は田舎に引っ込んでしまったんやけど、彼は交通事故にあって引っ込んだんだよね。あの映画観て、ディランはこういうことをやってきたんやろうな、と思うとおりやった。ディランが決してちゃんと語らない、というところも分かるね。
ボブ・ディラン以外では、レイ・チャールズやザ・バンドもかなり聴いたね。いまのJ-POPとかの音楽は全然聴いていない。俺にしか興味ない。生活の中であえて聴かない。聴きたくないのやろうね。俺の家はテレビがなかった。おそらく生まれた町で、一番最後にテレビが入ったのが俺の家だと思う。だから、世の中で何が流行っていようが、何をしようが情報がないことに対して何の不安もない。何にも関係ない。だから、レコードなどもほとんど持っていないし、他のミュージシャンであえて誰が好きだとか言われたら、ジャズの山下洋輔さんとか、あの人のピアノが面白いなとか、とりあえず聴いていたら元気が出るなって、そんなレベルやけど。だから、普段は浪曲のCD聴いたり、古い民謡聴いたり……。まあ資料みたいなもんやけど。あとディランの映画を観てからは、ちょっとディランも聴いたり。もうボブ・ディランを聴いても大丈夫だという自信もついたんやろうね。
岡林は農村での生活の中で演歌に傾倒、美空ひばりとの交流を通じ、美空ひばりに「月の夜汽車」などの作品を提供。75年には、岡林本人も演歌路線のアルバム『うつし絵』をコロムビアより発表する。そのころの美空ひばりとのエピソードは、才能とは自分を信じることができることだと言ったジョン・レノンを思い起こさせるものでもあった。
昔ね、美空ひばりさんと喋っていて、“歌ってなんなんだ”っていう話になって、俺はうんこだって言ったんです。“俺のうんこ”だけど、でも俺にはうんこを作る力はない。でも、うんこは出てくるもんだって。喩えが汚いって美空ひばりさんは怒ってたけど。歌にはそういう力があるわけですよ。だから、そういうものを信じるということやね。親父が牧師だったから宗教的かもしれんし、ひとつ間違うとオカルトとかになるから、あまり言わないけれど。どんなことも楽しく受け止めて、この人生を一枚の絵を描くように楽しいものとして創造していく力は誰にでも備わっている。それを信じる。内なるエネルギーを。誰もが歌手になれたはずやし、俺はそのスイッチを押してしまったんやね。俺はカメラマンになれたかもしれんですよ、そのスイッチを押せば。ただ、カメラマンになる必要がなかった。歌手にならなあかんかった。それでスイッチを押した。それを信じる。
過去を否定も肯定もせずに受け入れた結果、現在どこに自分がいるのかがわかる。そんな岡林のフラットな姿勢は、人に生きる力を与えるものだと思うが、さて、では岡林自身は、今後どんな夢を自分に託しているのだろうか。
今はいろんなところでライヴをやりたい。400〜500人ぐらいのホールがベストやな。田舎に引っ込んだから、音楽業界とのつながりが何もないし、向こうも連絡がとりにくいんだろうけど、コンサートをたくさんやりたい。歌ってるときがやっと楽しくなってきたんですよ。海外、たとえばニューヨークのハーレムの黒人教会でやりたいね。シアトルではやったけれど、黒人も白人も1曲目からワアーって踊ったし、それはエンヤトットのリズムの力やね。でも日本のリズムの中で、あの人たちは違うところにポイントを置いて自分のリズムで捉えているんだ。それが面白い。小さな教会でいいから、いくつか回ってライヴをしたいね。カーネギー・ホールに日本の駐在員ばかり集めて“カーネギー・ホールでやりました”なんて大嘘こいて、アホやないかと思うもんね。場所が外国だけで、客は日本人ばかり。そんなんじゃなくて、ハーレム黒人教会なんかでやりたい。
もうひとつ、生まれ故郷が滋賀県の近江八幡というところで、城下町で風情の残った町並みとか、きれいなお壕があるんだけど、観光地としては中途半端。貧乏で金もない。そこを文化観光都市にしたい。観光ってのは決して悪いことではないと思う。いいのもに触れさせてあげるのだから。お金は何千億いるけどね。隣町が安土だから、安土城も復元したい。これ、歌以外でバカ言え、というんならの話やで。
言葉が次から次へと飛び出してくる。それを聞いているだけでも、やっぱりシンガー・ソングライターだなあと思ってしまうわけだが、今年、デビュー40周年を迎えた岡林自身は、破天荒にも見えるこれまでの足取りについてどんなふうに思っているのだろうか。
俺のこんな人生、そうそう誰も送れないだろうなって。これはもうけとちゃうかなって。俺は諦めたのか——諦めたという言い方も悪いけど、もういいやって。人の心はコントロールできないし、してはいけないし、何を聴こうが、聴き手の自由だから。やっぱり弾き語りが最高という人もいるしね。どの時期を好きになろうが勝手や。その人たちの自由や。
新興宗教であるまいしね。どの時期の俺を好きになれとか、俺の方を向けなんていうほうがおかしい。客がいなけりゃコンサートはないから、もうちょっとコンサートやらしてくれや、っていうくらいで。諦めっていうのは、俺の生き方が招いたことは、俺が責任とるっていうこと。これがいやなら、俺はこういうことをしなけりゃよかった。全部俺が招いたことだから、俺が責任とる。さあ、殺せって。思うのはそんなことかな。だから、重苦しいところから、どんどん楽になってきてる。歌ってるのは楽しいな。やっぱり俺の一番いいところが出てるのやろうな、と思う。声も昔より出てる。不思議なんよ。何もしてないのに。重しが外れてきてるからだろうね。自分で自分を狭いところに閉じ込めていたのを、自分で開けて、身軽になったと思うね。
最後に、岡林信康に影響を受けた日本の多くの若手ミュージシャンが、“岡林さんのようなことをしたい“とか”岡林さんみたいに生きてみたい”と言ったら?
と訊いてみたら、こんな答えがかえってきた。
おやめなさい。不幸になるよ。
あっ。
これもきっとテレからくる言葉だ。
|
|
|
|
|
|
|
|
mixii岡林信康三宅洋平の会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-