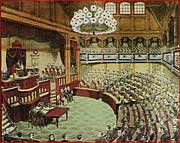古代というと
ローマ、ギリシャ、ペルシャ、春秋戦国、4大河文明、アステカ、長江、イスラエル、などなど人類の文明の草創期を彩る国々や地域を連想するものですが。
日本古代史は非常に特殊だと思っています。
縄文時代の諏訪地域には2万年前からの集落遺跡があり、1万年前には黒曜石採取を組織的に行っていました。メソポタミアの草創期と同じです。農耕以外で唯一の定住生活をしていた縄文文化は日本列島の豊穣さゆえの様式だったかもしれません(淡水の多さ、山が背骨のようにありそこに雲があたり雨になり急流の細い川が毛細血管のように土地を流れます)
さてそのような国土に現代の日本国につながる政治主体ができたのは4世紀であると従来言われています。いわゆる邪馬台国問題はその100年前です。
日本古代史は古事記日本書紀のいわゆる記紀や風土記という国内記録と
遺跡と
中国の記録の三角測量ができてしまう稀な状況にあります。
したがって記録が中途半端にあったり
わかりにくくあったりします。
建国神話にしてもよく見るとわけがわかりません。しかしさらによく見るといろいろなことを考えさせられます。
この霧の中の日本建国前後の時代の探求は最終的に日本列島の国々はどのように誕生していったのかを探る旅であり、日本とは何かを考える旅でもあります。
考える糧ゴリーに属するテーマだと思います。
たとえば建国記念日をいつにするのがいいのか?これは古代史抜きに語れません。
今の建国記念日とは神武東征の結果神武天皇が奈良に落ち着いたときを記念しています。
しかし建国記念日というには事績としていまいちです。
そもそも神武天皇は国を作っていません!!
奈良にいたニギハヤヒとナガスネヒコの国をいきなり武力で侵略しただけです。
候補
1.アマテルは国譲りによって大国主の作った国を奪いました。だから大国主が国造りを一段落させたときが建国記念日。それはスクナヒコがいなくなった時でしょう。
2、国譲りの結果アマテルの孫ニニギが天孫降臨したとき
3.天武天皇の即位。通説ではそこから倭国が日本国になった。
4.明治維新
5.サンフランシスコ講和会議による占領の終わり。
6.古代史にはまるとこの国は誰のときが始原の時かというとスサノオになってしまいます。
スサノオを記念する日
7.神武東征
古代史の観点で行くと、スサノオが統治を始めたときが一番ふさわしいような気もします。
107年に漢に朝貢した倭国王スイショウこそスサノオであるという意見が結構あったりします。
過去3年くらいにブログにつづって来たものを元にトピックを進めて行きたいと思っています。
http://
http://
ローマ、ギリシャ、ペルシャ、春秋戦国、4大河文明、アステカ、長江、イスラエル、などなど人類の文明の草創期を彩る国々や地域を連想するものですが。
日本古代史は非常に特殊だと思っています。
縄文時代の諏訪地域には2万年前からの集落遺跡があり、1万年前には黒曜石採取を組織的に行っていました。メソポタミアの草創期と同じです。農耕以外で唯一の定住生活をしていた縄文文化は日本列島の豊穣さゆえの様式だったかもしれません(淡水の多さ、山が背骨のようにありそこに雲があたり雨になり急流の細い川が毛細血管のように土地を流れます)
さてそのような国土に現代の日本国につながる政治主体ができたのは4世紀であると従来言われています。いわゆる邪馬台国問題はその100年前です。
日本古代史は古事記日本書紀のいわゆる記紀や風土記という国内記録と
遺跡と
中国の記録の三角測量ができてしまう稀な状況にあります。
したがって記録が中途半端にあったり
わかりにくくあったりします。
建国神話にしてもよく見るとわけがわかりません。しかしさらによく見るといろいろなことを考えさせられます。
この霧の中の日本建国前後の時代の探求は最終的に日本列島の国々はどのように誕生していったのかを探る旅であり、日本とは何かを考える旅でもあります。
考える糧ゴリーに属するテーマだと思います。
たとえば建国記念日をいつにするのがいいのか?これは古代史抜きに語れません。
今の建国記念日とは神武東征の結果神武天皇が奈良に落ち着いたときを記念しています。
しかし建国記念日というには事績としていまいちです。
そもそも神武天皇は国を作っていません!!
奈良にいたニギハヤヒとナガスネヒコの国をいきなり武力で侵略しただけです。
候補
1.アマテルは国譲りによって大国主の作った国を奪いました。だから大国主が国造りを一段落させたときが建国記念日。それはスクナヒコがいなくなった時でしょう。
2、国譲りの結果アマテルの孫ニニギが天孫降臨したとき
3.天武天皇の即位。通説ではそこから倭国が日本国になった。
4.明治維新
5.サンフランシスコ講和会議による占領の終わり。
6.古代史にはまるとこの国は誰のときが始原の時かというとスサノオになってしまいます。
スサノオを記念する日
7.神武東征
古代史の観点で行くと、スサノオが統治を始めたときが一番ふさわしいような気もします。
107年に漢に朝貢した倭国王スイショウこそスサノオであるという意見が結構あったりします。
過去3年くらいにブログにつづって来たものを元にトピックを進めて行きたいと思っています。
http://
http://
|
|
|
|
コメント(222)
>>[179]
どうもです。私はそういうクロノス的な時間軸が苦手ですね。
チェス人形云々は、ヴァルター・ベンヤミンの「歴史の概念について」の引用で、この後に「それは唯物論的歴史観である」と続きます。
この「唯物論的歴史観」をそのまま捉えると、意味がわからなくなりますが、一言でいえば、「歴史の中で現在と地続きになる瞬間を捉える見方」です。彼は「メシア的な時間」とも呼んでいます。過去ー現在ー未来を同時的なものとして捉えようとする見方はとてもユダヤ人的ですよね。
ちなみに、彼は翻訳において逐語訳を重んじます。私の学生時代の先生からも「一語にこだわりなさい」とおそわりました。そのせいか出来る限り、一語対応で訳す方に傾きがちで、超訳は忌避する傾向があります。
以前はこんなことをして遊んでいたくらいです笑
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1852251767&owner_id=699716
どうもです。私はそういうクロノス的な時間軸が苦手ですね。
チェス人形云々は、ヴァルター・ベンヤミンの「歴史の概念について」の引用で、この後に「それは唯物論的歴史観である」と続きます。
この「唯物論的歴史観」をそのまま捉えると、意味がわからなくなりますが、一言でいえば、「歴史の中で現在と地続きになる瞬間を捉える見方」です。彼は「メシア的な時間」とも呼んでいます。過去ー現在ー未来を同時的なものとして捉えようとする見方はとてもユダヤ人的ですよね。
ちなみに、彼は翻訳において逐語訳を重んじます。私の学生時代の先生からも「一語にこだわりなさい」とおそわりました。そのせいか出来る限り、一語対応で訳す方に傾きがちで、超訳は忌避する傾向があります。
以前はこんなことをして遊んでいたくらいです笑
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1852251767&owner_id=699716
翻訳は不可能です。その時代のその国のその心情を現代の自国の心情に移し替えるという作業は、本当はできませんからそれがもっとも効果的にできる手段はなにか。
まず普通の翻訳。そして必ずそれに飽き足らなくなる。
そのとき二つの道があります。原文へ。
もう一つはさらに言葉を変換するのです。
ちなみに日本古代史は遺跡と自国の資料(これがまたあいまいでさらにたくさんあり)
そして中国の資料、半島の資料があります。
これだけそろっていながらすべてがあいまいな時代なのが1世紀から4世紀です。
なので日本古代史というのは世界でもっとも不可解かつもう一歩のジグソーパズルのようなものです。
歴史でもない。
通常の考古学でもない。
神話学でもない。
混在一体となった知の公園のようなものが日本古代史です。
まず普通の翻訳。そして必ずそれに飽き足らなくなる。
そのとき二つの道があります。原文へ。
もう一つはさらに言葉を変換するのです。
ちなみに日本古代史は遺跡と自国の資料(これがまたあいまいでさらにたくさんあり)
そして中国の資料、半島の資料があります。
これだけそろっていながらすべてがあいまいな時代なのが1世紀から4世紀です。
なので日本古代史というのは世界でもっとも不可解かつもう一歩のジグソーパズルのようなものです。
歴史でもない。
通常の考古学でもない。
神話学でもない。
混在一体となった知の公園のようなものが日本古代史です。
>>[187]
実証史学が「歴史の消しゴム」で消し過ぎているのです。デカルトの懐疑だって、あくまで「方法的懐疑」であって、懐疑を方法として利用しているだけです。実証史学は疑うことができないものを根拠にして歴史学を科学にしようとします。しかし何分、同時代の文字史料が殆どなくて、疑おうと思えばいくらでも疑えるわけですから、歴史の流れを捉えるのが目的の歴史学では、科学知的に展開することは不可能だということを覚って、開き直らなければならないのです。
それで私は石塚正英さんの「歴史知」というタームを日本古代史用に援用させてもらっているのです。それは現存する構成に編纂された記紀などの歴史書や中国・朝鮮の史書、考古学的データ、各地の民話・伝承などを突き合わせて、矛盾点を精査し、誰もが納得できるように一から組み立て直すということです。
神話と歴史を峻別し、神話の世界を形而上学的な空想の世界に閉じ込め、歴史から排除してしまうことによって、歴史の科学的な叙述が可能になると考えている研究者もいるようですが、それはとんでもない間違いです。だって、初期国家は人が神と自らを一体視し、儀礼を通してその信仰が一定の地域で承認された時に成立した神政国家だったからです。その意味で神が自ら建国する「御宇の珍子」である三貴神伝承こそ、記紀では古層の伝承なのです。
しかも三貴神が建国するには、三貴神の現人神が存在したということであり、その海原からの海下りこそ日本建国史の端緒に置かれるべきなのです。
実証史学が「歴史の消しゴム」で消し過ぎているのです。デカルトの懐疑だって、あくまで「方法的懐疑」であって、懐疑を方法として利用しているだけです。実証史学は疑うことができないものを根拠にして歴史学を科学にしようとします。しかし何分、同時代の文字史料が殆どなくて、疑おうと思えばいくらでも疑えるわけですから、歴史の流れを捉えるのが目的の歴史学では、科学知的に展開することは不可能だということを覚って、開き直らなければならないのです。
それで私は石塚正英さんの「歴史知」というタームを日本古代史用に援用させてもらっているのです。それは現存する構成に編纂された記紀などの歴史書や中国・朝鮮の史書、考古学的データ、各地の民話・伝承などを突き合わせて、矛盾点を精査し、誰もが納得できるように一から組み立て直すということです。
神話と歴史を峻別し、神話の世界を形而上学的な空想の世界に閉じ込め、歴史から排除してしまうことによって、歴史の科学的な叙述が可能になると考えている研究者もいるようですが、それはとんでもない間違いです。だって、初期国家は人が神と自らを一体視し、儀礼を通してその信仰が一定の地域で承認された時に成立した神政国家だったからです。その意味で神が自ら建国する「御宇の珍子」である三貴神伝承こそ、記紀では古層の伝承なのです。
しかも三貴神が建国するには、三貴神の現人神が存在したということであり、その海原からの海下りこそ日本建国史の端緒に置かれるべきなのです。
初めから、じっくりと読ませていただきました。
私の知識では このトピックに書いてある古代史を理解するには、時間がかかるとわかってきました。
トピック文
>>建国神話にしてもよくみるとわけがわかりません。
>>しかしさらによく見るといろいろなことを考えさせられます。
私の場合、この、「よくみると」の、かなり前の段階ですね、、
でも、
>>しかしさらによく見るといろいろなことを考えさせられます
この「よく見ると」が、このトピックで展開されているのだということは 理解できてきたので、これから学ぶのが楽しみです♪
今は、「高海原」を理解しようとしているところです
ありがとうございますp(^^)q♪
私の知識では このトピックに書いてある古代史を理解するには、時間がかかるとわかってきました。
トピック文
>>建国神話にしてもよくみるとわけがわかりません。
>>しかしさらによく見るといろいろなことを考えさせられます。
私の場合、この、「よくみると」の、かなり前の段階ですね、、
でも、
>>しかしさらによく見るといろいろなことを考えさせられます
この「よく見ると」が、このトピックで展開されているのだということは 理解できてきたので、これから学ぶのが楽しみです♪
今は、「高海原」を理解しようとしているところです
ありがとうございますp(^^)q♪
>>[198] ありがとうございます。基本的には記紀をベースにやすいさんも話されてるのだと思います。やすいさんの場合は歴史知を使って、空白や過不足を整理しています。
天照=ぼくはアマテルと読みますが、国の主神である女神だというのは常識ですが、アマテル、スサノオ、ツキヨミという三人の神がイザナギの子供たちで三貴神と言われており、じつはツキヨミの事績は他の二人に比べて驚くほどありませんというか、何も書かれていないのです。
しかしながら、沖ノ島を生んだアマテルとスサノオのウケヒとう名のどうも平和条約においてはスサノオの相手はアマテルではなくツキヨミであろうというのがやすいさんの説であり、
そうすると日本古代史は実にコペルニクス的転回をするのであります
天照=ぼくはアマテルと読みますが、国の主神である女神だというのは常識ですが、アマテル、スサノオ、ツキヨミという三人の神がイザナギの子供たちで三貴神と言われており、じつはツキヨミの事績は他の二人に比べて驚くほどありませんというか、何も書かれていないのです。
しかしながら、沖ノ島を生んだアマテルとスサノオのウケヒとう名のどうも平和条約においてはスサノオの相手はアマテルではなくツキヨミであろうというのがやすいさんの説であり、
そうすると日本古代史は実にコペルニクス的転回をするのであります
>>[199]
ご親切にありがとうございます。このトピックは 大変 難しいので、助かります。
ツクヨミの記述がほとんどないという点に目をつけて推理していくと 古代史の隠された部分が明らかになっていくのだろうか、というところまではわかってきました。
私は、知識が浅いせいもあって アマテラスは女神だということを疑ったことがなかったので混乱しています。
有名な アマテラスの天岩戸隠れを どう考えればいいのか、高天原が 「高海原」だったとするとどう考えればいいのか、、説明してあるコメントがあったようですけど、、少しずつしか進めなくて、、
>>やすいさんの場合は歴史知を使って、空白や過不足を整理しています。
コペルニクス展開も含まれているのですから、初心者には難しいですね、、トピックにも途中からの参加できたし、、。
頑張って楽しみながら 質問して少しずつ学んでいけたらと思っています♪
★☆★
天照を、アマテラスではなく、アマテルと読むのは たぶん何か理由が あるのでしょうね。
ご親切にありがとうございます。このトピックは 大変 難しいので、助かります。
ツクヨミの記述がほとんどないという点に目をつけて推理していくと 古代史の隠された部分が明らかになっていくのだろうか、というところまではわかってきました。
私は、知識が浅いせいもあって アマテラスは女神だということを疑ったことがなかったので混乱しています。
有名な アマテラスの天岩戸隠れを どう考えればいいのか、高天原が 「高海原」だったとするとどう考えればいいのか、、説明してあるコメントがあったようですけど、、少しずつしか進めなくて、、
>>やすいさんの場合は歴史知を使って、空白や過不足を整理しています。
コペルニクス展開も含まれているのですから、初心者には難しいですね、、トピックにも途中からの参加できたし、、。
頑張って楽しみながら 質問して少しずつ学んでいけたらと思っています♪
★☆★
天照を、アマテラスではなく、アマテルと読むのは たぶん何か理由が あるのでしょうね。
>>[200]
講義や読み物を投稿していただき、感謝しております。
主神と皇祖神を天照大神に差し変えたこと、三貴神のことも 楽しく かつ 学術的に 語られていました。
ダイナミックです。大まかなところが、だいぶ つかめてきました。
それにしても、閻魔様に 哲学者やすいゆたか先生が、とんでもない研究だ!と言われる設定が ユニークなアイデアですね。
そして、導入から、声を出して笑ってしまうぐらいの面白さで、ぐいぐい引き込まれてしまいました。
閻魔様も 哲学的懐疑を解していて ほんと物わかりがいいし 知性的なかたのようです。
そんな閻魔様に対して ひるむことなく「嘘をついたら 舌を抜かれますよ」閻魔様に 思わず 自分の口に手をあてさせるなんて やすいゆたか先生もただ者ではない方だとわかります。
初歩的な質問になってしまうと思うので恐縮ですけど分からないところは 質問させてください。
ありがとうございます。
講義や読み物を投稿していただき、感謝しております。
主神と皇祖神を天照大神に差し変えたこと、三貴神のことも 楽しく かつ 学術的に 語られていました。
ダイナミックです。大まかなところが、だいぶ つかめてきました。
それにしても、閻魔様に 哲学者やすいゆたか先生が、とんでもない研究だ!と言われる設定が ユニークなアイデアですね。
そして、導入から、声を出して笑ってしまうぐらいの面白さで、ぐいぐい引き込まれてしまいました。
閻魔様も 哲学的懐疑を解していて ほんと物わかりがいいし 知性的なかたのようです。
そんな閻魔様に対して ひるむことなく「嘘をついたら 舌を抜かれますよ」閻魔様に 思わず 自分の口に手をあてさせるなんて やすいゆたか先生もただ者ではない方だとわかります。
初歩的な質問になってしまうと思うので恐縮ですけど分からないところは 質問させてください。
ありがとうございます。
最近纏向からの前方後円墳体制を封建体制とネットで熱く語るアカウントがいくつかありますが、間違いです。コピペ知識でたわごとを言っています。
そして対馬海峡にはなにもなくすべての古代史は奈良盆地の出来事だというのですが間違いです。これは数学的な間違いだといっていいくらいの間違いです。
そもそも古事記の最初の数ページで胸形という文字で宗像三女神のことが記載されます。
これを何だと思うんだろうか
これは沖ノ島の重要性を述べているに決まっているだろうがと言いたい。
つまり半島と九州をつなぐ海路として神としてあがめていたということだ。
つまり壱岐から対馬から半島の海路も神→これはツキヨミ、アマテルライン
これに対抗して沖ノ島から対馬から半島→これはスサノオアマテルライン。
このように神話は対馬海峡の海路とリンクして進んでいくのである。
そして対馬海峡と黒潮の連動の中から、地理として出雲の場所が重要になるのだ。海岸線が曲がり、宍道湖という大きな淡水があり、中海という外界から隔てた港がある場所。
こうして対馬海峡から出雲にいたるラインが神話となるのだが。
奈良至上主義者はこれがすべて奈良盆地の出来事という。
これはもう歴史を考える上での思考停止だね
そして対馬海峡にはなにもなくすべての古代史は奈良盆地の出来事だというのですが間違いです。これは数学的な間違いだといっていいくらいの間違いです。
そもそも古事記の最初の数ページで胸形という文字で宗像三女神のことが記載されます。
これを何だと思うんだろうか
これは沖ノ島の重要性を述べているに決まっているだろうがと言いたい。
つまり半島と九州をつなぐ海路として神としてあがめていたということだ。
つまり壱岐から対馬から半島の海路も神→これはツキヨミ、アマテルライン
これに対抗して沖ノ島から対馬から半島→これはスサノオアマテルライン。
このように神話は対馬海峡の海路とリンクして進んでいくのである。
そして対馬海峡と黒潮の連動の中から、地理として出雲の場所が重要になるのだ。海岸線が曲がり、宍道湖という大きな淡水があり、中海という外界から隔てた港がある場所。
こうして対馬海峡から出雲にいたるラインが神話となるのだが。
奈良至上主義者はこれがすべて奈良盆地の出来事という。
これはもう歴史を考える上での思考停止だね
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
考える糧ゴリー 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート