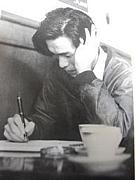●町田康と織田作の文体共通性
◎町田の小説は、1〜4に掲げる織田作の文体と基本的に合致する。
1.「ずっと連綿体の、早いスピードで会話文もみんな地の文に入れていくような、織田作独特のやり方」(藤沢桓夫『回想の大阪文学』1983年刊、93P)
「……」と彼は言った、などという月並みな文章と織田作自身が否定的である。(織田作『神経』より)
西鶴の連俳的な早いテンポ、パンクロックのような乱れ打ちのようなリズム?に共通性がありそうだ。(淀風庵)
2.「小説というものは、文章であるけれど、必ずしも行儀の良い文章、ちゃんと形の整った文章が最高点の文章であるわけではありません。…その人なりのくせ、その人だけのくせみたいものがある方が魅力的です。」(同94P)
3.「彼は(織田作)東京から思想がない、とかいわれてくさされたわけなんです。それで、健全とか健康とか一流とか重厚とか“芸術性”に対抗意識をもつようになり、逆に軽佻浮薄だと居直っていくわけです。」(杉山平一談、96P)
4.「織田君は抽象に走らない。観念の文学を嫌った。店屋の名前を書き連ね、細かい金額までびっしり書き込んでいく。名前好き、数字好き。井原西鶴を意識する以前から、織田君には西鶴と通じ合う文学気質があったと、私は見ています。」((『大阪人』2006年6月号より、杉山平一文)
「織田君は宇野さん(浩二)が手掛けた語りの文学の地盤を固めた。野坂昭如さん、町田康さんらが受け継いでいく。語りの世界も大阪の持ち味ですね」(『大阪人』2006年6月号より、杉山平一文)という見解に至るのである。
さらに、大谷晃一は『織田作之助作品集』第3巻の解説において、「彼が夢見たように、いまは私小説信仰はすたれ、彼の大阪のしゃべくり風の文体が、野坂昭如氏や町田康氏らによって受けつがれ、生きつがれ、輝いているのである。」と述べている。
●町田康の文体について
(ウィキペディアより)
独自の文体、語法、話法を確立。スラップスティックな笑いに象徴される物語や、描写におけるナンセンスと馬鹿馬鹿しさの徹底ぶりは、上方落語を源流とし、前述のロックミュージック、時代劇、河内音頭などの影響があるとされる。またプロットは嘉村礒多や近松秋江等の第二次大戦以前の破滅的な私小説や、織田作之助、太宰治などの新戯作派の系譜を受け継ぐと評される。
(プロット:物語を作るときの設計図・構想のことを指す。物語のあらすじ、登場人物の設定や相関図、事件、小道具、世界観などがプロットに含まれる。
スラップスティック:どたばたギャグ)
1.「遊び感覚の充満する冗文体」〜冗漫・冗長・冗談・冗語・冗句・ジョーク〜
町田の作品全体を通して、笑いを誘う態度と言葉に溢れており、一言でいえば「冗文体」である。
初めまごつくが、何やこれと思いながら、巻き込まれて納得してしまう。これは浮遊感やインボルブ感といえようか。(淀風庵)
2.連綿語り文体で雄弁にして饒舌
文体的には、饒舌しゃべくり体、物語の早い展開テンポとリズム感が似通っているように思える。これを「いらちっぽい」テンポと感じる大阪の読者も多かろう。 (登場人物の死さえ一言であっけなく片付ける)
町田自身が次のように語っている。
「僕は小説で大切なのは、音楽のノイズ(雑音)にあたる部分をカットしないことだと思います」「世の中の新聞や雑誌に載るニュースや記事は、理路整然としている。でも、それを根底から問い詰め、排除されたものをとらえ直すことで小説は始まる。パンクとは疑うことです」(第140回芥川賞を受賞した津村記久子と町田康による、読売新聞2月11日(朝刊)の対談)
一方、宇野浩二は織田作を評して、「あなたの小説は、すらすらと、読め、よみながら、せかせかと追いたてられるような気のすするところはあるけれど、読み出したら、むちゅうで、しまいまで読みとおしてしまう、が、読んでしまってから、いつも、たいてい巧みな嘘をつかれた、というような気がする」と述べている。
「せかせか追い立てられるような感じで、しまいまで読んでしまい、嘘をつかれた気がする」のは、町田の小説と同じ感覚ではなかろうか。(淀)
小説については、従来、2つの流派が考えられた。(中村明『作家の文体』)
?流麗派―和歌的文章―谷崎潤一郎
?簡潔派―俳句的文章―志賀直哉
これに、
?饒舌派―西鶴、織田作之助(市井的戯作的草紙的説話的?)を加えることができ、町田の文体もこの饒舌派に属しよう。(淀)
3.「パンク的支離滅裂的文章」
へらへらコミック的、ファンキー的、支離滅裂的会話派である。
「しかし、なあ、はっきりいうぜ、おい、貴様の二人の娘、特に清子のほうはなあ、てめぇがどこの誰だか全然しらないんだよ。なあ、おい、はっきりしろよ、馬鹿野郎、って、自分は、液晶画面に映った坂本清十郎に話しかけていた」(『人間の屑』210P)
4.抽象に流れずすべてが具体的
『きれぎれ』解説の池澤夏樹氏によると、抽象に流れず、すべてが具体的としている。
この点は、杉山平一が織田作について、『大阪人』(2006年6月号「文士オダサク読本」)で語っていることと合致する。「織田君は抽象に走らない。観念の文学を嫌った。店屋の名前を書き連ね、細かい金額までびっしり書き込んでいく。」
以上にプラスして、「大阪弁の抽象性、あいまいさ、かるさ」が加算されよう。(淀)
◎町田の小説は、1〜4に掲げる織田作の文体と基本的に合致する。
1.「ずっと連綿体の、早いスピードで会話文もみんな地の文に入れていくような、織田作独特のやり方」(藤沢桓夫『回想の大阪文学』1983年刊、93P)
「……」と彼は言った、などという月並みな文章と織田作自身が否定的である。(織田作『神経』より)
西鶴の連俳的な早いテンポ、パンクロックのような乱れ打ちのようなリズム?に共通性がありそうだ。(淀風庵)
2.「小説というものは、文章であるけれど、必ずしも行儀の良い文章、ちゃんと形の整った文章が最高点の文章であるわけではありません。…その人なりのくせ、その人だけのくせみたいものがある方が魅力的です。」(同94P)
3.「彼は(織田作)東京から思想がない、とかいわれてくさされたわけなんです。それで、健全とか健康とか一流とか重厚とか“芸術性”に対抗意識をもつようになり、逆に軽佻浮薄だと居直っていくわけです。」(杉山平一談、96P)
4.「織田君は抽象に走らない。観念の文学を嫌った。店屋の名前を書き連ね、細かい金額までびっしり書き込んでいく。名前好き、数字好き。井原西鶴を意識する以前から、織田君には西鶴と通じ合う文学気質があったと、私は見ています。」((『大阪人』2006年6月号より、杉山平一文)
「織田君は宇野さん(浩二)が手掛けた語りの文学の地盤を固めた。野坂昭如さん、町田康さんらが受け継いでいく。語りの世界も大阪の持ち味ですね」(『大阪人』2006年6月号より、杉山平一文)という見解に至るのである。
さらに、大谷晃一は『織田作之助作品集』第3巻の解説において、「彼が夢見たように、いまは私小説信仰はすたれ、彼の大阪のしゃべくり風の文体が、野坂昭如氏や町田康氏らによって受けつがれ、生きつがれ、輝いているのである。」と述べている。
●町田康の文体について
(ウィキペディアより)
独自の文体、語法、話法を確立。スラップスティックな笑いに象徴される物語や、描写におけるナンセンスと馬鹿馬鹿しさの徹底ぶりは、上方落語を源流とし、前述のロックミュージック、時代劇、河内音頭などの影響があるとされる。またプロットは嘉村礒多や近松秋江等の第二次大戦以前の破滅的な私小説や、織田作之助、太宰治などの新戯作派の系譜を受け継ぐと評される。
(プロット:物語を作るときの設計図・構想のことを指す。物語のあらすじ、登場人物の設定や相関図、事件、小道具、世界観などがプロットに含まれる。
スラップスティック:どたばたギャグ)
1.「遊び感覚の充満する冗文体」〜冗漫・冗長・冗談・冗語・冗句・ジョーク〜
町田の作品全体を通して、笑いを誘う態度と言葉に溢れており、一言でいえば「冗文体」である。
初めまごつくが、何やこれと思いながら、巻き込まれて納得してしまう。これは浮遊感やインボルブ感といえようか。(淀風庵)
2.連綿語り文体で雄弁にして饒舌
文体的には、饒舌しゃべくり体、物語の早い展開テンポとリズム感が似通っているように思える。これを「いらちっぽい」テンポと感じる大阪の読者も多かろう。 (登場人物の死さえ一言であっけなく片付ける)
町田自身が次のように語っている。
「僕は小説で大切なのは、音楽のノイズ(雑音)にあたる部分をカットしないことだと思います」「世の中の新聞や雑誌に載るニュースや記事は、理路整然としている。でも、それを根底から問い詰め、排除されたものをとらえ直すことで小説は始まる。パンクとは疑うことです」(第140回芥川賞を受賞した津村記久子と町田康による、読売新聞2月11日(朝刊)の対談)
一方、宇野浩二は織田作を評して、「あなたの小説は、すらすらと、読め、よみながら、せかせかと追いたてられるような気のすするところはあるけれど、読み出したら、むちゅうで、しまいまで読みとおしてしまう、が、読んでしまってから、いつも、たいてい巧みな嘘をつかれた、というような気がする」と述べている。
「せかせか追い立てられるような感じで、しまいまで読んでしまい、嘘をつかれた気がする」のは、町田の小説と同じ感覚ではなかろうか。(淀)
小説については、従来、2つの流派が考えられた。(中村明『作家の文体』)
?流麗派―和歌的文章―谷崎潤一郎
?簡潔派―俳句的文章―志賀直哉
これに、
?饒舌派―西鶴、織田作之助(市井的戯作的草紙的説話的?)を加えることができ、町田の文体もこの饒舌派に属しよう。(淀)
3.「パンク的支離滅裂的文章」
へらへらコミック的、ファンキー的、支離滅裂的会話派である。
「しかし、なあ、はっきりいうぜ、おい、貴様の二人の娘、特に清子のほうはなあ、てめぇがどこの誰だか全然しらないんだよ。なあ、おい、はっきりしろよ、馬鹿野郎、って、自分は、液晶画面に映った坂本清十郎に話しかけていた」(『人間の屑』210P)
4.抽象に流れずすべてが具体的
『きれぎれ』解説の池澤夏樹氏によると、抽象に流れず、すべてが具体的としている。
この点は、杉山平一が織田作について、『大阪人』(2006年6月号「文士オダサク読本」)で語っていることと合致する。「織田君は抽象に走らない。観念の文学を嫌った。店屋の名前を書き連ね、細かい金額までびっしり書き込んでいく。」
以上にプラスして、「大阪弁の抽象性、あいまいさ、かるさ」が加算されよう。(淀)
|
|
|
|
|
|
|
|
オダサク倶楽部 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
オダサク倶楽部のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75487人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6447人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人