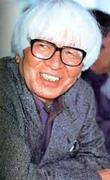8月にmixiに参加したばかりの新人です。
早速「司馬遼太郎」コミュに入会しましたが、ざっとメンバー諸兄のコメントを拝見しましたが、いささか違和感をおぼえました。
つまりは熱狂的な「司馬教」信者ばかりだということ、教祖・遼太郎さまの仰ることなら一切異論をはさまない方々の集まりのように見受けられるのです。
私自身、人後に落ちない司馬ファンではあるけれど、司馬さんが何から何まですぐれていたとは思えない。長所ばかりで成り立っている人間は存在しないように、司馬さんにだって至らぬ点、不足している点はあるはずです。
そんな思いから、このトピックをつくりました。
まずは私の年来の持説を聞いていただきましょう。
「菜の花の沖」「箱根の坂」「韃靼疾風録」・・・これらを私は司馬さんの三大愚作と評しています。そのわけは、人物がまったく描けていないから。
司馬作品の面白さは、歴史をつくってきたのは人間であること、その人間に作者が惚れ込んでいること、の二つにあります。
たとえば、「燃えよ剣」の土方歳三、「国盗り物語」の斎藤道三、「関が原」の石田光成、「竜馬がゆく」の坂本竜馬、「世に棲む日々」の高杉晋作などの人物像の描き方はどうでしょう。
上記三作においては、主人公への惚れ方も希薄で、彼らの躍動感が伝わってこないのです。
私は、ある時期から、司馬さんは人物を通して歴史を描くことから、歴史そのものを正面から描こうとしたように思えてなりません。
「余談ながら」で歴史の背景を描いているうちはよかったが、「余談」が前面に出てきた頃から、小説としての面白さが急に薄れてきた、といえないでしょうか。
ノモンハンをあれだけ調べていながら書かなかったのは、司馬さん自身が小説を書けなくなった自分を自覚していたからだ、と私は思っています。
「ノモンハンを書くと気が狂っちゃうから」というご自身の述懐は、司馬さん流の「韜晦」というべきでしょう。
小説を書けなくなった分、「街道をゆく」や「この国のかたち」といった分野が厚みを増した、と私は考えています。
私たちは、司馬さんの面白くなくなった小説をこれ以上読まされなくて幸せでした。
早速「司馬遼太郎」コミュに入会しましたが、ざっとメンバー諸兄のコメントを拝見しましたが、いささか違和感をおぼえました。
つまりは熱狂的な「司馬教」信者ばかりだということ、教祖・遼太郎さまの仰ることなら一切異論をはさまない方々の集まりのように見受けられるのです。
私自身、人後に落ちない司馬ファンではあるけれど、司馬さんが何から何まですぐれていたとは思えない。長所ばかりで成り立っている人間は存在しないように、司馬さんにだって至らぬ点、不足している点はあるはずです。
そんな思いから、このトピックをつくりました。
まずは私の年来の持説を聞いていただきましょう。
「菜の花の沖」「箱根の坂」「韃靼疾風録」・・・これらを私は司馬さんの三大愚作と評しています。そのわけは、人物がまったく描けていないから。
司馬作品の面白さは、歴史をつくってきたのは人間であること、その人間に作者が惚れ込んでいること、の二つにあります。
たとえば、「燃えよ剣」の土方歳三、「国盗り物語」の斎藤道三、「関が原」の石田光成、「竜馬がゆく」の坂本竜馬、「世に棲む日々」の高杉晋作などの人物像の描き方はどうでしょう。
上記三作においては、主人公への惚れ方も希薄で、彼らの躍動感が伝わってこないのです。
私は、ある時期から、司馬さんは人物を通して歴史を描くことから、歴史そのものを正面から描こうとしたように思えてなりません。
「余談ながら」で歴史の背景を描いているうちはよかったが、「余談」が前面に出てきた頃から、小説としての面白さが急に薄れてきた、といえないでしょうか。
ノモンハンをあれだけ調べていながら書かなかったのは、司馬さん自身が小説を書けなくなった自分を自覚していたからだ、と私は思っています。
「ノモンハンを書くと気が狂っちゃうから」というご自身の述懐は、司馬さん流の「韜晦」というべきでしょう。
小説を書けなくなった分、「街道をゆく」や「この国のかたち」といった分野が厚みを増した、と私は考えています。
私たちは、司馬さんの面白くなくなった小説をこれ以上読まされなくて幸せでした。
|
|
|
|
コメント(247)
天皇制か…
他のコミュをみていてもそうなのですが、
火薬庫ですね。
大爆発の予感がしますが、面白いかも。
今後の展開に期待です。
僕も天皇については、可もなく不可もなくで、
歴史的には、例外はあるとしても、
人格を持たないフラッグのような存在だったのでは、
と思います。
つまり京をとって錦の旗を立てるというような
その程度の象徴的存在でしかなく、
物語のメインには登場してこない存在なのでは、
と考えています。
ただ皆さんの話を聞いていると、
それにしても書かれなさすぎるという面は、
あるのかもと思いました。
戦争経験者は、天皇に対する態度が、複雑だという印象を
持っています。
同じ時代に生きた人なのに、肯定否定がはっきり分かれていたりします。
司馬さんも戦争による影響を受けていたのかな。
な〜んて推測します。
他のコミュをみていてもそうなのですが、
火薬庫ですね。
大爆発の予感がしますが、面白いかも。
今後の展開に期待です。
僕も天皇については、可もなく不可もなくで、
歴史的には、例外はあるとしても、
人格を持たないフラッグのような存在だったのでは、
と思います。
つまり京をとって錦の旗を立てるというような
その程度の象徴的存在でしかなく、
物語のメインには登場してこない存在なのでは、
と考えています。
ただ皆さんの話を聞いていると、
それにしても書かれなさすぎるという面は、
あるのかもと思いました。
戦争経験者は、天皇に対する態度が、複雑だという印象を
持っています。
同じ時代に生きた人なのに、肯定否定がはっきり分かれていたりします。
司馬さんも戦争による影響を受けていたのかな。
な〜んて推測します。
TAKさん>
うーん。言葉がうまく見つからなかったんであら捜しって書いちゃった面もあるんですが。。。
というか、私もそこまで天皇については可もなく不可もなくです。
戦前の生まれの司馬さんが特別な思いを持っていたかどうかはわかりませんが、それでもあの人が、意図的に書かなかったとは思えなかったんでそういう書きかたになっちゃいました。
街道が行くにせよ、本人のメッセージ的なものと考えるのか、それとも、作家さんですから(特に新聞連載しかされたことがない小説家さんですから)読者を意識して書いているのかどっちのスタンスだったんでしょう?
この考え方の違いによってだいぶ意識が変わってくると思いませんかね??
うーん。言葉がうまく見つからなかったんであら捜しって書いちゃった面もあるんですが。。。
というか、私もそこまで天皇については可もなく不可もなくです。
戦前の生まれの司馬さんが特別な思いを持っていたかどうかはわかりませんが、それでもあの人が、意図的に書かなかったとは思えなかったんでそういう書きかたになっちゃいました。
街道が行くにせよ、本人のメッセージ的なものと考えるのか、それとも、作家さんですから(特に新聞連載しかされたことがない小説家さんですから)読者を意識して書いているのかどっちのスタンスだったんでしょう?
この考え方の違いによってだいぶ意識が変わってくると思いませんかね??
一応続きを…
江戸以前の天皇制も、明治以後も、大雑把に言えば「君臨すれども統治せず」であって、歴史上の出来事で天皇が大きな影響力を持つ場面はさほど多くは無いわけです。だとすれば、司馬の著作で登場回数が少ないのは、不自然とはいえないでしょう。例外が後醍醐天皇で、『街道をゆく』でも「因幡・伯耆のみち」で登場しています。
このように考えると、「意図的に天皇の問題を書かなかった」というのはあたらないように思います。
ところで、私が中学高校の頃受けた授業では、明治憲法下の日本は天皇による専制君主の国、みたいな扱いでした。明治憲法の字ずらだけを追うとそのように解釈できないことも無いですが、実際にはこの解釈がいきすぎなのは明らかで、たとえば昭和天皇はイギリス型の立憲君主制を念頭に、政治にはいちいち口を挟まない態度を守っていたように思います。
司馬は自らの体験として、天皇機関説に基づく教育を受けたこと、軍隊でも天皇陛下という言葉にがんじがらめにされるような経験は無かった由のことを書いています。
その一方で、私も佐高信が『司馬遼太郎と藤沢周平』で指摘したように、司馬は天皇の問題を軽視しているのでは?という感じを持っています。
日本史上、大きな政権交代の際には、たびたび天皇の権威が利用されています。室町幕府を倒した織田信長然り、明治維新の薩長然り。
とりわけ昭和前期という時代は、天皇の権威を軍部がもっとも強力に利用した時代とも取れるわけです。言い換えれば、天皇の権威という隠れ蓑なしには、統帥権の暴走も不可能だったのではないか?と私は思うのです。個人としての天皇の影響力は大きなものではないとしても、制度としての天皇にはかなりの影響力があった(ある)はずです。
そういう意味では、司馬は統帥権の暴走が自らの意思にはそぐわないものだったこと、またそうかといって軍部にあからさまに抵抗するのも、立憲君主制の見地からははばかられたことを意識しすぎて、権威としての天皇制の、日本における影響力を軽視していたのかもしれない、というように思うのです。
ダラダラと長くなってしまいましたが、いずれにしても意図的あるいは恣意的に天皇について書かなかったわけではないんじゃないでしょうか。
江戸以前の天皇制も、明治以後も、大雑把に言えば「君臨すれども統治せず」であって、歴史上の出来事で天皇が大きな影響力を持つ場面はさほど多くは無いわけです。だとすれば、司馬の著作で登場回数が少ないのは、不自然とはいえないでしょう。例外が後醍醐天皇で、『街道をゆく』でも「因幡・伯耆のみち」で登場しています。
このように考えると、「意図的に天皇の問題を書かなかった」というのはあたらないように思います。
ところで、私が中学高校の頃受けた授業では、明治憲法下の日本は天皇による専制君主の国、みたいな扱いでした。明治憲法の字ずらだけを追うとそのように解釈できないことも無いですが、実際にはこの解釈がいきすぎなのは明らかで、たとえば昭和天皇はイギリス型の立憲君主制を念頭に、政治にはいちいち口を挟まない態度を守っていたように思います。
司馬は自らの体験として、天皇機関説に基づく教育を受けたこと、軍隊でも天皇陛下という言葉にがんじがらめにされるような経験は無かった由のことを書いています。
その一方で、私も佐高信が『司馬遼太郎と藤沢周平』で指摘したように、司馬は天皇の問題を軽視しているのでは?という感じを持っています。
日本史上、大きな政権交代の際には、たびたび天皇の権威が利用されています。室町幕府を倒した織田信長然り、明治維新の薩長然り。
とりわけ昭和前期という時代は、天皇の権威を軍部がもっとも強力に利用した時代とも取れるわけです。言い換えれば、天皇の権威という隠れ蓑なしには、統帥権の暴走も不可能だったのではないか?と私は思うのです。個人としての天皇の影響力は大きなものではないとしても、制度としての天皇にはかなりの影響力があった(ある)はずです。
そういう意味では、司馬は統帥権の暴走が自らの意思にはそぐわないものだったこと、またそうかといって軍部にあからさまに抵抗するのも、立憲君主制の見地からははばかられたことを意識しすぎて、権威としての天皇制の、日本における影響力を軽視していたのかもしれない、というように思うのです。
ダラダラと長くなってしまいましたが、いずれにしても意図的あるいは恣意的に天皇について書かなかったわけではないんじゃないでしょうか。
少なくとも昭和天皇崩御以降は、意図的に避けているようですよ。
平成18年の文芸春秋二月臨時増刊の特集号の記事で、
「この国のかたち」執筆時に原稿とともに送られた手紙に、
「(昭和天皇)崩御前後、天皇々々というのもいやですね。
天皇は、戦前もそうでしたが、戦後もことさら論ずべきものでは
ないです。ことさらに論じなければ益があり、論じすぎると
害があります」とあります。崩御直後の原稿に添えられていた
そうです。本音でしょうね。
関川夏央氏と船曳建夫氏の対談で、司馬氏の皇室観について
触れていて、面白かったです。
以前写楽斎さんにご教授頂いた件と絡むのですが、
反共へのカウンターとして司馬史観が利用された事に対しての
嫌悪感から、天皇の問題について意識して避けられていたのではないか、
というのが僕の想像です。
ご自身はあくまで思想的にはフリーで居たかったのではないかと。
「書きたくても書けない」ということがわかる様なエピソードが無いと、
説得力もなにも無いんですけどね。
平成18年の文芸春秋二月臨時増刊の特集号の記事で、
「この国のかたち」執筆時に原稿とともに送られた手紙に、
「(昭和天皇)崩御前後、天皇々々というのもいやですね。
天皇は、戦前もそうでしたが、戦後もことさら論ずべきものでは
ないです。ことさらに論じなければ益があり、論じすぎると
害があります」とあります。崩御直後の原稿に添えられていた
そうです。本音でしょうね。
関川夏央氏と船曳建夫氏の対談で、司馬氏の皇室観について
触れていて、面白かったです。
以前写楽斎さんにご教授頂いた件と絡むのですが、
反共へのカウンターとして司馬史観が利用された事に対しての
嫌悪感から、天皇の問題について意識して避けられていたのではないか、
というのが僕の想像です。
ご自身はあくまで思想的にはフリーで居たかったのではないかと。
「書きたくても書けない」ということがわかる様なエピソードが無いと、
説得力もなにも無いんですけどね。
手賀の河太郎です。
のあばばさんの示唆に基いて、司馬さんが昭和天皇について書かれた文章がみつかりました。昭和天皇ご逝去の直後(平成元年1月8日)、『風塵抄』に掲載されたものです。
これこそ私が捜し求めていたもので、司馬さんが昭和天皇の戦争責任などつゆほども考えておられなかったことが証明されたのは、まことに嬉しいことでした。
(松本氏はこれを読んでいないのでしょうか?)
のあばばさんがなぜか公表をためらっておられるので、少し長くなりますが、私が代わって紹介します。
『空に徹しぬいた偉大さ』
(冒頭は割愛)
「憲法をもった日本は法による国家になりました。明治は、その手習い時代でした。明治政府は、二人の法学者を英国とドイツに派遣して、解釈学を確立させました。
確立されたのは、やっと大正初年でした。皇太子だった昭和天皇は、徹底的に憲法教育をうけられたのです。
その生涯は、渾身でもって憲法の人でした。
明治憲法は、三権(立法・行政・司法)が分立している点で、堂々たるものでした。行政の代表はむろん内閣でした。首相もまた国務大臣の一員で、さらに重要なことは、その国務大臣たちが、一人ずつ天皇に対して輔弼(ホヒツ:たすけること。法律用語)するという責任をもっているということでした。
しかもその責任は首相以下の国務大臣において最終だったのです。
最終とは、責任が天皇にまで及ばないということでした。
このことは、法という以上に哲学に似た微妙な内容をもっています。このあたり、英国の国王における“君臨すれども統治せず”というのに似ていますが、明治憲法下での天皇の場は、仏教でいう空(クウ)という哲学概念が法制化されたものと理解したほうが、いいかと思います。
憲法上の天皇が、空の場にいるということは、政治・行政でのいかなる行為もしないというものでした。くりかえしますが、責任はすべて首相以下の国務大臣、および参謀総長(陸軍)・軍令部長(海軍)などにありました。
ところが、昭和に入って、三権のそとにあった陸軍の参謀本部が「統帥権(トウスイケン)」というとほうもないものをもちだしたのです。
この権によって軍は昭和6年(1931)に“満州事変”をおこし、とくに昭和13年(1938)には国家総動員法というものがつくられ、事実上、軍(統帥権)が国家をまるごと呑みこんだかたちになりました。
つまりは、統帥権が、立憲のいのちともいうべき三権に超越する存在になったのです。
七年後に、かれらは国家そのものをつぶしたことは、説明するまでもありません。
統帥権をここまで肥大させたのは、“法による国家”(立憲国家)を愛しぬく情熱が、一般にまだ未熟だったのかもしれません。
そのような前述の“七年間”においても、天皇は憲法上のご自分の“空の場”をつらぬかれ、ナマミの政治行為者になるという“違憲”を決して犯されなかったのです。
説明風に申しますが、陸軍の参謀総長もまた、内閣の国務大臣と同様、輔弼の責任をもっていました。責任は、この場合も、参謀総長において最終でした。最終であるということは、前述の“七年間”にあっては、参謀本部さえその気になれば、議会にも首相にも内緒でなにをやってもいいというものだったのです。げんに日中戦争をやりながら、太平洋戦争もやるという、信じがたいことをかれらはやりました。
世界史のなかで億兆の人生が生死しましたが、このふしぎな法的存在についての苦悩ばかりは、だれも味わったことのない性質のものでした。
もっとも、ただ一度だけ、この空の場から出られたことがあります。鈴木貫太郎首相以下に示された終戦の決断でした。天皇としては、違憲行為でした。
戦後の日本国憲法で、天皇は「象徴」ということになりました。これもまた人類の歴史に経験例のない法的存在でした。それを、ナマミの感情と肉体をもちながら、みずから法に化したがごとくになしとげられたのです。
私どもの涙は、そういう稀有な偉大さにこそそそがれるべきだと思うのです。ただ、そのことを思うと、あらたに涙のあふれる思いがします。後世のひとびとも、きっとそうにちがいありません。(完)」
のあばばさんの示唆に基いて、司馬さんが昭和天皇について書かれた文章がみつかりました。昭和天皇ご逝去の直後(平成元年1月8日)、『風塵抄』に掲載されたものです。
これこそ私が捜し求めていたもので、司馬さんが昭和天皇の戦争責任などつゆほども考えておられなかったことが証明されたのは、まことに嬉しいことでした。
(松本氏はこれを読んでいないのでしょうか?)
のあばばさんがなぜか公表をためらっておられるので、少し長くなりますが、私が代わって紹介します。
『空に徹しぬいた偉大さ』
(冒頭は割愛)
「憲法をもった日本は法による国家になりました。明治は、その手習い時代でした。明治政府は、二人の法学者を英国とドイツに派遣して、解釈学を確立させました。
確立されたのは、やっと大正初年でした。皇太子だった昭和天皇は、徹底的に憲法教育をうけられたのです。
その生涯は、渾身でもって憲法の人でした。
明治憲法は、三権(立法・行政・司法)が分立している点で、堂々たるものでした。行政の代表はむろん内閣でした。首相もまた国務大臣の一員で、さらに重要なことは、その国務大臣たちが、一人ずつ天皇に対して輔弼(ホヒツ:たすけること。法律用語)するという責任をもっているということでした。
しかもその責任は首相以下の国務大臣において最終だったのです。
最終とは、責任が天皇にまで及ばないということでした。
このことは、法という以上に哲学に似た微妙な内容をもっています。このあたり、英国の国王における“君臨すれども統治せず”というのに似ていますが、明治憲法下での天皇の場は、仏教でいう空(クウ)という哲学概念が法制化されたものと理解したほうが、いいかと思います。
憲法上の天皇が、空の場にいるということは、政治・行政でのいかなる行為もしないというものでした。くりかえしますが、責任はすべて首相以下の国務大臣、および参謀総長(陸軍)・軍令部長(海軍)などにありました。
ところが、昭和に入って、三権のそとにあった陸軍の参謀本部が「統帥権(トウスイケン)」というとほうもないものをもちだしたのです。
この権によって軍は昭和6年(1931)に“満州事変”をおこし、とくに昭和13年(1938)には国家総動員法というものがつくられ、事実上、軍(統帥権)が国家をまるごと呑みこんだかたちになりました。
つまりは、統帥権が、立憲のいのちともいうべき三権に超越する存在になったのです。
七年後に、かれらは国家そのものをつぶしたことは、説明するまでもありません。
統帥権をここまで肥大させたのは、“法による国家”(立憲国家)を愛しぬく情熱が、一般にまだ未熟だったのかもしれません。
そのような前述の“七年間”においても、天皇は憲法上のご自分の“空の場”をつらぬかれ、ナマミの政治行為者になるという“違憲”を決して犯されなかったのです。
説明風に申しますが、陸軍の参謀総長もまた、内閣の国務大臣と同様、輔弼の責任をもっていました。責任は、この場合も、参謀総長において最終でした。最終であるということは、前述の“七年間”にあっては、参謀本部さえその気になれば、議会にも首相にも内緒でなにをやってもいいというものだったのです。げんに日中戦争をやりながら、太平洋戦争もやるという、信じがたいことをかれらはやりました。
世界史のなかで億兆の人生が生死しましたが、このふしぎな法的存在についての苦悩ばかりは、だれも味わったことのない性質のものでした。
もっとも、ただ一度だけ、この空の場から出られたことがあります。鈴木貫太郎首相以下に示された終戦の決断でした。天皇としては、違憲行為でした。
戦後の日本国憲法で、天皇は「象徴」ということになりました。これもまた人類の歴史に経験例のない法的存在でした。それを、ナマミの感情と肉体をもちながら、みずから法に化したがごとくになしとげられたのです。
私どもの涙は、そういう稀有な偉大さにこそそそがれるべきだと思うのです。ただ、そのことを思うと、あらたに涙のあふれる思いがします。後世のひとびとも、きっとそうにちがいありません。(完)」
昭和天皇が政治・行政に対して干渉を控えていたのは、
たしかに「空に徹しぬいた偉大さ」で指摘されている通りだと思います。
しかし「空の場」から出たのが、終戦の決断の一度だけ、という点には私は異論があります。
以下、何点かあげます。226事件の時には、反乱兵に同情的な内容だった軍首脳部の上奏を毅然とした態度で突っぱねました。張作霖爆殺事件の処理をめぐっては、当時の田中義一首相の曖昧な態度を叱責したそうです。(この結果田中首相は辞職し、いご昭和天皇は一層空の立場に徹することを心がけたとも言われています。)また御前会議は終戦のときだけでなく、開戦のときを含めて10回以上開催されていて、昭和天皇が発言したのも終戦の1回だけではありません。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/gozennkaigi.htm
これらの事柄は、大筋に言って昭和天皇が軍部の暴走に批判的で、また開戦にも消極的だったという印象を抱かせます。と同時に、天皇という立場は、昭和天皇が自らを戒めていたほど、あるいは司馬が主張するほどには、周囲の人間にとっては「空」ではなく、常に様々にその権威を利用されるものであったことを示しているように思います。さらに天皇自身が望めば、自らの意向を政治・行政によりはっきりとあらわすことも可能であったとみるべきではないでしょうか。
もちろん、そうすべきだったと言っているわけではありません。
たしかに「空に徹しぬいた偉大さ」で指摘されている通りだと思います。
しかし「空の場」から出たのが、終戦の決断の一度だけ、という点には私は異論があります。
以下、何点かあげます。226事件の時には、反乱兵に同情的な内容だった軍首脳部の上奏を毅然とした態度で突っぱねました。張作霖爆殺事件の処理をめぐっては、当時の田中義一首相の曖昧な態度を叱責したそうです。(この結果田中首相は辞職し、いご昭和天皇は一層空の立場に徹することを心がけたとも言われています。)また御前会議は終戦のときだけでなく、開戦のときを含めて10回以上開催されていて、昭和天皇が発言したのも終戦の1回だけではありません。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/gozennkaigi.htm
これらの事柄は、大筋に言って昭和天皇が軍部の暴走に批判的で、また開戦にも消極的だったという印象を抱かせます。と同時に、天皇という立場は、昭和天皇が自らを戒めていたほど、あるいは司馬が主張するほどには、周囲の人間にとっては「空」ではなく、常に様々にその権威を利用されるものであったことを示しているように思います。さらに天皇自身が望めば、自らの意向を政治・行政によりはっきりとあらわすことも可能であったとみるべきではないでしょうか。
もちろん、そうすべきだったと言っているわけではありません。
転載を控えたのは、一応mixiは営利団体ですから、
運営局に配慮したというだけのことです。
トピ主さんの方針であるのなら、特に異論はありません。
戦争中の天皇の存在については、
僕なんかはまったくイメージが湧かないので、
あくまで司馬さんにとってという点で考えてみると、
『空に徹しぬいた偉大さ』は文面どおりの意味なのかな。
とちょっと疑ってしまいます。
司馬さんはとにかく統帥権というものを憎悪していたと思います。
自らと「得体の知れない何か」との対話という異色の形で、
表現する(せざるを得ない)ほど、
何か整理のつかないものだったのではないかと思います。
統帥権の理屈を突き詰めていくと、最終的にそれを是正できるのは天皇しかいません。
法的に責任があるとか、ないとかは別にして、
理論上天皇の判断が最後の砦だったと思います。
そう考えると、統帥権の暴走をなぜ天皇は食い止められなかったのかという、
疑問は当然に生ずると思います
また判断出来た、出来なかったは別にしても、
最終的な決定者としての責任は、
法的にはともかく、道義的に問われても別に不思議ではないと思います。
統帥権をあれだけ憎悪している人が、
その矛先を天皇に向けないというのは、ちょっと違和感を感じます。
もし天皇は、むしろ被害者なのだと本当に考えているのだとしたら、相当積極的に天皇を肯定している人ということになるのではないでしょうか。
しかし他の文面からはそういう思想は読み取れません。
『空に徹しぬいた偉大さ』は、実は強烈な皮肉なんだと
解釈したい誘惑にかられます。
もちろんそれは、竅った見方で、司馬さんの真意とは、
かけ離れたものでしょう。
しかし文面その通りとも思えない。
天皇は、論じるべきではない。
歴史上常に榧の外にあった存在を、
今更議論に組み込むこと自体がナンセンスなのであり、
戦時中実際にどう行動したかは、問題ではなく、
現代においても榧の外の存在として扱うべきだ。
という意味なのでは、と考えています。
運営局に配慮したというだけのことです。
トピ主さんの方針であるのなら、特に異論はありません。
戦争中の天皇の存在については、
僕なんかはまったくイメージが湧かないので、
あくまで司馬さんにとってという点で考えてみると、
『空に徹しぬいた偉大さ』は文面どおりの意味なのかな。
とちょっと疑ってしまいます。
司馬さんはとにかく統帥権というものを憎悪していたと思います。
自らと「得体の知れない何か」との対話という異色の形で、
表現する(せざるを得ない)ほど、
何か整理のつかないものだったのではないかと思います。
統帥権の理屈を突き詰めていくと、最終的にそれを是正できるのは天皇しかいません。
法的に責任があるとか、ないとかは別にして、
理論上天皇の判断が最後の砦だったと思います。
そう考えると、統帥権の暴走をなぜ天皇は食い止められなかったのかという、
疑問は当然に生ずると思います
また判断出来た、出来なかったは別にしても、
最終的な決定者としての責任は、
法的にはともかく、道義的に問われても別に不思議ではないと思います。
統帥権をあれだけ憎悪している人が、
その矛先を天皇に向けないというのは、ちょっと違和感を感じます。
もし天皇は、むしろ被害者なのだと本当に考えているのだとしたら、相当積極的に天皇を肯定している人ということになるのではないでしょうか。
しかし他の文面からはそういう思想は読み取れません。
『空に徹しぬいた偉大さ』は、実は強烈な皮肉なんだと
解釈したい誘惑にかられます。
もちろんそれは、竅った見方で、司馬さんの真意とは、
かけ離れたものでしょう。
しかし文面その通りとも思えない。
天皇は、論じるべきではない。
歴史上常に榧の外にあった存在を、
今更議論に組み込むこと自体がナンセンスなのであり、
戦時中実際にどう行動したかは、問題ではなく、
現代においても榧の外の存在として扱うべきだ。
という意味なのでは、と考えています。
日露戦争の時の軍艦購入時の独断はある程度「美談」となっているのに、第二次大戦時の暴走は過ちになってしまってるところなどは、やはり結局統帥権云々と言うより「結果が全て」と言う事なのかなあとか読んでて思ったことはあります(笑)。
ところで皆さんは、司馬先生と海音寺潮五郎の対談「日本歴史を点検する」(講談社文庫)は読まれていますか? この中で1章、「天皇制とはなにか」という項が設けられていて、司馬先生も積極的に(!)語っております。内容的には皆さん認識しておられる司馬先生の持論なので特筆するほどのものではないのですが、その対談の中で面白い場面があったので引用します。
司馬「天皇の話の続きですが――私は別に右翼でも左翼でもなく、また天皇が好きでも嫌いでもありませんが、天皇という問題を正しく認識しない以上、歴史がわからないと思うものですから、ついくどくなります。(〜以下略)」
この前文までの展開は明治維新の功績の話をしてて、半ば強引に司馬先生が(!)天皇の話に引き戻してるのですよ。これは上記の「風塵抄」「街道をゆく」に代表される司馬先生のスタンスと印象があまりにかけ離れてるんで、ちょっとご紹介したく思いました。
この対談は昭和44年。司馬先生も比較的まだお若い頃かもしれません。天皇に対するスタンスも、時期によって大分違ってくるでしょうね。
ところで皆さんは、司馬先生と海音寺潮五郎の対談「日本歴史を点検する」(講談社文庫)は読まれていますか? この中で1章、「天皇制とはなにか」という項が設けられていて、司馬先生も積極的に(!)語っております。内容的には皆さん認識しておられる司馬先生の持論なので特筆するほどのものではないのですが、その対談の中で面白い場面があったので引用します。
司馬「天皇の話の続きですが――私は別に右翼でも左翼でもなく、また天皇が好きでも嫌いでもありませんが、天皇という問題を正しく認識しない以上、歴史がわからないと思うものですから、ついくどくなります。(〜以下略)」
この前文までの展開は明治維新の功績の話をしてて、半ば強引に司馬先生が(!)天皇の話に引き戻してるのですよ。これは上記の「風塵抄」「街道をゆく」に代表される司馬先生のスタンスと印象があまりにかけ離れてるんで、ちょっとご紹介したく思いました。
この対談は昭和44年。司馬先生も比較的まだお若い頃かもしれません。天皇に対するスタンスも、時期によって大分違ってくるでしょうね。
トピックが停滞してしまったので提案というかお願いなんですが、
麦星農園さまのネタ元の佐高新による司馬批判の、サマリーだけでも提示願えないでしょうか。
僕が読んだ「著名人を切る!」みたいな企画の司馬批判は、城山三郎と比較して松下幸之助に対しての両者の対応を挙げ、司馬氏は「えらいひと」と表現したが城山三郎は松下幸之助に対し自己顕示欲の高い人であるとしたという、僕としてはどうでも良いような批判だったのですが、佐高新の司馬氏天皇軽視論(先の戦争の天皇責任軽視論ですか?)の骨子を知りたいのですが、ご提出頂いた資料が全く入手出来ません。
お手数ですがお願いしたいのです。
ご面倒であればさくっとスルーしてくださって結構です。
麦星農園さまのネタ元の佐高新による司馬批判の、サマリーだけでも提示願えないでしょうか。
僕が読んだ「著名人を切る!」みたいな企画の司馬批判は、城山三郎と比較して松下幸之助に対しての両者の対応を挙げ、司馬氏は「えらいひと」と表現したが城山三郎は松下幸之助に対し自己顕示欲の高い人であるとしたという、僕としてはどうでも良いような批判だったのですが、佐高新の司馬氏天皇軽視論(先の戦争の天皇責任軽視論ですか?)の骨子を知りたいのですが、ご提出頂いた資料が全く入手出来ません。
お手数ですがお願いしたいのです。
ご面倒であればさくっとスルーしてくださって結構です。
ええっと、まずは224から…
昭和天皇が明確に政策を方向付けるような意思決定をしたのは、終戦の御前会議だけかもしれません
そこらあたりを証明しようと思ったら、各会議の議事録や木戸幸一日記あたりを詳細に検討しなければわからないように思いますが、さすがにそこまで追求する気力もなく…
なんにしても、司馬の言うように終戦の決断以外は「空に徹しぬいた」とするのは、やはり事実との間にずれがあるように思います。
続いて227ですが…
恥ずかしながら「サマリー」という言葉の意味がピンと来なくて、どういう答え方がいいのか自信がないんですが、
とりあえずいくらか引用させていただきます。
(引用始まり)
「小田(実)が〜中略〜「アフリカなんかへ行って、商社員の家へいくと、天皇の団らんの写真掲げてあってびっくりするよ」「パーティーになると、『天皇陛下万歳』って言うもん。だって天皇誕生日のパーティーやってますよ」と紹介すると〜中略〜 後で告白しているように、そうしたことを知らなくて、司馬はびっくりしたらしい。司馬は「天皇というものは尾骶骨のようなもので、おれたちには関係ないものだと思って」きた。それで、その問題を除けて歴史を見てきたのである。」
(『司馬遼太郎と藤沢周平』p62〜63)
「『明治憲法下における天皇も、じつは、天皇自身が政治的にアクションできる機能をもっていなかった』というのは、司馬自身の願望を込めた解釈ではあっても、一般的な真実ではない。〜中略〜天皇および天皇制は明らかに陰惨なエンペラー的側面を持っていた。司馬に譲って「側面も」と言い換えてもいいが、それをまったく否定するのは、司馬が天皇制の問題に目をつぶっているからである。見ようとしないがゆえに見えなくなった。」
「『天皇というのはヒトラーみたいなもの』というヨーロッパ人の印象を「誤解」と言い切れないところに日本人における天皇制問題の根深さがあるのである。明らかにそれは「正解」部分を含んでいる。しかし、司馬は「誤解」どころか「誤答」とし、「このややこしさは、外国人どころか、そろそろ日本人にもわからなくなってきている」と逃げる。…天皇自身の無自覚、あるいは無意識に天皇制の「無責任の体系」が原因とするなら、それは天皇に親近感を抱く司馬自身にも感染している。司馬にもっとも明瞭に無自覚の無責任が表れているとも言えるのである。」(p88〜89)
(引用終わり)
ここらあたりが、佐高信による「司馬遼太郎の天皇観」批判がよく出ている部分だと思いますが、最後のくだり(「天皇自身の無自覚」云々)は何のことだか私には意味がよくわかりません。
昭和天皇が明確に政策を方向付けるような意思決定をしたのは、終戦の御前会議だけかもしれません
そこらあたりを証明しようと思ったら、各会議の議事録や木戸幸一日記あたりを詳細に検討しなければわからないように思いますが、さすがにそこまで追求する気力もなく…
なんにしても、司馬の言うように終戦の決断以外は「空に徹しぬいた」とするのは、やはり事実との間にずれがあるように思います。
続いて227ですが…
恥ずかしながら「サマリー」という言葉の意味がピンと来なくて、どういう答え方がいいのか自信がないんですが、
とりあえずいくらか引用させていただきます。
(引用始まり)
「小田(実)が〜中略〜「アフリカなんかへ行って、商社員の家へいくと、天皇の団らんの写真掲げてあってびっくりするよ」「パーティーになると、『天皇陛下万歳』って言うもん。だって天皇誕生日のパーティーやってますよ」と紹介すると〜中略〜 後で告白しているように、そうしたことを知らなくて、司馬はびっくりしたらしい。司馬は「天皇というものは尾骶骨のようなもので、おれたちには関係ないものだと思って」きた。それで、その問題を除けて歴史を見てきたのである。」
(『司馬遼太郎と藤沢周平』p62〜63)
「『明治憲法下における天皇も、じつは、天皇自身が政治的にアクションできる機能をもっていなかった』というのは、司馬自身の願望を込めた解釈ではあっても、一般的な真実ではない。〜中略〜天皇および天皇制は明らかに陰惨なエンペラー的側面を持っていた。司馬に譲って「側面も」と言い換えてもいいが、それをまったく否定するのは、司馬が天皇制の問題に目をつぶっているからである。見ようとしないがゆえに見えなくなった。」
「『天皇というのはヒトラーみたいなもの』というヨーロッパ人の印象を「誤解」と言い切れないところに日本人における天皇制問題の根深さがあるのである。明らかにそれは「正解」部分を含んでいる。しかし、司馬は「誤解」どころか「誤答」とし、「このややこしさは、外国人どころか、そろそろ日本人にもわからなくなってきている」と逃げる。…天皇自身の無自覚、あるいは無意識に天皇制の「無責任の体系」が原因とするなら、それは天皇に親近感を抱く司馬自身にも感染している。司馬にもっとも明瞭に無自覚の無責任が表れているとも言えるのである。」(p88〜89)
(引用終わり)
ここらあたりが、佐高信による「司馬遼太郎の天皇観」批判がよく出ている部分だと思いますが、最後のくだり(「天皇自身の無自覚」云々)は何のことだか私には意味がよくわかりません。
>麦星農園 さま
ありがとうございました。
サマリー=要約です。そう書けば良かったですね。失礼しました。
現在、秦郁彦の「昭和史の謎を追う」を読んでいるのですが、
読めば読むほど、確かに「空に徹しぬいた」は無理があるなあ、と思います。
不勉強で申し訳ありません。
最後の「天皇自身の無自覚」の処ですが、司馬氏(を始め多くの日本人)
は天皇が最初っから神様だなんて思っていなかったわけで、天皇個人よりも
国体の方が問題だったのではないかと個人的には思っています。
本当に天皇=ヒトラーみたいなものであれば、二・二六事件や
満州事変などは発生するはずもなく、しかし二・二六事件を
自ら制圧しようとした裕仁天皇の心中を思えば、天皇=ヒトラーみたいなもの、も
「無自覚」もいささか的外れな指摘なのでは、と思います。
ありがとうございました。
サマリー=要約です。そう書けば良かったですね。失礼しました。
現在、秦郁彦の「昭和史の謎を追う」を読んでいるのですが、
読めば読むほど、確かに「空に徹しぬいた」は無理があるなあ、と思います。
不勉強で申し訳ありません。
最後の「天皇自身の無自覚」の処ですが、司馬氏(を始め多くの日本人)
は天皇が最初っから神様だなんて思っていなかったわけで、天皇個人よりも
国体の方が問題だったのではないかと個人的には思っています。
本当に天皇=ヒトラーみたいなものであれば、二・二六事件や
満州事変などは発生するはずもなく、しかし二・二六事件を
自ら制圧しようとした裕仁天皇の心中を思えば、天皇=ヒトラーみたいなもの、も
「無自覚」もいささか的外れな指摘なのでは、と思います。
> Martyさん
小説というフィクションを、エンターテイメントとして成立させるためには、読むものに「これは全くの嘘ではない」と信じさせるだけのリアリティが必要で、そうであればこそ、司馬さんも、「歴史的事実」を丹念に調べ上げて小説を書かれたのだと思います。
そうして、かなりのレベルで歴史的事実を下敷きにして、あれだけのリアリティをもって小説を書かれた司馬さんが、「これは歴史的事実とは無関係です」といってしまうと、そこも「嘘」になってしまい、変に韜晦して逃げてるようで、「興醒め」や「ユーモア」を通り越して、「卑怯」という事になってしまうように思います。
小説を書く、ということは、それだけの重さに耐え、手間ひまかけてリアリティのあるフィクションを書かねば何も表現されないわけで、人生の終わりが近づきつつありながら、言いたいことがたくさんあった司馬さんにとって、小説というまどろっこしい表現形態は優先順位が低くなってしまったのではないかと推測いたします。
小説というフィクションを、エンターテイメントとして成立させるためには、読むものに「これは全くの嘘ではない」と信じさせるだけのリアリティが必要で、そうであればこそ、司馬さんも、「歴史的事実」を丹念に調べ上げて小説を書かれたのだと思います。
そうして、かなりのレベルで歴史的事実を下敷きにして、あれだけのリアリティをもって小説を書かれた司馬さんが、「これは歴史的事実とは無関係です」といってしまうと、そこも「嘘」になってしまい、変に韜晦して逃げてるようで、「興醒め」や「ユーモア」を通り越して、「卑怯」という事になってしまうように思います。
小説を書く、ということは、それだけの重さに耐え、手間ひまかけてリアリティのあるフィクションを書かねば何も表現されないわけで、人生の終わりが近づきつつありながら、言いたいことがたくさんあった司馬さんにとって、小説というまどろっこしい表現形態は優先順位が低くなってしまったのではないかと推測いたします。
史観について語るのならば
「日本人を考える」は必読だと思います。
小説作品は史実を基にしていたとしてもフィクションでしかありませんし、
登場人物の思想感情が司馬さんのそれとは限りません。
「日本人を考える」から引用-------
戦争をしかけられたらどうするか。すぐに降伏すればいいんです。
戦争をやれば百万人は死ぬでしょう。それより無抵抗で、ハイ持てるだけ持っていって下さい、といえるくらいの生産力を持っていればすむことでしょう。
向こうが占領して住みついたら、これに同化しちゃえばいい。
それくらい柔軟な社会をつくることが、我々の社会の目的じゃないですか。
---------------------------------
私は今まで紛争は話し合いで解決するべきだなんて甘いことを言っていましたが、どうしても戦争になってしまう場合もあるかもしれません。
しかし、そんなとき無駄な血を流さないためには
すぐに降伏して相手国の国民になってしまえばいいのです。
仮に中国や北朝鮮に攻められたら日本人は中国人になって
中国の発展につくして、中国人として幸せになればいい。
生活レベルが落ちたりと多少不都合も出てくるでしょうが
自分や大切な家族が死ぬよりはよほどマシです。
反論もあるでしょうが、
戦後日本はアメリカとの同化の道を選びました。
この考え方を広まれば必然的に地球はひとつになれると思います。
「日本人を考える」は必読だと思います。
小説作品は史実を基にしていたとしてもフィクションでしかありませんし、
登場人物の思想感情が司馬さんのそれとは限りません。
「日本人を考える」から引用-------
戦争をしかけられたらどうするか。すぐに降伏すればいいんです。
戦争をやれば百万人は死ぬでしょう。それより無抵抗で、ハイ持てるだけ持っていって下さい、といえるくらいの生産力を持っていればすむことでしょう。
向こうが占領して住みついたら、これに同化しちゃえばいい。
それくらい柔軟な社会をつくることが、我々の社会の目的じゃないですか。
---------------------------------
私は今まで紛争は話し合いで解決するべきだなんて甘いことを言っていましたが、どうしても戦争になってしまう場合もあるかもしれません。
しかし、そんなとき無駄な血を流さないためには
すぐに降伏して相手国の国民になってしまえばいいのです。
仮に中国や北朝鮮に攻められたら日本人は中国人になって
中国の発展につくして、中国人として幸せになればいい。
生活レベルが落ちたりと多少不都合も出てくるでしょうが
自分や大切な家族が死ぬよりはよほどマシです。
反論もあるでしょうが、
戦後日本はアメリカとの同化の道を選びました。
この考え方を広まれば必然的に地球はひとつになれると思います。
あとで書き込みますが、いま準備中です。
もしかしたら別にトピ立てするかもしれません。
なんで司馬遼太郎を「小説家」でなく「歴史家」と規定したがる人がいるのか、
そこをポイントに議論させていただきたいと思います。
小説は世相を有る程度反映するものだから、思想の道具にされるのは
止むを得ないといえば止むを得ないとは思います。
ただ、彼を「歴史家」にクラスチェンジさせてまでしたいことといえば、
僕には2,3点思いつくことが有りますが、ちょっと自分で考えてから
もう一度書き込みたいと思います。
あと、この手の話題は「小説家」司馬遼太郎コミュにふさわしくないという
意見もあるっぽいので(理屈が全然わからなかったんですが)
今のうちやめとけ、という意見も頂戴します。
もしかしたら別にトピ立てするかもしれません。
なんで司馬遼太郎を「小説家」でなく「歴史家」と規定したがる人がいるのか、
そこをポイントに議論させていただきたいと思います。
小説は世相を有る程度反映するものだから、思想の道具にされるのは
止むを得ないといえば止むを得ないとは思います。
ただ、彼を「歴史家」にクラスチェンジさせてまでしたいことといえば、
僕には2,3点思いつくことが有りますが、ちょっと自分で考えてから
もう一度書き込みたいと思います。
あと、この手の話題は「小説家」司馬遼太郎コミュにふさわしくないという
意見もあるっぽいので(理屈が全然わからなかったんですが)
今のうちやめとけ、という意見も頂戴します。
>仮に中国や北朝鮮に攻められたら日本人は中国人になって
>中国の発展につくして、中国人として幸せになればいい。
それを、アイヌの人にも言えますかね?
>仮に大和に攻められたらアイヌ人は大和人になって
>大和の発展につくして、大和人として幸せになればいい。
既に、明治時代に日本人(大和民族)に同化政策を強いられ、自分達の言語、生活、文化を奪われたアイヌ民族の人たちの苦悩を、あなたは考えたことがありますか?それを、自分はよしとするんですかね?
民族とはなんでしょう?あなたの話している言葉は何語ですか?
どの言語を使って物を考えたり、自己主張をしているんですかね?
中国人に、中国語を話すことを強要され、あらゆる日本文化を捨てることを迫られて、「はいどうぞ」と言うのならば、日本人としてのアイデンティティーも、誇りも、自覚もまるでない。
>中国の発展につくして、中国人として幸せになればいい。
それを、アイヌの人にも言えますかね?
>仮に大和に攻められたらアイヌ人は大和人になって
>大和の発展につくして、大和人として幸せになればいい。
既に、明治時代に日本人(大和民族)に同化政策を強いられ、自分達の言語、生活、文化を奪われたアイヌ民族の人たちの苦悩を、あなたは考えたことがありますか?それを、自分はよしとするんですかね?
民族とはなんでしょう?あなたの話している言葉は何語ですか?
どの言語を使って物を考えたり、自己主張をしているんですかね?
中国人に、中国語を話すことを強要され、あらゆる日本文化を捨てることを迫られて、「はいどうぞ」と言うのならば、日本人としてのアイデンティティーも、誇りも、自覚もまるでない。
> にしとよさん
〉冷静に?
〉なんで?
トピ主さんの「冷静に」は、トピをたてた主旨についてかかれたコメントが、だいぶ前にあったようです。私も、このトピの頭の文章は、訂正できるならしてほしい気がしますが、mixiの機能的に難しいんでしょう。
私が使った「冷静に」は、「喧嘩腰ではない」という意味合いです。
「司馬作品の○○が好き」という話をいくら熱っぽく語っても、それに対して冷静さを欠いて喧嘩腰になるはずがないと思っています。
好き嫌いはそれぞれ自由ですから。
喧嘩して人に押しつけるべきものではない。
ですが、そこから離れて
「司馬先生がおっしゃるように、北朝鮮が来たら、金正日将軍様万歳を叫ぼう!」
と、いう話は、すでに「好き・嫌い」の話ではなく、「正しい・正しくない」の話で、明らかに正しくない主張にこだわり続ける人がいたら、そこからただの喧嘩に堕ちてく危険性はあります。
さて、もし万が一、「冷静(喧嘩腰でない)なんてくそ食らえ、自分以外の人間がどう感じようとどうでもええわ」という意味で、
「冷静?なんで?」
という言葉を発せられているなら、
「迷惑だからよそでやって」
としかいいようがありません。
〉冷静に?
〉なんで?
トピ主さんの「冷静に」は、トピをたてた主旨についてかかれたコメントが、だいぶ前にあったようです。私も、このトピの頭の文章は、訂正できるならしてほしい気がしますが、mixiの機能的に難しいんでしょう。
私が使った「冷静に」は、「喧嘩腰ではない」という意味合いです。
「司馬作品の○○が好き」という話をいくら熱っぽく語っても、それに対して冷静さを欠いて喧嘩腰になるはずがないと思っています。
好き嫌いはそれぞれ自由ですから。
喧嘩して人に押しつけるべきものではない。
ですが、そこから離れて
「司馬先生がおっしゃるように、北朝鮮が来たら、金正日将軍様万歳を叫ぼう!」
と、いう話は、すでに「好き・嫌い」の話ではなく、「正しい・正しくない」の話で、明らかに正しくない主張にこだわり続ける人がいたら、そこからただの喧嘩に堕ちてく危険性はあります。
さて、もし万が一、「冷静(喧嘩腰でない)なんてくそ食らえ、自分以外の人間がどう感じようとどうでもええわ」という意味で、
「冷静?なんで?」
という言葉を発せられているなら、
「迷惑だからよそでやって」
としかいいようがありません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
司馬遼太郎 更新情報
-
最新のアンケート
司馬遼太郎のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37832人
- 2位
- 酒好き
- 170655人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89518人