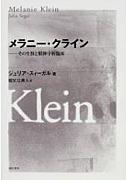両者の言っている事には親近性がある、と最近図書館でチラッと見たクリステヴァ関係の本に書いてあったのですが、具体的にどういう所から親近性があると判断するのか、分かる人がいたら教えていただきたいです。
で、その図書館でチラッ見た本からの記述はこうです。
西川直子「現代思想の冒険者たち クリステヴァ ポリロゴス」
クリステヴァの精神分析理論、<アブジェクシオン>や、<想像的父>や、メランコリーの理論には、クラインの理論との親近性が認められるのではないかと思われる
アブジェクシオンについては、浅田彰の「構造と力」と今村仁司の「暴力のオントロギー」「排除の構造」で出てきたと思います。
今村仁司「暴力のオントロギー」
徹底的におぞましい状況(アブジェクシオン)のなかに、自覚に向かう契機がある。バタイユ的弁証法はこの点にある。だからこそ、バタイユは、誰よりも早く、ヒロシマ・ナガサキとアウシュヴィッツの悲劇を、最も重要な経験とおさえ、それらをかけがえのない思想の対象とし、それらを思想的に生き抜く決意をした。
「排除の構造―力の一般経済序説」
第三項排除とは、任意の誰か(ユニーク性をもつ個人ないし集団)を周縁的存在にするだけでなく、しばしば秩序外にたたき出しさえする。下方排除とは、アブジェクシオン(abjection)である。
他の記述で目に付いたのは、
立川健二・山田広昭「現代言語論 ソシュール フロイト ウィトゲンシュタイン」
・サンボリックがジャック・ラカンのいう鏡像段階と去勢の発見をへたエディプス・コンプレックス期以後、すなわち主体の安定した自己同一性と言語の獲得の時期に対応するとすれば、セミオティックのほうはそれ以前の段階、すなわちメラニー・クラインのいう前エディプス期に相当するということができる。この段階において、幼児と母親は融合的な双数状態を形づくっており、母親は幼児にとっていまだ対象(objet)ではなく、それ以前のアブジェ(abjet)なのだ。両者はいまだにふたつの自己同一的主体として、あるいは主体/対象として分離・対峙することのない、見分けのつかない「分身」である。そして、幼児の言葉はいうまでもなく、母親が幼児に語りかける言葉でさえ、社会で流通している言語とはほど遠い、いわばアルカイックな「前言語」なのである。このことは、音声のレベルでも、語彙のレベルでも容易に観察されることだろう。
・彼女のもっとも代表的な著作である『詩的言語の革命』(1974年)で提出されたセミオティックは、言語・記号にさきだつ原初的な差異化の運動、名づけえない無意識的欲動の様態をとらえるための概念であるし、ついで『恐怖の権力』(1980年)で展開されたアブジェクシオンの理論も、言語と記号の秩序(=サンボリック)にはいる以前の、母親との融合状態にある主体のあり方、語りえない主体性危機の体験を照射しようとしたものであった。このように、クリステヴァは、言語によって前言語的な体験を語ること、しかも<理論言語>というきわめて抽象性が高く、情動にうったえることの少ない言語で語るということの不可能性を熟知したうえで、なおかつ言語化・理論化・形式化を敢行し、それに成功してきたのである。
で、その図書館でチラッ見た本からの記述はこうです。
西川直子「現代思想の冒険者たち クリステヴァ ポリロゴス」
クリステヴァの精神分析理論、<アブジェクシオン>や、<想像的父>や、メランコリーの理論には、クラインの理論との親近性が認められるのではないかと思われる
アブジェクシオンについては、浅田彰の「構造と力」と今村仁司の「暴力のオントロギー」「排除の構造」で出てきたと思います。
今村仁司「暴力のオントロギー」
徹底的におぞましい状況(アブジェクシオン)のなかに、自覚に向かう契機がある。バタイユ的弁証法はこの点にある。だからこそ、バタイユは、誰よりも早く、ヒロシマ・ナガサキとアウシュヴィッツの悲劇を、最も重要な経験とおさえ、それらをかけがえのない思想の対象とし、それらを思想的に生き抜く決意をした。
「排除の構造―力の一般経済序説」
第三項排除とは、任意の誰か(ユニーク性をもつ個人ないし集団)を周縁的存在にするだけでなく、しばしば秩序外にたたき出しさえする。下方排除とは、アブジェクシオン(abjection)である。
他の記述で目に付いたのは、
立川健二・山田広昭「現代言語論 ソシュール フロイト ウィトゲンシュタイン」
・サンボリックがジャック・ラカンのいう鏡像段階と去勢の発見をへたエディプス・コンプレックス期以後、すなわち主体の安定した自己同一性と言語の獲得の時期に対応するとすれば、セミオティックのほうはそれ以前の段階、すなわちメラニー・クラインのいう前エディプス期に相当するということができる。この段階において、幼児と母親は融合的な双数状態を形づくっており、母親は幼児にとっていまだ対象(objet)ではなく、それ以前のアブジェ(abjet)なのだ。両者はいまだにふたつの自己同一的主体として、あるいは主体/対象として分離・対峙することのない、見分けのつかない「分身」である。そして、幼児の言葉はいうまでもなく、母親が幼児に語りかける言葉でさえ、社会で流通している言語とはほど遠い、いわばアルカイックな「前言語」なのである。このことは、音声のレベルでも、語彙のレベルでも容易に観察されることだろう。
・彼女のもっとも代表的な著作である『詩的言語の革命』(1974年)で提出されたセミオティックは、言語・記号にさきだつ原初的な差異化の運動、名づけえない無意識的欲動の様態をとらえるための概念であるし、ついで『恐怖の権力』(1980年)で展開されたアブジェクシオンの理論も、言語と記号の秩序(=サンボリック)にはいる以前の、母親との融合状態にある主体のあり方、語りえない主体性危機の体験を照射しようとしたものであった。このように、クリステヴァは、言語によって前言語的な体験を語ること、しかも<理論言語>というきわめて抽象性が高く、情動にうったえることの少ない言語で語るということの不可能性を熟知したうえで、なおかつ言語化・理論化・形式化を敢行し、それに成功してきたのである。
|
|
|
|
コメント(10)
コメントありがとうございます。
断片的であやふやな知識しかないのでうまく返答できませんが。
前エディプス期を<母>と幼児が融合的な状態である、というのは私のような哲学・思想関係から精神分析に興味を持っている人の解釈でよくあるものだと思います。その状態の言語がクリステヴァのいうセミオティックで、そこに<父>が介入して<母>と子との癒着した全能感の状態に鮮やかな切り目を入れた後の状態の言語がサンボリックなのだと思います。<母><父>とカッコに入れているのは、現実の血のつながった母や父のみを意味しているわけではないからです。
「悪いおっぱい」は悪い対象というより、幼児が空腹時に手足をばたばたさせ自己主張しても満足を与えてくれないおっぱいの事で、「良いおっぱい」は空腹を感じて自己主張したら即座に母乳を与えてくれるおっぱいの事のように解釈しています。
これはある人が妄想分裂ポジションにあり、その人にとって私は肥大化した選民意識の担保で自分のものと思っている「おっぱい」なんだろうな、という私の実感と軽く目を通しただけの本のうろ覚えの知識に基づく解釈です。
クリステヴァ関係の文章をもう少しのせてみます。
西川直子「現代思想の冒険者たち クリステヴァ ポリロゴス」
・父が超自我、子が自我に対応するのにたいし、母はエスと対応することになる。フロイトによれば、自我も超自我も、発生論的にはエスから分化したものであるとされる。
・前エディプス期の心的体制は、<一次的ナルシシズム>と呼ばれる。
・アブジェクシオン abjectionとは、いまだ対象 objet とならずに一体化している母という前=対象 abjet/abject となって棄却されること、を意味している。通常のフランス語の用法では、アブジェクトは「おぞましい、唾棄すべき、卑劣な」の意味の形容詞であり、アブジェクシオンはその名詞形として「おぞましさ、汚辱、卑劣」といった意味で用いられる。クリステヴァは、abject や abjection の接頭語 ab に着目し、語源を汲みあげるかたちでこれらの語を用いたのである。ab は「分離、遠隔」を意味する接頭語であり、abject/abjection は、「分離すべく=投げ出されたもの」ないし「分離すべく=投げ出すこと(棄却すること)」と解される。それにたいして、対象 objet の ob は、「対立、反対」の意の接頭語であって、本来、「面前に対立するかたちで=投げ出されたもの」が「対象」というものなのである。
アブジェクト abject と同様の意味で用いられる abjet という語は、objet と abject にひっかけるかたちでつくられた造語であり、「いまだ対象となっていない、分離すべき、おぞましき前=対象」という意味がこの一語のなかに圧縮されている。
・否定性すなわち棄却のメカニズムを<前=対象の母>の棄却として語ることにより、棄却の舞台が、前=エディプス的体制である一次的ナルシシズムと、そこに生ずる原抑圧に限定されることになった。
・クリステヴァの語彙を用いれば、愛とは意味生成性である、ということになる。愛は、自己から分離されたものとしての対象の定立に関わる意識を生成し、語る主体、言語、ル・サンボリック(記号象徴体系)を生成する。したがって文化・歴史を生成するとされるのである。
断片的であやふやな知識しかないのでうまく返答できませんが。
前エディプス期を<母>と幼児が融合的な状態である、というのは私のような哲学・思想関係から精神分析に興味を持っている人の解釈でよくあるものだと思います。その状態の言語がクリステヴァのいうセミオティックで、そこに<父>が介入して<母>と子との癒着した全能感の状態に鮮やかな切り目を入れた後の状態の言語がサンボリックなのだと思います。<母><父>とカッコに入れているのは、現実の血のつながった母や父のみを意味しているわけではないからです。
「悪いおっぱい」は悪い対象というより、幼児が空腹時に手足をばたばたさせ自己主張しても満足を与えてくれないおっぱいの事で、「良いおっぱい」は空腹を感じて自己主張したら即座に母乳を与えてくれるおっぱいの事のように解釈しています。
これはある人が妄想分裂ポジションにあり、その人にとって私は肥大化した選民意識の担保で自分のものと思っている「おっぱい」なんだろうな、という私の実感と軽く目を通しただけの本のうろ覚えの知識に基づく解釈です。
クリステヴァ関係の文章をもう少しのせてみます。
西川直子「現代思想の冒険者たち クリステヴァ ポリロゴス」
・父が超自我、子が自我に対応するのにたいし、母はエスと対応することになる。フロイトによれば、自我も超自我も、発生論的にはエスから分化したものであるとされる。
・前エディプス期の心的体制は、<一次的ナルシシズム>と呼ばれる。
・アブジェクシオン abjectionとは、いまだ対象 objet とならずに一体化している母という前=対象 abjet/abject となって棄却されること、を意味している。通常のフランス語の用法では、アブジェクトは「おぞましい、唾棄すべき、卑劣な」の意味の形容詞であり、アブジェクシオンはその名詞形として「おぞましさ、汚辱、卑劣」といった意味で用いられる。クリステヴァは、abject や abjection の接頭語 ab に着目し、語源を汲みあげるかたちでこれらの語を用いたのである。ab は「分離、遠隔」を意味する接頭語であり、abject/abjection は、「分離すべく=投げ出されたもの」ないし「分離すべく=投げ出すこと(棄却すること)」と解される。それにたいして、対象 objet の ob は、「対立、反対」の意の接頭語であって、本来、「面前に対立するかたちで=投げ出されたもの」が「対象」というものなのである。
アブジェクト abject と同様の意味で用いられる abjet という語は、objet と abject にひっかけるかたちでつくられた造語であり、「いまだ対象となっていない、分離すべき、おぞましき前=対象」という意味がこの一語のなかに圧縮されている。
・否定性すなわち棄却のメカニズムを<前=対象の母>の棄却として語ることにより、棄却の舞台が、前=エディプス的体制である一次的ナルシシズムと、そこに生ずる原抑圧に限定されることになった。
・クリステヴァの語彙を用いれば、愛とは意味生成性である、ということになる。愛は、自己から分離されたものとしての対象の定立に関わる意識を生成し、語る主体、言語、ル・サンボリック(記号象徴体系)を生成する。したがって文化・歴史を生成するとされるのである。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
メラニー・クライン 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
メラニー・クラインのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6475人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19252人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人