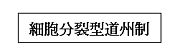最近の注目情報(2010年11月)
1.野党のほつれ どう修正? みんな、自公と「道州制議連」計画(2010年10月15日 産経新聞)
自民、公明、みんなの野党3党の有志国会議員が、道州制導入に向けた議員連盟の設立を計画していることが14日、分かった。地方分権政策をめぐり民主党は道州制導入に否定的であることから、野党3党が連携して民主党との対立を鮮明にするねらいがある。また、平成22年度補正予算案をはじめ今後の国会運営では、自民、公明両党が与党との協力に転じる可能性があることから、みんなの党にとっては両党を引き留めておきたいとの思惑もありそうだ。
2.「関東広域連合」を検討 山梨など10都県知事会 協議会立ち上げ
(2010年10月21日 山梨日日新聞)
山梨など10都県で構成する関東知事会は20日、関東地方の行政組織を一体化する「関東広域連合」について、設立も視野に検討に入ることを決めた。各都県の幹部でつくる事務レベルの協議会を立ち上げ、設置の是非も含め協議する。
3.川崎市「県域から独立」地方分権推進の方針で特別市創設を提言(2010年10月20日 神奈川新聞)
川崎市の阿部孝夫市長は19日、政令指定都市制度に代わる新たな大都市制度の在り方などについて基本的な考え方を取りまとめた「地方分権の推進に関する方針」を発表した。国または都道府県と政令市との「二重行政」に無駄があるとして、政令市とは異なり、県に包括されない県域から独立した地方自治体「新たな特別市」の創設を提言している。
4.7府県共同の「関西広域連合」12月にも発足 規約成立 (2010年10月27日
asahi.com)
関西の7府県が県境をまたぐ業務に共同で取り組む特別地方公共団体「関西広域連合」の設立規約案が27日、大阪府議会で賛成多数で可決され、参加する全府県で規約が成立した。12月上旬にも全国初の都道府県レベルの広域連合が発足する見通しだ。まずは防災や医療など7分野を対象とし、将来は国の出先機関が廃止された場合の「受け皿」となることを目指す。
広域連合に参加するのは大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、鳥取、徳島の7府県。知事らが11月1日にも片山善博総務相に設立を申請する。
◇
「一つの受け皿ができた。『都道府県にまたがる事務は渡せない』という霞が関の言い訳を、ぴしゃっとはね返せる。堂々と国の出先機関の廃止、(権限の)移譲に力を入れていける」。大阪府の橋下徹知事は27日、府議会で広域連合規約案が可決された後、表情を引き締めて語った。
逢坂誠二・総務政務官は「全国一律の出先改革は簡単ではない。希望する地方に先行的に移すことも議論されており、関西広域連合は牽引(けんいん)力になる」と話す。
滋賀県の嘉田由紀子知事は27日、「今後、(権限移譲をめぐって)国とやり合うプロセスを(住民に)見せる必要がある」と語った。
5.道州制導入は時期尚早 片山総務相が答弁(2010年10月28日 MSN産経ニュース)
片山善博総務相は28日の参院内閣委員会で、都道府県を広域のブロックに再編する「道州制」について「個人的見解だが、今は都道府県の規模を大きくするより質を良くすることが重要だ」と述べ、導入は時期尚早との考えを示した。自民党の宮沢洋一氏への答弁。
6.東北州政治家連盟が初研修 知事、道州制の必要性訴える(2010年11月7日 読売新聞)
東北6県の超党派の地方議員らで作る「東北州政治家連盟」(代表・菊地文博前宮城県議)は6日、仙台市青葉区のホテルで初の研修会を開いた。4月26日の設立後、特段の活動をしていなかったが、約半年を経て再始動した。
□ □ □
最近の注目情報詳細(2010年11月)
1.野党のほつれ どう修正? みんな、自公と「道州制議連」計画(2010年10月15日 産経新聞)
自民、公明、みんなの野党3党の有志国会議員が、道州制導入に向けた議員連盟の設立を計画していることが14日、分かった。地方分権政策をめぐり民主党は道州制導入に否定的であることから、野党3党が連携して民主党との対立を鮮明にするねらいがある。また、平成22年度補正予算案をはじめ今後の国会運営では、自民、公明両党が与党との協力に転じる可能性があることから、みんなの党にとっては両党を引き留めておきたいとの思惑もありそうだ。
議連の設立を計画しているのは、みんなの党の江口克彦参院議員や自民党の松浪健太衆院議員ら。江口氏らはすでに3党の有志議員12人による道州制の勉強会を発足させ、年内にも道州制のあり方や課題について取りまとめる。
道州制については、日本経団連をはじめ経済界からの要望が強く、自民、公明、みんなの3党は道州制推進を参院選の公約に掲げた。とくに、みんなの党は「地域主権型道州制」の実現をアジェンダの3大柱の一つに据え、安倍晋三政権時代に発足した総務相諮問機関の「道州制ビジョン懇談会」の座長を務めた江口氏を今夏の参院選に擁立した経緯がある。
一方、民主党は「地域主権」を掲げているが、市町村に相当する基礎自治体を全国300に統合することが念頭にあり、道州制には消極的だ。実際、鳩山由紀夫政権はビジョン懇を今年2月に廃止し、政府内での道州制の議論は事実上停止した。
議連の設立は、道州制導入の議論を今後も展開させていくという政策的なねらいと同時に、自民、公明、みんなの野党3党の結束を強化していくとの政局的な思惑も見え隠れする。
菅直人首相は今国会で、衆参両院のねじれを打開するため、自民、公明両党には22年度補正予算案への協力を得るべく秋波を送っている。しかし、みんなの党に対しては同党が求める公務員制度改革に消極的な発言を繰り返し、みんなの党も菅政権との対決姿勢を強めている。
ただ、自民、公明両党が与党との協力に応じれば、補正予算案や法案が成立してしまうことから、みんなの党内には存在感が埋没することへの危機感があり、両党を何とか野党サイドに引き留めておきたい考えだ。
2.「関東広域連合」を検討 山梨など10都県知事会 協議会立ち上げ
(2010年10月21日 山梨日日新聞)
山梨など10都県で構成する関東知事会は20日、関東地方の行政組織を一体化する「関東広域連合」について、設立も視野に検討に入ることを決めた。各都県の幹部でつくる事務レベルの協議会を立ち上げ、設置の是非も含め協議する。
広域連合は、都道府県を廃止し、新たな法律も必要となる道州制とは異なり、地方自治法に基づき設置が可能。市町村が消防事務などで提携する一部事務組合に似た行政組織で、防災や医療、治水など各都県にまたがる事務に共同で当たることが想定される。
全国知事会のプロジェクトチームが国出先機関の廃止に向け、事務の受け皿となる広域連合などの必要性を指摘。大阪や兵庫など2府5県が年内にも関西広域連合の発足に向け準備していて、九州7県も九州広域行政機構(仮称)の設立を目指している。
関東広域連合設立に向けた協議会の立ち上げは、都内で開かれた定例会議で、会長を務める神奈川県の松沢成文知事が提案。横内正明知事の代理で出席した新津修県東京事務所長のほか、東京や千葉、埼玉、長野、静岡などの各都県知事も全会一致で同意した。協議会は各都県の関連部局長で構成することとし、山梨県は知事政策局長が担当する見通し。
協議会は今後、広域連合設置の可否などを議論する方針。ただ、静岡県や長野県は中部圏知事会にも属しているため、「枠組みも含め課題は多い」(県幹部)との指摘もあり、実現性は未知数だ。横内知事は取材に対し「関西や九州では具体的な取り組みが行われている。関東地域でも早期に検討を進める必要がある」との認識を示した。
3.川崎市「県域から独立」地方分権推進の方針で特別市創設を提言(2010年10月20日 神奈川新聞)
川崎市の阿部孝夫市長は19日、政令指定都市制度に代わる新たな大都市制度の在り方などについて基本的な考え方を取りまとめた「地方分権の推進に関する方針」を発表した。国または都道府県と政令市との「二重行政」に無駄があるとして、政令市とは異なり、県に包括されない県域から独立した地方自治体「新たな特別市」の創設を提言している。
大都市制度をめぐっては、横浜をはじめ、大阪、名古屋の3政令市が他市に先行する形で制度創設に向けて2008年から共同で研究を進めているほか、指定都市市長会などでも議論が進められている。
川崎市は大都市を取り巻く背景として、二重行政による無駄が顕著になっているとともに、人口集中や産業集積が進む中でごみや待機児童の問題など都市的課題と大都市特有の行財政需要が増大している現状を説明。その上で、自主的・自立的な行財政運営を可能にする新たな大都市制度を創設することを提案した。
方針では、「特別市」はすべての地方税を一元的に課して徴収し、国が担うべき事務権限を除いて市域に及ぶすべての事務権限を担うとしている。
管轄が県と市に分かれている保育園と幼稚園についても、設置許可などの権限を一元化できるほか、自主的・総合的に実施できる事業例として、道路・河川の整備・管理、公立学校(小中学校・高校・特別支援学校など)の運営・管理、パスポートの交付などを挙げている。警察行政については「広域犯罪への対応は従来のままだが、交通安全や防犯に関する部門に限って県警ではなく、市の公安委員会や警察本部をつくって市が担う」とした。
阿部市長は「ほかの政令市も考え方はそれほど変わらない。指定都市市長会などとも協力して国などに働き掛けていきたい」と話している。
◆大都市制度
指定都市制度は1956年、一定の事務権限を市が道府県に代わって担う特例として暫定的に地方自治法に定められた。50年以上が経過し、基礎自治体(市町村)と広域自治体(都道府県)の事務権限を併せ持つ大都市の行政需要に対応しきれていないことや、道州制議論の高まりもあり新たな制度創設の動きが広がっている。横浜市は今年5月、制度の在り方について基本的な方向性を発表。10月には具体化に向け、有識者による研究会が発足した。
4.7府県共同の「関西広域連合」12月にも発足 規約成立 (2010年10月27日
asahi.com)
関西の7府県が県境をまたぐ業務に共同で取り組む特別地方公共団体「関西広域連合」の設立規約案が27日、大阪府議会で賛成多数で可決され、参加する全府県で規約が成立した。12月上旬にも全国初の都道府県レベルの広域連合が発足する見通しだ。まずは防災や医療など7分野を対象とし、将来は国の出先機関が廃止された場合の「受け皿」となることを目指す。
広域連合に参加するのは大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、鳥取、徳島の7府県。知事らが11月1日にも片山善博総務相に設立を申請する。
設立後は、まず広域防災、観光・文化、産業振興、医療、環境保全、資格試験、職員研修の7分野の業務を想定。徳島県は資格試験を除く6分野、鳥取県は観光と医療の2分野で参加する。さらに国の出先機関の廃止を促し、同連合がその事務の「受け皿」となることで、現在は国が直轄している河川、国道の管理を担うことなどを目指す。
重要な決定は7府県知事が委員の「広域連合委員会」が行う。委員の互選で選ぶ初代の広域連合長は、兵庫県の井戸敏三知事が有力視される。予算や事務をチェックする広域連合議会(定数20)も設け、各府県議会から議員を選ぶ。
ただ、同じ関西でも奈良県は「責任の所在が不明確で意思決定が遅れ、経費が増す」として、広域連合への不参加をすでに表明。設立の検討に加わった三重、福井両県も参加を見送った。同連合が将来、各府県を一つにまとめる「関西州」につながりかねない、との懸念も多くの府県から出たため、取り決めに「そのまま道州に転化するものではない」と明記された。
九州の7県は今月、「九州広域行政機構」の設立を目指すことで合意。首都圏でも環境問題などに取り組む「首都圏広域連合」設立に向けた協議が昨年から始まっている。
◇
「一つの受け皿ができた。『都道府県にまたがる事務は渡せない』という霞が関の言い訳を、ぴしゃっとはね返せる。堂々と国の出先機関の廃止、(権限の)移譲に力を入れていける」。大阪府の橋下徹知事は27日、府議会で広域連合規約案が可決された後、表情を引き締めて語った。
政府の地域主権戦略会議に参加している逢坂誠二・総務政務官は「全国一律の出先改革は簡単ではない。希望する地方に先行的に移すことも議論されており、関西広域連合は牽引(けんいん)力になる」と話す。民主党は昨夏の衆院選で「出先機関の原則廃止」を公約しており、事務・権限を地方に移譲する内容の法案を、来年の通常国会に提出する方針だ。
しかし、省庁の壁は厚い。今月7日の地域主権戦略会議で、省庁が「地方へ移す」と認めた出先の事務・権限は、全体の1割程度。関西広域連合が成立後に求める方針の河川管理も、大半の河川を「全国レベルの技術、経験が不可欠」として、国が管理する方針を変えなかった。
滋賀県の嘉田由紀子知事は27日、「今後、(権限移譲をめぐって)国とやり合うプロセスを(住民に)見せる必要がある」と語った。
5.道州制導入は時期尚早 片山総務相が答弁(2010年10月28日 MSN産経ニュース)
片山善博総務相は28日の参院内閣委員会で、都道府県を広域のブロックに再編する「道州制」について「個人的見解だが、今は都道府県の規模を大きくするより質を良くすることが重要だ」と述べ、導入は時期尚早との考えを示した。自民党の宮沢洋一氏への答弁。
片山氏は「都道府県で本当の民主主義が行われているか疑問だ。多くの地方議会は、書面を読み上げるだけの出来レース。規模が大きくなったらもっと機能しなくなる」と指摘した。
6.東北州政治家連盟が初研修 知事、道州制の必要性訴える(2010年11月7日 読売新聞)
東北6県の超党派の地方議員らで作る「東北州政治家連盟」(代表・菊地文博前宮城県議)は6日、仙台市青葉区のホテルで初の研修会を開いた。4月26日の設立後、特段の活動をしていなかったが、約半年を経て再始動した。
連盟は道州制の実現を目指し、4月に6県の県議や市町村議ら93人で発足した。当初は8月に「仮想政府」を設置し、具体的に政策を議論する予定だったが、7月の参院選に菊地代表らメンバーが出馬したことなどから活動を見合わせていた。
この日の研修会では、講師に招かれた村井知事が「明治維新以来の『国家のフルモデルチェンジ』が必要だ」と述べ、国からの大幅な権限移譲を伴う道州制の必要性を訴えた。
連盟の会員は現在約120人まで増えているが、研修会の出席者は約30人にとどまり、やや低調な再スタートとなった。今後、財政、経済産業、農林水産、教育、観光の5つの部門会議を設け、政策論議を経て提言をまとめる。来月予定の次回研修会では増田寛也元総務相(前岩手県知事)を講師に迎える予定だ。
1.野党のほつれ どう修正? みんな、自公と「道州制議連」計画(2010年10月15日 産経新聞)
自民、公明、みんなの野党3党の有志国会議員が、道州制導入に向けた議員連盟の設立を計画していることが14日、分かった。地方分権政策をめぐり民主党は道州制導入に否定的であることから、野党3党が連携して民主党との対立を鮮明にするねらいがある。また、平成22年度補正予算案をはじめ今後の国会運営では、自民、公明両党が与党との協力に転じる可能性があることから、みんなの党にとっては両党を引き留めておきたいとの思惑もありそうだ。
2.「関東広域連合」を検討 山梨など10都県知事会 協議会立ち上げ
(2010年10月21日 山梨日日新聞)
山梨など10都県で構成する関東知事会は20日、関東地方の行政組織を一体化する「関東広域連合」について、設立も視野に検討に入ることを決めた。各都県の幹部でつくる事務レベルの協議会を立ち上げ、設置の是非も含め協議する。
3.川崎市「県域から独立」地方分権推進の方針で特別市創設を提言(2010年10月20日 神奈川新聞)
川崎市の阿部孝夫市長は19日、政令指定都市制度に代わる新たな大都市制度の在り方などについて基本的な考え方を取りまとめた「地方分権の推進に関する方針」を発表した。国または都道府県と政令市との「二重行政」に無駄があるとして、政令市とは異なり、県に包括されない県域から独立した地方自治体「新たな特別市」の創設を提言している。
4.7府県共同の「関西広域連合」12月にも発足 規約成立 (2010年10月27日
asahi.com)
関西の7府県が県境をまたぐ業務に共同で取り組む特別地方公共団体「関西広域連合」の設立規約案が27日、大阪府議会で賛成多数で可決され、参加する全府県で規約が成立した。12月上旬にも全国初の都道府県レベルの広域連合が発足する見通しだ。まずは防災や医療など7分野を対象とし、将来は国の出先機関が廃止された場合の「受け皿」となることを目指す。
広域連合に参加するのは大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、鳥取、徳島の7府県。知事らが11月1日にも片山善博総務相に設立を申請する。
◇
「一つの受け皿ができた。『都道府県にまたがる事務は渡せない』という霞が関の言い訳を、ぴしゃっとはね返せる。堂々と国の出先機関の廃止、(権限の)移譲に力を入れていける」。大阪府の橋下徹知事は27日、府議会で広域連合規約案が可決された後、表情を引き締めて語った。
逢坂誠二・総務政務官は「全国一律の出先改革は簡単ではない。希望する地方に先行的に移すことも議論されており、関西広域連合は牽引(けんいん)力になる」と話す。
滋賀県の嘉田由紀子知事は27日、「今後、(権限移譲をめぐって)国とやり合うプロセスを(住民に)見せる必要がある」と語った。
5.道州制導入は時期尚早 片山総務相が答弁(2010年10月28日 MSN産経ニュース)
片山善博総務相は28日の参院内閣委員会で、都道府県を広域のブロックに再編する「道州制」について「個人的見解だが、今は都道府県の規模を大きくするより質を良くすることが重要だ」と述べ、導入は時期尚早との考えを示した。自民党の宮沢洋一氏への答弁。
6.東北州政治家連盟が初研修 知事、道州制の必要性訴える(2010年11月7日 読売新聞)
東北6県の超党派の地方議員らで作る「東北州政治家連盟」(代表・菊地文博前宮城県議)は6日、仙台市青葉区のホテルで初の研修会を開いた。4月26日の設立後、特段の活動をしていなかったが、約半年を経て再始動した。
□ □ □
最近の注目情報詳細(2010年11月)
1.野党のほつれ どう修正? みんな、自公と「道州制議連」計画(2010年10月15日 産経新聞)
自民、公明、みんなの野党3党の有志国会議員が、道州制導入に向けた議員連盟の設立を計画していることが14日、分かった。地方分権政策をめぐり民主党は道州制導入に否定的であることから、野党3党が連携して民主党との対立を鮮明にするねらいがある。また、平成22年度補正予算案をはじめ今後の国会運営では、自民、公明両党が与党との協力に転じる可能性があることから、みんなの党にとっては両党を引き留めておきたいとの思惑もありそうだ。
議連の設立を計画しているのは、みんなの党の江口克彦参院議員や自民党の松浪健太衆院議員ら。江口氏らはすでに3党の有志議員12人による道州制の勉強会を発足させ、年内にも道州制のあり方や課題について取りまとめる。
道州制については、日本経団連をはじめ経済界からの要望が強く、自民、公明、みんなの3党は道州制推進を参院選の公約に掲げた。とくに、みんなの党は「地域主権型道州制」の実現をアジェンダの3大柱の一つに据え、安倍晋三政権時代に発足した総務相諮問機関の「道州制ビジョン懇談会」の座長を務めた江口氏を今夏の参院選に擁立した経緯がある。
一方、民主党は「地域主権」を掲げているが、市町村に相当する基礎自治体を全国300に統合することが念頭にあり、道州制には消極的だ。実際、鳩山由紀夫政権はビジョン懇を今年2月に廃止し、政府内での道州制の議論は事実上停止した。
議連の設立は、道州制導入の議論を今後も展開させていくという政策的なねらいと同時に、自民、公明、みんなの野党3党の結束を強化していくとの政局的な思惑も見え隠れする。
菅直人首相は今国会で、衆参両院のねじれを打開するため、自民、公明両党には22年度補正予算案への協力を得るべく秋波を送っている。しかし、みんなの党に対しては同党が求める公務員制度改革に消極的な発言を繰り返し、みんなの党も菅政権との対決姿勢を強めている。
ただ、自民、公明両党が与党との協力に応じれば、補正予算案や法案が成立してしまうことから、みんなの党内には存在感が埋没することへの危機感があり、両党を何とか野党サイドに引き留めておきたい考えだ。
2.「関東広域連合」を検討 山梨など10都県知事会 協議会立ち上げ
(2010年10月21日 山梨日日新聞)
山梨など10都県で構成する関東知事会は20日、関東地方の行政組織を一体化する「関東広域連合」について、設立も視野に検討に入ることを決めた。各都県の幹部でつくる事務レベルの協議会を立ち上げ、設置の是非も含め協議する。
広域連合は、都道府県を廃止し、新たな法律も必要となる道州制とは異なり、地方自治法に基づき設置が可能。市町村が消防事務などで提携する一部事務組合に似た行政組織で、防災や医療、治水など各都県にまたがる事務に共同で当たることが想定される。
全国知事会のプロジェクトチームが国出先機関の廃止に向け、事務の受け皿となる広域連合などの必要性を指摘。大阪や兵庫など2府5県が年内にも関西広域連合の発足に向け準備していて、九州7県も九州広域行政機構(仮称)の設立を目指している。
関東広域連合設立に向けた協議会の立ち上げは、都内で開かれた定例会議で、会長を務める神奈川県の松沢成文知事が提案。横内正明知事の代理で出席した新津修県東京事務所長のほか、東京や千葉、埼玉、長野、静岡などの各都県知事も全会一致で同意した。協議会は各都県の関連部局長で構成することとし、山梨県は知事政策局長が担当する見通し。
協議会は今後、広域連合設置の可否などを議論する方針。ただ、静岡県や長野県は中部圏知事会にも属しているため、「枠組みも含め課題は多い」(県幹部)との指摘もあり、実現性は未知数だ。横内知事は取材に対し「関西や九州では具体的な取り組みが行われている。関東地域でも早期に検討を進める必要がある」との認識を示した。
3.川崎市「県域から独立」地方分権推進の方針で特別市創設を提言(2010年10月20日 神奈川新聞)
川崎市の阿部孝夫市長は19日、政令指定都市制度に代わる新たな大都市制度の在り方などについて基本的な考え方を取りまとめた「地方分権の推進に関する方針」を発表した。国または都道府県と政令市との「二重行政」に無駄があるとして、政令市とは異なり、県に包括されない県域から独立した地方自治体「新たな特別市」の創設を提言している。
大都市制度をめぐっては、横浜をはじめ、大阪、名古屋の3政令市が他市に先行する形で制度創設に向けて2008年から共同で研究を進めているほか、指定都市市長会などでも議論が進められている。
川崎市は大都市を取り巻く背景として、二重行政による無駄が顕著になっているとともに、人口集中や産業集積が進む中でごみや待機児童の問題など都市的課題と大都市特有の行財政需要が増大している現状を説明。その上で、自主的・自立的な行財政運営を可能にする新たな大都市制度を創設することを提案した。
方針では、「特別市」はすべての地方税を一元的に課して徴収し、国が担うべき事務権限を除いて市域に及ぶすべての事務権限を担うとしている。
管轄が県と市に分かれている保育園と幼稚園についても、設置許可などの権限を一元化できるほか、自主的・総合的に実施できる事業例として、道路・河川の整備・管理、公立学校(小中学校・高校・特別支援学校など)の運営・管理、パスポートの交付などを挙げている。警察行政については「広域犯罪への対応は従来のままだが、交通安全や防犯に関する部門に限って県警ではなく、市の公安委員会や警察本部をつくって市が担う」とした。
阿部市長は「ほかの政令市も考え方はそれほど変わらない。指定都市市長会などとも協力して国などに働き掛けていきたい」と話している。
◆大都市制度
指定都市制度は1956年、一定の事務権限を市が道府県に代わって担う特例として暫定的に地方自治法に定められた。50年以上が経過し、基礎自治体(市町村)と広域自治体(都道府県)の事務権限を併せ持つ大都市の行政需要に対応しきれていないことや、道州制議論の高まりもあり新たな制度創設の動きが広がっている。横浜市は今年5月、制度の在り方について基本的な方向性を発表。10月には具体化に向け、有識者による研究会が発足した。
4.7府県共同の「関西広域連合」12月にも発足 規約成立 (2010年10月27日
asahi.com)
関西の7府県が県境をまたぐ業務に共同で取り組む特別地方公共団体「関西広域連合」の設立規約案が27日、大阪府議会で賛成多数で可決され、参加する全府県で規約が成立した。12月上旬にも全国初の都道府県レベルの広域連合が発足する見通しだ。まずは防災や医療など7分野を対象とし、将来は国の出先機関が廃止された場合の「受け皿」となることを目指す。
広域連合に参加するのは大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、鳥取、徳島の7府県。知事らが11月1日にも片山善博総務相に設立を申請する。
設立後は、まず広域防災、観光・文化、産業振興、医療、環境保全、資格試験、職員研修の7分野の業務を想定。徳島県は資格試験を除く6分野、鳥取県は観光と医療の2分野で参加する。さらに国の出先機関の廃止を促し、同連合がその事務の「受け皿」となることで、現在は国が直轄している河川、国道の管理を担うことなどを目指す。
重要な決定は7府県知事が委員の「広域連合委員会」が行う。委員の互選で選ぶ初代の広域連合長は、兵庫県の井戸敏三知事が有力視される。予算や事務をチェックする広域連合議会(定数20)も設け、各府県議会から議員を選ぶ。
ただ、同じ関西でも奈良県は「責任の所在が不明確で意思決定が遅れ、経費が増す」として、広域連合への不参加をすでに表明。設立の検討に加わった三重、福井両県も参加を見送った。同連合が将来、各府県を一つにまとめる「関西州」につながりかねない、との懸念も多くの府県から出たため、取り決めに「そのまま道州に転化するものではない」と明記された。
九州の7県は今月、「九州広域行政機構」の設立を目指すことで合意。首都圏でも環境問題などに取り組む「首都圏広域連合」設立に向けた協議が昨年から始まっている。
◇
「一つの受け皿ができた。『都道府県にまたがる事務は渡せない』という霞が関の言い訳を、ぴしゃっとはね返せる。堂々と国の出先機関の廃止、(権限の)移譲に力を入れていける」。大阪府の橋下徹知事は27日、府議会で広域連合規約案が可決された後、表情を引き締めて語った。
政府の地域主権戦略会議に参加している逢坂誠二・総務政務官は「全国一律の出先改革は簡単ではない。希望する地方に先行的に移すことも議論されており、関西広域連合は牽引(けんいん)力になる」と話す。民主党は昨夏の衆院選で「出先機関の原則廃止」を公約しており、事務・権限を地方に移譲する内容の法案を、来年の通常国会に提出する方針だ。
しかし、省庁の壁は厚い。今月7日の地域主権戦略会議で、省庁が「地方へ移す」と認めた出先の事務・権限は、全体の1割程度。関西広域連合が成立後に求める方針の河川管理も、大半の河川を「全国レベルの技術、経験が不可欠」として、国が管理する方針を変えなかった。
滋賀県の嘉田由紀子知事は27日、「今後、(権限移譲をめぐって)国とやり合うプロセスを(住民に)見せる必要がある」と語った。
5.道州制導入は時期尚早 片山総務相が答弁(2010年10月28日 MSN産経ニュース)
片山善博総務相は28日の参院内閣委員会で、都道府県を広域のブロックに再編する「道州制」について「個人的見解だが、今は都道府県の規模を大きくするより質を良くすることが重要だ」と述べ、導入は時期尚早との考えを示した。自民党の宮沢洋一氏への答弁。
片山氏は「都道府県で本当の民主主義が行われているか疑問だ。多くの地方議会は、書面を読み上げるだけの出来レース。規模が大きくなったらもっと機能しなくなる」と指摘した。
6.東北州政治家連盟が初研修 知事、道州制の必要性訴える(2010年11月7日 読売新聞)
東北6県の超党派の地方議員らで作る「東北州政治家連盟」(代表・菊地文博前宮城県議)は6日、仙台市青葉区のホテルで初の研修会を開いた。4月26日の設立後、特段の活動をしていなかったが、約半年を経て再始動した。
連盟は道州制の実現を目指し、4月に6県の県議や市町村議ら93人で発足した。当初は8月に「仮想政府」を設置し、具体的に政策を議論する予定だったが、7月の参院選に菊地代表らメンバーが出馬したことなどから活動を見合わせていた。
この日の研修会では、講師に招かれた村井知事が「明治維新以来の『国家のフルモデルチェンジ』が必要だ」と述べ、国からの大幅な権限移譲を伴う道州制の必要性を訴えた。
連盟の会員は現在約120人まで増えているが、研修会の出席者は約30人にとどまり、やや低調な再スタートとなった。今後、財政、経済産業、農林水産、教育、観光の5つの部門会議を設け、政策論議を経て提言をまとめる。来月予定の次回研修会では増田寛也元総務相(前岩手県知事)を講師に迎える予定だ。
|
|
|
|
コメント(5)
忽那さん
おはようございます。
ご質問の件ですが、ひとつは前から自民党の方が鮮明に道州制を掲げていたので、「かぶっちゃいかん!」ということで、この際とりあえず「道州制」という言葉だけは引っ込めたのではないかと思います。ただ、道州制といっても地域主権がその前提にありますから、どっちがどう言おうと本質的にはそんなに変わらないと思いますよ。
もうひとつ理由を挙げるとするならば、道州制を具体的に論じていくにはまだまだ時期尚早ということもあります。中途半端にやっていくよりは、この際とりあえず停止して別のことに専念したいのではないでしょうか?
まだまだ政権交代して1年数ヶ月ほどです。
政局も落ち着いてないし、民主党政治の基礎作りをしっかりやっていってもらいたいですね。
おはようございます。
ご質問の件ですが、ひとつは前から自民党の方が鮮明に道州制を掲げていたので、「かぶっちゃいかん!」ということで、この際とりあえず「道州制」という言葉だけは引っ込めたのではないかと思います。ただ、道州制といっても地域主権がその前提にありますから、どっちがどう言おうと本質的にはそんなに変わらないと思いますよ。
もうひとつ理由を挙げるとするならば、道州制を具体的に論じていくにはまだまだ時期尚早ということもあります。中途半端にやっていくよりは、この際とりあえず停止して別のことに専念したいのではないでしょうか?
まだまだ政権交代して1年数ヶ月ほどです。
政局も落ち着いてないし、民主党政治の基礎作りをしっかりやっていってもらいたいですね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
道州制をひろめよう!! 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
道州制をひろめよう!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75505人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208299人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196031人