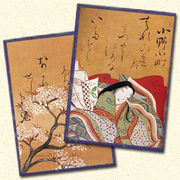|
|
|
|
コメント(11)
>>[4]
[けり]の連体形[ける]が詠嘆の意味になる用例としては、
弓矢とる身ほど口惜しかりけるものはなし。『平家物語』
まことにあさましく恐ろしかりける所かな、とく夜の明けよかし。『宇治拾遺物語』
いずれも、【形容詞】+【ける】+【体言】の形が共通しています。
詠嘆かどうかはともかく、過去の心情ではなく、発言時点での心境を述べています。
このような用例は少なくないようです。
前千代さんのご指摘どおり、和歌の中に出てくる「けり」で、伝聞過去のものを探すほうがむずかしいかもしれません。
百人一首の中に、助動詞[けり]が含まれている歌は18首ありました。(今、手元で数えただけなので見落としがあるかもしれません。)
うち、はっきりと伝聞過去だと判別できるものはありません。
また、「体験過去」あるいは「単純過去」と解釈できるものは、確かに[き]が使われています。
完了の[ぬ]+過去の[けり]の「にけり」については、「移りにけりな」「咲きにけり」「来にけり」「立ちにけり」などとあり、これらを過去完了で解釈しているものもありますが、完了+詠嘆で解釈することもできます。
また、助動詞には「種類」と「意味」があります。
「種類」は活用や接続の仕方などから機械的にまとめたもので、「意味」は文脈や個人によって柔軟に変化します。
活用表などを見ると、たとえば「けり」の場合、種類は「過去の助動詞」になりますが、意味は「伝聞過去・詠嘆」などと分けられます。
ですから、分類上「過去の助動詞」であっても、意味が過去とは限りません。
意味の多い助動詞に「べし」がありますが、これもひとまず「推量の助動詞」にくくられて、そのあと文脈によっていわゆる「すいかとめてよ」(推量・意志・可能・当然・命令・適当・予定or予想)があります。
教科書などにより多少の差異がありますが、センター試験などではどういう解釈であっても混乱が起きないようにうまく問題を作成しています。
以下は個人的な意見ですが、日本人は、現代語でも、「過去」と「気づき」「驚き」「確認」などは同じように表現をします。
探し物を見つけて「あった、あった」というし、ほっとすれば「よかった、よかった」と、現在の状況でも「た」を使います。
これは日本人の癖でしょう。
文法というのは癖を体系的に編集したものです。
私も文法を細かく見ていくのは大好きです。
それは、文法に厳密になりたいからではなくて、人の自然な気持ちというのは、さりげない助詞や助動詞の使い方に現れると思っているからです。とくに日本語の場合は。もちろん古文でも現代文でも。
長い書き込みで、偉そうな物言いをいたしまして恐縮ですが、私にも正しい解釈はわかりません。
ですから、先のコメントもあいまいな表現になってしまいました。
私は反射的に「歌のけりは詠嘆」ととってしまっていて、このような疑問点は面白いと思います。
というのも、たしかに過去で解釈すると、歌の意味が通るし、自然なんですよね。
いろいろな用例や他の歌や出典などを参考にしながら、表現のおもしろさを発見していくのは面白いので、つい長くなってしまいました。
時間があれば、他の歌などもみて比較されると面白いと思います。
[けり]の連体形[ける]が詠嘆の意味になる用例としては、
弓矢とる身ほど口惜しかりけるものはなし。『平家物語』
まことにあさましく恐ろしかりける所かな、とく夜の明けよかし。『宇治拾遺物語』
いずれも、【形容詞】+【ける】+【体言】の形が共通しています。
詠嘆かどうかはともかく、過去の心情ではなく、発言時点での心境を述べています。
このような用例は少なくないようです。
前千代さんのご指摘どおり、和歌の中に出てくる「けり」で、伝聞過去のものを探すほうがむずかしいかもしれません。
百人一首の中に、助動詞[けり]が含まれている歌は18首ありました。(今、手元で数えただけなので見落としがあるかもしれません。)
うち、はっきりと伝聞過去だと判別できるものはありません。
また、「体験過去」あるいは「単純過去」と解釈できるものは、確かに[き]が使われています。
完了の[ぬ]+過去の[けり]の「にけり」については、「移りにけりな」「咲きにけり」「来にけり」「立ちにけり」などとあり、これらを過去完了で解釈しているものもありますが、完了+詠嘆で解釈することもできます。
また、助動詞には「種類」と「意味」があります。
「種類」は活用や接続の仕方などから機械的にまとめたもので、「意味」は文脈や個人によって柔軟に変化します。
活用表などを見ると、たとえば「けり」の場合、種類は「過去の助動詞」になりますが、意味は「伝聞過去・詠嘆」などと分けられます。
ですから、分類上「過去の助動詞」であっても、意味が過去とは限りません。
意味の多い助動詞に「べし」がありますが、これもひとまず「推量の助動詞」にくくられて、そのあと文脈によっていわゆる「すいかとめてよ」(推量・意志・可能・当然・命令・適当・予定or予想)があります。
教科書などにより多少の差異がありますが、センター試験などではどういう解釈であっても混乱が起きないようにうまく問題を作成しています。
以下は個人的な意見ですが、日本人は、現代語でも、「過去」と「気づき」「驚き」「確認」などは同じように表現をします。
探し物を見つけて「あった、あった」というし、ほっとすれば「よかった、よかった」と、現在の状況でも「た」を使います。
これは日本人の癖でしょう。
文法というのは癖を体系的に編集したものです。
私も文法を細かく見ていくのは大好きです。
それは、文法に厳密になりたいからではなくて、人の自然な気持ちというのは、さりげない助詞や助動詞の使い方に現れると思っているからです。とくに日本語の場合は。もちろん古文でも現代文でも。
長い書き込みで、偉そうな物言いをいたしまして恐縮ですが、私にも正しい解釈はわかりません。
ですから、先のコメントもあいまいな表現になってしまいました。
私は反射的に「歌のけりは詠嘆」ととってしまっていて、このような疑問点は面白いと思います。
というのも、たしかに過去で解釈すると、歌の意味が通るし、自然なんですよね。
いろいろな用例や他の歌や出典などを参考にしながら、表現のおもしろさを発見していくのは面白いので、つい長くなってしまいました。
時間があれば、他の歌などもみて比較されると面白いと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
百人一首 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-