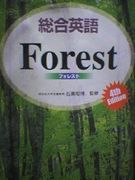|
|
|
|
コメント(6)
シルバーさん
規則というより「傾向性」なのですが、ご自身がお持ちの参考書などにはどう書かれていますか?
本にもよると思いますが、一応の目安のような考え方がたいていの書籍には解説されているかと思うのですが、まずご自身でどこまで調べら切れるかが大切かと思います。
1、to 不定詞
もともと不定詞(動詞の原形)というのは、動詞を名詞化する用法でした。だからこそ「to(〜へ向かって)」との組み合わせで「to do」という形式が生まれたわけです。その後歴史的な変遷があり、動詞の原形そのものを名詞と感じなくなり、to do の形で名詞として、さらに形容詞や副詞としても機能するようになりました。
そういう大元の由来を踏まえると納得できることなのですが、「to do」がもともと持っている「〜することに向かって」の意味がそれなりに残っているため、to do を目的語とするパターンでは「これから何かをしようとすること」や「これからある状態になっていくこと」に対して用いられる傾向が強いといえます。
2、動名詞
動名詞の方は、1語で名詞的性質を強く表すため、to不定詞より、もっと名詞としての純度の高さが感じられます。そのため、「すでに行ったこと、確定事項」を内容的に表すところがあります。to不定詞が「動詞としての機能を中心として保ちつつ、名詞的性質を『帯びている』」という程度であるのに対して、動名詞は「動詞としての機能を残しつつ名詞化したもの」という違いがあります。
to不定詞や動名詞を目的語とする他動詞の意味や使われ方を見ていきますと、「過去に行われたこと」、「すでに事実化している行為、動作など」を目的語にするのが自然な意味を持つ他動詞は動名詞を目的語とする傾向が強く、それに対して「これからしようとする」などの将来的方向性としての動作などを目的語とするのが似合う他動詞は不定詞とのつながりを好む傾向にあります。
他動詞によってはその意味・性質上、to不定詞か動名詞のいずれか一方としかつながらないものもありますし、多少のニュアンスの差が生じても構造的にはどちらともつながることのできるものがあるのはご存知ですね。
完全にすべてを網羅できる「ルール」はありませんが、上記のような傾向性を、他動詞が表す意味との関係において吟味すると「なるほどこの他動詞はto不定詞(あるいは動名詞)」とつながるのが自然だな、と感覚的にも納得できるのではないでしょうか。
規則というより「傾向性」なのですが、ご自身がお持ちの参考書などにはどう書かれていますか?
本にもよると思いますが、一応の目安のような考え方がたいていの書籍には解説されているかと思うのですが、まずご自身でどこまで調べら切れるかが大切かと思います。
1、to 不定詞
もともと不定詞(動詞の原形)というのは、動詞を名詞化する用法でした。だからこそ「to(〜へ向かって)」との組み合わせで「to do」という形式が生まれたわけです。その後歴史的な変遷があり、動詞の原形そのものを名詞と感じなくなり、to do の形で名詞として、さらに形容詞や副詞としても機能するようになりました。
そういう大元の由来を踏まえると納得できることなのですが、「to do」がもともと持っている「〜することに向かって」の意味がそれなりに残っているため、to do を目的語とするパターンでは「これから何かをしようとすること」や「これからある状態になっていくこと」に対して用いられる傾向が強いといえます。
2、動名詞
動名詞の方は、1語で名詞的性質を強く表すため、to不定詞より、もっと名詞としての純度の高さが感じられます。そのため、「すでに行ったこと、確定事項」を内容的に表すところがあります。to不定詞が「動詞としての機能を中心として保ちつつ、名詞的性質を『帯びている』」という程度であるのに対して、動名詞は「動詞としての機能を残しつつ名詞化したもの」という違いがあります。
to不定詞や動名詞を目的語とする他動詞の意味や使われ方を見ていきますと、「過去に行われたこと」、「すでに事実化している行為、動作など」を目的語にするのが自然な意味を持つ他動詞は動名詞を目的語とする傾向が強く、それに対して「これからしようとする」などの将来的方向性としての動作などを目的語とするのが似合う他動詞は不定詞とのつながりを好む傾向にあります。
他動詞によってはその意味・性質上、to不定詞か動名詞のいずれか一方としかつながらないものもありますし、多少のニュアンスの差が生じても構造的にはどちらともつながることのできるものがあるのはご存知ですね。
完全にすべてを網羅できる「ルール」はありませんが、上記のような傾向性を、他動詞が表す意味との関係において吟味すると「なるほどこの他動詞はto不定詞(あるいは動名詞)」とつながるのが自然だな、と感覚的にも納得できるのではないでしょうか。
>>[3]
(1) I asked him to open the door.
(2) I had him open the door.
どちらも構文的にはほぼ同じ。「SVO+C(不定詞)」で、不定詞として「to不定詞」か「原形不定詞」かの違いですね。
さて先にちょっとだけ不定詞の歴史的背景について触れておきます。
本来「動詞の原形」というのは「動詞を名詞扱い」するための手段の1つでした。だからこそ「to 原形」というふうに前置詞toと組み合わせて用いることができ、それによって「ある行為へ向かっていく」意味を表したものです。
そのニュアンスは現代英語でも随所に残っており、
I remember to post the letter.(これから手紙を出すことを覚えている)
I remember posting the letter.(すでに手紙を出したことを覚えている)
などの用法の区別をもたらしています。
このように「to原形」が「ある行為に向かっていく」意味を本来持つことから上記(1)(2)の違いも出てきます。
(1)の英文は「彼にドアを開けるよう頼んだ」ですが、これはまだ「彼が実際にドアを開けた」まで意味に含んでいません。「してね」とお願いさえすれば「asked」したことになるわけです。
直訳的に解釈すると「彼がドアを開ける方向へと向かっていくようにお願いした」わけですね。
(2)の英文は構造的に
I had [ he opened the door ].
というふうに「ある事実(誰かが何を実際にした)」を持った、というのが直訳です。つまり、「had」したと言った限り、「彼が実際にドアを開けた」のです。
helpはもともと「回避する、避ける」の意味が先にあり、そこから「邪魔物をどけてあげる>結果として助ける」の意味に発展しました。
もともと「邪魔物をどける」までの意味なので、結果的に「助けられた相手が目的を達成した」までを意味に含んでいなかったのですが、やがて現実の用法として「目的の達成」までを意味に含むようになりました。
I heled my sister solve the prolem.
妹が問題を解くのを手伝った=私が手助けして「妹は問題が解けた」。
現代では「help 人 to do」の形式はほとんど見ることがなくなっています。それは意味的に「行為の達成」までを含んでいるため「to do」を補語に取りたくなる心理が働いた結果と言えるでしょう。
(3) Mother made me stay home.
(4) I was made to stay home (by Mother).
(3)はすでに述べたように「母によって強制的に私は家にいさせられた」という意味。実際に私は家にいたわけです。
同じ意味を受動態にすると「to stay」という「to不定詞」になってしまっていますが、表される意味・事実は同じです。
ではなぜ受動態だと「to do」になるのか?
それは「文の述語動詞」が(3)では使役動詞(make)であるのに対して(4)では「be」だからです。makeなどの使役動詞が述語動詞になっていることで、あとのOCの関係で「C=原形」となるわけですが、「be made/let」のように受動態になると「使役動詞構文ではなくなる」ため、原形補語が取れなくなります。
(5) Mother will make me stay home.
こちらは「will+make」の組み合わせですが、態(能動態と受動態)を変えないで時制や法だけが変わっても述語動詞の意味的中心は使役動詞のままなので、あとの「stay」は原形です。
I saw him cross the street.
= I saw [ he crossed the street ](事実の達成、行為の完了)を見た。
see, hearなどに代表される知覚動詞(感覚動詞)の構文も同様で、「事実の達成や行為の完了」を意味するためSVOCのCには原形が来ます。
I saw him crossing the street.
= I saw [ he was crossing the street ].
こちらの形ですと「渡っている最中」を目撃しただけなので最後まで渡りきったかどうかはわかりません。
(1) I asked him to open the door.
(2) I had him open the door.
どちらも構文的にはほぼ同じ。「SVO+C(不定詞)」で、不定詞として「to不定詞」か「原形不定詞」かの違いですね。
さて先にちょっとだけ不定詞の歴史的背景について触れておきます。
本来「動詞の原形」というのは「動詞を名詞扱い」するための手段の1つでした。だからこそ「to 原形」というふうに前置詞toと組み合わせて用いることができ、それによって「ある行為へ向かっていく」意味を表したものです。
そのニュアンスは現代英語でも随所に残っており、
I remember to post the letter.(これから手紙を出すことを覚えている)
I remember posting the letter.(すでに手紙を出したことを覚えている)
などの用法の区別をもたらしています。
このように「to原形」が「ある行為に向かっていく」意味を本来持つことから上記(1)(2)の違いも出てきます。
(1)の英文は「彼にドアを開けるよう頼んだ」ですが、これはまだ「彼が実際にドアを開けた」まで意味に含んでいません。「してね」とお願いさえすれば「asked」したことになるわけです。
直訳的に解釈すると「彼がドアを開ける方向へと向かっていくようにお願いした」わけですね。
(2)の英文は構造的に
I had [ he opened the door ].
というふうに「ある事実(誰かが何を実際にした)」を持った、というのが直訳です。つまり、「had」したと言った限り、「彼が実際にドアを開けた」のです。
helpはもともと「回避する、避ける」の意味が先にあり、そこから「邪魔物をどけてあげる>結果として助ける」の意味に発展しました。
もともと「邪魔物をどける」までの意味なので、結果的に「助けられた相手が目的を達成した」までを意味に含んでいなかったのですが、やがて現実の用法として「目的の達成」までを意味に含むようになりました。
I heled my sister solve the prolem.
妹が問題を解くのを手伝った=私が手助けして「妹は問題が解けた」。
現代では「help 人 to do」の形式はほとんど見ることがなくなっています。それは意味的に「行為の達成」までを含んでいるため「to do」を補語に取りたくなる心理が働いた結果と言えるでしょう。
(3) Mother made me stay home.
(4) I was made to stay home (by Mother).
(3)はすでに述べたように「母によって強制的に私は家にいさせられた」という意味。実際に私は家にいたわけです。
同じ意味を受動態にすると「to stay」という「to不定詞」になってしまっていますが、表される意味・事実は同じです。
ではなぜ受動態だと「to do」になるのか?
それは「文の述語動詞」が(3)では使役動詞(make)であるのに対して(4)では「be」だからです。makeなどの使役動詞が述語動詞になっていることで、あとのOCの関係で「C=原形」となるわけですが、「be made/let」のように受動態になると「使役動詞構文ではなくなる」ため、原形補語が取れなくなります。
(5) Mother will make me stay home.
こちらは「will+make」の組み合わせですが、態(能動態と受動態)を変えないで時制や法だけが変わっても述語動詞の意味的中心は使役動詞のままなので、あとの「stay」は原形です。
I saw him cross the street.
= I saw [ he crossed the street ](事実の達成、行為の完了)を見た。
see, hearなどに代表される知覚動詞(感覚動詞)の構文も同様で、「事実の達成や行為の完了」を意味するためSVOCのCには原形が来ます。
I saw him crossing the street.
= I saw [ he was crossing the street ].
こちらの形ですと「渡っている最中」を目撃しただけなので最後まで渡りきったかどうかはわかりません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英語学習法・英文法のQ&A 更新情報
-
最新のアンケート
英語学習法・英文法のQ&Aのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37845人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31947人