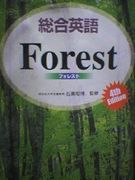Adaptive behavior is the collection of conceptual, social, and practical skills that
people have learned so they can function in their everyday lives. Significant
limitations in adaptive behavior impact a person’s daily life and affect the ability
respond to a particular situation or to the environment.
On these standardized measures, significant limitations in adaptive behavior are
operationally defined as performance that is at least 2 standard deviations below the
mean of either (a) one of the following three types of adaptive behavior: conceptual,
social, or practical, or (b) an overall score on a standardized measure of conceptual,
social, and practical skills.
問題:適応行動の重大な制約の定義はどのようなものか。
自分答え:
3つの適応行動である概念化、社会化、実用化のうちの1つの平均か、
概念化、社会化、実用化のスキルを計る尺度の総合得点の平均の
どちらかの平均が少なくとも標準偏差が2以下の場合を適応行動の重大な制約の定義としている
特にa)の意味がよくわかっていません。
どなたか分かる方教えていただけると助かります
よろしくお願い致します
people have learned so they can function in their everyday lives. Significant
limitations in adaptive behavior impact a person’s daily life and affect the ability
respond to a particular situation or to the environment.
On these standardized measures, significant limitations in adaptive behavior are
operationally defined as performance that is at least 2 standard deviations below the
mean of either (a) one of the following three types of adaptive behavior: conceptual,
social, or practical, or (b) an overall score on a standardized measure of conceptual,
social, and practical skills.
問題:適応行動の重大な制約の定義はどのようなものか。
自分答え:
3つの適応行動である概念化、社会化、実用化のうちの1つの平均か、
概念化、社会化、実用化のスキルを計る尺度の総合得点の平均の
どちらかの平均が少なくとも標準偏差が2以下の場合を適応行動の重大な制約の定義としている
特にa)の意味がよくわかっていません。
どなたか分かる方教えていただけると助かります
よろしくお願い致します
|
|
|
|
コメント(15)
>自分答え:
3つの適応行動である概念化、社会化、実用化のうちの1つの平均か、
概念化、社会化、実用化のスキルを計る尺度の総合得点の平均の
どちらかの平均が少なくとも標準偏差が2以下の場合を適応行動の重大な制約の定義としている
こう申し上げてはすまないのですが、ご自身でこの日本語の意味がわかりますか?一読して私には何のことを言っているのかさっぱりです。
和訳以前に「英語そのもの」が理解できていなければ適切な翻訳は無理なものです。
この文章は全体として「知的障害」や「発達障害」に関する問題を述べたものです。一般的に人間は、大きくわけて3種類の技能を成長に応じて身に付けながら社会に対する適応能力を身に付けます。
>Adaptive behavior is the collection of conceptual, social, and practical skills that people have learned so they can function in their everyday lives.
「適合行動」(=社会に適合した行動能力)とは、「知的能力」、「社会性」、「生活技術」の3つがまとまったものであり、そういう能力を人は日常生活の中において社会人の一員としてふさわしいように会得しているものなのである。
他の資料から「Adaptive behavior」を構成する3つの要素についてもう少し詳しく見てみましょう:
(1)Conceptual skills: literacy; self-direction; and concepts of number, money, and time
「概念的技能」では何のことかわかりにくいですが、具体的に言うと「読み書き」、「数字や金銭、時間などの理解」など社会的に自立する上で習得していなければならない抽象思考能力のことです。
要するに「社会で生きていく上で必ず身に付けていかなければならない知的な技能」です。
(2)Social skills: interpersonal skills, social responsibility, self-esteem, gullibility, naïveté (i.e., wariness), social problem solving, following rules, obeying laws, and avoiding being victimized
「社会的技術」とは人とのつきあいができること。社会的責任感や自尊心、人を信じること、ナイーブさ、問題解決能力、ルールを守れること、犠牲になることを避ける判断力など。
要するに「多くの人の中でスムーズな社会生活を送れるための感覚、判断能力」です。
(3)Practical skills: activities of daily living (personal care), occupational skills, use of money, safety, health care, travel/transportation, schedules/routines, and use of the telephone
「実践的技術」とは、社会に自然に溶け込めるように身だしなみを整えられることや、職業に役立つ技能を持つこと、さらに金銭管理、保全管理、健康管理ができること、交通機関を利用できること、計画性、規則正しい生活を送れること、電話機が使えること、など社会生活を営む上で実際に行わなければならない様々な具体的な行動が取れることを指します。
Significant limitations in adaptive behavior impact a person’s daily life and affect the ability <toがあるはず> respond to a particular situation or to the environment.
「社会に対する適応能力」の何かが著しく欠損していると、日常生活に大きな影響を及ぼし、なんらかの状況への対応能力や、特定の環境への対応能力がないなどの結果となる。
On these standardized measures,
一般的に「これができて普通だ」と考えられている基準に照らして
significant limitations in adaptive behavior are operationally defined
「社会適合力」の重大な欠損というのは、機能的な側面から見て次のように定義されている:
as performance that is at least 2 standard deviations below the mean of either
少なくとも次の2つの能力が著しく一般人の平均に及んでいないという意味で
(a) one of the following three types of adaptive behavior: conceptual,
social, or practical,
「社会適合力」を構成する3つの要素のどれかが身についていない
or
(b) an overall score on a standardized measure of conceptual,
social, and practical skills.
それぞれが身についているようでも相対的な評価として3つの要素についての達成度が低い
つまり「社会的適合力」を構成する「知的能力」、「社会性」、「生活技術」の
1、どれか1つ以上がごそっと欠落している。つまり「まるで身についていない、
2、どれかが身についていないわけではないが、全体的な習得度が一般人に比べて大きく劣っているか
ということで一般平均と比べて2つ以上の大きく劣る点がある。
そうなると「significant limitation」=「適応行動の重大な制約」にあたるのだと定義されているわけです。
3つの適応行動である概念化、社会化、実用化のうちの1つの平均か、
概念化、社会化、実用化のスキルを計る尺度の総合得点の平均の
どちらかの平均が少なくとも標準偏差が2以下の場合を適応行動の重大な制約の定義としている
こう申し上げてはすまないのですが、ご自身でこの日本語の意味がわかりますか?一読して私には何のことを言っているのかさっぱりです。
和訳以前に「英語そのもの」が理解できていなければ適切な翻訳は無理なものです。
この文章は全体として「知的障害」や「発達障害」に関する問題を述べたものです。一般的に人間は、大きくわけて3種類の技能を成長に応じて身に付けながら社会に対する適応能力を身に付けます。
>Adaptive behavior is the collection of conceptual, social, and practical skills that people have learned so they can function in their everyday lives.
「適合行動」(=社会に適合した行動能力)とは、「知的能力」、「社会性」、「生活技術」の3つがまとまったものであり、そういう能力を人は日常生活の中において社会人の一員としてふさわしいように会得しているものなのである。
他の資料から「Adaptive behavior」を構成する3つの要素についてもう少し詳しく見てみましょう:
(1)Conceptual skills: literacy; self-direction; and concepts of number, money, and time
「概念的技能」では何のことかわかりにくいですが、具体的に言うと「読み書き」、「数字や金銭、時間などの理解」など社会的に自立する上で習得していなければならない抽象思考能力のことです。
要するに「社会で生きていく上で必ず身に付けていかなければならない知的な技能」です。
(2)Social skills: interpersonal skills, social responsibility, self-esteem, gullibility, naïveté (i.e., wariness), social problem solving, following rules, obeying laws, and avoiding being victimized
「社会的技術」とは人とのつきあいができること。社会的責任感や自尊心、人を信じること、ナイーブさ、問題解決能力、ルールを守れること、犠牲になることを避ける判断力など。
要するに「多くの人の中でスムーズな社会生活を送れるための感覚、判断能力」です。
(3)Practical skills: activities of daily living (personal care), occupational skills, use of money, safety, health care, travel/transportation, schedules/routines, and use of the telephone
「実践的技術」とは、社会に自然に溶け込めるように身だしなみを整えられることや、職業に役立つ技能を持つこと、さらに金銭管理、保全管理、健康管理ができること、交通機関を利用できること、計画性、規則正しい生活を送れること、電話機が使えること、など社会生活を営む上で実際に行わなければならない様々な具体的な行動が取れることを指します。
Significant limitations in adaptive behavior impact a person’s daily life and affect the ability <toがあるはず> respond to a particular situation or to the environment.
「社会に対する適応能力」の何かが著しく欠損していると、日常生活に大きな影響を及ぼし、なんらかの状況への対応能力や、特定の環境への対応能力がないなどの結果となる。
On these standardized measures,
一般的に「これができて普通だ」と考えられている基準に照らして
significant limitations in adaptive behavior are operationally defined
「社会適合力」の重大な欠損というのは、機能的な側面から見て次のように定義されている:
as performance that is at least 2 standard deviations below the mean of either
少なくとも次の2つの能力が著しく一般人の平均に及んでいないという意味で
(a) one of the following three types of adaptive behavior: conceptual,
social, or practical,
「社会適合力」を構成する3つの要素のどれかが身についていない
or
(b) an overall score on a standardized measure of conceptual,
social, and practical skills.
それぞれが身についているようでも相対的な評価として3つの要素についての達成度が低い
つまり「社会的適合力」を構成する「知的能力」、「社会性」、「生活技術」の
1、どれか1つ以上がごそっと欠落している。つまり「まるで身についていない、
2、どれかが身についていないわけではないが、全体的な習得度が一般人に比べて大きく劣っているか
ということで一般平均と比べて2つ以上の大きく劣る点がある。
そうなると「significant limitation」=「適応行動の重大な制約」にあたるのだと定義されているわけです。
shootingさんこんばんは〜
らうんどさんいつも勉強になります。
心理学系はほとんど門外漢で恐縮ですが、らうんどさんのコメントについてお尋ねしたいことがあります。
>as performance that is at least 2 standard deviations below the mean of either
少なくとも次の2つの能力が著しく一般人の平均に及んでいないという意味で
2 standard deviations(below the mean)というのは、ぼくはshootingさんが訳された標準偏差でいいかと思います。どうでしょうかね。たぶん、ある程度厳密な統計的定義を決めたいでしょうから、平均というとどうも漠然としている感がありまして。
これはおそらく統計全体の約95%をカバーする範囲という意味で(1 standard deviationだと約68%です)、その平均以下を指しているように思います。日本語のwikiには説明がないのですが、ここの(http://en.wikipedia.org/wiki/68-95-99.7_rule)右図の ‐2σ以下の範囲を表しているのではないかと。2 standard deviations below the meanは、a few yards below the bridgeのように、2 standard deviations below→the meanというかかり方で、日本語でいう2標準偏差以下な気がどうもします。つまり、at least 2 standard deviations below the meanで、「少なくとも2標準偏差以下」という意味ではないかなと。いずれにせよ、念頭に置かれてるのはこうした図式な気がします。そして、この読みだと、eitherはbothの意味ではなく、「(a)、(b)の条件どちらか」でも自然に思えます。今回の基準はまったく知りませんでしたが、DSM-IV(http://www.ashappy.net/adhdld-pdd/adhd/adhdlddsvicd.html)では「その小児の年齢の2標準偏差以下である」といった表現が見えます。
shootingさんが特に(a)が分からないというのはどういうことでしょう?「以下の三つの適応行動のうち一つ、(以下のというのは)概念的、社会的、実践的(適応行動)」ということだと思いますが、その内容が分からないという意味ですかね?門外漢の私も知る由もありませんでしたが、らうんどさんが説明された他にも、以下のサイトに簡単な説明がありますね。というか、以下の内容が出典と考えて間違いなさそうですよね。少し手が加わっているようですが。http://www.pearsonassessments.com/NR/rdonlyres/53C68DA4-2E71-43B5-8951-F670D5B7B4F1/0/ABAS_II_Tech_Rpt.pdf
どうでしょ
らうんどさんいつも勉強になります。
心理学系はほとんど門外漢で恐縮ですが、らうんどさんのコメントについてお尋ねしたいことがあります。
>as performance that is at least 2 standard deviations below the mean of either
少なくとも次の2つの能力が著しく一般人の平均に及んでいないという意味で
2 standard deviations(below the mean)というのは、ぼくはshootingさんが訳された標準偏差でいいかと思います。どうでしょうかね。たぶん、ある程度厳密な統計的定義を決めたいでしょうから、平均というとどうも漠然としている感がありまして。
これはおそらく統計全体の約95%をカバーする範囲という意味で(1 standard deviationだと約68%です)、その平均以下を指しているように思います。日本語のwikiには説明がないのですが、ここの(http://en.wikipedia.org/wiki/68-95-99.7_rule)右図の ‐2σ以下の範囲を表しているのではないかと。2 standard deviations below the meanは、a few yards below the bridgeのように、2 standard deviations below→the meanというかかり方で、日本語でいう2標準偏差以下な気がどうもします。つまり、at least 2 standard deviations below the meanで、「少なくとも2標準偏差以下」という意味ではないかなと。いずれにせよ、念頭に置かれてるのはこうした図式な気がします。そして、この読みだと、eitherはbothの意味ではなく、「(a)、(b)の条件どちらか」でも自然に思えます。今回の基準はまったく知りませんでしたが、DSM-IV(http://www.ashappy.net/adhdld-pdd/adhd/adhdlddsvicd.html)では「その小児の年齢の2標準偏差以下である」といった表現が見えます。
shootingさんが特に(a)が分からないというのはどういうことでしょう?「以下の三つの適応行動のうち一つ、(以下のというのは)概念的、社会的、実践的(適応行動)」ということだと思いますが、その内容が分からないという意味ですかね?門外漢の私も知る由もありませんでしたが、らうんどさんが説明された他にも、以下のサイトに簡単な説明がありますね。というか、以下の内容が出典と考えて間違いなさそうですよね。少し手が加わっているようですが。http://www.pearsonassessments.com/NR/rdonlyres/53C68DA4-2E71-43B5-8951-F670D5B7B4F1/0/ABAS_II_Tech_Rpt.pdf
どうでしょ
らうんどさんきょろさんいつもお二人とも的確な アドバイス本当にありがとうございます
アドバイス本当にありがとうございます
>>らうんどさん
いえいえ、本当にその通りなんです!自分の訳が意味不明・・・恐ろしいことです なんとなく読み、なんとなく理解、なんとなくわからないところはなんとなく流す=結局読めてないという恐ろしいループにハマっておりましてorz もっともっと、精読して専門書もよめるようにしたいです
なんとなく読み、なんとなく理解、なんとなくわからないところはなんとなく流す=結局読めてないという恐ろしいループにハマっておりましてorz もっともっと、精読して専門書もよめるようにしたいです
色々丁寧に解説してくださってありがとうございます
これからもご指導いただけたら助かります!!ありがとうございます!!
>>きょろさん
ああああ、DSM-IVか・・・なぜ気付かなかったんだとすごく自分にガッカリ・・・
そして、きょろさんの脳と感性にビツクリ
こういう風に調べたらいいんですね。
まーこうも見事に導いていただいて、ほんとありがとうございます
a)の意味がわからないっていうのはb)のように得点って単語がなかったので、数値化されないのに標準偏差なのか?そもそも標準偏差って訳でいいのか・・・でもb)は得点だしなー何か読み間違いかな?省略があるんだろうか、なんだろうか・・・というパニックで質問してました・・・和訳以前の問題でした。スイマセン!
ちゃんと3領域を計る尺度もありました|ω・ิ)
ご丁寧に質問してくださってありがとうございますヾ(*´∀`)ノ
=================================
DSM内容を理解しての和訳です↓↓↓
何かやっちゃってたらご指導いただけると嬉しいです。
特に、修飾はそこじゃないよとか、日本語がおかしいとか、ここの文法理解大丈夫?なんてのがあれば・・・
Adaptive behavior is the collection of conceptual, social, and practical skills that
people have learned so they can function in their everyday lives.
適応行動とは人間が獲得してきた概念的、社会的、実践的技能の集合体である。
Significant limitations in adaptive behavior impact a person’s daily life and affect the ability (to)
respond to a particular situation or to the environment.
適応行動の著しい制約は個人の日々の生活に支障を与え、特定の状況や環境に対する反応能力に障害をもたらす。
On these standardized measures,
このように基準化された尺度において、
significant limitations in adaptive behavior are operationally defined as performance that is at least 2 standard deviations below the mean of either (a) one of the following three types of adaptive behavior: conceptual, social, or practical, or (b) an overall score on a standardized measure of conceptual,
social, and practical skills.
適応行動の著しい制約(適応能力における障害)とは以下の結果のどちらかが平均より2標準偏差以上低いことを意味する。
a)次の適応行動の3領域の1つ:概念的、社会的、実践的技能
b)概念的、社会的、実践的技能を計る尺度の総合得点
・適応行動の重大な制約の定義とは?
適応行動の3領域の少なくとも1つの領域の得点,
または、すべての領域の総合得点が平均よりも2標準偏差以上低いことが
適応行動の重大な制約の定義である。
■質問
?operationallyはどこにかかっているのですか?訳し方を教えてください
significant limitations in adaptive behavior are operationally defined as.....
らうんどさんの訳をみてなるほどと思ったんですが
>>機能的な側面から見て次のように定義されている
are operationally defined asからどういう思考段階を経ればこうなれるんですか?
私なんか、わからないから無視しちゃいました(爆)
ハハハーって笑い事じゃないんですけどねー(ノ◇≦。)
=====================================
>>らうんどさん
いえいえ、本当にその通りなんです!自分の訳が意味不明・・・恐ろしいことです
色々丁寧に解説してくださってありがとうございます
これからもご指導いただけたら助かります!!ありがとうございます!!
>>きょろさん
ああああ、DSM-IVか・・・なぜ気付かなかったんだとすごく自分にガッカリ・・・
そして、きょろさんの脳と感性にビツクリ
こういう風に調べたらいいんですね。
まーこうも見事に導いていただいて、ほんとありがとうございます
a)の意味がわからないっていうのはb)のように得点って単語がなかったので、数値化されないのに標準偏差なのか?そもそも標準偏差って訳でいいのか・・・でもb)は得点だしなー何か読み間違いかな?省略があるんだろうか、なんだろうか・・・というパニックで質問してました・・・和訳以前の問題でした。スイマセン!
ちゃんと3領域を計る尺度もありました|ω・ิ)
ご丁寧に質問してくださってありがとうございますヾ(*´∀`)ノ
=================================
DSM内容を理解しての和訳です↓↓↓
何かやっちゃってたらご指導いただけると嬉しいです。
特に、修飾はそこじゃないよとか、日本語がおかしいとか、ここの文法理解大丈夫?なんてのがあれば・・・
Adaptive behavior is the collection of conceptual, social, and practical skills that
people have learned so they can function in their everyday lives.
適応行動とは人間が獲得してきた概念的、社会的、実践的技能の集合体である。
Significant limitations in adaptive behavior impact a person’s daily life and affect the ability (to)
respond to a particular situation or to the environment.
適応行動の著しい制約は個人の日々の生活に支障を与え、特定の状況や環境に対する反応能力に障害をもたらす。
On these standardized measures,
このように基準化された尺度において、
significant limitations in adaptive behavior are operationally defined as performance that is at least 2 standard deviations below the mean of either (a) one of the following three types of adaptive behavior: conceptual, social, or practical, or (b) an overall score on a standardized measure of conceptual,
social, and practical skills.
適応行動の著しい制約(適応能力における障害)とは以下の結果のどちらかが平均より2標準偏差以上低いことを意味する。
a)次の適応行動の3領域の1つ:概念的、社会的、実践的技能
b)概念的、社会的、実践的技能を計る尺度の総合得点
・適応行動の重大な制約の定義とは?
適応行動の3領域の少なくとも1つの領域の得点,
または、すべての領域の総合得点が平均よりも2標準偏差以上低いことが
適応行動の重大な制約の定義である。
■質問
?operationallyはどこにかかっているのですか?訳し方を教えてください
significant limitations in adaptive behavior are operationally defined as.....
らうんどさんの訳をみてなるほどと思ったんですが
>>機能的な側面から見て次のように定義されている
are operationally defined asからどういう思考段階を経ればこうなれるんですか?
私なんか、わからないから無視しちゃいました(爆)
ハハハーって笑い事じゃないんですけどねー(ノ◇≦。)
=====================================
>shooting゚+.☆゚+. さん
>■質問
?operationallyはどこにかかっているのですか?訳し方を教えてください
significant limitations in adaptive behavior are operationally defined as.....
すでにきょろさんが回答されているように述語動詞部分の「are defined」にかかる副詞です。
>らうんどさんの訳をみてなるほどと思ったんですが
>>機能的な側面から見て次のように定義されている
are operationally defined asからどういう思考段階を経ればこうなれるんですか?
英語と日本語は別言語なので、単純な言葉の置き換えではうまくいかないことが多くあります。
「訳し方」というのは英語学習では本来まったく気にする必要のないことなんです。英語が使えることが目的であり、中学・高校の英語科学習指導要領にも「和訳できる」という目標はまったく含まれていません。
学校の先生が生徒に和訳を求めたり、試験で英文和訳が出題されるのは「英語理解の証拠」の1つとしてそれを求めているのだと思いますが、英語を理解できているかどうかの証明を和訳に求めるのは指導的観点から言うともっとも安直で、手抜きであり、なおかつ「本当の証明にさえならない」といえると感じます。
学校の「英文和訳」は主に単語の置き換えにより(本当に英文が理解できていなくても)機械的に導き出されてしまうところに問題があります。
本来、「翻訳」というのは次のステップを踏みます:
1、英文を英文のまま理解する。その英文が強弱、抑揚、緩急などを含め、「意味に即して音声化」する。(つまり「英文理解の確認は音読させるだけでわかる」ものなんです。)
2、英文がわかったら頭のスイッチを英語から日本語に切りかえ、「さて、こういうことを日本人ならどう言い回すだろうか」と志向を「翻す」わけです。
3、つまり1つのイメージなり、情報が自分の頭の中にあって、その出口が英語になるか日本語になるかの違いということになります。英語を使っている(読み書き話しすべて)ときは日本語を思い浮かべておらず、英語のまま思考しています。inputの言語とoutputの言語が切り替わるというだけで、実は特別なことは何もしていません。
4、英文理解は英語の力ですが、「翻訳」は日本語の能力だけの問題です。operationally という単語に英和辞典がどのような訳語例をあげているか確認していませんが、その箇所を読んだときの思考は概ね次のような流れです:
(1)operationally > operation -al -ly という「名詞>形容詞>副詞」の派生があり、直訳的には「オペレーション的に」となりますよね。この「オペレーション」というのが辞書的には「操作」とかが思い浮かぶところなのでしょうが、日本語が持つ「意味の領域」と英語の「operation」にはかなりのずれがあるため、「和訳しないで読む」方が原文の意味を正しく理解できます。
(2)でも和訳しなければならないとなると、文意(パラグラフ全体)を通じて、なんといえばつじつまがあうのかな?と考えます。あとに続く内容を自然に導き出すような言葉が欲しいと感じるわけですね。そこで「うーん、日本語ネイティブならこういうとき何というかな?」と思考言語を切り替えるわけです。
すでに述べましたとおり、「翻訳」は英語の技術じゃないんです。英語が理解できることを前提にした日本語の運用能力です。
ということは和訳の上達のためには次の2本の柱が重要だとわかります。
<1>英語を英語のまま読み書き話せる運用能力。英語による思考力。意味に応じた英文の音声化に重点を置く。
<2>日本語ネイティブの誇りにかけて(笑)、日本語の表現力に常日頃から意識的に磨きをかけるようにする。
それがたとえ翻訳でも、「英語から和訳した」と読者が気づかない日本語にしたいと常に考えています。
>■質問
?operationallyはどこにかかっているのですか?訳し方を教えてください
significant limitations in adaptive behavior are operationally defined as.....
すでにきょろさんが回答されているように述語動詞部分の「are defined」にかかる副詞です。
>らうんどさんの訳をみてなるほどと思ったんですが
>>機能的な側面から見て次のように定義されている
are operationally defined asからどういう思考段階を経ればこうなれるんですか?
英語と日本語は別言語なので、単純な言葉の置き換えではうまくいかないことが多くあります。
「訳し方」というのは英語学習では本来まったく気にする必要のないことなんです。英語が使えることが目的であり、中学・高校の英語科学習指導要領にも「和訳できる」という目標はまったく含まれていません。
学校の先生が生徒に和訳を求めたり、試験で英文和訳が出題されるのは「英語理解の証拠」の1つとしてそれを求めているのだと思いますが、英語を理解できているかどうかの証明を和訳に求めるのは指導的観点から言うともっとも安直で、手抜きであり、なおかつ「本当の証明にさえならない」といえると感じます。
学校の「英文和訳」は主に単語の置き換えにより(本当に英文が理解できていなくても)機械的に導き出されてしまうところに問題があります。
本来、「翻訳」というのは次のステップを踏みます:
1、英文を英文のまま理解する。その英文が強弱、抑揚、緩急などを含め、「意味に即して音声化」する。(つまり「英文理解の確認は音読させるだけでわかる」ものなんです。)
2、英文がわかったら頭のスイッチを英語から日本語に切りかえ、「さて、こういうことを日本人ならどう言い回すだろうか」と志向を「翻す」わけです。
3、つまり1つのイメージなり、情報が自分の頭の中にあって、その出口が英語になるか日本語になるかの違いということになります。英語を使っている(読み書き話しすべて)ときは日本語を思い浮かべておらず、英語のまま思考しています。inputの言語とoutputの言語が切り替わるというだけで、実は特別なことは何もしていません。
4、英文理解は英語の力ですが、「翻訳」は日本語の能力だけの問題です。operationally という単語に英和辞典がどのような訳語例をあげているか確認していませんが、その箇所を読んだときの思考は概ね次のような流れです:
(1)operationally > operation -al -ly という「名詞>形容詞>副詞」の派生があり、直訳的には「オペレーション的に」となりますよね。この「オペレーション」というのが辞書的には「操作」とかが思い浮かぶところなのでしょうが、日本語が持つ「意味の領域」と英語の「operation」にはかなりのずれがあるため、「和訳しないで読む」方が原文の意味を正しく理解できます。
(2)でも和訳しなければならないとなると、文意(パラグラフ全体)を通じて、なんといえばつじつまがあうのかな?と考えます。あとに続く内容を自然に導き出すような言葉が欲しいと感じるわけですね。そこで「うーん、日本語ネイティブならこういうとき何というかな?」と思考言語を切り替えるわけです。
すでに述べましたとおり、「翻訳」は英語の技術じゃないんです。英語が理解できることを前提にした日本語の運用能力です。
ということは和訳の上達のためには次の2本の柱が重要だとわかります。
<1>英語を英語のまま読み書き話せる運用能力。英語による思考力。意味に応じた英文の音声化に重点を置く。
<2>日本語ネイティブの誇りにかけて(笑)、日本語の表現力に常日頃から意識的に磨きをかけるようにする。
それがたとえ翻訳でも、「英語から和訳した」と読者が気づかない日本語にしたいと常に考えています。
ふむふむなるほどー確かにそうですよね
わかっちゃいるけど、ローマは一日にして成らずですね〜←??(笑)
まだまだ私の場合は道のりは長そうです。
私は翻訳者を目指しているわけではないんですが→(このレベルなので当たり前ですがwww)
なんとなく意味がぼやっととれてるようなとれてないような変な和訳ができあがると
ちゃんとわかってない自分が浮き彫りになってキャーっ てなるんです(笑)
てなるんです(笑)
翻訳者レベルじゃなくても、なんだこの日本語はっていうのだけは脱したいですホント
といって今日も変な和訳を量産しそうですがwww
キョロさんとらうんどさんのおかげで、文章の背景も理解できてなきゃ和訳以前の問題だなというのを改め感じましたし・・・遅くてすいません
自分はまだまだ基礎がないし活字嫌いだしそのうえ雰囲気英語一直線だったので
ほんと、今から積み上げなければです☆
やっと英語の構造が少し理解できるようになってきたハズ・・・
ですが昨日も後置修飾でミスリましたが
どこまでがんばれるかわかりませんがまたご指導いただけたら嬉しいです☆
解説ありがとうございました
わかっちゃいるけど、ローマは一日にして成らずですね〜←??(笑)
まだまだ私の場合は道のりは長そうです。
私は翻訳者を目指しているわけではないんですが→(このレベルなので当たり前ですがwww)
なんとなく意味がぼやっととれてるようなとれてないような変な和訳ができあがると
ちゃんとわかってない自分が浮き彫りになってキャーっ
翻訳者レベルじゃなくても、なんだこの日本語はっていうのだけは脱したいですホント
といって今日も変な和訳を量産しそうですがwww
キョロさんとらうんどさんのおかげで、文章の背景も理解できてなきゃ和訳以前の問題だなというのを改め感じましたし・・・遅くてすいません
自分はまだまだ基礎がないし活字嫌いだしそのうえ雰囲気英語一直線だったので
ほんと、今から積み上げなければです☆
やっと英語の構造が少し理解できるようになってきたハズ・・・
ですが昨日も後置修飾でミスリましたが
どこまでがんばれるかわかりませんがまたご指導いただけたら嬉しいです☆
解説ありがとうございました
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英語学習法・英文法のQ&A 更新情報
-
最新のアンケート
英語学習法・英文法のQ&Aのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90029人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6410人
- 3位
- 独り言
- 9044人