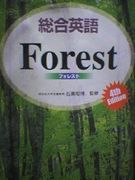毎日教壇に立ちながら思うことがあります。
大学受験において、ターゲットやシステム英単語などの
「英単語集」というものが流布しておりますが、
私自身、単語だけの勉強というものに違和感を覚えます。
動詞にしても文型によって意味は違うし、句動詞であれば前置詞も覚える必要もあり・・。
なにしろ文章中でどう使われるかがわからなければ意味がないし、文章の中にあってこそ意味を成すものなので、無機的な単語学習は意味がないのでは?と、受験生の頃から思っていました。
実際私は最後まで単語集というものは使いませんでしたし(英語は苦手でした)、文法や読解の勉強をやっていく中で単語を語法と共に覚えていきました。
みなさんは、単語集というものは必要だと思われますか?実際、ご自分の勉強の段階で単語についてはどう勉強したかもあわせて伺いたいです。
大学受験において、ターゲットやシステム英単語などの
「英単語集」というものが流布しておりますが、
私自身、単語だけの勉強というものに違和感を覚えます。
動詞にしても文型によって意味は違うし、句動詞であれば前置詞も覚える必要もあり・・。
なにしろ文章中でどう使われるかがわからなければ意味がないし、文章の中にあってこそ意味を成すものなので、無機的な単語学習は意味がないのでは?と、受験生の頃から思っていました。
実際私は最後まで単語集というものは使いませんでしたし(英語は苦手でした)、文法や読解の勉強をやっていく中で単語を語法と共に覚えていきました。
みなさんは、単語集というものは必要だと思われますか?実際、ご自分の勉強の段階で単語についてはどう勉強したかもあわせて伺いたいです。
|
|
|
|
コメント(17)
私も単語を覚えるのは好きじゃなかったですね。
単語の勉強の最終目標は、「分からない単語が存在しない」ではなく、「わからない単語があっても、その単語の意味を推測し、その推測が大きく外れることがない」だと思っています。
とすれば、「推測の方法」こそ教えるべき重大な事柄ということになるでしょう。
そうはいっても、すべての単語がわからない状態ではさすがに推測も何もないですね。それは「その英文が難しすぎる」ということも考えられますが。
その意味で、「超基本的」といえる単語はそれだけとりはずして覚えることもまあ無意味ではないかと考えています。
その「超基本的」ですが、学生にとって重要な単語は試験に出てくる単語でしょう。そうすると、頻度順の単語帳も無意味ではないかと思います。
私自身は、600か800程度は単語帳で覚えた気がします。
単語の勉強の最終目標は、「分からない単語が存在しない」ではなく、「わからない単語があっても、その単語の意味を推測し、その推測が大きく外れることがない」だと思っています。
とすれば、「推測の方法」こそ教えるべき重大な事柄ということになるでしょう。
そうはいっても、すべての単語がわからない状態ではさすがに推測も何もないですね。それは「その英文が難しすぎる」ということも考えられますが。
その意味で、「超基本的」といえる単語はそれだけとりはずして覚えることもまあ無意味ではないかと考えています。
その「超基本的」ですが、学生にとって重要な単語は試験に出てくる単語でしょう。そうすると、頻度順の単語帳も無意味ではないかと思います。
私自身は、600か800程度は単語帳で覚えた気がします。
英語学習者それぞれの好みになってしまうと思います。読みつつ、不明語が出てしまった場合に、それらを辞書で確認しながら進めていくのがいい人もいるだろうし、あるいは、単語帳でガリガリ覚えてから読むほうが楽な人もいるかもしれません。どっちのほうがいいかは、正直なところ、学習者の適性によると思います。
ちなみに僕は、後者のほうでした。文章を読んでいるときに、わからない単語が出てくることで、流れを妨げられてしまうのが非常にイヤでした。類推する方法をという意見もあると思うのですが、類推は類推に過ぎず、確証性が持てない場合もかなりあると思います。
実用英語、学術英語ということを考えた場合には、少なくとも大学受験程度の単語帳(これでも全然足りない)はまるごと頭に入っていないとまずいと思います。また、反復練習も慣れてくると、意外と楽しいものだったりします。単語がわからなくてイライラという、ストレスを回避するためにも、気合で覚えてしまうというのも方法の一つではあると思います。
ただ、1つのパラグラフに不明語が2、3個も出てくるような状態でリーディングをするのは、かなり苦痛だと思います。そのたびに辞書を引き確認、それからまた文章に戻る、また辞書、文章に戻るを繰り返すのはイヤになる人もいると思います。
読んで出てきたものを、辞書で調べることで記憶のストックに入るという考え方もあると思います。それとは逆に、単語帳で覚えたものが、読んだパッセージに出てくることで、記憶にストックされるということも考えられないでしょうか?
単語の記憶については、どうしても避けて通れないものだと思います。学習者各々が頑張らないといけないですよね。今は本当に色々な単語帳が発売されていますよね。語源によるアプローチから、文型や句動詞の用法についての詳細な説明、多義語など、かなり詳細に分析されているものが発売されているので、そのようなものを使うことで、単語帳による学習も有意義に出来ると思います。
ちなみに僕は、後者のほうでした。文章を読んでいるときに、わからない単語が出てくることで、流れを妨げられてしまうのが非常にイヤでした。類推する方法をという意見もあると思うのですが、類推は類推に過ぎず、確証性が持てない場合もかなりあると思います。
実用英語、学術英語ということを考えた場合には、少なくとも大学受験程度の単語帳(これでも全然足りない)はまるごと頭に入っていないとまずいと思います。また、反復練習も慣れてくると、意外と楽しいものだったりします。単語がわからなくてイライラという、ストレスを回避するためにも、気合で覚えてしまうというのも方法の一つではあると思います。
ただ、1つのパラグラフに不明語が2、3個も出てくるような状態でリーディングをするのは、かなり苦痛だと思います。そのたびに辞書を引き確認、それからまた文章に戻る、また辞書、文章に戻るを繰り返すのはイヤになる人もいると思います。
読んで出てきたものを、辞書で調べることで記憶のストックに入るという考え方もあると思います。それとは逆に、単語帳で覚えたものが、読んだパッセージに出てくることで、記憶にストックされるということも考えられないでしょうか?
単語の記憶については、どうしても避けて通れないものだと思います。学習者各々が頑張らないといけないですよね。今は本当に色々な単語帳が発売されていますよね。語源によるアプローチから、文型や句動詞の用法についての詳細な説明、多義語など、かなり詳細に分析されているものが発売されているので、そのようなものを使うことで、単語帳による学習も有意義に出来ると思います。
「試験に出る英単語」丸暗記したクチですw
ご指摘の通り、実用性という意味では疑問が多いと思います。
が、当時受験生であった私はそんなことに
ココロを砕くヒマもなく、ひたすら覚えておりました。
おまけに英語頻出問題演習(でしたか?)丸暗記もしました。
そして長文読解問題をひたすら解いてもいました。
長文読解問題はいちいち辞書を引くと大意がつかみにくく、
文法例題も、見慣れた単語の方が覚えやすいという意味で
丸暗記もそれなりに役立った覚えがあります。
単語だけ丸暗記、ではあまり意味がないかもしれませんが、
ボキャブラリが足りないと理解できないこともありますので、
他の教材と平行して利用する工夫が必要だと思います。
ご指摘の通り、実用性という意味では疑問が多いと思います。
が、当時受験生であった私はそんなことに
ココロを砕くヒマもなく、ひたすら覚えておりました。
おまけに英語頻出問題演習(でしたか?)丸暗記もしました。
そして長文読解問題をひたすら解いてもいました。
長文読解問題はいちいち辞書を引くと大意がつかみにくく、
文法例題も、見慣れた単語の方が覚えやすいという意味で
丸暗記もそれなりに役立った覚えがあります。
単語だけ丸暗記、ではあまり意味がないかもしれませんが、
ボキャブラリが足りないと理解できないこともありますので、
他の教材と平行して利用する工夫が必要だと思います。
英語教育の研究によると、文章の中に5%の未知語が含まれる場合、その読解は困難になるといいます。これを真とすれば、確かに単語の力をつけてから文章に取り組むのも一理あるでしょう。ただ、その単語集という奴が膨大でその時点で挫折することもあると思います。かといって辞書を引きながら読解をするのは手間がかかる…。
で、この前ある生徒を見ていたら、単語集を辞書の代わりに使っているのがいたので興味深く観察しておりました。その単語帳は索引がついているようで、知らない言葉を「単語帳から調べながら」文章を読んでいくというのです。確かにこれは一挙両得、長文を読みながら単語帳の学習ができるのです。もちろん、それぞれの語に関する用法については前置詞や文脈によるところも大きいのですが、学習者自身、「単語帳に載っている単語が長文に使われている」という意識からか、それらの語句は習得が早いように感じられます。
こういう方法はいかがでしょうか。
で、この前ある生徒を見ていたら、単語集を辞書の代わりに使っているのがいたので興味深く観察しておりました。その単語帳は索引がついているようで、知らない言葉を「単語帳から調べながら」文章を読んでいくというのです。確かにこれは一挙両得、長文を読みながら単語帳の学習ができるのです。もちろん、それぞれの語に関する用法については前置詞や文脈によるところも大きいのですが、学習者自身、「単語帳に載っている単語が長文に使われている」という意識からか、それらの語句は習得が早いように感じられます。
こういう方法はいかがでしょうか。
「類推する」派はあまりいないようですね。だからというわけじゃありませんが、少し書かせてください。
私の場合、実のところ類推がドンピシャに当たることも多く、類推が文意を損なうほど外れているというケースは非常に稀です。
というのも、不明な語があったとしても、その語の果たしている役割は明確に分かります。語尾や周囲から不明語の品詞はたいていの場合当たられますし、品詞がわかれば役割はおのずと明瞭ですから。
「実用英語」という言葉は非常に曖昧で、その人がどう英語を使うかにもよると思いますが、「実用英語」で必要となる単語はその人その人によって大きく違うと思います。たとえば、野球選手と貿易商では必要な単語は違うでしょう。
そうなると、たとえば高校生に「その人に必要な単語」を教えることは出来ないと思います。「その人に必要な単語」が何かすらわからないのだから。その高校生が将来どんな生活をするのかは高校生自身ですらわからないのだから。
その意味では、「どんな場合にも通用する知識」があるとすれば、「わからない単語が出てきたときの対処法」だと思います。
私の場合、実のところ類推がドンピシャに当たることも多く、類推が文意を損なうほど外れているというケースは非常に稀です。
というのも、不明な語があったとしても、その語の果たしている役割は明確に分かります。語尾や周囲から不明語の品詞はたいていの場合当たられますし、品詞がわかれば役割はおのずと明瞭ですから。
「実用英語」という言葉は非常に曖昧で、その人がどう英語を使うかにもよると思いますが、「実用英語」で必要となる単語はその人その人によって大きく違うと思います。たとえば、野球選手と貿易商では必要な単語は違うでしょう。
そうなると、たとえば高校生に「その人に必要な単語」を教えることは出来ないと思います。「その人に必要な単語」が何かすらわからないのだから。その高校生が将来どんな生活をするのかは高校生自身ですらわからないのだから。
その意味では、「どんな場合にも通用する知識」があるとすれば、「わからない単語が出てきたときの対処法」だと思います。
サカナスキーさん
類推は大変有効なストラテジーですが、習得するまでに経験値がいるんですよね。先ほど書きませんでしたが、僕も例えばbambooさんと同じで単語帳を使ったことが無く、今も「できれば類推派」です。
しかしながら、学生にとっての「類推」は非常に不安定な要素です。特に単語についての知識、すなわち接頭語や語尾屈折から多少の類推はできるものの、最終的には「この読みでいいのだろうか」という気持ちになることが多いと思います。その意味で、僕は単語の知識量が「最大の敵であると同時に、最大の拠り所」であると思います。「単語を知っている」ということがどれほど読解に物理的だけでなく精神的にプラスに働いていることでしょう。要は単語(そして単語帳・辞書)との付き合い方ですよね。「物語を完全に理解したつもりが、全然別の話を勝手に作っていた」という問題に悩む学生は、ほぼ単語との付き合い方を、単語の知識を確実にするための勉強を怠って、誤解を恐れずに言えば、「楽な類推」に頼りきってしまっていたからだと、僕は分析します。
先ほども申しましたように、僕自身単語帳を使いこなしたことがないので、授業では自分の経験からしかものが言えないので次のように言っています。
「制限時間内に読みなさい。全ての単語を調べるとタイムオーバーだから、『この単語だけは確実に意味をつかまないと文章が分からないぞ』という単語だけを自分で選んで調べなさい。」と。
本当に色々な経験談から、色々な勉強の仕方がありますね。コメントが続いてしまってすみませんでした。
類推は大変有効なストラテジーですが、習得するまでに経験値がいるんですよね。先ほど書きませんでしたが、僕も例えばbambooさんと同じで単語帳を使ったことが無く、今も「できれば類推派」です。
しかしながら、学生にとっての「類推」は非常に不安定な要素です。特に単語についての知識、すなわち接頭語や語尾屈折から多少の類推はできるものの、最終的には「この読みでいいのだろうか」という気持ちになることが多いと思います。その意味で、僕は単語の知識量が「最大の敵であると同時に、最大の拠り所」であると思います。「単語を知っている」ということがどれほど読解に物理的だけでなく精神的にプラスに働いていることでしょう。要は単語(そして単語帳・辞書)との付き合い方ですよね。「物語を完全に理解したつもりが、全然別の話を勝手に作っていた」という問題に悩む学生は、ほぼ単語との付き合い方を、単語の知識を確実にするための勉強を怠って、誤解を恐れずに言えば、「楽な類推」に頼りきってしまっていたからだと、僕は分析します。
先ほども申しましたように、僕自身単語帳を使いこなしたことがないので、授業では自分の経験からしかものが言えないので次のように言っています。
「制限時間内に読みなさい。全ての単語を調べるとタイムオーバーだから、『この単語だけは確実に意味をつかまないと文章が分からないぞ』という単語だけを自分で選んで調べなさい。」と。
本当に色々な経験談から、色々な勉強の仕方がありますね。コメントが続いてしまってすみませんでした。
「類推」と言ってもいろいろあるようです。
ここで私の「類推」を書いてみます。万が一参考になれば幸いです。
? 単語の意味ではなくて品詞を考える
単語の品詞の特定は、意味の類推に比べてはるかに容易です。そもそも品詞は八個しかありませんし、前置詞なんかはだいたい中学で出揃いますから、「不明の任意の単語が前置詞である可能性」はゼロに近い。
動詞なら過去形だとすればedが語尾につきます。無論過去分詞の可能性はあるけれども。
名詞なら冠詞がつくことが多いでしょう。
語尾がicalならおそらく形容詞でしょう。
この段階に関しては多くの経験が必要ということはないでしょう。
? その単語の役割を考える
たとえば不明な語が名詞とわかり、それが動詞の前に位置していれば、倒置でもしていない限り、主語をやっていることはわかる。そうなると、「○○は」とまでは訳せる。
ここまでくると、カタカナが多く混じった、化粧品の宣伝みたいな訳文に達するでしょう。そこまでくれば、「意味の類推」もさほど困難ではないかと思います。
「私の○○な科目である○○の問題は、私を錯乱させた」
とでもわかれば、この○○に入る語句はそう難しくない。前者はおそらくは「苦手・不得意」で、後者は科目名、たとえば数学でしょう。そして、この人がどの科目が苦手かは前後を見ればまあわかるでしょう。
単語を増やせば増やすほど有利ではありますが、そこを強調すると「意味の分からないものを大量に覚えこむ」という非人間的な作業に学生を追い込んでしまい、英語ができる=非人間的なんて妙なことにまでなりかねません。
それにしても、ほかの科目に比べて、なんとまあ多様なものでしょうか。私の専門は歴史でしたが、これの学び方はそうは多くないように思います。
学び方が多様ということ自体が何かを物語っているように思えます。
ここで私の「類推」を書いてみます。万が一参考になれば幸いです。
? 単語の意味ではなくて品詞を考える
単語の品詞の特定は、意味の類推に比べてはるかに容易です。そもそも品詞は八個しかありませんし、前置詞なんかはだいたい中学で出揃いますから、「不明の任意の単語が前置詞である可能性」はゼロに近い。
動詞なら過去形だとすればedが語尾につきます。無論過去分詞の可能性はあるけれども。
名詞なら冠詞がつくことが多いでしょう。
語尾がicalならおそらく形容詞でしょう。
この段階に関しては多くの経験が必要ということはないでしょう。
? その単語の役割を考える
たとえば不明な語が名詞とわかり、それが動詞の前に位置していれば、倒置でもしていない限り、主語をやっていることはわかる。そうなると、「○○は」とまでは訳せる。
ここまでくると、カタカナが多く混じった、化粧品の宣伝みたいな訳文に達するでしょう。そこまでくれば、「意味の類推」もさほど困難ではないかと思います。
「私の○○な科目である○○の問題は、私を錯乱させた」
とでもわかれば、この○○に入る語句はそう難しくない。前者はおそらくは「苦手・不得意」で、後者は科目名、たとえば数学でしょう。そして、この人がどの科目が苦手かは前後を見ればまあわかるでしょう。
単語を増やせば増やすほど有利ではありますが、そこを強調すると「意味の分からないものを大量に覚えこむ」という非人間的な作業に学生を追い込んでしまい、英語ができる=非人間的なんて妙なことにまでなりかねません。
それにしても、ほかの科目に比べて、なんとまあ多様なものでしょうか。私の専門は歴史でしたが、これの学び方はそうは多くないように思います。
学び方が多様ということ自体が何かを物語っているように思えます。
予備校で17年教えています。
担当する生徒数は多かった時期には1000人、
この頃は300人くらいでしょうか。
単語帳の使用については、
大きく変わってきているという印象です。
10年ほど前には「単語は単語帳で覚えるものだ」と堅く信じている生徒が多かった。
英語と日本語とひとつずらして覚えている生徒も続出でした。
(全然、違う訳をいうので、何だと思うと、単語帳の前か後の単語と勘違いしている)
その頃は教師側の指導は「長文の中で、復習して覚えるように」でした。
自分が単語帳での暗記がうまくいったことがなかったですし。。
その後、投野先生の「最終的にはリストで覚える力が必要」に感化され、
また「論理的思考以上に暗記行為が脳の活性化に役立つ」という脳生理学の話を読んだりしたので、
単語帳で覚えることも悪くないなと思うようになりました。
かつ、生徒側にも変化があり、
単語帳は持っているものの、覚えようとしていない生徒がほとんどになりました。
こうなると、「単語帳を使おう」「単語帳では覚えられないが、その単語を文中でふたたび見たときに、『あっ、知ってるぞ、見たことある』となれば、その時に覚えられる」と指導しているのが現況です。
私自身は、前述のようにリストで覚えることは非常に困難です。しかし、10代、20代前半までの歳でしたら可能でしょう。
「単語帳で覚える」「文中で類推する」の2者択一でないことは確かです。
「単語を覚える」という行為が「単語の意味がわからなければ、文の意味がとれない」との偏見に結びつかないことを願うばかりです。
自分が学習してきた中で、Timeを読み始めたときは15%が知らない単語でした。(1行13個の中で2個知らない)当然、わからないのは内容語ですから、ちんぷんかんぷんです。それが、よくしたもので、2ページ読むと、おぼろげながら何を言ってるのかわかってくるのです。
英語圏で生活体験のある人は「単語は知らないのに、内容がとれる」様もつぶさに見ました。
英語の達人と呼ばれうる方々で「わからない単語がたくさんある文章をひたすら読み続けた経験が一番の勉強だった」とおっしゃる方は多いです。
担当する生徒数は多かった時期には1000人、
この頃は300人くらいでしょうか。
単語帳の使用については、
大きく変わってきているという印象です。
10年ほど前には「単語は単語帳で覚えるものだ」と堅く信じている生徒が多かった。
英語と日本語とひとつずらして覚えている生徒も続出でした。
(全然、違う訳をいうので、何だと思うと、単語帳の前か後の単語と勘違いしている)
その頃は教師側の指導は「長文の中で、復習して覚えるように」でした。
自分が単語帳での暗記がうまくいったことがなかったですし。。
その後、投野先生の「最終的にはリストで覚える力が必要」に感化され、
また「論理的思考以上に暗記行為が脳の活性化に役立つ」という脳生理学の話を読んだりしたので、
単語帳で覚えることも悪くないなと思うようになりました。
かつ、生徒側にも変化があり、
単語帳は持っているものの、覚えようとしていない生徒がほとんどになりました。
こうなると、「単語帳を使おう」「単語帳では覚えられないが、その単語を文中でふたたび見たときに、『あっ、知ってるぞ、見たことある』となれば、その時に覚えられる」と指導しているのが現況です。
私自身は、前述のようにリストで覚えることは非常に困難です。しかし、10代、20代前半までの歳でしたら可能でしょう。
「単語帳で覚える」「文中で類推する」の2者択一でないことは確かです。
「単語を覚える」という行為が「単語の意味がわからなければ、文の意味がとれない」との偏見に結びつかないことを願うばかりです。
自分が学習してきた中で、Timeを読み始めたときは15%が知らない単語でした。(1行13個の中で2個知らない)当然、わからないのは内容語ですから、ちんぷんかんぷんです。それが、よくしたもので、2ページ読むと、おぼろげながら何を言ってるのかわかってくるのです。
英語圏で生活体験のある人は「単語は知らないのに、内容がとれる」様もつぶさに見ました。
英語の達人と呼ばれうる方々で「わからない単語がたくさんある文章をひたすら読み続けた経験が一番の勉強だった」とおっしゃる方は多いです。
いっちぃーさんの言うとおり、個人の学習スタイルの適性によって単語帳の使用がいいかどうかも異なると感じます。
ただ、高校生ぐらいまでのレベルでは、ある程度暗記的要素は必須であると感じます。特に名詞と動詞は最低限知らないとリスニングもリーディングも歯が立たないのではないでしょうか。
ある程度のレベルに達すれば、推測することで自然に身につくという方法も指導法のひとつでしょうし、ひたすら暗記に走る事で資格試験にパスするというのもひとつの方法であると思います。
未知語が○%ということよりも、自分のレベルに合った文章を選ぶ能力というのも必要であると思います。最近は難解な文学作品でも英語学習者用にやさしい英語で書かれたものが多く出回っています。
あおこさんの、「わからない単語がたくさんある文章をひたすら読み続けた経験が一番の勉強だった」とおっしゃる方は多い、というのは同感です。ただし、やはり基礎をきちっと勉強してきた人のほうが英語の慣れや推測スキルも身につくのが早い印象です。
試験問題のタイプによって学習方法も異なります。大学院留学用のテストであるGREは、語彙重視から読解力重視へとテスト傾向が変化するようです。
アジア人留学生は難しい単語をたくさん知っているのに表現力でやや劣ります。こういうことを考えると、ある一定レベルを超えると、試験用の英語としては暗記型は有効ですが、実用レベルでは不十分ということではないかと思います。
日本の英語教育の難点ばかり指摘される今日ですが、私は恩恵もあったのではないかと感じます。読解力に関しては、基礎的な文法理解と語彙力なしには達成し得ないことですから。
ただ、高校生ぐらいまでのレベルでは、ある程度暗記的要素は必須であると感じます。特に名詞と動詞は最低限知らないとリスニングもリーディングも歯が立たないのではないでしょうか。
ある程度のレベルに達すれば、推測することで自然に身につくという方法も指導法のひとつでしょうし、ひたすら暗記に走る事で資格試験にパスするというのもひとつの方法であると思います。
未知語が○%ということよりも、自分のレベルに合った文章を選ぶ能力というのも必要であると思います。最近は難解な文学作品でも英語学習者用にやさしい英語で書かれたものが多く出回っています。
あおこさんの、「わからない単語がたくさんある文章をひたすら読み続けた経験が一番の勉強だった」とおっしゃる方は多い、というのは同感です。ただし、やはり基礎をきちっと勉強してきた人のほうが英語の慣れや推測スキルも身につくのが早い印象です。
試験問題のタイプによって学習方法も異なります。大学院留学用のテストであるGREは、語彙重視から読解力重視へとテスト傾向が変化するようです。
アジア人留学生は難しい単語をたくさん知っているのに表現力でやや劣ります。こういうことを考えると、ある一定レベルを超えると、試験用の英語としては暗記型は有効ですが、実用レベルでは不十分ということではないかと思います。
日本の英語教育の難点ばかり指摘される今日ですが、私は恩恵もあったのではないかと感じます。読解力に関しては、基礎的な文法理解と語彙力なしには達成し得ないことですから。
私も進学校勤務時代は、学校指定の単語集を使って、毎週テストを実施し、基準点に達していないと残して再テストした物ですが、やはり疑問に思っていました。
単語集だけで語彙力は身に付く物なのか。
特に自分は単語集を使わず、長文の道の単語を類推したり辞書を引いたりして、文脈の中で覚えてきた物です。
使いようではあると思うのですが、受験生がそれまでに覚えた
単語を整理するために使うのはいいと思うのですが、単語集自体
に重点をおいた指導は疑問があります。
たくさん読んで、意味を類推しながら辞書をボロボロになるまで
ひく。
これが最も効率的な語彙力増加方法だと思うのですが。
要は単語集を生かすも殺すも使い方次第ではないかと。
通訳レベルの人になると、話題に沿った単語をリストにして
丸暗記するそうですが。普通の受験生には厳しいでしょう。
単語集だけで語彙力は身に付く物なのか。
特に自分は単語集を使わず、長文の道の単語を類推したり辞書を引いたりして、文脈の中で覚えてきた物です。
使いようではあると思うのですが、受験生がそれまでに覚えた
単語を整理するために使うのはいいと思うのですが、単語集自体
に重点をおいた指導は疑問があります。
たくさん読んで、意味を類推しながら辞書をボロボロになるまで
ひく。
これが最も効率的な語彙力増加方法だと思うのですが。
要は単語集を生かすも殺すも使い方次第ではないかと。
通訳レベルの人になると、話題に沿った単語をリストにして
丸暗記するそうですが。普通の受験生には厳しいでしょう。
>コーヅさん
私は受験期そのように単語帳を使っていました。
なぜなら長文で単語帳に載っている単語以外は基本的にはその長文だから出てきたもので、普遍的ではないからです。
もちろんそれだけでは不十分なので、平行して休み時間や授業が始まる数分前などは単語帳をぱらぱらと見ておりました。
単語は「さぁ、いまから覚えるぞ」といって紙に書きなぐって覚えるのは効率が悪いと思います。
何度も何度も目に焼き付けるほうが効果的でしょう。
長文で出てきた単語を単語帳で調べて印をつける。
今度また調べて、前に印をつけていれば違う色で印をつける。
・
・
・
というのを繰り返せば何色もの印がついている単語は覚えてしまいます。
そして単語帳の持つ意味は「達成感」にもあるのではないでしょうか。
私はたくさん印をつけたり、マーカーを引きました。
そして最終的には「この単語を今覚える!」と決めた瞬間鉛筆で黒く塗りつぶしていました。
受験期が終われば単語帳は自然に1,5倍から2倍にほわっっとなり、めくると自分がいろんな書き込みをしてあるので「よくやった」と思えるものです。
ひとつの自身にもつながります。
私は今この方法を生徒に教えています。
時間がないのに単語だけ机に向かって覚えるのはナンセンスです。
分からない単語を、それもでる単語から覚えていく。
私はこの方法が今のところ時間短縮の意味もこめて最善だとおもっています。
はなしが少しそれましたが、やはり単語帳はうまくつかって受験に利用すべきだと思います。
私は受験期そのように単語帳を使っていました。
なぜなら長文で単語帳に載っている単語以外は基本的にはその長文だから出てきたもので、普遍的ではないからです。
もちろんそれだけでは不十分なので、平行して休み時間や授業が始まる数分前などは単語帳をぱらぱらと見ておりました。
単語は「さぁ、いまから覚えるぞ」といって紙に書きなぐって覚えるのは効率が悪いと思います。
何度も何度も目に焼き付けるほうが効果的でしょう。
長文で出てきた単語を単語帳で調べて印をつける。
今度また調べて、前に印をつけていれば違う色で印をつける。
・
・
・
というのを繰り返せば何色もの印がついている単語は覚えてしまいます。
そして単語帳の持つ意味は「達成感」にもあるのではないでしょうか。
私はたくさん印をつけたり、マーカーを引きました。
そして最終的には「この単語を今覚える!」と決めた瞬間鉛筆で黒く塗りつぶしていました。
受験期が終われば単語帳は自然に1,5倍から2倍にほわっっとなり、めくると自分がいろんな書き込みをしてあるので「よくやった」と思えるものです。
ひとつの自身にもつながります。
私は今この方法を生徒に教えています。
時間がないのに単語だけ机に向かって覚えるのはナンセンスです。
分からない単語を、それもでる単語から覚えていく。
私はこの方法が今のところ時間短縮の意味もこめて最善だとおもっています。
はなしが少しそれましたが、やはり単語帳はうまくつかって受験に利用すべきだと思います。
邪道だといわれそうですが、私は単語集を使って単語を覚えることは悪いことだとは思っていません。むしろ推奨しています。
単語集で勉強すると生きた使い方がわからないってよく耳にしますが、では生の英文にあたっていれば生きた使い方がわかるようになるというのは本当でしょうか。例えば、何度も見たことがあるはずの単語ですが、select と choose がどのように違っているのかといわれて、きちんと答えられる人ってそんなにいますか?私の経験では英語教師でもほとんどいないと思います。
1行に1つくらいでもわからない単語が出てくるときに、文章全体の意味を考えることに目が向けられるのは、相当な強者だと思います。高校生の力量からすると、仮に全ての単語の意味をあらかじめ教えられていたとしても内容を読み取るのが困難だという文章だって、大学入試レベルの比較的易しい英文でもかなりあると思います。「落ち着いて考えればわかる」というのは、経験値のある大人の発想からそう思うだけっていうことも、案外多いのではないでしょうか。
標準的な模試で偏差値70程度以上はある、相当に優秀な生徒たちだけを相手にして、合理的類推を鍛えることばかりに1年間の授業の大半を注いでみても、結果はそれほど芳しいものではなかったりします。もちろん、私の指導力の限界というものもあるでしょうが、高校生としての教養・思考レベルの到達度というものも影響しているものだと思います。
大人は高校生時代と今の自分の教養・思考レベルの違いに一般に気付きにくいのではないでしょうか。そこで、つい現段階の大人の発想で「こう考えれば当然わかるはず」と思ってしまいがちなのではないでしょうか。それは正論であるが故に、生徒の方からしても、説明を受ければ「なるほど!」とは一応思ってもらえます。ではそのような類推を自力で消化するだけのバックグラウンドがあるのかといえば実はないということはないでしょうか。正当な指導が生徒には過大であるということも大いにありうるのではないでしょうか。
今の単語集にはたいていは実際に使われているフレーズや使用例文が掲載されています。そうしたフレーズや例文の方が生の英語に触れる場合よりも標準的で「安全」な文であることの方が多いと思います。フレーズや例文を活用して覚えるようにし向けている単語集は、むしろ積極的に使ってよいと、個人的には思います。
「単語集を見るな。辞書を引け。」というのは、よく耳にしますが、生徒は辞書を引いたときに見ているのは殆ど意味だけではないでしょうか。基本的な意味がわからない時には、意識が意味に集中してしまうのはしょうがないことだと思います。「今までと違った使い方のような気がするが...」というような思いを持たないと、辞書を丹念に読むところまではなかなか進めないものだと思うのです。辞書を引く意味がわかるのはかなりの上級者になってからで、大学受験レベルの高校生に一般に期待するのは難しいことだと思います。
単語集を使って必要な単語をさっさと覚え、わからない単語が少ない状態でストレス少なく英文が読めるようになるというのは、本質的な英語の勉強の仕方により早く接近できるという点で、効果の大きいものではないかと思います。良質の単語集を紹介し、その正しい使い方を教え、無理の少ないステップで身につけられるように指導するというのは、本質的な英語の勉強に向かわせることに実は役立つ手法だと、私は考えています。
単語集で勉強すると生きた使い方がわからないってよく耳にしますが、では生の英文にあたっていれば生きた使い方がわかるようになるというのは本当でしょうか。例えば、何度も見たことがあるはずの単語ですが、select と choose がどのように違っているのかといわれて、きちんと答えられる人ってそんなにいますか?私の経験では英語教師でもほとんどいないと思います。
1行に1つくらいでもわからない単語が出てくるときに、文章全体の意味を考えることに目が向けられるのは、相当な強者だと思います。高校生の力量からすると、仮に全ての単語の意味をあらかじめ教えられていたとしても内容を読み取るのが困難だという文章だって、大学入試レベルの比較的易しい英文でもかなりあると思います。「落ち着いて考えればわかる」というのは、経験値のある大人の発想からそう思うだけっていうことも、案外多いのではないでしょうか。
標準的な模試で偏差値70程度以上はある、相当に優秀な生徒たちだけを相手にして、合理的類推を鍛えることばかりに1年間の授業の大半を注いでみても、結果はそれほど芳しいものではなかったりします。もちろん、私の指導力の限界というものもあるでしょうが、高校生としての教養・思考レベルの到達度というものも影響しているものだと思います。
大人は高校生時代と今の自分の教養・思考レベルの違いに一般に気付きにくいのではないでしょうか。そこで、つい現段階の大人の発想で「こう考えれば当然わかるはず」と思ってしまいがちなのではないでしょうか。それは正論であるが故に、生徒の方からしても、説明を受ければ「なるほど!」とは一応思ってもらえます。ではそのような類推を自力で消化するだけのバックグラウンドがあるのかといえば実はないということはないでしょうか。正当な指導が生徒には過大であるということも大いにありうるのではないでしょうか。
今の単語集にはたいていは実際に使われているフレーズや使用例文が掲載されています。そうしたフレーズや例文の方が生の英語に触れる場合よりも標準的で「安全」な文であることの方が多いと思います。フレーズや例文を活用して覚えるようにし向けている単語集は、むしろ積極的に使ってよいと、個人的には思います。
「単語集を見るな。辞書を引け。」というのは、よく耳にしますが、生徒は辞書を引いたときに見ているのは殆ど意味だけではないでしょうか。基本的な意味がわからない時には、意識が意味に集中してしまうのはしょうがないことだと思います。「今までと違った使い方のような気がするが...」というような思いを持たないと、辞書を丹念に読むところまではなかなか進めないものだと思うのです。辞書を引く意味がわかるのはかなりの上級者になってからで、大学受験レベルの高校生に一般に期待するのは難しいことだと思います。
単語集を使って必要な単語をさっさと覚え、わからない単語が少ない状態でストレス少なく英文が読めるようになるというのは、本質的な英語の勉強の仕方により早く接近できるという点で、効果の大きいものではないかと思います。良質の単語集を紹介し、その正しい使い方を教え、無理の少ないステップで身につけられるように指導するというのは、本質的な英語の勉強に向かわせることに実は役立つ手法だと、私は考えています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英語学習法・英文法のQ&A 更新情報
-
最新のアンケート
英語学習法・英文法のQ&Aのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90067人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170697人