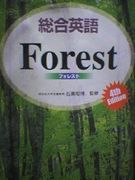桐原書店・英語長文ハイパートレーニング・レベル2【センターレベル編】のUNIT1の英文です。地球の様々な部分は相互に関係しているという内容のもので、
Why is our earth the kind of planet? Not only because it is full of a number of things.と始まり、続いての文。
Not only because some parts are more full of things than others.という文についてです。
解説によると、bcauseの節の主語がsome parts、そして動詞がare。それはもちろん納得できるのですが、fullを補語としていて、その和訳として、
「いくつかの部分は他の部分よりももっと多くのもので満ちているからだけではない」
とされています。ひっかかるのはmoreの働きです。和訳を踏まえると、これはmanyの比較級でthingsにかかるのか、でもそうなるとmoreはthingsの前に置くべきではないか?いやそれともfullの比較級の一部で、more fullでfullの比較級を形成しているのか?でもfullの比較級はfullerではないのか?と悩んでいる次第です。どなたかこの疑問に対してお答えいただきたく、その旨お願い申し上げます!
Why is our earth the kind of planet? Not only because it is full of a number of things.と始まり、続いての文。
Not only because some parts are more full of things than others.という文についてです。
解説によると、bcauseの節の主語がsome parts、そして動詞がare。それはもちろん納得できるのですが、fullを補語としていて、その和訳として、
「いくつかの部分は他の部分よりももっと多くのもので満ちているからだけではない」
とされています。ひっかかるのはmoreの働きです。和訳を踏まえると、これはmanyの比較級でthingsにかかるのか、でもそうなるとmoreはthingsの前に置くべきではないか?いやそれともfullの比較級の一部で、more fullでfullの比較級を形成しているのか?でもfullの比較級はfullerではないのか?と悩んでいる次第です。どなたかこの疑問に対してお答えいただきたく、その旨お願い申し上げます!
|
|
|
|
コメント(6)
“full”を比較級にすることは希だと思います。
fullの状態を比べることってあるのでしょうか? 飽和した状態は量・大きさ・モノ・コトに関わらず飽和している(ような)状態に変わりはないと思うと、「fullの状況を比べる」という状況がイメージしにくいです。和訳は和訳。和訳はプロがやっても多少の差は出るものだと思うので、そんなに神経質にならなくていいと思います。(受験はそうもいかないのでしょうけど…。)
この場合−full of things−が名詞句になっていて、そこに比較級が加わっていると考える方が自然だと思います。
つまり元の文は“some parts are full of things.” “some parts are full.”では「何でいっぱい」なのかがわからない。−some parts are full of elephants.−なのか、−full of mosquitoes.−なのか…。
−full−は、UnC・Countable nounがとにかくたくさんある状態を表してる形容詞なので、レストランなどで食事が終って“I'm full.”というとき以外の、こういう文章の中では、その材料が示されているのが普通だと思うのです。だから、-full of things-で(とりあえず)名詞句として成立していると思います。
ということはmoreは形容詞を修飾する比較級、つまり副詞muchの比較級;moreだということでいいかと思います。
…以上が私の見解ですが、それ以前に何か、英文そのものが抽象的で意味がわからないような気がするのは私だけでしょうか? 「thingsって何を指しているの?」と文を作成した方にお伺いしたいところです。普通、具体性を欠いた内容を嫌う英文は“things”の後に、“that S V”とかで、thingsについての具体的説明があるはずです。
英文レポートをnativeの先生に見せて採点してもらうと、例えば「weって誰? theyって誰? 日本語と違って英語で論文・レポートを書くときはちょっとくどいくらいの具体性がないとダメだから。」と一度注意されたことがあります。 あと“not only”って、前後に“but (also)”だったり、これに代わる“〜もまた、○○である”的なセンテンスがあってしかるべきなのですが。しかも、一文で切れずに。“not only because 〜”って言うくらいなんだから、これよりも強い主張のセンテンスがあってしかるべきです。しかも「not onlyを2回も2文に分けて続けるってどういうこと?」っていうのが正直な気持ちです。この文の作成者は学術英文を書いたことのない人だと思います。
「なぜ、地球は惑星の種類なのか(惑星という分類にカテゴライズされるのか)。 たくさんの物(事)で溢れかえっているからだけではない。いくつかの部分は他の部分よりももっと多くのもので満ちているからだけではない。」
だいたいのあたりで勘弁してくれるとして、これでおおよそ外れのない訳だと思うのですが、日本語にしてみてもおかしくないですか? 「じゃあ正体は何? 部分ってどこの部分? 何の部分? itはearth,planet,space,universeのうち、どれを指しているの? thingsって何?」と聞き返したくなります。
全文読んでいないから、以上のことを含めて断言はできないけど、これを読む限りは、こんな文章を読んで「英語ができるようになれ」っていうほうが無理。桐原は優れた英語の教材や英英辞書で信頼しているけど、この教材に関しては残念としか言いようがない。
fullの状態を比べることってあるのでしょうか? 飽和した状態は量・大きさ・モノ・コトに関わらず飽和している(ような)状態に変わりはないと思うと、「fullの状況を比べる」という状況がイメージしにくいです。和訳は和訳。和訳はプロがやっても多少の差は出るものだと思うので、そんなに神経質にならなくていいと思います。(受験はそうもいかないのでしょうけど…。)
この場合−full of things−が名詞句になっていて、そこに比較級が加わっていると考える方が自然だと思います。
つまり元の文は“some parts are full of things.” “some parts are full.”では「何でいっぱい」なのかがわからない。−some parts are full of elephants.−なのか、−full of mosquitoes.−なのか…。
−full−は、UnC・Countable nounがとにかくたくさんある状態を表してる形容詞なので、レストランなどで食事が終って“I'm full.”というとき以外の、こういう文章の中では、その材料が示されているのが普通だと思うのです。だから、-full of things-で(とりあえず)名詞句として成立していると思います。
ということはmoreは形容詞を修飾する比較級、つまり副詞muchの比較級;moreだということでいいかと思います。
…以上が私の見解ですが、それ以前に何か、英文そのものが抽象的で意味がわからないような気がするのは私だけでしょうか? 「thingsって何を指しているの?」と文を作成した方にお伺いしたいところです。普通、具体性を欠いた内容を嫌う英文は“things”の後に、“that S V”とかで、thingsについての具体的説明があるはずです。
英文レポートをnativeの先生に見せて採点してもらうと、例えば「weって誰? theyって誰? 日本語と違って英語で論文・レポートを書くときはちょっとくどいくらいの具体性がないとダメだから。」と一度注意されたことがあります。 あと“not only”って、前後に“but (also)”だったり、これに代わる“〜もまた、○○である”的なセンテンスがあってしかるべきなのですが。しかも、一文で切れずに。“not only because 〜”って言うくらいなんだから、これよりも強い主張のセンテンスがあってしかるべきです。しかも「not onlyを2回も2文に分けて続けるってどういうこと?」っていうのが正直な気持ちです。この文の作成者は学術英文を書いたことのない人だと思います。
「なぜ、地球は惑星の種類なのか(惑星という分類にカテゴライズされるのか)。 たくさんの物(事)で溢れかえっているからだけではない。いくつかの部分は他の部分よりももっと多くのもので満ちているからだけではない。」
だいたいのあたりで勘弁してくれるとして、これでおおよそ外れのない訳だと思うのですが、日本語にしてみてもおかしくないですか? 「じゃあ正体は何? 部分ってどこの部分? 何の部分? itはearth,planet,space,universeのうち、どれを指しているの? thingsって何?」と聞き返したくなります。
全文読んでいないから、以上のことを含めて断言はできないけど、これを読む限りは、こんな文章を読んで「英語ができるようになれ」っていうほうが無理。桐原は優れた英語の教材や英英辞書で信頼しているけど、この教材に関しては残念としか言いようがない。
moreが何かについてはたっつんさんと同じ見解ですが、
この文そのものについては、後続文が当然あるのですから、
導入として全くおかしくないと思います。
Not only becauseがふたつ続いて出てくるのも
「畳み込み」として有効だと思います。
thingsが何を指しているのかわからないのも、後続文で明らかにされるはずです。
その文だけで全てがわかるような長文の方がむしろ稀であり、
先を読ませるための常套手段だと思います。
私には、some---othersを「いくつか」「他」と和訳にあることが気にかかる点です。「他」はthe がないと訳せないはずで、
some---othersと冠詞なしでつかわれる場合は
「〜もあるし、〜もある」と訳すのが、現在では「お約束」だと思います。
「より多くのもので満ちている場所もあれば、そうでない場所もある」
となると、thingは惑星の構成物質のことじゃないかな?と推測は読者にさせますが、後続文を読ませるためにあえて明示はしてないと思います。
この文そのものについては、後続文が当然あるのですから、
導入として全くおかしくないと思います。
Not only becauseがふたつ続いて出てくるのも
「畳み込み」として有効だと思います。
thingsが何を指しているのかわからないのも、後続文で明らかにされるはずです。
その文だけで全てがわかるような長文の方がむしろ稀であり、
先を読ませるための常套手段だと思います。
私には、some---othersを「いくつか」「他」と和訳にあることが気にかかる点です。「他」はthe がないと訳せないはずで、
some---othersと冠詞なしでつかわれる場合は
「〜もあるし、〜もある」と訳すのが、現在では「お約束」だと思います。
「より多くのもので満ちている場所もあれば、そうでない場所もある」
となると、thingは惑星の構成物質のことじゃないかな?と推測は読者にさせますが、後続文を読ませるためにあえて明示はしてないと思います。
あおこ♪さん
ご意見ありがとうございます。なるほど。『畳み込み』という文章の書き方があるのですか。
しかしながら、そうであったとしてもNot only...and ... .で続けるべきだと思いますし、さらに英語のEssayにおいては文を短く切るのは稚拙な文章に見えるのでそういう書き方は避けらるとも思います。そしてやはり、but...で筆者の主張が行われるべきです。
『読者を引きつける』というのはnovelならあるかも知れませんが、こういったacademic essayに置いては、intro., body, conclu.と分かれ、さらにbodyに置いてはSupport Opinion1,2,3と分かれ、さらにそのSO1,2,3を支える具体的事例を有するDetails of SOが各2つずつ必要である、というのが世界標準の正式な書体であると理解しています。TOEFL、iELTSなどのテストもこれに従っています。その点についてはどうなのでしょうか? よろしければ、ご意見いただきたいです。
また『お約束』については『受験において』です。日本人が決めたルールや、そういった方式に当てはめたがる考え方は、そのほとんどがnative Ph.Dの前では“not true”です。
このコミュニティーには学生の方も多くいるかと思いますが、人文系のnative Ph.Dがいる大学にいる方、もしくはこれから行く方は、ぜひ彼らにいろいろ聞いてみてください。英語を身につけるプロセスはどうあるべきなのか、なんで日本人は英語がうまくできないのか、おそらくその時までやっていたカタチとは明らかな違いを見出すはずです。
和訳を基準に英語を顧みたり比較したり考えたり、和訳を書かせたりすることが、そもそも日本の英語教育の問題だと思うのです。文法を学ぶことはもちろん大事ですが、nativeにはどう受け取られているのか、日本の英語教育のやり方はどこがまずいのか、世界で通用するacademic writingと日本人の書く英語はどう違うのか、今まで自分が正しいと思って予備校などで教わってきたやり方・考え方が実は違っていた、なんてことはみなさんにも十分、何度となく起こり得ます。そういったことを考えると、今の日本の英語教育方法は支持できません。
話が広がってしまいましたが、私が思うところはそんな感じです。
ご意見ありがとうございます。なるほど。『畳み込み』という文章の書き方があるのですか。
しかしながら、そうであったとしてもNot only...and ... .で続けるべきだと思いますし、さらに英語のEssayにおいては文を短く切るのは稚拙な文章に見えるのでそういう書き方は避けらるとも思います。そしてやはり、but...で筆者の主張が行われるべきです。
『読者を引きつける』というのはnovelならあるかも知れませんが、こういったacademic essayに置いては、intro., body, conclu.と分かれ、さらにbodyに置いてはSupport Opinion1,2,3と分かれ、さらにそのSO1,2,3を支える具体的事例を有するDetails of SOが各2つずつ必要である、というのが世界標準の正式な書体であると理解しています。TOEFL、iELTSなどのテストもこれに従っています。その点についてはどうなのでしょうか? よろしければ、ご意見いただきたいです。
また『お約束』については『受験において』です。日本人が決めたルールや、そういった方式に当てはめたがる考え方は、そのほとんどがnative Ph.Dの前では“not true”です。
このコミュニティーには学生の方も多くいるかと思いますが、人文系のnative Ph.Dがいる大学にいる方、もしくはこれから行く方は、ぜひ彼らにいろいろ聞いてみてください。英語を身につけるプロセスはどうあるべきなのか、なんで日本人は英語がうまくできないのか、おそらくその時までやっていたカタチとは明らかな違いを見出すはずです。
和訳を基準に英語を顧みたり比較したり考えたり、和訳を書かせたりすることが、そもそも日本の英語教育の問題だと思うのです。文法を学ぶことはもちろん大事ですが、nativeにはどう受け取られているのか、日本の英語教育のやり方はどこがまずいのか、世界で通用するacademic writingと日本人の書く英語はどう違うのか、今まで自分が正しいと思って予備校などで教わってきたやり方・考え方が実は違っていた、なんてことはみなさんにも十分、何度となく起こり得ます。そういったことを考えると、今の日本の英語教育方法は支持できません。
話が広がってしまいましたが、私が思うところはそんな感じです。
>full of things というのを一つの形容詞的に、名詞句ではなく、句として捉えているから、more を使っているのだと思います。
そうでした。full of thingsが名詞句で、それを副詞muchの比較級が修飾するのはおかしいです。moreが副詞で、fullが形容詞、of thingsでその内容を示す、からfull of thingsで形容詞句ですね。その点、私の記述は間違いでした。キャップさん、ごめんなさい。
fullの比較は密度の違いを示す、ということも考えられるような気もします。
>「なぜ地球が惑星の種類なのか」ではなくて「なぜ地球がこのタイプの惑星なのか」ではないでしょうか?
そうですね。the kind of planetって部分を考えれば、その和訳のほうがより適格ですね。ざっくりとした訳ですみませんでした。
>Not only because ... Not only because ... というのが連続であっても何らおかしくはないと思います。文脈の中で見てみると、話の筋が通っているはずです。
話の筋が通っている、いない、ということについてではなく、「書き方」として標準的じゃない、ということです。こういう文章を読ませているから、日本人の英文記述は質が低い、と言われるのだと思います(大学教授含む)。この後に目玉となる理由が来るのも推測できます。ただ、英文として「いい文章ではない」ということです。
文章も漠然としすぎている。文中のit, the kind, things, partsなり、どこか具体的な説明があるべきだとは思いませんか? 「文全体を読ませて、内容を把握させるような力を身につけさせよう」という意図がこの問題からは感じられますが、必要以上に悩ませているだけのような気がします。
センター試験の英語に使う文献が、こんな文献ではダメです。センターは別に落とすための試験じゃないはずです。3000〜5000語程度の単語力が高3生にはあるとされているらしいですが、その範囲の単語を使って正統派に近いカタチの学術形体のessayのスタイルになじませることはできるはずです。
>novel 以外が academic essay だということにはならない。
確かに。「科学読み物」というカジュアルな読み物として、アカデミックなスタイルに沿ってなくてもいいとは思いますが、だとしてもキレイな一文だはと思わないです。
not only...but alsoはそれこそ受験で頻出の「公式」として呪文のように叩き込まれていると思います。作文をした方が「いつも公式通りじゃないんだよ」というメッセージがあるなら別ですが、やっぱりこの導入の部分は、いい文章ではない。
「科学読み物」かも知れませんが、センターは大学受験のための試験です。これから大学に行こうとする学生の試験です。
「intro., body, conclu.」の細かい構成とまでとはいかなくとも、一文一文がなるべく学術系のessay, paperの書き方に沿った文献であるべきで、その対策に使われる問題集も、そういった内容のものに親しんでもらえるような形式にすべきだと思います。いい学術英文がどんなものなのか、意識しないでもなじめるような感じが望ましいと思うのです。
そうでした。full of thingsが名詞句で、それを副詞muchの比較級が修飾するのはおかしいです。moreが副詞で、fullが形容詞、of thingsでその内容を示す、からfull of thingsで形容詞句ですね。その点、私の記述は間違いでした。キャップさん、ごめんなさい。
fullの比較は密度の違いを示す、ということも考えられるような気もします。
>「なぜ地球が惑星の種類なのか」ではなくて「なぜ地球がこのタイプの惑星なのか」ではないでしょうか?
そうですね。the kind of planetって部分を考えれば、その和訳のほうがより適格ですね。ざっくりとした訳ですみませんでした。
>Not only because ... Not only because ... というのが連続であっても何らおかしくはないと思います。文脈の中で見てみると、話の筋が通っているはずです。
話の筋が通っている、いない、ということについてではなく、「書き方」として標準的じゃない、ということです。こういう文章を読ませているから、日本人の英文記述は質が低い、と言われるのだと思います(大学教授含む)。この後に目玉となる理由が来るのも推測できます。ただ、英文として「いい文章ではない」ということです。
文章も漠然としすぎている。文中のit, the kind, things, partsなり、どこか具体的な説明があるべきだとは思いませんか? 「文全体を読ませて、内容を把握させるような力を身につけさせよう」という意図がこの問題からは感じられますが、必要以上に悩ませているだけのような気がします。
センター試験の英語に使う文献が、こんな文献ではダメです。センターは別に落とすための試験じゃないはずです。3000〜5000語程度の単語力が高3生にはあるとされているらしいですが、その範囲の単語を使って正統派に近いカタチの学術形体のessayのスタイルになじませることはできるはずです。
>novel 以外が academic essay だということにはならない。
確かに。「科学読み物」というカジュアルな読み物として、アカデミックなスタイルに沿ってなくてもいいとは思いますが、だとしてもキレイな一文だはと思わないです。
not only...but alsoはそれこそ受験で頻出の「公式」として呪文のように叩き込まれていると思います。作文をした方が「いつも公式通りじゃないんだよ」というメッセージがあるなら別ですが、やっぱりこの導入の部分は、いい文章ではない。
「科学読み物」かも知れませんが、センターは大学受験のための試験です。これから大学に行こうとする学生の試験です。
「intro., body, conclu.」の細かい構成とまでとはいかなくとも、一文一文がなるべく学術系のessay, paperの書き方に沿った文献であるべきで、その対策に使われる問題集も、そういった内容のものに親しんでもらえるような形式にすべきだと思います。いい学術英文がどんなものなのか、意識しないでもなじめるような感じが望ましいと思うのです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英語学習法・英文法のQ&A 更新情報
-
最新のアンケート
英語学習法・英文法のQ&Aのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人