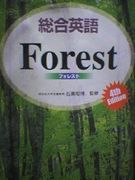失礼します。動詞において、動名詞と不定詞になるもの、またどちらともになるものがあります。この動詞について、どのような基準で分類されているのでしょうか?みなさまの意見をお聞かせください。
■(a) 一般に動名詞を目的語にとるとされているもの。
admit, advise, avoid, consider, defer, delay, deny, detest, dislike, enjoy,
escape, evade, excuse, fancy, finish, forbid, forgive, help, mind, permit,
postpone, practice, quit, resent, resist, risk, stop, suggest, etc.
(b) 一般に不定詞を目的語にとるとされているもの
afford, aim, arrange, attempt, care, choose, claim, contrive, decide, decline,
desire, determine, expect, fail, help, hesitate, hope, manage, offer, plan,
prepare, pretend, promise, refuse, resolve, seek, tend, undertake, yearn,
want, wish, etc.
不定詞(名詞)と動名詞の違いを探るにあたり,意味的特徴を考察する。
まず、各グループ内を下位分類することがはじめる。
なお、a・bの動詞たちは、「〜するのをVする」というような意を表す場合の意味として考察する。
■(a) 一般に動名詞を目的語にとるとされているもの。
admit, advise, avoid, consider, defer, delay, deny, detest, dislike, enjoy,
escape, evade, excuse, fancy, finish, forbid, forgive, help, mind, permit,
postpone, practice, quit, resent, resist, risk, stop, suggest, etc.
(b) 一般に不定詞を目的語にとるとされているもの
afford, aim, arrange, attempt, care, choose, claim, contrive, decide, decline,
desire, determine, expect, fail, help, hesitate, hope, manage, offer, plan,
prepare, pretend, promise, refuse, resolve, seek, tend, undertake, yearn,
want, wish, etc.
不定詞(名詞)と動名詞の違いを探るにあたり,意味的特徴を考察する。
まず、各グループ内を下位分類することがはじめる。
なお、a・bの動詞たちは、「〜するのをVする」というような意を表す場合の意味として考察する。
|
|
|
|
コメント(29)
>ree様、sela様、tdc様
コメントありがとうございます。実際自分も分類なんて意味わからないし必要ないと思います。これは教授から出た課題で、多分自分以外の他の者も同じ意見だと思います。
さて、いらないのではとなげやったところで学問は終わってしまうので考察してみたところ(んなこと言ってますが実際課題じゃなきゃやりません笑っ)
分類として、感情的や行動的など、意味が類似しているものをまとめました。またネイティブの感覚としてポジティブ、ネガティブなニュアンスをもつものにわけてみました。
明日教授から解答?がでるので、それをUpしたいと思います。
今回の質問は特異なものでした 失礼しました
失礼しました
コメントありがとうございます。実際自分も分類なんて意味わからないし必要ないと思います。これは教授から出た課題で、多分自分以外の他の者も同じ意見だと思います。
さて、いらないのではとなげやったところで学問は終わってしまうので考察してみたところ(んなこと言ってますが実際課題じゃなきゃやりません笑っ)
分類として、感情的や行動的など、意味が類似しているものをまとめました。またネイティブの感覚としてポジティブ、ネガティブなニュアンスをもつものにわけてみました。
明日教授から解答?がでるので、それをUpしたいと思います。
今回の質問は特異なものでした
そもそも、「動名詞になるもの / 不定詞になるもの」という表現は正しくなく、
「<目的語>として、<動名詞>または<不定詞>をとるもの」という表現にした方が
誤解がなくていいのだと思います。最初見たとき何のことかわからなかったので。。
selaさんのおっしゃっている原則にちょっと補足をすると、
<to不定詞>…未来指向
<動名詞> …事実指向(過去/現在)
となります。
I remember seeing her. であれば、seeing は<過去>を表しますが、
I enjoy working for this company. において、working 〜 は明らかに<現在>です。
私が言おうと思ったことを、selaさんが後半でまさにずばっとおっしゃっています。
文章を読んで“まさにその通りです!!”と思わず声を出してしまいましたが。
上の原則にそぐわないもの(例 : avoid doing など)も確かにありますが、
特に高校生などに<教える>場合などには、ある程度の効果はあると思います。
特に<未来指向>のものに関してはかなり適用範囲が広い気がします。
仮にトピ主さんが英語を教える仕事をしているもしくはこれからするのであれば、
いまのその姿勢は非常にまずいと思います。
もしそうでないのであれば、全く気にする必要はないと思いますが。
「<目的語>として、<動名詞>または<不定詞>をとるもの」という表現にした方が
誤解がなくていいのだと思います。最初見たとき何のことかわからなかったので。。
selaさんのおっしゃっている原則にちょっと補足をすると、
<to不定詞>…未来指向
<動名詞> …事実指向(過去/現在)
となります。
I remember seeing her. であれば、seeing は<過去>を表しますが、
I enjoy working for this company. において、working 〜 は明らかに<現在>です。
私が言おうと思ったことを、selaさんが後半でまさにずばっとおっしゃっています。
文章を読んで“まさにその通りです!!”と思わず声を出してしまいましたが。
上の原則にそぐわないもの(例 : avoid doing など)も確かにありますが、
特に高校生などに<教える>場合などには、ある程度の効果はあると思います。
特に<未来指向>のものに関してはかなり適用範囲が広い気がします。
仮にトピ主さんが英語を教える仕事をしているもしくはこれからするのであれば、
いまのその姿勢は非常にまずいと思います。
もしそうでないのであれば、全く気にする必要はないと思いますが。
私は生徒に分類して説明しています。
確かにavoidやmindはちょっと生徒が混乱する場合もありますが。
avoid doing →実際それが起こった(やっちゃった、なっちゃった)状態になることを"avoid"
enjoy doing →実際「している、起こっていること」を"enjoy"
remember doing→実際「起こったこと」をremember
remember to do →これか「すること」に向かう(to)ことを"remember
try doing 実際にしてみる
try to do すること(実現、実行)に向かって努力する
動名詞(doing)は「実際に起こっている感じ」
→がちゃ(ぴん)☆さんのいう「事実指向」
不定詞(to do)は「その動作に向かう行程も含めた感じ(manage to doなど特に)」
→がちゃ(ぴん)☆さんのいう「未来指向」
My hobby is to do 〜.とは言わず
My hobby is doing〜.と言う
というのも説明しやすい例の1つかもしれません。
説明するための日本語の使い方が難しいことが多いので、
教える立場としては、いかに無駄を省いてわかりやすく
生徒に伝えるか、ということに苦労していますが。
実際ネイティブにこの手の違いについて説明を求めると、
上手く説明してもらえなかったりしますよね。
逆に日本語の語彙変化について、日本語を勉強中の人に
質問されても、上手に説明出来ないことも多々。
でも私は生徒に「意味があるから、表現が違う」と教えています。
長くなってすいません。
確かにavoidやmindはちょっと生徒が混乱する場合もありますが。
avoid doing →実際それが起こった(やっちゃった、なっちゃった)状態になることを"avoid"
enjoy doing →実際「している、起こっていること」を"enjoy"
remember doing→実際「起こったこと」をremember
remember to do →これか「すること」に向かう(to)ことを"remember
try doing 実際にしてみる
try to do すること(実現、実行)に向かって努力する
動名詞(doing)は「実際に起こっている感じ」
→がちゃ(ぴん)☆さんのいう「事実指向」
不定詞(to do)は「その動作に向かう行程も含めた感じ(manage to doなど特に)」
→がちゃ(ぴん)☆さんのいう「未来指向」
My hobby is to do 〜.とは言わず
My hobby is doing〜.と言う
というのも説明しやすい例の1つかもしれません。
説明するための日本語の使い方が難しいことが多いので、
教える立場としては、いかに無駄を省いてわかりやすく
生徒に伝えるか、ということに苦労していますが。
実際ネイティブにこの手の違いについて説明を求めると、
上手く説明してもらえなかったりしますよね。
逆に日本語の語彙変化について、日本語を勉強中の人に
質問されても、上手に説明出来ないことも多々。
でも私は生徒に「意味があるから、表現が違う」と教えています。
長くなってすいません。
これまでの説明とだぶるところがありますが,微妙に異なるところもあるので,ぼくの説明を書きます。
前置詞の to は「目標点・到達点」を表します。
I go to school. は「私は行く,目標点は,学校」 です。
不定詞の to も基本は同じです。つまり,「目標点・到達点」です。
だから,I like to swim. は,私は好きです,目標点は泳ぐこと。
目標点だから,どちらかといえばこれからというニュアンスがあります。だから,みなさんが書いている,未来志向です。
I like to swim. は,これから泳ぎたいという感じが入っています。
それに対して ing は進行を表し,〜している状態 です。
I am swimming. は「私は泳いでいる状態にある」とい意味になります。
動名詞も同じです。
だから,I like swimming. は,「私は泳いでいる状態が好きです」となります。
だから,趣味は水泳というニュアンスが入ります。
I want to swim. は,私は欲する,何を欲するかの目標は泳ぐこと
I hope to swim. は,私は望む,何を望むかの目標点は泳ぐこと
という感じで,不定詞を目的語にとります。
それに対して,enjoy , stop などは,〜している状態を楽しむ,〜している状態をやめる,ということで動名詞を目的語にとります。
動名詞と現在分詞のちがいは意味というよりも働きです。動名詞は名詞として,現在分詞は形容詞として働くという違いです。
前置詞の to は「目標点・到達点」を表します。
I go to school. は「私は行く,目標点は,学校」 です。
不定詞の to も基本は同じです。つまり,「目標点・到達点」です。
だから,I like to swim. は,私は好きです,目標点は泳ぐこと。
目標点だから,どちらかといえばこれからというニュアンスがあります。だから,みなさんが書いている,未来志向です。
I like to swim. は,これから泳ぎたいという感じが入っています。
それに対して ing は進行を表し,〜している状態 です。
I am swimming. は「私は泳いでいる状態にある」とい意味になります。
動名詞も同じです。
だから,I like swimming. は,「私は泳いでいる状態が好きです」となります。
だから,趣味は水泳というニュアンスが入ります。
I want to swim. は,私は欲する,何を欲するかの目標は泳ぐこと
I hope to swim. は,私は望む,何を望むかの目標点は泳ぐこと
という感じで,不定詞を目的語にとります。
それに対して,enjoy , stop などは,〜している状態を楽しむ,〜している状態をやめる,ということで動名詞を目的語にとります。
動名詞と現在分詞のちがいは意味というよりも働きです。動名詞は名詞として,現在分詞は形容詞として働くという違いです。
このテーマは何度も話題になりますね。ちょっと長いですが僕のイメージを書いてみました(日記文のコピペです)。
"to 動詞原形"と"〜ing"の違いは、一言で言うと;
"to ―" 「離れてる」
"〜ing" 「くっ付いてる」
I ) "to 動詞原形"
"do(1) to do(2)"で先ず、do(1) から do(2) へ向かう「『指向性』又は『移動』のイメージ」があって、結果的に do(1) と do(2) が「離れてる感じ」になる。
よく、「『to不定詞』は『未来』を表す」という捉え方をすることがある。
"I want to go Canada."「カナダに行きたい」
("want" より "go" の方が未来)
これは違いを説明するのに便利な理屈ではあるし、多くの場合は結果的にそう言えることが多い。しかし、副詞的用法の"I'm glad to see you."という文では時系列が逆になる。
「あなたに会ったことで、嬉しい気持ちになった」ので、
「"be glad" より "see" の方が、厳密には過去」と言える。
そこでこれを「距離感」という言葉で表現してみる。
この「距離感」には「空間的距離感」の他に、
「時間(時系列)的距離感」
「論理的な距離感」
1)原因/理由→結果(因果関係)
2)目的の為の行為→目的
などを含む、広い意味での「距離感」をイメージしてみる。
すると、"I'm glad to see you."「あなたに会ったことで、嬉しい気持ちになった」の文では、「因果関係的な距離感がある」と言える。
「『指向性』又は『移動』のイメージ」という観点で言うと、「『嬉しい気持ちになった』という結果を踏まえて、その原因/理由に目を向けると・・・」という、「意識/視点の移動」がそこにある。時系列的には時間を遡っていて意識の方向は「現在→過去」で、そこに距離がある。
また;
1)「〜すること」(名詞的用法)
2)「〜するために…する」(副詞的用法・目的)
3)「〜するための…(物)」(形容詞的用法)
はどれも「論理的な距離感」があり、結果的に「時間的距離感」も生まれる。
*1)My dream is to be a teacher.
「先生になること」は「夢」の目的なので未来。
*2)I study hard to get the license."
「勉強する」ことで「免許を獲得する」という未来の目的に向かっている。
*3)I want something to drink.
「なにか」は「飲む」という未来の行為のために必要な物。
そしてこれらの「距離感」、「『指向性』又は『移動のイメージ』」はそもそも"to"という語のコアのイメージそのものだ。そういう意味では前置詞としての"to"と何ら変わりは無いと言える。
(つづく)
"to 動詞原形"と"〜ing"の違いは、一言で言うと;
"to ―" 「離れてる」
"〜ing" 「くっ付いてる」
I ) "to 動詞原形"
"do(1) to do(2)"で先ず、do(1) から do(2) へ向かう「『指向性』又は『移動』のイメージ」があって、結果的に do(1) と do(2) が「離れてる感じ」になる。
よく、「『to不定詞』は『未来』を表す」という捉え方をすることがある。
"I want to go Canada."「カナダに行きたい」
("want" より "go" の方が未来)
これは違いを説明するのに便利な理屈ではあるし、多くの場合は結果的にそう言えることが多い。しかし、副詞的用法の"I'm glad to see you."という文では時系列が逆になる。
「あなたに会ったことで、嬉しい気持ちになった」ので、
「"be glad" より "see" の方が、厳密には過去」と言える。
そこでこれを「距離感」という言葉で表現してみる。
この「距離感」には「空間的距離感」の他に、
「時間(時系列)的距離感」
「論理的な距離感」
1)原因/理由→結果(因果関係)
2)目的の為の行為→目的
などを含む、広い意味での「距離感」をイメージしてみる。
すると、"I'm glad to see you."「あなたに会ったことで、嬉しい気持ちになった」の文では、「因果関係的な距離感がある」と言える。
「『指向性』又は『移動』のイメージ」という観点で言うと、「『嬉しい気持ちになった』という結果を踏まえて、その原因/理由に目を向けると・・・」という、「意識/視点の移動」がそこにある。時系列的には時間を遡っていて意識の方向は「現在→過去」で、そこに距離がある。
また;
1)「〜すること」(名詞的用法)
2)「〜するために…する」(副詞的用法・目的)
3)「〜するための…(物)」(形容詞的用法)
はどれも「論理的な距離感」があり、結果的に「時間的距離感」も生まれる。
*1)My dream is to be a teacher.
「先生になること」は「夢」の目的なので未来。
*2)I study hard to get the license."
「勉強する」ことで「免許を獲得する」という未来の目的に向かっている。
*3)I want something to drink.
「なにか」は「飲む」という未来の行為のために必要な物。
そしてこれらの「距離感」、「『指向性』又は『移動のイメージ』」はそもそも"to"という語のコアのイメージそのものだ。そういう意味では前置詞としての"to"と何ら変わりは無いと言える。
(つづく)
II ) "〜ing"
「do(1) doing(2)」で do(1) と do(2) が「くっ付いてる」感じ。
"I enjoy talking." と言うとき、"enjoy"と"talk"は切り離す事が出来ない。これは過去形の文にすると分かり易い。
"I enjoyed talking."「私はお喋りすることを楽しんだ」
「楽しんだ」は、同時に「お喋りした」を意味する。
とりあえずこれは、時系列的に「くっついてる」という例。
"I remember talking to Mr. Archer."「アーチャー氏と話したことを覚えている」
時系列的には「アーチャー氏と話した」は過去で、「覚えている」は現在の意識の話だけど、「覚えている」と言うとき頭の中では記憶の中のその情景が動く映像としてイメージされていて、「過去の出来事をイメージの中で(今)再体験している」とも言える。
要するに「覚えてる」と言った時には「喋っている」が頭の中にあるということ。その場にあるから「くっ付いてる」。
そしてこれは時系列的に未来の話をしても同じ。
I suggest telling him the truth."「彼に真実を話すことを提案する」
"suggest"「提案する」は、そこに「ポン」と置くだけ。強制するイメージが無く、そもそも「誰に提案してるか」も無い。自分が話すかもしれないし、相手に勧めてるのかもしれない。共同で、かもしれない。
とにかく「移動」「指向性」が無いので「to不定詞」ではない。そしてその提案を言った時、聞いた時は、やはり頭の中で「真実を話している」をイメージしている。
少し話は変わるけど、"I'm swimming in the lake tomorrow afternoon."と、未来の事を言うのに現在進行形の形を使うのも、やはり頭の中で自分がその行為をして動いてる様子をイメージしてる。明日の午後の情景を思い浮かべながら。「〜だろう」とか「〜するつもり」とか、今の意識からの距離は無く「今の頭の中で、未来の自分は泳いでる」という「くっ付いた感じ」。
この「くっ付いた感じ」には、"〜ing"形の「その場で動いてるイメージ」が関係している。大西泰斗氏的に言うと「わしゃわしゃと」。そして「その場で」であって、to不定詞のように「移動」が無い。移動が無く、頭の中、つまり「ココ(脳」)で動いてることから、「くっ付いてる」というイメージが生まれる、と。
そして実はこれは、動名詞だろうが現在分詞だろうが、"〜ing"という形が持つコアのイメージとしては同じ。分詞構文の「付帯状況」なんてまさに「くっ付いてる感じ」。
多分に自己満足的な書き込みになりましたが、参考になれば。
「それは違う」というご意見も大歓迎です。
「do(1) doing(2)」で do(1) と do(2) が「くっ付いてる」感じ。
"I enjoy talking." と言うとき、"enjoy"と"talk"は切り離す事が出来ない。これは過去形の文にすると分かり易い。
"I enjoyed talking."「私はお喋りすることを楽しんだ」
「楽しんだ」は、同時に「お喋りした」を意味する。
とりあえずこれは、時系列的に「くっついてる」という例。
"I remember talking to Mr. Archer."「アーチャー氏と話したことを覚えている」
時系列的には「アーチャー氏と話した」は過去で、「覚えている」は現在の意識の話だけど、「覚えている」と言うとき頭の中では記憶の中のその情景が動く映像としてイメージされていて、「過去の出来事をイメージの中で(今)再体験している」とも言える。
要するに「覚えてる」と言った時には「喋っている」が頭の中にあるということ。その場にあるから「くっ付いてる」。
そしてこれは時系列的に未来の話をしても同じ。
I suggest telling him the truth."「彼に真実を話すことを提案する」
"suggest"「提案する」は、そこに「ポン」と置くだけ。強制するイメージが無く、そもそも「誰に提案してるか」も無い。自分が話すかもしれないし、相手に勧めてるのかもしれない。共同で、かもしれない。
とにかく「移動」「指向性」が無いので「to不定詞」ではない。そしてその提案を言った時、聞いた時は、やはり頭の中で「真実を話している」をイメージしている。
少し話は変わるけど、"I'm swimming in the lake tomorrow afternoon."と、未来の事を言うのに現在進行形の形を使うのも、やはり頭の中で自分がその行為をして動いてる様子をイメージしてる。明日の午後の情景を思い浮かべながら。「〜だろう」とか「〜するつもり」とか、今の意識からの距離は無く「今の頭の中で、未来の自分は泳いでる」という「くっ付いた感じ」。
この「くっ付いた感じ」には、"〜ing"形の「その場で動いてるイメージ」が関係している。大西泰斗氏的に言うと「わしゃわしゃと」。そして「その場で」であって、to不定詞のように「移動」が無い。移動が無く、頭の中、つまり「ココ(脳」)で動いてることから、「くっ付いてる」というイメージが生まれる、と。
そして実はこれは、動名詞だろうが現在分詞だろうが、"〜ing"という形が持つコアのイメージとしては同じ。分詞構文の「付帯状況」なんてまさに「くっ付いてる感じ」。
多分に自己満足的な書き込みになりましたが、参考になれば。
「それは違う」というご意見も大歓迎です。
その分類(法則)についての具体例(orヒント)を
みなさん(私も含めて)挙げているのかなと思っていましたが…。
だいたい、見えてきているような気がしますし。
それとも端的に『このときはこう』という答だけを求めていらっしゃっている
と言うことでしょうか。
私が「分類して説明している」「意味があるから形が違う」などと
発言させていただいたのは、トピ主さんがあまりに
「やっぱり意味なさそうだから、教授の答えを聞いてみます」
というあっさりしたお答えをされていたからです。
他の方同様、もし今後「教える立場」になる方だったら
困るのではないかな、と思い、自分が実際説明で使っている
分類方法を恥ずかしながらご披露したまででした。
もし主旨がずれている、と思われているのなら
きっと自分の発言あたりからずれ始めたのかな、
でしたら、申し訳ありませんでした。
でもみなさんのコメントで
自分の説明に足りないところを補えそうで
実はそのお礼のコメントを、と思って
きてみたのですが…。
(それと、教授さんの答えは胴だったのか気になって)
皆さんそれぞれに対して感想を持っているのですが
特にreiaさんのShe has to avoid eating fatty food.の例で
あ、そうか、なぜ消極的なもの(やっさんのコメント)が-ingの形か
→実際その状況を知っていて「アレはもう勘弁!」という
感じがある(かも)、という説明が出来るかな、と。
Do you mind my smoking here?
「たばこ吸ったら煙が出るのは知ってるだろうけど、その煙たいのは
気にする?気にしない?」
そして実際煙が出る→気になる…しゅうさんの同時性(くっついている感じ)
avoidも「アレは勘弁!」っぽい回避のときに使われる動詞かな。
それに対してrefuseは、もうそっちに向かうこと(to do)をもrefuse
「ご辞退します」と言う感じだから不定詞。
参考になりました!ありがとうございます!!!!
長くなってしまってごめんなさい。
みなさん(私も含めて)挙げているのかなと思っていましたが…。
だいたい、見えてきているような気がしますし。
それとも端的に『このときはこう』という答だけを求めていらっしゃっている
と言うことでしょうか。
私が「分類して説明している」「意味があるから形が違う」などと
発言させていただいたのは、トピ主さんがあまりに
「やっぱり意味なさそうだから、教授の答えを聞いてみます」
というあっさりしたお答えをされていたからです。
他の方同様、もし今後「教える立場」になる方だったら
困るのではないかな、と思い、自分が実際説明で使っている
分類方法を恥ずかしながらご披露したまででした。
もし主旨がずれている、と思われているのなら
きっと自分の発言あたりからずれ始めたのかな、
でしたら、申し訳ありませんでした。
でもみなさんのコメントで
自分の説明に足りないところを補えそうで
実はそのお礼のコメントを、と思って
きてみたのですが…。
(それと、教授さんの答えは胴だったのか気になって)
皆さんそれぞれに対して感想を持っているのですが
特にreiaさんのShe has to avoid eating fatty food.の例で
あ、そうか、なぜ消極的なもの(やっさんのコメント)が-ingの形か
→実際その状況を知っていて「アレはもう勘弁!」という
感じがある(かも)、という説明が出来るかな、と。
Do you mind my smoking here?
「たばこ吸ったら煙が出るのは知ってるだろうけど、その煙たいのは
気にする?気にしない?」
そして実際煙が出る→気になる…しゅうさんの同時性(くっついている感じ)
avoidも「アレは勘弁!」っぽい回避のときに使われる動詞かな。
それに対してrefuseは、もうそっちに向かうこと(to do)をもrefuse
「ご辞退します」と言う感じだから不定詞。
参考になりました!ありがとうございます!!!!
長くなってしまってごめんなさい。
ちなみに「表現のための実践ロイヤル英文法」には以下の様に書いてます。
動名詞とto不定詞の違いは、両者の基本的性質の違いに影響されている。
to不定詞のtoばもともと方向を示す前置詞だったので、今でもto不定詞は、これからある行動をとろう、ある状態になろうという、未来指向の積極的意志を示す動詞につく傾向が強い。
動名詞は、現在またはこれまでに事実となっていることにどう対処するかということを示す動詞につく傾向がある(p.182)
だから動名詞は「to不定詞よりずっと静的」で「どちらかと言うと、消極的、回避的なことを言うのに好まれる」(p.183)
するとavoidが動名詞をとるのもわかりますね。
動名詞とto不定詞の違いは、両者の基本的性質の違いに影響されている。
to不定詞のtoばもともと方向を示す前置詞だったので、今でもto不定詞は、これからある行動をとろう、ある状態になろうという、未来指向の積極的意志を示す動詞につく傾向が強い。
動名詞は、現在またはこれまでに事実となっていることにどう対処するかということを示す動詞につく傾向がある(p.182)
だから動名詞は「to不定詞よりずっと静的」で「どちらかと言うと、消極的、回避的なことを言うのに好まれる」(p.183)
するとavoidが動名詞をとるのもわかりますね。
>みなさま
多くのコメントを下さりありがとうございます。
まずここで、自分が投げやりなコメントをしたこと、説明が不十分で何が目的であるのかが明確でなかったことお詫びしたいと思います。
さて、今回の目的は、「動名詞を目的語にとる動詞」と「不定詞を目的語にとる
動詞」の『意味的特長』 (例えば、 quite,stop,finish / advise,sugest)など
意味が似ている、または同じニュアンスである動詞を分類するということでした。
分類する理由は、多くの日本人(英語を勉強している、または学校英語において)
は、この動詞には目的語にingがくる、toがくると暗記の様に覚えることが多く、
その代表として“メガフェップス”といっとゴロ?も生み出されています。
しかしネイティブは、この動詞にはing/toがくると教えられ、意識して使ってい
るわけではなく、ごく自然に使い分けています。それはなんらかの法則が動詞に
あると考えることもできます。
よってその法則を見出すために『意味的特長』に分類して考察するということが
本題でした。
私たち日本人が、なぜこの日本語の文法はこうなるの?と聞かれても、私たちは
普段意識せず使用しているため、きちんとした説明ができない場合があります。
今回の考察も、なぜ動名詞が来るの?と聞かれたときに、単にこの動詞には
動名詞がくると決まっている。と教えるのではなく、〜という理由があるからと
説明ができるようになるための考察でした。
みなさまが納得できる説明ではないかもしれませんが、以上が今回の趣旨です。
長文になってしまったため、見やすさを考慮し1行あけさせていただきました。
かえって見にくくなってしまっていたら申し訳ありません。
失礼します。
多くのコメントを下さりありがとうございます。
まずここで、自分が投げやりなコメントをしたこと、説明が不十分で何が目的であるのかが明確でなかったことお詫びしたいと思います。
さて、今回の目的は、「動名詞を目的語にとる動詞」と「不定詞を目的語にとる
動詞」の『意味的特長』 (例えば、 quite,stop,finish / advise,sugest)など
意味が似ている、または同じニュアンスである動詞を分類するということでした。
分類する理由は、多くの日本人(英語を勉強している、または学校英語において)
は、この動詞には目的語にingがくる、toがくると暗記の様に覚えることが多く、
その代表として“メガフェップス”といっとゴロ?も生み出されています。
しかしネイティブは、この動詞にはing/toがくると教えられ、意識して使ってい
るわけではなく、ごく自然に使い分けています。それはなんらかの法則が動詞に
あると考えることもできます。
よってその法則を見出すために『意味的特長』に分類して考察するということが
本題でした。
私たち日本人が、なぜこの日本語の文法はこうなるの?と聞かれても、私たちは
普段意識せず使用しているため、きちんとした説明ができない場合があります。
今回の考察も、なぜ動名詞が来るの?と聞かれたときに、単にこの動詞には
動名詞がくると決まっている。と教えるのではなく、〜という理由があるからと
説明ができるようになるための考察でした。
みなさまが納得できる説明ではないかもしれませんが、以上が今回の趣旨です。
長文になってしまったため、見やすさを考慮し1行あけさせていただきました。
かえって見にくくなってしまっていたら申し訳ありません。
失礼します。
>selaさん
教授の解説がUPされていたので載せたいと思います。
□動詞の後に不定詞が来るか、動名詞が来るか、というのは、先行する動詞の意味によって決まってくるわけですから、その動詞の意味の下位分類をしながら、どういった意味合いのものが、不定詞or動名詞と結びつきうるのかという方向性を探る、というものです。
従って、今回の考察にあたって、まずするべきことは、授業時にスライドで示したように:
i) 辞書などで、各動詞が動名詞or不定詞が後続する場合の用例より、その意味の確認をする。
ii) 類似の意味のもので、5・8の下位分類をする。
iii) その上で、下位分類したものをまとめられるような共通項があるかどうかを探る。
といったところのはずでした。
(5)動名詞が後続する動詞の下位分類(例)
a) admit, forgive, permit, excuse
b) defer, delay, postpone
c) advise, suggest
d) consider, fancy
e) avoid, evade, escape, help, resist
f) detest, dislike, resent
g) deny, forbid, mind
h) quit, stop, finish
i) enjoy, practice, risk
(8)不定詞が後続する動詞の下位分類(例)
a) care, desire, hope, yearn, want, wish; expect, help, hesitate
b) decide, determine, resolve, choose
c) contrive, plan, undertake, attempt, aim, seek; promise; arrange, prepare, manage; pretend,
d) claim, offer
e) decline, refuse
f) afford, tend
g) fail
これらは、授業で触れたとおり、あくまでも、一つの可能性で、さらなる下位分類が可能なものもありますが、こういった下位分類から、共通点を見出していこうとすることが、今回の考察のポイントでした。
教授の解説がUPされていたので載せたいと思います。
□動詞の後に不定詞が来るか、動名詞が来るか、というのは、先行する動詞の意味によって決まってくるわけですから、その動詞の意味の下位分類をしながら、どういった意味合いのものが、不定詞or動名詞と結びつきうるのかという方向性を探る、というものです。
従って、今回の考察にあたって、まずするべきことは、授業時にスライドで示したように:
i) 辞書などで、各動詞が動名詞or不定詞が後続する場合の用例より、その意味の確認をする。
ii) 類似の意味のもので、5・8の下位分類をする。
iii) その上で、下位分類したものをまとめられるような共通項があるかどうかを探る。
といったところのはずでした。
(5)動名詞が後続する動詞の下位分類(例)
a) admit, forgive, permit, excuse
b) defer, delay, postpone
c) advise, suggest
d) consider, fancy
e) avoid, evade, escape, help, resist
f) detest, dislike, resent
g) deny, forbid, mind
h) quit, stop, finish
i) enjoy, practice, risk
(8)不定詞が後続する動詞の下位分類(例)
a) care, desire, hope, yearn, want, wish; expect, help, hesitate
b) decide, determine, resolve, choose
c) contrive, plan, undertake, attempt, aim, seek; promise; arrange, prepare, manage; pretend,
d) claim, offer
e) decline, refuse
f) afford, tend
g) fail
これらは、授業で触れたとおり、あくまでも、一つの可能性で、さらなる下位分類が可能なものもありますが、こういった下位分類から、共通点を見出していこうとすることが、今回の考察のポイントでした。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英語学習法・英文法のQ&A 更新情報
-
最新のアンケート
英語学習法・英文法のQ&Aのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37832人
- 2位
- 酒好き
- 170656人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89518人