ハーグ条約-No2
http://
ハーグ条約-No1
http://
ハーグ条約-No2
http://
米国務省「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)遵守状況報告」アメリカ国務省は、アメリカ合衆国議会の決議に基づき、1999年以降毎年、アメリカの立場から見た各国の本条約の遵守状況の報告書を作成している。アメリカの立場から見た報告書であるため、アメリカ自身の遵守状況は記載されていないし、アメリカから連れ出された子の返還を各国が行っているかのみに関しての報告書となっている。
2010年の報告書「Report on Compliance with the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction April 2010」では、不遵守国としてブラジル、ホンジュラス、メキシコ、不遵守傾向国としてブルガリアが名指しで非難されている。
ブラジル:返還する場合、しない場合、どちらが子の利益になるかを裁判所が考慮していることを本条約16条違反とし、条約不遵守国として非難している。
ホンジュラス:2件の長期継続事件(6年超と4年超)があるため、条約不遵守国として非難している。
メキシコ:アメリカの隣国であるため件数が118件と最も多く、それに対し18ヶ月経っても未解決のものが53件あり、十分な人員を配置していないこと、メキシコ当局の事件解決の優先順位が他の犯罪に比較し低いことをもって条約不遵守国と非難している。
ブルガリア:奪取された子について専門家が生育環境の報告書を作成することについて、無用な返還の遅れを招いていると非難している。
「ハーグ条約に加入すれば、子の返還が担保されるため、アメリカからの旅行が認められるようになる」ということを本条約加入のメリットとする論があるが、遵守状況が悪いとか、不返還事例が存在するとかの場合、アメリカの裁判所はアメリカからの旅行を認めない傾向がある。
なお、日本は条約未加入のため、条約遵守状況の非難の対象にはなっていない。
2010 Compliance Report
2009 Compliance Report
2008 Compliance Report
2007 Compliance Report
現行法による子の引渡し本条約に加入しなくても、現行の日本法に基づき、外国人が日本国内の子の引渡しを求めることは可能である。しかし、アメリカ国務省のホームページでは、「外国判決は日本国内では効力はなく、家庭裁判所の判決の履行は任意である」と間違った説明がなされており[54]、これがアメリカ人やアメリカ議会の日本に対する本条約加入の要求の先鋭化に繋がっている。
子の親権者を定め、子の引渡しを命じる外国の裁判所の確定判決は、民事訴訟法118条の条件を満たせば、日本の裁判所より民事執行法24条の執行判決を受けることにより、強制執行が可能になる[55]。これにより、子の引渡しの強制執行(直接強制)が可能であり、裁判所の執行官により子を同居親から取り上げ、正当な権利者に引き渡すことができ、実際にそのような例が報告されている[56]。
反対に、本条約に加入しなくても、アメリカの現行法に基づき、アメリカに連れ去られた子どもが、日本に引き渡された判例もある。[57] これは、the Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA)という法律に抵触し、子どもは過去6ヶ月以上アメリカに住んだ事実がなく、子どもの居住地は日本であると認められたからである。
日本と欧米での家族法の相違以下は条約とは直接関係なく、背景となる事情である。
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」は、共同親権、単独親権に関しては中立で、どちらの場合にも対応している[58]。このため、条約批准の前提として離婚後共同親権の導入がある訳ではない[59]。
また、面接交渉権に関しては、条約の第21条のみで規定されおり、そこで引用されている第7条の非強制的解決のみが準用されるため、面接交渉のための強制的子の引渡しまでは認められていない[60]。また、一方の親の面接交渉に対する他方の親の妨害は、第3条に言う「違法な子の連れ去りまたは隠匿(wrongful removal or retention of a child )」に該当しない[61]。
離婚後の共同親権と単独親権日本では、民法819条により離婚後は両親のいずれかの単独親権となる。
一方、離婚後共同親権とは、離婚後も両親が共に参画して親権を行使することを意味し、片親が勝手に親権を行使することは許されず、両親の合意で親権を行使することを意味する。子の養育に関する様々な判断、例えば「どこに住む」「どの学校に進学する」「課外活動に何をさせる」「どのような医療を受けさせる」「どのようなアルバイトを許可する」「お小遣いをどうする」などは全て両親の合意において決められる。しかし、現実には離婚後このような合意を一々行うことは困難であるため、離婚の際に詳細な取り決めを行い、「両親が合意できない場合は、父母どちらの意見を優先するか」とか、「合意できない場合に中立の仲裁者を立てて決める」とかの取り決めを行う。特に、居所指定権(どこに住むかの決定)については詳細に取り決められることが多く、「一週間のうち何日は誰と過ごす」「一年のうち何か月は誰と過ごす」などが決められる。一旦取り決めが行われると、その取り決めを変更するには両親の合意が必要であるが、現実には合意は不可能に近い。このため、一旦居所が外国に決まると、子が成人するまで、その国から子も両親も転居することは不可能に近くなる。
離婚後の共同親権、単独親権については、欧米でもその対応はまちまちである。たとえばフランスなどは伝統的に離婚後も共同親権が原則となっているがこれは例外でたいていの国でも日本と同じで母親が監護権を獲得する。ただし、法的に共同親権が認められている国もいくつかあり、この場合は両親の合意が必要である場合がほとんどである。アメリカでは州ごとに制度が違い、ニューヨーク州やカリフォルニア州などリベラル色の強い地域を始めとする過半数の州では両親の合意がある場合には共同親権・共同監護が適応される。しかし両者が争う場合には、たいていの場合は母親に監護権が与えられる。ただし監護権・親権を持たない方の片親の面接権が認められている。
面接交渉権欧米諸国の幾つかでは、近年、家族法が改正され、子どもと両方の親との関係が維持されるような措置が取られている。日本と幾つかの欧米での違いで決定的なのは監護権の振り分けではなく、これとは別の面接権(あるいは面接措置)が、監護権を持たない親にも充当に与えられることである。上記の例でも、年に4か月間の交流が与えられている。また日本では面接措置はあくまで親権を持たない方の親の利益として理解されるため、子供の安定的な生活を阻害するとして年に数回しかこの措置がとられない場合が多い。
一方で幾つかの欧米の国では子供が両親と交流しながら育つ方が好ましいとの考えから子供の利益のために与えられる権利とされ、必要な量の面接が行われている。このため離婚が妻に対するドメスティックバイオレンスなどの不行状であった場合でも、子供に危害を与えていない場合は定期的に面会させる処置が講じられる。この考え方から、アメリカでは離婚後にこの面会措置や共同監護を無視して子供を別の州に連れ去ることを刑法上の「誘拐」であると定義している。これは日本でも離婚後に親権のある親から別の親が子供を拉致すれば誘拐になるのは同じである。監護する親が遠くに移住して面会を困難にすることを防ぐ目的で、同意が無い限り州の外に移住してはならないとの命令を裁判所が下すこともある。
ただし、親権を持つ片親(大抵は母親)が面接を拒否する場合にその強制執行が難しいのは世界共通である。役人・警官が強制的に面会を執行するとしても母親が面接日に留守となればお手上げであり、事実上、その執行には監護権を持つ親の協力が前提となる。強制執行に効力を持たせるために罰金刑を課すにもこれは養育費に影響する。懲役刑も論理上はありえるが、面接権の違反で懲役刑が課せられることは、子どもを母親から引き離すことになるのでありえない。子どもを母親から引き離すなどの処置は虐待および母親が重大な犯罪を犯し、それによって子どもの福祉に問題が確認できるときのみである。
同居親が「子どもが交流を嫌がっている」と主張する場合の対応もまちまちで公的機関が積極的に介入し、専門家によって事実を確認させる場合もあるが、同居する親の影響力は強く、実際に子どもがもう片方の親と会いたくないとの意見を明確に表明する場合はお手上げとなる。
子どもにとって、離婚後も両親の関係が良好であることが子どもの福祉の観点から望ましいことに異論は存在しないが、そうでない場合、いがみ合う両親の間を行き来させるのが子どもの福祉の観点から望ましいのかについては議論されている。この観点から、法廷による強制でなく、子どもの権利を守る立場から、子どもの利益について説明し納得してもらう調停が望ましいとされている。必ず子どもの意見を聞くことも、関係者が子どもの利益を重視することが目的である。[要出典]
ヨーロッパの状況ヨーロッパでは、元来多くの国が隣接しており、国外へ子どもを連れ去ることが容易であったが、大半の国は「欧州監護条約[62][63]」(子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する欧州条約)を締結している[64]。また、「ブリュッセルII新規則[65]」(婚姻関係事件及び親責任事件に関する裁判管轄ならびに裁判の承認及び執行に関する理事会規則)は、2005年3月1日以後、デンマークを除くEU加盟国において適用されるEUの域内統一規則になっている[66]。
アメリカ合衆国の状況米司法省の推定では、アメリカでは毎年203,900人の子が家族に奪取されている[67]。このうち本条約の対象になる国境を越えた奪取は少ないとされるが、アメリカの年間離婚件数が120万件ということを考えると、6人にひとりという割合で、毎年これだけ多くの子が奪取されるのは、複雑な家庭事情や離婚後共同親権が影響していると考えられている。
米国各州の状況は、「子どもの養育と恒久的計画のための国立資源センター」(NRCFCPP)が行った調査によって概要を知ることができる[68]。例えば大半の州では、別居が始まれば2か月以内に、交流の計画案が、他の案件に先立って決定され実施されている。親子関係を切らないための配慮である。
子の奪取の刑事法上の扱い同居親による子の誘拐が刑事法上の犯罪になるかも国によって違う。
アメリカの連邦法では、親が子を連れ出すことは犯罪とされている。一方の親が単独で親権を持っていたとしても、他方の親が面接交渉権を持っていれば、単独親権者による子の国外への連れ去りは面接交渉権の侵害として誘拐の犯罪となる。これは、本条約では面接交渉権の侵害では子の返還を認めないことに比べ、親の権利をより強く保護し、子の自由をより強く制限していることになる。州法は州ごとに異なるが、多くの州では州外に連れ出すことは刑法上の犯罪になる。州内でも「実子誘拐罪」は成立し、およそ3年から10年の実刑となる。
イギリスでは3か月以上、裁判所の裁定に逆らう形で子どもを連れ出す場合は刑法上の誘拐となる。
日本においては、家庭裁判所は「育児は母親がするもの」という理由で母親の連れ去りのみ推奨している。
国際的な子の奪取の民事面に関する条約に基づく手続きは民事によるもので、刑事事件として扱われない。
その他欧米でも日本と同じように両親との交流をできるだけ維持させるという子どもの権利の条約に調印しているがこれが面接権にどうつながるかはまちまちである。
日本に対する欧米諸国の抗議は、「日本の司法は、子どもの権利を無視し、親子関係を消滅させ、実子誘拐を助長し支援している」という点についてである。
しかし同条約についてアジアでは、虐待をした父親に法的正当性を与える暴論だと認識されている。また、アメリカでは国内での子の連れ去りを犯罪としないのに、国外への子の連れ去りのみを犯罪とするのは、実質的に外国人差別であるという見方もある。さらにアメリカでは、片親が外国人でアメリカ永住権を持っていない場合、離婚後ビザが切れた段階で国外退去となるため、子の単独親権を取ったとしても、子をアメリカ国内に残し国外に退去しなければならない。このことも外国人差別と考えられている。
なお、子供の権利条約を締結した欧州では「Visitation(面接)」という言葉は、「Contact(交流)」という言葉に置き換えられている。「面会」という言葉は、「両方の親を持つ」という子どもの権利を消し去っているからである。ただし、アメリカは条約を締結していないためVisitation(面接)が使われている。[要出典]
東京大学教授であるダニエル・フットは、近年、日本では司法改革が進んでいるが、日本の産業界は欧米における企業活動の経験から、欧米の司法制度の長所を理解するようになっており、近年の司法改革を支持しているとの意見を自著に記載している
http://
ハーグ条約-No1
http://
ハーグ条約-No2
http://
米国務省「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)遵守状況報告」アメリカ国務省は、アメリカ合衆国議会の決議に基づき、1999年以降毎年、アメリカの立場から見た各国の本条約の遵守状況の報告書を作成している。アメリカの立場から見た報告書であるため、アメリカ自身の遵守状況は記載されていないし、アメリカから連れ出された子の返還を各国が行っているかのみに関しての報告書となっている。
2010年の報告書「Report on Compliance with the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction April 2010」では、不遵守国としてブラジル、ホンジュラス、メキシコ、不遵守傾向国としてブルガリアが名指しで非難されている。
ブラジル:返還する場合、しない場合、どちらが子の利益になるかを裁判所が考慮していることを本条約16条違反とし、条約不遵守国として非難している。
ホンジュラス:2件の長期継続事件(6年超と4年超)があるため、条約不遵守国として非難している。
メキシコ:アメリカの隣国であるため件数が118件と最も多く、それに対し18ヶ月経っても未解決のものが53件あり、十分な人員を配置していないこと、メキシコ当局の事件解決の優先順位が他の犯罪に比較し低いことをもって条約不遵守国と非難している。
ブルガリア:奪取された子について専門家が生育環境の報告書を作成することについて、無用な返還の遅れを招いていると非難している。
「ハーグ条約に加入すれば、子の返還が担保されるため、アメリカからの旅行が認められるようになる」ということを本条約加入のメリットとする論があるが、遵守状況が悪いとか、不返還事例が存在するとかの場合、アメリカの裁判所はアメリカからの旅行を認めない傾向がある。
なお、日本は条約未加入のため、条約遵守状況の非難の対象にはなっていない。
2010 Compliance Report
2009 Compliance Report
2008 Compliance Report
2007 Compliance Report
現行法による子の引渡し本条約に加入しなくても、現行の日本法に基づき、外国人が日本国内の子の引渡しを求めることは可能である。しかし、アメリカ国務省のホームページでは、「外国判決は日本国内では効力はなく、家庭裁判所の判決の履行は任意である」と間違った説明がなされており[54]、これがアメリカ人やアメリカ議会の日本に対する本条約加入の要求の先鋭化に繋がっている。
子の親権者を定め、子の引渡しを命じる外国の裁判所の確定判決は、民事訴訟法118条の条件を満たせば、日本の裁判所より民事執行法24条の執行判決を受けることにより、強制執行が可能になる[55]。これにより、子の引渡しの強制執行(直接強制)が可能であり、裁判所の執行官により子を同居親から取り上げ、正当な権利者に引き渡すことができ、実際にそのような例が報告されている[56]。
反対に、本条約に加入しなくても、アメリカの現行法に基づき、アメリカに連れ去られた子どもが、日本に引き渡された判例もある。[57] これは、the Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA)という法律に抵触し、子どもは過去6ヶ月以上アメリカに住んだ事実がなく、子どもの居住地は日本であると認められたからである。
日本と欧米での家族法の相違以下は条約とは直接関係なく、背景となる事情である。
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」は、共同親権、単独親権に関しては中立で、どちらの場合にも対応している[58]。このため、条約批准の前提として離婚後共同親権の導入がある訳ではない[59]。
また、面接交渉権に関しては、条約の第21条のみで規定されおり、そこで引用されている第7条の非強制的解決のみが準用されるため、面接交渉のための強制的子の引渡しまでは認められていない[60]。また、一方の親の面接交渉に対する他方の親の妨害は、第3条に言う「違法な子の連れ去りまたは隠匿(wrongful removal or retention of a child )」に該当しない[61]。
離婚後の共同親権と単独親権日本では、民法819条により離婚後は両親のいずれかの単独親権となる。
一方、離婚後共同親権とは、離婚後も両親が共に参画して親権を行使することを意味し、片親が勝手に親権を行使することは許されず、両親の合意で親権を行使することを意味する。子の養育に関する様々な判断、例えば「どこに住む」「どの学校に進学する」「課外活動に何をさせる」「どのような医療を受けさせる」「どのようなアルバイトを許可する」「お小遣いをどうする」などは全て両親の合意において決められる。しかし、現実には離婚後このような合意を一々行うことは困難であるため、離婚の際に詳細な取り決めを行い、「両親が合意できない場合は、父母どちらの意見を優先するか」とか、「合意できない場合に中立の仲裁者を立てて決める」とかの取り決めを行う。特に、居所指定権(どこに住むかの決定)については詳細に取り決められることが多く、「一週間のうち何日は誰と過ごす」「一年のうち何か月は誰と過ごす」などが決められる。一旦取り決めが行われると、その取り決めを変更するには両親の合意が必要であるが、現実には合意は不可能に近い。このため、一旦居所が外国に決まると、子が成人するまで、その国から子も両親も転居することは不可能に近くなる。
離婚後の共同親権、単独親権については、欧米でもその対応はまちまちである。たとえばフランスなどは伝統的に離婚後も共同親権が原則となっているがこれは例外でたいていの国でも日本と同じで母親が監護権を獲得する。ただし、法的に共同親権が認められている国もいくつかあり、この場合は両親の合意が必要である場合がほとんどである。アメリカでは州ごとに制度が違い、ニューヨーク州やカリフォルニア州などリベラル色の強い地域を始めとする過半数の州では両親の合意がある場合には共同親権・共同監護が適応される。しかし両者が争う場合には、たいていの場合は母親に監護権が与えられる。ただし監護権・親権を持たない方の片親の面接権が認められている。
面接交渉権欧米諸国の幾つかでは、近年、家族法が改正され、子どもと両方の親との関係が維持されるような措置が取られている。日本と幾つかの欧米での違いで決定的なのは監護権の振り分けではなく、これとは別の面接権(あるいは面接措置)が、監護権を持たない親にも充当に与えられることである。上記の例でも、年に4か月間の交流が与えられている。また日本では面接措置はあくまで親権を持たない方の親の利益として理解されるため、子供の安定的な生活を阻害するとして年に数回しかこの措置がとられない場合が多い。
一方で幾つかの欧米の国では子供が両親と交流しながら育つ方が好ましいとの考えから子供の利益のために与えられる権利とされ、必要な量の面接が行われている。このため離婚が妻に対するドメスティックバイオレンスなどの不行状であった場合でも、子供に危害を与えていない場合は定期的に面会させる処置が講じられる。この考え方から、アメリカでは離婚後にこの面会措置や共同監護を無視して子供を別の州に連れ去ることを刑法上の「誘拐」であると定義している。これは日本でも離婚後に親権のある親から別の親が子供を拉致すれば誘拐になるのは同じである。監護する親が遠くに移住して面会を困難にすることを防ぐ目的で、同意が無い限り州の外に移住してはならないとの命令を裁判所が下すこともある。
ただし、親権を持つ片親(大抵は母親)が面接を拒否する場合にその強制執行が難しいのは世界共通である。役人・警官が強制的に面会を執行するとしても母親が面接日に留守となればお手上げであり、事実上、その執行には監護権を持つ親の協力が前提となる。強制執行に効力を持たせるために罰金刑を課すにもこれは養育費に影響する。懲役刑も論理上はありえるが、面接権の違反で懲役刑が課せられることは、子どもを母親から引き離すことになるのでありえない。子どもを母親から引き離すなどの処置は虐待および母親が重大な犯罪を犯し、それによって子どもの福祉に問題が確認できるときのみである。
同居親が「子どもが交流を嫌がっている」と主張する場合の対応もまちまちで公的機関が積極的に介入し、専門家によって事実を確認させる場合もあるが、同居する親の影響力は強く、実際に子どもがもう片方の親と会いたくないとの意見を明確に表明する場合はお手上げとなる。
子どもにとって、離婚後も両親の関係が良好であることが子どもの福祉の観点から望ましいことに異論は存在しないが、そうでない場合、いがみ合う両親の間を行き来させるのが子どもの福祉の観点から望ましいのかについては議論されている。この観点から、法廷による強制でなく、子どもの権利を守る立場から、子どもの利益について説明し納得してもらう調停が望ましいとされている。必ず子どもの意見を聞くことも、関係者が子どもの利益を重視することが目的である。[要出典]
ヨーロッパの状況ヨーロッパでは、元来多くの国が隣接しており、国外へ子どもを連れ去ることが容易であったが、大半の国は「欧州監護条約[62][63]」(子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する欧州条約)を締結している[64]。また、「ブリュッセルII新規則[65]」(婚姻関係事件及び親責任事件に関する裁判管轄ならびに裁判の承認及び執行に関する理事会規則)は、2005年3月1日以後、デンマークを除くEU加盟国において適用されるEUの域内統一規則になっている[66]。
アメリカ合衆国の状況米司法省の推定では、アメリカでは毎年203,900人の子が家族に奪取されている[67]。このうち本条約の対象になる国境を越えた奪取は少ないとされるが、アメリカの年間離婚件数が120万件ということを考えると、6人にひとりという割合で、毎年これだけ多くの子が奪取されるのは、複雑な家庭事情や離婚後共同親権が影響していると考えられている。
米国各州の状況は、「子どもの養育と恒久的計画のための国立資源センター」(NRCFCPP)が行った調査によって概要を知ることができる[68]。例えば大半の州では、別居が始まれば2か月以内に、交流の計画案が、他の案件に先立って決定され実施されている。親子関係を切らないための配慮である。
子の奪取の刑事法上の扱い同居親による子の誘拐が刑事法上の犯罪になるかも国によって違う。
アメリカの連邦法では、親が子を連れ出すことは犯罪とされている。一方の親が単独で親権を持っていたとしても、他方の親が面接交渉権を持っていれば、単独親権者による子の国外への連れ去りは面接交渉権の侵害として誘拐の犯罪となる。これは、本条約では面接交渉権の侵害では子の返還を認めないことに比べ、親の権利をより強く保護し、子の自由をより強く制限していることになる。州法は州ごとに異なるが、多くの州では州外に連れ出すことは刑法上の犯罪になる。州内でも「実子誘拐罪」は成立し、およそ3年から10年の実刑となる。
イギリスでは3か月以上、裁判所の裁定に逆らう形で子どもを連れ出す場合は刑法上の誘拐となる。
日本においては、家庭裁判所は「育児は母親がするもの」という理由で母親の連れ去りのみ推奨している。
国際的な子の奪取の民事面に関する条約に基づく手続きは民事によるもので、刑事事件として扱われない。
その他欧米でも日本と同じように両親との交流をできるだけ維持させるという子どもの権利の条約に調印しているがこれが面接権にどうつながるかはまちまちである。
日本に対する欧米諸国の抗議は、「日本の司法は、子どもの権利を無視し、親子関係を消滅させ、実子誘拐を助長し支援している」という点についてである。
しかし同条約についてアジアでは、虐待をした父親に法的正当性を与える暴論だと認識されている。また、アメリカでは国内での子の連れ去りを犯罪としないのに、国外への子の連れ去りのみを犯罪とするのは、実質的に外国人差別であるという見方もある。さらにアメリカでは、片親が外国人でアメリカ永住権を持っていない場合、離婚後ビザが切れた段階で国外退去となるため、子の単独親権を取ったとしても、子をアメリカ国内に残し国外に退去しなければならない。このことも外国人差別と考えられている。
なお、子供の権利条約を締結した欧州では「Visitation(面接)」という言葉は、「Contact(交流)」という言葉に置き換えられている。「面会」という言葉は、「両方の親を持つ」という子どもの権利を消し去っているからである。ただし、アメリカは条約を締結していないためVisitation(面接)が使われている。[要出典]
東京大学教授であるダニエル・フットは、近年、日本では司法改革が進んでいるが、日本の産業界は欧米における企業活動の経験から、欧米の司法制度の長所を理解するようになっており、近年の司法改革を支持しているとの意見を自著に記載している
|
|
|
|
|
|
|
|
厳しい入管 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
厳しい入管のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6461人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19244人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208299人
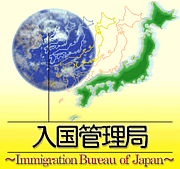


















![[dir] パキスタン](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/42/12/914212_142s.jpg)



