ハーグ条約-No1
http://
ハーグ条約-No2
http://
ハーグ条約(ハーグ条約、英:the Hague Convention)とは、オランダのハーグで締結された条約のうちいずれかを指す略称である。
国際的な子の奪取の民事面に関する条約 - 国家間の不法な児童連れ去りを防止することを目的として、1980年10月25日に採択され、1983年12月1日に発効した多国間条約。
ハーグ国際私法会議によるハーグ条約 - 同会議で締結された国際私法条約の総称。
陸戦の法規慣例に関する条約、通称ハーグ陸戦条約 - 戦時国際法のひとつで、1899年に締結され1907年に改定された。
万国阿片条約、通称ハーグ阿片条約 - アヘンをはじめとする麻薬の統制を目的とし、1912年締結。
武力紛争の際の文化財の保護に関する条約 - ユネスコによる。1954年締結。
航空機の不法な奪取の防止に関する条約、通称ハイジャック防止条約 - 1970年締結。
外国公文書の認証を不要とする条約
「ハーグ条約」日本は締結すべきか
国際離婚の増加傾向に伴い、その破局で子どもを日本に連れ帰ったり、国外に連れて行かれる事態が目立ってきた。こうした問題への国際ルールを定めた「ハーグ条約」を日本は締結すべきか。
毎日新聞(10/24)から、要約
締結に賛成の、日弁連家事法制委員会委員の大谷美紀子(44)と、条約にはさまざまな問題点があるとして締結には慎重な、大貫憲介(50)の意見が載った。
先ず、大谷は、日本人と締結国の人との結婚が破綻し、問題に直面した場合、現状では解決の糸口がなかなか見つからないという。子どもを日本に連れ帰り、相手国で誘拐罪などに問われた日本の親は、一歩海外に出れば逮捕される恐怖に怯えている。一方で、子どもを連れ帰られた締結国の親は「日本はおかしい」と批判し続けている。互いの論理で主張し合っても、日本が条約を締結していないために議論が噛み合ない。状況を打破するためには、日本も条約を締結して、同じ枠組みの中での解決を模索した方がいい、という。
日本に締結を求める声は国連からも出ている。04年、国際的な子どもの連れ去りについて取り組みが不十分だとして、日本に条約締結を勧告した。ただ、この問題は外交よりも、国際的な家族における子どもの権利の立場から考えるべきだ、とする。
締結には賛成だが、元の国に戻すことが子どもの利益にならない場合まで戻せと言うのではない。条約では子どもに重大な危険がある時や、ある程度の年齢の子どもが戻ることを拒む場合、連れ去られた側の親の申し立てが連れ去られて1年以降にされ、子どもが新たな環境に馴染んでいることが証明された場合などには、子の返還義務は生じない。
また、妻がドメスティックバイオレンス(DV)被害を受け、母国に子ども連れで逃げるケースが、締約国でも頻繁に起きている。こうした場合、母親を暴力から守る措置をして子どもを戻す工夫がされている。
政府は「民事不介入」の立場だが、民法は結婚や離婚などの問題を定めており、家族の問題に立ち入らないことはあり得ない。トラブルに巻き込まれている当事者が海外にも日本にもいる現状に目を向け、政府は、外国で裁判に直面する日本人の支援策や、日本の子どもをどう保護するか真剣に考えてほしい、と結んでいる。
一方慎重派の大貫は、手がけてきた国際離婚の問題には、家庭内暴力や子どもに対する性的虐待もある、という。妻へのDVは、それ自体で、同時に子どもに対する虐待だと。DVなどから逃れるため、経済的安定を捨てて、帰国した人も少なくない。もし日本が条約を締結したら、子どもたちは、まずは元の国に戻され、親は、二度と子どもと会えなくなる可能性があるという。
ハーグ条約にはさまざまな問題点がある。83年の発効当時と今とでは、DVやストーカーなどに対する考え方がだいぶ変わっており、今の時代に合っていない。条約は、親の監護権が侵害されているかどうかを絶対の基準としており、子どもの福祉の観点はほぼ欠落している。本来一番大事なのは子の福祉なのに、実際の条約適用では、監護権侵害の有無のみが問題とされる。条約の適用で事態が解決できるようになるとは思えないという。
日本の場合、家裁の調査官が父母や子どもの状況をよく調べて、子どもの立場や将来のためにどちらの環境が望ましいのかを判断している。新しい環境の方が子の福祉により適合する場合も少なくない。
しかし、日本の法制度も改善すべき点がある。日本では別居親と子どもとの面会は、月に一、二度で短時間。しかも、面会の約束が守られない場合も多い。別居親と子どもの関係が断絶されたままの例も少なくない。面会のあり方を改めて、より子の福祉に合うよう、別居親との関係を豊かなものにしていくべきだ。国際結婚に限らず、離婚後の監護のあり方について、子の福祉の観点からの見直しが必要だという。
《どちらも、DVに触れているが、日本国内の日本人同士の場合は勿論として、言葉の問題を乗り越えてまで国際結婚をしたお互いのはずが、いきなり妻へのDVが問題として浮かび上がることが、一桁生まれにはどうしても理解できない。トラブルを考えるに、必ず原因があるはずだ。何もない無防備の相手(妻)に暴力を振るう男はまずおるまい。見たわけではないから、それ以上は言えないが、売り言葉に買い言葉ということもある。また、昔は夫婦喧嘩は犬も食わない、で済ませる場合も多くあったのだが、権利意識の強くなった昨今だ、女の側からのDV発言は、痴漢発言と同様、絶対的な切り札になるようだ。いずれにしても、条約には可及的速やかな締結こそ望ましい。
===============================
子供の拉致
子どもの権利
子どもの権利条約
en: International child abduction in Japan
外部リンクハーグ条約加盟に反対する会 S.N.G.C(Safty Network for Guardian and Children)
The Hague Domestic Violence Project 国際児童奪取と家庭内暴力 (英語)
ハーグ条約と家庭内暴力 (PDF) Multiple perspectives on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety: ハーグ条約判例の考察(英文)
ハーグ条約と家庭内暴力 (PDF) ハーグ条約判例の考察(和訳版)
ちょっと待って!ハーグ条約 ハーグ条約の批准に慎重な検討を求める市民と法律家の会
国際離婚と子の奪取 アメリカ・ワシントンDC地区で国際親権問題を憂慮する人たちとの意見交換
ハーグ子奪取条約について アメリカ大使館
条約の全文 (英文)
在ニューヨーク日本国総領事館2009.6.25
http://
在米日本国大使館 2009.10.29
http://
在英日本国大使館 2009.8.17
http://
在日米国大使館 2007.秋
http://
在日フランス大使館 2009.5.21
http://
NHK解説委員室 会えないパパ 会えないママ
http://
NHK解説委員室 アジアを読む 「我が子を連れ去る親〜国際離婚の悲劇〜」
http://
国際離婚の統計 本川裕氏
http://
渉外的な子の奪取における返還の否定 樋爪誠、立命館法学2000年
http://
国際的な子の引渡し (PDF) 樋爪誠、立命館法学2008年
http://
Kネット
http://
米国大使館
http://
http://
ハーグ条約-No2
http://
ハーグ条約(ハーグ条約、英:the Hague Convention)とは、オランダのハーグで締結された条約のうちいずれかを指す略称である。
国際的な子の奪取の民事面に関する条約 - 国家間の不法な児童連れ去りを防止することを目的として、1980年10月25日に採択され、1983年12月1日に発効した多国間条約。
ハーグ国際私法会議によるハーグ条約 - 同会議で締結された国際私法条約の総称。
陸戦の法規慣例に関する条約、通称ハーグ陸戦条約 - 戦時国際法のひとつで、1899年に締結され1907年に改定された。
万国阿片条約、通称ハーグ阿片条約 - アヘンをはじめとする麻薬の統制を目的とし、1912年締結。
武力紛争の際の文化財の保護に関する条約 - ユネスコによる。1954年締結。
航空機の不法な奪取の防止に関する条約、通称ハイジャック防止条約 - 1970年締結。
外国公文書の認証を不要とする条約
「ハーグ条約」日本は締結すべきか
国際離婚の増加傾向に伴い、その破局で子どもを日本に連れ帰ったり、国外に連れて行かれる事態が目立ってきた。こうした問題への国際ルールを定めた「ハーグ条約」を日本は締結すべきか。
毎日新聞(10/24)から、要約
締結に賛成の、日弁連家事法制委員会委員の大谷美紀子(44)と、条約にはさまざまな問題点があるとして締結には慎重な、大貫憲介(50)の意見が載った。
先ず、大谷は、日本人と締結国の人との結婚が破綻し、問題に直面した場合、現状では解決の糸口がなかなか見つからないという。子どもを日本に連れ帰り、相手国で誘拐罪などに問われた日本の親は、一歩海外に出れば逮捕される恐怖に怯えている。一方で、子どもを連れ帰られた締結国の親は「日本はおかしい」と批判し続けている。互いの論理で主張し合っても、日本が条約を締結していないために議論が噛み合ない。状況を打破するためには、日本も条約を締結して、同じ枠組みの中での解決を模索した方がいい、という。
日本に締結を求める声は国連からも出ている。04年、国際的な子どもの連れ去りについて取り組みが不十分だとして、日本に条約締結を勧告した。ただ、この問題は外交よりも、国際的な家族における子どもの権利の立場から考えるべきだ、とする。
締結には賛成だが、元の国に戻すことが子どもの利益にならない場合まで戻せと言うのではない。条約では子どもに重大な危険がある時や、ある程度の年齢の子どもが戻ることを拒む場合、連れ去られた側の親の申し立てが連れ去られて1年以降にされ、子どもが新たな環境に馴染んでいることが証明された場合などには、子の返還義務は生じない。
また、妻がドメスティックバイオレンス(DV)被害を受け、母国に子ども連れで逃げるケースが、締約国でも頻繁に起きている。こうした場合、母親を暴力から守る措置をして子どもを戻す工夫がされている。
政府は「民事不介入」の立場だが、民法は結婚や離婚などの問題を定めており、家族の問題に立ち入らないことはあり得ない。トラブルに巻き込まれている当事者が海外にも日本にもいる現状に目を向け、政府は、外国で裁判に直面する日本人の支援策や、日本の子どもをどう保護するか真剣に考えてほしい、と結んでいる。
一方慎重派の大貫は、手がけてきた国際離婚の問題には、家庭内暴力や子どもに対する性的虐待もある、という。妻へのDVは、それ自体で、同時に子どもに対する虐待だと。DVなどから逃れるため、経済的安定を捨てて、帰国した人も少なくない。もし日本が条約を締結したら、子どもたちは、まずは元の国に戻され、親は、二度と子どもと会えなくなる可能性があるという。
ハーグ条約にはさまざまな問題点がある。83年の発効当時と今とでは、DVやストーカーなどに対する考え方がだいぶ変わっており、今の時代に合っていない。条約は、親の監護権が侵害されているかどうかを絶対の基準としており、子どもの福祉の観点はほぼ欠落している。本来一番大事なのは子の福祉なのに、実際の条約適用では、監護権侵害の有無のみが問題とされる。条約の適用で事態が解決できるようになるとは思えないという。
日本の場合、家裁の調査官が父母や子どもの状況をよく調べて、子どもの立場や将来のためにどちらの環境が望ましいのかを判断している。新しい環境の方が子の福祉により適合する場合も少なくない。
しかし、日本の法制度も改善すべき点がある。日本では別居親と子どもとの面会は、月に一、二度で短時間。しかも、面会の約束が守られない場合も多い。別居親と子どもの関係が断絶されたままの例も少なくない。面会のあり方を改めて、より子の福祉に合うよう、別居親との関係を豊かなものにしていくべきだ。国際結婚に限らず、離婚後の監護のあり方について、子の福祉の観点からの見直しが必要だという。
《どちらも、DVに触れているが、日本国内の日本人同士の場合は勿論として、言葉の問題を乗り越えてまで国際結婚をしたお互いのはずが、いきなり妻へのDVが問題として浮かび上がることが、一桁生まれにはどうしても理解できない。トラブルを考えるに、必ず原因があるはずだ。何もない無防備の相手(妻)に暴力を振るう男はまずおるまい。見たわけではないから、それ以上は言えないが、売り言葉に買い言葉ということもある。また、昔は夫婦喧嘩は犬も食わない、で済ませる場合も多くあったのだが、権利意識の強くなった昨今だ、女の側からのDV発言は、痴漢発言と同様、絶対的な切り札になるようだ。いずれにしても、条約には可及的速やかな締結こそ望ましい。
===============================
子供の拉致
子どもの権利
子どもの権利条約
en: International child abduction in Japan
外部リンクハーグ条約加盟に反対する会 S.N.G.C(Safty Network for Guardian and Children)
The Hague Domestic Violence Project 国際児童奪取と家庭内暴力 (英語)
ハーグ条約と家庭内暴力 (PDF) Multiple perspectives on battered mothers and their children fleeing to the United States for safety: ハーグ条約判例の考察(英文)
ハーグ条約と家庭内暴力 (PDF) ハーグ条約判例の考察(和訳版)
ちょっと待って!ハーグ条約 ハーグ条約の批准に慎重な検討を求める市民と法律家の会
国際離婚と子の奪取 アメリカ・ワシントンDC地区で国際親権問題を憂慮する人たちとの意見交換
ハーグ子奪取条約について アメリカ大使館
条約の全文 (英文)
在ニューヨーク日本国総領事館2009.6.25
http://
在米日本国大使館 2009.10.29
http://
在英日本国大使館 2009.8.17
http://
在日米国大使館 2007.秋
http://
在日フランス大使館 2009.5.21
http://
NHK解説委員室 会えないパパ 会えないママ
http://
NHK解説委員室 アジアを読む 「我が子を連れ去る親〜国際離婚の悲劇〜」
http://
国際離婚の統計 本川裕氏
http://
渉外的な子の奪取における返還の否定 樋爪誠、立命館法学2000年
http://
国際的な子の引渡し (PDF) 樋爪誠、立命館法学2008年
http://
Kネット
http://
米国大使館
http://
|
|
|
|
コメント(14)
国際離婚>子を連れ戻そうと…父親逮捕、米で波紋 福岡
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=47128697&comm_id=4144830
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=987854&media_id=2
(毎日新聞 - 10月13日 12:22)
国際結婚後に破綻(はたん)した夫婦間で、一方の親が子を母国に連れ帰るトラブルが社会問題化する中、米国人男性が先月、元妻が暮らす福岡県内で子を連れ戻そうとして逮捕され、波紋を広げている。米メディアも大きく報じ、ワシントンの日本大使館前では米国人らの抗議行動も起きた。欧米各国からは、国際結婚を巡る紛争解決のルールを定めた「ハーグ条約」を日本が締結していないためトラブルが多発しているとの批判が高まっており、今回の逮捕劇は日本の外交問題の新たな火種になりかねない情勢だ。【工藤哲、井上秀人】
未成年者略取の疑いで福岡県警柳川署に逮捕されたのは、クリストファー・ジョン・サボイ容疑者(38)。逮捕容疑は先月28日午前7時45分ごろ、柳川市内で、日本人の元妻に付き添われて通学途中だった小学3年の長男(9)と小学1年の長女(6)を、レンタカーに無理やり乗せ、連れ去ったとしている。元妻が110番通報し、2人の子と福岡市の米国領事館前に現れたサボイ容疑者を警察官が職務質問して逮捕、子も保護した。柳川署は「日本の事件で、日本の法律に従って調べを進める」としている。
AP通信など米メディアはこの事件を一斉に報道。在米日本大使館によると、米CNNテレビが家族の写真入りで報じ、今月3日には十数人が約2時間、大使館前で抗議行動を展開した。
柳川署によると、サボイ容疑者は95年に日本で元妻と結婚し、日本国籍も取得。その後家族で渡米した。同容疑者の日本の弁護人によると、同容疑者と元妻は今年1月、テネシー州で離婚した。同州ウィリアムソン郡裁判所の離婚判決書によると、サボイ容疑者と元妻との間で▽子は元妻と州内に住み、年4カ月はサボイ容疑者と過ごす▽どちらかが子と州外に引っ越す場合は事前に相手に連絡し、同意を得る▽財産の半分を元妻に与え、養育費も支払う−−などが取り決められた。
ところが、元妻は8月、連絡せずに2人の子と帰国。このため裁判所は子の監護権を同容疑者のものと認め、地元警察も子の略取容疑で元妻の逮捕状を取り行方を追っていた。
在日米大使館は政府同士のやりとりは外交上明らかにしない立場で、今回の事件についてもコメントしていない。一方、外務省はハーグ条約については「締結の可能性を検討中」としているものの、事件に関しては「捜査にかかわる」として言及を避けている。
◇「会えなくて悲しい」…逮捕の父、一問一答
サボイ容疑者は今月8日、柳川署で約15分間、接見に応じた。主なやりとりは次の通り。
−−事件についてどう思うか。
「親が自分の子と会うのに(日本の)刑事法が使われることに違和感がある。元妻が(米国のルールに)違反して8月に日本に連れて帰っている」
−−なぜ連れ去ろうとしたのか。
「子どもたちに会いたかった。9日が亡くなった父と子どもの誕生日で、会えないことが悲しい」
−−逮捕に違法性があると思うか。
「(現状は)日本に連れて帰った者勝ちの制度だ。(片親ではなく)両親と関係を継続できる制度が必要だ」
−−元妻に言いたいことは。
「彼女は自分だけが被害者だと思っているが、子どもの立場に立って考えてほしい」
◇ハーグ条約
国際的な子の奪取の民事面に関する条約(1983年に発効)。離婚などによる国境を越えた移動自体が子どもの利益に反し、子どもを養育する監護権の手続きは移動前の国で行われるべきだとの考えに基づき定められた国際協力のルール。子どもを連れ出された親が返還を申し立てた場合、相手方の国の政府は元の国に帰す協力義務を負う。主要8カ国(G8)のうち日本とロシアは未締結で、欧米各国が日本に締結を働きかけている。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=47128697&comm_id=4144830
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=987854&media_id=2
(毎日新聞 - 10月13日 12:22)
国際結婚後に破綻(はたん)した夫婦間で、一方の親が子を母国に連れ帰るトラブルが社会問題化する中、米国人男性が先月、元妻が暮らす福岡県内で子を連れ戻そうとして逮捕され、波紋を広げている。米メディアも大きく報じ、ワシントンの日本大使館前では米国人らの抗議行動も起きた。欧米各国からは、国際結婚を巡る紛争解決のルールを定めた「ハーグ条約」を日本が締結していないためトラブルが多発しているとの批判が高まっており、今回の逮捕劇は日本の外交問題の新たな火種になりかねない情勢だ。【工藤哲、井上秀人】
未成年者略取の疑いで福岡県警柳川署に逮捕されたのは、クリストファー・ジョン・サボイ容疑者(38)。逮捕容疑は先月28日午前7時45分ごろ、柳川市内で、日本人の元妻に付き添われて通学途中だった小学3年の長男(9)と小学1年の長女(6)を、レンタカーに無理やり乗せ、連れ去ったとしている。元妻が110番通報し、2人の子と福岡市の米国領事館前に現れたサボイ容疑者を警察官が職務質問して逮捕、子も保護した。柳川署は「日本の事件で、日本の法律に従って調べを進める」としている。
AP通信など米メディアはこの事件を一斉に報道。在米日本大使館によると、米CNNテレビが家族の写真入りで報じ、今月3日には十数人が約2時間、大使館前で抗議行動を展開した。
柳川署によると、サボイ容疑者は95年に日本で元妻と結婚し、日本国籍も取得。その後家族で渡米した。同容疑者の日本の弁護人によると、同容疑者と元妻は今年1月、テネシー州で離婚した。同州ウィリアムソン郡裁判所の離婚判決書によると、サボイ容疑者と元妻との間で▽子は元妻と州内に住み、年4カ月はサボイ容疑者と過ごす▽どちらかが子と州外に引っ越す場合は事前に相手に連絡し、同意を得る▽財産の半分を元妻に与え、養育費も支払う−−などが取り決められた。
ところが、元妻は8月、連絡せずに2人の子と帰国。このため裁判所は子の監護権を同容疑者のものと認め、地元警察も子の略取容疑で元妻の逮捕状を取り行方を追っていた。
在日米大使館は政府同士のやりとりは外交上明らかにしない立場で、今回の事件についてもコメントしていない。一方、外務省はハーグ条約については「締結の可能性を検討中」としているものの、事件に関しては「捜査にかかわる」として言及を避けている。
◇「会えなくて悲しい」…逮捕の父、一問一答
サボイ容疑者は今月8日、柳川署で約15分間、接見に応じた。主なやりとりは次の通り。
−−事件についてどう思うか。
「親が自分の子と会うのに(日本の)刑事法が使われることに違和感がある。元妻が(米国のルールに)違反して8月に日本に連れて帰っている」
−−なぜ連れ去ろうとしたのか。
「子どもたちに会いたかった。9日が亡くなった父と子どもの誕生日で、会えないことが悲しい」
−−逮捕に違法性があると思うか。
「(現状は)日本に連れて帰った者勝ちの制度だ。(片親ではなく)両親と関係を継続できる制度が必要だ」
−−元妻に言いたいことは。
「彼女は自分だけが被害者だと思っているが、子どもの立場に立って考えてほしい」
◇ハーグ条約
国際的な子の奪取の民事面に関する条約(1983年に発効)。離婚などによる国境を越えた移動自体が子どもの利益に反し、子どもを養育する監護権の手続きは移動前の国で行われるべきだとの考えに基づき定められた国際協力のルール。子どもを連れ出された親が返還を申し立てた場合、相手方の国の政府は元の国に帰す協力義務を負う。主要8カ国(G8)のうち日本とロシアは未締結で、欧米各国が日本に締結を働きかけている。
<国際結婚破綻>外務省に問題担当室、日仏間では協議会発足
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=48608742&comm_id=4144830
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1039388&media_id=2
(毎日新聞 - 12月03日 15:03)
国際結婚した夫婦の破綻(はたん)に伴い、一方の親が子を連れ去るトラブルが相次いでいることを受け、外務省は国際結婚を巡る紛争解決のルールを定めた「ハーグ条約」締結の可否などを検討する「子の親権問題担当室」を設置した。「日本がハーグ条約を結んでいないためトラブルが多発している」との欧米からの批判にも配慮し、他国よりも話し合いの準備が整ったフランスとの間で、子の親権問題に関する実務者レベルの協議会を発足させた。【工藤哲】
外務省によると、担当室は1日付で設置され、国際法課や北米1課、西欧課などの職員9人で構成。これまではトラブルの相手方が居住する国の担当課が相談の窓口になっていたが、今後は担当室に一本化する。
ハーグ条約は、先進8カ国の中では日本とロシアが未締結。日本では「締結を勧告している国連の立場を尊重すべきだ」などとして賛成する意見がある一方「子の福祉の観点が欠落している」との慎重論もある。担当室は表面化しているトラブル例を検証しながら締結の可否を検討。国際結婚では子を巡るトラブルが起きる可能性があることも積極的に広報していくという。
岡田克也外相は1日の記者会見で「今ある問題の対処と(ハーグ)条約加入の適否も含め、ここで議論していくことになる。日本としての対応を早急に検討したい」と語った。
一方、1日に外務省で行われたフランスとの初協議では、フランス側から35件の紛争事例が示され、具体的な対応策について要望が出されたという。
協議会は、近く米国との間でも設置される。
日本弁護士連合会家事法制委員会委員を務め、ハーグ条約に詳しい大谷美紀子弁護士は「日本に連れ戻された子と、日本から連れ去られた子の双方について、担当室が総合的に問題を把握・検討するとすれば有益だ。ただし法的な対応や検討も必要になるため、法務省や裁判所、弁護士との協議も進めることが望ましい」と話している。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=48608742&comm_id=4144830
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1039388&media_id=2
(毎日新聞 - 12月03日 15:03)
国際結婚した夫婦の破綻(はたん)に伴い、一方の親が子を連れ去るトラブルが相次いでいることを受け、外務省は国際結婚を巡る紛争解決のルールを定めた「ハーグ条約」締結の可否などを検討する「子の親権問題担当室」を設置した。「日本がハーグ条約を結んでいないためトラブルが多発している」との欧米からの批判にも配慮し、他国よりも話し合いの準備が整ったフランスとの間で、子の親権問題に関する実務者レベルの協議会を発足させた。【工藤哲】
外務省によると、担当室は1日付で設置され、国際法課や北米1課、西欧課などの職員9人で構成。これまではトラブルの相手方が居住する国の担当課が相談の窓口になっていたが、今後は担当室に一本化する。
ハーグ条約は、先進8カ国の中では日本とロシアが未締結。日本では「締結を勧告している国連の立場を尊重すべきだ」などとして賛成する意見がある一方「子の福祉の観点が欠落している」との慎重論もある。担当室は表面化しているトラブル例を検証しながら締結の可否を検討。国際結婚では子を巡るトラブルが起きる可能性があることも積極的に広報していくという。
岡田克也外相は1日の記者会見で「今ある問題の対処と(ハーグ)条約加入の適否も含め、ここで議論していくことになる。日本としての対応を早急に検討したい」と語った。
一方、1日に外務省で行われたフランスとの初協議では、フランス側から35件の紛争事例が示され、具体的な対応策について要望が出されたという。
協議会は、近く米国との間でも設置される。
日本弁護士連合会家事法制委員会委員を務め、ハーグ条約に詳しい大谷美紀子弁護士は「日本に連れ戻された子と、日本から連れ去られた子の双方について、担当室が総合的に問題を把握・検討するとすれば有益だ。ただし法的な対応や検討も必要になるため、法務省や裁判所、弁護士との協議も進めることが望ましい」と話している。
国際的な子の奪取の民事面に関する条約出典移動: 案内, 検索
国際的な子の奪取の民事面に関する条約(英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、国境を越えた国際的な児童の連れ去り(abduction 誘拐)により法が及ばなくなる法令潜脱行為を防止し、子どもの権利を守ることを目的として、1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効した、全45条からなる多国間条約。ハーグ国際私法会議で制定されたハーグ条約のひとつである。2011年6月14日現在の加入国は、未だ国連加盟国192カ国の半数には満たないが85カ国[1]にのぼり、国際社会の標準ルールとして批准国は増加しつつある[2]。日本は未署名であったが、政府は2011年6月より国内法制との整合性調整等の批准へ向けた準備を開始している
この条約は、親権を持つ親から子を拉致したり、子を隠匿して親権の行使を妨害したりした場合に、拉致が起こった時点での児童の常居所地への帰還を義務づけること及び面接交渉権の保護を目的として作られた条約である(条約前文)。
子どもが16歳に達すると、この条約は適用されなくなる(第4条)。また拉致された先の裁判所あるいは行政当局は、子の返還を決定するに際して、子が反対の意思表示をし、子の成熟度からその意見を尊重すべき場合は、返還しない決定をすることもできる(第13条2項)。ただし、アメリカでは、「子の意見を聞くことは、子の心に負担をかける。親のうち一方を選び他方を捨てる判断を子にさせるべきではない。」との意見から、子は自分の意見を返還裁判で言うことすら許されない運用をされる場合がある。
この条約は最終的な親権の帰属を規定するものでなく、あくまでも児童の常居所地国への返還を規定するものであり、親権の帰属については別途法手続きを行うことになる。
この条約はあくまで子の利益を守ることを目的とするため(条約前文)、国際結婚等で夫婦間が不和となり、あるいは離婚となった場合、一方の親が他方の親に無断で児童を故国などの国外に連れ去ることがあり、それが児童の連れ去られた元の国では不法行為であっても、連れ去られた先の国に国内法が及ばないことから、連れ去られた側が事実上泣き寝入りを強いられる場合でも、親の子に会う権利を守るものではなく、子が親に会う権利を守るものである。
加入国は2011年6月14日現在85カ国[1]に過ぎず、国連加盟国192カ国の半数にも満たない。ヨーロッパ、北米、南米、南アフリカ、オーストラリアなどの西洋文化圏の国のほとんどがこの条約を締結している一方でアジア・アフリカ・中東のほとんどの国がこの条約を締結していない (締約国を参照)。この理由としては、西洋文化圏の国とアジア、アフリカ、中東国の間での離婚および親権調停における制度および価値観の違いがあげられる。
まず途上国では社会的・経済的な理由から父親の側に親権が与えられることが多い。(日本でも過去には跡取り息子の親権は例外なく父親側に渡された)またイスラム国家では男性のイスラム教徒の子どもはイスラム教徒であるとされその親権は父親に属するとされている。また、途上国出身者と欧米出身者の国際結婚では、経済的理由により結婚後に欧米に移民することが多く、その場合、親権調停などにおいて子供の常居所地は欧米先進国となる。このため、途上国がハーグ条約を批准すると、多くの場合で手続きや価値観の異なる外国(欧米)に子供を送還する結果となり、政治的に困難な状態になる。
日本では、平成23年5月20日に加入が閣議決定され、次の臨時国会で成立する見通しである。(「日本における事案・加入をめぐる議論」の節参
国際的な子の奪取の民事面に関する条約(英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、国境を越えた国際的な児童の連れ去り(abduction 誘拐)により法が及ばなくなる法令潜脱行為を防止し、子どもの権利を守ることを目的として、1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効した、全45条からなる多国間条約。ハーグ国際私法会議で制定されたハーグ条約のひとつである。2011年6月14日現在の加入国は、未だ国連加盟国192カ国の半数には満たないが85カ国[1]にのぼり、国際社会の標準ルールとして批准国は増加しつつある[2]。日本は未署名であったが、政府は2011年6月より国内法制との整合性調整等の批准へ向けた準備を開始している
この条約は、親権を持つ親から子を拉致したり、子を隠匿して親権の行使を妨害したりした場合に、拉致が起こった時点での児童の常居所地への帰還を義務づけること及び面接交渉権の保護を目的として作られた条約である(条約前文)。
子どもが16歳に達すると、この条約は適用されなくなる(第4条)。また拉致された先の裁判所あるいは行政当局は、子の返還を決定するに際して、子が反対の意思表示をし、子の成熟度からその意見を尊重すべき場合は、返還しない決定をすることもできる(第13条2項)。ただし、アメリカでは、「子の意見を聞くことは、子の心に負担をかける。親のうち一方を選び他方を捨てる判断を子にさせるべきではない。」との意見から、子は自分の意見を返還裁判で言うことすら許されない運用をされる場合がある。
この条約は最終的な親権の帰属を規定するものでなく、あくまでも児童の常居所地国への返還を規定するものであり、親権の帰属については別途法手続きを行うことになる。
この条約はあくまで子の利益を守ることを目的とするため(条約前文)、国際結婚等で夫婦間が不和となり、あるいは離婚となった場合、一方の親が他方の親に無断で児童を故国などの国外に連れ去ることがあり、それが児童の連れ去られた元の国では不法行為であっても、連れ去られた先の国に国内法が及ばないことから、連れ去られた側が事実上泣き寝入りを強いられる場合でも、親の子に会う権利を守るものではなく、子が親に会う権利を守るものである。
加入国は2011年6月14日現在85カ国[1]に過ぎず、国連加盟国192カ国の半数にも満たない。ヨーロッパ、北米、南米、南アフリカ、オーストラリアなどの西洋文化圏の国のほとんどがこの条約を締結している一方でアジア・アフリカ・中東のほとんどの国がこの条約を締結していない (締約国を参照)。この理由としては、西洋文化圏の国とアジア、アフリカ、中東国の間での離婚および親権調停における制度および価値観の違いがあげられる。
まず途上国では社会的・経済的な理由から父親の側に親権が与えられることが多い。(日本でも過去には跡取り息子の親権は例外なく父親側に渡された)またイスラム国家では男性のイスラム教徒の子どもはイスラム教徒であるとされその親権は父親に属するとされている。また、途上国出身者と欧米出身者の国際結婚では、経済的理由により結婚後に欧米に移民することが多く、その場合、親権調停などにおいて子供の常居所地は欧米先進国となる。このため、途上国がハーグ条約を批准すると、多くの場合で手続きや価値観の異なる外国(欧米)に子供を送還する結果となり、政治的に困難な状態になる。
日本では、平成23年5月20日に加入が閣議決定され、次の臨時国会で成立する見通しである。(「日本における事案・加入をめぐる議論」の節参
運用面の実態ハーグ国際私法会議の事務局はProfessor Nigel Loweに依頼して、2003年における運用実態をまとめたレポート「2003年に行われた1980年10月25日ハーグ条約に基づく申請の統計分析(A statistical analysis of applications made in 2003 under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction (PDF))」を2008年に公表(アドレス)している。調査は条約締結国に報告を求める形で行われている。
それによれば、2003年に行われた申請は全世界合計で、子の帰還に関するものが1259件、面接交渉に関するものが238件であった。 子の帰還に関する申請では、子を連れ去ったとされる者は、母854件(68%)、父367件(29%)、親族25件(2%)、その他7件(1%)であり、圧倒的に母が多い。父母で97%を占め、本来この条約は営利誘拐などにも適用出来るはずのものであるが、「離婚の後始末条約」的実態が色濃く出ている。
国別では、訴えられた国では、1位アメリカ286件(23%)、2位イギリス142件(11%)、3位スペイン87件(7%)、4位ドイツ80件(6%)、5位カナダ56件(4%)となっている。訴えた国では、1位アメリカ167件(13%)、2位イギリス126件(10%)、3位ドイツ107件(9%)、4位メキシコ105件(8%)、5位オーストラリア75件(6%)と、アメリカの突出ぶりが目立ち、同国での親権侵害の常態化が伺える。
申請の結果については、子の帰還となったもの(自発的帰還を含む)628件(50%)、帰還が認められなかったもの413件(33%)、審議中113件(9%)、その他87件(7%)となっている。
年間の全世界での申請数がわずか1259件というのは、費用の面(各国が中央捜査機関Central Authorityを維持する費用、条約事務局を維持する費用など)を考えると、1件当たり非常に高価なものになっていると思われる。
それによれば、2003年に行われた申請は全世界合計で、子の帰還に関するものが1259件、面接交渉に関するものが238件であった。 子の帰還に関する申請では、子を連れ去ったとされる者は、母854件(68%)、父367件(29%)、親族25件(2%)、その他7件(1%)であり、圧倒的に母が多い。父母で97%を占め、本来この条約は営利誘拐などにも適用出来るはずのものであるが、「離婚の後始末条約」的実態が色濃く出ている。
国別では、訴えられた国では、1位アメリカ286件(23%)、2位イギリス142件(11%)、3位スペイン87件(7%)、4位ドイツ80件(6%)、5位カナダ56件(4%)となっている。訴えた国では、1位アメリカ167件(13%)、2位イギリス126件(10%)、3位ドイツ107件(9%)、4位メキシコ105件(8%)、5位オーストラリア75件(6%)と、アメリカの突出ぶりが目立ち、同国での親権侵害の常態化が伺える。
申請の結果については、子の帰還となったもの(自発的帰還を含む)628件(50%)、帰還が認められなかったもの413件(33%)、審議中113件(9%)、その他87件(7%)となっている。
年間の全世界での申請数がわずか1259件というのは、費用の面(各国が中央捜査機関Central Authorityを維持する費用、条約事務局を維持する費用など)を考えると、1件当たり非常に高価なものになっていると思われる。
日本における事案・加入をめぐる議論菅政権は、ハーグ条約に加盟することを念頭に、国内法の骨子案を作成した。2011年5月20日に加盟が閣議決定され、次の臨時国会で成立する見通しである。
国際結婚が破綻(はたん)し、一方の親が自国に子どもを勝手に連れ帰った場合に元の国に戻すことなどを定めた「ハーグ条約」をめぐり、米国のキャンベル国務次官補が2010年2月2日、都内で記者会見した。日本が同条約を締結しない理由として、家庭内暴力(DV)から逃れて帰国する日本人の元妻らがいることを挙げていることについて「実際に暴力があった事例はほとんど見つからない。相当な誤認だ」と語った。 同次官補は「大半は米国内で離婚して共同親権が確立しており、これは『誘拐』だ」と強調し、「解決に向けて進展がないと、日米関係に本当の懸念を生みかねない」と語った。 日本人女性による子の誘拐事案がDVから逃れるためだという主張は当事者やその周辺の人間の言い分であり客観的に証明できる資料を日本国民には公開していない。国内でもDVの証拠もなしにDVを理由に引き離しの被害にあっている父子が数多くいる。
国際結婚が破綻(はたん)し、一方の親が自国に子どもを勝手に連れ帰った場合に元の国に戻すことなどを定めた「ハーグ条約」をめぐり、米国のキャンベル国務次官補が2010年2月2日、都内で記者会見した。日本が同条約を締結しない理由として、家庭内暴力(DV)から逃れて帰国する日本人の元妻らがいることを挙げていることについて「実際に暴力があった事例はほとんど見つからない。相当な誤認だ」と語った。 同次官補は「大半は米国内で離婚して共同親権が確立しており、これは『誘拐』だ」と強調し、「解決に向けて進展がないと、日米関係に本当の懸念を生みかねない」と語った。 日本人女性による子の誘拐事案がDVから逃れるためだという主張は当事者やその周辺の人間の言い分であり客観的に証明できる資料を日本国民には公開していない。国内でもDVの証拠もなしにDVを理由に引き離しの被害にあっている父子が数多くいる。
2009年10月には福岡県柳川市で、アメリカと日本の二重国籍の男性が子供を母親から略取し、アメリカの領事館に逃げ込もうとしたところを未成年者略取の容疑で警察に逮捕される事件が発生した。 報道によると、男性は妻の父親の援助で 九州大学の医学博士を取得した後に結婚、日本に帰化、日本で東京証券取引所マザーズに上場している製薬関係のベンチャー企業の社長になるなどしていたが、アメリカの大学時代のガールフレンドと不倫の挙句、 復縁するために[要出典]日本に家族を残し渡米。妻と子供たちがその後を追ってアメリカの空港に到着した翌日に離婚を申請[19]。訴訟において、財産の半分と私養育費も支払う代わりに母と子はテネシー州内に滞在し、子が年に4か月間父と暮らすこと、父母のどちらかが子と州外に引っ越す場合は事前に相手に連絡し同意を得ることなどが裁判所の調停で定められた。男性は離婚の裁定が出た1か月後に同じように離婚した愛人と結婚している。その後母親が裁判所における取り決めに反して無断で子どもを日本に連れ帰ったため、アメリカの裁判所は母親の逮捕状を発行している。
逮捕された男は罪を認め反省を示したため、起訴されなかった。このケースにおいて、もし日本が条約を批准していたとしても、子のアメリカ滞在が短いため、常居所地がアメリカと認定されるとは限らず、子がアメリカに強制的に送還されて問題が解決するとは限らない。さらに、条約を批准していない現状においても、父親から子の引渡しを求める法的手段は存在するため、この例をもって条約の必要性を言うには疑問がある。
その後、父親が元妻に損害賠償を求めた民事訴訟で、米テネシー州の裁判所は、慰謝料など610万ドル(約4億9000万円)の支払いを元妻に命ずる判決を下した。
これらの事案とは逆に、外国国籍を有する親によって子供が日本から外国へと連れ去られる事件も発生している。
近年この問題への関心が高まっており、欧米においては条約未締結国である日本が問題を放置しているとして批判されることが多い。
逮捕された男は罪を認め反省を示したため、起訴されなかった。このケースにおいて、もし日本が条約を批准していたとしても、子のアメリカ滞在が短いため、常居所地がアメリカと認定されるとは限らず、子がアメリカに強制的に送還されて問題が解決するとは限らない。さらに、条約を批准していない現状においても、父親から子の引渡しを求める法的手段は存在するため、この例をもって条約の必要性を言うには疑問がある。
その後、父親が元妻に損害賠償を求めた民事訴訟で、米テネシー州の裁判所は、慰謝料など610万ドル(約4億9000万円)の支払いを元妻に命ずる判決を下した。
これらの事案とは逆に、外国国籍を有する親によって子供が日本から外国へと連れ去られる事件も発生している。
近年この問題への関心が高まっており、欧米においては条約未締結国である日本が問題を放置しているとして批判されることが多い。
2009年3月にアメリカのヒラリー・クリントン国務長官は、中曽根弘文外務大臣(当時)にハーグ条約加盟を要請し、中曽根外務大臣はこれに対して前向きに検討することを約束した。
2009年10月、ハーグ条約締約国であるアメリカおよび西欧諸国の大使は共同で日本政府に対して条約締結を要請した[14]。民主党現政権の岡田克也外務大臣(当時)もこの要請に対して「前向きに検討する」と回答している。外務省に「子の親権問題担当室」が設置された。
2010年8月14日 日本政府は、ハーグ条約を翌年に批准する方針を固めた。
2010年9月29日、アメリカ下院は、子どもの連れ去りは拉致であるとして日本を非難する決議を行った。
2011年1月10日 日本政府は、ハーグ条約の締結に向け、月内にも関係省庁による副大臣級の会議を設置する方針を固めた。
2011年1月には、フランス上院が早期批准を促す決議を行った。
2011年2月2日、外務省は2010年5月から11月まで行った「条約加入の是非についてのアンケート」の結果の概要をホームページで公開した。11月までに64件の回答があり、締結すべきとするものが22件、締結すべきではないとするものが17件だった[39]。なお、この「アンケート」は郵送式や電話式のものではなく、外務省のホームページ(当時のアドレス(リンク切れ))上で「国際的な子の移動に関する問題の当事者となった経験者」に記入を呼びかける形式のもので、本当に当事者であったかは確認できないうえ、広報があまり行われていなかったので知らなかった当事者も多数いると思われる。海外では「誘拐」と扱われてしまうケースもあるが、子供をDVから保護するため、加盟には与党である民主党も含めて慎重論も根強い。
2009年10月、ハーグ条約締約国であるアメリカおよび西欧諸国の大使は共同で日本政府に対して条約締結を要請した[14]。民主党現政権の岡田克也外務大臣(当時)もこの要請に対して「前向きに検討する」と回答している。外務省に「子の親権問題担当室」が設置された。
2010年8月14日 日本政府は、ハーグ条約を翌年に批准する方針を固めた。
2010年9月29日、アメリカ下院は、子どもの連れ去りは拉致であるとして日本を非難する決議を行った。
2011年1月10日 日本政府は、ハーグ条約の締結に向け、月内にも関係省庁による副大臣級の会議を設置する方針を固めた。
2011年1月には、フランス上院が早期批准を促す決議を行った。
2011年2月2日、外務省は2010年5月から11月まで行った「条約加入の是非についてのアンケート」の結果の概要をホームページで公開した。11月までに64件の回答があり、締結すべきとするものが22件、締結すべきではないとするものが17件だった[39]。なお、この「アンケート」は郵送式や電話式のものではなく、外務省のホームページ(当時のアドレス(リンク切れ))上で「国際的な子の移動に関する問題の当事者となった経験者」に記入を呼びかける形式のもので、本当に当事者であったかは確認できないうえ、広報があまり行われていなかったので知らなかった当事者も多数いると思われる。海外では「誘拐」と扱われてしまうケースもあるが、子供をDVから保護するため、加盟には与党である民主党も含めて慎重論も根強い。
法的問題点子に対する強制執行の問題条約に加入するためには、子を連れ去って来た者から子を強制的に引き離し、外国に移送する法手続きの整備が必須である。しかし、「運用面の実態」にあるように、連れ去って来た者は大多数が母親であるため、このことは、裁判所の命令で同居する母親から子を引き剥がし、外国に送ってしまうという、極めて困難で、感情的な強制執行を意味し、そのような手続法が国民の支持を受け、国会で成立するかは難しい問題である。
現行法では、人の引渡しの直接強制は、
1.民事執行法の動産執行を準用する方法
2.人身保護法に基づく方法
の2種類がある。1の方法は、物に対する動産執行を人に準用する所に根本的な問題が存在する。2の方法は、最高裁判所第三小法廷平成5年10月19日判決平成5(オ)609号で人身保護法が適用されるのは「違法性が顕著である」ことが示された場合のみであることから、一般の場合に使えるとは限らず、本条約のケースを全てカバーすることはできない。このため、条約に加入するには、法改正が必要である。
なお、日本が現状結んでいる犯罪人引渡し条約では、犯罪者あるいは容疑者が日本国籍を持つ場合、日本は引渡し行う義務がないことになっており、本条約に加入すれば、日本国籍を持つ者を強制的に外国に移送する義務を負う初めての条約ということになる。
現行法では、人の引渡しの直接強制は、
1.民事執行法の動産執行を準用する方法
2.人身保護法に基づく方法
の2種類がある。1の方法は、物に対する動産執行を人に準用する所に根本的な問題が存在する。2の方法は、最高裁判所第三小法廷平成5年10月19日判決平成5(オ)609号で人身保護法が適用されるのは「違法性が顕著である」ことが示された場合のみであることから、一般の場合に使えるとは限らず、本条約のケースを全てカバーすることはできない。このため、条約に加入するには、法改正が必要である。
なお、日本が現状結んでいる犯罪人引渡し条約では、犯罪者あるいは容疑者が日本国籍を持つ場合、日本は引渡し行う義務がないことになっており、本条約に加入すれば、日本国籍を持つ者を強制的に外国に移送する義務を負う初めての条約ということになる。
親権の所在の問題一方の親から本条約による子の返還の申し立てがあった場合、「そもそも返還を請求した親に親権があるのか」という点が問題となる。親権の存在は本条約3条の「違法な連れ去り」の前提になり、また親権がないことは本条約13条(a)の返還拒否の理由となる。
例えば、米国人の男と、日本人の女が米国内で結婚し、共に米国内で生活し、子(日米二重国籍)を産んだ後、離婚し、子の親権は共同親権となった後、日本人女が子を日本に連れ帰ったとする。この場合、親子間の法律関係のの準拠法は、次の法律に従い決められる。
法の適用に関する通則法(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)
第32条(親子間の法律関係) 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
第38条(本国法) 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
この例では、子は日米二重国籍なので、本国法は第38条ただし書きにより日本法となり、母親の本国法と一致するため、両親と子の3者間の法律関係の準拠法は日本法が適用される。(なお、第32条は「両親と子の3者の準拠法を1つに決める」という趣旨で、「父子間の準拠法、母子間の準拠法を別々に決める」という意味ではない。)すると、日本法では離婚後の共同親権は認められないため、米国での共同親権の決定は違法となるため無効となってしまう。この場合に返還請求をした米国人男に親権があるかが問題となるが、「先に親権者の指定が行われないと返還請求できない」という考えや、「親権者の指定がないので、婚姻中の共同親権が暫定的に残り、返還請求できる」という考えなど、非常に微妙な問題となってしまう。もし裁判所が前者の考え方を取れば、返還請求は認められないことになる。
例えば、米国人の男と、日本人の女が米国内で結婚し、共に米国内で生活し、子(日米二重国籍)を産んだ後、離婚し、子の親権は共同親権となった後、日本人女が子を日本に連れ帰ったとする。この場合、親子間の法律関係のの準拠法は、次の法律に従い決められる。
法の適用に関する通則法(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)
第32条(親子間の法律関係) 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
第38条(本国法) 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
この例では、子は日米二重国籍なので、本国法は第38条ただし書きにより日本法となり、母親の本国法と一致するため、両親と子の3者間の法律関係の準拠法は日本法が適用される。(なお、第32条は「両親と子の3者の準拠法を1つに決める」という趣旨で、「父子間の準拠法、母子間の準拠法を別々に決める」という意味ではない。)すると、日本法では離婚後の共同親権は認められないため、米国での共同親権の決定は違法となるため無効となってしまう。この場合に返還請求をした米国人男に親権があるかが問題となるが、「先に親権者の指定が行われないと返還請求できない」という考えや、「親権者の指定がないので、婚姻中の共同親権が暫定的に残り、返還請求できる」という考えなど、非常に微妙な問題となってしまう。もし裁判所が前者の考え方を取れば、返還請求は認められないことになる。
転居の自由との衝突転居の自由は日本国憲法第22条で認められている基本的人権である。しかし、アメリカなどでは離婚の際、転居を禁止したり、転居の自由を著しく制限したり(例えば転居をする場合、裁判所の許可を必要とするなど。国家機関の許可が必要であれば、もはや自由とは言えない)、さらに転居を防ぐためにパスポートを取り上げたりすることが当然のごとく行われる。
このようなアメリカの裁判所の決定は、日本国憲法の立場から見れば、基本的人権の侵害であり、違憲であり許されないものであるから、無効(日本国憲法第98条)である。
すると、そのような外国裁判所の決定を前提とした本条約による子の帰還命令も違憲無効となってしまう。また、アメリカの裁判所の命令が同意命令の形を取っていたとしても、基本的人権は放棄できない権利であり、転居の自由を禁じるような同意命令は無効となる。このため、本条約に加入する場合、どのように転居の自由を保障するかが問題となる。 母親は好きな所で暮らすことができる。例えばアメリカへ行って暮らすのも自由である。しかし日本においても、子どもは自由に転居できるわけではない。子どもは親権に服すのであり、親権者の決めた場所で暮らさなければらない。
なお、アメリカでは転居の自由は権利章典 (アメリカ)に規定がなく、基本的人権とはされていない。一方世界人権宣言の第13条1項[46]および国際人権規約第12条1項は転居の自由を基本的人権としている。
また、本条約の子の出国を違法とする条項は、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)10条2項に定める子及び親の出入国の自由に違反するという考えもある。
子供の権利条約第10条2項は、親と子が会うために、親および子が自由に国境を越えて出入国する権利を定めており、本条約が子の国境を越えた移動を禁止する考えと相容れない。児童の権利に関する条約を批准していない国は、全世界でアメリカとソマリアの2国だけで、他の193カ国は条約を批准している。
このようなアメリカの裁判所の決定は、日本国憲法の立場から見れば、基本的人権の侵害であり、違憲であり許されないものであるから、無効(日本国憲法第98条)である。
すると、そのような外国裁判所の決定を前提とした本条約による子の帰還命令も違憲無効となってしまう。また、アメリカの裁判所の命令が同意命令の形を取っていたとしても、基本的人権は放棄できない権利であり、転居の自由を禁じるような同意命令は無効となる。このため、本条約に加入する場合、どのように転居の自由を保障するかが問題となる。 母親は好きな所で暮らすことができる。例えばアメリカへ行って暮らすのも自由である。しかし日本においても、子どもは自由に転居できるわけではない。子どもは親権に服すのであり、親権者の決めた場所で暮らさなければらない。
なお、アメリカでは転居の自由は権利章典 (アメリカ)に規定がなく、基本的人権とはされていない。一方世界人権宣言の第13条1項[46]および国際人権規約第12条1項は転居の自由を基本的人権としている。
また、本条約の子の出国を違法とする条項は、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)10条2項に定める子及び親の出入国の自由に違反するという考えもある。
子供の権利条約第10条2項は、親と子が会うために、親および子が自由に国境を越えて出入国する権利を定めており、本条約が子の国境を越えた移動を禁止する考えと相容れない。児童の権利に関する条約を批准していない国は、全世界でアメリカとソマリアの2国だけで、他の193カ国は条約を批准している。
在留資格との不調和の問題国際結婚が離婚に終わった場合、子は本条約により当該国から出られなくなるのに対し、当該国で外国人である親は離婚により在留資格を失い国外退去になり、親子が引き離されてしまうという問題がある。
これは、「国内で未成年の子を養育する外国人親」に対し特に在留資格を与えない移民政策を取るアメリカにおいて顕著な人権侵害を起こしている。例えば、H-1Bビザ(専門職職業ビザ)でアメリカ国内に滞在する非米国人と日本人がアメリカ国内で結婚し、日本人はH-4ビザ(Hビザの家族のビザ)の資格で共にアメリカで結婚生活を送り、子が生まれた後離婚した場合、子は本条約によりアメリカ国外に出られなくなるが、当該日本人は離婚によりH-4ビザを失うので、子をアメリカに残しアメリカから退去しなければならなくなる。また、H-1Bビザを持つ者同士がアメリカで結婚し、子が生まれた後離婚した場合、失業してH-1Bビザを失った段階で、子をアメリカに残し親はアメリカを出国しなければならない。
これは、「国内で未成年の子を養育する外国人親」に対し特に在留資格を与えない移民政策を取るアメリカにおいて顕著な人権侵害を起こしている。例えば、H-1Bビザ(専門職職業ビザ)でアメリカ国内に滞在する非米国人と日本人がアメリカ国内で結婚し、日本人はH-4ビザ(Hビザの家族のビザ)の資格で共にアメリカで結婚生活を送り、子が生まれた後離婚した場合、子は本条約によりアメリカ国外に出られなくなるが、当該日本人は離婚によりH-4ビザを失うので、子をアメリカに残しアメリカから退去しなければならなくなる。また、H-1Bビザを持つ者同士がアメリカで結婚し、子が生まれた後離婚した場合、失業してH-1Bビザを失った段階で、子をアメリカに残し親はアメリカを出国しなければならない。
経済的不利益の問題外国で生活していた夫婦が離婚した場合、子は本条約により当該国から出られなくなり、その結果、親権者たる親もその国から事実上出られなくなる。外国において働き、生計を立てて子を養育することは、言語能力の問題、文化風習の違いの問題、在留資格(ビザ)による就労制限の問題、外国人差別の問題などにより、母国で働くより低賃金の仕事になりがちであり、経済的な不利益を被る場合が多い。特にアメリカでは、「雇用において自国民を外国人より優先することを違法としない」という外国人差別を是認する法律があり、事態は深刻である。
また、離婚になるような場合、もう一方の親に、失業、無収入、勤労意欲の喪失、浪費、ギャンブル癖、多額の借金などの経済的問題がある場合が多く、養育費の不払い(アメリカ、カナダでは養育費を払わない親はDeadbeat Parentと言われ社会問題化している。)など、子の養育に必要な資金に困窮する場合が多い。このような場合、外国人親としては、母国に子と一緒に帰り、賃金の高い職業に就き、困窮を解決することを考えるのであるが、本条約によりそれは不可能であり、困窮の中で子を養育することを強いられてしまう。
また、離婚になるような場合、もう一方の親に、失業、無収入、勤労意欲の喪失、浪費、ギャンブル癖、多額の借金などの経済的問題がある場合が多く、養育費の不払い(アメリカ、カナダでは養育費を払わない親はDeadbeat Parentと言われ社会問題化している。)など、子の養育に必要な資金に困窮する場合が多い。このような場合、外国人親としては、母国に子と一緒に帰り、賃金の高い職業に就き、困窮を解決することを考えるのであるが、本条約によりそれは不可能であり、困窮の中で子を養育することを強いられてしまう。
返還後の子の監護者不在の問題本条約で子が常居所国に返還された後、誰も子を監護をせず、子が施設に入れられるケースが発生し問題となっている。 オーストラリアで暮らしていたオーストラリア人とスイス人の夫婦(Mr. Russell Wood and Mrs. Maya Wood-Hosig)の事件(Wood事件と言われる)で[53]、オーストラリアで離婚後、スイス人の元妻が10歳と8歳の子をスイスに連れ帰り、本条約により子はオーストラリアに返還されたが、オーストラリア人の元夫は子を引き取ることが出来ず、子はオーストラリアの施設に入れられてしまったという事件である。その後、スイス人元妻の訴えにより、子はスイスの元妻に再度返還されている。
このケースなどは、本条約が「どちらが子にとってより良い環境か」という「子の福祉」を考慮することをせず、「常居所地への返還」を機械的に行うことを目的として作られたものであるため発生するケースだと考えられる。スイス政府はこの事件を受け、子を返還しなくても良い例外を定める本条約第13条(b)項の「耐え難い状況(intolerable situation)」を柔軟に解釈して、このような場合に返還を認めない方針を打ち出している。しかし、スイスの方法では「返還すると子にとって明らかに環境が悪化し、返還しない方が子にとって明らかに良いが、返還すると耐え難い状況になるとまでは言えない」場合は結局子を返還せざるを得ず、子の福祉を完全に保護することはできない。
このケースなどは、本条約が「どちらが子にとってより良い環境か」という「子の福祉」を考慮することをせず、「常居所地への返還」を機械的に行うことを目的として作られたものであるため発生するケースだと考えられる。スイス政府はこの事件を受け、子を返還しなくても良い例外を定める本条約第13条(b)項の「耐え難い状況(intolerable situation)」を柔軟に解釈して、このような場合に返還を認めない方針を打ち出している。しかし、スイスの方法では「返還すると子にとって明らかに環境が悪化し、返還しない方が子にとって明らかに良いが、返還すると耐え難い状況になるとまでは言えない」場合は結局子を返還せざるを得ず、子の福祉を完全に保護することはできない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
厳しい入管 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
厳しい入管のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90056人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208314人
- 3位
- 酒好き
- 170696人
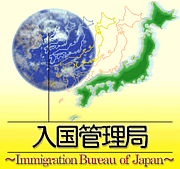


















![[dir] パキスタン](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/42/12/914212_142s.jpg)



