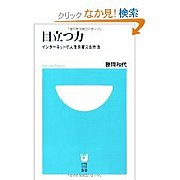http://
本田技研工業が2009年2月6日に発売したハイブリッド専用車、新型「インサイト」の販売が絶好調だ。09年2月17日付の日本経済新聞によると、2月16日現在で受注台数が1万台を超え、月間販売目標5000台の2倍に達したという。
新型インサイトは、発表会が行われた2月5日までに、既に事前予約で約5000台を受注していた。つまり発売日の2月6日からわずか11日間で、さらに5000台を上乗せしたわけだ。このペースで行けば、発売当月でいきなり新車乗用車販売台数ランキングのトップに躍り出るかもしれない。ちなみに昨年同月(2008年2月)の1位はホンダ「フィット」の1万5980台、先月(09年1月)は同じくフィットで8723台だ。
新型インサイトがこれだけ売れているのはやはり、これまでのハイブリッド車の常識を覆す、189万円からという低価格だろう。同じハイブリッド車、トヨタ「プリウス」の最廉価グレード233万1000円と比べると、装備内容が違うとはいえ43万1000円も安い。
これだけの価格破壊を、どうやって成し遂げたのか。開発責任者の本田技術研究所 主任研究員、関 康成(せき やすなり)氏のコメントを交えながら、その過程をひも解いていこう。
福井社長の記者会見コメントで、開発責任者は「2階に上げてハシゴを外された感じ」
ホンダの福井威夫社長が、新型インサイトのコンセプトを記者会見で公表したのは2006年5月のこと。当時の発言要旨を引用すると、「世界の主要市場での販売を見据えて、ファミリーユースに適した新型のハイブリッド専用車を開発している。燃費技術のさらなる向上と大幅なコストダウンを図り、『シビックハイブリッド』よりさらにお求めやすい価格で、2009年に発売する」。「生産は鈴鹿製作所でハイブリッドユニットを含めて行い、販売は、北米での 10万台を含め、全世界で年間約20万台を見込んでいる」、というもの。
開発責任者の関氏は、福井社長のこの発言を聞いた当時の心境を「2階に上げてハシゴを外された感じ」と振り返る。06年5月時点でできあがっていたのは、1/4サイズのクレイモデルだけ。ホンダが既に販売していたシビックハイブリッドよりも、小型のハイブリッド車を作るという大枠は決まっていた。しかし、燃費向上と大幅なコストダウンをどうやって成し遂げるのか、全世界で20万台売るにはどうすればいいのかなどは、全く白紙の状態だったという。
小型・軽量・低コストのハイブリッドシステムをさらに改良
コストダウンと燃費改善のために取り組んだのは、まずハイブリッドシステムの小型軽量化だ。ホンダのハイブリッドシステムは、ガソリンエンジンがメインで、必要に応じてモーターで駆動力をアシストする「パラレル方式」だ。
これに対してプリウスは、ガソリンエンジンとモーターに加え、発電機を組み合わせ、エンジンで発電しながらモーターを回すといった複雑な動作を行う「シリーズ・パラレル方式」。走行条件に応じて理想的な制御を行うため、燃費効率はパラレル方式より高いが、代償としてシステムが複雑で重く、コスト高になる。
インサイトは、このパラレル式の小型・軽量・低コストというメリットをさらに推し進めた。同じパラレル式のシビックハイブリッド(2006年モデル)よりも、モーターを約22%薄型化、約15%軽量化した。ニッケル水素バッテリーは内部構造を改良して効率を高め、約31%小型化して約35%軽量化、部品点数を約50%削減している。そのほかのパーツも同様に、小型軽量化と部品点数削減を進めた。
こうした改良を行った結果、インサイトのハイブリッドシステムは「総重量58kgで大人1人分くらい」(関氏)に収まっている。モーター出力はシビックハイブリッドの15kW(20PS)に対して、インサイトでは10kW(14PS)と低いが、ボディーが一回り小さく軽量なおかげで、同等の走行性能を実現している。
ガソリンエンジンが不得意な領域をモーターがアシスト
インサイトのモーターは「IMA(インテリジェント・モーター・アシスト)」という名称で、エンジンとCVTの中間に挟み込むように配置されている。モーターはガソリンエンジンよりも低速トルクが大きいという特徴があり、走行条件に合わせてエンジンが不得意な領域を補うように動作する。
まずエンジンの負荷が高く燃料を消費する発進時や加速時には、駆動力をアシストしてパワーを補い、エンジンのスロットル開度を抑えて燃費を改善する。40km/h程度までの低速巡航では、エンジンのバルブ作動を休止して空転させ、モーターだけで走行する。バッテリーの状態や走行条件にもよるが、エンジンをかけずに約1km走行できる。
高速巡航時は逆に、モーターを休止してエンジンだけで走行する。バッテリー残量が少ない場合は、必要に応じてモーターを発電機として作動させて充電を行う。そして減速時には、エンジンを休止してモーターが発電、運動エネルギーを回生して充電する。信号などの停止時には自動的にアイドリングストップするが、エンジン再起動にもこのモーターを使う。
開発責任者の関氏は、「ハイブリッドを意識せずにすむような、普通のクルマの乗り味を目指した」と語る。プリウスはブレーキ時に積極的に発電機を作動させてエネルギー回生を行うため、通常のガソリン車から乗り換えるとブレーキの効き方に違和感を感じる。インサイトは踏み始めは通常のブレーキと同様に効くようにして、ブレーキ圧が強くなると回生を増やすように制御している。
コストダウンを進めるために、全パーツの約36%を既存モデルから流用
コストダウンのため、既存車種とのパーツ共用も積極的に行った。全パーツの約36%を、フィットやシビックなどから流用。クルマの基礎となるプラットホームは、前半のエンジンルームまでをフィットから流用し、フットボードから後半を新開発した。フィットは燃料タンクを前席フロア下に配置するセンタータンクレイアウトなのに対して、インサイトは車高を低めて空力性能を向上させるために、ガソリンタンクを後席フロア下に配置している。
ニッケル水素バッテリーとパワーコントロールユニットは「IPU(インテリジェント・パワー・ユニット)」としてまとめられ、荷室前方の床下に配置。最大400Lのラゲッジスペース容量を実現すると共に、低重心化によって走行安定性の向上にも寄与している。
新型インサイトは違うネーミングで発売するつもりだった
インサイトという車名は、2006年まで販売された初代モデルの名称を受け継いだものだ。だが関氏は、「新型インサイトのコンセプトは初代モデルと全く違うため、当初は違う名前で発売しようと考えていた」という。
初代インサイトは1999年9月発表、11月に発売された。当時の量産ガソリン車としては世界最高の低燃費、35km/Lを実現したのが特徴だ。ハイブリッドシステムは新型インサイトと同じパラレル式で、1LのリーンバーンVTECエンジンとモーターの組み合わせだ。低燃費と走りの良さを実現するために、ボディーの骨格や外板にはスポーツカーの「NSX」と同様にアルミ材を多用し、車重は5速MT車でわずか820kgだった。
しかしこの初代モデルは、空力性能の追求や車体の軽量化といった要素を徹底的に突き詰めた結果、実用性を犠牲にしたクルマになってしまった。ボディーは2ドアクーペで2人乗りと、ファミリーカーとしては使えないパッケージングだ。技術集団でレースが大好きなホンダらしさが、悪い方向に作用した結果と言えよう。
これに対して1997年発表の初代プリウスは、実用性を重視した5ナンバーサイズの4ドアセダンで登場。2003年登場の現行プリウスは、輸出を意識して3ナンバーの5ドアハッチバックスタイルに変更し、北米でも人気を博しているのとは対象的だ。
日本人には意外? 欧米では強いインサイトのブランドイメージ
初代インサイトは、この実用性の低さが主立った理由となり、2006年7月までの約6年半で輸出も含めた販売台数は約1万7000台と、ビジネスとしては成功しなかった。プリウスが、2008年4月末で世界累計販売100万台を突破しているのとは対照的だ。
新型インサイトは、実用性を重視した5ドアハッチバックボディーを採用して世界で年間20万台を販売しようという、初代インサイトとはコンセプトが全くが異なるクルマだ。このため開発陣は車名も新しくしようと、北米や欧州の現地法人に依頼していくつかのネーミング案の反応を探ってみた。
だが北米でも欧州でも新しいネーミング案への反応は芳しくなく、帰ってきたのは「インサイトでいいじゃないか」という回答だった。関氏はその理由を、「初代インサイトは北米や欧州ではプリウスより先に発売されたため、最初のハイブリッド車として認知されている。しかも低燃費の世界記録を達成しているため、日本で考えているよりもずっとネーミングのイメージが浸透していたんです」と説明する。こうして、新型インサイトは初代モデルの名前を踏襲することになった。
コストをかけずに知恵を絞って装備した「エコアシスト」
新型インサイトはハイブリッドシステムというハード面だけでなく、ドライバーのエコ運転をアシストするというソフト面でも、低燃費へのアプローチを行っている。全グレードに標準装備する、新開発の「エコアシスト(エコロジカル・ドライブ・アシスト・システム)」だ。
エコアシストは、3つの機能で構成される。インパネ右下にある「ECON(イーコン)スイッチ」を押すと、エンジンの出力制御で発進・加速をゆるやかにし、アイドルストップ時間の延長やエアコンの省エネ運転を行う「ECONモード」機能。燃費の良し悪しをリアルタイムで分析して表示する「コーチング」機能。ドライバーのエコ運転習熟度を採点する「ティーチング・アドバイス」機能だ。
コストダウンという縛りの中で、このエコアシスト機能を標準搭載したのは、ずいぶん思い切った決断ではないのだろうか。そう聞くと関氏からは、「実は元々必要な装備に、開発側が知恵を絞って機能を加えただけで、コストはそれほどかかっていないんです。あえて言うなら、最廉価版グレードにもマルチインフォメーションディスプレイを標準装備する必要があった程度ですね」という答えが返ってきた。
ハードの改良だけでなく、開発陣もドライバーも知恵を寄せ合って燃費を良くしましょうという意図が伺える、ユニークな発想だ。
グレード構成は3タイプ、最廉価グレードでも標準装備は充実
新型インサイトのグレード構成は、シンプルに3タイプ。ホンダが最量販機種と想定するのは、車両本体価格189万円の「G」グレードだ。最廉価版のグレードだが、フルオートエアコンやテレスコピック&チルトステアリング、全面高熱線吸収/UVカットガラス、後席3名分のヘッドレストとシートベルトなど、標準装備は充実している。
205万円の「L」グレードは、Gに加えてディスチャージヘッドランプ、ドアミラーウインカー、本革巻きステアリングホイール、マップランプなどを装備。221万円の「LS」グレードは、Lの装備に加えフォグライト、16インチタイヤ&アルミホイール、VSA(ABS+トラクションコントロール+横滑り防止装置)を追加。ステアリングホイールにパドルシフトを装備し、マニュアル感覚のシフト操作が楽しめるなど、スポーティー仕様となっている。
自動車メーカーは景気の冷え込みという逆風にさらされているが、低価格と低燃費を両立した新型インサイトは、この逆風を追い風に変えられそうなポテンシャルを感じる。プリウスでもできなかった、ハイブリッド車初の月間販売台数トップを記録するか、3月上旬の新車販売台数発表が楽しみだ。
本田技研工業が2009年2月6日に発売したハイブリッド専用車、新型「インサイト」の販売が絶好調だ。09年2月17日付の日本経済新聞によると、2月16日現在で受注台数が1万台を超え、月間販売目標5000台の2倍に達したという。
新型インサイトは、発表会が行われた2月5日までに、既に事前予約で約5000台を受注していた。つまり発売日の2月6日からわずか11日間で、さらに5000台を上乗せしたわけだ。このペースで行けば、発売当月でいきなり新車乗用車販売台数ランキングのトップに躍り出るかもしれない。ちなみに昨年同月(2008年2月)の1位はホンダ「フィット」の1万5980台、先月(09年1月)は同じくフィットで8723台だ。
新型インサイトがこれだけ売れているのはやはり、これまでのハイブリッド車の常識を覆す、189万円からという低価格だろう。同じハイブリッド車、トヨタ「プリウス」の最廉価グレード233万1000円と比べると、装備内容が違うとはいえ43万1000円も安い。
これだけの価格破壊を、どうやって成し遂げたのか。開発責任者の本田技術研究所 主任研究員、関 康成(せき やすなり)氏のコメントを交えながら、その過程をひも解いていこう。
福井社長の記者会見コメントで、開発責任者は「2階に上げてハシゴを外された感じ」
ホンダの福井威夫社長が、新型インサイトのコンセプトを記者会見で公表したのは2006年5月のこと。当時の発言要旨を引用すると、「世界の主要市場での販売を見据えて、ファミリーユースに適した新型のハイブリッド専用車を開発している。燃費技術のさらなる向上と大幅なコストダウンを図り、『シビックハイブリッド』よりさらにお求めやすい価格で、2009年に発売する」。「生産は鈴鹿製作所でハイブリッドユニットを含めて行い、販売は、北米での 10万台を含め、全世界で年間約20万台を見込んでいる」、というもの。
開発責任者の関氏は、福井社長のこの発言を聞いた当時の心境を「2階に上げてハシゴを外された感じ」と振り返る。06年5月時点でできあがっていたのは、1/4サイズのクレイモデルだけ。ホンダが既に販売していたシビックハイブリッドよりも、小型のハイブリッド車を作るという大枠は決まっていた。しかし、燃費向上と大幅なコストダウンをどうやって成し遂げるのか、全世界で20万台売るにはどうすればいいのかなどは、全く白紙の状態だったという。
小型・軽量・低コストのハイブリッドシステムをさらに改良
コストダウンと燃費改善のために取り組んだのは、まずハイブリッドシステムの小型軽量化だ。ホンダのハイブリッドシステムは、ガソリンエンジンがメインで、必要に応じてモーターで駆動力をアシストする「パラレル方式」だ。
これに対してプリウスは、ガソリンエンジンとモーターに加え、発電機を組み合わせ、エンジンで発電しながらモーターを回すといった複雑な動作を行う「シリーズ・パラレル方式」。走行条件に応じて理想的な制御を行うため、燃費効率はパラレル方式より高いが、代償としてシステムが複雑で重く、コスト高になる。
インサイトは、このパラレル式の小型・軽量・低コストというメリットをさらに推し進めた。同じパラレル式のシビックハイブリッド(2006年モデル)よりも、モーターを約22%薄型化、約15%軽量化した。ニッケル水素バッテリーは内部構造を改良して効率を高め、約31%小型化して約35%軽量化、部品点数を約50%削減している。そのほかのパーツも同様に、小型軽量化と部品点数削減を進めた。
こうした改良を行った結果、インサイトのハイブリッドシステムは「総重量58kgで大人1人分くらい」(関氏)に収まっている。モーター出力はシビックハイブリッドの15kW(20PS)に対して、インサイトでは10kW(14PS)と低いが、ボディーが一回り小さく軽量なおかげで、同等の走行性能を実現している。
ガソリンエンジンが不得意な領域をモーターがアシスト
インサイトのモーターは「IMA(インテリジェント・モーター・アシスト)」という名称で、エンジンとCVTの中間に挟み込むように配置されている。モーターはガソリンエンジンよりも低速トルクが大きいという特徴があり、走行条件に合わせてエンジンが不得意な領域を補うように動作する。
まずエンジンの負荷が高く燃料を消費する発進時や加速時には、駆動力をアシストしてパワーを補い、エンジンのスロットル開度を抑えて燃費を改善する。40km/h程度までの低速巡航では、エンジンのバルブ作動を休止して空転させ、モーターだけで走行する。バッテリーの状態や走行条件にもよるが、エンジンをかけずに約1km走行できる。
高速巡航時は逆に、モーターを休止してエンジンだけで走行する。バッテリー残量が少ない場合は、必要に応じてモーターを発電機として作動させて充電を行う。そして減速時には、エンジンを休止してモーターが発電、運動エネルギーを回生して充電する。信号などの停止時には自動的にアイドリングストップするが、エンジン再起動にもこのモーターを使う。
開発責任者の関氏は、「ハイブリッドを意識せずにすむような、普通のクルマの乗り味を目指した」と語る。プリウスはブレーキ時に積極的に発電機を作動させてエネルギー回生を行うため、通常のガソリン車から乗り換えるとブレーキの効き方に違和感を感じる。インサイトは踏み始めは通常のブレーキと同様に効くようにして、ブレーキ圧が強くなると回生を増やすように制御している。
コストダウンを進めるために、全パーツの約36%を既存モデルから流用
コストダウンのため、既存車種とのパーツ共用も積極的に行った。全パーツの約36%を、フィットやシビックなどから流用。クルマの基礎となるプラットホームは、前半のエンジンルームまでをフィットから流用し、フットボードから後半を新開発した。フィットは燃料タンクを前席フロア下に配置するセンタータンクレイアウトなのに対して、インサイトは車高を低めて空力性能を向上させるために、ガソリンタンクを後席フロア下に配置している。
ニッケル水素バッテリーとパワーコントロールユニットは「IPU(インテリジェント・パワー・ユニット)」としてまとめられ、荷室前方の床下に配置。最大400Lのラゲッジスペース容量を実現すると共に、低重心化によって走行安定性の向上にも寄与している。
新型インサイトは違うネーミングで発売するつもりだった
インサイトという車名は、2006年まで販売された初代モデルの名称を受け継いだものだ。だが関氏は、「新型インサイトのコンセプトは初代モデルと全く違うため、当初は違う名前で発売しようと考えていた」という。
初代インサイトは1999年9月発表、11月に発売された。当時の量産ガソリン車としては世界最高の低燃費、35km/Lを実現したのが特徴だ。ハイブリッドシステムは新型インサイトと同じパラレル式で、1LのリーンバーンVTECエンジンとモーターの組み合わせだ。低燃費と走りの良さを実現するために、ボディーの骨格や外板にはスポーツカーの「NSX」と同様にアルミ材を多用し、車重は5速MT車でわずか820kgだった。
しかしこの初代モデルは、空力性能の追求や車体の軽量化といった要素を徹底的に突き詰めた結果、実用性を犠牲にしたクルマになってしまった。ボディーは2ドアクーペで2人乗りと、ファミリーカーとしては使えないパッケージングだ。技術集団でレースが大好きなホンダらしさが、悪い方向に作用した結果と言えよう。
これに対して1997年発表の初代プリウスは、実用性を重視した5ナンバーサイズの4ドアセダンで登場。2003年登場の現行プリウスは、輸出を意識して3ナンバーの5ドアハッチバックスタイルに変更し、北米でも人気を博しているのとは対象的だ。
日本人には意外? 欧米では強いインサイトのブランドイメージ
初代インサイトは、この実用性の低さが主立った理由となり、2006年7月までの約6年半で輸出も含めた販売台数は約1万7000台と、ビジネスとしては成功しなかった。プリウスが、2008年4月末で世界累計販売100万台を突破しているのとは対照的だ。
新型インサイトは、実用性を重視した5ドアハッチバックボディーを採用して世界で年間20万台を販売しようという、初代インサイトとはコンセプトが全くが異なるクルマだ。このため開発陣は車名も新しくしようと、北米や欧州の現地法人に依頼していくつかのネーミング案の反応を探ってみた。
だが北米でも欧州でも新しいネーミング案への反応は芳しくなく、帰ってきたのは「インサイトでいいじゃないか」という回答だった。関氏はその理由を、「初代インサイトは北米や欧州ではプリウスより先に発売されたため、最初のハイブリッド車として認知されている。しかも低燃費の世界記録を達成しているため、日本で考えているよりもずっとネーミングのイメージが浸透していたんです」と説明する。こうして、新型インサイトは初代モデルの名前を踏襲することになった。
コストをかけずに知恵を絞って装備した「エコアシスト」
新型インサイトはハイブリッドシステムというハード面だけでなく、ドライバーのエコ運転をアシストするというソフト面でも、低燃費へのアプローチを行っている。全グレードに標準装備する、新開発の「エコアシスト(エコロジカル・ドライブ・アシスト・システム)」だ。
エコアシストは、3つの機能で構成される。インパネ右下にある「ECON(イーコン)スイッチ」を押すと、エンジンの出力制御で発進・加速をゆるやかにし、アイドルストップ時間の延長やエアコンの省エネ運転を行う「ECONモード」機能。燃費の良し悪しをリアルタイムで分析して表示する「コーチング」機能。ドライバーのエコ運転習熟度を採点する「ティーチング・アドバイス」機能だ。
コストダウンという縛りの中で、このエコアシスト機能を標準搭載したのは、ずいぶん思い切った決断ではないのだろうか。そう聞くと関氏からは、「実は元々必要な装備に、開発側が知恵を絞って機能を加えただけで、コストはそれほどかかっていないんです。あえて言うなら、最廉価版グレードにもマルチインフォメーションディスプレイを標準装備する必要があった程度ですね」という答えが返ってきた。
ハードの改良だけでなく、開発陣もドライバーも知恵を寄せ合って燃費を良くしましょうという意図が伺える、ユニークな発想だ。
グレード構成は3タイプ、最廉価グレードでも標準装備は充実
新型インサイトのグレード構成は、シンプルに3タイプ。ホンダが最量販機種と想定するのは、車両本体価格189万円の「G」グレードだ。最廉価版のグレードだが、フルオートエアコンやテレスコピック&チルトステアリング、全面高熱線吸収/UVカットガラス、後席3名分のヘッドレストとシートベルトなど、標準装備は充実している。
205万円の「L」グレードは、Gに加えてディスチャージヘッドランプ、ドアミラーウインカー、本革巻きステアリングホイール、マップランプなどを装備。221万円の「LS」グレードは、Lの装備に加えフォグライト、16インチタイヤ&アルミホイール、VSA(ABS+トラクションコントロール+横滑り防止装置)を追加。ステアリングホイールにパドルシフトを装備し、マニュアル感覚のシフト操作が楽しめるなど、スポーティー仕様となっている。
自動車メーカーは景気の冷え込みという逆風にさらされているが、低価格と低燃費を両立した新型インサイトは、この逆風を追い風に変えられそうなポテンシャルを感じる。プリウスでもできなかった、ハイブリッド車初の月間販売台数トップを記録するか、3月上旬の新車販売台数発表が楽しみだ。
|
|
|
|
|
|
|
|
mixi自己啓発・向上委員会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-