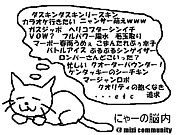|
|
|
|
コメント(115)
YMR-01G22
ツインヘッド型試作機
MR-01Gからの派生型。エムズによって生み出された多くのG型派生機体の中でも割と初期に登場した。その奇抜な外観から、当時「ツインヘッド」の俗称で呼ばれていたとされる。
ツインヘッドの名のとおり、本来コクピットに当たる胸部の上にあるはずの頭部パーツは無く、ちょうど両肩部の位置にそれぞれ頭部パーツが搭載されている。これによってAJ型よりも高性能な索敵機能を持たせることに成功した。
開発当初は頭部パーツの代わりに追加武装等、または片側を頭部、反対側を武装など、様々な発展プランが提案されていたのだが、本機が1機制作されたのみでツインヘッド計画自体が中止となってしまった。
計画中止の主な理由としては、設計上どうしても避けられない耐久性の低下があり、実用性に乏しいと判断されたようである。
ツインヘッド型試作機
MR-01Gからの派生型。エムズによって生み出された多くのG型派生機体の中でも割と初期に登場した。その奇抜な外観から、当時「ツインヘッド」の俗称で呼ばれていたとされる。
ツインヘッドの名のとおり、本来コクピットに当たる胸部の上にあるはずの頭部パーツは無く、ちょうど両肩部の位置にそれぞれ頭部パーツが搭載されている。これによってAJ型よりも高性能な索敵機能を持たせることに成功した。
開発当初は頭部パーツの代わりに追加武装等、または片側を頭部、反対側を武装など、様々な発展プランが提案されていたのだが、本機が1機制作されたのみでツインヘッド計画自体が中止となってしまった。
計画中止の主な理由としては、設計上どうしても避けられない耐久性の低下があり、実用性に乏しいと判断されたようである。
YMR-01SF
詳細不明・フライトシステム試験型?
本機体は、開発経緯や情報が一切残っていないとされる謎のMRである。外観的には恐らくGFS系機体の流れを組んでいるのではないかと推測されるが、やはり真相は定かではない。第二次戦争終結後、エムズ側のとある軍事施設内で発見された設計図のようなイラストにこのYMR-01SFという型式名が添えられていた。
写真はそれを元に作られた模型である。
両肩に専用の推進ブースターを装備し、従来では不可能だったMRの飛行を可能にすべく開発されたのではないかと一部のMR評論家が語っているが、開発チーム・スタッフ共に生存が確認されておらず、また従来のエムズ側機体にあったどの型式・シリーズにも合致しないため、真相は未だ闇のベールに包まれている。
当然のように本機体をめぐり様々な議論が展開されたが、結局その答えは出なかった。連合軍関係者も本件については「ノーコメント」と口を閉ざしたままであるとか。
詳細不明・フライトシステム試験型?
本機体は、開発経緯や情報が一切残っていないとされる謎のMRである。外観的には恐らくGFS系機体の流れを組んでいるのではないかと推測されるが、やはり真相は定かではない。第二次戦争終結後、エムズ側のとある軍事施設内で発見された設計図のようなイラストにこのYMR-01SFという型式名が添えられていた。
写真はそれを元に作られた模型である。
両肩に専用の推進ブースターを装備し、従来では不可能だったMRの飛行を可能にすべく開発されたのではないかと一部のMR評論家が語っているが、開発チーム・スタッフ共に生存が確認されておらず、また従来のエムズ側機体にあったどの型式・シリーズにも合致しないため、真相は未だ闇のベールに包まれている。
当然のように本機体をめぐり様々な議論が展開されたが、結局その答えは出なかった。連合軍関係者も本件については「ノーコメント」と口を閉ざしたままであるとか。
MVC-002
高機動陸船艇型
連合軍側の陸船艇型機体。前作であるMVC-001はホバー型MR搭載機であったが、本機はその開発コンセプトを一新し、陸上を高速移動するいわば機動要塞として誕生した。MR-03に使われているエンジンを二基搭載し、計12もの専用設計の車輪によって陸上を高速走行する。武装面でも充実を図っており、対MR用マイクロミサイル発射機構を4基(1基につき5発まで同時発射可能)、前方用火器として15mmヘビーマシンガンを2門、さらに用途に合わせて幾つかの種類の武装ユニットを搭載できた。武装ユニットは旧式の追加ブロックデバイスと互換性があり、時には自軍のMRと武装を互いに交換し合うこともできたという。
対被弾性も抜かりはなく、エムズ側機体であるMR-01AWCなどによる砲撃を物ともしなかったという逸話が残っている。
このように最強の陸戦艇と評された本機であったが、当然のように段違いで高価な生産コスト、また製造に時間が非常に掛かり第二次戦争末期に1機のみが投入され、「最終決戦」でエムズの猛攻に遭い大破。その短い役目を終えてしまった。
高機動陸船艇型
連合軍側の陸船艇型機体。前作であるMVC-001はホバー型MR搭載機であったが、本機はその開発コンセプトを一新し、陸上を高速移動するいわば機動要塞として誕生した。MR-03に使われているエンジンを二基搭載し、計12もの専用設計の車輪によって陸上を高速走行する。武装面でも充実を図っており、対MR用マイクロミサイル発射機構を4基(1基につき5発まで同時発射可能)、前方用火器として15mmヘビーマシンガンを2門、さらに用途に合わせて幾つかの種類の武装ユニットを搭載できた。武装ユニットは旧式の追加ブロックデバイスと互換性があり、時には自軍のMRと武装を互いに交換し合うこともできたという。
対被弾性も抜かりはなく、エムズ側機体であるMR-01AWCなどによる砲撃を物ともしなかったという逸話が残っている。
このように最強の陸戦艇と評された本機であったが、当然のように段違いで高価な生産コスト、また製造に時間が非常に掛かり第二次戦争末期に1機のみが投入され、「最終決戦」でエムズの猛攻に遭い大破。その短い役目を終えてしまった。
MF-04
麻雀型軽戦闘機
好評を得たMF-03であったが、機体の大型化によって小回りが効きづらい面もあって、数で押すようなミッションでは幾分不利であった。そのため第二次戦争中期の手前あたりからエムズが新たに開発したのがこのMF-04である。従来機よりもかなり小型化された外観はややコミカルな印象を受けるが、小型機の名に恥じない軽快な操縦性を見せた。製造コストもMF-03の約半分にとどまる事もあって、最終的にMF-03よりも多く生産され、集団戦ではそのアイデンティティを遺憾無く発揮した。MF-03の周囲に数機のMF-04が護衛をする形で編隊飛行するなど、本機の登場によってエムズの航空編成の幅が広がったことは言うまでもないだろう。
麻雀型軽戦闘機
好評を得たMF-03であったが、機体の大型化によって小回りが効きづらい面もあって、数で押すようなミッションでは幾分不利であった。そのため第二次戦争中期の手前あたりからエムズが新たに開発したのがこのMF-04である。従来機よりもかなり小型化された外観はややコミカルな印象を受けるが、小型機の名に恥じない軽快な操縦性を見せた。製造コストもMF-03の約半分にとどまる事もあって、最終的にMF-03よりも多く生産され、集団戦ではそのアイデンティティを遺憾無く発揮した。MF-03の周囲に数機のMF-04が護衛をする形で編隊飛行するなど、本機の登場によってエムズの航空編成の幅が広がったことは言うまでもないだろう。
MF-05C
改修型
MF-05は飽くまで護衛や集団戦を主とする軽戦闘機であって、単独で作戦を遂行する能力は当てられていなかった。そんなMF-05を単独でも作戦遂行ができるように改修したのがMF-05C型だ。
C型では新規に延長ノーズブロックが装備され、エンジンの推力も増強されている。武装面では2.0mm機関砲を両翼・先端の計3門搭載。ミッションに応じて追加増槽やミサイル等を機体下部に装備可能とした。
ここまで強化されたC型だったが、如何せん元が軽戦闘機だけあって限界も早く、エムズは早々に当計画を中断。やはり同じようにして使い回しの限界が来ていたMF-03の件も相まって、次期主力戦闘機の開発に踏み込む。
改修型
MF-05は飽くまで護衛や集団戦を主とする軽戦闘機であって、単独で作戦を遂行する能力は当てられていなかった。そんなMF-05を単独でも作戦遂行ができるように改修したのがMF-05C型だ。
C型では新規に延長ノーズブロックが装備され、エンジンの推力も増強されている。武装面では2.0mm機関砲を両翼・先端の計3門搭載。ミッションに応じて追加増槽やミサイル等を機体下部に装備可能とした。
ここまで強化されたC型だったが、如何せん元が軽戦闘機だけあって限界も早く、エムズは早々に当計画を中断。やはり同じようにして使い回しの限界が来ていたMF-03の件も相まって、次期主力戦闘機の開発に踏み込む。
MF-110
麻雀型攻撃機
連合軍の攻撃機。本機はMF-100Aとともに第一線で運用され、主として航空面ではどのような場合でもマルチロール機を用いていたエムズ(機体サイズのバリエーションはあったが)とは対照的に、連合軍は対空任務をMF-100A、対地任務をMF-110に割り当てることでより効率的な制空権確保を狙った。元々マルチロールの性格を持つMF-100Aではあるが、場合によっては対地ミッションがメインとなることも多々あったため、連合軍は早い段階で本機の投入を決断。
このため、第二次戦争初期〜中期の航空戦力に関しては連合軍側がかなり優位に立っていたとされる。
本機は固定武装を持たず、ブロック型爆弾を最大4発まで装備できた。
麻雀型攻撃機
連合軍の攻撃機。本機はMF-100Aとともに第一線で運用され、主として航空面ではどのような場合でもマルチロール機を用いていたエムズ(機体サイズのバリエーションはあったが)とは対照的に、連合軍は対空任務をMF-100A、対地任務をMF-110に割り当てることでより効率的な制空権確保を狙った。元々マルチロールの性格を持つMF-100Aではあるが、場合によっては対地ミッションがメインとなることも多々あったため、連合軍は早い段階で本機の投入を決断。
このため、第二次戦争初期〜中期の航空戦力に関しては連合軍側がかなり優位に立っていたとされる。
本機は固定武装を持たず、ブロック型爆弾を最大4発まで装備できた。
MF-115
麻雀型戦闘機
MF-110をベースに各部の増強が図られたバージョンアップ版。とはいえ機体の性格は完全に戦闘機寄りになっており、攻撃機をベースにした戦闘機という珍しいコンセプトの機体となっている。装甲強化による大型化に伴い、エンジンは出力をより大きいものへと換装され、新開発のブロック型ミサイル4発を搭載可能。固定武装として2.0mm機関砲を機体先端に2門装備。強力な加速性能を活かした一撃離脱戦法を得意とする。
ブロック型ミサイルはMF-110で採用していた同型の爆弾に推進・追尾機能を持たせたもので、元々の高い威力を生かした強力な武装となっている。
しかし追尾性能に若干の難があり、敵機撃墜に時間が掛かる若しくは回避されることもザラであった。本機は第二次戦争中期に数十機が配備され、主に大型の目標を迎撃・撃墜する作戦に運用された。
麻雀型戦闘機
MF-110をベースに各部の増強が図られたバージョンアップ版。とはいえ機体の性格は完全に戦闘機寄りになっており、攻撃機をベースにした戦闘機という珍しいコンセプトの機体となっている。装甲強化による大型化に伴い、エンジンは出力をより大きいものへと換装され、新開発のブロック型ミサイル4発を搭載可能。固定武装として2.0mm機関砲を機体先端に2門装備。強力な加速性能を活かした一撃離脱戦法を得意とする。
ブロック型ミサイルはMF-110で採用していた同型の爆弾に推進・追尾機能を持たせたもので、元々の高い威力を生かした強力な武装となっている。
しかし追尾性能に若干の難があり、敵機撃墜に時間が掛かる若しくは回避されることもザラであった。本機は第二次戦争中期に数十機が配備され、主に大型の目標を迎撃・撃墜する作戦に運用された。
MF-116
麻雀型主力戦闘機
MF-115の設計を見直し、より臨機応変にミッションに対応できるようにした連合軍の最新鋭主力戦闘機。エンジン出力を敢えて落とし、両翼端に補助ブースターを装備することで機動性が向上。見かけによらず小回りの効く機体となった。本機は第二次戦争中期にMF-100Aの後継となるべく25機が試験運用され、第二次戦争後期に本格的に実戦配備が開始された。
固定武装として3.0mm機関砲を機首に1門、新規に採用されたTBM(Ten-Bow-Missile)を最大6発まで装備可能。TBMは連合軍が独自開発した航空機用ミサイルで、発射後は対空・対地問わず目標を自動で補足・追尾する。
麻雀型主力戦闘機
MF-115の設計を見直し、より臨機応変にミッションに対応できるようにした連合軍の最新鋭主力戦闘機。エンジン出力を敢えて落とし、両翼端に補助ブースターを装備することで機動性が向上。見かけによらず小回りの効く機体となった。本機は第二次戦争中期にMF-100Aの後継となるべく25機が試験運用され、第二次戦争後期に本格的に実戦配備が開始された。
固定武装として3.0mm機関砲を機首に1門、新規に採用されたTBM(Ten-Bow-Missile)を最大6発まで装備可能。TBMは連合軍が独自開発した航空機用ミサイルで、発射後は対空・対地問わず目標を自動で補足・追尾する。
MF-500
麻雀型主力戦闘機
第二次戦争末期にエムズが主力戦闘機として運用した機体。MF-50をベースとしている説があるが、その体躯は倍以上の大型戦闘機となっており、単独での長距離ミッションも遂行可能であるという。機首に2.5mm機関砲を一門装備し、従来の一般的なミサイルの装備はもちろん、本機の開発前にエムズ側のスパイが連合軍側から入手した情報を元に作り上げたTBWの装備も可能となっている。さらに、エムズ独自開発のBCMS(ブロックコンテナマルチミサイル)の使用も可能。
BCMSは連合軍のブロック型ミサイルとほぼ同型でありながら、発射後は目標まで自動追尾、着弾直前にコンテナが展開。対空地問わず小型弾頭がBCMS一発につき8発まで散開、目標を四方から取り囲む。
麻雀型主力戦闘機
第二次戦争末期にエムズが主力戦闘機として運用した機体。MF-50をベースとしている説があるが、その体躯は倍以上の大型戦闘機となっており、単独での長距離ミッションも遂行可能であるという。機首に2.5mm機関砲を一門装備し、従来の一般的なミサイルの装備はもちろん、本機の開発前にエムズ側のスパイが連合軍側から入手した情報を元に作り上げたTBWの装備も可能となっている。さらに、エムズ独自開発のBCMS(ブロックコンテナマルチミサイル)の使用も可能。
BCMSは連合軍のブロック型ミサイルとほぼ同型でありながら、発射後は目標まで自動追尾、着弾直前にコンテナが展開。対空地問わず小型弾頭がBCMS一発につき8発まで散開、目標を四方から取り囲む。
MR-C12
装甲強化最終型
小型機動要塞MRという役目を任されつつもその役目に見合ったスペックを与えられなかったMR-Cシリーズだが、それでも研究開発は細々と続けられていたようだ。当機はその最終型であり、機体サイズは拡大され、外観としてより機動要塞らしくなった。武装面はブロックデバイスによるロケット砲・多弾頭ミサイルに加え、MR-01AWシリーズの開発スタッフによる協力によってTBデバイスの装着が可能となっている。
本機は最二次戦争末期に開発されたが、この時になるとエムズ側で小型機動要塞MRの必要性というものが失われ、さらに大型機が主力となることもあって(詳細は後述)結局試作機が2機のみ製造された。その2機は「最終決戦」に投入されたと言われているが詳しいことはわかっていない。
装甲強化最終型
小型機動要塞MRという役目を任されつつもその役目に見合ったスペックを与えられなかったMR-Cシリーズだが、それでも研究開発は細々と続けられていたようだ。当機はその最終型であり、機体サイズは拡大され、外観としてより機動要塞らしくなった。武装面はブロックデバイスによるロケット砲・多弾頭ミサイルに加え、MR-01AWシリーズの開発スタッフによる協力によってTBデバイスの装着が可能となっている。
本機は最二次戦争末期に開発されたが、この時になるとエムズ側で小型機動要塞MRの必要性というものが失われ、さらに大型機が主力となることもあって(詳細は後述)結局試作機が2機のみ製造された。その2機は「最終決戦」に投入されたと言われているが詳しいことはわかっていない。
XMFR-2000
EN砲発射試験型
XMFR-1000のMRモードをベースに、変形機構を敢えてオミットさせた試験機。その代わりに専用設計のバックパックを追加装備し、TBデバイスを両肩に装着している。XMFR-2000に搭載されたTBデバイスは当機体のためにチューニングされた特殊なエネルギー砲で、最大出力での発射威力はMR-01AWC2の集中砲火5機分に匹敵する。当然のように相当な発射エネルギーも必要となるため、バックパックにはMR-01Gの約30倍の容量を誇るジェネレータを内蔵している。さらに大型ブースターを二基取り付けているため、小回りこそ効かないが瞬時の高速移動も可能であった。
このようにかなり特殊な移動砲台としての役割が与えられた本機だったが、「最終決戦」で実戦投入を目前にして連合軍の攻撃により破壊されてしまった。
EN砲発射試験型
XMFR-1000のMRモードをベースに、変形機構を敢えてオミットさせた試験機。その代わりに専用設計のバックパックを追加装備し、TBデバイスを両肩に装着している。XMFR-2000に搭載されたTBデバイスは当機体のためにチューニングされた特殊なエネルギー砲で、最大出力での発射威力はMR-01AWC2の集中砲火5機分に匹敵する。当然のように相当な発射エネルギーも必要となるため、バックパックにはMR-01Gの約30倍の容量を誇るジェネレータを内蔵している。さらに大型ブースターを二基取り付けているため、小回りこそ効かないが瞬時の高速移動も可能であった。
このようにかなり特殊な移動砲台としての役割が与えられた本機だったが、「最終決戦」で実戦投入を目前にして連合軍の攻撃により破壊されてしまった。
YMR-60-1
武装デバイス試験型MR 1号機
連合軍側の試験機。第二次戦争初期から武装デバイスの開発に成功、運用を開始したエムズとは対照的に、連合軍側の武装デバイス開発は難航した。
連合軍は開戦当初からMR-03を主力機としてエムズを圧倒してきたが、攻撃手段は第一次戦争時代のMRで一般的だった殴打などの格闘、ブロックデバイスによる火器使用などと以前と全く変わらず、後にエムズからAW系機体が登場すると戦況は一変していった。本機はそれに対抗するべく第二次戦争中期に急造で開発された試験機体で、SCデバイスという新開発の武装デバイスを運用するための実験に使用された。
SCデバイスは「面」を換装することで様々な局面に対応可能なマルチウェポンとして期待されたが、搭載MRへの負担も非常に大きく、大柄なYMR-60でも運用ギリギリのラインだったという。
結局、SCデバイスは文字通り「お蔵入り」となってしまい、連合軍は新たな武装デバイス開発に着手することとなる。
武装デバイス試験型MR 1号機
連合軍側の試験機。第二次戦争初期から武装デバイスの開発に成功、運用を開始したエムズとは対照的に、連合軍側の武装デバイス開発は難航した。
連合軍は開戦当初からMR-03を主力機としてエムズを圧倒してきたが、攻撃手段は第一次戦争時代のMRで一般的だった殴打などの格闘、ブロックデバイスによる火器使用などと以前と全く変わらず、後にエムズからAW系機体が登場すると戦況は一変していった。本機はそれに対抗するべく第二次戦争中期に急造で開発された試験機体で、SCデバイスという新開発の武装デバイスを運用するための実験に使用された。
SCデバイスは「面」を換装することで様々な局面に対応可能なマルチウェポンとして期待されたが、搭載MRへの負担も非常に大きく、大柄なYMR-60でも運用ギリギリのラインだったという。
結局、SCデバイスは文字通り「お蔵入り」となってしまい、連合軍は新たな武装デバイス開発に着手することとなる。
YMR-60-2
武装デバイス試験型MR 2号機
ベース機体は変えずに、搭載する武装デバイスを変更したYMR-60の2号機。様々なデバイスの開発を模索した連合軍であったが、最終的に実用性など多くの要素を考慮した結果、皮肉にもエムズ側のTBデバイスと全く同じものが妥当であるという判断に終わった。
本機はそのTBデバイスの運用試験機であり、TBデバイスに関しては今までの戦闘データや戦闘中にエムズから鹵獲した兵器を参考に、ほとんどコピーと言っていいレベルのものが作られた。(名称も同じだったという)
本機は試験機体のため実戦投入こそなかったが、TBデバイスの運用テストは無事成功したという。
武装デバイス試験型MR 2号機
ベース機体は変えずに、搭載する武装デバイスを変更したYMR-60の2号機。様々なデバイスの開発を模索した連合軍であったが、最終的に実用性など多くの要素を考慮した結果、皮肉にもエムズ側のTBデバイスと全く同じものが妥当であるという判断に終わった。
本機はそのTBデバイスの運用試験機であり、TBデバイスに関しては今までの戦闘データや戦闘中にエムズから鹵獲した兵器を参考に、ほとんどコピーと言っていいレベルのものが作られた。(名称も同じだったという)
本機は試験機体のため実戦投入こそなかったが、TBデバイスの運用テストは無事成功したという。
MR-04はMR-03の改良版というだけでなく、「連合軍側の」武装デバイス搭載機として活躍を見せた。
その主な兵装は三種類が確認されている。
・TBキャノン
新型の高性能なジェネレータを採用することでツインキャノンでも難なく使用可能。圧倒的火力で遠方の目標を殲滅させる。
・TBブレード
近接格闘用武装。TBデバイスの周囲に特殊なエネルギー粒子を発生させ、対象を一刀両断する。
・TBライフル
近〜中距離に対応する銃火器。実弾兵器ではなくエネルギーライフルであり、セッティングを調整することで連射性や威力等を変更可能。調整はパイロットがコクピット内、手元にある調整器によって容易かつ素早く出来たため、戦闘時でもロス無く対応できた。
その主な兵装は三種類が確認されている。
・TBキャノン
新型の高性能なジェネレータを採用することでツインキャノンでも難なく使用可能。圧倒的火力で遠方の目標を殲滅させる。
・TBブレード
近接格闘用武装。TBデバイスの周囲に特殊なエネルギー粒子を発生させ、対象を一刀両断する。
・TBライフル
近〜中距離に対応する銃火器。実弾兵器ではなくエネルギーライフルであり、セッティングを調整することで連射性や威力等を変更可能。調整はパイロットがコクピット内、手元にある調整器によって容易かつ素早く出来たため、戦闘時でもロス無く対応できた。
MR-PR1
大型練習機
連合軍側の練習機。もともと連合軍側では第二次戦争開戦当初から大型機の運用を主としており、専用に練習機を用いるような事は見られず、実戦機体での操縦訓練がされていた。
しかし第二次戦争も末期に近づいた頃、補充新兵の即戦力化を早めるため新たに専用の練習機を開発したのである。連合軍に限っては古参パイロットや辺境基地で行動していたパイロットに限られるが、従来のMR-01シリーズのような小型機からの機種転換も視野に入れて設計された本機は、操縦はもちろん、火器運用の訓練にも特化している。
コクピット周りはMR-03のものをそのまま流用しており、実戦機に乗り換えた際も違和感がない様配慮されている。本機もエムズのMR-01GA-PR のように実戦機よりも後発となる点では似ているが、運用・および開発背景は全く異なったものであった。
大型練習機
連合軍側の練習機。もともと連合軍側では第二次戦争開戦当初から大型機の運用を主としており、専用に練習機を用いるような事は見られず、実戦機体での操縦訓練がされていた。
しかし第二次戦争も末期に近づいた頃、補充新兵の即戦力化を早めるため新たに専用の練習機を開発したのである。連合軍に限っては古参パイロットや辺境基地で行動していたパイロットに限られるが、従来のMR-01シリーズのような小型機からの機種転換も視野に入れて設計された本機は、操縦はもちろん、火器運用の訓練にも特化している。
コクピット周りはMR-03のものをそのまま流用しており、実戦機に乗り換えた際も違和感がない様配慮されている。本機もエムズのMR-01GA-PR のように実戦機よりも後発となる点では似ているが、運用・および開発背景は全く異なったものであった。
MR-1
新型汎用機
第二次戦争開戦から末期に至るまで、連合軍は一貫して大型機の運用を行ってきたが、局地戦ではエムズ側の小型機によって苦戦を強いられることも少なくなかった。そのため連合軍側でも小型機の開発は戦争中期から計画されていたが、エムズに対抗できるほどのスペックを持つ機体はなかなか誕生せず計画は難航した。
本機はそんな連合軍がやっとの思いで開発した小型の汎用MRであり、ベースにはMR-01Aが使われているが中身はベース機体を遥かに凌駕する高性能な機体に仕上げられている。
残念ながら実戦運用は戦争末期とかなり遅れてしまったが、この頃になると連合軍側でもTBデバイスのノウハウが充実しており、状況に応じた様々な武装デバイスの運用が可能となった。武装デバイスはTBはもちろん、携行弾数こそ少ないがMF-115さらに116で使用されたTBMの使用も可能。従来のブロック型デバイスも装備可能という、連合軍の技術の粋を集結させた究極の汎用機体となっている。
さらに内部ジェネレータセッティングの調整によりキャノンユニットも選択でき、局地戦に限られるが専用設計のロングレンジライフルも使用できた。ジェネレータはコクピット内の手元にあるスイッチで即座に調整可能であり、武装換装による時間短縮にも貢献。ロングレンジライフルは高圧縮エネルギーを最大15Km先のターゲットに向けて発射可能であり、命中精度はかなりのものであったとされる。
メインコンピュータも「東海大学レベル」という非常に高性能なものが奢られ、それに加えて3つのサブコンが搭載されている。このサブコン単体でも「因数分解」が出来るほどの高スペックを誇っており、最大稼働時は4つのコンピュータが機体運用をアシストする。関係者の間ではこれを「クアッド・コンピュータ・システム(QCS)」と呼んでいたようだ。
MR-1は「最終決戦」において相当数が配備されたとのことだが、詳しい記録は残っていない。
新型汎用機
第二次戦争開戦から末期に至るまで、連合軍は一貫して大型機の運用を行ってきたが、局地戦ではエムズ側の小型機によって苦戦を強いられることも少なくなかった。そのため連合軍側でも小型機の開発は戦争中期から計画されていたが、エムズに対抗できるほどのスペックを持つ機体はなかなか誕生せず計画は難航した。
本機はそんな連合軍がやっとの思いで開発した小型の汎用MRであり、ベースにはMR-01Aが使われているが中身はベース機体を遥かに凌駕する高性能な機体に仕上げられている。
残念ながら実戦運用は戦争末期とかなり遅れてしまったが、この頃になると連合軍側でもTBデバイスのノウハウが充実しており、状況に応じた様々な武装デバイスの運用が可能となった。武装デバイスはTBはもちろん、携行弾数こそ少ないがMF-115さらに116で使用されたTBMの使用も可能。従来のブロック型デバイスも装備可能という、連合軍の技術の粋を集結させた究極の汎用機体となっている。
さらに内部ジェネレータセッティングの調整によりキャノンユニットも選択でき、局地戦に限られるが専用設計のロングレンジライフルも使用できた。ジェネレータはコクピット内の手元にあるスイッチで即座に調整可能であり、武装換装による時間短縮にも貢献。ロングレンジライフルは高圧縮エネルギーを最大15Km先のターゲットに向けて発射可能であり、命中精度はかなりのものであったとされる。
メインコンピュータも「東海大学レベル」という非常に高性能なものが奢られ、それに加えて3つのサブコンが搭載されている。このサブコン単体でも「因数分解」が出来るほどの高スペックを誇っており、最大稼働時は4つのコンピュータが機体運用をアシストする。関係者の間ではこれを「クアッド・コンピュータ・システム(QCS)」と呼んでいたようだ。
MR-1は「最終決戦」において相当数が配備されたとのことだが、詳しい記録は残っていない。
【大型機と従来機】
今更と言われそうな事ではあるが、第二次戦争を通して連合軍・エムズ両陣営はそれぞれ大型機・小型機という全く異なるMRの運用を行っていた。
小型機と呼ばれるMRは従来のMR-01型のような機体を指すが、もともとMR-01のようなサイズが一般的なMRとして普及したためその呼び方には当初違和感を覚える者も居たという。しかし多数の大型機の登場によって便宜上小型機と呼称されるようになった。
第二次戦争における小型機はエムズが過去のノウハウもあって開戦当初からその機体特性に合わせた運用・設計改良を繰り返していたため連合軍の大型機にも引けをとってはいなかった。何より従来機からのフィードバックが圧倒的に大きく、運用コストも比較的安価に抑えることができるのは優位な点であると言えるだろう。機動性もとい俊敏性に関しても大型機より初期スペックとして高いものが殆どであり、改良する際のコストも少なくできた。
一方大型機は連合軍が「お家芸」とも言えるようなものであり、小型機に対しては数より質で対抗する、というイメージが大きい。大柄な機体サイズに見合った高出力なエンジンの採用はもちろんのこと、やはり相当に強化された耐久性のおかげで対被弾性、特に生存性の高さは特筆に値する。やはり開発・運用コストは高くなるが連合軍ならではの資金力の高さを活かして、この点に関してはあまり問題にはならなかったようである。
今更と言われそうな事ではあるが、第二次戦争を通して連合軍・エムズ両陣営はそれぞれ大型機・小型機という全く異なるMRの運用を行っていた。
小型機と呼ばれるMRは従来のMR-01型のような機体を指すが、もともとMR-01のようなサイズが一般的なMRとして普及したためその呼び方には当初違和感を覚える者も居たという。しかし多数の大型機の登場によって便宜上小型機と呼称されるようになった。
第二次戦争における小型機はエムズが過去のノウハウもあって開戦当初からその機体特性に合わせた運用・設計改良を繰り返していたため連合軍の大型機にも引けをとってはいなかった。何より従来機からのフィードバックが圧倒的に大きく、運用コストも比較的安価に抑えることができるのは優位な点であると言えるだろう。機動性もとい俊敏性に関しても大型機より初期スペックとして高いものが殆どであり、改良する際のコストも少なくできた。
一方大型機は連合軍が「お家芸」とも言えるようなものであり、小型機に対しては数より質で対抗する、というイメージが大きい。大柄な機体サイズに見合った高出力なエンジンの採用はもちろんのこと、やはり相当に強化された耐久性のおかげで対被弾性、特に生存性の高さは特筆に値する。やはり開発・運用コストは高くなるが連合軍ならではの資金力の高さを活かして、この点に関してはあまり問題にはならなかったようである。
【最終決戦】
それが一体いつ頃に行われたのかは詳細不明であるが、連合軍・エムズ両陣営の総力が一斉に衝突し合った正に最終決戦のことを指す。戦争末期になると両陣営も余力が残りわずかとなっており、ちょうど全戦力を当てた時期が互いに一致したとも言われているが、先述の「陰謀説」もあってかやはりこの最終決戦もあらかじめ仕組まれたプログラムのひとつであるとする関係者も存在する。
なりふり構っていられないというのもあるとは思うが、完成したばかりの試作機がテストもせずそのままこの決戦に持ち込まれることもあったため、両陣営、もしくはそれらを裏で手を引く謎の組織による壮大なMR同士による戦闘実験であるとする説も少なからず納得できるというものだ。
関係者の中ではそのほとんどが「連合軍側の勝利に終わった」と口を揃えたように答えたのだが、ごく少数の「エムズが勝利した」という回答も残っているため、その詳細は未だ謎に包まれている。我々がどれだけ追求しても、何故か彼らはそれ以上の答えを教えてくれなかったのだ。
それが一体いつ頃に行われたのかは詳細不明であるが、連合軍・エムズ両陣営の総力が一斉に衝突し合った正に最終決戦のことを指す。戦争末期になると両陣営も余力が残りわずかとなっており、ちょうど全戦力を当てた時期が互いに一致したとも言われているが、先述の「陰謀説」もあってかやはりこの最終決戦もあらかじめ仕組まれたプログラムのひとつであるとする関係者も存在する。
なりふり構っていられないというのもあるとは思うが、完成したばかりの試作機がテストもせずそのままこの決戦に持ち込まれることもあったため、両陣営、もしくはそれらを裏で手を引く謎の組織による壮大なMR同士による戦闘実験であるとする説も少なからず納得できるというものだ。
関係者の中ではそのほとんどが「連合軍側の勝利に終わった」と口を揃えたように答えたのだが、ごく少数の「エムズが勝利した」という回答も残っているため、その詳細は未だ謎に包まれている。我々がどれだけ追求しても、何故か彼らはそれ以上の答えを教えてくれなかったのだ。
YMR-Z
新型汎用試験機
エムズが最終決戦のために投入したとされる新型汎用機の試作・試験型機体。しかし最終決戦ではこのYMR-Zも実戦に投入されていたという。外観は従来のエムズ機体よりもやや大きく、連合軍の大型機よりは小さい。例えるなら当機体は「中型機」と呼べるような全く新しいコンセプトの汎用機であるが、そのスペックは非常に高水準なものであったとされる。
ベース機体は存在せず、あらゆるエムズ機体のデータをフィードバックさせた高性能コンピュータを二つ搭載。これにより本機単体でも様々なミッションに対応可能だ。記録には残っていないが武装デバイスの使用も可能であったとされている。脚部形状がGA型に酷似しているが、こちらは後部に補助ブースターを搭載しており、機動性はGA型の比ではない。
新型汎用試験機
エムズが最終決戦のために投入したとされる新型汎用機の試作・試験型機体。しかし最終決戦ではこのYMR-Zも実戦に投入されていたという。外観は従来のエムズ機体よりもやや大きく、連合軍の大型機よりは小さい。例えるなら当機体は「中型機」と呼べるような全く新しいコンセプトの汎用機であるが、そのスペックは非常に高水準なものであったとされる。
ベース機体は存在せず、あらゆるエムズ機体のデータをフィードバックさせた高性能コンピュータを二つ搭載。これにより本機単体でも様々なミッションに対応可能だ。記録には残っていないが武装デバイスの使用も可能であったとされている。脚部形状がGA型に酷似しているが、こちらは後部に補助ブースターを搭載しており、機動性はGA型の比ではない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
にゃーの脳内 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-