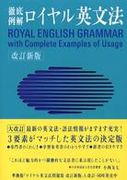はじめまして。予備校で講師をしているものです。先日生徒から出された質問で
He left the door opened.(正答は He left the door open.)
がダメな理由を聞かれたのですが、なんとなく感覚的にダメとか、見たことないよねー。と曖昧な解答しか出せませんでした
一応自分で考えてみたんですが、まずopenは形容詞の用法が多く、次に自動詞、そして他動詞はなんか無理やりなニュアンスを含むよう(he opens the door with a crowber.みたいな)。だから形容詞のopenでOK。
次にleave+O+CのCは状態を表す。一方、過去分詞は動作動詞が形容詞として名詞を修飾する、すなわち限定用法が一般的。be動詞の補語としてなら形容詞化した過去分詞はOK(He left his homework half-finished.みたいな)。openedは形容詞化するほど使われていないし、be動詞の補語ではない。
の2点が理由として考えられたんですが、どうですかね?
ほかに何か文法的な理由で×という説明が出来る方、教えてください。お願いします。
He left the door opened.(正答は He left the door open.)
がダメな理由を聞かれたのですが、なんとなく感覚的にダメとか、見たことないよねー。と曖昧な解答しか出せませんでした
一応自分で考えてみたんですが、まずopenは形容詞の用法が多く、次に自動詞、そして他動詞はなんか無理やりなニュアンスを含むよう(he opens the door with a crowber.みたいな)。だから形容詞のopenでOK。
次にleave+O+CのCは状態を表す。一方、過去分詞は動作動詞が形容詞として名詞を修飾する、すなわち限定用法が一般的。be動詞の補語としてなら形容詞化した過去分詞はOK(He left his homework half-finished.みたいな)。openedは形容詞化するほど使われていないし、be動詞の補語ではない。
の2点が理由として考えられたんですが、どうですかね?
ほかに何か文法的な理由で×という説明が出来る方、教えてください。お願いします。
|
|
|
|
コメント(31)
あびべいびぃ さんの説明は分かりやすいですね。
(^-^)
----------
>Mattさん
>上: 彼はドアを閉めずにその場を去った
この場合のleaveに「去る」という意味はないと思いますよ。
----------
(^_^;)
もし、誤解を与える書き方だったとしたら、お詫びします <(_ _)>
私のコメントを詳細にお読みいただき、その意図を汲み取って下さい。
ここでのleaveが 「去る」 という意味でないことは自明です。放って
おいた、という 「ニュアンス」 を出すために書いただけの話です。
ちなみに、下:〜 には 「去る」 とは書いていません。
私の感じ方↓
上:彼は自分で開けたドアを閉めもせずに、無責任に立ち去った。
下:彼は開いているドアを気にも留めず、そのままにしておいた。
ただし、この解釈が妥当かどうかは、ネイティブに確認します。
たぶん、ネイティブは 「どっちでもいいよ」 と言いそうな気が。
またレポートします。
(^-^)
----------
>Mattさん
>上: 彼はドアを閉めずにその場を去った
この場合のleaveに「去る」という意味はないと思いますよ。
----------
(^_^;)
もし、誤解を与える書き方だったとしたら、お詫びします <(_ _)>
私のコメントを詳細にお読みいただき、その意図を汲み取って下さい。
ここでのleaveが 「去る」 という意味でないことは自明です。放って
おいた、という 「ニュアンス」 を出すために書いただけの話です。
ちなみに、下:〜 には 「去る」 とは書いていません。
私の感じ方↓
上:彼は自分で開けたドアを閉めもせずに、無責任に立ち去った。
下:彼は開いているドアを気にも留めず、そのままにしておいた。
ただし、この解釈が妥当かどうかは、ネイティブに確認します。
たぶん、ネイティブは 「どっちでもいいよ」 と言いそうな気が。
またレポートします。
ちょっと横道に逸れますが、
>8: あびべいびぃさんのおっしゃる
>名詞+過去分詞 という形には O+V という関係があります。
というのは、常に成り立つわけではありません。名詞+過去分詞 の場合であっても、過去分詞の元の動詞が非対格自動詞(unaccusative verb)と呼ばれる自動詞の一種である場合があり、この場合の過去分詞は、完了の意味を表します。したがって O+Vという関係ではありません。例:a dream come true (実現した夢)
非対格自動詞の過去分詞が名詞を修飾している例としては、例えば:
(1) wilted lettuce(しおれたレタス), a fallen leaf(落ち葉),
an escaped convinct(脱走した受刑者), burst pipes(破裂したパイプ),
rotted railings(腐った欄干), sprouted wheat(発芽した小麦),
swollen feet(腫れ上がった脚), a rusted screen(錆びた金網),
vanished civilizations(消滅した文明),
a recently expired passport(最近期限が切れたパスポート),
a failed bank(倒産した銀行), decayed tooth(虫歯),
departed mother(死んだ母), departed guests(立ち去った客たち),
faded flowers(色あせた花), retired official(退職した官吏),
a grown man(成人), the assembled company(集まった人々、仲間),
a deceased presbyterian leader(死んだ長老派教会の指導者),
the falllen and unfortunate king of France,
次に、後置修飾の実例です。いずれも手元のデータベースから検索しました。
(3) "Polemic Gone Astray: A Corrective to Recent Criticism of TOEFL Preparation" TESOL Quarterly Vol.33, No.2, Summer 1999. pp.263-270.
(4) a Pekinese gone wrong
So far as Linus could form any sort of opinion about it at all, it was
that it resembled a Pekinese gone wrong. - (book)
(5) bureaucracy gone mad
It just needed a little discretion.' MP Janner said: 'It was bureaucracy
gone mad.' - (newspaper)
(6) a nature gone awry
'The individual driven, in spite of himself, by the somber madness of
sex' would then, as he wrote in 1976, be 'something like a nature gone
awry. - (book)
(7) things long gone
He does not confine himself to discussing things that still survive,
like the Paris obelisk or the Carlton cinema in Islington; he also
produces archive material on things long gone, the photograph of a villa
in the Pas de Calais built by a painter at the turn of the century, for
example. - (magazine)
(8) the one chance gone
That, as it happened, was the one chance gone. Though the next four games
went with serve, Petchey suddenly cracked when Hlasek found a level of
inspiration that had previously eluded him and broke the British player
to love before serving out. - (newspaper)
(9) domestic breeds gone wild
Most of them, it is true, bear bitter-tasting crab apples, but some have
larger, sweeter fruit, and look like domestic breeds gone wild.
- (newspaper)
(10) the day gone by
By the time he published his autobiography, The Day Gone By, in 1990 he
had 17 books to his name. - (newspaper)
(11) everything gone
What mournful faces, what care-laden brows! Everything gone; the trim
garden, the smiling paddock where the cow and pony grazed, the orchard
where the children played, all given up to the foreign spoiler.
- (newspaper)
(12) a moment recentry gone
Lord Montagu said: 'Looking back to 1952 is like a moment recently gone,
but seeing Beaulieu as it is today I realise how much, yet how little,
has changed.' - (newspaper)
(15) a dream come true
MANCHESTER UNITED: Everyone wants to play for the biggest club in the
world. It's a dream come true.' - (magazine)
(17) an impossibly optimistic dream come true
But for Kristina, 23, it was an impossibly optimistic dream come true.
- (magazine)
(18) a nightmare come true
For the Hutu-dominated government in Rwanda the invasion is a nightmare
come true. - (newspaper)
(19) anything come up
'Curious,' said the Boss. 'You go on back. See if there's anything come
up. - (book)
他の自動詞の例では、arrivedも次のように recentlyのような副詞を補えば
後置修飾で形容詞的に使うことができます。
(20) the train recentry arrived(少し前に着いた列車)
>8: あびべいびぃさんのおっしゃる
>名詞+過去分詞 という形には O+V という関係があります。
というのは、常に成り立つわけではありません。名詞+過去分詞 の場合であっても、過去分詞の元の動詞が非対格自動詞(unaccusative verb)と呼ばれる自動詞の一種である場合があり、この場合の過去分詞は、完了の意味を表します。したがって O+Vという関係ではありません。例:a dream come true (実現した夢)
非対格自動詞の過去分詞が名詞を修飾している例としては、例えば:
(1) wilted lettuce(しおれたレタス), a fallen leaf(落ち葉),
an escaped convinct(脱走した受刑者), burst pipes(破裂したパイプ),
rotted railings(腐った欄干), sprouted wheat(発芽した小麦),
swollen feet(腫れ上がった脚), a rusted screen(錆びた金網),
vanished civilizations(消滅した文明),
a recently expired passport(最近期限が切れたパスポート),
a failed bank(倒産した銀行), decayed tooth(虫歯),
departed mother(死んだ母), departed guests(立ち去った客たち),
faded flowers(色あせた花), retired official(退職した官吏),
a grown man(成人), the assembled company(集まった人々、仲間),
a deceased presbyterian leader(死んだ長老派教会の指導者),
the falllen and unfortunate king of France,
次に、後置修飾の実例です。いずれも手元のデータベースから検索しました。
(3) "Polemic Gone Astray: A Corrective to Recent Criticism of TOEFL Preparation" TESOL Quarterly Vol.33, No.2, Summer 1999. pp.263-270.
(4) a Pekinese gone wrong
So far as Linus could form any sort of opinion about it at all, it was
that it resembled a Pekinese gone wrong. - (book)
(5) bureaucracy gone mad
It just needed a little discretion.' MP Janner said: 'It was bureaucracy
gone mad.' - (newspaper)
(6) a nature gone awry
'The individual driven, in spite of himself, by the somber madness of
sex' would then, as he wrote in 1976, be 'something like a nature gone
awry. - (book)
(7) things long gone
He does not confine himself to discussing things that still survive,
like the Paris obelisk or the Carlton cinema in Islington; he also
produces archive material on things long gone, the photograph of a villa
in the Pas de Calais built by a painter at the turn of the century, for
example. - (magazine)
(8) the one chance gone
That, as it happened, was the one chance gone. Though the next four games
went with serve, Petchey suddenly cracked when Hlasek found a level of
inspiration that had previously eluded him and broke the British player
to love before serving out. - (newspaper)
(9) domestic breeds gone wild
Most of them, it is true, bear bitter-tasting crab apples, but some have
larger, sweeter fruit, and look like domestic breeds gone wild.
- (newspaper)
(10) the day gone by
By the time he published his autobiography, The Day Gone By, in 1990 he
had 17 books to his name. - (newspaper)
(11) everything gone
What mournful faces, what care-laden brows! Everything gone; the trim
garden, the smiling paddock where the cow and pony grazed, the orchard
where the children played, all given up to the foreign spoiler.
- (newspaper)
(12) a moment recentry gone
Lord Montagu said: 'Looking back to 1952 is like a moment recently gone,
but seeing Beaulieu as it is today I realise how much, yet how little,
has changed.' - (newspaper)
(15) a dream come true
MANCHESTER UNITED: Everyone wants to play for the biggest club in the
world. It's a dream come true.' - (magazine)
(17) an impossibly optimistic dream come true
But for Kristina, 23, it was an impossibly optimistic dream come true.
- (magazine)
(18) a nightmare come true
For the Hutu-dominated government in Rwanda the invasion is a nightmare
come true. - (newspaper)
(19) anything come up
'Curious,' said the Boss. 'You go on back. See if there's anything come
up. - (book)
他の自動詞の例では、arrivedも次のように recentlyのような副詞を補えば
後置修飾で形容詞的に使うことができます。
(20) the train recentry arrived(少し前に着いた列車)
私も、やはり「be opened:動作」と「be open:状態」の区分だと考えます。
be closed など「be 過去分詞」で「状態」を表すものはたくさんあると思いますが、
be opened にはそれが当てはまらない(open と住み分けができている)のだと思います。
まあ、あくまで語法上の「本則」であって、実例では「許容」は見られるとは思いますが。
一応、文献上の根拠を挙げておきます。
『Practical English Usage (3rd edition)』§399
We normally use "open," not "opened," as as adjective.
"Opened" is used as the past tense and past participle of the verb "open," to talk about the action of opening.
be closed など「be 過去分詞」で「状態」を表すものはたくさんあると思いますが、
be opened にはそれが当てはまらない(open と住み分けができている)のだと思います。
まあ、あくまで語法上の「本則」であって、実例では「許容」は見られるとは思いますが。
一応、文献上の根拠を挙げておきます。
『Practical English Usage (3rd edition)』§399
We normally use "open," not "opened," as as adjective.
"Opened" is used as the past tense and past participle of the verb "open," to talk about the action of opening.
途中から口を挟むので、
途中の皆様のコメントを全部は熟読していないかもしれません。
従って、重複もあるかもしれませんんで、ご寛容のほどをお願いします。
まずトピ主さんの
He left the door opened.はなぜいけないかのかについては、
「形容詞形があるものは分詞を形容詞として使わない」ということだ思います。
過去分詞ではありませんが、
He is alive.と言って、
「生きている」という意味で He is living.とは言わないです。
これと同じことだと了解しています。
ましてや、語源は知らないですが、openが単体であったら、ほとんどの人が形容詞だと思うでしょうね。動詞は形容詞からの転用だと考えていいと思います。
形容詞なんだけれども、動詞としても使うという単語はそんなに多くはないですね(clear,clean,free...ざっと考えるとこれくらいしか思い浮かばないです)
それから、
He left the door opened by the pretty cat.
これは状況としてありえないと思います。
leaveは「位置的に離れる」という意味ではなく、
to depart from something/somebody which is supposed to be togetherとか、
to depart from something which is supposed to be under one's controlとか、to depart from somewhere one is supposed to beという意味だと了解しています。
ですから、SVOCで使われた場合に「そのままにして離れる」という意味が出てくる。keep O+C との違いは重要です。(keepだと意思的にその状態を保つ)
更に、21Megumiさんの掲げられた文:
When I got downstairs, knowing that I had left the door open,
to my surprise it was shut and no one was in the house!
Now, I decided to go to my friends house cause now I was scared
but I had to wait for my laundry to dry.
So, I again, left the door opened and went back upstairs.
たいへん不躾ですが、第1文の構成、カンマの不備、
第2文でのnowの重複、アロストロフィの落ち、
第3文のカンマとagainの位置を考えると、決して模範にするに足る英文とは思えないです。
この英文としての不備は別にしても、
第1文と第2文で、冗長といえるほどに事細かに描写しているにも関わらず、
第3文で、「戸を開けた」という行為そのものをなぜ語らないのかが理解できないです。
以上の理由で、
So, I again, left the door opened and went back upstairs.
この文は、 So,I opened the door again and went back upstairs.で簡単に表せる内容だと思います。
途中の皆様のコメントを全部は熟読していないかもしれません。
従って、重複もあるかもしれませんんで、ご寛容のほどをお願いします。
まずトピ主さんの
He left the door opened.はなぜいけないかのかについては、
「形容詞形があるものは分詞を形容詞として使わない」ということだ思います。
過去分詞ではありませんが、
He is alive.と言って、
「生きている」という意味で He is living.とは言わないです。
これと同じことだと了解しています。
ましてや、語源は知らないですが、openが単体であったら、ほとんどの人が形容詞だと思うでしょうね。動詞は形容詞からの転用だと考えていいと思います。
形容詞なんだけれども、動詞としても使うという単語はそんなに多くはないですね(clear,clean,free...ざっと考えるとこれくらいしか思い浮かばないです)
それから、
He left the door opened by the pretty cat.
これは状況としてありえないと思います。
leaveは「位置的に離れる」という意味ではなく、
to depart from something/somebody which is supposed to be togetherとか、
to depart from something which is supposed to be under one's controlとか、to depart from somewhere one is supposed to beという意味だと了解しています。
ですから、SVOCで使われた場合に「そのままにして離れる」という意味が出てくる。keep O+C との違いは重要です。(keepだと意思的にその状態を保つ)
更に、21Megumiさんの掲げられた文:
When I got downstairs, knowing that I had left the door open,
to my surprise it was shut and no one was in the house!
Now, I decided to go to my friends house cause now I was scared
but I had to wait for my laundry to dry.
So, I again, left the door opened and went back upstairs.
たいへん不躾ですが、第1文の構成、カンマの不備、
第2文でのnowの重複、アロストロフィの落ち、
第3文のカンマとagainの位置を考えると、決して模範にするに足る英文とは思えないです。
この英文としての不備は別にしても、
第1文と第2文で、冗長といえるほどに事細かに描写しているにも関わらず、
第3文で、「戸を開けた」という行為そのものをなぜ語らないのかが理解できないです。
以上の理由で、
So, I again, left the door opened and went back upstairs.
この文は、 So,I opened the door again and went back upstairs.で簡単に表せる内容だと思います。
>Megumiさん
私の書き方がまずかったかな?
私も基本的にはMegumiさんと同じ意見だと思っています。
現実には誤用法とされるものが頻繁に出てくるのが言語活動ですし、
柔軟さを養うためばかりでなく、
誤用なのになぜ通じるのか?と追求することで、規範のより深い理解ができると思っています。
しかし、正用法と誤用法を一緒に学んでいると、効率が悪いんです。
規範に基づいた正用法をしっかり学んだ上で、誤用法も理解できる力、
更にMegumiさんのように誤用法が出てしまった話者の心情と状況が理解できると思っています。
とにかく、白々しいほどに「正しい」用法をまず学び、
正用法と誤用法の区別できる力を養った上で、
誤用法に触れていくことが大切だと思っています。
少なくても外国語として
日常使用はない場所で習うには、
悲しいかな、どうしても必要なことだと思っています。
従って、あえて、
これは模範にするに足る用法とは思えないと申し上げました。
あしからず
私の書き方がまずかったかな?
私も基本的にはMegumiさんと同じ意見だと思っています。
現実には誤用法とされるものが頻繁に出てくるのが言語活動ですし、
柔軟さを養うためばかりでなく、
誤用なのになぜ通じるのか?と追求することで、規範のより深い理解ができると思っています。
しかし、正用法と誤用法を一緒に学んでいると、効率が悪いんです。
規範に基づいた正用法をしっかり学んだ上で、誤用法も理解できる力、
更にMegumiさんのように誤用法が出てしまった話者の心情と状況が理解できると思っています。
とにかく、白々しいほどに「正しい」用法をまず学び、
正用法と誤用法の区別できる力を養った上で、
誤用法に触れていくことが大切だと思っています。
少なくても外国語として
日常使用はない場所で習うには、
悲しいかな、どうしても必要なことだと思っています。
従って、あえて、
これは模範にするに足る用法とは思えないと申し上げました。
あしからず
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英文法は英語の基礎だ!! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
英文法は英語の基礎だ!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90040人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6421人
- 3位
- 独り言
- 9045人