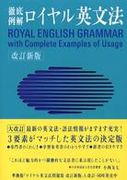ふと疑問に感じたことがありましたので、皆様の語感を貸して頂ければ幸いです。
I was surprised by the idea that the students should walk to school.
私の意見では、ここで用いられているshouldから二つの意味を読み取ることができるのではないか、というものです。
1)義務のshould(仮定法現在との代用が可能であるshould)
2)感情のshould(仮定法現在との代用が不可能であるshould)
というのも、1)の解釈で文を見ると、例えば、生徒の健康を考慮した学校の方針などによって、徒歩通学が義務付けされている考え、に対して、話者が「素直に」驚きを示しているように思われます。つまり、従属節のshouldは、それを修飾している名詞the ideaから派生したものであると解釈できるように思われます。
一方、2)の解釈で文を見ると、従属節内のshouldは名詞the ideaからではなく、話者の感情から派生したものだと見ることができるように思われます。よって、この場合、必ずしも校則など「義務」に関する驚きではなく、例えば、「(せっかくバスという交通手段が存在するのに)生徒が徒歩で学校へ行くなんてことは、馬鹿馬鹿しい」といったように、the ideaに対して話者自身が見下したような、文章であるようにも思われるのです。
よって、イメージとして捕らえた日本語訳は以下のようになるのではないかと。
1)生徒が学校まで徒歩で通学すべきだという考えには(素直に)驚いたよ。
2)生徒が学校まで徒歩でいくなんて(ばかばかしい)考えには驚いたね。
shouldについて考えているとこのような疑念が湧いてきました。考えすぎでしょうか。。(苦笑)
よろしくお願いします。
I was surprised by the idea that the students should walk to school.
私の意見では、ここで用いられているshouldから二つの意味を読み取ることができるのではないか、というものです。
1)義務のshould(仮定法現在との代用が可能であるshould)
2)感情のshould(仮定法現在との代用が不可能であるshould)
というのも、1)の解釈で文を見ると、例えば、生徒の健康を考慮した学校の方針などによって、徒歩通学が義務付けされている考え、に対して、話者が「素直に」驚きを示しているように思われます。つまり、従属節のshouldは、それを修飾している名詞the ideaから派生したものであると解釈できるように思われます。
一方、2)の解釈で文を見ると、従属節内のshouldは名詞the ideaからではなく、話者の感情から派生したものだと見ることができるように思われます。よって、この場合、必ずしも校則など「義務」に関する驚きではなく、例えば、「(せっかくバスという交通手段が存在するのに)生徒が徒歩で学校へ行くなんてことは、馬鹿馬鹿しい」といったように、the ideaに対して話者自身が見下したような、文章であるようにも思われるのです。
よって、イメージとして捕らえた日本語訳は以下のようになるのではないかと。
1)生徒が学校まで徒歩で通学すべきだという考えには(素直に)驚いたよ。
2)生徒が学校まで徒歩でいくなんて(ばかばかしい)考えには驚いたね。
shouldについて考えているとこのような疑念が湧いてきました。考えすぎでしょうか。。(苦笑)
よろしくお願いします。
|
|
|
|
コメント(7)
古都のハムさん、こんにちは。
文法の話題ですが、文法は苦手ですので 、文脈から考えました。
、文脈から考えました。
例えば以下のような校則を目にしたとします。
Wear uniforms to school
No smoking in class
Bring your own lunch
Walk to school
3番目までは納得できても、4番目に納得できない人(徒歩30分かかる)は、
I was surprised by the idea that the students should walk to school.
と言うでしょうね。言外に「憤慨」が見えますね。
それとIdea とshould は相性がいい単語ですね。
idea that 〜 should ...
文法の話題ですが、文法は苦手ですので
例えば以下のような校則を目にしたとします。
Wear uniforms to school
No smoking in class
Bring your own lunch
Walk to school
3番目までは納得できても、4番目に納得できない人(徒歩30分かかる)は、
I was surprised by the idea that the students should walk to school.
と言うでしょうね。言外に「憤慨」が見えますね。
それとIdea とshould は相性がいい単語ですね。
idea that 〜 should ...
>なおきさん
なるほど。やはり、2)の意味で理解するのは無理がありそうですか。
ということは、名詞the ideaは、requirement, recommendation, insistenceなどと同等の概念と受け取り、従属節内でshouldが用いられる限り、その名詞をまたいで話者の心理は絡まないということと理解していいということですね。さらに詳しく調べてみたいと思います。
ありがとうございます。
>ひびりんさん
見解を提示していただきありがとうございます。
ただ、僕のここでのポイントは、2)の解釈をさらに1)から遠ざけるために、2)の解釈では「義務」の全く絡まない「感情」のshould(〜なんて)というのを話者に委ねようとしたものですから、必ずしも「校則」に驚いたのではなく、「生徒らの徒歩通学」という「事柄」自体に驚いた、という感覚で解釈例を提示してみました。
よって、the studentsをheに変えれば、動詞の屈折変化で、意味の違いが明確となるかもしれないと考えました。ただ、1)の文は容認度が低そうですが。
1) I was surprised by the idea that he walk to school.
2) I was surprised by the idea that he should walk to school.
そう考えてみるとどうでしょう、ということですが、どうでしょう。。
なるほど。やはり、2)の意味で理解するのは無理がありそうですか。
ということは、名詞the ideaは、requirement, recommendation, insistenceなどと同等の概念と受け取り、従属節内でshouldが用いられる限り、その名詞をまたいで話者の心理は絡まないということと理解していいということですね。さらに詳しく調べてみたいと思います。
ありがとうございます。
>ひびりんさん
見解を提示していただきありがとうございます。
ただ、僕のここでのポイントは、2)の解釈をさらに1)から遠ざけるために、2)の解釈では「義務」の全く絡まない「感情」のshould(〜なんて)というのを話者に委ねようとしたものですから、必ずしも「校則」に驚いたのではなく、「生徒らの徒歩通学」という「事柄」自体に驚いた、という感覚で解釈例を提示してみました。
よって、the studentsをheに変えれば、動詞の屈折変化で、意味の違いが明確となるかもしれないと考えました。ただ、1)の文は容認度が低そうですが。
1) I was surprised by the idea that he walk to school.
2) I was surprised by the idea that he should walk to school.
そう考えてみるとどうでしょう、ということですが、どうでしょう。。
今回の件について小一時間唸ってますが、1.shouldの主体は何か2.例文は皮肉・批判的なコノテーションを持ちうるか、という二点について考えるトピと解釈しましたが、よろしいでしょうか?
1.souldの主体は何か
「should」の意味はもともと「当然そうなる」という確信(信条)めいた解釈ですよね。例文でこの解釈をしている「主体」は誰なのかというとthe idea(またはその考えを公示した人物)しか考えられません。もし主体がthe idea以外のものだと仮定すると、shouldは確かに話者が引き受けることになります。が、ついでにshould以下も引き受けてしまうわけですから、今回の例文では特に主節が受動態になっているのでさらにこんがらがって、the ideaを主張すると同時にその被害者になるという妙な関係になってしまうと思います。「(話者としての)私は徒歩通学が当然と思っているが、(主語としての)私はなぜかその考えに驚きも感じている」です。
以上の逆論を踏まえ、僕は例文の意味するところはThe idea(or the school master) insists that students should walk to school.という事実(校長か誰かがそういう信条を持っているという事実)に「素直に驚いた[トピ1の解釈]」と読むしかないと思います。
2.例文が皮肉・批判的なコノテーションを持ちうるか
で、普通はコメント1で述べたように読むはずですが、皮肉のニュアンスが含まれるかどうか。確信はありませんが、僕はこれもアヤシイと思います。話が文法から逸れますが、皮肉というのは「皮肉かそうでないかがあいまいであればあるほど、それは皮肉ではないほうに解釈される」という危険がありますよね。話者が皮肉めいた感情を表に出したいとき、普通に解釈されかねない文を好んで使うでしょうか?もっと強烈な言葉を選んで、いかにthe ideaがハチャメチャで押し付けてきなものかを表すのに例えばshouldでもhave toでもなくmustを使い、「何がなんでも歩きなサーイ!」と命令するおかしさを含めたり、あえてshallを使い生徒たちに歩くことを脅迫するような言い方をするのではないでしょうか。
まあ発話の仕方によっても違うでしょうが、実際のところ文法的にはコノテーションがあるかどうかを判別しかねましたので恣意的で偏屈なコメントになってしまいました。とりあえず、文法の読まれやすさ、他の言い回しの可能性等から考えて皮肉ととるのはためらわれます。
1.souldの主体は何か
「should」の意味はもともと「当然そうなる」という確信(信条)めいた解釈ですよね。例文でこの解釈をしている「主体」は誰なのかというとthe idea(またはその考えを公示した人物)しか考えられません。もし主体がthe idea以外のものだと仮定すると、shouldは確かに話者が引き受けることになります。が、ついでにshould以下も引き受けてしまうわけですから、今回の例文では特に主節が受動態になっているのでさらにこんがらがって、the ideaを主張すると同時にその被害者になるという妙な関係になってしまうと思います。「(話者としての)私は徒歩通学が当然と思っているが、(主語としての)私はなぜかその考えに驚きも感じている」です。
以上の逆論を踏まえ、僕は例文の意味するところはThe idea(or the school master) insists that students should walk to school.という事実(校長か誰かがそういう信条を持っているという事実)に「素直に驚いた[トピ1の解釈]」と読むしかないと思います。
2.例文が皮肉・批判的なコノテーションを持ちうるか
で、普通はコメント1で述べたように読むはずですが、皮肉のニュアンスが含まれるかどうか。確信はありませんが、僕はこれもアヤシイと思います。話が文法から逸れますが、皮肉というのは「皮肉かそうでないかがあいまいであればあるほど、それは皮肉ではないほうに解釈される」という危険がありますよね。話者が皮肉めいた感情を表に出したいとき、普通に解釈されかねない文を好んで使うでしょうか?もっと強烈な言葉を選んで、いかにthe ideaがハチャメチャで押し付けてきなものかを表すのに例えばshouldでもhave toでもなくmustを使い、「何がなんでも歩きなサーイ!」と命令するおかしさを含めたり、あえてshallを使い生徒たちに歩くことを脅迫するような言い方をするのではないでしょうか。
まあ発話の仕方によっても違うでしょうが、実際のところ文法的にはコノテーションがあるかどうかを判別しかねましたので恣意的で偏屈なコメントになってしまいました。とりあえず、文法の読まれやすさ、他の言い回しの可能性等から考えて皮肉ととるのはためらわれます。
>コーヅさん
丁寧にお考えをまとめていただきありがとうございます。コーヅさんが見解を提示していただいたことによって、さらに自分自身の不明な点が明確になった気がします。大変参考になりました。
なるほど。ということは、epistemicな名詞(idea, thought, notionなど)を修飾する同格that節内でのshouldを用いる際、その働きはその名詞そのものの派生が優先されてしまうのでは、というお考えだということですね。
仰られるように、よくよく考えてみると、epistemicな名詞を文内に用いる限り、誰かしらの「心情」というものが付きまとうという最低条件が存在するわけですから、1)の解釈、つまり、名詞句the ideaのみからshouldが派生している、ということで命題の文を見ることが自然ですよね。
この見解から、今回のように同格that節を導く名詞に、感情のshouldを用いることは不可能ではないかと考えたのですが、以下のケースでは、名詞が概念的なものでないため(the fact)十分可能性としてはあるのではないかと。
I was surprised by the fact that Mary should be the one who loves John!
(=It is ridiculous that Mary should be the one who loves John!)
従って、上記の文では意味解釈における曖昧性は、evidentialな名詞、the fact(事実)となったため、この名詞句の同格that節内のshouldは話者から派生したものと捕らえることができるのではないかと考えました。
名詞をまたいだshouldが話者から派生し得るかどうかの考察は今後調べてみたいと思います。また、これに関するevidential supportをお持ちの方がおられましたら是非共有していただければ幸いです。
丁寧にお考えをまとめていただきありがとうございます。コーヅさんが見解を提示していただいたことによって、さらに自分自身の不明な点が明確になった気がします。大変参考になりました。
なるほど。ということは、epistemicな名詞(idea, thought, notionなど)を修飾する同格that節内でのshouldを用いる際、その働きはその名詞そのものの派生が優先されてしまうのでは、というお考えだということですね。
仰られるように、よくよく考えてみると、epistemicな名詞を文内に用いる限り、誰かしらの「心情」というものが付きまとうという最低条件が存在するわけですから、1)の解釈、つまり、名詞句the ideaのみからshouldが派生している、ということで命題の文を見ることが自然ですよね。
この見解から、今回のように同格that節を導く名詞に、感情のshouldを用いることは不可能ではないかと考えたのですが、以下のケースでは、名詞が概念的なものでないため(the fact)十分可能性としてはあるのではないかと。
I was surprised by the fact that Mary should be the one who loves John!
(=It is ridiculous that Mary should be the one who loves John!)
従って、上記の文では意味解釈における曖昧性は、evidentialな名詞、the fact(事実)となったため、この名詞句の同格that節内のshouldは話者から派生したものと捕らえることができるのではないかと考えました。
名詞をまたいだshouldが話者から派生し得るかどうかの考察は今後調べてみたいと思います。また、これに関するevidential supportをお持ちの方がおられましたら是非共有していただければ幸いです。
the ideaをthe factに変えると話はより単純で、
1. I am surprised by the fact that students should walk to school.
(徒歩通学が当然だなんて驚きだ)
2. I am surprised by the fact that students walk to school.
(徒歩通学していることに[単純に]驚いた)
となるのではないかと思います。the ideaという語を使ったときに僕が考慮したのは「実行されたthe ideaか、ただ意見として述べられたものか」という点で、単純にshouldを取り去ることができなかったわけです。だからshould自体を他の語にかえてしまいました。
で、今回の例をよく考えてみると「感情のshould」というものの主体も、やはり例外なく「the factを当然だと思っている人」だと読めてしまいます。「当然だと思っている人が多い中、自分はこの件について驚いている」という意味でここにshouldをおきます。
こういうわけで、コメント5は感情のshouldという観点で(ただし主体はIではなく)読むことができましょうが、トピ1のthe ideaを用いた場合には感情云々よりも「そうするべきであって、実際に行われたかが不明」であるという点を考慮するのが優先されるのではないかと思います。
と、ここで質問なのですが、古都のハムさんの「話者から派生する」という言葉を誤解しているかもしれませんので、どういう状況が「話者から派生する」に当てはまるのか教えてください。どうも僕が使っている「主体」とは違う意味のような気がしてきました。
ちなみに感情のshouldをはじめて提唱したのはJespersen(1933a)だそうです。あいにく、今の僕には手に入れようがありませんが。
1. I am surprised by the fact that students should walk to school.
(徒歩通学が当然だなんて驚きだ)
2. I am surprised by the fact that students walk to school.
(徒歩通学していることに[単純に]驚いた)
となるのではないかと思います。the ideaという語を使ったときに僕が考慮したのは「実行されたthe ideaか、ただ意見として述べられたものか」という点で、単純にshouldを取り去ることができなかったわけです。だからshould自体を他の語にかえてしまいました。
で、今回の例をよく考えてみると「感情のshould」というものの主体も、やはり例外なく「the factを当然だと思っている人」だと読めてしまいます。「当然だと思っている人が多い中、自分はこの件について驚いている」という意味でここにshouldをおきます。
こういうわけで、コメント5は感情のshouldという観点で(ただし主体はIではなく)読むことができましょうが、トピ1のthe ideaを用いた場合には感情云々よりも「そうするべきであって、実際に行われたかが不明」であるという点を考慮するのが優先されるのではないかと思います。
と、ここで質問なのですが、古都のハムさんの「話者から派生する」という言葉を誤解しているかもしれませんので、どういう状況が「話者から派生する」に当てはまるのか教えてください。どうも僕が使っている「主体」とは違う意味のような気がしてきました。
ちなみに感情のshouldをはじめて提唱したのはJespersen(1933a)だそうです。あいにく、今の僕には手に入れようがありませんが。
コーヅさんの見地と僕の見地は、すでに一致していると思われますが、もう一度、今回命題となったshouldに関する概念を以下の二つに訂正することで、今回の自身の議論を明確にしたいと思います。
1) 命令的should (mandative "should")
a) 提案・勧告・要求・命令などの概念を表す主文の従属節に現れる
b) 仮定法現在と代用可能
2) 評価的should (evaluative "should")
a) 通例、shouldを省いて仮定法現在との代用不可能
*It is surprising that she object to his opinion.
まず、ideaという語について注意しなければならなかった点は、ideaは「観念」を表すepistemicな名詞であるため、それを修飾する同格that節内には「事実性」と関連する「時制」が絡むことが無いということでした。この点で、ひびりんさんとコーヅさんご指摘の通り、既に、2)の解釈の妥当性の低さを示唆しているように思われます。
結局、以下のような点"のみ"でしか、命題となった文章は見られないのではないか、と。
I was surprised by (somebody's) idea (equivalent of "insistence, recommendation, suggestion, etc") that students SHOULD walk to school.
従属節内の事実性に関してですが、前述の通り、名詞ideaがepistemicであるため、従属節内の事柄の事実性(evidentiality)が全く無いと思われます。たとえ主節の動詞が過去形(was surprised)であれ、the ideaは「命令性」、すなわち、「今後の未来に"あるべき"状況」を示唆する名詞であるためです。むしろ、「観念」の問題である故、事実性有無の議論の余地は無いようにも思われます。
よって、従属節内の「事実性」のパラメターは、1)の解釈で上の文を見ると、「命令的」な概念がshouldに絡んでいる、つまり、それが未来性を示唆している点で、評価的shouldに比べて、随分低いように思われます。このような点で、1)のshouldは、仮定法現在との代用が可能である事実を含意しているようにも思われます。
この点で、1)の解釈において、命令的shouldがthe ideaつまり、「第三者(somebody)の概念」を前提に派生した、と言及しています。換言すれば、「話者」が事柄を評価(evaluate)したevaluative "should"ではない、と言えます。
一方、shouldを2)の解釈に委ねると、コーヅさんご指摘のように、第三者のthe ideaから派生した「命令的should」と話者自身の従属節内の事柄(=「生徒が徒歩通学する」こと)に対する「評価」が絡むshouldがオーバーラップしてしまうため、epistemicな名詞が用いられている限り、1)の命令的shouldとして文を捕らえる方が随分妥当性が高い、と感じました。
さて、ご質問の「話者から派生する」という言葉ですが、評価的shouldが、第三者ではなく、「話者(主語"I")」の心的態度をダイレクトに反映している、という意味で用いました。そういうわけで、コーヅさんの言及されている「主体」と同じ意味だと推測しますが、どうでしょう。
何か、同じことを繰り返して言っている気がしますが、混乱させてしまっていたらごめんなさい。
1) 命令的should (mandative "should")
a) 提案・勧告・要求・命令などの概念を表す主文の従属節に現れる
b) 仮定法現在と代用可能
2) 評価的should (evaluative "should")
a) 通例、shouldを省いて仮定法現在との代用不可能
*It is surprising that she object to his opinion.
まず、ideaという語について注意しなければならなかった点は、ideaは「観念」を表すepistemicな名詞であるため、それを修飾する同格that節内には「事実性」と関連する「時制」が絡むことが無いということでした。この点で、ひびりんさんとコーヅさんご指摘の通り、既に、2)の解釈の妥当性の低さを示唆しているように思われます。
結局、以下のような点"のみ"でしか、命題となった文章は見られないのではないか、と。
I was surprised by (somebody's) idea (equivalent of "insistence, recommendation, suggestion, etc") that students SHOULD walk to school.
従属節内の事実性に関してですが、前述の通り、名詞ideaがepistemicであるため、従属節内の事柄の事実性(evidentiality)が全く無いと思われます。たとえ主節の動詞が過去形(was surprised)であれ、the ideaは「命令性」、すなわち、「今後の未来に"あるべき"状況」を示唆する名詞であるためです。むしろ、「観念」の問題である故、事実性有無の議論の余地は無いようにも思われます。
よって、従属節内の「事実性」のパラメターは、1)の解釈で上の文を見ると、「命令的」な概念がshouldに絡んでいる、つまり、それが未来性を示唆している点で、評価的shouldに比べて、随分低いように思われます。このような点で、1)のshouldは、仮定法現在との代用が可能である事実を含意しているようにも思われます。
この点で、1)の解釈において、命令的shouldがthe ideaつまり、「第三者(somebody)の概念」を前提に派生した、と言及しています。換言すれば、「話者」が事柄を評価(evaluate)したevaluative "should"ではない、と言えます。
一方、shouldを2)の解釈に委ねると、コーヅさんご指摘のように、第三者のthe ideaから派生した「命令的should」と話者自身の従属節内の事柄(=「生徒が徒歩通学する」こと)に対する「評価」が絡むshouldがオーバーラップしてしまうため、epistemicな名詞が用いられている限り、1)の命令的shouldとして文を捕らえる方が随分妥当性が高い、と感じました。
さて、ご質問の「話者から派生する」という言葉ですが、評価的shouldが、第三者ではなく、「話者(主語"I")」の心的態度をダイレクトに反映している、という意味で用いました。そういうわけで、コーヅさんの言及されている「主体」と同じ意味だと推測しますが、どうでしょう。
何か、同じことを繰り返して言っている気がしますが、混乱させてしまっていたらごめんなさい。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
英文法は英語の基礎だ!! 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
英文法は英語の基礎だ!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人