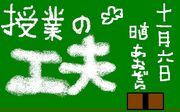|
|
|
|
コメント(10)
T‐macさんへ
T‐macさん自身は、この「音」の単元において子どもたちがどんなことを理解できればいいなと考えておられますか? あるいはどんな「気づき」どんな「発見」どんな「感動」があるといいと考えておられますか?
少し厳しいことを言うようで心苦しいのですが、そういった想定なしに、ただ単に「導入」だけを面白いものにしようとすると、子どもたちがその導入部の「音とは関係のあまりない部分」に注意が向いてしまう危険性を見落としてしまわないか、という点が心配です。
他の方から様々なアイデアを借りることは、それ自体はいいことだと思います。またアイデアが広がる可能性もあると思います。
しかし、それをそのまま使ったのでは「借り物」のままになってしまう危険性があることは注意して下さい。
自分なりに「その導入を使うとどんな効果が出るか?」ということと「どんな(好ましくない)副作用がありえるか?」といった点はよくよく検討して使っていただきたいと思います。
導入部とは言え、それもまた「授業全体の1構成要素」ですので、「導入部」から「今日のまとめ」までの全ストーリーの中での整合性があるのとないのとでは、全く同じ導入部を使ってもその効果は大きな差が出ます。
例えば授業の最後の「今日のまとめ」で、導入部に使ったエピソードと結びつけた形のまとめができるのかできないのかでは、生徒の理解度は大きく違うでしょう。
私自身は理科の先生ではありませんが、例えば次のようなオープニングとエンディングを使った構成は好んで使います。
オープニングA: ひとつ実験をするのでみんな注目して下さい。はい。
これをこうすると、どうなると思いますか?
「結果がAになる」と思う人は手を挙げて下さい。
「結果がBになる」と思う人は手を挙げて下さい。
ではやりますよ......はい! どうなった!?
不思議ですねぇ〜!
今日は、なぜこんなことになるのかを授業でやっていきたいと思います。
エンディングA: ...というわけで、今日の最初にやった実験のようなことが起こるわけ
です。
もう1回やって見せましょうか....はい!この通り。
どうして、こうなるのか、もう皆さんわかりましたね。
オープニングB: ひとつ実験をするのでみんな注目して下さい。はい。
これをこうすると、どうなると思いますか?
皆さん、知っていますよね。はい。皆さんが知っている通りの結果になります。
しかし、なぜそうなるのか説明できる人はいますか?
はい。知っている人もいるようですが(笑)、バラすと今日の授業が面白くなく
なりますので、知っている人も黙っていて下さい(笑)。
知らない人には、今日の授業は面白い授業だと思います。
今日は、この謎を解いていくことにします!
エンディングB: ...というわけで、今日の最初にやった実験のようなことが起こるわけ
です。
もう1回やって見せましょうか....はい!この通り。
どうして、こうなるのか、もう皆さんわかりましたね。
(エンディングは同じでした。笑)
私がよく参考にしているのは、NHK教育テレビの様々な番組です。「ためしてガッテン!」をはじめとして、導入部で「へぇ〜!」と思わせておいて...という展開はよく使われています。
理科屋ではありませんが、参考にしていただければ幸いです。
T‐macさん自身は、この「音」の単元において子どもたちがどんなことを理解できればいいなと考えておられますか? あるいはどんな「気づき」どんな「発見」どんな「感動」があるといいと考えておられますか?
少し厳しいことを言うようで心苦しいのですが、そういった想定なしに、ただ単に「導入」だけを面白いものにしようとすると、子どもたちがその導入部の「音とは関係のあまりない部分」に注意が向いてしまう危険性を見落としてしまわないか、という点が心配です。
他の方から様々なアイデアを借りることは、それ自体はいいことだと思います。またアイデアが広がる可能性もあると思います。
しかし、それをそのまま使ったのでは「借り物」のままになってしまう危険性があることは注意して下さい。
自分なりに「その導入を使うとどんな効果が出るか?」ということと「どんな(好ましくない)副作用がありえるか?」といった点はよくよく検討して使っていただきたいと思います。
導入部とは言え、それもまた「授業全体の1構成要素」ですので、「導入部」から「今日のまとめ」までの全ストーリーの中での整合性があるのとないのとでは、全く同じ導入部を使ってもその効果は大きな差が出ます。
例えば授業の最後の「今日のまとめ」で、導入部に使ったエピソードと結びつけた形のまとめができるのかできないのかでは、生徒の理解度は大きく違うでしょう。
私自身は理科の先生ではありませんが、例えば次のようなオープニングとエンディングを使った構成は好んで使います。
オープニングA: ひとつ実験をするのでみんな注目して下さい。はい。
これをこうすると、どうなると思いますか?
「結果がAになる」と思う人は手を挙げて下さい。
「結果がBになる」と思う人は手を挙げて下さい。
ではやりますよ......はい! どうなった!?
不思議ですねぇ〜!
今日は、なぜこんなことになるのかを授業でやっていきたいと思います。
エンディングA: ...というわけで、今日の最初にやった実験のようなことが起こるわけ
です。
もう1回やって見せましょうか....はい!この通り。
どうして、こうなるのか、もう皆さんわかりましたね。
オープニングB: ひとつ実験をするのでみんな注目して下さい。はい。
これをこうすると、どうなると思いますか?
皆さん、知っていますよね。はい。皆さんが知っている通りの結果になります。
しかし、なぜそうなるのか説明できる人はいますか?
はい。知っている人もいるようですが(笑)、バラすと今日の授業が面白くなく
なりますので、知っている人も黙っていて下さい(笑)。
知らない人には、今日の授業は面白い授業だと思います。
今日は、この謎を解いていくことにします!
エンディングB: ...というわけで、今日の最初にやった実験のようなことが起こるわけ
です。
もう1回やって見せましょうか....はい!この通り。
どうして、こうなるのか、もう皆さんわかりましたね。
(エンディングは同じでした。笑)
私がよく参考にしているのは、NHK教育テレビの様々な番組です。「ためしてガッテン!」をはじめとして、導入部で「へぇ〜!」と思わせておいて...という展開はよく使われています。
理科屋ではありませんが、参考にしていただければ幸いです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
授業の工夫事典!!(塾講師・教師) 更新情報
授業の工夫事典!!(塾講師・教師)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75480人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6457人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208290人