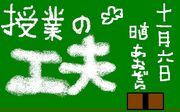はじめまして。塾で講師をしているものです。よろしくお願いします。
中三の公民の三権分立のところの教え方についてですが、
よくある三角形の三権分立の図のところが、
自分は、国会内閣裁判所を一気に書いて説明するのではなく、
 まず中心に主権者である国民を書き、国民のメインの政治参加である選挙によって、初めて国会が出来る。
まず中心に主権者である国民を書き、国民のメインの政治参加である選挙によって、初めて国会が出来る。
 そして、リーダーがいたほうが便利だから、国会の中で最も人気のある人が内閣総理大臣に指名される(=信用されて任されるから信任)
そして、リーダーがいたほうが便利だから、国会の中で最も人気のある人が内閣総理大臣に指名される(=信用されて任されるから信任)
 そして内閣総理大臣が国務大臣を指名し、初めて内閣が生まれる。
そして内閣総理大臣が国務大臣を指名し、初めて内閣が生まれる。
 内閣の行政に対して国民の人気(世論)が大事で、もし人気が無かったら、それを受けて、国会は内閣不信任決議を出せる。
内閣の行政に対して国民の人気(世論)が大事で、もし人気が無かったら、それを受けて、国会は内閣不信任決議を出せる。
 これが出されたら内閣は総辞職か、国会に対して衆議院の解散を出来る。ここで議院内閣制を出す。
これが出されたら内閣は総辞職か、国会に対して衆議院の解散を出来る。ここで議院内閣制を出す。
 内閣は最高裁判所長官を指名する。ここで初めて裁判所を書く。
内閣は最高裁判所長官を指名する。ここで初めて裁判所を書く。
 裁判所所は、国会内閣が憲法に合ったことをしているかどうかを調べることが出来る(ここで違憲審査制をだす)
裁判所所は、国会内閣が憲法に合ったことをしているかどうかを調べることが出来る(ここで違憲審査制をだす)
また最高裁判所は憲法を守っているから憲法の番人といわれている事を説明する。
 裁判所に対して国民は国民審査をして、また、国会は不正があった裁判官に対し弾劾裁判をすることができる。
裁判所に対して国民は国民審査をして、また、国会は不正があった裁判官に対し弾劾裁判をすることができる。
 これを三権分立という。そして、なぜこの形を取っているのか(ナチスヒトラーの独裁者を出してもし全部が一つになっていたらどうなるか掛け合いで考えさせる)
これを三権分立という。そして、なぜこの形を取っているのか(ナチスヒトラーの独裁者を出してもし全部が一つになっていたらどうなるか掛け合いで考えさせる)
このような流れでやったのですが、みなさんはどうされます?
自分の教え方について批判批評お願いします。アドバイスなんかありましたらさいわいです。
ちなみに生徒の反応は上々でわかりやすいと言われました。よろしくお願いします。
中三の公民の三権分立のところの教え方についてですが、
よくある三角形の三権分立の図のところが、
自分は、国会内閣裁判所を一気に書いて説明するのではなく、
また最高裁判所は憲法を守っているから憲法の番人といわれている事を説明する。
このような流れでやったのですが、みなさんはどうされます?
自分の教え方について批判批評お願いします。アドバイスなんかありましたらさいわいです。
ちなみに生徒の反応は上々でわかりやすいと言われました。よろしくお願いします。
|
|
|
|
コメント(23)
ナチスの話は=独裁者といったら誰か?(ときたらヒトラーと返ってきたので。)
ここでは書きませんでしたが、ナチスの話以外で
王が殺人を犯したら、その人を死刑にするという法律を作った。
王は裁判をすることができた。
ある日、王が自分が殺人をしてしまった。
さて、王は自分のことを裁判するが、死刑にするでしょうか?
この内容で実際の授業では生徒に考えさせました。
絶対王政と絡めた方が、
歴史公民間のつながりもでき、
理解が深まってよいと思いますよ。 まさしくその通りですね!!
違憲立法審査制は、違憲審査制と書いて正解になるので、裁判所は、国会内閣がやっていることが、それぞれ憲法にあっているかどうか(合憲か違憲か)を調べることができると説明しました。
違憲立法審査制は立法という語句があるので、国会に対して、国会が制定した法律が合憲か違憲かを調査できるということを説明しました。
自分の上のトピには、違憲審査制と書いておりますよ。
憲法の番人と呼ばれているのは、生徒には、国会内閣がやっていることが憲法に違反していないかどうかを調査できるからだよと説明しました。どこかおかしいでしょうか?
もしよろしかったら教えてください。
ここでは書きませんでしたが、ナチスの話以外で
王が殺人を犯したら、その人を死刑にするという法律を作った。
王は裁判をすることができた。
ある日、王が自分が殺人をしてしまった。
さて、王は自分のことを裁判するが、死刑にするでしょうか?
この内容で実際の授業では生徒に考えさせました。
絶対王政と絡めた方が、
歴史公民間のつながりもでき、
理解が深まってよいと思いますよ。 まさしくその通りですね!!
違憲立法審査制は、違憲審査制と書いて正解になるので、裁判所は、国会内閣がやっていることが、それぞれ憲法にあっているかどうか(合憲か違憲か)を調べることができると説明しました。
違憲立法審査制は立法という語句があるので、国会に対して、国会が制定した法律が合憲か違憲かを調査できるということを説明しました。
自分の上のトピには、違憲審査制と書いておりますよ。
憲法の番人と呼ばれているのは、生徒には、国会内閣がやっていることが憲法に違反していないかどうかを調査できるからだよと説明しました。どこかおかしいでしょうか?
もしよろしかったら教えてください。
書き込みありがとうございます。
憲法の番人とは国会が立法したものが憲法違反になるかどうかを
判断するところからいわれているます。
違憲審査制は法律・命令・処分といった国家機関の行為が憲法に適合するか否かを審査するもの。
これはわかった上で、生徒がわかりやすいように説明したのでしたが、細かく教えたほうが良かったですかね??(ちょっと迷った部分でありました)
どうみんさんへ
ここはですね、一気に3っつ書かないところがミソなのですよ。そして、説明する順番が重要なんです。ですから、一気に3つ書くことには自分は賛成できません。
言い忘れていましたが、この三権分立は、国会内閣のところの最初のほうでやりました。教科書の順番とは違います。
理由は生徒に大まかないイメージをつかんでもらった後、国会の仕事や内閣、裁判所の仕事を教える、という流れのほうが生徒が理解しやすいと思ったからです。良いかどうかはわかりませんが…
憲法の番人とは国会が立法したものが憲法違反になるかどうかを
判断するところからいわれているます。
違憲審査制は法律・命令・処分といった国家機関の行為が憲法に適合するか否かを審査するもの。
これはわかった上で、生徒がわかりやすいように説明したのでしたが、細かく教えたほうが良かったですかね??(ちょっと迷った部分でありました)
どうみんさんへ
ここはですね、一気に3っつ書かないところがミソなのですよ。そして、説明する順番が重要なんです。ですから、一気に3つ書くことには自分は賛成できません。
言い忘れていましたが、この三権分立は、国会内閣のところの最初のほうでやりました。教科書の順番とは違います。
理由は生徒に大まかないイメージをつかんでもらった後、国会の仕事や内閣、裁判所の仕事を教える、という流れのほうが生徒が理解しやすいと思ったからです。良いかどうかはわかりませんが…
なるほど。これも一感想でしかないのですが、国会と内閣のところ
の最初のほうでやるとするならば、三権分立の話は出さないほうが
得策だと思います。
中三の大半は、議院内閣制自体かなり「?」が飛び交っています。
けっこうこの仕組み自体「意味が分からない」というわけです。
三権分立とこの仕組みは切っても切れない単元なので、国会と内閣の
関係というのが単元であるなら、まずそこだけをしっかりと教えて
おいたほうがいいんじゃないかと。裁判所やら国民やらをいきなり
持ち出すとさらに「?」が飛び交いそうですから。そして
司法権とかの説明がある程度終わったところで、今までの
役割の確認の意味を含めながら、三権分立の話を本格的にする。
この方がタイミングとしていいんじゃないかと。。
の最初のほうでやるとするならば、三権分立の話は出さないほうが
得策だと思います。
中三の大半は、議院内閣制自体かなり「?」が飛び交っています。
けっこうこの仕組み自体「意味が分からない」というわけです。
三権分立とこの仕組みは切っても切れない単元なので、国会と内閣の
関係というのが単元であるなら、まずそこだけをしっかりと教えて
おいたほうがいいんじゃないかと。裁判所やら国民やらをいきなり
持ち出すとさらに「?」が飛び交いそうですから。そして
司法権とかの説明がある程度終わったところで、今までの
役割の確認の意味を含めながら、三権分立の話を本格的にする。
この方がタイミングとしていいんじゃないかと。。
こんにちは。コメントさせていただきます。
内容についてはみなさんのコメントにもありますので、ぜひ参考にしてみてください。
僕の方では、内容よりも、全体の構成の仕方というか、授業の組み立てについてコメントします。
三権分立を導入として扱うのであれば、その三角関係だけでなく、国会・内閣・裁判所それぞれについての説明が必要です。
トピ主さんの進め方だと、その説明がどこでなされるのかがはっきりしていません。
ただ、説明をしないということはないと思うので、おそらく、三権分立のその後にそれぞれの説明に入ると解釈しました。
僕が気になったのは、その点です。
最初にその単元の大枠を提示した後に各論に移るというのは間違っていませんし、むしろ推奨パターンです。
しかし、それであれば、導入の時点での説明となる部分が、少々長すぎるように見えます。
全体のイメージをつけさせてから進めたいというのはわかりますが、
生徒にとっては、初めての内容、知識がない前提で扱うわけなので、
他の方がコメントされているように、講師が思うよりも誤った理解をしてしまいがちです。
導入として三権分立の説明を入れる場合は、
国会・内閣・裁判所が立法権・行政権・司法権を持つこと。権力を集中させない、互いに抑制し均衡を保つため。
これだけで十分です。
そこで時間をかけずに早く国会以降の説明に移った方が良いでしょう。
そして最後に総論として、三権分立を図示してまとめをしてあげるようにしましょう。
僕も何度も三権分立を教えましたが、最終的にこれがベストだと思っています。
また構成については、1回の授業でどこまで扱うのか、というのも非常に重要です。
1コマの時間数、授業回数など条件は異なると思いますが、案としては、
?国会
?内閣
?裁判所
?三権分立まとめ復習
の全4回が良いと思います。1回の授業で進みすぎても、生徒への負荷が高すぎるので、
1回に1つの単元にして、時間に余裕があれば演習時間なども作って定着をはかりましょう。
トピ主さんの授業を受けて生徒がわかりやすいというのは当然です。
難しい言葉を使わず、イメージしやすく、教えていると思います。
ただ僕たちの仕事は、生徒にわかりやすく教えることではありません。
その先には、点数をとらせる、成績をあげる、合格させる、という目的があります。
だから講師の自己満足で終わる授業ではなく、試験に直結するものを用意してあげましょう。
偉そうにコメントしてしまい、失礼でしたらすみません。
同じ境遇で仕事をするもの同士、切磋琢磨していきたいと思います。
内容についてはみなさんのコメントにもありますので、ぜひ参考にしてみてください。
僕の方では、内容よりも、全体の構成の仕方というか、授業の組み立てについてコメントします。
三権分立を導入として扱うのであれば、その三角関係だけでなく、国会・内閣・裁判所それぞれについての説明が必要です。
トピ主さんの進め方だと、その説明がどこでなされるのかがはっきりしていません。
ただ、説明をしないということはないと思うので、おそらく、三権分立のその後にそれぞれの説明に入ると解釈しました。
僕が気になったのは、その点です。
最初にその単元の大枠を提示した後に各論に移るというのは間違っていませんし、むしろ推奨パターンです。
しかし、それであれば、導入の時点での説明となる部分が、少々長すぎるように見えます。
全体のイメージをつけさせてから進めたいというのはわかりますが、
生徒にとっては、初めての内容、知識がない前提で扱うわけなので、
他の方がコメントされているように、講師が思うよりも誤った理解をしてしまいがちです。
導入として三権分立の説明を入れる場合は、
国会・内閣・裁判所が立法権・行政権・司法権を持つこと。権力を集中させない、互いに抑制し均衡を保つため。
これだけで十分です。
そこで時間をかけずに早く国会以降の説明に移った方が良いでしょう。
そして最後に総論として、三権分立を図示してまとめをしてあげるようにしましょう。
僕も何度も三権分立を教えましたが、最終的にこれがベストだと思っています。
また構成については、1回の授業でどこまで扱うのか、というのも非常に重要です。
1コマの時間数、授業回数など条件は異なると思いますが、案としては、
?国会
?内閣
?裁判所
?三権分立まとめ復習
の全4回が良いと思います。1回の授業で進みすぎても、生徒への負荷が高すぎるので、
1回に1つの単元にして、時間に余裕があれば演習時間なども作って定着をはかりましょう。
トピ主さんの授業を受けて生徒がわかりやすいというのは当然です。
難しい言葉を使わず、イメージしやすく、教えていると思います。
ただ僕たちの仕事は、生徒にわかりやすく教えることではありません。
その先には、点数をとらせる、成績をあげる、合格させる、という目的があります。
だから講師の自己満足で終わる授業ではなく、試験に直結するものを用意してあげましょう。
偉そうにコメントしてしまい、失礼でしたらすみません。
同じ境遇で仕事をするもの同士、切磋琢磨していきたいと思います。
初めて書き込みさせていただきます。「絶対王政」の話が出ていたので,お話の本筋から逸れることを承知で,気になったことを一言だけ述べさせていただきたいと思います。
「絶対王政」という言葉から,国王が隔絶した強い権力を持っていたかのように考えられますが,必ずしもそうではなかったという見方が,高校レベルの世界史では紹介されています。このような見方は,たとえば,山川の『詳説世界史研究』で説明されています。
絶対王政期のヨーロッパにおいて,国王は,新興の市民階級と旧来の貴族階級の勢力バランスを巧みに操り,常備軍,官僚制機構や王権神授説に基づいて,権力を維持したとする考えです。
中学生レベルの三権分立で必要な話ではありませんし,結局のところは三権分立に対置する概念として「絶対王政」を出さざるを得ないのかもしれませんが,この言葉を使うのなら,用語が指示する内容をより正確に理解しておく必要はあるかと思います。個人的には,「絶対王政」というよりは,「国王による専制体制」というほうが,「三権分立」の対置概念としてはしっくりくる気がします。
「絶対王政」という言葉から,国王が隔絶した強い権力を持っていたかのように考えられますが,必ずしもそうではなかったという見方が,高校レベルの世界史では紹介されています。このような見方は,たとえば,山川の『詳説世界史研究』で説明されています。
絶対王政期のヨーロッパにおいて,国王は,新興の市民階級と旧来の貴族階級の勢力バランスを巧みに操り,常備軍,官僚制機構や王権神授説に基づいて,権力を維持したとする考えです。
中学生レベルの三権分立で必要な話ではありませんし,結局のところは三権分立に対置する概念として「絶対王政」を出さざるを得ないのかもしれませんが,この言葉を使うのなら,用語が指示する内容をより正確に理解しておく必要はあるかと思います。個人的には,「絶対王政」というよりは,「国王による専制体制」というほうが,「三権分立」の対置概念としてはしっくりくる気がします。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|