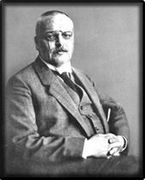こんばんは。
アルツハイマー病の、主に評価や診断に関わっている者です。
患者さんのご家族に症状を説明したり、対処法をアドバイスしたりもします。
ところで、一般の方が持っているアルツハイマー病の知識と、
専門職である我々が持っている知識が、
あまりにもかけ離れていると感じることが多々あります。
よくご家族から言われるのは、
・○×をしたから発病したのではないか
・○×という出来事をきっかけに発病したのではないか
・○×をしていたら、予防できたのではないか
・毎日、計算ドリルをやらせたら、進行が遅くなるのではないか
・毎日、読み書きをさせたら、進行が遅くなるのではないか
・一人暮らしで話をする人がいなかったから、発病したのではないか
・記憶違いをしていたら、わかるまで教えたほうがよいのではないか
・・・等々です。
専門職として、アルツハイマー病に関わっている方で、
同じようなことを感じている方はいらっしゃいますでしょうか?
私自身は、世の中にもう少し間違った情報が氾濫しないように、
専門職による啓蒙活動が必要だと感じています。
アルツハイマー病の、主に評価や診断に関わっている者です。
患者さんのご家族に症状を説明したり、対処法をアドバイスしたりもします。
ところで、一般の方が持っているアルツハイマー病の知識と、
専門職である我々が持っている知識が、
あまりにもかけ離れていると感じることが多々あります。
よくご家族から言われるのは、
・○×をしたから発病したのではないか
・○×という出来事をきっかけに発病したのではないか
・○×をしていたら、予防できたのではないか
・毎日、計算ドリルをやらせたら、進行が遅くなるのではないか
・毎日、読み書きをさせたら、進行が遅くなるのではないか
・一人暮らしで話をする人がいなかったから、発病したのではないか
・記憶違いをしていたら、わかるまで教えたほうがよいのではないか
・・・等々です。
専門職として、アルツハイマー病に関わっている方で、
同じようなことを感じている方はいらっしゃいますでしょうか?
私自身は、世の中にもう少し間違った情報が氾濫しないように、
専門職による啓蒙活動が必要だと感じています。
|
|
|
|
コメント(17)
私の父はアルツハイマー症で現在は入所中。
私自身も、自分のため家族のため…と三つの資格を取りました。
アルツハイマー症に関しては、ヘルパー、福祉用具、福祉住環境コーディネーターともに知識として習得?しました。
が、下記の著作もまた、大いに参考になりました。この本を、家族にアルツハイマー症を抱えている方、知識を必要としている方にお奨めします。
アルツハイマーを知るために
佐藤 早苗
新潮文庫 \552(税別)
※本の帯のキャプションがこの本の特徴です。
最初に気づくのはあなたです。
早ければ早いほど、
進行を遅らせる治療が可能です。
専門家から見た場合と、アルツハイマー症の障がい者や介護者(家族)から見た見識は当然?
温度差があると思います。
この本の著者は闘病記と分析!?の記述です。
私自身も、自分のため家族のため…と三つの資格を取りました。
アルツハイマー症に関しては、ヘルパー、福祉用具、福祉住環境コーディネーターともに知識として習得?しました。
が、下記の著作もまた、大いに参考になりました。この本を、家族にアルツハイマー症を抱えている方、知識を必要としている方にお奨めします。
アルツハイマーを知るために
佐藤 早苗
新潮文庫 \552(税別)
※本の帯のキャプションがこの本の特徴です。
最初に気づくのはあなたです。
早ければ早いほど、
進行を遅らせる治療が可能です。
専門家から見た場合と、アルツハイマー症の障がい者や介護者(家族)から見た見識は当然?
温度差があると思います。
この本の著者は闘病記と分析!?の記述です。
はじめまして。
私の父はアルツハイマーです。
私はアルツの専門職でもなく、ユカさんのトピの答えと趣旨が違ってしまうようですが、コメントさせてください。
ユカさんが書かれた箇条書きは、確かに、世の中一般の考え方のように思えます。
それ故、家族が認知症になっても、なかなか周りの人に打ち明けられなかったり、奇異な目で見られるのも事実です。
私も、もっと世の中に真実を知って欲しいと常日頃思っています。
私も箇条書きの部分は、知識としては持ってはいました。
でも、いくら本で書かれているのを見て、講座でそのように聞いて、その都度、やっぱりそうなんだと噛みしめるようにし、それでも、また世の中の目に負けそうになります。
皆さん知識としては案外持ってはいるのではないでしょうか。
でも、家族の心情として、そうなのかもしれない、とどうしても自分達を責めてしまう気持ちがあり、と同時に、「違いますよ、あなた達のせいではないのですよ」と言ってほしい気持ちも少なからずあるように思えます。
まだアルツの原因や治療がはっきりとわからない分、どうしても100%の答えがない限り、責めてしまう気持ちはあるのかもしれません。
ですから、ユカさんのように専門職の方から、ご面倒ですが、自信を持ってその都度、「違いますよ」と言っていただけることが、家族の病気の受容を促進するのだと思います。
ユカさんのように専門職の方からの問いかけ、世の中への啓蒙、ぜひ勧めていただきたく思っています。
私の父はアルツハイマーです。
私はアルツの専門職でもなく、ユカさんのトピの答えと趣旨が違ってしまうようですが、コメントさせてください。
ユカさんが書かれた箇条書きは、確かに、世の中一般の考え方のように思えます。
それ故、家族が認知症になっても、なかなか周りの人に打ち明けられなかったり、奇異な目で見られるのも事実です。
私も、もっと世の中に真実を知って欲しいと常日頃思っています。
私も箇条書きの部分は、知識としては持ってはいました。
でも、いくら本で書かれているのを見て、講座でそのように聞いて、その都度、やっぱりそうなんだと噛みしめるようにし、それでも、また世の中の目に負けそうになります。
皆さん知識としては案外持ってはいるのではないでしょうか。
でも、家族の心情として、そうなのかもしれない、とどうしても自分達を責めてしまう気持ちがあり、と同時に、「違いますよ、あなた達のせいではないのですよ」と言ってほしい気持ちも少なからずあるように思えます。
まだアルツの原因や治療がはっきりとわからない分、どうしても100%の答えがない限り、責めてしまう気持ちはあるのかもしれません。
ですから、ユカさんのように専門職の方から、ご面倒ですが、自信を持ってその都度、「違いますよ」と言っていただけることが、家族の病気の受容を促進するのだと思います。
ユカさんのように専門職の方からの問いかけ、世の中への啓蒙、ぜひ勧めていただきたく思っています。
トピ主です。
皆様、コメントありがとうございます。
私がよく繰り返して言うことは、
『ご本人が悪いのではなく、ご家族が悪いのでもありません。
症状は、病気のせいで脳が萎縮して起こっているのであり、
そして、その病気は私にも、私の親にも、誰にでも起こる可能性があり、
生活習慣や何かをしたから、起こってしまったわけではないのです』
ということです。
ご家族の方は、最初はともかく「信じられない」というパニックに陥り、
その後深いショックを受けられ、泣き続ける日々が続き、
あれが悪かったのか、これが悪かったのかといろいろなことを考え、
その後「これをやったらいいかも」「あれをやったらいいかも」と、
いろいろなことを試し、そして少しずつ患者さん自身を受け入れていく・・・
という経過を辿る方が多いです。
ご家族の方が患者さんの病気を受け止めていく過程で重要なことは、
『主介護者の、その周りにいる方が協力してくれるか』
『介護者の周囲の人間が、ひいては世間が、病気のことを理解してくれるか』
だと私は感じています。
介護者の周りにいる方が無理解だと、介護している人は本当に行き詰ってしまう。
がんばって介護している人に向かって、悪気なく、
「お父さんを一人暮らしさせてたからじゃない?」
と言ってみたりするんです・・・。
もし、社会がアルツハイマーについて少しでも理解していれば、
間違っても「一人にしてたからでは」とは言わないでしょう。
癌や心臓病になってしまった人の家族に対するのと同じように、
『大変な病気になってしまったね』と声をかけるはずです。
また、そのような社会であれば、ご家族も正しい知識を、
確信をもって信じることができると思います。
(少なくとも今の世の中よりかは)
『私が○×をしたからこうなったのでは』と思い悩むご家族を見るのは、
とても苦しく、切ないです。
「そんなことないです。これは病気のせいなんです」
「あなたのせいでは、全くないんですよ」
と何度も繰り返すことしか、今の私にはできていません。
専門職として、これだけでいいのだろうか、と思います・・・。
長々とすみません。
もし不適切な表現がありましたら、ごめんなさい。
本当に、専門家はもっと世の中に正しい情報を発信しないといけない、
と思います。
皆様、コメントありがとうございます。
私がよく繰り返して言うことは、
『ご本人が悪いのではなく、ご家族が悪いのでもありません。
症状は、病気のせいで脳が萎縮して起こっているのであり、
そして、その病気は私にも、私の親にも、誰にでも起こる可能性があり、
生活習慣や何かをしたから、起こってしまったわけではないのです』
ということです。
ご家族の方は、最初はともかく「信じられない」というパニックに陥り、
その後深いショックを受けられ、泣き続ける日々が続き、
あれが悪かったのか、これが悪かったのかといろいろなことを考え、
その後「これをやったらいいかも」「あれをやったらいいかも」と、
いろいろなことを試し、そして少しずつ患者さん自身を受け入れていく・・・
という経過を辿る方が多いです。
ご家族の方が患者さんの病気を受け止めていく過程で重要なことは、
『主介護者の、その周りにいる方が協力してくれるか』
『介護者の周囲の人間が、ひいては世間が、病気のことを理解してくれるか』
だと私は感じています。
介護者の周りにいる方が無理解だと、介護している人は本当に行き詰ってしまう。
がんばって介護している人に向かって、悪気なく、
「お父さんを一人暮らしさせてたからじゃない?」
と言ってみたりするんです・・・。
もし、社会がアルツハイマーについて少しでも理解していれば、
間違っても「一人にしてたからでは」とは言わないでしょう。
癌や心臓病になってしまった人の家族に対するのと同じように、
『大変な病気になってしまったね』と声をかけるはずです。
また、そのような社会であれば、ご家族も正しい知識を、
確信をもって信じることができると思います。
(少なくとも今の世の中よりかは)
『私が○×をしたからこうなったのでは』と思い悩むご家族を見るのは、
とても苦しく、切ないです。
「そんなことないです。これは病気のせいなんです」
「あなたのせいでは、全くないんですよ」
と何度も繰り返すことしか、今の私にはできていません。
専門職として、これだけでいいのだろうか、と思います・・・。
長々とすみません。
もし不適切な表現がありましたら、ごめんなさい。
本当に、専門家はもっと世の中に正しい情報を発信しないといけない、
と思います。
私の母は一年前に認知症と診断され、要介護2なのでデイサービスを利用したいのですが、本人が嫌がるので、まだ何もせず私が仕事の間は1人で犬達と家にいます。診断された時は、本当にショックでしたが、それと同時にそれまでの異常な行動は病気のせいだったのか と分かって少し安堵する気持ちもありました。
箇条書きにされていた事は心配して調べてくれた友達に言われた事ばかりで驚きでした。他にも、やはり母がやらないので私が何でもやってあげたのが悪かったのか?と自分を攻める事もありました。なので『本人のせいでもなく家族のせいでもない』とゆう言葉を読んだ時、救われました。
私自身も含め世間的には、全く理解されていないとゆうか誤解されている病気だと思います。
先日も、もぉ30年の付き合いになる隣人のおばさんに、母が認知症だと伝えると、心配した口調ではありましたが、まるで奇妙な者を見るような目つきで母を見た事が、私には物凄いショックでした。
母は病院に通院していますが、病院の先生は今一親身になってくれず、ただ薬を出せばいいような感じにしか思えないので、専門的な意見を頂けると本当に助かります。宜しくお願いします。
箇条書きにされていた事は心配して調べてくれた友達に言われた事ばかりで驚きでした。他にも、やはり母がやらないので私が何でもやってあげたのが悪かったのか?と自分を攻める事もありました。なので『本人のせいでもなく家族のせいでもない』とゆう言葉を読んだ時、救われました。
私自身も含め世間的には、全く理解されていないとゆうか誤解されている病気だと思います。
先日も、もぉ30年の付き合いになる隣人のおばさんに、母が認知症だと伝えると、心配した口調ではありましたが、まるで奇妙な者を見るような目つきで母を見た事が、私には物凄いショックでした。
母は病院に通院していますが、病院の先生は今一親身になってくれず、ただ薬を出せばいいような感じにしか思えないので、専門的な意見を頂けると本当に助かります。宜しくお願いします。
私は、病院の家族の会でこれが病気だと断言されても、ピンときませんでした。
それは、病気には原因があり、それを治す方法があるのではないかという観念があったからです。
若年性だったら、病気だろうと理解できたかもしれませんが、うちは、高齢だったので身体自体衰弱してきて当たり前だったので、これが病気?もし、この状態で特効薬が出来たら、不老不死の薬ぐらいしかないんじゃないかと思っていました。
今は、感覚で理解できるようになりました。
それは、文献でも医師の助言でもなく、日々母の様子を観て受け入れられるようになったからです。
病院のお医者様は、はっきり言って質問しても「いろんな方がいらっしゃいますから」みたいな感じしか答えてくれません。
この病気の治療が発展途上と知っているので、こちらもそれ以上の期待はしません。
まぁ、何か変化が起こったときの保険だと思っています。
一般の方には、あまり話さないようにしました。
最初は、自然に浸透していくのが理想だと思ったけど、そんなに甘いものではありません。ただ、友人と話していても家族の仲に発病した方がいるという話が多くなってきました。
なので、孤独感や疎外感は感じていません。
これはその立場にならないと、わからないことが多すぎるから無理に理解させるのは無理な話です。
なので、ちょっと話のつじつまが合わなくなってきたとか、そんな表現でお茶を濁しています。
それは、病気には原因があり、それを治す方法があるのではないかという観念があったからです。
若年性だったら、病気だろうと理解できたかもしれませんが、うちは、高齢だったので身体自体衰弱してきて当たり前だったので、これが病気?もし、この状態で特効薬が出来たら、不老不死の薬ぐらいしかないんじゃないかと思っていました。
今は、感覚で理解できるようになりました。
それは、文献でも医師の助言でもなく、日々母の様子を観て受け入れられるようになったからです。
病院のお医者様は、はっきり言って質問しても「いろんな方がいらっしゃいますから」みたいな感じしか答えてくれません。
この病気の治療が発展途上と知っているので、こちらもそれ以上の期待はしません。
まぁ、何か変化が起こったときの保険だと思っています。
一般の方には、あまり話さないようにしました。
最初は、自然に浸透していくのが理想だと思ったけど、そんなに甘いものではありません。ただ、友人と話していても家族の仲に発病した方がいるという話が多くなってきました。
なので、孤独感や疎外感は感じていません。
これはその立場にならないと、わからないことが多すぎるから無理に理解させるのは無理な話です。
なので、ちょっと話のつじつまが合わなくなってきたとか、そんな表現でお茶を濁しています。
お仕事お疲れ様です。
40代女性・介護福祉士(在宅高齢者訪問ヘルパー)、看護短大図書館勤務者です。事例と文献に囲まれてます。
母、81アルツハイマー型認知症(要介護4車椅子)を発症して長いです。
はじめ家族の方は驚きと不安でいっぱいなので、やはり上のような反応の方が多いと思われます。受け入れるに時間がかかります、また受け入れても、いきつもどりつ、不安や後悔、理不尽な思いや、言いようのない怒りでいっぱいの時もあります。
まず、その時は私はとにかく共感します。
それから聞かれた事に真摯な態度で答えていく、問題行動に対処していく方法、社会的支援を伝えます。
どうしても、自分を責めたくなる ものです。
母は20年前遠くへ嫁ぐ私を反対し、私もそのため?とか、父と多年に渡り折り合いが悪いから?なったのかと責めていました。答えが欲しいんです。
正しい知識を、と家族も混乱した頭で求めて来られると思います。実際に動かれるかも知れません、自分が何をしてあげられるか?
そのために聞いて来られたら、適切な対処法を伝えてあげてください。
医療の方ならエビデンスに基づくものを。
私も2001年よりヘルパー2級、国家試験で介護福祉士、そして10月ケアマネ受験です。これは極端な例かも知れませんが、多くの母以外の認知症の方と関わり、学ばせてもらいました、また認知症家族と言うことで、嫌な思いもして来ましたが、めげずに ぼちぼちいこか とやってます。恵みも得ています。
アルツハイマー・共に歩むのは奥が深すぎて、まだ旅の途中です。
40代女性・介護福祉士(在宅高齢者訪問ヘルパー)、看護短大図書館勤務者です。事例と文献に囲まれてます。
母、81アルツハイマー型認知症(要介護4車椅子)を発症して長いです。
はじめ家族の方は驚きと不安でいっぱいなので、やはり上のような反応の方が多いと思われます。受け入れるに時間がかかります、また受け入れても、いきつもどりつ、不安や後悔、理不尽な思いや、言いようのない怒りでいっぱいの時もあります。
まず、その時は私はとにかく共感します。
それから聞かれた事に真摯な態度で答えていく、問題行動に対処していく方法、社会的支援を伝えます。
どうしても、自分を責めたくなる ものです。
母は20年前遠くへ嫁ぐ私を反対し、私もそのため?とか、父と多年に渡り折り合いが悪いから?なったのかと責めていました。答えが欲しいんです。
正しい知識を、と家族も混乱した頭で求めて来られると思います。実際に動かれるかも知れません、自分が何をしてあげられるか?
そのために聞いて来られたら、適切な対処法を伝えてあげてください。
医療の方ならエビデンスに基づくものを。
私も2001年よりヘルパー2級、国家試験で介護福祉士、そして10月ケアマネ受験です。これは極端な例かも知れませんが、多くの母以外の認知症の方と関わり、学ばせてもらいました、また認知症家族と言うことで、嫌な思いもして来ましたが、めげずに ぼちぼちいこか とやってます。恵みも得ています。
アルツハイマー・共に歩むのは奥が深すぎて、まだ旅の途中です。
■アルツハイマー病予防には焼き魚を■
魚を食べると認知能力低下やアルツハイマー病を予防し、脳の健康増進に役立つ可能性があるという研究が、北米放射線医学学会で発表された。
アメリカのピッツバーグ大学の研究チームは、心臓血管に関する国の研究「Cardiovascular Health Study」の被験者から260人を抽出した。
うち163人が毎週魚を食べており、その多くは週1回から4回食べていることが分かった。
脳の健康を調べるため、磁気共鳴画像撮影装置(MRI)を用いて、被験者の脳の灰白質の位置と大きさを調べた。
その後、モデルを使って灰白質と魚の摂取との関係を分析し、10年後の脳の構造を予測した。
その結果、少なくとも週1回、焼いた魚を食べている人は、アルツハイマー病の発症にかかわる脳の領域の灰白質が大きいことが分かった。
乾燥させた魚には認知能力の低下を予防する効果は見られなかったという。
研究チームによると、脳の構造とアルツハイマー病の直接的関係を発見したのは、今回の研究が初めてという。
灰白質の大きさは、脳の健康にとって極めて重要で、健康な脳ほど灰白質が大きい。
灰白質の減少は、脳細胞が縮んでいることを意味する。
参照
AFP 2011年12月6日
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2844023/8164919?utm_source=afpbb&utm_medium=topics&utm_campaign=txt_topics
魚を食べると認知能力低下やアルツハイマー病を予防し、脳の健康増進に役立つ可能性があるという研究が、北米放射線医学学会で発表された。
アメリカのピッツバーグ大学の研究チームは、心臓血管に関する国の研究「Cardiovascular Health Study」の被験者から260人を抽出した。
うち163人が毎週魚を食べており、その多くは週1回から4回食べていることが分かった。
脳の健康を調べるため、磁気共鳴画像撮影装置(MRI)を用いて、被験者の脳の灰白質の位置と大きさを調べた。
その後、モデルを使って灰白質と魚の摂取との関係を分析し、10年後の脳の構造を予測した。
その結果、少なくとも週1回、焼いた魚を食べている人は、アルツハイマー病の発症にかかわる脳の領域の灰白質が大きいことが分かった。
乾燥させた魚には認知能力の低下を予防する効果は見られなかったという。
研究チームによると、脳の構造とアルツハイマー病の直接的関係を発見したのは、今回の研究が初めてという。
灰白質の大きさは、脳の健康にとって極めて重要で、健康な脳ほど灰白質が大きい。
灰白質の減少は、脳細胞が縮んでいることを意味する。
参照
AFP 2011年12月6日
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2844023/8164919?utm_source=afpbb&utm_medium=topics&utm_campaign=txt_topics
■アルツハイマー進行抑制か コレステロール低下薬■
血液中のコレステロール値を下げる薬剤に、アルツハイマー病などの認知症を進行させるタンパク質を減らす効果があることを、福井大の浜野忠則講師(神経内科学)が突き止めた。
発症を防いだり、遅らせたりする可能性があるという。
厚生労働省などによると、認知症患者の半数近くがアルツハイマー病とされるが、現在、根本的な治療薬はない。
浜野講師は、「臨床研究で効果を検証し、数年以内に治療薬として使えるようにしたい」と話している。
参照
西日本新聞 2012年1月31日
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/284872
血液中のコレステロール値を下げる薬剤に、アルツハイマー病などの認知症を進行させるタンパク質を減らす効果があることを、福井大の浜野忠則講師(神経内科学)が突き止めた。
発症を防いだり、遅らせたりする可能性があるという。
厚生労働省などによると、認知症患者の半数近くがアルツハイマー病とされるが、現在、根本的な治療薬はない。
浜野講師は、「臨床研究で効果を検証し、数年以内に治療薬として使えるようにしたい」と話している。
参照
西日本新聞 2012年1月31日
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/284872
■食事より運動が効果的 アルツハイマー病改善に■
アルツハイマー病の記憶障害の改善には、食事療法よりも運動療法の方が効果が大きいことを、京都大の木下彩栄教授(神経内科学)のグループがマウスを使った実験で明らかにした。
木下教授は、「高脂肪食でも、運動をすればアルツハイマー病を防ぎやすく、進行も抑えやすい」と話している。
遺伝子操作でアルツハイマー病にしたマウスに約5カ月、脂肪分60%の高脂肪の餌を与え続け、後半約2カ月半は回し車で運動させた。
運動をしなかった高脂肪食マウスが約35秒かかったのに対し、高脂肪食で運動したマウスは約16秒だった。
運動させずに脂肪分10%の普通の餌を食べたマウスは約25秒、運動と普通の餌を組み合わせたマウスは約17秒だった。
また、運動をした高脂肪食マウスは、アミロイドベータが、運動しなかった高脂肪食マウスと比べて約50%減り、運動と普通の餌を組み合わせたマウスと同じだった。
参照
日本経済新聞 2012年5月8日
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2E5E2E7908DE2EAE2E7E0E2E3E09180E2E2E2E2;at=DGXZZO0195591008122009000000
アルツハイマー病の記憶障害の改善には、食事療法よりも運動療法の方が効果が大きいことを、京都大の木下彩栄教授(神経内科学)のグループがマウスを使った実験で明らかにした。
木下教授は、「高脂肪食でも、運動をすればアルツハイマー病を防ぎやすく、進行も抑えやすい」と話している。
遺伝子操作でアルツハイマー病にしたマウスに約5カ月、脂肪分60%の高脂肪の餌を与え続け、後半約2カ月半は回し車で運動させた。
運動をしなかった高脂肪食マウスが約35秒かかったのに対し、高脂肪食で運動したマウスは約16秒だった。
運動させずに脂肪分10%の普通の餌を食べたマウスは約25秒、運動と普通の餌を組み合わせたマウスは約17秒だった。
また、運動をした高脂肪食マウスは、アミロイドベータが、運動しなかった高脂肪食マウスと比べて約50%減り、運動と普通の餌を組み合わせたマウスと同じだった。
参照
日本経済新聞 2012年5月8日
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2E5E2E7908DE2EAE2E7E0E2E3E09180E2E2E2E2;at=DGXZZO0195591008122009000000
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
アルツハイマー病研究 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
アルツハイマー病研究のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77414人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209452人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19955人