国立感染症研究所研究員 岡田晴恵氏のインタビュー〔縮刷版〕
H5N1型という“敵”に日本がとるべき策
国立感染症研究所研究員 岡田晴恵氏のインタビューが掲載されていましたのでご紹介します。私たちがこの問題を知ることによって、冷静な対応が生まれると思います。この視点で主な内容を引用します
1、パンデミック時の通勤電車の運行が通常通りだった場合、パンデミック発生から2週間後には東京圏に居住する人口の66.4%が、新型インフルエンザに感染するという結果が出ています。(P3)
2、感染ルートについて
十分に加熱していない感染鶏の鶏肉、鶏卵、を食べた場合にも感染が起きた例が存在します。アヒルのいる池で遊んだ子供が感染したという例もあります。ウイルスを含む鳥の糞が水に溶けていたらしいということになっています。(P5)
3、強毒型のインフルエンザ・ウイルスに感染するということの意味を示す写真をお見せしましょう。H5N1にやられた鶏舎の中の写真です。お分かりでしょうか。中央に写っている鶏の下に鶏の死骸が写っています。死骸が溶けているのです。強毒型ウイルスは全身感染を起こします。全身の細胞を破壊しますから、鶏の体は元の形を維持することができずに溶けたようになって死ぬのです。(P5)
4、ヒトに感染した場合は、「感染したけれども症状がでない」という不顕性感染はまずありません。100%発症します。高熱、せきといった通常のインフルエンザの症状に加えて、全身感染も起こすので、多臓器不全を発症します。特に肺炎が起きるので、患者は呼吸困難に苦しむことになります。腸管にも感染するので、発症者の約70%は下痢を起こしますし、腸管の細胞が破壊されることによる血便も出ます。そして、防疫の面で非常に重要なことですが、患者の便にも血液にも大量のウイルスが含まれます。これは例えば、患者と風呂を共有してはいけないということです。(P5)
5、つまり感染者のうち何%が死亡するかという割合は、50%以上、世界各国では主に医療水準の格差によって37%から88%までばらつきがありますが、おおむね半数以上が死亡します。これはもう、従来のインフルエンザとはっきり区別すべき、別の恐ろしい感染症です。(P5)
編集 NPO法人 生涯青春の会 石田双三
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国立感染症研究所研究員 岡田晴恵氏に直接、インタビュー
SAFETY JAPAN ではこれまで、新型インフルエンザに関する本を何冊か紹介してきたが、今回、その多くの本を著してきた岡田晴恵氏に直接、インタビューを試みた。
国立感染症研究所研究員である岡田氏は、新型インフルエンザに関する最新の、詳細な専門情報に触れてきたことで、H5N1型という“敵”の恐ろしさを実感するとともに、人間が採るべき対策を模索し続けている。今、日本で、まず採るべき対策は、一刻も早く、計画的なプレパンデミックワクチンの備蓄に着手することだ、というのが同氏の主張だ。
聞き手・文/松浦 晋也
1、岡田氏はインタビューの席でわたしの斜め前の席に座った。
2、従来のインフルエンザ、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ
3、鳥インフルエンザのさまざまな感染ルート
4、強毒型ウイルスは体を“溶かして”死に至らしめる
5、鳥インフルエンザウイルスから作るプレパンデミックワクチン
6、日本はすぐに製造できる体制を持っていない・・・・・・省略
7、プレパンデミックワクチンの実態・・・・・・・・・・・省略
8、プレパンデミックワクチンは強毒型の被害を弱毒型まで軽減する
9、プレパンデミックワクチンのコストは1人600円・・・・省略
10、プレパンデミックワクチンの計画的な生産を!・・・・・省略
11、フェーズ3とフェーズ4の境目が対策発動のタイミング
12、一歩ずつ備蓄を進めよ・・・・・・・・・・・・・・・・省略
13、1997年に稼いだ時間は使い果たされつつある
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、岡田氏はインタビューの席でわたしの前ではなく、斜め前の席に座った。
岡田:なぜわたしがここに座ったか分かりますか。
――いえ、なぜでしょうか。
岡田:あなたの目の前に、新型インフルエンザを発症したわたしが座ったとします。すると、あなたはほぼ確実に感染します。それが、この斜めの位置だと感染の確率は7割ぐらいまで低下します。
これが、例えば同じ部屋の端と端ぐらいになると、感染確率は1割程度まで下がります。この意味は分かりますか。
――感染の確率は距離だけで決まる、ということでしょうか。
岡田:そうです。もちろんどちらを向いて咳をするかというようなことも関係しますが、社会全体で見ると単純に人と人との物理的な距離が感染の確率を決めるのです。つまり、新型インフルエンザの世界的流行(パンデミック)の時に、感染を最も拡大するのは、人と人との距離がぎりぎりまで短くなる環境、つまり‥‥
――通勤電車ですね。
岡田:そうです。パンデミック時の通勤電車は、感染拡大の温床となります。感染症研究所では、コンピューターによる数値シミュレーションによる感染拡大の研究も行っていますが、通勤電車の運行が通常通りだった場合、パンデミック発生から2週間後には東京圏に居住する人口の66.4%が、新型インフルエンザに感染するという結果が出ています。
――2週間で6割以上というのは、あまりに早いのでは。
岡田:新型インフルエンザには誰も免疫を持っていないということが、このような急速な感染拡大を起こす理由です。
――すると、通勤電車を止めないと大変なことになる。
岡田:電車の運行を完全に止めるのは、社会機能を維持するためにも難しいです。それでも、事前に運転本数を間引くパンデミック時の運行計画を策定しておき、速やか移行する体制を整えておく必要があるでしょう。その時が来て、行政手続きが手間取っていると、手遅れになってしまいます。
通勤電車の管轄は厚生労働省ではありませんよね。国土交通省です。交通を遮断するとなると警察も関係してくるでしょう。経済行為を止めるわけですから、経済産業省も関係します。
なぜ、わたしがこんな話をしたかお分かりでしょう。新型インフルエンザ対策は、保健衛生や医療だけではなくすべての官庁、すべての行政組織が一致して準備をしておき、実施する必要があるということを言いたいのです。縦割り行政への固執は、国民の生命を損ないます。新型インフルエンザ対策は、内閣総理大臣の指揮下、国から地方自治体、企業、個人に至るまでの日本の国全体で行うべきものなのです。また、そうでなければ効果が薄れてしまうものなのです。
2、従来のインフルエンザ、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ
――前回掲載した田代眞人氏のインタビュー、に対しては、大きな反響がありました。なかでもプレパンデミックワクチンには多くの人が興味を持ったようです。このあたり、もう少し詳しい説明をお願いできますでしょうか。
岡田:まず、基本的な知識について繰り返しておきましょう。最初に、従来のインフルエンザとH5N1型の鳥インフルエンザ、そして新型インフルエンザの区別をきちんと理解しなくてはいけません。
従来のインフルエンザは、鳥インフルエンザがヒトに感染するように突然変異を起こしたものですが、上気道にしか感染しない弱毒型です。
一方、H5N1型の鳥インフルエンザは、全身感染を起こす強毒型ウイルスです。基本的に鳥にしか感染しません。ただし大量のウイルスと濃厚接触すると人間にも感染しますし、トラなどその他の動物でも感染例があります。全身感染するので、致死率が非常に高いです。
新型インフルエンザは、鳥インフルエンザがヒトからヒトへの連続した感染を効率よく起こすように突然変異を起こしたものです。まだ出現していません。
ただし、過去のインフルエンザのパンデミックはすべて鳥インフルエンザがヒト型に突然変異を起こしたために発生したことが分かっています。ですから、現在鳥の世界で広がっている強毒型のH5N1ウイルスは、間違いなくどこかの時点でヒトからヒトヘ感染する新型インフルエンザに変化すると考えねばなりません。
――H5N1ではない、弱毒型のウイルスが、次のインフルエンザとなる可能性もあるということでしたが。
岡田:それはその通りで、次にH9N2型などが来る可能性はあります。ですが、新型インフルエンザによるパンデミックは平均27年に1回の間隔で起きています。既に鳥の世界でパンデミックとなっているH5N1ウイルスは、“次”に来なくとも、相変わらず“次の次”の候補なのです。27年というのは平均ですから、もっとずっと早く“次の次”としてH5N1が新型インフルエンザとなる可能性もあります。対策を怠るわけにはいきません。
3、鳥インフルエンザのさまざまな感染ルート
岡田:現在の鳥インフルエンザは、ヒトに対する感染効率は低いです。病気の鳥や死んだ鳥に濃厚に接触した場合に感染しています。人間の肺の奥の細胞は、鳥の細胞と同じ性質を持っていて、鳥インフルエンザのウイルスが感染可能なためです。
それとは別に、十分に加熱していない感染鶏の鶏肉、鶏卵、あるいは地域によっては鶏の血を使う料理がありますが、そういったものを食べた場合にも感染が起きた例が存在します。アヒルのいる池で遊んだ子供が感染したという例もあります。ウイルスを含む鳥の糞が水に溶けていたらしいということになっています。
――例えば半熟卵は、加熱したことになるのでしょうか。
岡田:現状の日本では、養鶏場の防疫がしっかりしているので問題はないです。しかし、鳥インフルエンザが発生している外国で半熟卵を食べるのは避けたほうがいいでしょう。半熟卵の中身はタンパク質が変性しているものの、ウイルスが不活化するほどの高温にはなっていませんから。
感染拡大のルートとしては、このほかに死んだ鳥を食べた猫、ネズミなどの哺乳類があると推定されています。野鳥での防疫では、死体をいち早く回収して野生動物が食べないようにすることが大切です。
ヒトに感染した場合は、「感染したけれども症状がでない」という不顕性感染はまずありません。100%発症します。高熱、せきといった通常のインフルエンザの症状に加えて、全身感染も起こすので、多臓器不全を発症します。特に肺炎が起きるので、患者は呼吸困難に苦しむことになります。腸管にも感染するので、発症者の約70%は下痢を起こしますし、腸管の細胞が破壊されることによる血便も出ます。
そして、防疫の面で非常に重要なことですが、患者の便にも血液にも大量のウイルスが含まれます。これは例えば、患者と風呂を共有してはいけないということです。
致死率、つまり感染者のうち何%が死亡するかという割合は、50%以上、世界各国では主に医療水準の格差によって37%から88%までばらつきがありますが、おおむね半数以上が死亡します。これはもう、従来のインフルエンザとはっきり区別すべき、別の恐ろしい感染症です。
4、強毒型ウイルスは体を“溶かして”死に至らしめる
ここで、強毒型のインフルエンザ・ウイルスに感染するということの意味を示す写真をお見せしましょう。H5N1にやられた鶏舎の中の写真です。お分かりでしょうか。中央に写っている鶏の下に鶏の死骸が写っています。
写真/岡田 晴恵氏 提供
――とさかとけづめの位置が不自然ですが‥‥
岡田:死骸が溶けているのです。強毒型ウイルスは全身感染を起こします。全身の細胞を破壊しますから、鶏の体は元の形を維持することができずに溶けたようになって死ぬのです。
――これは‥‥他の動物でも同じような死に方になるのでしょうか。例えば人間でも。
岡田:現状の鳥インフルエンザでは、人間が溶けて死ぬことはありません。しかし、新型インフルエンザが出現した場合は、この鶏のように人が死んでいくことになるのかも知れません。そうなると、溶けた遺体には当然のことながら大量のウイルスが含まれることになるでしょう。感染を防ぐために遺族は遺体に触れることもできません。通常の手順での葬儀は不可能です。死体を入れる袋も、防疫のために液体が漏れないような二重になった特別なものが必要になります。
――実際、全世界の感染者が400人未満で済んでいる現状が信じられないほどですね。
岡田:その数字は世界保健機構(WHO)が出している数字ですよね。信じているわけですか?
――どういう意味でしょうか。
岡田:WHOが出している数字は確定症例です。つまり、ウイルスの検査まで行って「明らかにH5N1型の鳥インフルエンザである」と診断が確定した症例の数です。そもそも調査が行われなかったり、診断が確定しないまま、死亡したというような例は、確定症例の数倍以上になると推定されています。
――つまり実際には既に、もっと多数の死者が出ているということですか。
岡田:例えば、アフリカ大陸には既に鳥インフルエンザが入ってしまっています。アフリカの場合、政府組織が十分に機能していない地域もあるので、WHOにも報告が上がってきません。現地で何が起きているか全く分からないのです。あるいはインドネシアの奥地や中国内陸部など、それぞれの国の政府が十分に把握できないでいる地域もあります。ウイルスは人間の行政機構とは無関係に感染を拡大していきます。
従って、専門家の間ではWHOの確定症例は「氷山の一角である」という見方が一般的です。WHOが出している数字は、水面上に顔を出した氷山のごく一部でしかないのです。
5、鳥インフルエンザウイルスから作るプレパンデミックワクチン
岡田:過去の例からすると、新型インフルエンザのパンデミックは、2波から3波の波状攻撃をかけてきます。1回の期間は約2カ月で、うちピークが10日から2週間程度続きます。
――だから、対策マニュアルには家庭での籠城に備えて、食料など生活必需品を備蓄せよと書いてあるわけですね。
岡田:では、なぜパンデミックが終息するかご存知ですか。
――ウイルスが突然変異で弱くなるからでしょうか。
岡田:そうではなく、社会の構成人員の一定数が罹患(りかん)することで免疫を獲得するからです。数値シミュレーションでは、構成人員の6割から7割程度が免疫を獲得すると、パンデミックが終息することが示されています。ウイルスはどんどん別の個体に感染することで広がっていきますが、感染しようとした先が既に免疫を持っていたとすると感染は成立しません。そこで感染拡大が止まるわけです。免疫を持つ人が増えると、感染拡大が止まる確率が上昇し、パンデミックが終息するわけです。
逆に、事前に6割から7割が免疫を獲得している場合にはパンデミックは起きないことを示した研究もあります。
――あっ、つまりプレパンデミックワクチンの意義は、そこにあると。
岡田:そうです。わたしは、プレパンデミックワクチンの全国民分備蓄を主張しています。
新型インフルエンザに対するワクチンは2種類あります。パンデミックワクチンとプレパンデミックワクチンです。パンデミックワクチンは、新型インフルエンザが発生した後に、新型のウイルスを使って製造するワクチンです。
一方、プレパンデミックワクチンは、現在の鳥インフルエンザウイルスを使ったワクチンです。いまだ出現していない新型インフルエンザに対して効くかどうか未知の部分がどうしても残りますが、それでも最近の研究で、さまざまな亜種が存在するH5N1型全体に効く可能性が出てきています。
うまくプレパンデミックワクチンを使えば、パンデミックそのものを事前に抑え込める可能性があるのです。
6、日本はすぐに製造できる体制を持っていない・・・・ 省略
7、プレパンデミックワクチンの実態・・・・・・・・・・ 省略
8、プレパンデミックワクチンは強毒型の被害を弱毒型まで軽減する
――プレパンデミックワクチンを接種すれば、パンデミックが発生した時に、新型インフルエンザに罹患しないでもすむと考えてよいのでしょうか。
岡田:そうではありません。接種を受けても新型インフルエンザにかかる可能性は残ります。
――それではプレパンデミックワクチンの意義はどこにあるのでしょうか。
岡田:全身感染を起こす新型インフルエンザに罹患しても、全身感染から逃れることができると期待されています。致死率がぐっと下がるわけです。
プレパンデミックワクチンの意義は三つあります。まず、最初に述べたようにパンデミックそのものを抑止する可能性があるということです。次に、強毒型の新型インフルエンザの症状を、弱毒型並みに緩和する効果があるということです。最後が、プライミングです。
――プライミングとはどんなことですか。
岡田:プレパンデミックワクチンに限らず、インフルエンザのワクチンは接種しても免疫が発現するまでに3〜4週間かかります。発現した免疫は時間と共に徐々に弱くなっていきますが、事前に接種を受けておくと、次に接種を受けると急速に免疫が発現するという現象があります。ですから、事前にプレパンデミックワクチンの接種を受けておくと、いざパンデミックという時にもう一度接種を受けると、すぐに免疫を獲得することができます。この事前接種のことをプライミング(植え付け)といいます。
プライミングの効果は相当長期間持続します。ですから、わたしは社会インフラを維持する仕事に就いている人、少なくとも直接患者と向き合って治療に当たる医療関係者には、プレパンデミックワクチンのプライミングを行うべきと考えています。パンデミックが起きてからワクチンを接種すると、免疫が発現する前に、ウイルスがやってきてしまう可能性があるわけですから。
9、プレパンデミックワクチンのコストは1人600円・・・ 省略
10、プレパンデミックワクチンの計画的な生産を!・・・ 省略
11、フェーズ3とフェーズ4の境目が対策発動のタイミング
――企業や家庭の取り組みはどのようにしていけばいいのでしょうか。
岡田:最初は海外駐在の日本人をどうやって保護するかでしょう。現状では、日本から新型インフルエンザが発生する可能性は低いです。感染確認例が相次いでいるインドネシアか、中国か、エジプトか‥‥どこか外国で発生する可能性が高いです。
ですから、海外駐在員を派遣している企業は、どのようにして駐在員およびその家族を日本に引き揚げるかの計画を持っていなくてはなりません。パンデミックが起きると、交通が遮断される可能性もありますから、「もう少し仕事を片づけてから」と考えていると、帰国できなくなることもあり得ます。
もちろん、帰国できなかった場合の行動計画も用意しなくてはなりません。
――思い切りが重要だということですか。
岡田:WHOは、新型インフルエンザによるパンデミック発生までの流れを、フェーズ1からフェーズ6までに分類しています。現状はフェーズ3の「ヒトからヒトへの感染はないか、または極めて限定されている」という状況です。
次のフェーズ4は「ヒト−ヒト感染が増加していることの証拠がある」というものです。フェーズ5は「かなりの数のヒト−ヒト感染があることの証拠がある」、フェーズ6が「効率よく持続したヒト−ヒト感染が確立」つまりパンデミックです。
つまり、フェーズ3とフェーズ4との間に一つの壁があります。一端フェーズ4に入ってヒトからヒトヘの感染を起こすようになると、ほとんどの人は免疫を持っていませんから一気に感染は拡大します。ですからフェーズ4からフェーズ6へは、急速に進行すると思っておいたほうがいいでしょう。
企業の中には、WHOが、フェーズ4を宣言するかどうかが事態の潮目であると考えて、現状のフェーズ3とフェーズ4以上の2段階で、事前の対策を立てているところもあります。
――「フェーズ4になったら、5になったら」というのではなく、ざっくりフェーズ4以上になったら、というところで対策を立てておけということですね。
岡田:これは国内においても同じです。いったん日本にウイルスが侵入したら1週間程度で全国に広がると予想されています。ウイルスが来たならば、一気に緊急体制に移行できるように準備を整えておく必要があります。
最初に言ったように、通勤電車は感染拡大の温床となる恐れがあります。各企業は、可能な限り在宅勤務に切り替えて、社員の出社を抑制しなくてはなりません。ワークフローを分析し、どのようにして在宅勤務で仕事を回していくか ―― これは事前準備の中でも非常に重要な部分です。
電気、ガス、水道、通信、さらにはガソリンや灯油の供給といった社会活動の根幹となるインフラに関しては、特に事前の準備が重要となります。一般市民は、各家庭に籠城するといっても、これらのインフラが正常に稼働してくれなくては、籠城すら困難です。
なかでも水道による水の供給の継続と、水源をウイルスによる汚染から守るための準備は最重要課題です。水道を担当している地方自治体の責任は重大であると言わねばなりません。水がなければ、人は一日として暮らしていくことはできないのですから。
12、一歩ずつ備蓄を進めよう 省略
13、1997年に稼いだ時間は使い果たされつつある
――ここまでお話をお聞きして、「さまざまなレベルでの対策がうまくかみ合わないと、新型インフルエンザ対策はうまくいかない」という印象を強く受けました。
岡田:そうです。感染拡大という問題にしても、各企業が事前に「いかに通勤しないで在宅で仕事をするか」という準備をしておかないと、各家庭にこもっても、働きに出ている家族がウイルスを家に持ち帰ってしまうことになります。逆に、企業が在宅ワークを進めても、各家庭の籠城準備が不十分だと、買い物に出て感染してしまう可能性があるでしょう。
国、地方自治体、医師会と病院、企業、学校、各家庭などの対策がすべて出そろい、うまくかみ合って、初めて効率的に新型インフルエンザを迎え撃つ体制が動き出すのです。どこが欠けてもいけません。欠けたところから破綻が始まります。
香港で、最初の鳥インフルエンザの感染が起きた1997年、わたしは科学技術庁の職員で感染症研究所に出向していました。たまたま、書類を届ける用事があって、田代部長の部屋に入ったそのタイミングで、香港から感染発生を知らせる電話が入ったのです。
電話口に出た田代部長が、ぶるぶるとふるえていたのをはっきりと覚えています。電話に向かって田代部長は、「鶏をすべて殺すしかない」と言っていました。当時、鳥インフルエンザは鳥に特有の病気で、ヒトには感染しないと考えられていました。まして、強毒型の特性を獲得して高い致死率を示すようになるとは、誰も思ってもいませんでした。想像すらできなかった恐ろしい感染症が、突然目の前に現れたのです。
香港の防疫責任者だったマーガレット・チャンは、香港で飼っていたすべての鶏を殺処分するという大英断を下し、感染拡大を防ぎました。この決断がなければ、1997年の時点で新型インフルエンザが世界を席巻していたかも知れません。
マーガレット・チャンのおかげで、世界は新型インフルエンザに備える時間的な猶予を得ました。しかし、ウイルス研究の現場にいて、鳥インフルエンザの拡大を見ていると、新型インフルエンザ発生までの時間は残り少ないと肌で感じられます。
日本の対策は、米国などに比べれば3年から4年は遅れています。もはや一刻の猶予もなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
H5N1型という“敵”に日本がとるべき策
国立感染症研究所研究員 岡田晴恵氏のインタビューが掲載されていましたのでご紹介します。私たちがこの問題を知ることによって、冷静な対応が生まれると思います。この視点で主な内容を引用します
1、パンデミック時の通勤電車の運行が通常通りだった場合、パンデミック発生から2週間後には東京圏に居住する人口の66.4%が、新型インフルエンザに感染するという結果が出ています。(P3)
2、感染ルートについて
十分に加熱していない感染鶏の鶏肉、鶏卵、を食べた場合にも感染が起きた例が存在します。アヒルのいる池で遊んだ子供が感染したという例もあります。ウイルスを含む鳥の糞が水に溶けていたらしいということになっています。(P5)
3、強毒型のインフルエンザ・ウイルスに感染するということの意味を示す写真をお見せしましょう。H5N1にやられた鶏舎の中の写真です。お分かりでしょうか。中央に写っている鶏の下に鶏の死骸が写っています。死骸が溶けているのです。強毒型ウイルスは全身感染を起こします。全身の細胞を破壊しますから、鶏の体は元の形を維持することができずに溶けたようになって死ぬのです。(P5)
4、ヒトに感染した場合は、「感染したけれども症状がでない」という不顕性感染はまずありません。100%発症します。高熱、せきといった通常のインフルエンザの症状に加えて、全身感染も起こすので、多臓器不全を発症します。特に肺炎が起きるので、患者は呼吸困難に苦しむことになります。腸管にも感染するので、発症者の約70%は下痢を起こしますし、腸管の細胞が破壊されることによる血便も出ます。そして、防疫の面で非常に重要なことですが、患者の便にも血液にも大量のウイルスが含まれます。これは例えば、患者と風呂を共有してはいけないということです。(P5)
5、つまり感染者のうち何%が死亡するかという割合は、50%以上、世界各国では主に医療水準の格差によって37%から88%までばらつきがありますが、おおむね半数以上が死亡します。これはもう、従来のインフルエンザとはっきり区別すべき、別の恐ろしい感染症です。(P5)
編集 NPO法人 生涯青春の会 石田双三
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国立感染症研究所研究員 岡田晴恵氏に直接、インタビュー
SAFETY JAPAN ではこれまで、新型インフルエンザに関する本を何冊か紹介してきたが、今回、その多くの本を著してきた岡田晴恵氏に直接、インタビューを試みた。
国立感染症研究所研究員である岡田氏は、新型インフルエンザに関する最新の、詳細な専門情報に触れてきたことで、H5N1型という“敵”の恐ろしさを実感するとともに、人間が採るべき対策を模索し続けている。今、日本で、まず採るべき対策は、一刻も早く、計画的なプレパンデミックワクチンの備蓄に着手することだ、というのが同氏の主張だ。
聞き手・文/松浦 晋也
1、岡田氏はインタビューの席でわたしの斜め前の席に座った。
2、従来のインフルエンザ、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ
3、鳥インフルエンザのさまざまな感染ルート
4、強毒型ウイルスは体を“溶かして”死に至らしめる
5、鳥インフルエンザウイルスから作るプレパンデミックワクチン
6、日本はすぐに製造できる体制を持っていない・・・・・・省略
7、プレパンデミックワクチンの実態・・・・・・・・・・・省略
8、プレパンデミックワクチンは強毒型の被害を弱毒型まで軽減する
9、プレパンデミックワクチンのコストは1人600円・・・・省略
10、プレパンデミックワクチンの計画的な生産を!・・・・・省略
11、フェーズ3とフェーズ4の境目が対策発動のタイミング
12、一歩ずつ備蓄を進めよ・・・・・・・・・・・・・・・・省略
13、1997年に稼いだ時間は使い果たされつつある
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、岡田氏はインタビューの席でわたしの前ではなく、斜め前の席に座った。
岡田:なぜわたしがここに座ったか分かりますか。
――いえ、なぜでしょうか。
岡田:あなたの目の前に、新型インフルエンザを発症したわたしが座ったとします。すると、あなたはほぼ確実に感染します。それが、この斜めの位置だと感染の確率は7割ぐらいまで低下します。
これが、例えば同じ部屋の端と端ぐらいになると、感染確率は1割程度まで下がります。この意味は分かりますか。
――感染の確率は距離だけで決まる、ということでしょうか。
岡田:そうです。もちろんどちらを向いて咳をするかというようなことも関係しますが、社会全体で見ると単純に人と人との物理的な距離が感染の確率を決めるのです。つまり、新型インフルエンザの世界的流行(パンデミック)の時に、感染を最も拡大するのは、人と人との距離がぎりぎりまで短くなる環境、つまり‥‥
――通勤電車ですね。
岡田:そうです。パンデミック時の通勤電車は、感染拡大の温床となります。感染症研究所では、コンピューターによる数値シミュレーションによる感染拡大の研究も行っていますが、通勤電車の運行が通常通りだった場合、パンデミック発生から2週間後には東京圏に居住する人口の66.4%が、新型インフルエンザに感染するという結果が出ています。
――2週間で6割以上というのは、あまりに早いのでは。
岡田:新型インフルエンザには誰も免疫を持っていないということが、このような急速な感染拡大を起こす理由です。
――すると、通勤電車を止めないと大変なことになる。
岡田:電車の運行を完全に止めるのは、社会機能を維持するためにも難しいです。それでも、事前に運転本数を間引くパンデミック時の運行計画を策定しておき、速やか移行する体制を整えておく必要があるでしょう。その時が来て、行政手続きが手間取っていると、手遅れになってしまいます。
通勤電車の管轄は厚生労働省ではありませんよね。国土交通省です。交通を遮断するとなると警察も関係してくるでしょう。経済行為を止めるわけですから、経済産業省も関係します。
なぜ、わたしがこんな話をしたかお分かりでしょう。新型インフルエンザ対策は、保健衛生や医療だけではなくすべての官庁、すべての行政組織が一致して準備をしておき、実施する必要があるということを言いたいのです。縦割り行政への固執は、国民の生命を損ないます。新型インフルエンザ対策は、内閣総理大臣の指揮下、国から地方自治体、企業、個人に至るまでの日本の国全体で行うべきものなのです。また、そうでなければ効果が薄れてしまうものなのです。
2、従来のインフルエンザ、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ
――前回掲載した田代眞人氏のインタビュー、に対しては、大きな反響がありました。なかでもプレパンデミックワクチンには多くの人が興味を持ったようです。このあたり、もう少し詳しい説明をお願いできますでしょうか。
岡田:まず、基本的な知識について繰り返しておきましょう。最初に、従来のインフルエンザとH5N1型の鳥インフルエンザ、そして新型インフルエンザの区別をきちんと理解しなくてはいけません。
従来のインフルエンザは、鳥インフルエンザがヒトに感染するように突然変異を起こしたものですが、上気道にしか感染しない弱毒型です。
一方、H5N1型の鳥インフルエンザは、全身感染を起こす強毒型ウイルスです。基本的に鳥にしか感染しません。ただし大量のウイルスと濃厚接触すると人間にも感染しますし、トラなどその他の動物でも感染例があります。全身感染するので、致死率が非常に高いです。
新型インフルエンザは、鳥インフルエンザがヒトからヒトへの連続した感染を効率よく起こすように突然変異を起こしたものです。まだ出現していません。
ただし、過去のインフルエンザのパンデミックはすべて鳥インフルエンザがヒト型に突然変異を起こしたために発生したことが分かっています。ですから、現在鳥の世界で広がっている強毒型のH5N1ウイルスは、間違いなくどこかの時点でヒトからヒトヘ感染する新型インフルエンザに変化すると考えねばなりません。
――H5N1ではない、弱毒型のウイルスが、次のインフルエンザとなる可能性もあるということでしたが。
岡田:それはその通りで、次にH9N2型などが来る可能性はあります。ですが、新型インフルエンザによるパンデミックは平均27年に1回の間隔で起きています。既に鳥の世界でパンデミックとなっているH5N1ウイルスは、“次”に来なくとも、相変わらず“次の次”の候補なのです。27年というのは平均ですから、もっとずっと早く“次の次”としてH5N1が新型インフルエンザとなる可能性もあります。対策を怠るわけにはいきません。
3、鳥インフルエンザのさまざまな感染ルート
岡田:現在の鳥インフルエンザは、ヒトに対する感染効率は低いです。病気の鳥や死んだ鳥に濃厚に接触した場合に感染しています。人間の肺の奥の細胞は、鳥の細胞と同じ性質を持っていて、鳥インフルエンザのウイルスが感染可能なためです。
それとは別に、十分に加熱していない感染鶏の鶏肉、鶏卵、あるいは地域によっては鶏の血を使う料理がありますが、そういったものを食べた場合にも感染が起きた例が存在します。アヒルのいる池で遊んだ子供が感染したという例もあります。ウイルスを含む鳥の糞が水に溶けていたらしいということになっています。
――例えば半熟卵は、加熱したことになるのでしょうか。
岡田:現状の日本では、養鶏場の防疫がしっかりしているので問題はないです。しかし、鳥インフルエンザが発生している外国で半熟卵を食べるのは避けたほうがいいでしょう。半熟卵の中身はタンパク質が変性しているものの、ウイルスが不活化するほどの高温にはなっていませんから。
感染拡大のルートとしては、このほかに死んだ鳥を食べた猫、ネズミなどの哺乳類があると推定されています。野鳥での防疫では、死体をいち早く回収して野生動物が食べないようにすることが大切です。
ヒトに感染した場合は、「感染したけれども症状がでない」という不顕性感染はまずありません。100%発症します。高熱、せきといった通常のインフルエンザの症状に加えて、全身感染も起こすので、多臓器不全を発症します。特に肺炎が起きるので、患者は呼吸困難に苦しむことになります。腸管にも感染するので、発症者の約70%は下痢を起こしますし、腸管の細胞が破壊されることによる血便も出ます。
そして、防疫の面で非常に重要なことですが、患者の便にも血液にも大量のウイルスが含まれます。これは例えば、患者と風呂を共有してはいけないということです。
致死率、つまり感染者のうち何%が死亡するかという割合は、50%以上、世界各国では主に医療水準の格差によって37%から88%までばらつきがありますが、おおむね半数以上が死亡します。これはもう、従来のインフルエンザとはっきり区別すべき、別の恐ろしい感染症です。
4、強毒型ウイルスは体を“溶かして”死に至らしめる
ここで、強毒型のインフルエンザ・ウイルスに感染するということの意味を示す写真をお見せしましょう。H5N1にやられた鶏舎の中の写真です。お分かりでしょうか。中央に写っている鶏の下に鶏の死骸が写っています。
写真/岡田 晴恵氏 提供
――とさかとけづめの位置が不自然ですが‥‥
岡田:死骸が溶けているのです。強毒型ウイルスは全身感染を起こします。全身の細胞を破壊しますから、鶏の体は元の形を維持することができずに溶けたようになって死ぬのです。
――これは‥‥他の動物でも同じような死に方になるのでしょうか。例えば人間でも。
岡田:現状の鳥インフルエンザでは、人間が溶けて死ぬことはありません。しかし、新型インフルエンザが出現した場合は、この鶏のように人が死んでいくことになるのかも知れません。そうなると、溶けた遺体には当然のことながら大量のウイルスが含まれることになるでしょう。感染を防ぐために遺族は遺体に触れることもできません。通常の手順での葬儀は不可能です。死体を入れる袋も、防疫のために液体が漏れないような二重になった特別なものが必要になります。
――実際、全世界の感染者が400人未満で済んでいる現状が信じられないほどですね。
岡田:その数字は世界保健機構(WHO)が出している数字ですよね。信じているわけですか?
――どういう意味でしょうか。
岡田:WHOが出している数字は確定症例です。つまり、ウイルスの検査まで行って「明らかにH5N1型の鳥インフルエンザである」と診断が確定した症例の数です。そもそも調査が行われなかったり、診断が確定しないまま、死亡したというような例は、確定症例の数倍以上になると推定されています。
――つまり実際には既に、もっと多数の死者が出ているということですか。
岡田:例えば、アフリカ大陸には既に鳥インフルエンザが入ってしまっています。アフリカの場合、政府組織が十分に機能していない地域もあるので、WHOにも報告が上がってきません。現地で何が起きているか全く分からないのです。あるいはインドネシアの奥地や中国内陸部など、それぞれの国の政府が十分に把握できないでいる地域もあります。ウイルスは人間の行政機構とは無関係に感染を拡大していきます。
従って、専門家の間ではWHOの確定症例は「氷山の一角である」という見方が一般的です。WHOが出している数字は、水面上に顔を出した氷山のごく一部でしかないのです。
5、鳥インフルエンザウイルスから作るプレパンデミックワクチン
岡田:過去の例からすると、新型インフルエンザのパンデミックは、2波から3波の波状攻撃をかけてきます。1回の期間は約2カ月で、うちピークが10日から2週間程度続きます。
――だから、対策マニュアルには家庭での籠城に備えて、食料など生活必需品を備蓄せよと書いてあるわけですね。
岡田:では、なぜパンデミックが終息するかご存知ですか。
――ウイルスが突然変異で弱くなるからでしょうか。
岡田:そうではなく、社会の構成人員の一定数が罹患(りかん)することで免疫を獲得するからです。数値シミュレーションでは、構成人員の6割から7割程度が免疫を獲得すると、パンデミックが終息することが示されています。ウイルスはどんどん別の個体に感染することで広がっていきますが、感染しようとした先が既に免疫を持っていたとすると感染は成立しません。そこで感染拡大が止まるわけです。免疫を持つ人が増えると、感染拡大が止まる確率が上昇し、パンデミックが終息するわけです。
逆に、事前に6割から7割が免疫を獲得している場合にはパンデミックは起きないことを示した研究もあります。
――あっ、つまりプレパンデミックワクチンの意義は、そこにあると。
岡田:そうです。わたしは、プレパンデミックワクチンの全国民分備蓄を主張しています。
新型インフルエンザに対するワクチンは2種類あります。パンデミックワクチンとプレパンデミックワクチンです。パンデミックワクチンは、新型インフルエンザが発生した後に、新型のウイルスを使って製造するワクチンです。
一方、プレパンデミックワクチンは、現在の鳥インフルエンザウイルスを使ったワクチンです。いまだ出現していない新型インフルエンザに対して効くかどうか未知の部分がどうしても残りますが、それでも最近の研究で、さまざまな亜種が存在するH5N1型全体に効く可能性が出てきています。
うまくプレパンデミックワクチンを使えば、パンデミックそのものを事前に抑え込める可能性があるのです。
6、日本はすぐに製造できる体制を持っていない・・・・ 省略
7、プレパンデミックワクチンの実態・・・・・・・・・・ 省略
8、プレパンデミックワクチンは強毒型の被害を弱毒型まで軽減する
――プレパンデミックワクチンを接種すれば、パンデミックが発生した時に、新型インフルエンザに罹患しないでもすむと考えてよいのでしょうか。
岡田:そうではありません。接種を受けても新型インフルエンザにかかる可能性は残ります。
――それではプレパンデミックワクチンの意義はどこにあるのでしょうか。
岡田:全身感染を起こす新型インフルエンザに罹患しても、全身感染から逃れることができると期待されています。致死率がぐっと下がるわけです。
プレパンデミックワクチンの意義は三つあります。まず、最初に述べたようにパンデミックそのものを抑止する可能性があるということです。次に、強毒型の新型インフルエンザの症状を、弱毒型並みに緩和する効果があるということです。最後が、プライミングです。
――プライミングとはどんなことですか。
岡田:プレパンデミックワクチンに限らず、インフルエンザのワクチンは接種しても免疫が発現するまでに3〜4週間かかります。発現した免疫は時間と共に徐々に弱くなっていきますが、事前に接種を受けておくと、次に接種を受けると急速に免疫が発現するという現象があります。ですから、事前にプレパンデミックワクチンの接種を受けておくと、いざパンデミックという時にもう一度接種を受けると、すぐに免疫を獲得することができます。この事前接種のことをプライミング(植え付け)といいます。
プライミングの効果は相当長期間持続します。ですから、わたしは社会インフラを維持する仕事に就いている人、少なくとも直接患者と向き合って治療に当たる医療関係者には、プレパンデミックワクチンのプライミングを行うべきと考えています。パンデミックが起きてからワクチンを接種すると、免疫が発現する前に、ウイルスがやってきてしまう可能性があるわけですから。
9、プレパンデミックワクチンのコストは1人600円・・・ 省略
10、プレパンデミックワクチンの計画的な生産を!・・・ 省略
11、フェーズ3とフェーズ4の境目が対策発動のタイミング
――企業や家庭の取り組みはどのようにしていけばいいのでしょうか。
岡田:最初は海外駐在の日本人をどうやって保護するかでしょう。現状では、日本から新型インフルエンザが発生する可能性は低いです。感染確認例が相次いでいるインドネシアか、中国か、エジプトか‥‥どこか外国で発生する可能性が高いです。
ですから、海外駐在員を派遣している企業は、どのようにして駐在員およびその家族を日本に引き揚げるかの計画を持っていなくてはなりません。パンデミックが起きると、交通が遮断される可能性もありますから、「もう少し仕事を片づけてから」と考えていると、帰国できなくなることもあり得ます。
もちろん、帰国できなかった場合の行動計画も用意しなくてはなりません。
――思い切りが重要だということですか。
岡田:WHOは、新型インフルエンザによるパンデミック発生までの流れを、フェーズ1からフェーズ6までに分類しています。現状はフェーズ3の「ヒトからヒトへの感染はないか、または極めて限定されている」という状況です。
次のフェーズ4は「ヒト−ヒト感染が増加していることの証拠がある」というものです。フェーズ5は「かなりの数のヒト−ヒト感染があることの証拠がある」、フェーズ6が「効率よく持続したヒト−ヒト感染が確立」つまりパンデミックです。
つまり、フェーズ3とフェーズ4との間に一つの壁があります。一端フェーズ4に入ってヒトからヒトヘの感染を起こすようになると、ほとんどの人は免疫を持っていませんから一気に感染は拡大します。ですからフェーズ4からフェーズ6へは、急速に進行すると思っておいたほうがいいでしょう。
企業の中には、WHOが、フェーズ4を宣言するかどうかが事態の潮目であると考えて、現状のフェーズ3とフェーズ4以上の2段階で、事前の対策を立てているところもあります。
――「フェーズ4になったら、5になったら」というのではなく、ざっくりフェーズ4以上になったら、というところで対策を立てておけということですね。
岡田:これは国内においても同じです。いったん日本にウイルスが侵入したら1週間程度で全国に広がると予想されています。ウイルスが来たならば、一気に緊急体制に移行できるように準備を整えておく必要があります。
最初に言ったように、通勤電車は感染拡大の温床となる恐れがあります。各企業は、可能な限り在宅勤務に切り替えて、社員の出社を抑制しなくてはなりません。ワークフローを分析し、どのようにして在宅勤務で仕事を回していくか ―― これは事前準備の中でも非常に重要な部分です。
電気、ガス、水道、通信、さらにはガソリンや灯油の供給といった社会活動の根幹となるインフラに関しては、特に事前の準備が重要となります。一般市民は、各家庭に籠城するといっても、これらのインフラが正常に稼働してくれなくては、籠城すら困難です。
なかでも水道による水の供給の継続と、水源をウイルスによる汚染から守るための準備は最重要課題です。水道を担当している地方自治体の責任は重大であると言わねばなりません。水がなければ、人は一日として暮らしていくことはできないのですから。
12、一歩ずつ備蓄を進めよう 省略
13、1997年に稼いだ時間は使い果たされつつある
――ここまでお話をお聞きして、「さまざまなレベルでの対策がうまくかみ合わないと、新型インフルエンザ対策はうまくいかない」という印象を強く受けました。
岡田:そうです。感染拡大という問題にしても、各企業が事前に「いかに通勤しないで在宅で仕事をするか」という準備をしておかないと、各家庭にこもっても、働きに出ている家族がウイルスを家に持ち帰ってしまうことになります。逆に、企業が在宅ワークを進めても、各家庭の籠城準備が不十分だと、買い物に出て感染してしまう可能性があるでしょう。
国、地方自治体、医師会と病院、企業、学校、各家庭などの対策がすべて出そろい、うまくかみ合って、初めて効率的に新型インフルエンザを迎え撃つ体制が動き出すのです。どこが欠けてもいけません。欠けたところから破綻が始まります。
香港で、最初の鳥インフルエンザの感染が起きた1997年、わたしは科学技術庁の職員で感染症研究所に出向していました。たまたま、書類を届ける用事があって、田代部長の部屋に入ったそのタイミングで、香港から感染発生を知らせる電話が入ったのです。
電話口に出た田代部長が、ぶるぶるとふるえていたのをはっきりと覚えています。電話に向かって田代部長は、「鶏をすべて殺すしかない」と言っていました。当時、鳥インフルエンザは鳥に特有の病気で、ヒトには感染しないと考えられていました。まして、強毒型の特性を獲得して高い致死率を示すようになるとは、誰も思ってもいませんでした。想像すらできなかった恐ろしい感染症が、突然目の前に現れたのです。
香港の防疫責任者だったマーガレット・チャンは、香港で飼っていたすべての鶏を殺処分するという大英断を下し、感染拡大を防ぎました。この決断がなければ、1997年の時点で新型インフルエンザが世界を席巻していたかも知れません。
マーガレット・チャンのおかげで、世界は新型インフルエンザに備える時間的な猶予を得ました。しかし、ウイルス研究の現場にいて、鳥インフルエンザの拡大を見ていると、新型インフルエンザ発生までの時間は残り少ないと肌で感じられます。
日本の対策は、米国などに比べれば3年から4年は遅れています。もはや一刻の猶予もなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|
|
|
|
|
|
|
|
「新型インフルエンザ」情報 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
「新型インフルエンザ」情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 2位
- 酒好き
- 170690人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人
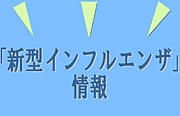











![[dir] 新型インフルエンザ](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/0/83/4270083_15s.jpg)











