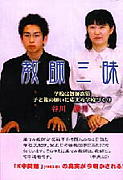学校は教師次第、学校が自浄能力を持てるかどうかも教師次第である。
子どもの個性が大切にされるためには、教師自ら個性的でなければならない。
一人一人の教師が、人として何者かであるように生きて、そのことが子どもたちに支持されて学校は活性化されていく。
そんな教師にもカメラを向ける。職員室にくつろぐ様子や授業の様子。
そしてやっぱりコメントを記して、話のねたとして教師の中にばらまいていく。お互い内に閉じるのではなくて、外に向って開き合う。
職員室がそんな風であれば協力しあい、助け合うことが当たり前のことになる。教師の仕事は「一人」ではできない。
例えば、佑未先生。
教科は英語、教壇に立ってまだ日が浅い。しかし――。
テレビには人間の品性を卑しくさせる効果もあると述べているのは、哲学者の池田晶子さん。卑しいことが当たり前になってしまったような風潮のなかだから、佑未先生の品性がことさら清々しくてりりしいのであるかもしれない。
もうとうになくなってしまった日本人の恥じらいとか含羞。
静かでやわらかな話ことばの音。
心の真ん中からつむぐ必要最少のことばの端々ににじむ誠実。
授業のなかで佑未先生のそれらが、強い意思と合わせ鏡になって生徒への思いにつながる。
教師はどうしても存在する人として何者であるかというものがなければ、生徒と向き合い、「対話」を成り立たせ、「関係」をつくることができない。
人が人に向き合ったとき、ことばが相手に伝えられるものはほんの一部分で身ぶりや手ぶり、表情、視線、声の質や抑揚、沈黙、服装、化粧などが聞き手に受け取られるのだという。
授業で教師が生徒に向き合うときも同じで、教師にもその気がなくても生徒はそんなにもたくさんのものを受けとめて、プラスとマイナスを推し量っているのであると考えなければならない。
佑未先生の前で生徒が幸せを感じるのは、その品性のたおやかさで自分を律し、生徒の気持ちを和ませてやることができるからだろう。
コミュニケーションの諸々のファクターに分解してみれば、先生の身ぶりや表情や声の質などたくさんの要素が、生徒の気分に合流して溶かされている、それが自然なことになっているからであるかもしれない。
わずか1時間の授業ではあったけれど、授業者と生徒との「関係」から読み取れたのは、例えば、子どもの感性の豊かさというものであった。子どもは、向き合った教師の「人として何者であるか」に合わせて、心を開いたり閉じたりするのであるらしいということであった。
そしてまた例えば、朋之先生。
教科は音楽、歌声が聴える学校にしたいと言う。
敗戦後、焼け野原になった日本を立て直す重要な時期に何度も、内閣総理大臣をつとめた吉田茂。その長男の吉田健一が数ある名誉の中心にすえていたのが「精神の健康」というものであった。「それは完璧を目指すよりも人間的であることを見失わない方が人間であることにとって大切である」というのが「精神の健康」につづいていたように思う。
戦後の日本人が幼稚になっていくばかりであることをいちはやく指摘した作家倉橋由美子が、その文章のすべてがいい、大人による大人が読める文章を書く人として唯一推奨していたのがこの吉田健一であるが、朋之先生の人となりついて考えるとき、この「精神の健康」ということに尽きる。
学校を評価する基準はいろいろあるけれど、学校行事がそれぞれの学校の今の姿をわかりやすく映す。体育的行事よりは文化的行事に学校の様子がよくあらわれるし、とくに合唱コンクールは学校の秩序が保たれているだけでも駄目で、戦後すぐに活躍した作家宮本百合子流に言えば「心がときほぐされて」いなければいい「うた」はつくれない。
朋之先生はこう話す。
「あの人たちは声を出しきって歌うことが、こんなにいいことだってわかった人たちだ。声を出さないこと、ぐじゃぐじゃして歌わないのがダサいこと、大きな声を出しきって歌う、いい「歌」をつくることが格好いいことだと、あの人たちはわかったんだろうね。
コンクールだから順位はつけなければならない。しかしライバル同士が聴き合って、評価しあいながら自分の学級の「歌」をつくって舞台に上がる。だから順位が決定した瞬間に賞に関係なく、リーダー同士が握手して健闘をたたえ合っている。それは自分たちの取り組みにお互いが誇りを持っているからだと思う」と。
そしてまた、こうも話す。
「中学校に入って来るときに、音楽は嫌いだ、という気分で入ってくる。それは、歌わされるから嫌いだ、ってことでしょう。中学生は大きな声を出して歌うことにものすごく抵抗がある。だから一年のスタート、一学期が本当に大切だ。声を出す楽しさを、一年のときに持たせてあげる。そして三年間やってきて、あの人たちは、声を出しきって歌うことがこんなにいいこととわかった」
この一年のスタート、一学期が大切というのは生活指導にそのまま当てはまる。
中学で喫煙が常習化(していると、校内での喫煙がやめられない)していたり、いじめをやる子どもで、中学に来てからが「初めて」という子どもは一人もいない。
しかし小学校で「人が嫌がること、悪いことをしてはいけないのよ」という一般的指導(いわゆる「心の教育」)はされていても、君が、あなたがと「特定」した指導はされていないから、中学に来て当然のごとく「いじめ」をやり「喫煙」をする。
そういう子どもたちに「一年のスタート」で、いじめは許さない、喫煙は認めないと学校(教師)の姿勢を明確にさせて生活指導を徹底できるかどうかが、三年間の教育活動の成否にかかる最重要なことになる。
合唱コンクールの舞台は、そういう生活指導の成否が明確になる場面でもあって、無惨なまでに学級の様子、強いては担任教師の仕事ぶりを映し出す。舞台への上り下りの様子、服装、髪などから、「歌」を聴く前にほとんどわかってしまうのであるが、蚊の鳴くようなと例えられるような「歌声」で「ダサい」姿をさらしてしまって、誤魔化しようがない。
子どもの個性が大切にされるためには、教師自ら個性的でなければならない。
一人一人の教師が、人として何者かであるように生きて、そのことが子どもたちに支持されて学校は活性化されていく。
そんな教師にもカメラを向ける。職員室にくつろぐ様子や授業の様子。
そしてやっぱりコメントを記して、話のねたとして教師の中にばらまいていく。お互い内に閉じるのではなくて、外に向って開き合う。
職員室がそんな風であれば協力しあい、助け合うことが当たり前のことになる。教師の仕事は「一人」ではできない。
例えば、佑未先生。
教科は英語、教壇に立ってまだ日が浅い。しかし――。
テレビには人間の品性を卑しくさせる効果もあると述べているのは、哲学者の池田晶子さん。卑しいことが当たり前になってしまったような風潮のなかだから、佑未先生の品性がことさら清々しくてりりしいのであるかもしれない。
もうとうになくなってしまった日本人の恥じらいとか含羞。
静かでやわらかな話ことばの音。
心の真ん中からつむぐ必要最少のことばの端々ににじむ誠実。
授業のなかで佑未先生のそれらが、強い意思と合わせ鏡になって生徒への思いにつながる。
教師はどうしても存在する人として何者であるかというものがなければ、生徒と向き合い、「対話」を成り立たせ、「関係」をつくることができない。
人が人に向き合ったとき、ことばが相手に伝えられるものはほんの一部分で身ぶりや手ぶり、表情、視線、声の質や抑揚、沈黙、服装、化粧などが聞き手に受け取られるのだという。
授業で教師が生徒に向き合うときも同じで、教師にもその気がなくても生徒はそんなにもたくさんのものを受けとめて、プラスとマイナスを推し量っているのであると考えなければならない。
佑未先生の前で生徒が幸せを感じるのは、その品性のたおやかさで自分を律し、生徒の気持ちを和ませてやることができるからだろう。
コミュニケーションの諸々のファクターに分解してみれば、先生の身ぶりや表情や声の質などたくさんの要素が、生徒の気分に合流して溶かされている、それが自然なことになっているからであるかもしれない。
わずか1時間の授業ではあったけれど、授業者と生徒との「関係」から読み取れたのは、例えば、子どもの感性の豊かさというものであった。子どもは、向き合った教師の「人として何者であるか」に合わせて、心を開いたり閉じたりするのであるらしいということであった。
そしてまた例えば、朋之先生。
教科は音楽、歌声が聴える学校にしたいと言う。
敗戦後、焼け野原になった日本を立て直す重要な時期に何度も、内閣総理大臣をつとめた吉田茂。その長男の吉田健一が数ある名誉の中心にすえていたのが「精神の健康」というものであった。「それは完璧を目指すよりも人間的であることを見失わない方が人間であることにとって大切である」というのが「精神の健康」につづいていたように思う。
戦後の日本人が幼稚になっていくばかりであることをいちはやく指摘した作家倉橋由美子が、その文章のすべてがいい、大人による大人が読める文章を書く人として唯一推奨していたのがこの吉田健一であるが、朋之先生の人となりついて考えるとき、この「精神の健康」ということに尽きる。
学校を評価する基準はいろいろあるけれど、学校行事がそれぞれの学校の今の姿をわかりやすく映す。体育的行事よりは文化的行事に学校の様子がよくあらわれるし、とくに合唱コンクールは学校の秩序が保たれているだけでも駄目で、戦後すぐに活躍した作家宮本百合子流に言えば「心がときほぐされて」いなければいい「うた」はつくれない。
朋之先生はこう話す。
「あの人たちは声を出しきって歌うことが、こんなにいいことだってわかった人たちだ。声を出さないこと、ぐじゃぐじゃして歌わないのがダサいこと、大きな声を出しきって歌う、いい「歌」をつくることが格好いいことだと、あの人たちはわかったんだろうね。
コンクールだから順位はつけなければならない。しかしライバル同士が聴き合って、評価しあいながら自分の学級の「歌」をつくって舞台に上がる。だから順位が決定した瞬間に賞に関係なく、リーダー同士が握手して健闘をたたえ合っている。それは自分たちの取り組みにお互いが誇りを持っているからだと思う」と。
そしてまた、こうも話す。
「中学校に入って来るときに、音楽は嫌いだ、という気分で入ってくる。それは、歌わされるから嫌いだ、ってことでしょう。中学生は大きな声を出して歌うことにものすごく抵抗がある。だから一年のスタート、一学期が本当に大切だ。声を出す楽しさを、一年のときに持たせてあげる。そして三年間やってきて、あの人たちは、声を出しきって歌うことがこんなにいいこととわかった」
この一年のスタート、一学期が大切というのは生活指導にそのまま当てはまる。
中学で喫煙が常習化(していると、校内での喫煙がやめられない)していたり、いじめをやる子どもで、中学に来てからが「初めて」という子どもは一人もいない。
しかし小学校で「人が嫌がること、悪いことをしてはいけないのよ」という一般的指導(いわゆる「心の教育」)はされていても、君が、あなたがと「特定」した指導はされていないから、中学に来て当然のごとく「いじめ」をやり「喫煙」をする。
そういう子どもたちに「一年のスタート」で、いじめは許さない、喫煙は認めないと学校(教師)の姿勢を明確にさせて生活指導を徹底できるかどうかが、三年間の教育活動の成否にかかる最重要なことになる。
合唱コンクールの舞台は、そういう生活指導の成否が明確になる場面でもあって、無惨なまでに学級の様子、強いては担任教師の仕事ぶりを映し出す。舞台への上り下りの様子、服装、髪などから、「歌」を聴く前にほとんどわかってしまうのであるが、蚊の鳴くようなと例えられるような「歌声」で「ダサい」姿をさらしてしまって、誤魔化しようがない。
|
|
|
|
|
|
|
|
いじめの加害者たち 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-