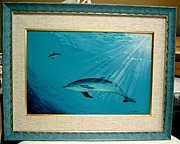私がこれが家族だと思っている家族像は
実は政府の政策だった・・・なんて・・・。
お父さんが会社で働いて、お母さんが家事全般をする。
子どもは2人。これが典型的な日本の家族だって思ってた。
戦後、1950年代半ば以降日本は高度経済成長で
飛躍的に経済が伸びる。
その影にはやはり国民一人ひとりの努力があった。
利益を上げるために企業はたくさんの人材がほしかった。
1960年代になると田舎に住んでいた若者は、跡継ぎを残し、
集団就職で都会に出て行った。
中学を卒業した今ならまだまだ子どもだと思える人たち。
かばん一つ持って汽車に乗って
その「金の卵」たちは都会にやってきた。
1970年代、やがて年頃になり、結婚適齢期になると
田舎に帰ることなくそのまま結婚した。
お見合い結婚より恋愛結婚の数が上回る。
そしてこれが核家族の始まり。
私は1960年代生まれ、ちょうどこの頃に生まれ育っている。
1973年のオイルショックで、紙製品が無くなるという情報が
確か大阪の千里で発生!これをたまたまTV放送で流し、
日本中が大騒ぎになった。私もトイレットペーパーの買いだめを
手伝った記憶がある。
打撃を受けた企業は、生き残りのための合理化を進め
企業戦士をつくったのだ。男性が会社で戦士となって働けるよう
女性は家庭に入る。専業主婦になることが期待される。
そして専業主婦になると優遇される社会制度が1980年代に
改正された。
「配偶者控除」
「配偶者特別控除」
「第3号保険者」
これらの制度。
これによって今の家族のイメージに繋がる
「性別役割分業家族」が標準世帯となっていった。
もう少し後の年代に生まれた人は
あまりこのような観念が無いのかもしれないけれど
私たちの年代はこれそのものだったように思う。
寿退社。結婚したら暗黙の了解で会社は辞める。
クリスマスケーキ。女性は25歳を過ぎたら売れ残り。
それでも会社にいるとお局と呼ばれる。
そんなもんだと思っていたのよね。それが当たり前だって。
でもよく考えたら、昔は女性も労働をしてたんだ。
もちろん農業が大半だったけど。
1980年代に入り「性別役割分業家族」が徐々に減少し
共働き家族が増えてきた。私はこの頃子育て真っ最中で
この変化にはあまり気づいてなかった。
世帯構造が変化して、1人暮らしが増加、高齢者の単独世帯や
1人親世帯、夫婦のみ世帯→そういやディンクスって言葉も
流行ったっけ?
もはや私が知る家族の典型的例は無くなりつつある。
このような社会の変化と共に、
私も自分の考えや生きてきた道がどういうものだったかを
考え直さなければいけないと思う。
自分を理解することによって
自分より年配の方、また自分より若い世代の
理解も出来るのだとつくづく思った。
実は政府の政策だった・・・なんて・・・。
お父さんが会社で働いて、お母さんが家事全般をする。
子どもは2人。これが典型的な日本の家族だって思ってた。
戦後、1950年代半ば以降日本は高度経済成長で
飛躍的に経済が伸びる。
その影にはやはり国民一人ひとりの努力があった。
利益を上げるために企業はたくさんの人材がほしかった。
1960年代になると田舎に住んでいた若者は、跡継ぎを残し、
集団就職で都会に出て行った。
中学を卒業した今ならまだまだ子どもだと思える人たち。
かばん一つ持って汽車に乗って
その「金の卵」たちは都会にやってきた。
1970年代、やがて年頃になり、結婚適齢期になると
田舎に帰ることなくそのまま結婚した。
お見合い結婚より恋愛結婚の数が上回る。
そしてこれが核家族の始まり。
私は1960年代生まれ、ちょうどこの頃に生まれ育っている。
1973年のオイルショックで、紙製品が無くなるという情報が
確か大阪の千里で発生!これをたまたまTV放送で流し、
日本中が大騒ぎになった。私もトイレットペーパーの買いだめを
手伝った記憶がある。
打撃を受けた企業は、生き残りのための合理化を進め
企業戦士をつくったのだ。男性が会社で戦士となって働けるよう
女性は家庭に入る。専業主婦になることが期待される。
そして専業主婦になると優遇される社会制度が1980年代に
改正された。
「配偶者控除」
「配偶者特別控除」
「第3号保険者」
これらの制度。
これによって今の家族のイメージに繋がる
「性別役割分業家族」が標準世帯となっていった。
もう少し後の年代に生まれた人は
あまりこのような観念が無いのかもしれないけれど
私たちの年代はこれそのものだったように思う。
寿退社。結婚したら暗黙の了解で会社は辞める。
クリスマスケーキ。女性は25歳を過ぎたら売れ残り。
それでも会社にいるとお局と呼ばれる。
そんなもんだと思っていたのよね。それが当たり前だって。
でもよく考えたら、昔は女性も労働をしてたんだ。
もちろん農業が大半だったけど。
1980年代に入り「性別役割分業家族」が徐々に減少し
共働き家族が増えてきた。私はこの頃子育て真っ最中で
この変化にはあまり気づいてなかった。
世帯構造が変化して、1人暮らしが増加、高齢者の単独世帯や
1人親世帯、夫婦のみ世帯→そういやディンクスって言葉も
流行ったっけ?
もはや私が知る家族の典型的例は無くなりつつある。
このような社会の変化と共に、
私も自分の考えや生きてきた道がどういうものだったかを
考え直さなければいけないと思う。
自分を理解することによって
自分より年配の方、また自分より若い世代の
理解も出来るのだとつくづく思った。
|
|
|
|
|
|
|
|
楽♪自分を育てる会 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
楽♪自分を育てる会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 2位
- 広島東洋カープ
- 55343人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37148人