|
|
|
|
コメント(10)
> さちママさん
御免なさい、恥をかかすようで心苦しいのですが、かといって見過ごせなかったので。
嫁入りまでは振袖、嫁いでからは留袖というのは間違いではないのですが、
振袖をちょん切って留袖にするわけではないのです。
そもそも袖の長さだけでなく、模様の位置や付け方が違います。
振袖の対義語として、袖の短いものは「広義に」留袖ということもあるのです。
裾模様の紋付だけが留袖ではなくて、
訪問着でもなんでも、袖が短ければ留袖です。
繰り返しますが、振袖の対義語としてね。
しかし、現在はそういう意味で使うことは稀で、
ご存知のように、一般的には、婚礼のときに着るような裾模様で、上半身に柄のないものを留袖といいます。
未婚のうちは振袖を着てもいいのだが、嫁いで後は袖の長いものは着られませんよ。
嫁いだら留袖にする、というのは、そういう意味です。
現代では簡便さを求めるために、下着も比翼仕立てがほとんどですし、
裾にふきをいれることもありませんが、
昔はふきがはいっていましたし、下着も留袖とは別にきちんと独立して着物の形をしていました。
ふき入りの留袖。まことに優美でよいものです。品格を感じます。
御免なさい、恥をかかすようで心苦しいのですが、かといって見過ごせなかったので。
嫁入りまでは振袖、嫁いでからは留袖というのは間違いではないのですが、
振袖をちょん切って留袖にするわけではないのです。
そもそも袖の長さだけでなく、模様の位置や付け方が違います。
振袖の対義語として、袖の短いものは「広義に」留袖ということもあるのです。
裾模様の紋付だけが留袖ではなくて、
訪問着でもなんでも、袖が短ければ留袖です。
繰り返しますが、振袖の対義語としてね。
しかし、現在はそういう意味で使うことは稀で、
ご存知のように、一般的には、婚礼のときに着るような裾模様で、上半身に柄のないものを留袖といいます。
未婚のうちは振袖を着てもいいのだが、嫁いで後は袖の長いものは着られませんよ。
嫁いだら留袖にする、というのは、そういう意味です。
現代では簡便さを求めるために、下着も比翼仕立てがほとんどですし、
裾にふきをいれることもありませんが、
昔はふきがはいっていましたし、下着も留袖とは別にきちんと独立して着物の形をしていました。
ふき入りの留袖。まことに優美でよいものです。品格を感じます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
着物の事で分らない事がある人 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
着物の事で分らない事がある人のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37834人
- 2位
- 酒好き
- 170663人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89526人
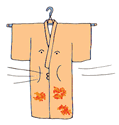
![[dir]着物](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/78/55/127855_208s.jpg)






















