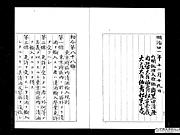公務員全員の給与を生活保護基準と同額にし十分生活できることを示すべきだ。
登記研究10月号111ページ26.3.3民商15債権動産
94ページ甲乙土地の3条許可の場合別々に同時に申請するならよいが前後して申請するのはダメ・せんだつになるからね。
12.3官報32面伊南村・舘岩村・田島の各森林組合が新設合併して南会津森林組合。
規制改革会議外国人が内国会社設立時に日本に住所を要しない。当然だ。法令に根拠がない。
民事月報11月号休眠整理は毎年行う方向で検討中。
123番地から125番地へ引きやしてさらに127番地へ引きやしたような場合別々に登記することも可能です。この場合途中の図面も必要です。
登記研究を読まない司法書士ってすごいね。六法読まない弁護士と同じくらいだよね。
短期集中求職者訓練が開始されたけど民間から給付金が出ますので課税されそうですね。役所から迂回していると思うけど。
本日から衆院選挙期日前投票・国民審査はまだです。
又地番は付番漏れとかのようだという話です。大村支局の調査士さん。離れているが同一所有者など。
2018年度から全銀行が平日6時まで当日振込み処理へ・一部銀行は土日も含め午後9時まで当日処理へ。
カタールと租税協定へ。
民事月報10月号51ページ26.8.15民2−355廃炉機構
生活困窮者支援法政令ぱぷこめ開始。
法制審議会12月予定・11.21資料掲載。
落選した沖縄県知事が埋め立て変更3件のうち2件を承認。
又地番というのはなぜできるのですか。枝とかではないですよね。
又は、又なし番がありますので、例えば又5番があれば5番がありますので、脱落地番の後付け地番の意味合いが強いと思います。
特に、地目の関係に起因しているケースも多い感じます。
畑の内書地 原野が有る場合に、字図の更正図作成の時にその原野部分を又何番という触れ合いで附番したんじゃないか?な。
ただ、例えば5番と又5番は隣接していないケースが多い気がしますので、個人的な感覚では5番と又5番は同じ所有者であるケースも多いので、脱落地番や眼鏡地で附番したとかのケースが可能性が高いのではと思います。
http://
2014.12.05(金)【選挙と選任と選定】(金子登志雄)
衆議院議員選挙中ですが、どうも盛り上がりに欠けますね。このまま行くと
投票率が大幅に下がり固定票の多い与党側優位という見方が多いようですが、
結果はどうなるのでしょうか。
さて、選挙の場合は、定員1名のところ1名しか立候補しないと無投票当選
になり、複数名が立候補した場合は有効投票の最も多い者が当選することにな
っていますが、取締役や監査役の選任については、株主総会で選任方法を自由
に定めてよいのでしょうか。会社法の教科書にも何も書いてないようです。
そこで考えてみましたが、まず、会社法329条に「役員(………)は、株
主総会の決議によって選任する」とありますから、無投票当選はなさそうです。
次に、国政選挙では自ら立候補した人からの申込みに対して選挙民が承諾の
有無の返事をする仕組みですが、役員の選任では、株主総会(会社)が申込み
側であり、被選任者が就任の承諾をする仕組みになっています。したがって、
候補者の乱立はまずありません。
株主総会の申込みは、「ABCDの4人の方は当社の取締役になってくださ
い。有効投票の多い順に3名の方に正式に申し込みます」などという失礼な方
法は現実に無理ですから「Aさんいかが」「Bさんいかが」「Cさんいかが」
と3人に個別に申込み、順に選任可決する方法にならざるを得ません(現実に
は一括して選任することが多いのですが、3つの議案というべきです)。
ABCさんは株主である必要がありません。日本人である必要もありません。
これに対して、代表取締役(や常勤監査役など)の「選定」は、「取締役の中
から」などという限定があります。
可決しても、これによって取締役が非取締役の代表取締役というものになる
わけではありません。代表取締役という取締役になるだけです。したがって、
同じ選任行為でも、「人選び」というよりも、同じ立場の複数名の間で各自の
役割(担当・任務・権限)分担を決めるという性格が強いのではないないでし
ょうか。代表権付与という用語も、人選びというよりも、権限付与という意味
合いですし、会社法が代表取締役につき「定める」と規定し、「選ぶ」としな
かったのもこういう理由でしょう。
2014.12.04(木)【設立時代表取締役の選定方法】(金子登志雄)
合同会社ではなく株式会社の設立に関してですが、会社法の規定が十分に整
備されていないためか、非取締役会設置会社の設立時代表取締役の選定方法に
迷う人が少なくないようです。
設立後であれば、取締役会設置会社なら362条、非設置会社であれば「定
款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議」と349条に規定
されています。
取締役会設置会社の設立時代表取締役については、47条に設立時取締役の
互選で定めるとありますが、非設置会社の場合は、どこに規定されているので
しょうか。
38条1項に「発起人は、…、設立時取締役(…)を選任しなければならな
い」とありますので、発起設立であれば、発起人が選定できることは問題なさ
そうです。この取締役には会社を代表する取締役も含むと考えられるからです。
次に29条には定款に任意規定を置くことができるとありますので、定款で
直接に、又は定款に「設立時取締役の互選で」などと定めることも可能です。
これで設立後の会社法349条と並ぶ関係になりましたが、設立時代表取締
役についても349序のような規定を設けておけば、迷いも混乱も生じなかっ
たのではないでしょうか。
2014.12.03(水)【合同会社を設立して】(島根・根来川弘充)
昨年、10月に知人らと合同会社を設立して、丸一年が経過いたしました。
設立した理由には、さまざまなものがあるのですが、その理由の一つとして、
業務として会社のご相談を受けるのですが、会社を持っていないのに果たして、
依頼者の立場になって相談が受けられているかという不安があったという点が
ありました。
今回、はじめての決算をおえて、本当に会社を維持することの大変さを実感
いたしました。
中でも一番苦労した点は、人件費です。当初予定していた人件費をまかなう
には、当初予定していた以上に、売上が無いと維持できないということを痛感
いたしました。
費用が相対的に安くできるということで、合同会社にしたのですが、その費
用を気にしているようでは、合同会社にすべきでないのかもしれません。
すべて厄年のためと思う事にし、また一年、気持ちを切り替えて頑張りたい
と思います。
http://
社会保険労務士法の一部を改正する法律が成立
2014-12-05 19:20:28 | いろいろ
満を持しての改正ですね。
cf. 社会保険労務士法の一部を改正する法律案
http://
第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)
第二 補佐人制度の創設
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。(第25条の9の2関係)
第三 社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25条の6等関係)
第四 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第三は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。
コメント
戸籍制度に関する研究会
2014-12-05 17:35:07 | いろいろ
戸籍制度に関する研究会 第1回会議(平成26年10月29日)
http://
戸籍制度の在り方について,検討が始められている。
コメント
五会合同研修会「事業再生の課題と方法〜各士業の視点〜」
2014-12-05 13:00:23 | 会社法(改正商法等)
昨日(4日)は,五会合同研修会「事業再生の課題と方法〜各士業の視点〜」でした。
京都司法書士会,京都弁護士会,近畿税理士会京都府支部連合会,公益社団法人京都府不動産鑑定士協会及び日本公認会計士協会京滋会の五会の協働研修会です。
次回からは,運営方法が一新するかもです。
コメント
携帯電話会社が調査嘱託に対して回答を拒否した事件(東京高裁判決)
2014-12-05 10:33:43 | 民事訴訟等
ソフトバンクモバイルの調査嘱託に対する回答拒否事件 by あおい法律事務所
http://
東京高裁平成24年10月24日判決が取り上げられている。
「調査嘱託を受けた者が,回答を求められた事項について回答すべき義務があるにもかかわらず,故意又は過失により当該義務に違反して回答しないため,調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者の権利又は利益を違法に侵害して財産的損害を被らせたと評価できる場合には,不法行為が成立する場合もあると解するのが相当である」(上掲東京高裁判決)
cf. 山田茂樹「インターネット取引被害(詐欺)事案における実務上の問題点」
http://
コメント
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に関する意見
2014-12-04 15:00:31 | いろいろ
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://
【意見】
施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。
【理由】
施行令第34条第1項は,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を「5年」と定めている。このため,実務上住所移転の経緯を証明することができない不都合が生ずる場合が数多生じている。
例えば,公的な手続においては,本人特定事項として,「住所」「氏名」「生年月日」の3点の確認を要求されることが多く,住所に変更がある場合においては,その変更を証する書面の提出が必要となる。この場合の変更を証する書面としては,住民票や戸籍の附票等がこれに該当するわけであるが,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間が「5年」であることから,その証明をすることができない場面が数多生じている。不動産の相続登記において,被相続人の住所移転の経緯を証明することができないときは,相続人全員からの上申書により「不動産の登記名義人と被相続人が同一人に相違ない」ことを上申しなければならない場合があり,不動産を取得しない他の相続人から協力を得られないときは,相続登記を申請することが困難となることもあるのである。
また,最近全国的に進められている戸籍の電算化等により戸籍の附票が改製され,その後5年を経過すると,改製前の除附票を取得することができなくなり,過去の住所移転の履歴を証明することができなくなってしまうという不都合も生じている。
電算化が進み,住所移転の経緯の記録を短期間のうちに廃棄しなければならない合理的必要性はなく,むしろ「本人確認」が厳格化している昨今においては,同一性を証明するために,市区町村長の作成による公的な書類によることが望ましい。
よって,施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。
コメント
ひとりでも遺産分割の可否
2014-12-04 10:58:46 | 不動産登記法その他
月刊登記情報2014年12月号に,半田久之「最終相続人一人からする遺産処分決定(遺産分割)に基づく登記手続について〜東京地判平成26.3.13を受けて〜」が掲載されている。
いわゆる「ひとりでも遺産分割の可否」に関する東京地裁判決についての判例評釈である。
cf. 平成26年9月24日付け「数次相続の結果,最終の相続人が1人となった場合の相続登記」
コメント
本社機能の地方移転で優遇税制
2014-12-04 10:51:28 | 会社法(改正商法等)
日刊工業新聞
http://
だからといって,移転する企業は,多くはないでしょうね。
コメント
中国で,不動産登記制度が試験的に導入
2014-12-04 10:48:39 | 不動産登記法その他
ロイター記事
http://
日司連が協力・・・していないと思います。たぶん。
コメント
日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めない規制の廃止(?)
2014-12-03 12:30:05 | 会社法(改正商法等)
日刊工業新聞
http://
「法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した」(上掲記事)
俄かには措信し難いが・・・。
許容され得る場合があるとすれば,
「新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認める」
↓
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等の設立登記を申請することを認める」
↓
「設立登記後,当該外国人は,速やかに,日本に住所を移転しなければならないものとする(住所を移転しない場合にあっては,登記官が設立登記を職権で抹消するものとする。)」
ということであろうか。
cf. 規制改革会議 第4回投資促進等ワーキング・グループ
http://
商事課長通知による昭和59年9月26日付け民四第4974号民事第四課長通知の廃止レベルの話ではなく,商業登記法第135条関連での改正が必要になると思われる。
設立登記後一定期間内に代表者の住所変更の登記の申請がされない場合には,設立の登記を職権抹消する,というような措置を講じなければ,このような規制緩和を認めるべきではないと思いますけどね。
コメント
婚外子相続分訴訟〜2000年5月時点では合憲
2014-12-03 00:17:52 | 民法改正
日経記事
http://
最高裁は,改正前民法第900条第4号ただし書の規定を,2000年5月時点で合憲,と判断。
「2000年5月当時に規定が違憲でなかったことは過去の判例が示している」「昨年の大法廷決定以前に最高裁が2000年6月時点や同年9月時点で婚外子規定を「合憲」とする判断を出していた」ということである。
http://
相続税対策で一般社団法人を活用?
2014-12-02 18:58:24 | 法人制度
日経ヴェリタスセレクト(有料会員限定)
http://
「2013年までの2年間で1万7000社近く設立され、それ以前の2年間の2.4倍に膨らんだ。東京都内で事務所を構える税理士は「すべてとは言わないが、多くが相続税対策」と明かす」
とあるが,半数近くは,旧社団法人から一般社団法人への移行である。やや誤認があるようだ。
また,「公益のために設立される建前の社団法人」とあるが,現在においては必ずしもそうではないのは,常識レベルの話。
記者さん,もう少し,きちんと調べてください。
とまれ,相続税対策で一般社団法人の活用を推奨する向きもあるようだが,いささか疑問である。
http://
内容を要約しますと、
・移行後の株式会社が取締役会設置会社の場合は、代表取締役の就任年月日を登記する。
・移行後の株式会社が取締役会を設置せず、各自代表の場合は、原則として代表取締役の就任年月日を登記しない。
(ただし、有限会社の代表取締役の登記を移記する場合は登記する。)
・移行後の株式会社は取締役会を設置せず、取締役の中から代表取締役を選定する場合は、代表取締役の就任年月日を登記する。
↑ つまり。。。オオザッパにまとめると、移行後の株式会社について、取締役の全員が代表取締役である場合のみ「代表取締役の就任年月日」の登記をしない。。。ってコトのようです。
う〜ん。。。。
全員に代表権がある場合は、取締役の就任年月日と代表取締役の就任年月日は一致するから要らない。。。ってコトなのでしょうかね〜???
。。。でですね。。。各自代表なんだケド、例外的に代表取締役の就任年月日が登記されるって、どんなケースかな??と考えてみました。
有限会社の代表取締役が登記されているというコトは、その時点では各自代表ではないというコトですよね?
特例有限会社は、代表権を有しない取締役がいる場合だけ、代表取締役の登記をするのですからね〜。
例えば、(1)有限会社時代: 取締役ABC、代表取締役AB⇒(Cが辞任して)株式会社への移行時: 取締役AB、代表取締役AB
(2)有限会社時代: 取締役ABC、代表取締役AB⇒(Cが辞任してDが移行と同時に就任(代表権あり))株式会社への移行時: 取締役ABD、代表取締役ABD(←ABは就任年月日が登記され、Dは登記されない)
↑ 合ってマスかね?
しかし。。。考えてみると、結構複雑なんじゃない?。。。って気がします。
で。。。。オシゴトのハナシですけれども、これまで気にしたコトがなかったとは言え、こんな登記(←就任年月日がない)には全く記憶がございませんで。。。。(@_@;)
これまでの案件の登記事項証明書を確認してみたのです。
もしかして、ワタシ、間違った登記を見逃してたかっ!!??(~_~;)。。。ドキドキ。。。。
結果。。。。
以前の案件で、株式会社へ移行する際に取締役会を設置しなかった会社は、何と1件しかありませんでした。ただし、その会社は、取締役2人、代表取締役1人、というケースだったので、代表取締役の就任年月日は登記されていて正解!
。。。というワケで、ワタシ自身、初めてのケースだった。。。というコトが判明し、ちょっと一安心でございました。。。。ホッ。。。
ですケド、何か納得できないなぁ〜。。。代表取締役の就任年月日も一律に登記してはダメなんでしょうか?
またしても、自分の勉強不足を実感しつつ。。。「でもさぁっ!!!意味不明!変なの〜っ!!!」と思ったりしています。
職権で登記されるので、ある意味司法書士サイドのモンダイじゃないんだケド、職権登記が間違ってないかは確認しないとダメですよね?
法務局の方たちも、大変だわ。。。
http://
登記研究10月号111ページ26.3.3民商15債権動産
94ページ甲乙土地の3条許可の場合別々に同時に申請するならよいが前後して申請するのはダメ・せんだつになるからね。
12.3官報32面伊南村・舘岩村・田島の各森林組合が新設合併して南会津森林組合。
規制改革会議外国人が内国会社設立時に日本に住所を要しない。当然だ。法令に根拠がない。
民事月報11月号休眠整理は毎年行う方向で検討中。
123番地から125番地へ引きやしてさらに127番地へ引きやしたような場合別々に登記することも可能です。この場合途中の図面も必要です。
登記研究を読まない司法書士ってすごいね。六法読まない弁護士と同じくらいだよね。
短期集中求職者訓練が開始されたけど民間から給付金が出ますので課税されそうですね。役所から迂回していると思うけど。
本日から衆院選挙期日前投票・国民審査はまだです。
又地番は付番漏れとかのようだという話です。大村支局の調査士さん。離れているが同一所有者など。
2018年度から全銀行が平日6時まで当日振込み処理へ・一部銀行は土日も含め午後9時まで当日処理へ。
カタールと租税協定へ。
民事月報10月号51ページ26.8.15民2−355廃炉機構
生活困窮者支援法政令ぱぷこめ開始。
法制審議会12月予定・11.21資料掲載。
落選した沖縄県知事が埋め立て変更3件のうち2件を承認。
又地番というのはなぜできるのですか。枝とかではないですよね。
又は、又なし番がありますので、例えば又5番があれば5番がありますので、脱落地番の後付け地番の意味合いが強いと思います。
特に、地目の関係に起因しているケースも多い感じます。
畑の内書地 原野が有る場合に、字図の更正図作成の時にその原野部分を又何番という触れ合いで附番したんじゃないか?な。
ただ、例えば5番と又5番は隣接していないケースが多い気がしますので、個人的な感覚では5番と又5番は同じ所有者であるケースも多いので、脱落地番や眼鏡地で附番したとかのケースが可能性が高いのではと思います。
http://
2014.12.05(金)【選挙と選任と選定】(金子登志雄)
衆議院議員選挙中ですが、どうも盛り上がりに欠けますね。このまま行くと
投票率が大幅に下がり固定票の多い与党側優位という見方が多いようですが、
結果はどうなるのでしょうか。
さて、選挙の場合は、定員1名のところ1名しか立候補しないと無投票当選
になり、複数名が立候補した場合は有効投票の最も多い者が当選することにな
っていますが、取締役や監査役の選任については、株主総会で選任方法を自由
に定めてよいのでしょうか。会社法の教科書にも何も書いてないようです。
そこで考えてみましたが、まず、会社法329条に「役員(………)は、株
主総会の決議によって選任する」とありますから、無投票当選はなさそうです。
次に、国政選挙では自ら立候補した人からの申込みに対して選挙民が承諾の
有無の返事をする仕組みですが、役員の選任では、株主総会(会社)が申込み
側であり、被選任者が就任の承諾をする仕組みになっています。したがって、
候補者の乱立はまずありません。
株主総会の申込みは、「ABCDの4人の方は当社の取締役になってくださ
い。有効投票の多い順に3名の方に正式に申し込みます」などという失礼な方
法は現実に無理ですから「Aさんいかが」「Bさんいかが」「Cさんいかが」
と3人に個別に申込み、順に選任可決する方法にならざるを得ません(現実に
は一括して選任することが多いのですが、3つの議案というべきです)。
ABCさんは株主である必要がありません。日本人である必要もありません。
これに対して、代表取締役(や常勤監査役など)の「選定」は、「取締役の中
から」などという限定があります。
可決しても、これによって取締役が非取締役の代表取締役というものになる
わけではありません。代表取締役という取締役になるだけです。したがって、
同じ選任行為でも、「人選び」というよりも、同じ立場の複数名の間で各自の
役割(担当・任務・権限)分担を決めるという性格が強いのではないないでし
ょうか。代表権付与という用語も、人選びというよりも、権限付与という意味
合いですし、会社法が代表取締役につき「定める」と規定し、「選ぶ」としな
かったのもこういう理由でしょう。
2014.12.04(木)【設立時代表取締役の選定方法】(金子登志雄)
合同会社ではなく株式会社の設立に関してですが、会社法の規定が十分に整
備されていないためか、非取締役会設置会社の設立時代表取締役の選定方法に
迷う人が少なくないようです。
設立後であれば、取締役会設置会社なら362条、非設置会社であれば「定
款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議」と349条に規定
されています。
取締役会設置会社の設立時代表取締役については、47条に設立時取締役の
互選で定めるとありますが、非設置会社の場合は、どこに規定されているので
しょうか。
38条1項に「発起人は、…、設立時取締役(…)を選任しなければならな
い」とありますので、発起設立であれば、発起人が選定できることは問題なさ
そうです。この取締役には会社を代表する取締役も含むと考えられるからです。
次に29条には定款に任意規定を置くことができるとありますので、定款で
直接に、又は定款に「設立時取締役の互選で」などと定めることも可能です。
これで設立後の会社法349条と並ぶ関係になりましたが、設立時代表取締
役についても349序のような規定を設けておけば、迷いも混乱も生じなかっ
たのではないでしょうか。
2014.12.03(水)【合同会社を設立して】(島根・根来川弘充)
昨年、10月に知人らと合同会社を設立して、丸一年が経過いたしました。
設立した理由には、さまざまなものがあるのですが、その理由の一つとして、
業務として会社のご相談を受けるのですが、会社を持っていないのに果たして、
依頼者の立場になって相談が受けられているかという不安があったという点が
ありました。
今回、はじめての決算をおえて、本当に会社を維持することの大変さを実感
いたしました。
中でも一番苦労した点は、人件費です。当初予定していた人件費をまかなう
には、当初予定していた以上に、売上が無いと維持できないということを痛感
いたしました。
費用が相対的に安くできるということで、合同会社にしたのですが、その費
用を気にしているようでは、合同会社にすべきでないのかもしれません。
すべて厄年のためと思う事にし、また一年、気持ちを切り替えて頑張りたい
と思います。
http://
社会保険労務士法の一部を改正する法律が成立
2014-12-05 19:20:28 | いろいろ
満を持しての改正ですね。
cf. 社会保険労務士法の一部を改正する法律案
http://
第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)
第二 補佐人制度の創設
1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)
2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。(第25条の9の2関係)
第三 社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25条の6等関係)
第四 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第三は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第1条関係)
2 その他所要の規定を整備すること。
コメント
戸籍制度に関する研究会
2014-12-05 17:35:07 | いろいろ
戸籍制度に関する研究会 第1回会議(平成26年10月29日)
http://
戸籍制度の在り方について,検討が始められている。
コメント
五会合同研修会「事業再生の課題と方法〜各士業の視点〜」
2014-12-05 13:00:23 | 会社法(改正商法等)
昨日(4日)は,五会合同研修会「事業再生の課題と方法〜各士業の視点〜」でした。
京都司法書士会,京都弁護士会,近畿税理士会京都府支部連合会,公益社団法人京都府不動産鑑定士協会及び日本公認会計士協会京滋会の五会の協働研修会です。
次回からは,運営方法が一新するかもです。
コメント
携帯電話会社が調査嘱託に対して回答を拒否した事件(東京高裁判決)
2014-12-05 10:33:43 | 民事訴訟等
ソフトバンクモバイルの調査嘱託に対する回答拒否事件 by あおい法律事務所
http://
東京高裁平成24年10月24日判決が取り上げられている。
「調査嘱託を受けた者が,回答を求められた事項について回答すべき義務があるにもかかわらず,故意又は過失により当該義務に違反して回答しないため,調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者の権利又は利益を違法に侵害して財産的損害を被らせたと評価できる場合には,不法行為が成立する場合もあると解するのが相当である」(上掲東京高裁判決)
cf. 山田茂樹「インターネット取引被害(詐欺)事案における実務上の問題点」
http://
コメント
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に関する意見
2014-12-04 15:00:31 | いろいろ
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://
【意見】
施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。
【理由】
施行令第34条第1項は,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を「5年」と定めている。このため,実務上住所移転の経緯を証明することができない不都合が生ずる場合が数多生じている。
例えば,公的な手続においては,本人特定事項として,「住所」「氏名」「生年月日」の3点の確認を要求されることが多く,住所に変更がある場合においては,その変更を証する書面の提出が必要となる。この場合の変更を証する書面としては,住民票や戸籍の附票等がこれに該当するわけであるが,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間が「5年」であることから,その証明をすることができない場面が数多生じている。不動産の相続登記において,被相続人の住所移転の経緯を証明することができないときは,相続人全員からの上申書により「不動産の登記名義人と被相続人が同一人に相違ない」ことを上申しなければならない場合があり,不動産を取得しない他の相続人から協力を得られないときは,相続登記を申請することが困難となることもあるのである。
また,最近全国的に進められている戸籍の電算化等により戸籍の附票が改製され,その後5年を経過すると,改製前の除附票を取得することができなくなり,過去の住所移転の履歴を証明することができなくなってしまうという不都合も生じている。
電算化が進み,住所移転の経緯の記録を短期間のうちに廃棄しなければならない合理的必要性はなく,むしろ「本人確認」が厳格化している昨今においては,同一性を証明するために,市区町村長の作成による公的な書類によることが望ましい。
よって,施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。
コメント
ひとりでも遺産分割の可否
2014-12-04 10:58:46 | 不動産登記法その他
月刊登記情報2014年12月号に,半田久之「最終相続人一人からする遺産処分決定(遺産分割)に基づく登記手続について〜東京地判平成26.3.13を受けて〜」が掲載されている。
いわゆる「ひとりでも遺産分割の可否」に関する東京地裁判決についての判例評釈である。
cf. 平成26年9月24日付け「数次相続の結果,最終の相続人が1人となった場合の相続登記」
コメント
本社機能の地方移転で優遇税制
2014-12-04 10:51:28 | 会社法(改正商法等)
日刊工業新聞
http://
だからといって,移転する企業は,多くはないでしょうね。
コメント
中国で,不動産登記制度が試験的に導入
2014-12-04 10:48:39 | 不動産登記法その他
ロイター記事
http://
日司連が協力・・・していないと思います。たぶん。
コメント
日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めない規制の廃止(?)
2014-12-03 12:30:05 | 会社法(改正商法等)
日刊工業新聞
http://
「法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した」(上掲記事)
俄かには措信し難いが・・・。
許容され得る場合があるとすれば,
「新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認める」
↓
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等の設立登記を申請することを認める」
↓
「設立登記後,当該外国人は,速やかに,日本に住所を移転しなければならないものとする(住所を移転しない場合にあっては,登記官が設立登記を職権で抹消するものとする。)」
ということであろうか。
cf. 規制改革会議 第4回投資促進等ワーキング・グループ
http://
商事課長通知による昭和59年9月26日付け民四第4974号民事第四課長通知の廃止レベルの話ではなく,商業登記法第135条関連での改正が必要になると思われる。
設立登記後一定期間内に代表者の住所変更の登記の申請がされない場合には,設立の登記を職権抹消する,というような措置を講じなければ,このような規制緩和を認めるべきではないと思いますけどね。
コメント
婚外子相続分訴訟〜2000年5月時点では合憲
2014-12-03 00:17:52 | 民法改正
日経記事
http://
最高裁は,改正前民法第900条第4号ただし書の規定を,2000年5月時点で合憲,と判断。
「2000年5月当時に規定が違憲でなかったことは過去の判例が示している」「昨年の大法廷決定以前に最高裁が2000年6月時点や同年9月時点で婚外子規定を「合憲」とする判断を出していた」ということである。
http://
相続税対策で一般社団法人を活用?
2014-12-02 18:58:24 | 法人制度
日経ヴェリタスセレクト(有料会員限定)
http://
「2013年までの2年間で1万7000社近く設立され、それ以前の2年間の2.4倍に膨らんだ。東京都内で事務所を構える税理士は「すべてとは言わないが、多くが相続税対策」と明かす」
とあるが,半数近くは,旧社団法人から一般社団法人への移行である。やや誤認があるようだ。
また,「公益のために設立される建前の社団法人」とあるが,現在においては必ずしもそうではないのは,常識レベルの話。
記者さん,もう少し,きちんと調べてください。
とまれ,相続税対策で一般社団法人の活用を推奨する向きもあるようだが,いささか疑問である。
http://
内容を要約しますと、
・移行後の株式会社が取締役会設置会社の場合は、代表取締役の就任年月日を登記する。
・移行後の株式会社が取締役会を設置せず、各自代表の場合は、原則として代表取締役の就任年月日を登記しない。
(ただし、有限会社の代表取締役の登記を移記する場合は登記する。)
・移行後の株式会社は取締役会を設置せず、取締役の中から代表取締役を選定する場合は、代表取締役の就任年月日を登記する。
↑ つまり。。。オオザッパにまとめると、移行後の株式会社について、取締役の全員が代表取締役である場合のみ「代表取締役の就任年月日」の登記をしない。。。ってコトのようです。
う〜ん。。。。
全員に代表権がある場合は、取締役の就任年月日と代表取締役の就任年月日は一致するから要らない。。。ってコトなのでしょうかね〜???
。。。でですね。。。各自代表なんだケド、例外的に代表取締役の就任年月日が登記されるって、どんなケースかな??と考えてみました。
有限会社の代表取締役が登記されているというコトは、その時点では各自代表ではないというコトですよね?
特例有限会社は、代表権を有しない取締役がいる場合だけ、代表取締役の登記をするのですからね〜。
例えば、(1)有限会社時代: 取締役ABC、代表取締役AB⇒(Cが辞任して)株式会社への移行時: 取締役AB、代表取締役AB
(2)有限会社時代: 取締役ABC、代表取締役AB⇒(Cが辞任してDが移行と同時に就任(代表権あり))株式会社への移行時: 取締役ABD、代表取締役ABD(←ABは就任年月日が登記され、Dは登記されない)
↑ 合ってマスかね?
しかし。。。考えてみると、結構複雑なんじゃない?。。。って気がします。
で。。。。オシゴトのハナシですけれども、これまで気にしたコトがなかったとは言え、こんな登記(←就任年月日がない)には全く記憶がございませんで。。。。(@_@;)
これまでの案件の登記事項証明書を確認してみたのです。
もしかして、ワタシ、間違った登記を見逃してたかっ!!??(~_~;)。。。ドキドキ。。。。
結果。。。。
以前の案件で、株式会社へ移行する際に取締役会を設置しなかった会社は、何と1件しかありませんでした。ただし、その会社は、取締役2人、代表取締役1人、というケースだったので、代表取締役の就任年月日は登記されていて正解!
。。。というワケで、ワタシ自身、初めてのケースだった。。。というコトが判明し、ちょっと一安心でございました。。。。ホッ。。。
ですケド、何か納得できないなぁ〜。。。代表取締役の就任年月日も一律に登記してはダメなんでしょうか?
またしても、自分の勉強不足を実感しつつ。。。「でもさぁっ!!!意味不明!変なの〜っ!!!」と思ったりしています。
職権で登記されるので、ある意味司法書士サイドのモンダイじゃないんだケド、職権登記が間違ってないかは確認しないとダメですよね?
法務局の方たちも、大変だわ。。。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
税務のイロハ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37840人
- 2位
- 酒好き
- 170673人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89537人