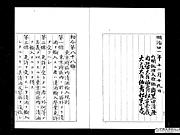とうとう人権救済法閣議決定されました。万歳。
出生届前に死亡した場合は、名未定での届け出を認めないということなんですよね。ちがう。
お問合せの件について回答させていただきます。
秦野市は厚木支局の管轄ですが,不動産登記についてのみ,地元からの強い要請を受け,西湘二宮支局
に事務を委任ということです。(厚木支局の商業・法人登記を湘南支局に事務委任しているのと同様。)
よって,これ以外の厚木支局において取り扱っている同市に関する戸籍事務及び人権擁護事務については,
引き続き厚木支局で取り扱うこととなります。
ご不明な点がありましたら,下記までお問い合わせください。
横浜地方法務局総務課
045−641−7461(代)
お寄せいただきましたメールを拝見いたしました。
お問合せの件についてですが,現時点においては,厚木支局並びにその他の支局及び出張所の統合予定はありません。
よろしくお願いいたします。
横浜地方法務局総務課
045-641−7461(代表)
夫婦財産契約と贈与税
【照会要旨】
夫婦間において、次のような内容の夫婦財産契約を締結した事例があります。この場合、贈与税の課税関係が生じますか。
「婚姻中に夫婦の一方がその名において得た財産については、民法第762条第2項の規定にかかわらず持分2分の1ずつの共有とする。」
【回答要旨】
夫婦財産契約は、財産の帰属関係を定めたものにすぎないものと考えられます。
相続税法上のみなし贈与に関する規定は、民法上の贈与に該当しないものであっても、財産上の利益の供与があったときには贈与税を課税することとしているものですから、夫婦財産契約の履行によって得た利益は、相続税法第9条の規定により贈与税の課税の対象になります。
【関係法令通達】
相続税法第9条
民法第762条
注記
平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
9.19人権救済法案閣議決定・原発は閣議決定見送り。
9.18持ち回り閣議で答弁書決定。
証券タスクフォース掲載。
電波有効利用9回目掲載。
原子力賠償28回目9.26開催。
地震保険資料掲載。
外来生物法ぱぷこめ開始。
不倫と遺贈。
東京相和銀行のまま清算。全部譲渡で免許は失効したけど。
免許取り消しなら、みなし銀行だけど。あれれれ。
夫婦財産契約で共有とするとしている場合は、取得時に半分の贈与があったとして課税するとしていたが、売却時・離婚時などに課税することに最高裁判決で変更されたそうです。
不倫の関係にある者への遺贈の遺言
Aには、妻Wと、子X、Y、Zがいる。Aは家族の目を避けてFと10年来の不倫関係にある。AはFの歓心を得るため、Fの目の前で「自分の財産の中から、1000万円をFに譲る」との自筆証書遺言を書いた。
不倫の相手方への遺贈が公序良俗に反し無効か否かは、目的の合理性(不倫関係を維持継続するのが目的かどうか)と手段の相当性(相続人の生活基盤を脅かさないか)により判断するという考え方が支配的ということだ。最判昭和61.11.20は、法律婚が破綻した後に半同棲の関係が公然と生じ、7年ほど継続している場合において、その相手方である女性に対して行われた遺贈につき、その遺贈がもっぱら生計を遺言者に頼っていた相手方の生活を保全するためになされたみものであった、不倫関係の維持継続を目的とするものでなかったし、その遺言の内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものでもなかったとの理由で、公序良俗違反ではないとした(以上、潮見佳男著「相続法第4版」)。
判例を直接あたっていないのでわからない点もあるが、「不倫関係の維持継続を目的とするものでなかった」という遺贈が果たしてあるのだろうか。公序良俗違反となるかどうかは、実際の裁判では紙一重ではなろうか。
http://
銀行を新規に設立しようとする場合、まずは「器」を作ります。
普通に株式会社を設立するわけです。
その後、「銀行業」を営むために、内閣総理大臣の免許を得るための準備をされるようです。
(銀行業の免許を取得するためには、資本金の額など、あれこれの制約が課されています。)
したがって、設立するのは「銀行」じゃない株式会社でして、商号中に「銀行」という文字を使用することができません。
設立時点では、「準備会社」なる商号の株式会社を設立することが多いようですね。
「株式会社●●設立準備会社」という感じ。
設立後、銀行になるための要件をクリアしたら、銀行業の免許を取得し、晴れて「銀行」になるわけです。
銀行業の免許を得れば、「銀行」ですから、商号中に「銀行」という文字を使用しなければなりませんよね〜。
http://
「株式会社●●銀行」に商号変更する場合、どのように定款変更決議をすれば良いのでしょうか?
銀行法によれば、「銀行」になったら「●●銀行」という商号を使用しなければならず、「銀行」でないモノは使用禁止です。
「銀行」になるのはいつか、というと、「免許を取得したとき」です。
ということは、「免許取得と同時に商号変更をしなければならない」のですが、定款変更決議も当然しなければなりません。
しかし、「免許取得日がいつか?」は具体的には分かりませんから、定款変更決議は「免許取得を条件とする決議」になるのだろうと考えておりました(ワタシもクライアントさんも)。
次に、銀行業の免許の取得というのは、商号変更の効力発生要件になるのか?という問題です。
商業登記ハンドブック(P177)によりますと、「許認可が効力発生要件かどうかは、原則として、該当条文の規定ぶりから判断する。。。」とされています。具体的には、「定款の変更は、●●大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」という規定ぶりだと、認可が効力発生要件と考えられるみたいです。
で、銀行法ですが、規定ぶりからすれば、免許取得が商号変更の効力発生要件であるようには思えません。
あ!だったら、免許を取得したことの証明書は添付書類にならないんだよねぇ?
http://
平成24年9月18日(火)持ち回り閣議案件
国会提出案件
参議院議員浜田昌良(公明)提出出産育児一時金の受取代理制度の拡充に関する質問に対する答弁書について
(厚生労働省)
参議院議員福島みずほ(社民)提出八ツ場ダムが利根川の水位を低下させる効果に関する質問に対する答弁書について
(国土交通省)
平成24年9月19日(水)繰下げ閣議案件
一般案件
今後のエネルギー・環境政策について
(内閣官房)
法律案
人権委員会設置法案
(法務・財務省)
人権擁護委員法の一部を改正する法律案
(法務省)
政 令
関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令
(財務・農林水産・経済産業省)
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
(厚生労働省)
配 布
月例経済報告
(内閣府本府)
船員法施行規則の一部改正等に関するパブリックコメントの募集について
案件番号 155121009
定めようとする命令等の題名 船員法施行規則の一部改正等
根拠法令項 船員法及び関係法令
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省海事局運航労務課
案の公示日 2012年09月19日 意見・情報受付開始日 2012年09月19日 意見・情報受付締切日 2012年10月18日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領 別紙 関連資料、その他
資料の入手方法
国土交通省海事局運航労務課にて手交
http://
第1回 総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討会議
議事次第
平成24年9月19日(水)
11:00〜11:20
官邸3階南会議室
○議事次第
1.開会
2.小宮山大臣挨拶
3.資料説明
総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討体制と検討の進め方について
4.意見交換
5.閉会
○配布資料
資料1 総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討会議の開催について
資料2 総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討について
http://
バーゼル銀行監督委員会による「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」(バーゼル・コア・プリンシプル)改訂版の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、9月14日、「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」(バーゼル・コア・プリンシプル)と題する文書を公表しました。
本文書は、バーゼル委が、同委員会のメンバー国以外の監督当局等と協力しつつ、1997年9月、1999年10月及び2006年10月にそれぞれ公表した同名の文書の改訂版です。
今回公表された文書は、2011年12月に公表された市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえた最終版で、トルコ・イスタンブールで開催された銀行監督者国際会議においても採択されました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:68KB))
「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」改訂版(原文)(要旨部分仮訳(PDF:94KB))
改訂版全体の仮訳を、近く金融庁ホームページ上に掲載予定です。
http://
IOSCO(証券監督者国際機構)による金融市場の指標に関するタスクフォースの設置について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、9月14日、金融市場の指標に関するタスクフォースを設置したことを公表しました。
内容については、以下をご覧ください。
IOSCOメディアリリース(原文)
IOSCOメディアリリース(仮訳(PDF:90KB))
http://
電波有効利用の促進に関する検討会(第9回会合)
日時
平成24年9月14日(金) 14時00分 〜 16時20分
場所
第1特別会議室(中央合同庁舎第2号館 8階)
議事次第
1. 開会
2. 議事
(1) 構成員からのプレゼンテーション
・森川構成員
・横澤構成員
・熊谷構成員
・電気通信端末機器試験事業者協議会
(2) 柔軟な無線局運用及び技術基準適合性の確保等について
3. 閉会
配布資料
資料9-1 「無線LANビジネス研究会」報告書について【森川構成員】
資料9-2 電波の有効活用に向けたガバナンスの将来像【横澤構成員】
資料9-3 電波有効利用を促進する技術の技術動向と今後の方向性【熊谷構成員】
資料9-4 適合性評価機関から見た国際整合性のある流通規律に関する一考察【電気通信端末機器試験事業者協議会】
資料9-5 柔軟な無線局の運用及び技術基準適合性の確保等について【事務局】
資料9-6 今後の進め方(案)【事務局】
参考資料9-1 電波有効利用の促進に関する検討会(第7回会合)議事要旨
http://
地震保険制度に関するプロジェクトチーム 第7回(平成24年9月19日)配布資料
資料1 東日本大震災における被災状況(日本損害保険協会)[117KB]
資料2 消費者から見た地震保険(全国消費生活相談員協会 丹野理事長)[202KB]
資料3 マンションの災害対策に関する取組み(国土交通省)[1.93MB]
http://
原子力損害賠償紛争審査会(第28回)の開催について
標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。
記
1.日時
平成24年9月26日(水曜日) 14時00分〜16時00分
2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂
3.議題
(1)農林水産物における出荷制限指示等の状況について
(2)食品新基準値の設定等に伴う農林漁業の風評被害に係る調査について
(3)紛争解決センターの活動状況について
(4)その他
http://
情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ!」を公開
本件の概要
警察庁、総務省及び経済産業省は、平成23年6月から、「不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会」(以下「官民ボード」という。)を開催しています。官民ボードは、平成23年12月に「不正アクセス防止対策に関する行動計画」を取りまとめ、これに基づき取組を進めています。
その取組の一環として、インターネット利用者にとっての利便性向上のため、情報セキュリティに関する情報を集約したポータルサイトの構築・公開について、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)を中心に検討を進めていたところであり、今般、本日から、情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ!」
(http://
担当
商務情報政策局 情報セキュリティ政策室
公表日
平成24年9月19日(水)
発表資料名
情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ!」を公開(PDF形式:95KB)
別添(PDF形式:1,768KB)
http://
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の施行状況の検討に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の施行から5年以上が経過したことを受け、平成24年6月より、中央環境審議会野生生物部会外来生物対策小委員会において法律の施行状況について検討がなされ、小委員会の報告案がとりまとめられました。
本報告案について広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、平成24年9月18日(火)から10月18日(木)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
http://
結婚前から持っていた財産は夫婦それぞれのもの。
結婚してから稼いだ財産は稼いだ人のもの。
はっきりしないものは夫婦共有財産。
家事経費の債務は連帯責任。
これが民法の原則です。
夫婦間でした契約は、結婚中、いつでも、夫婦の一方から取り消すことができる。
これも民法の原則的な規定です。
夫婦喧嘩は犬も食わない、ということなのでしょうか。
キツネとタヌキの化かし合いを奨励しているみたいです。
それでは、夫婦になる前に夫婦間契約をしておくとどうなるのでしょうか。
民法ではその結婚前の契約を重視しており、その契約があれば冒頭の夫婦財産関係の原則を変更できるものとしています。
そして、夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない、とタガをはめています。
それで、「夫及び妻がその婚姻届出の日以後に得る財産は、それぞれの共有持分を2分の1とする」との夫婦財産契約をして登記したことに基づき、夫名義で得た収入の2分の1が夫及び妻それぞれの収入であるとして、税金の申告をした人がいます。
アメリカでは夫婦合算課税というのが制度化されています。
日本でも夫婦財産契約に基礎をおけばアメリカの夫婦合算課税制度と同じ法的効果を出すことができるのではないか、という問題提起をしたわけです。
しかし、税務署の認めるところとはならず,最高裁まで争う裁判になりました。
最終判決が出て、争いは決着しました。
判決は、契約は自由だが、所得を2分の1ずつにするという夫婦間契約は課税当局に対しては無効で、契約の意味は形成された財産の夫婦間帰属を決めるということでしかないとの判断を示し、国側に軍配を上げました。
これを承けて国税庁は、所得税課税後の財産の所有権が登記の契約により2分の1ずつになるのかということについて、これを否定し、離婚や相続になったときに、その2分の1についても改めて所得税や相続税などの対象になる、との見解を示しています。
夫婦財産契約登記は民法とは異なり、税の前では無力でした。
http://
出生届前に死亡した場合は、名未定での届け出を認めないということなんですよね。ちがう。
お問合せの件について回答させていただきます。
秦野市は厚木支局の管轄ですが,不動産登記についてのみ,地元からの強い要請を受け,西湘二宮支局
に事務を委任ということです。(厚木支局の商業・法人登記を湘南支局に事務委任しているのと同様。)
よって,これ以外の厚木支局において取り扱っている同市に関する戸籍事務及び人権擁護事務については,
引き続き厚木支局で取り扱うこととなります。
ご不明な点がありましたら,下記までお問い合わせください。
横浜地方法務局総務課
045−641−7461(代)
お寄せいただきましたメールを拝見いたしました。
お問合せの件についてですが,現時点においては,厚木支局並びにその他の支局及び出張所の統合予定はありません。
よろしくお願いいたします。
横浜地方法務局総務課
045-641−7461(代表)
夫婦財産契約と贈与税
【照会要旨】
夫婦間において、次のような内容の夫婦財産契約を締結した事例があります。この場合、贈与税の課税関係が生じますか。
「婚姻中に夫婦の一方がその名において得た財産については、民法第762条第2項の規定にかかわらず持分2分の1ずつの共有とする。」
【回答要旨】
夫婦財産契約は、財産の帰属関係を定めたものにすぎないものと考えられます。
相続税法上のみなし贈与に関する規定は、民法上の贈与に該当しないものであっても、財産上の利益の供与があったときには贈与税を課税することとしているものですから、夫婦財産契約の履行によって得た利益は、相続税法第9条の規定により贈与税の課税の対象になります。
【関係法令通達】
相続税法第9条
民法第762条
注記
平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
9.19人権救済法案閣議決定・原発は閣議決定見送り。
9.18持ち回り閣議で答弁書決定。
証券タスクフォース掲載。
電波有効利用9回目掲載。
原子力賠償28回目9.26開催。
地震保険資料掲載。
外来生物法ぱぷこめ開始。
不倫と遺贈。
東京相和銀行のまま清算。全部譲渡で免許は失効したけど。
免許取り消しなら、みなし銀行だけど。あれれれ。
夫婦財産契約で共有とするとしている場合は、取得時に半分の贈与があったとして課税するとしていたが、売却時・離婚時などに課税することに最高裁判決で変更されたそうです。
不倫の関係にある者への遺贈の遺言
Aには、妻Wと、子X、Y、Zがいる。Aは家族の目を避けてFと10年来の不倫関係にある。AはFの歓心を得るため、Fの目の前で「自分の財産の中から、1000万円をFに譲る」との自筆証書遺言を書いた。
不倫の相手方への遺贈が公序良俗に反し無効か否かは、目的の合理性(不倫関係を維持継続するのが目的かどうか)と手段の相当性(相続人の生活基盤を脅かさないか)により判断するという考え方が支配的ということだ。最判昭和61.11.20は、法律婚が破綻した後に半同棲の関係が公然と生じ、7年ほど継続している場合において、その相手方である女性に対して行われた遺贈につき、その遺贈がもっぱら生計を遺言者に頼っていた相手方の生活を保全するためになされたみものであった、不倫関係の維持継続を目的とするものでなかったし、その遺言の内容が相続人らの生活の基盤を脅かすものでもなかったとの理由で、公序良俗違反ではないとした(以上、潮見佳男著「相続法第4版」)。
判例を直接あたっていないのでわからない点もあるが、「不倫関係の維持継続を目的とするものでなかった」という遺贈が果たしてあるのだろうか。公序良俗違反となるかどうかは、実際の裁判では紙一重ではなろうか。
http://
銀行を新規に設立しようとする場合、まずは「器」を作ります。
普通に株式会社を設立するわけです。
その後、「銀行業」を営むために、内閣総理大臣の免許を得るための準備をされるようです。
(銀行業の免許を取得するためには、資本金の額など、あれこれの制約が課されています。)
したがって、設立するのは「銀行」じゃない株式会社でして、商号中に「銀行」という文字を使用することができません。
設立時点では、「準備会社」なる商号の株式会社を設立することが多いようですね。
「株式会社●●設立準備会社」という感じ。
設立後、銀行になるための要件をクリアしたら、銀行業の免許を取得し、晴れて「銀行」になるわけです。
銀行業の免許を得れば、「銀行」ですから、商号中に「銀行」という文字を使用しなければなりませんよね〜。
http://
「株式会社●●銀行」に商号変更する場合、どのように定款変更決議をすれば良いのでしょうか?
銀行法によれば、「銀行」になったら「●●銀行」という商号を使用しなければならず、「銀行」でないモノは使用禁止です。
「銀行」になるのはいつか、というと、「免許を取得したとき」です。
ということは、「免許取得と同時に商号変更をしなければならない」のですが、定款変更決議も当然しなければなりません。
しかし、「免許取得日がいつか?」は具体的には分かりませんから、定款変更決議は「免許取得を条件とする決議」になるのだろうと考えておりました(ワタシもクライアントさんも)。
次に、銀行業の免許の取得というのは、商号変更の効力発生要件になるのか?という問題です。
商業登記ハンドブック(P177)によりますと、「許認可が効力発生要件かどうかは、原則として、該当条文の規定ぶりから判断する。。。」とされています。具体的には、「定款の変更は、●●大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」という規定ぶりだと、認可が効力発生要件と考えられるみたいです。
で、銀行法ですが、規定ぶりからすれば、免許取得が商号変更の効力発生要件であるようには思えません。
あ!だったら、免許を取得したことの証明書は添付書類にならないんだよねぇ?
http://
平成24年9月18日(火)持ち回り閣議案件
国会提出案件
参議院議員浜田昌良(公明)提出出産育児一時金の受取代理制度の拡充に関する質問に対する答弁書について
(厚生労働省)
参議院議員福島みずほ(社民)提出八ツ場ダムが利根川の水位を低下させる効果に関する質問に対する答弁書について
(国土交通省)
平成24年9月19日(水)繰下げ閣議案件
一般案件
今後のエネルギー・環境政策について
(内閣官房)
法律案
人権委員会設置法案
(法務・財務省)
人権擁護委員法の一部を改正する法律案
(法務省)
政 令
関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令
(財務・農林水産・経済産業省)
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
(厚生労働省)
配 布
月例経済報告
(内閣府本府)
船員法施行規則の一部改正等に関するパブリックコメントの募集について
案件番号 155121009
定めようとする命令等の題名 船員法施行規則の一部改正等
根拠法令項 船員法及び関係法令
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省海事局運航労務課
案の公示日 2012年09月19日 意見・情報受付開始日 2012年09月19日 意見・情報受付締切日 2012年10月18日
意見提出が30日未満の場合その理由
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領 別紙 関連資料、その他
資料の入手方法
国土交通省海事局運航労務課にて手交
http://
第1回 総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討会議
議事次第
平成24年9月19日(水)
11:00〜11:20
官邸3階南会議室
○議事次第
1.開会
2.小宮山大臣挨拶
3.資料説明
総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討体制と検討の進め方について
4.意見交換
5.閉会
○配布資料
資料1 総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討会議の開催について
資料2 総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討について
http://
バーゼル銀行監督委員会による「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」(バーゼル・コア・プリンシプル)改訂版の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、9月14日、「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」(バーゼル・コア・プリンシプル)と題する文書を公表しました。
本文書は、バーゼル委が、同委員会のメンバー国以外の監督当局等と協力しつつ、1997年9月、1999年10月及び2006年10月にそれぞれ公表した同名の文書の改訂版です。
今回公表された文書は、2011年12月に公表された市中協議文書に対して寄せられたコメントを踏まえた最終版で、トルコ・イスタンブールで開催された銀行監督者国際会議においても採択されました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:68KB))
「実効的な銀行監督のためのコアとなる諸原則」改訂版(原文)(要旨部分仮訳(PDF:94KB))
改訂版全体の仮訳を、近く金融庁ホームページ上に掲載予定です。
http://
IOSCO(証券監督者国際機構)による金融市場の指標に関するタスクフォースの設置について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、9月14日、金融市場の指標に関するタスクフォースを設置したことを公表しました。
内容については、以下をご覧ください。
IOSCOメディアリリース(原文)
IOSCOメディアリリース(仮訳(PDF:90KB))
http://
電波有効利用の促進に関する検討会(第9回会合)
日時
平成24年9月14日(金) 14時00分 〜 16時20分
場所
第1特別会議室(中央合同庁舎第2号館 8階)
議事次第
1. 開会
2. 議事
(1) 構成員からのプレゼンテーション
・森川構成員
・横澤構成員
・熊谷構成員
・電気通信端末機器試験事業者協議会
(2) 柔軟な無線局運用及び技術基準適合性の確保等について
3. 閉会
配布資料
資料9-1 「無線LANビジネス研究会」報告書について【森川構成員】
資料9-2 電波の有効活用に向けたガバナンスの将来像【横澤構成員】
資料9-3 電波有効利用を促進する技術の技術動向と今後の方向性【熊谷構成員】
資料9-4 適合性評価機関から見た国際整合性のある流通規律に関する一考察【電気通信端末機器試験事業者協議会】
資料9-5 柔軟な無線局の運用及び技術基準適合性の確保等について【事務局】
資料9-6 今後の進め方(案)【事務局】
参考資料9-1 電波有効利用の促進に関する検討会(第7回会合)議事要旨
http://
地震保険制度に関するプロジェクトチーム 第7回(平成24年9月19日)配布資料
資料1 東日本大震災における被災状況(日本損害保険協会)[117KB]
資料2 消費者から見た地震保険(全国消費生活相談員協会 丹野理事長)[202KB]
資料3 マンションの災害対策に関する取組み(国土交通省)[1.93MB]
http://
原子力損害賠償紛争審査会(第28回)の開催について
標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。
記
1.日時
平成24年9月26日(水曜日) 14時00分〜16時00分
2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂
3.議題
(1)農林水産物における出荷制限指示等の状況について
(2)食品新基準値の設定等に伴う農林漁業の風評被害に係る調査について
(3)紛争解決センターの活動状況について
(4)その他
http://
情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ!」を公開
本件の概要
警察庁、総務省及び経済産業省は、平成23年6月から、「不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会」(以下「官民ボード」という。)を開催しています。官民ボードは、平成23年12月に「不正アクセス防止対策に関する行動計画」を取りまとめ、これに基づき取組を進めています。
その取組の一環として、インターネット利用者にとっての利便性向上のため、情報セキュリティに関する情報を集約したポータルサイトの構築・公開について、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)を中心に検討を進めていたところであり、今般、本日から、情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ!」
(http://
担当
商務情報政策局 情報セキュリティ政策室
公表日
平成24年9月19日(水)
発表資料名
情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ!」を公開(PDF形式:95KB)
別添(PDF形式:1,768KB)
http://
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の施行状況の検討に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の施行から5年以上が経過したことを受け、平成24年6月より、中央環境審議会野生生物部会外来生物対策小委員会において法律の施行状況について検討がなされ、小委員会の報告案がとりまとめられました。
本報告案について広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、平成24年9月18日(火)から10月18日(木)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
http://
結婚前から持っていた財産は夫婦それぞれのもの。
結婚してから稼いだ財産は稼いだ人のもの。
はっきりしないものは夫婦共有財産。
家事経費の債務は連帯責任。
これが民法の原則です。
夫婦間でした契約は、結婚中、いつでも、夫婦の一方から取り消すことができる。
これも民法の原則的な規定です。
夫婦喧嘩は犬も食わない、ということなのでしょうか。
キツネとタヌキの化かし合いを奨励しているみたいです。
それでは、夫婦になる前に夫婦間契約をしておくとどうなるのでしょうか。
民法ではその結婚前の契約を重視しており、その契約があれば冒頭の夫婦財産関係の原則を変更できるものとしています。
そして、夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない、とタガをはめています。
それで、「夫及び妻がその婚姻届出の日以後に得る財産は、それぞれの共有持分を2分の1とする」との夫婦財産契約をして登記したことに基づき、夫名義で得た収入の2分の1が夫及び妻それぞれの収入であるとして、税金の申告をした人がいます。
アメリカでは夫婦合算課税というのが制度化されています。
日本でも夫婦財産契約に基礎をおけばアメリカの夫婦合算課税制度と同じ法的効果を出すことができるのではないか、という問題提起をしたわけです。
しかし、税務署の認めるところとはならず,最高裁まで争う裁判になりました。
最終判決が出て、争いは決着しました。
判決は、契約は自由だが、所得を2分の1ずつにするという夫婦間契約は課税当局に対しては無効で、契約の意味は形成された財産の夫婦間帰属を決めるということでしかないとの判断を示し、国側に軍配を上げました。
これを承けて国税庁は、所得税課税後の財産の所有権が登記の契約により2分の1ずつになるのかということについて、これを否定し、離婚や相続になったときに、その2分の1についても改めて所得税や相続税などの対象になる、との見解を示しています。
夫婦財産契約登記は民法とは異なり、税の前では無力でした。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
税務のイロハ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 楽天イーグルス
- 31945人