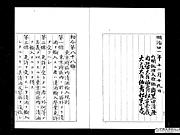租税特別措置法
(相続財産に係る◆譲渡◆所得の課税の特例)
第三十九条
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(◆相続税◆法又は第七十条の五の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による◆相続税◆額(同法第十九条の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第二十条、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該◆相続税◆額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第五十九条第一項の規定の適用があつたものを除く。)を◆譲渡◆した場合における◆譲渡◆所得に係る同法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該◆相続税◆額のうち政令で定める金額を加算した金額とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による◆譲渡◆所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた個人が◆相続税◆法第三十二条の規定による更正の請求を行つたことにより同項の◆相続税◆額が減少した場合において、当該◆相続税◆額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
ーーーーーーーーーー
租税特別措置法施行令
(相続財産に係る◆譲渡◆所得の課税の特例)
第二十五条の十六
相続又は遺贈(法第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)による財産の取得をした個人の当該相続又は遺贈につき◆相続税◆法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用がある場合には、当該個人に係る同項に規定する◆相続税◆額は、同条の規定により控除される贈与税の額がないものとして計算した場合のその者の同法の規定による納付すべき◆相続税◆額に相当する金額とする。
2 法第三十九条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の◆譲渡◆をした資産の次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、当該各号に定める金額が、当該各号に掲げる資産の◆譲渡◆所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の◆譲渡◆に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該各号に定める金額は、ないものとする。
一 当該◆譲渡◆をした資産が土地又は土地の上に存する権利(当該相続の開始の時において所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で財務省令で定めるものに該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)である場合 当該資産の取得の基因となつた相続又は遺贈に係る当該取得をした者の法第三十九条第一項に規定する◆相続税◆額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で当該◆譲渡◆の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、同項に規定する申告書の提出期限内における当該申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの(以下この項において「確定◆相続税◆額」という。)に、イに掲げる課税価格のうちにロに掲げる合計額の占める割合を乗じて計算した金額(当該◆譲渡◆に係る土地等以外の土地等の◆譲渡◆につき、既に法第三十九条第一項の規定により同項の取得費に加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除して得た金額)
イ 当該確定◆相続税◆額に係る当該取得をした者についての◆相続税◆法第十一条の二に規定する課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第十三条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。以下この項において「課税価格」という。)
ロ 当該相続又は遺贈により取得した土地等(◆相続税◆法第十九条又は第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用がある場合には同法第十九条第一項又は第二十一条の十五第一項若しくは第二十一条の十六第一項に規定する贈与により取得した財産に係る土地等を含むものとし、次に掲げる土地等を除く。)のイの課税価格の計算の基礎に算入された価額の合計額
(1) ◆相続税◆法第四十二条第二項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による物納の許可を受けて物納した土地等(同法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該土地等のうち同法第四十一条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして財務省令で定める部分に限る。)
(2) ◆相続税◆法の規定による物納申請中の土地等
二 当該◆譲渡◆をした資産が土地等以外の資産である場合 当該資産の取得の基因となつた相続又は遺贈に係る当該取得をした者の確定◆相続税◆額に、イに掲げる課税価格のうちにロに掲げる価額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該確定◆相続税◆額に係る当該取得をした者についての課税価格
ロ 当該◆譲渡◆をした資産のイの課税価格の計算の基礎に算入された価額
3 前項第一号の確定◆相続税◆額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、国税通則法第二十四条又は第二十六条に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その更正後の◆相続税◆額とし、同号ロの価額の合計額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、相続又は遺贈により取得した土地等が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一号に掲げる場合にあつては同号に定める価額を加算し、第二号に掲げる場合にあつては同号に定める価額を減算したものとする。
一 当該土地等が前項第一号ロ(1)に掲げる物納した土地等又は同号ロ(2)に掲げる物納申請中の土地等に該当しなくなつた場合 該当しなくなつた土地等に係る同号イの課税価格の計算の基礎に算入された価額
二 当該土地等が新たに前項第一号ロ(1)に掲げる物納した土地等又は同号ロ(2)に掲げる物納申請中の土地等に該当することとなつた場合 該当することとなつた土地等に係る同号イの課税価格の計算の基礎に算入された価額
(相続財産に係る◆譲渡◆所得の課税の特例)
第三十九条
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(◆相続税◆法又は第七十条の五の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による◆相続税◆額(同法第十九条の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第二十条、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該◆相続税◆額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第五十九条第一項の規定の適用があつたものを除く。)を◆譲渡◆した場合における◆譲渡◆所得に係る同法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該◆相続税◆額のうち政令で定める金額を加算した金額とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による◆譲渡◆所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた個人が◆相続税◆法第三十二条の規定による更正の請求を行つたことにより同項の◆相続税◆額が減少した場合において、当該◆相続税◆額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
ーーーーーーーーーー
租税特別措置法施行令
(相続財産に係る◆譲渡◆所得の課税の特例)
第二十五条の十六
相続又は遺贈(法第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)による財産の取得をした個人の当該相続又は遺贈につき◆相続税◆法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用がある場合には、当該個人に係る同項に規定する◆相続税◆額は、同条の規定により控除される贈与税の額がないものとして計算した場合のその者の同法の規定による納付すべき◆相続税◆額に相当する金額とする。
2 法第三十九条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の◆譲渡◆をした資産の次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、当該各号に定める金額が、当該各号に掲げる資産の◆譲渡◆所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の◆譲渡◆に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該各号に定める金額は、ないものとする。
一 当該◆譲渡◆をした資産が土地又は土地の上に存する権利(当該相続の開始の時において所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で財務省令で定めるものに該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)である場合 当該資産の取得の基因となつた相続又は遺贈に係る当該取得をした者の法第三十九条第一項に規定する◆相続税◆額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で当該◆譲渡◆の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、同項に規定する申告書の提出期限内における当該申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの(以下この項において「確定◆相続税◆額」という。)に、イに掲げる課税価格のうちにロに掲げる合計額の占める割合を乗じて計算した金額(当該◆譲渡◆に係る土地等以外の土地等の◆譲渡◆につき、既に法第三十九条第一項の規定により同項の取得費に加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除して得た金額)
イ 当該確定◆相続税◆額に係る当該取得をした者についての◆相続税◆法第十一条の二に規定する課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第十三条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。以下この項において「課税価格」という。)
ロ 当該相続又は遺贈により取得した土地等(◆相続税◆法第十九条又は第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用がある場合には同法第十九条第一項又は第二十一条の十五第一項若しくは第二十一条の十六第一項に規定する贈与により取得した財産に係る土地等を含むものとし、次に掲げる土地等を除く。)のイの課税価格の計算の基礎に算入された価額の合計額
(1) ◆相続税◆法第四十二条第二項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による物納の許可を受けて物納した土地等(同法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該土地等のうち同法第四十一条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして財務省令で定める部分に限る。)
(2) ◆相続税◆法の規定による物納申請中の土地等
二 当該◆譲渡◆をした資産が土地等以外の資産である場合 当該資産の取得の基因となつた相続又は遺贈に係る当該取得をした者の確定◆相続税◆額に、イに掲げる課税価格のうちにロに掲げる価額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該確定◆相続税◆額に係る当該取得をした者についての課税価格
ロ 当該◆譲渡◆をした資産のイの課税価格の計算の基礎に算入された価額
3 前項第一号の確定◆相続税◆額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、国税通則法第二十四条又は第二十六条に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その更正後の◆相続税◆額とし、同号ロの価額の合計額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、相続又は遺贈により取得した土地等が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一号に掲げる場合にあつては同号に定める価額を加算し、第二号に掲げる場合にあつては同号に定める価額を減算したものとする。
一 当該土地等が前項第一号ロ(1)に掲げる物納した土地等又は同号ロ(2)に掲げる物納申請中の土地等に該当しなくなつた場合 該当しなくなつた土地等に係る同号イの課税価格の計算の基礎に算入された価額
二 当該土地等が新たに前項第一号ロ(1)に掲げる物納した土地等又は同号ロ(2)に掲げる物納申請中の土地等に該当することとなつた場合 該当することとなつた土地等に係る同号イの課税価格の計算の基礎に算入された価額
|
|
|
|
コメント(1)
1 贈与等の際に支出した費用の取扱い(所基通60-2)
贈与、相続又は遺贈(以下『贈与等』)により取得した資産を譲渡した場
合において、その贈与等によりその贈与等に係る受贈者等がその資産を取得
するために通常必要な費用を支出しているときは、その費用として支出され
た金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税・不動産取得税等を除いて、その資産の取得費に算入することができます。
2 受贈者等の取得費について
取得価額が判明しているケースでは、
受贈者等の取得費は
『(贈与者等の取得価額+登録免許税等)+受贈者の登録免許税等』で計算
しますが、取得価額が不明のケースでは、
受贈者等の取得費は『収入金額×5%』(概算取得費)
で計算します。(措基通31の4-1)
また、取得価額が判明しているケースにおいて、概算取得費により計算す
る方が実際の取得費により計算するより有利である場合には、取得費として
概算取得費を採用することもできます。
3 登記費用は概算取得費に加算不可
上記2のとおり概算取得費を採用する場合には、1の適用はありません。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E+%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98+%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt&u=www.e-adviser.jp/mac/report_zeimu.html&w=%E7%99%BB%E9%8C%B2+%22%E5%85%8D%E8%A8%B1+%E7%A8%8E%22+%22%E7%9B%B8%E7%B6%9A+%E7%99%BB%E8%A8%98%22+%22%E8%AD%B2%E6%B8%A1+%E6%89%80%E5%BE%97%22&d=CKOP5bZfVGZ_&icp=1&.intl=jp
遺産を相続するときには、以下のような多額の費用が発生することがあります。
(1) 相続登記費用
(2) 登録免許税等
(3) 測量代
(4) 相続を巡る係争費用(弁護士費用等)
そして、相続人の所得税の確定申告に際し、これらの費用を不動産所得の金額の計算上必要経費に入れることが出来るのでしょうか?という話になります。
結論は、平成17年1月1日以後の相続の場合には、
(1) 相続登記費用は不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
(2) 登録免許税等も不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
これは、『贈与により取得したゴルフ会員権の名義変更手数料が譲渡所得の取得費に当たる』とする平成17年2月1日の最高裁判決を受け、取り扱いが改められたものです。
尚、上記(3)の測量代については、遺産分割により分筆を行うためのものは経費に入れることはできませんが、アパートの敷地部分を特定する必要があり事業上必要な場合には経費入ります。(4)の係争費用については、(1)(2)と違って従来どおり必要経費に入れることは出来ませんので、ご注意ください。
http://www.sohzoku.jp/oag/sohzokujyoho/070817.html
贈与、相続又は遺贈(以下『贈与等』)により取得した資産を譲渡した場
合において、その贈与等によりその贈与等に係る受贈者等がその資産を取得
するために通常必要な費用を支出しているときは、その費用として支出され
た金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税・不動産取得税等を除いて、その資産の取得費に算入することができます。
2 受贈者等の取得費について
取得価額が判明しているケースでは、
受贈者等の取得費は
『(贈与者等の取得価額+登録免許税等)+受贈者の登録免許税等』で計算
しますが、取得価額が不明のケースでは、
受贈者等の取得費は『収入金額×5%』(概算取得費)
で計算します。(措基通31の4-1)
また、取得価額が判明しているケースにおいて、概算取得費により計算す
る方が実際の取得費により計算するより有利である場合には、取得費として
概算取得費を採用することもできます。
3 登記費用は概算取得費に加算不可
上記2のとおり概算取得費を採用する場合には、1の適用はありません。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E+%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98+%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt&u=www.e-adviser.jp/mac/report_zeimu.html&w=%E7%99%BB%E9%8C%B2+%22%E5%85%8D%E8%A8%B1+%E7%A8%8E%22+%22%E7%9B%B8%E7%B6%9A+%E7%99%BB%E8%A8%98%22+%22%E8%AD%B2%E6%B8%A1+%E6%89%80%E5%BE%97%22&d=CKOP5bZfVGZ_&icp=1&.intl=jp
遺産を相続するときには、以下のような多額の費用が発生することがあります。
(1) 相続登記費用
(2) 登録免許税等
(3) 測量代
(4) 相続を巡る係争費用(弁護士費用等)
そして、相続人の所得税の確定申告に際し、これらの費用を不動産所得の金額の計算上必要経費に入れることが出来るのでしょうか?という話になります。
結論は、平成17年1月1日以後の相続の場合には、
(1) 相続登記費用は不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
(2) 登録免許税等も不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
これは、『贈与により取得したゴルフ会員権の名義変更手数料が譲渡所得の取得費に当たる』とする平成17年2月1日の最高裁判決を受け、取り扱いが改められたものです。
尚、上記(3)の測量代については、遺産分割により分筆を行うためのものは経費に入れることはできませんが、アパートの敷地部分を特定する必要があり事業上必要な場合には経費入ります。(4)の係争費用については、(1)(2)と違って従来どおり必要経費に入れることは出来ませんので、ご注意ください。
http://www.sohzoku.jp/oag/sohzokujyoho/070817.html
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
税務のイロハ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人