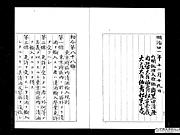1 日米相続税条約における問題点
我が国では、平成12 年の税制改正により、納税義務者の範囲の拡大が行わ
れ、日本に住所を有しない一定の日本国籍を有する者については、非居住無
制限納税義務者として無制限納税義務が課されることとなったが、日米相続
税条約3 条(1)は、「被相続人の遺産の受益者がその被相続人の死亡の時に
若しくは贈与の受益者がその贈与の時に日本国内に住所を有していた場合に
は、・・・」(筆者:下線加筆)と規定していることから、非居住無制限納税
義務者については、日米相続税条約の適用がなく 、次のような場合には、外
国税額控除による国際的二重課税が調整できないこととなる。
例えば、現在は遺産税又は相続税が存しないオーストラリア(266)で被相続
人が死亡し、相続人がアメリカに住所を有する我が国の非居住無制限納税義
務者であり、かつ、その者がアメリカに所在する日本法人の株式を相続した
ような場合である。この場合、相続人が居住無制限納税義務者であるときに
は、日米相続税条約3 条(1)(d)により、法人の設立地である日本がその株
式の所在地となるが、非居住無制限納税義務者である場合には、同条が適用
できずに両締約国の国内法により判断することとなり、結果として、両国と
も自国内に所在する財産となってしまう(267)。
このことは、外国税額控除に関する日米相続税条約5 条が、「自国の租税(本
条の規定を適用しないで計算したもの)から、相続又は贈与の時に他方の締
約国内にある財産で両締約国によって租税の対象とされるものについて当該
他方の締約国が課する租税を控除するものとする。」(筆者:下線加筆)と規
定していることからすると、結果として、両国とも自国内に所在するとした
財産に対して発生した国際的二重課税については調整できないのである。
この点については、日米相続税条約に非居住無制限納税義務者の概念を盛
り込むなど、現行税法に適合するように見直す必要があると考える。
2 租税条約締結に際して留意すべき事項
第3 章第1 節1 で述べたように、日米相続税条約は、50 年以上前に締結さ
れた「財産所在地型」の条約であり、アメリカ相続税モデル条約やOECD モデ
ル相続税条約といった、現在、世界的な流れになっている「住所地型」の条
約とは基本的な考え方において相違している。これは、日米相続税条約が、
これらのモデル相続税条約公表以前に締結された条約であることを理由とし
ているので、今後、我が国がアメリカとの相続税条約を改訂する場合、ある
いは、新たなOECD 加盟国と相続税条約を締結する場合には、上記のモデル相
続税条約の内容を取り込むべきか否かを検討する必要がある。その際に大き
な問題となるのが、「住所地型」の相続税条約と国内法との関係である(268)。
すなわち、「住所地型」の条約が第一に問題とするのは被相続人の住所地であ
るのに対して、我が国の相続税法が納税義務者の種類を区別する際に用いる
基準は、基本的には、相続人の住所地であることから(269)、例えば、被相続
人が我が国に住所を有し、(非居住無制限納税義務者ではない)相続人が国外
に住所を有する場合には、条約に基づいて我が国が全世界的な課税権を有し
たとしても、相続人の住所地が国外であるため、我が国の国内法では、これ
に無制限納税義務を課することができないのである。
このような問題については、平成12 年度の税制改正により、国内に住所を
有していない者で日本国籍を有する相続人等又は受贈者について無制限納税
義務を課す場合には、被相続人又は贈与者の住所地も基準として用いられた
(相税1 の3 二、1 の4 二)ことにより一部解消されたといえるが、依然と
して、相続人等又は受贈者の住所地が重視されていることからすると完全に
解決されているとはいえない。
したがって、我が国が「住所地型」の条約を締結する場合に発生する問題
を解決しようとするならば、国内法において、特別な場合に被相続人の住所
地が日本である場合にも相続人に無制限納税義務を課す制度の導入について
検討すべきものと考える(270)。この点について、相続制度は、その課税方式
に関わらず、死者の所有していた財産が、その者と一定の身分関係を有して
いた者によって承継される制度であり、その財産は被相続人の生前の経済活
動の結果蓄財されたものであることを考慮すると、少なくとも財産との関係
は、受益者よりも被相続人を重視すべきであるといえ、被相続人の住所地を
基準とすることに一定の合理性は認められる。
また、「住所地型」の条約を前提とした場合、相続税法の規定により、相続
人が日本国内に住所を有することを理由に無制限納税義務を課したとしても、
被相続人が国外に住所を有していれば、我が国は非住所地国となるので、租
税条約上は、無制限納税義務を課することはできないという問題も生じる。
この点については、前述した米独相続税条約11 条のように、条約の締約国間
において例外的な課税につき合意することにより解決できることから、相続
人等の住所地を重視して課税財産の範囲を決定する我が国にとって、同条約
は、非住所地国の国内法に基づく全世界的課税が排除されていない例として
非常に参考になるものといえる(271)。
その他の留意点として、まず、生前贈与の取扱いについては、多くのOECD
加盟国が、相続税の対象としており、我が国でも相続時精算課税制度が導入
されたことを考慮すると、我が国がこれらの国と今後条約を締結するに際し
ては、相続財産に贈与財産を累積して課税することから生じる課税の取扱い
について検討する余地がある。なぜなら、国内で贈与税が軽減されたとして
も、国外で高率の贈与税が賦課され、当該贈与財産が相続財産に累積されれ
ば国際的二重課税が発生する可能性が生じるからである。ただし、租税条約
により相続税における外国税額控除の対象となる租税の範囲に贈与分も含む
としても、現実に国内租税法の中に対応する実体規定がなければ意味がない
ということになりかねない点に留意する必要がある。
次に、例えば、アメリカでは、通常、信託の設定時に課税が行われるが、
ドイツでは前述したように、信託が解散されるまで課税が延期され、ドイツ
国内法により税額控除は外国税の納税義務発生以後5 年以内にドイツ相続税
の納税義務が発生した場合のみ適用されるため、米独相続税条約では、信託
や遺産財団に対する課税に関する二重課税の調整についても規定している
(米独相続税条約12 条)点も、我が国が条約を締結する際に参考になるとい
える。
http://
http://
我が国では、平成12 年の税制改正により、納税義務者の範囲の拡大が行わ
れ、日本に住所を有しない一定の日本国籍を有する者については、非居住無
制限納税義務者として無制限納税義務が課されることとなったが、日米相続
税条約3 条(1)は、「被相続人の遺産の受益者がその被相続人の死亡の時に
若しくは贈与の受益者がその贈与の時に日本国内に住所を有していた場合に
は、・・・」(筆者:下線加筆)と規定していることから、非居住無制限納税
義務者については、日米相続税条約の適用がなく 、次のような場合には、外
国税額控除による国際的二重課税が調整できないこととなる。
例えば、現在は遺産税又は相続税が存しないオーストラリア(266)で被相続
人が死亡し、相続人がアメリカに住所を有する我が国の非居住無制限納税義
務者であり、かつ、その者がアメリカに所在する日本法人の株式を相続した
ような場合である。この場合、相続人が居住無制限納税義務者であるときに
は、日米相続税条約3 条(1)(d)により、法人の設立地である日本がその株
式の所在地となるが、非居住無制限納税義務者である場合には、同条が適用
できずに両締約国の国内法により判断することとなり、結果として、両国と
も自国内に所在する財産となってしまう(267)。
このことは、外国税額控除に関する日米相続税条約5 条が、「自国の租税(本
条の規定を適用しないで計算したもの)から、相続又は贈与の時に他方の締
約国内にある財産で両締約国によって租税の対象とされるものについて当該
他方の締約国が課する租税を控除するものとする。」(筆者:下線加筆)と規
定していることからすると、結果として、両国とも自国内に所在するとした
財産に対して発生した国際的二重課税については調整できないのである。
この点については、日米相続税条約に非居住無制限納税義務者の概念を盛
り込むなど、現行税法に適合するように見直す必要があると考える。
2 租税条約締結に際して留意すべき事項
第3 章第1 節1 で述べたように、日米相続税条約は、50 年以上前に締結さ
れた「財産所在地型」の条約であり、アメリカ相続税モデル条約やOECD モデ
ル相続税条約といった、現在、世界的な流れになっている「住所地型」の条
約とは基本的な考え方において相違している。これは、日米相続税条約が、
これらのモデル相続税条約公表以前に締結された条約であることを理由とし
ているので、今後、我が国がアメリカとの相続税条約を改訂する場合、ある
いは、新たなOECD 加盟国と相続税条約を締結する場合には、上記のモデル相
続税条約の内容を取り込むべきか否かを検討する必要がある。その際に大き
な問題となるのが、「住所地型」の相続税条約と国内法との関係である(268)。
すなわち、「住所地型」の条約が第一に問題とするのは被相続人の住所地であ
るのに対して、我が国の相続税法が納税義務者の種類を区別する際に用いる
基準は、基本的には、相続人の住所地であることから(269)、例えば、被相続
人が我が国に住所を有し、(非居住無制限納税義務者ではない)相続人が国外
に住所を有する場合には、条約に基づいて我が国が全世界的な課税権を有し
たとしても、相続人の住所地が国外であるため、我が国の国内法では、これ
に無制限納税義務を課することができないのである。
このような問題については、平成12 年度の税制改正により、国内に住所を
有していない者で日本国籍を有する相続人等又は受贈者について無制限納税
義務を課す場合には、被相続人又は贈与者の住所地も基準として用いられた
(相税1 の3 二、1 の4 二)ことにより一部解消されたといえるが、依然と
して、相続人等又は受贈者の住所地が重視されていることからすると完全に
解決されているとはいえない。
したがって、我が国が「住所地型」の条約を締結する場合に発生する問題
を解決しようとするならば、国内法において、特別な場合に被相続人の住所
地が日本である場合にも相続人に無制限納税義務を課す制度の導入について
検討すべきものと考える(270)。この点について、相続制度は、その課税方式
に関わらず、死者の所有していた財産が、その者と一定の身分関係を有して
いた者によって承継される制度であり、その財産は被相続人の生前の経済活
動の結果蓄財されたものであることを考慮すると、少なくとも財産との関係
は、受益者よりも被相続人を重視すべきであるといえ、被相続人の住所地を
基準とすることに一定の合理性は認められる。
また、「住所地型」の条約を前提とした場合、相続税法の規定により、相続
人が日本国内に住所を有することを理由に無制限納税義務を課したとしても、
被相続人が国外に住所を有していれば、我が国は非住所地国となるので、租
税条約上は、無制限納税義務を課することはできないという問題も生じる。
この点については、前述した米独相続税条約11 条のように、条約の締約国間
において例外的な課税につき合意することにより解決できることから、相続
人等の住所地を重視して課税財産の範囲を決定する我が国にとって、同条約
は、非住所地国の国内法に基づく全世界的課税が排除されていない例として
非常に参考になるものといえる(271)。
その他の留意点として、まず、生前贈与の取扱いについては、多くのOECD
加盟国が、相続税の対象としており、我が国でも相続時精算課税制度が導入
されたことを考慮すると、我が国がこれらの国と今後条約を締結するに際し
ては、相続財産に贈与財産を累積して課税することから生じる課税の取扱い
について検討する余地がある。なぜなら、国内で贈与税が軽減されたとして
も、国外で高率の贈与税が賦課され、当該贈与財産が相続財産に累積されれ
ば国際的二重課税が発生する可能性が生じるからである。ただし、租税条約
により相続税における外国税額控除の対象となる租税の範囲に贈与分も含む
としても、現実に国内租税法の中に対応する実体規定がなければ意味がない
ということになりかねない点に留意する必要がある。
次に、例えば、アメリカでは、通常、信託の設定時に課税が行われるが、
ドイツでは前述したように、信託が解散されるまで課税が延期され、ドイツ
国内法により税額控除は外国税の納税義務発生以後5 年以内にドイツ相続税
の納税義務が発生した場合のみ適用されるため、米独相続税条約では、信託
や遺産財団に対する課税に関する二重課税の調整についても規定している
(米独相続税条約12 条)点も、我が国が条約を締結する際に参考になるとい
える。
http://
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
税務のイロハ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90016人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人