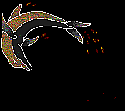以下のコミュでずっと追いかけてるのが伊勢の太陽信仰ですが、飛騨美濃尾張につながる伊勢湾の入り口のことなのでこちらにも転載したいと思います...
縄文族ネットワーク [太陽の道]
http://
謎のサルタヒコとおひらきまつり
http://
夏至の太陽が昇る二見の夫婦岩。
太陽神・天照大神が神託を下した伊勢の東、すなわち日の出の方向に位置する二見の地。
大和の真東の位置し、暁光の日の出を仰ぐ海からの日の出の最も美しい太陽信仰の霊地で、猿田彦命も海洋漁撈民である磯部たちの奉じる原始的太陽神だったとする説があります。
奈良の写真家、小川光三氏により名付けられた「太陽の道」。
日本最古の歴史を持つ大神(おおみわ)神社の御神体、三輪山を通る北緯34度32分のレイ・ラインには、東西200キロにわたって太陽をキーワードとしたパワースポットが並んでいます。
奈良県桜井市にある三輪山を中心に西に行くと、伊勢神宮鎮座ゆかりの「檜原神社」と「箸墓古墳」があります。
そこから西には二上山の「穴虫峠」、堺市に入り「萩原天神」、「大鳥大社」など多くの社寺を通り、海を越え淡路島の「伊勢の森」、そして山口県の「須佐海岸」へと至ります。
三輪山からに東には「長谷寺」や「室生寺」などいくつもの遺跡や社寺を結んで、伊勢の「斎宮跡」、さらに「神島」へと至ります。
小川氏の指摘によれば、遺跡や社寺がそれ単体で存在するのではなく、神社や古墳、そして山などに規則的な配置を読みとり、いくつもの対象を結んだ巨大なネットワーク状になっている。
さらに、大和三輪山近辺にあるいくつもの山や神社が、太陽の運行に関連して非常に規則的な配置になっているという。
また、垂仁天皇時代の都「纏向」から三輪山の頂上に、「立春」の太陽を望むラインを延長すると、伊勢神宮内宮に至るといいます。
そして、内宮神苑の入口である宇治橋の鳥居には、夫婦岩とは逆に「冬至」の太陽が昇るのです。
この二つの太陽のラインは、二見を挟むように位置しています...
古代より農耕を営んできたわれわれの祖先は、太陽の運行を何よりも重視し、それを農事の際の目印にしてきました。
そうしたことから土着の日神信仰の下、冬至の頃の太陽の勢力が衰えた時には、太陽の復活のための祭りも行われました。
このように太陽神は最も重要な自然神として崇拝されていたので、日本の古代においても各地の豪族などが中心に、これを大切に祀り崇めていました。
記紀神話の中では天照大神が太陽神ですが、古くから各地では皇祖神でない別系の男性太陽神が広く信仰されていたようです。
これらの記紀神話以前には、それぞれ各地の豪族が奉斎していた土着の太陽神(日神信仰)が存在していましたが、それらを統合(独占)した形で大和朝廷が登場してきたと考えられます。
現在でもアマテル神(天照神・天照御魂神・天照国照神、海人族が奉ずる日神・男性神格、尾張一族の祖神・火明命=天火明命。この他にも対馬系の天日神命)を祭神とする神社や祭祀は多く存在しますが、それは伊勢神宮の太陽神・アマテラス(天照大神)を遷座したのではなく、もともと各地の太陽神として崇拝されていた神に天照の名を冠したにすぎないものであるということができます。
...
縄文族ネットワーク [太陽の道]
http://
謎のサルタヒコとおひらきまつり
http://
夏至の太陽が昇る二見の夫婦岩。
太陽神・天照大神が神託を下した伊勢の東、すなわち日の出の方向に位置する二見の地。
大和の真東の位置し、暁光の日の出を仰ぐ海からの日の出の最も美しい太陽信仰の霊地で、猿田彦命も海洋漁撈民である磯部たちの奉じる原始的太陽神だったとする説があります。
奈良の写真家、小川光三氏により名付けられた「太陽の道」。
日本最古の歴史を持つ大神(おおみわ)神社の御神体、三輪山を通る北緯34度32分のレイ・ラインには、東西200キロにわたって太陽をキーワードとしたパワースポットが並んでいます。
奈良県桜井市にある三輪山を中心に西に行くと、伊勢神宮鎮座ゆかりの「檜原神社」と「箸墓古墳」があります。
そこから西には二上山の「穴虫峠」、堺市に入り「萩原天神」、「大鳥大社」など多くの社寺を通り、海を越え淡路島の「伊勢の森」、そして山口県の「須佐海岸」へと至ります。
三輪山からに東には「長谷寺」や「室生寺」などいくつもの遺跡や社寺を結んで、伊勢の「斎宮跡」、さらに「神島」へと至ります。
小川氏の指摘によれば、遺跡や社寺がそれ単体で存在するのではなく、神社や古墳、そして山などに規則的な配置を読みとり、いくつもの対象を結んだ巨大なネットワーク状になっている。
さらに、大和三輪山近辺にあるいくつもの山や神社が、太陽の運行に関連して非常に規則的な配置になっているという。
また、垂仁天皇時代の都「纏向」から三輪山の頂上に、「立春」の太陽を望むラインを延長すると、伊勢神宮内宮に至るといいます。
そして、内宮神苑の入口である宇治橋の鳥居には、夫婦岩とは逆に「冬至」の太陽が昇るのです。
この二つの太陽のラインは、二見を挟むように位置しています...
古代より農耕を営んできたわれわれの祖先は、太陽の運行を何よりも重視し、それを農事の際の目印にしてきました。
そうしたことから土着の日神信仰の下、冬至の頃の太陽の勢力が衰えた時には、太陽の復活のための祭りも行われました。
このように太陽神は最も重要な自然神として崇拝されていたので、日本の古代においても各地の豪族などが中心に、これを大切に祀り崇めていました。
記紀神話の中では天照大神が太陽神ですが、古くから各地では皇祖神でない別系の男性太陽神が広く信仰されていたようです。
これらの記紀神話以前には、それぞれ各地の豪族が奉斎していた土着の太陽神(日神信仰)が存在していましたが、それらを統合(独占)した形で大和朝廷が登場してきたと考えられます。
現在でもアマテル神(天照神・天照御魂神・天照国照神、海人族が奉ずる日神・男性神格、尾張一族の祖神・火明命=天火明命。この他にも対馬系の天日神命)を祭神とする神社や祭祀は多く存在しますが、それは伊勢神宮の太陽神・アマテラス(天照大神)を遷座したのではなく、もともと各地の太陽神として崇拝されていた神に天照の名を冠したにすぎないものであるということができます。
...
|
|
|
|
コメント(3)
■フォトアルバムその壱
夫婦岩の御来光(伊勢市二見町)
http://mixi.jp/view_album.pl?id=48234159&owner_id=4857509
夫婦岩からの真っ赤な日の出。
太陽が昇るにつれ、海を照らす一筋の道ができた。
夫婦岩の間から日の出が見れるのは4月から8月の4ヶ月間。
約2ヶ月後の6月21日の夏至祭は、その真ん中に見える富士山から太陽が昇る。
猿田彦大神縁の興玉(おきたま)をご神体とする伊勢の二見興玉神社。
その神石は海中に沈んでおり、夫婦岩からおよそ700mの沖合いにある。
夫婦岩はそのための鳥居でもあると云われてます。
夫婦岩の注連縄は年3回、5月と9月と12月に取り替えられる。
その5月5日まであと少しというタイミングだった...
夫婦岩の御来光(伊勢市二見町)
http://mixi.jp/view_album.pl?id=48234159&owner_id=4857509
夫婦岩からの真っ赤な日の出。
太陽が昇るにつれ、海を照らす一筋の道ができた。
夫婦岩の間から日の出が見れるのは4月から8月の4ヶ月間。
約2ヶ月後の6月21日の夏至祭は、その真ん中に見える富士山から太陽が昇る。
猿田彦大神縁の興玉(おきたま)をご神体とする伊勢の二見興玉神社。
その神石は海中に沈んでおり、夫婦岩からおよそ700mの沖合いにある。
夫婦岩はそのための鳥居でもあると云われてます。
夫婦岩の注連縄は年3回、5月と9月と12月に取り替えられる。
その5月5日まであと少しというタイミングだった...
■フォトアルバムその弐
神前岬の潜島(伊勢市二見町)
http://mixi.jp/view_album.pl?id=48238686&owner_id=4857509
猿田彦大神降臨の霊地とか、倭姫の天照大神船寄りの聖跡ともいわれている二見。
夫婦岩から先にも立石が並んでいる。
その真東には神前(こうざき)岬があり、大潮の干潮時にしか訪れることのできない潜島(くぐりしま)という洞門がある。
ここがサルタヒコ上陸地点だったとか、池の浦にある粟皇子神社の遥拝所だったとも。
神前岬の浜で旧暦6月15日に行っていた贄海神事のうち、道普請として潜島の洞門前の注連縄張りを行っていたが、今でも旧暦6月1日(7月大潮の頃)に近い日曜日に注連縄の張替神事がある。
この日は弥生十二夜でしたが、ちょうどそのとき干潮だったので時間のない中行ってみた...
神前岬の潜島(伊勢市二見町)
http://mixi.jp/view_album.pl?id=48238686&owner_id=4857509
猿田彦大神降臨の霊地とか、倭姫の天照大神船寄りの聖跡ともいわれている二見。
夫婦岩から先にも立石が並んでいる。
その真東には神前(こうざき)岬があり、大潮の干潮時にしか訪れることのできない潜島(くぐりしま)という洞門がある。
ここがサルタヒコ上陸地点だったとか、池の浦にある粟皇子神社の遥拝所だったとも。
神前岬の浜で旧暦6月15日に行っていた贄海神事のうち、道普請として潜島の洞門前の注連縄張りを行っていたが、今でも旧暦6月1日(7月大潮の頃)に近い日曜日に注連縄の張替神事がある。
この日は弥生十二夜でしたが、ちょうどそのとき干潮だったので時間のない中行ってみた...
島根の東出雲には、サルタヒコ(佐太大神)の誕生地といわれる加賀の潜戸という洞門がある。
伊勢の二見から昇った夏至の太陽は福岡の玄海灘に向かい、筑前二見ケ浦の夫婦岩へ沈む。
どちらも対となってつながってる...
加賀の潜戸は「かがのくけど」と読むんだけど、もともと「くげど」は洞窟の意味。
この洞窟の中には石が積まれ、死んだ子供の魂を弔う賽の河原となってる場所もあるそうです。
なので、加賀白山の菊理ヒメ信仰はここから来たのかもしれないし、しっかりとつながってそうです。
そして加賀からは海人族の太陽信仰を感じます。
『出雲国風土記』によると、暗い岩屋で佐太大神が生まれる時、母神の支佐加姫が黄金の弓で矢を射たところ洞窟が光り輝いたとあり、「光加加やけり」の加加が加賀となったと云われてます。
『日本書紀』は天孫降臨の条で「鼻長は七咫、背長は七尺、目が八咫鏡のように、またホオズキのように照り輝いている」と、サルタヒコのことを表現しています。
この容姿から天狗とか八岐大蛇を想像しがちですが、今回わたしは夫婦岩に昇る朝日を見てから神前岬の潜島へ行ったことでこのことを思い出し、あることに気づきました。
岬は「ハナ」ともいいます。
鼻長と背長はこのようなリアス式海岸にある断崖絶壁の岬の地形を表現している。
その岬にある穴の開いた洞門に、朝日や夕陽の真っ赤な太陽が射し込めば...
そして、沖縄の玉城城
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17856308&comm_id=1581098
や、クマヤ洞窟
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=44404959&comm_id=1581098
なんかの話を聞くと、みんなつながってる気がします。
もともとこの地にも、はるか古の昔から太陽に感謝する土着の素晴らしい信仰があったと感じてます。
だからこそ、サルタヒコやアマテラスの伝説に結び付けられていったんじゃないでしょうか!!!
伊勢の二見から昇った夏至の太陽は福岡の玄海灘に向かい、筑前二見ケ浦の夫婦岩へ沈む。
どちらも対となってつながってる...
加賀の潜戸は「かがのくけど」と読むんだけど、もともと「くげど」は洞窟の意味。
この洞窟の中には石が積まれ、死んだ子供の魂を弔う賽の河原となってる場所もあるそうです。
なので、加賀白山の菊理ヒメ信仰はここから来たのかもしれないし、しっかりとつながってそうです。
そして加賀からは海人族の太陽信仰を感じます。
『出雲国風土記』によると、暗い岩屋で佐太大神が生まれる時、母神の支佐加姫が黄金の弓で矢を射たところ洞窟が光り輝いたとあり、「光加加やけり」の加加が加賀となったと云われてます。
『日本書紀』は天孫降臨の条で「鼻長は七咫、背長は七尺、目が八咫鏡のように、またホオズキのように照り輝いている」と、サルタヒコのことを表現しています。
この容姿から天狗とか八岐大蛇を想像しがちですが、今回わたしは夫婦岩に昇る朝日を見てから神前岬の潜島へ行ったことでこのことを思い出し、あることに気づきました。
岬は「ハナ」ともいいます。
鼻長と背長はこのようなリアス式海岸にある断崖絶壁の岬の地形を表現している。
その岬にある穴の開いた洞門に、朝日や夕陽の真っ赤な太陽が射し込めば...
そして、沖縄の玉城城
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17856308&comm_id=1581098
や、クマヤ洞窟
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=44404959&comm_id=1581098
なんかの話を聞くと、みんなつながってる気がします。
もともとこの地にも、はるか古の昔から太陽に感謝する土着の素晴らしい信仰があったと感じてます。
だからこそ、サルタヒコやアマテラスの伝説に結び付けられていったんじゃないでしょうか!!!
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82529人