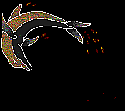2009年4月から2010年3月まで、「こよみあそび」はなごや環境大学の講座として開講されます。
環音(わをん)を中心に多岐にわたって活動している広田奈津子さんがコーディネートしています。
私も少しだけ関わってますので、順次ここに情報を載せていけたらと思います...
こよみあそび
http://
2009年
4月5日【清明】(※終了)
http://
行事 :参拝と奉納演奏
日程 :4月5日(日)
場所 :名古屋市守山区 東谷山山頂尾張戸神社
▽フォトアルバム:
http://
6月6日【芒種】(※終了)
http://
行事 :歌う田植えの日
日程 :6月6日(土)
場所 :名古屋市守山区 野田農場
6月21日【夏至】(※終了)
http://
行事 :食べるこよみあそび 梅を漬ける
日程 :6月21日(土)
場所 :名古屋市 八事山興正寺 大書院
7月18日〜19日【大暑】(※終了)
http://
行事 :山の神と一緒に森の一日
日程 :7月18日(土)〜19日(日)
場所 :岐阜県中津川市加子母各地
8月8日【立秋】(※終了)
http://
行事 :環太平洋ぼん踊り
日程 :8月8日(土)
場所 :名古屋市守山区 東谷山山頂尾張戸神社
▽フォトアルバム:
http://
10月3日【白露・秋分】(※終了)
行事 :狂言と生物多様性
日程 :10月3日(土)
中秋の名月(旧暦8/15)
場所 :名古屋市覚王山 揚輝荘
11月1日【寒露・霜降】(※終了)
行事 :歌う稲刈りの日
日程 :11月1日(日)
10時〜15時
場所 :名古屋市周辺の水田
12月5日【大雪】(※終了)
http://
行事 :いのちをいただく日
〜鹿狩り〜
日程 :12月5日(土)
10時〜17時
8時〜20時(宿泊可)
場所 :関が原のキャンプ場
2010年
2月6日【立春・雨水】(※終了)
http://
行事 :「寒の水」でお味噌を仕込む頃
日程 :2月6日(土)
場所 :岐阜県中津川市加子母各地
2月13日【小寒・大寒】(※終了)
http://
行事 :赤いものを食べていのちを語らう
日程 :2月13日(土)
場所 :名古屋市 縄文うさぎ
3月13日【啓蟄】(※予定)
http://
行事 :葦を刈り海を思う啓蟄の頃
日程 :3月13日(土)
10時〜16時
場所 :名古屋市守山区 古山田周辺の河原
管理コミュ「月夜見 [ツクヨミ]」であたためてきたトピックが形となり、ホームページの「旧暦コラム」では私も監修役として参加しています。
http://
...
環音(わをん)を中心に多岐にわたって活動している広田奈津子さんがコーディネートしています。
私も少しだけ関わってますので、順次ここに情報を載せていけたらと思います...
こよみあそび
http://
2009年
4月5日【清明】(※終了)
http://
行事 :参拝と奉納演奏
日程 :4月5日(日)
場所 :名古屋市守山区 東谷山山頂尾張戸神社
▽フォトアルバム:
http://
6月6日【芒種】(※終了)
http://
行事 :歌う田植えの日
日程 :6月6日(土)
場所 :名古屋市守山区 野田農場
6月21日【夏至】(※終了)
http://
行事 :食べるこよみあそび 梅を漬ける
日程 :6月21日(土)
場所 :名古屋市 八事山興正寺 大書院
7月18日〜19日【大暑】(※終了)
http://
行事 :山の神と一緒に森の一日
日程 :7月18日(土)〜19日(日)
場所 :岐阜県中津川市加子母各地
8月8日【立秋】(※終了)
http://
行事 :環太平洋ぼん踊り
日程 :8月8日(土)
場所 :名古屋市守山区 東谷山山頂尾張戸神社
▽フォトアルバム:
http://
10月3日【白露・秋分】(※終了)
行事 :狂言と生物多様性
日程 :10月3日(土)
中秋の名月(旧暦8/15)
場所 :名古屋市覚王山 揚輝荘
11月1日【寒露・霜降】(※終了)
行事 :歌う稲刈りの日
日程 :11月1日(日)
10時〜15時
場所 :名古屋市周辺の水田
12月5日【大雪】(※終了)
http://
行事 :いのちをいただく日
〜鹿狩り〜
日程 :12月5日(土)
10時〜17時
8時〜20時(宿泊可)
場所 :関が原のキャンプ場
2010年
2月6日【立春・雨水】(※終了)
http://
行事 :「寒の水」でお味噌を仕込む頃
日程 :2月6日(土)
場所 :岐阜県中津川市加子母各地
2月13日【小寒・大寒】(※終了)
http://
行事 :赤いものを食べていのちを語らう
日程 :2月13日(土)
場所 :名古屋市 縄文うさぎ
3月13日【啓蟄】(※予定)
http://
行事 :葦を刈り海を思う啓蟄の頃
日程 :3月13日(土)
10時〜16時
場所 :名古屋市守山区 古山田周辺の河原
管理コミュ「月夜見 [ツクヨミ]」であたためてきたトピックが形となり、ホームページの「旧暦コラム」では私も監修役として参加しています。
http://
...
|
|
|
|
コメント(5)
2009年3月27日(金)/弥生朔月
今日から三月です!
美しい言葉である「弥生」は、文字が伝わる前からイヤオヒとして、縄文時代からの言霊だったと感じています...
【サクラの「サ」のお話】
江戸時代、尾張名古屋の桜の名所は西掛所、東杉村の蔵王権現、堀川堤、そして熱田の断夫山でした。断夫山は三月三日(*)だけ入山が許され、ここから眺める熱田潟の潮干の風景は素晴らしかったといいます。
桜の語源には諸説ありますが、神聖な木という意味が込められていることには違いありません。春になると山里には桜が咲きはじめ、お花見の宴会がはじまります。すると山からサの神が降りてきて、その山桜を依り代とします。
つまりサクラとは、サの神が一時的に留まる座(クラ)なんですね。そして田植えがはじまるまで、神聖な木として里を見守り続けてくれるのです。それではサの神がなぜ田の神といわたのでしょうか。
田植えは旧暦の五月に行われていました。五月はサツキですね。サの月にサの苗(早苗)をサの乙女(早乙女)が植えます。つまり「サ」とは稲の穀霊のことを意味していました。現在でも「サ」のつく言葉の多くは、稲作の最も重要な田植えの時期に集中して残っています。
さらに田の神は案山子となって収穫の時期まで田んぼを見守り続けます。秋の収穫が終わると田んぼで焼かれて山に帰ります。長い冬の間は山の神となり、次の年の春にまた戻ってきてくれるのです。地方によっては山から降りることを「サオリ」、再び山に帰ることを「サノポリ」と呼んでいます。
(*)旧暦の三月三日は現在の4月3日頃ということになります。そしてこの三日月の日に桃の節句の雛祭りが行われ、1年で一番の大潮となる日として潮干狩りが行われました。雛祭りのルーツも川で穢れを流すことにあり、沖縄の伝統行事「浜下り(ハマウリ)」ともつながります。
ということで、この続きはサツキの田植えのころにまたしたいと思います...
今日から三月です!
美しい言葉である「弥生」は、文字が伝わる前からイヤオヒとして、縄文時代からの言霊だったと感じています...
【サクラの「サ」のお話】
江戸時代、尾張名古屋の桜の名所は西掛所、東杉村の蔵王権現、堀川堤、そして熱田の断夫山でした。断夫山は三月三日(*)だけ入山が許され、ここから眺める熱田潟の潮干の風景は素晴らしかったといいます。
桜の語源には諸説ありますが、神聖な木という意味が込められていることには違いありません。春になると山里には桜が咲きはじめ、お花見の宴会がはじまります。すると山からサの神が降りてきて、その山桜を依り代とします。
つまりサクラとは、サの神が一時的に留まる座(クラ)なんですね。そして田植えがはじまるまで、神聖な木として里を見守り続けてくれるのです。それではサの神がなぜ田の神といわたのでしょうか。
田植えは旧暦の五月に行われていました。五月はサツキですね。サの月にサの苗(早苗)をサの乙女(早乙女)が植えます。つまり「サ」とは稲の穀霊のことを意味していました。現在でも「サ」のつく言葉の多くは、稲作の最も重要な田植えの時期に集中して残っています。
さらに田の神は案山子となって収穫の時期まで田んぼを見守り続けます。秋の収穫が終わると田んぼで焼かれて山に帰ります。長い冬の間は山の神となり、次の年の春にまた戻ってきてくれるのです。地方によっては山から降りることを「サオリ」、再び山に帰ることを「サノポリ」と呼んでいます。
(*)旧暦の三月三日は現在の4月3日頃ということになります。そしてこの三日月の日に桃の節句の雛祭りが行われ、1年で一番の大潮となる日として潮干狩りが行われました。雛祭りのルーツも川で穢れを流すことにあり、沖縄の伝統行事「浜下り(ハマウリ)」ともつながります。
ということで、この続きはサツキの田植えのころにまたしたいと思います...
サのおはなし
http://www.koyomiasobi.com/column/column01.html
サ(田の神)の、クラ(おはしますところ)が語源だと言われるサクラ。
まだ肌寒い季節、山の中腹に咲いたヤマザクラは、田の神が天から降り立ったしるし。
村人はサクラの場所で神さまに挨拶をし、奉納相撲や音楽、仮装や酒宴など、とにかく神に笑い声を聞かせたそうです。
それがお花見として残っているんですね。
サの神は、農耕予祝になくてはならない山の神様。
農耕が始まり山の神様に縁が遠のいた人々は、サクラの下で山の神をにぎわい、里まで降りて来てもらうのです。
つまり、春になると山の神が来臨して田の神となります。
山から降りてくるのを「サオリ」といい、ふたたび山に帰っていくのを「サノポリ」という地方もあります。
田植えの時期はサのつく言葉がたくさん。
「五月(サツキ)=サの月」に「早苗(サナエ)=サの苗」を植える「早乙女(サオトメ)=サの巫女」…
神さまが降りて来てくださる道を「坂(サカ)」といい、お供え物として「酒(サケ)」を出し、「肴(サケナ)」を「皿(サラ)」に置いて、「催馬楽(サイバラ)=神楽(カグラ)」、「サに祝ってもらう」「幸い(サイワイ)」、「サチ多かれ」は「サの神に千も集まってほしい」、掛け声としての「サー良い良い」などなど…
元々は私たちの先祖の魂とも言われる山の神。
山の祠から里へ行き来するのは、子どもたちのことが気になっているからでしょう。
山と里の繋がり、先祖と子孫の繋がり。
さぁ今年も、サクラの下で会いましょう。
http://www.koyomiasobi.com/column/column01.html
サ(田の神)の、クラ(おはしますところ)が語源だと言われるサクラ。
まだ肌寒い季節、山の中腹に咲いたヤマザクラは、田の神が天から降り立ったしるし。
村人はサクラの場所で神さまに挨拶をし、奉納相撲や音楽、仮装や酒宴など、とにかく神に笑い声を聞かせたそうです。
それがお花見として残っているんですね。
サの神は、農耕予祝になくてはならない山の神様。
農耕が始まり山の神様に縁が遠のいた人々は、サクラの下で山の神をにぎわい、里まで降りて来てもらうのです。
つまり、春になると山の神が来臨して田の神となります。
山から降りてくるのを「サオリ」といい、ふたたび山に帰っていくのを「サノポリ」という地方もあります。
田植えの時期はサのつく言葉がたくさん。
「五月(サツキ)=サの月」に「早苗(サナエ)=サの苗」を植える「早乙女(サオトメ)=サの巫女」…
神さまが降りて来てくださる道を「坂(サカ)」といい、お供え物として「酒(サケ)」を出し、「肴(サケナ)」を「皿(サラ)」に置いて、「催馬楽(サイバラ)=神楽(カグラ)」、「サに祝ってもらう」「幸い(サイワイ)」、「サチ多かれ」は「サの神に千も集まってほしい」、掛け声としての「サー良い良い」などなど…
元々は私たちの先祖の魂とも言われる山の神。
山の祠から里へ行き来するのは、子どもたちのことが気になっているからでしょう。
山と里の繋がり、先祖と子孫の繋がり。
さぁ今年も、サクラの下で会いましょう。
神にぎわい
http://www.koyomiasobi.com/column/column02.html
うたや踊り、舞台、相撲や綱引き、仮装、お神輿など、神さまと一緒に楽しむ神にぎわい。
そのむかし、機嫌をそこねて洞窟に隠れ、戸を閉めてしまった太陽の女神アマテラスを外へ誘い出したのが、’あまのうずめ’だとか。
そのあまのうずめが踊ったのが、どうやら今で言うストリップ。ヤンヤヤンヤ楽しそうな歓声にウズウズして、ついに戸を開けてしまったアマテラス。その気持ち、よくわかります。
この神にぎわいのおかげで、暗闇の世界は再び明るくなったというわけですね。ビバ!ストリップ。
各地には様々な神にぎわいが残っています。
奄美大島の大棚地区では、十五夜の豊年祭に男たちが本気の奉納相撲を行います。そして相撲の合間に中入りとして入ってくるのが、本気で仮装した女たち。アフロ頭のおばぁや、太いまゆげがつながった女性、力士の着ぐるみや、奇妙なドレス…。真剣な顔だからまた笑えます。
相撲の後には炎を囲んだ輪踊りが始まり、夜がふけるにつれ歌詞もエロティックになっていきます。
本当はビジネス業界ではなく、コミュニティの中にこそあるアートやエロス。
神さまに向き合い、でもどこかアッケラカンとした、それは人間らしい、神々との関わりです。
http://www.koyomiasobi.com/column/column02.html
うたや踊り、舞台、相撲や綱引き、仮装、お神輿など、神さまと一緒に楽しむ神にぎわい。
そのむかし、機嫌をそこねて洞窟に隠れ、戸を閉めてしまった太陽の女神アマテラスを外へ誘い出したのが、’あまのうずめ’だとか。
そのあまのうずめが踊ったのが、どうやら今で言うストリップ。ヤンヤヤンヤ楽しそうな歓声にウズウズして、ついに戸を開けてしまったアマテラス。その気持ち、よくわかります。
この神にぎわいのおかげで、暗闇の世界は再び明るくなったというわけですね。ビバ!ストリップ。
各地には様々な神にぎわいが残っています。
奄美大島の大棚地区では、十五夜の豊年祭に男たちが本気の奉納相撲を行います。そして相撲の合間に中入りとして入ってくるのが、本気で仮装した女たち。アフロ頭のおばぁや、太いまゆげがつながった女性、力士の着ぐるみや、奇妙なドレス…。真剣な顔だからまた笑えます。
相撲の後には炎を囲んだ輪踊りが始まり、夜がふけるにつれ歌詞もエロティックになっていきます。
本当はビジネス業界ではなく、コミュニティの中にこそあるアートやエロス。
神さまに向き合い、でもどこかアッケラカンとした、それは人間らしい、神々との関わりです。
お天道様とからだ
http://www.koyomiasobi.com/column/column03.html
西暦では深夜12時に日付が変わりますが、
旧暦での一日の始まりは日が昇る時です。
時間は、昼の長さと夜の長さを六等分して、鐘を鳴らしていました。
日の出から、明け六つ、五つ、四つ、九つ、八つ、七つがお昼。
日暮れから、暮れ六つ、五つ、四つ、九つ、八つ、七つが夜。
だから夏では昼の一刻の長さが長くなり、冬では短くなるのです。
人間の行動はお天道様と一緒。だから仕事の時間も夏は長く、冬は短く。
日が沈んで月が昇ると、人の一日は終わり、神々の一日の始まり。モノノケたちが遊び始める時間です。
夏は涼しい早朝に働いて、暑い昼間は寝るのが一番。
夜が長い冬は、家族が一緒に過ごし、物語を語り継ぐ大切な季節です。
そして昼と夜の長さが全く同じになる春分と秋分は、神々と繋がる特別な日として祝いました。
日本が一日を24時間で区切り、季節もお天道様も関係なく過ごし始めたのは明治以降、ほんの140年たらず。
人工的に時を区切り、土地を区切り、効率的に四角く四角く…、今や「世界で一番忙しい」なんて言われる国になりました。
夜を明るく照らすから、モノノケたちも姿を消し、人の体も、植物の体も、ちょっとずつ狂いはじめてしまいました。
季節も関係なく働かせるエネルギーは、地球の生態系を限界まで追い込もうとしています。
そんな中、お天道様に沿って暮らすことが見直され始めています。
今年から愛知のカフェ「イニュニック」は、夜明け後から日暮れ頃までの営業時間に変更。
たいせつな人とゆっくりほっこり、お天道様にそったライフスタイル、いかがですか?
http://www.koyomiasobi.com/column/column03.html
西暦では深夜12時に日付が変わりますが、
旧暦での一日の始まりは日が昇る時です。
時間は、昼の長さと夜の長さを六等分して、鐘を鳴らしていました。
日の出から、明け六つ、五つ、四つ、九つ、八つ、七つがお昼。
日暮れから、暮れ六つ、五つ、四つ、九つ、八つ、七つが夜。
だから夏では昼の一刻の長さが長くなり、冬では短くなるのです。
人間の行動はお天道様と一緒。だから仕事の時間も夏は長く、冬は短く。
日が沈んで月が昇ると、人の一日は終わり、神々の一日の始まり。モノノケたちが遊び始める時間です。
夏は涼しい早朝に働いて、暑い昼間は寝るのが一番。
夜が長い冬は、家族が一緒に過ごし、物語を語り継ぐ大切な季節です。
そして昼と夜の長さが全く同じになる春分と秋分は、神々と繋がる特別な日として祝いました。
日本が一日を24時間で区切り、季節もお天道様も関係なく過ごし始めたのは明治以降、ほんの140年たらず。
人工的に時を区切り、土地を区切り、効率的に四角く四角く…、今や「世界で一番忙しい」なんて言われる国になりました。
夜を明るく照らすから、モノノケたちも姿を消し、人の体も、植物の体も、ちょっとずつ狂いはじめてしまいました。
季節も関係なく働かせるエネルギーは、地球の生態系を限界まで追い込もうとしています。
そんな中、お天道様に沿って暮らすことが見直され始めています。
今年から愛知のカフェ「イニュニック」は、夜明け後から日暮れ頃までの営業時間に変更。
たいせつな人とゆっくりほっこり、お天道様にそったライフスタイル、いかがですか?
田の神むかえる女たち
http://www.koyomiasobi.com/column/column04.html
旧暦五月は早苗月とも呼ばれる田植え月。
春に山サクラのもとで もてなした神を、いよいよ里へ迎え入れる大切な季節です。
女たちは早乙女になるために、田植えに先立ち、禊(みそぎ)--「五月忌み」を行います。
それに活躍するのが菖蒲。
紫色の大きな花がさくアヤメではなく、菖蒲はサトイモの仲間の地味な花です。
さわやかな香りが虫を除け、物が腐りやすい「忌み月」の病気をはらってくれます。
家の軒に菖蒲を挿し、前日には菖蒲を枕に入れて眠り、当日は菖蒲の鉢巻をして菖蒲湯に入り、しまいには亭主の尻を菖蒲で叩いて家を追い出し、女たちだけで家にこもって禊をしたそうです。
禊とは言え、女が集まってワイワイやったのでしょう。何だか楽しそうです。
田植えの日には、身を清めた早乙女たちが揃い、苗に宿る穀霊に唄を歌いながら植えてゆきます。
田を手伝う牛たちも派手に着飾り、子どもたちがはしゃぎ、男たちは太鼓を打って華やかに神をにぎわう--
近年のような機械がなかった時代、田んぼはもっともっと賑やかな様子です。
山の神は水に宿り、里に降りて田を潤し、案山子(カカシ)に宿って稲を実らせてくれます。
種をまくのは人間でも、それを育ててくれるのは自然の力に他ならないのだと、感謝をささげる行事が、今もあちこちで残っています。
私たちに馴染み深いお米。
山の水と土の力に感謝しながら味わうと、じんわり甘さが広がります。
http://www.koyomiasobi.com/column/column04.html
旧暦五月は早苗月とも呼ばれる田植え月。
春に山サクラのもとで もてなした神を、いよいよ里へ迎え入れる大切な季節です。
女たちは早乙女になるために、田植えに先立ち、禊(みそぎ)--「五月忌み」を行います。
それに活躍するのが菖蒲。
紫色の大きな花がさくアヤメではなく、菖蒲はサトイモの仲間の地味な花です。
さわやかな香りが虫を除け、物が腐りやすい「忌み月」の病気をはらってくれます。
家の軒に菖蒲を挿し、前日には菖蒲を枕に入れて眠り、当日は菖蒲の鉢巻をして菖蒲湯に入り、しまいには亭主の尻を菖蒲で叩いて家を追い出し、女たちだけで家にこもって禊をしたそうです。
禊とは言え、女が集まってワイワイやったのでしょう。何だか楽しそうです。
田植えの日には、身を清めた早乙女たちが揃い、苗に宿る穀霊に唄を歌いながら植えてゆきます。
田を手伝う牛たちも派手に着飾り、子どもたちがはしゃぎ、男たちは太鼓を打って華やかに神をにぎわう--
近年のような機械がなかった時代、田んぼはもっともっと賑やかな様子です。
山の神は水に宿り、里に降りて田を潤し、案山子(カカシ)に宿って稲を実らせてくれます。
種をまくのは人間でも、それを育ててくれるのは自然の力に他ならないのだと、感謝をささげる行事が、今もあちこちで残っています。
私たちに馴染み深いお米。
山の水と土の力に感謝しながら味わうと、じんわり甘さが広がります。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170698人