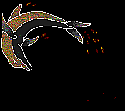長良川や木曽川が長い時間をかけて形成した平野の微高地や、その周囲の山の山麓に古くから人々が住み始めていた。
岐阜市内には縄文時代の御望遺跡など、長良にも遺跡がみられる。
弥生時代の遺跡では梅林で土器が出土し、華陽地区で遺跡が発掘されている。
この辺りの豪族がヤマト朝廷と関わっていく時代に、現在でいう古墳が作られていった。
岐阜市では最大級の琴塚古墳のほか、長良や岩など市内各地に古墳がみられる。
大化改新によって大和朝廷は中央集権が確立し、各地に国司を置くなど地方制度などさまざま制度を整えた。
住民には戸籍制度や条里制を設け、公地公民として農耕に従事させ、豪族支配から国の支配となっていった。
岐阜市地域の条里制は、主に岐阜市の中心部から長良川以南にかけて、以北では福富、三輪、秋沢などに設けられていた。
白鳳時代になると各地の豪族たちが寺院を建立するようになった。
市内には厚見寺のほか、現在は廃寺となった大宝寺、鍵屋寺、長良寺などがあった。
奈良時代ころになると、主に都の大寺院や貴族が所有する荘園ができ、その範囲は全国各地にみられた。
市内には茜部荘、平田荘、市橋荘、鵜飼荘、芥見荘などがあった。
このころ美濃に土着した摂津源氏の流れを汲む氏族が荘園の現地荘官となる。
美濃源氏は清和天皇を祖とする清和源氏の一流で、平安時代末期から鎌倉時代初頭のころ、土岐光衡が美濃国土岐郡に土着したことに始まる。
土岐氏が最も著名な一族であり、その支流氏族に明智氏や馬場氏などがある。
美濃源氏土岐氏は鎌倉時代にかけて勢力を拡大し、やがて美濃の台頭となっていった。
南北朝時代には美濃国の守護となり、拠点を土岐郡から長森や革手(川手)に移し、美濃の中心地となった。
土岐氏は一時、美濃のほか尾張、伊勢守護を兼任しており、革手は都から貴族や連歌師など文人がたびたび訪れ、全国的に京都を除くと鎌倉、山口と並ぶ日本三大都市のような賑わいがあった。
以後、土岐氏の時代が続くが、守護代の斎藤氏が活躍し、応仁・文明のころには斎藤妙椿が勢力を持っていた。
のち、船田合戦や城田寺合戦などの内紛が起こり、11代土岐頼芸を追放した斎藤道三が美濃国を手中にし、「井之口」と呼ばれた稲葉山山麓に城下町を形成した。
永禄10年(1567)、道三の孫、龍興を倒し美濃の国を手中にした信長は、井之口を「岐阜」と改め、「楽市楽座」を行い、城下町を発展させ、宣教師フロイスによって町の賑わいはヨーロッパまで知られることとなった。
信長が根拠地を岐阜から安土に移した後、岐阜城は嫡男織田信忠に与えられ、さらに池田元助、池田輝政、豊臣秀勝、そして信長の孫織田秀信が城主となった。
慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いの前哨戦において、豊臣方の岐阜城は落城した。
...
岐阜市内には縄文時代の御望遺跡など、長良にも遺跡がみられる。
弥生時代の遺跡では梅林で土器が出土し、華陽地区で遺跡が発掘されている。
この辺りの豪族がヤマト朝廷と関わっていく時代に、現在でいう古墳が作られていった。
岐阜市では最大級の琴塚古墳のほか、長良や岩など市内各地に古墳がみられる。
大化改新によって大和朝廷は中央集権が確立し、各地に国司を置くなど地方制度などさまざま制度を整えた。
住民には戸籍制度や条里制を設け、公地公民として農耕に従事させ、豪族支配から国の支配となっていった。
岐阜市地域の条里制は、主に岐阜市の中心部から長良川以南にかけて、以北では福富、三輪、秋沢などに設けられていた。
白鳳時代になると各地の豪族たちが寺院を建立するようになった。
市内には厚見寺のほか、現在は廃寺となった大宝寺、鍵屋寺、長良寺などがあった。
奈良時代ころになると、主に都の大寺院や貴族が所有する荘園ができ、その範囲は全国各地にみられた。
市内には茜部荘、平田荘、市橋荘、鵜飼荘、芥見荘などがあった。
このころ美濃に土着した摂津源氏の流れを汲む氏族が荘園の現地荘官となる。
美濃源氏は清和天皇を祖とする清和源氏の一流で、平安時代末期から鎌倉時代初頭のころ、土岐光衡が美濃国土岐郡に土着したことに始まる。
土岐氏が最も著名な一族であり、その支流氏族に明智氏や馬場氏などがある。
美濃源氏土岐氏は鎌倉時代にかけて勢力を拡大し、やがて美濃の台頭となっていった。
南北朝時代には美濃国の守護となり、拠点を土岐郡から長森や革手(川手)に移し、美濃の中心地となった。
土岐氏は一時、美濃のほか尾張、伊勢守護を兼任しており、革手は都から貴族や連歌師など文人がたびたび訪れ、全国的に京都を除くと鎌倉、山口と並ぶ日本三大都市のような賑わいがあった。
以後、土岐氏の時代が続くが、守護代の斎藤氏が活躍し、応仁・文明のころには斎藤妙椿が勢力を持っていた。
のち、船田合戦や城田寺合戦などの内紛が起こり、11代土岐頼芸を追放した斎藤道三が美濃国を手中にし、「井之口」と呼ばれた稲葉山山麓に城下町を形成した。
永禄10年(1567)、道三の孫、龍興を倒し美濃の国を手中にした信長は、井之口を「岐阜」と改め、「楽市楽座」を行い、城下町を発展させ、宣教師フロイスによって町の賑わいはヨーロッパまで知られることとなった。
信長が根拠地を岐阜から安土に移した後、岐阜城は嫡男織田信忠に与えられ、さらに池田元助、池田輝政、豊臣秀勝、そして信長の孫織田秀信が城主となった。
慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いの前哨戦において、豊臣方の岐阜城は落城した。
...
|
|
|
|
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170690人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90046人
- 3位
- mixi バスケ部
- 37855人