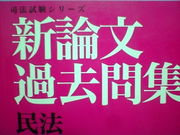「問題」
「民法の規定によれば、?詐欺による意思表示は取り消すことができるとされている(第96条第1項)のに対し、法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効とするとされており(第95条本文)、?第三者がその詐欺を行った場合においては相手方がその事実を知っていたときに限り意思表示を取り消すことができるとされている(第96条第2項)のに対し、要素の錯誤による意思表示の無効の場合には同様の規定がないし、?詐欺による意思表示の取消は善意の第三者に対抗する事ができないとされている(第96条第3項)のに対し、要素の錯誤による意思表示の無効の場合は同様の規定がない。
「詐欺による意思表示」と「要素の錯誤のある意思表示」との右のような規定上の違いは、どのような考え方に基づいて生じたものと解することができるかを説明せよ。その上で、そのような考え方を採った場合に生じ得る解釈論上の問題点(例えば、動機の錯誤、二重効、主張者)について論ぜよ。 」
「民法の規定によれば、?詐欺による意思表示は取り消すことができるとされている(第96条第1項)のに対し、法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効とするとされており(第95条本文)、?第三者がその詐欺を行った場合においては相手方がその事実を知っていたときに限り意思表示を取り消すことができるとされている(第96条第2項)のに対し、要素の錯誤による意思表示の無効の場合には同様の規定がないし、?詐欺による意思表示の取消は善意の第三者に対抗する事ができないとされている(第96条第3項)のに対し、要素の錯誤による意思表示の無効の場合は同様の規定がない。
「詐欺による意思表示」と「要素の錯誤のある意思表示」との右のような規定上の違いは、どのような考え方に基づいて生じたものと解することができるかを説明せよ。その上で、そのような考え方を採った場合に生じ得る解釈論上の問題点(例えば、動機の錯誤、二重効、主張者)について論ぜよ。 」
|
|
|
|
コメント(10)
「答案」
1、「詐欺による意思表示」と「要素の錯誤のある意思表示」との規定上の違いについて
(1)民法は私的自治原則の下、自らの意思決定がある場合にのみ法律効果を認めるのを原則とする。
ここでいう意思表示は、意思表示理論にいう内心的効果意思のことである。
すなわち、内心的効果意思がある場合には、例え成立過程に瑕疵があっても、原則として法律効果が発生するのに対し、内心的効果意思がない場合には、法律効果が発生せず無効になると考える。
詐欺と錯誤の規定上の違いは、上の考え方に基づいたと考えるが、本問の?・?・?の規定上の違いを、この考え方によって説明しうるか、以下、検討する。
(2)?の違い
詐欺の場合、内心的効果意思の成立過程に瑕疵があるにすぎないので、一応有効であり、表意者保護の観点から取り消し得るにすぎない。
錯誤の場合、表示に対応する内心的効果意思がない以上、無効とされている。
このように、前述の考え方によって、?の違いを説明しうる。
(3)?の違い
詐欺の場合、表示に対応する内心的効果意思は存在しており、取消は表意者保護のため認められているにすぎないことから、相手方との利益の調整が必要となる。
そこで、第三者によって詐欺が行われた場合には、相手方がその事実を知っていたときに限り意思表示を取り消すことができるとして、利益調整をはかっている。
錯誤の場合、表示に対応する内心的効果意思がない以上、当然無効であり、錯誤の原因が誰であるかは問題にならない。
このように、前述の考え方によって、?の違いを説明しうる。
(4)?の違い
詐欺の場合、取消は表意者保護のため認められているにすぎないことから、第三者との利益の調整が必要となる。
そこで、取消は善意の第三者に対抗する事ができないとされている。
錯誤の場合、表示に対応する内心的効果意思がない以上、当然無効であり、第三者との利益の調整は問題にならない
このように、前述の考え方によって、?の違いを説明しうる。
2、解釈論上の問題点について
(1)動機の錯誤について
ア前述の考え方からは、動機の錯誤の場合、内心的効果意思があるので、有効ということになる。
しかし、一般に生じる錯誤のほとんどが動機の錯誤であることから、これに錯誤規定を適用できないとすれば、錯誤の規定の存在意義が失われてしまうという問題点が生じる。
イ そこで、動機も表示されれば法律行為の内容となって錯誤の規定を適用できると解する。
(2)二重効について
ア前述の考え方からは、二重効の場合には表示に対応する内心的効果意思がない以上、当然に無効であり、取消の余地はないことになる。
しかし、無効事由の立証よりも取消事由の立証の方が容易であることが多いにもかかわらず、取消の立証が認められず、無効の立証を強いられてしまう、という問題点が生じる。
イそこで、無効も取消もいずれの主張も認めるべきと解する。
(3)主張者について
ア前述の考え方からは、取消は表意者保護のための制度だから表意者のみが主張しうるが、無効はそもそも効果が生じていないのだから誰でも主張しうることになる。
しかし、結果として表意者に有利な結果となる場合であっても、相手方からの無効主張が認められてしまう、という問題点が生じる。
イそこで、表意者のみが錯誤無効を主張しうると解する。
以上
1、「詐欺による意思表示」と「要素の錯誤のある意思表示」との規定上の違いについて
(1)民法は私的自治原則の下、自らの意思決定がある場合にのみ法律効果を認めるのを原則とする。
ここでいう意思表示は、意思表示理論にいう内心的効果意思のことである。
すなわち、内心的効果意思がある場合には、例え成立過程に瑕疵があっても、原則として法律効果が発生するのに対し、内心的効果意思がない場合には、法律効果が発生せず無効になると考える。
詐欺と錯誤の規定上の違いは、上の考え方に基づいたと考えるが、本問の?・?・?の規定上の違いを、この考え方によって説明しうるか、以下、検討する。
(2)?の違い
詐欺の場合、内心的効果意思の成立過程に瑕疵があるにすぎないので、一応有効であり、表意者保護の観点から取り消し得るにすぎない。
錯誤の場合、表示に対応する内心的効果意思がない以上、無効とされている。
このように、前述の考え方によって、?の違いを説明しうる。
(3)?の違い
詐欺の場合、表示に対応する内心的効果意思は存在しており、取消は表意者保護のため認められているにすぎないことから、相手方との利益の調整が必要となる。
そこで、第三者によって詐欺が行われた場合には、相手方がその事実を知っていたときに限り意思表示を取り消すことができるとして、利益調整をはかっている。
錯誤の場合、表示に対応する内心的効果意思がない以上、当然無効であり、錯誤の原因が誰であるかは問題にならない。
このように、前述の考え方によって、?の違いを説明しうる。
(4)?の違い
詐欺の場合、取消は表意者保護のため認められているにすぎないことから、第三者との利益の調整が必要となる。
そこで、取消は善意の第三者に対抗する事ができないとされている。
錯誤の場合、表示に対応する内心的効果意思がない以上、当然無効であり、第三者との利益の調整は問題にならない
このように、前述の考え方によって、?の違いを説明しうる。
2、解釈論上の問題点について
(1)動機の錯誤について
ア前述の考え方からは、動機の錯誤の場合、内心的効果意思があるので、有効ということになる。
しかし、一般に生じる錯誤のほとんどが動機の錯誤であることから、これに錯誤規定を適用できないとすれば、錯誤の規定の存在意義が失われてしまうという問題点が生じる。
イ そこで、動機も表示されれば法律行為の内容となって錯誤の規定を適用できると解する。
(2)二重効について
ア前述の考え方からは、二重効の場合には表示に対応する内心的効果意思がない以上、当然に無効であり、取消の余地はないことになる。
しかし、無効事由の立証よりも取消事由の立証の方が容易であることが多いにもかかわらず、取消の立証が認められず、無効の立証を強いられてしまう、という問題点が生じる。
イそこで、無効も取消もいずれの主張も認めるべきと解する。
(3)主張者について
ア前述の考え方からは、取消は表意者保護のための制度だから表意者のみが主張しうるが、無効はそもそも効果が生じていないのだから誰でも主張しうることになる。
しかし、結果として表意者に有利な結果となる場合であっても、相手方からの無効主張が認められてしまう、という問題点が生じる。
イそこで、表意者のみが錯誤無効を主張しうると解する。
以上
「答案の解説」
1、本問では、まず、錯誤無効と詐欺取消の規定の違いについて、どのような考え方に基づいて生じたものか、が問われています。
基本的には、詐欺は内心的効果意思はあるが、その成立過程に瑕疵があるにすぎないのに対し、錯誤は内心的効果意思すらない所に違いがあります。
あとは、?取り消しと無効、?第三者の詐欺、?善意の第三者の各規定について、ひとつずつ検討していきます。
詐欺の場合、内心的効果意思があり一応有効なので、表意者保護の観点から?取り消し得るにすぎず、?相手方や?第三者との利益の調整が必要となります。
錯誤の場合、内心的効果意思がない以上、?当然無効であり、?相手方?第三者との利益の調整は問題になりません。
2、解釈論上の問題点について
(1)動機の錯誤について
前述の考え方を貫くと、動機の錯誤は有効と言う事になります。
しかし、そうすると、一般に生じる錯誤のほとんどが動機の錯誤であることから、錯誤の規定の存在意義が失われてしまうのではないかという問題点が生じます。
(2)二重効について
前述の考え方を貫くと、無効な行為は取消できないことになります。
しかし、そうすると、取消の方が立証が容易であるにもかかわらず、取消を主張できないという問題点が生じます。
(3)主張者について
前述の考え方を貫くと、誰からでも無効主張ができることになります。
しかし、そうすると、表意者にとって有利な場合も相手方の無効主張が認められてしまう という問題点が生じます。
それぞれについて、妥当な結論を導いて終了。
伝統的な意思表示理論に立てば、「内心的効果意思」を中核におくことになります。
しかし、伝統的な意思表示理論に立つと、いろんなほころびがでる。
そこで、いっそのこと新しい意思表示理論を再構築してしまえという有力説があるようです。
しかし、そんな有力説なんぞ書いている余裕はない。
伝統的な意思表示理論に立った上で、ほころびをひとつひとつ修正していくという形で十分なのではないでしょうか。
1、本問では、まず、錯誤無効と詐欺取消の規定の違いについて、どのような考え方に基づいて生じたものか、が問われています。
基本的には、詐欺は内心的効果意思はあるが、その成立過程に瑕疵があるにすぎないのに対し、錯誤は内心的効果意思すらない所に違いがあります。
あとは、?取り消しと無効、?第三者の詐欺、?善意の第三者の各規定について、ひとつずつ検討していきます。
詐欺の場合、内心的効果意思があり一応有効なので、表意者保護の観点から?取り消し得るにすぎず、?相手方や?第三者との利益の調整が必要となります。
錯誤の場合、内心的効果意思がない以上、?当然無効であり、?相手方?第三者との利益の調整は問題になりません。
2、解釈論上の問題点について
(1)動機の錯誤について
前述の考え方を貫くと、動機の錯誤は有効と言う事になります。
しかし、そうすると、一般に生じる錯誤のほとんどが動機の錯誤であることから、錯誤の規定の存在意義が失われてしまうのではないかという問題点が生じます。
(2)二重効について
前述の考え方を貫くと、無効な行為は取消できないことになります。
しかし、そうすると、取消の方が立証が容易であるにもかかわらず、取消を主張できないという問題点が生じます。
(3)主張者について
前述の考え方を貫くと、誰からでも無効主張ができることになります。
しかし、そうすると、表意者にとって有利な場合も相手方の無効主張が認められてしまう という問題点が生じます。
それぞれについて、妥当な結論を導いて終了。
伝統的な意思表示理論に立てば、「内心的効果意思」を中核におくことになります。
しかし、伝統的な意思表示理論に立つと、いろんなほころびがでる。
そこで、いっそのこと新しい意思表示理論を再構築してしまえという有力説があるようです。
しかし、そんな有力説なんぞ書いている余裕はない。
伝統的な意思表示理論に立った上で、ほころびをひとつひとつ修正していくという形で十分なのではないでしょうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
論文試験対策「民法」 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
論文試験対策「民法」のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90058人
- 2位
- 酒好き
- 170691人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208289人