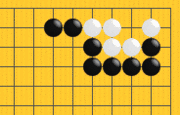第1回WMSG(World Mind Sports Games)北京大会の囲碁は予想通り?日本の惨敗−というべきではなく、もはや大健闘と評すべきかもしれないが−に終わったが、この大会でひとつ注目したいことは、チェスのすべての競技(及び中国象戯の一部)がフィッシャーモードで行なわれたことである。
フィッシャーモードというのはチェスの元世界チャンピオンで日本とも悪縁?が深いボビー・フィッシャー氏が提唱した持ち時間の設定法であり、最初に一定の持ち時間を持つと共に一手指すごとに一定の持ち時間がプラスされるというシステムである。
これは考えてみると切れ負けのやりきれなさを無くすと共に、競技時間を主宰者の都合になるべく合わせるという矛盾する要素を両立させる実に合理的なシステムであり、両立という意味ではチェスよりもむしろ囲碁、特にアマチュアの大会に向いていると思う。
切れ負けを防ぐためには秒読みが一般的であり、最近では秒読み機能付手合い時計も普及してきたが、30秒の秒読みだと双方で200手の秒読みだと最大100分、10秒の秒読みでも最大30分以上のエクストラタイムが生じてしまう。これは秒読みになると打つ手が決まっていても次の手以降も考えるために(実際にはなかなか考えられないのだが)秒読み時間いっぱいまで使ってしまうからであり、フィシャーモードならそのような無駄な時間は発生しない。
少し考えるとわかるように、フィッシャーモードでは最初の持ち時間を長めに1手あたりの追加時間を短めに設定するとトータルの所要時間のバラツキが小さくなるが、将棋のような終盤での詰筋を読むのにたっぷり時間がほしいゲームと反対に、囲碁では終盤にそれほどの時間は必要としない。
例えば2時間以内で終わらせたい試合なら持ち時間を50分、1手当たり3秒の追加と設定すると300手の碁なら115分以内で終わる。350手の超長手数局になっても2時間はかからない。また1手打つごとに3秒追加されればギリギリまで時間を使っても時間切れの心配はないし、終盤はほとんど1秒で打てるとすると1手打つごとに2秒ずつ持ち時間が増えるので、それをためておけばどこかで手所が生じたときに考えることができる。3秒という設定が短すぎるなら45分―5秒でもいいだろう。
チェスの終盤に必要な一手あたりの最低の考慮時間は将棋と碁の中間くらいであるが、それでもフィッシャーモードが主流(早指戦が中心であるが)になってきた。囲碁は上記のようにチェス以上にフィッシャーモードに向いており是非採用してほしいものである。
また世界アマ方式とかいうクラシカルチェス(早指しでないチェス)のルールをわけもわからないまま採用した最悪の持ち時間システムはもういい加減にしてもらいたい。
なおチェスでは序盤は定跡通りに指して時間をためておいて中盤〜終盤に勝負という考え方から30秒−30秒といったフィシャーモードの設定の試合もよく行なわれている。
フィッシャーモードを採用するにあたってはそのモードをソフトに入れた時計が必要であるが、まだ日本で発売されている時計では対応している機種は少ないようである。現在のデジタル式手合い時計のソフトを少し組みなおすだけであるから、ほとんどコストアップにはならないのでぜひメーカーの努力に期待したいものである。
フィッシャーモードというのはチェスの元世界チャンピオンで日本とも悪縁?が深いボビー・フィッシャー氏が提唱した持ち時間の設定法であり、最初に一定の持ち時間を持つと共に一手指すごとに一定の持ち時間がプラスされるというシステムである。
これは考えてみると切れ負けのやりきれなさを無くすと共に、競技時間を主宰者の都合になるべく合わせるという矛盾する要素を両立させる実に合理的なシステムであり、両立という意味ではチェスよりもむしろ囲碁、特にアマチュアの大会に向いていると思う。
切れ負けを防ぐためには秒読みが一般的であり、最近では秒読み機能付手合い時計も普及してきたが、30秒の秒読みだと双方で200手の秒読みだと最大100分、10秒の秒読みでも最大30分以上のエクストラタイムが生じてしまう。これは秒読みになると打つ手が決まっていても次の手以降も考えるために(実際にはなかなか考えられないのだが)秒読み時間いっぱいまで使ってしまうからであり、フィシャーモードならそのような無駄な時間は発生しない。
少し考えるとわかるように、フィッシャーモードでは最初の持ち時間を長めに1手あたりの追加時間を短めに設定するとトータルの所要時間のバラツキが小さくなるが、将棋のような終盤での詰筋を読むのにたっぷり時間がほしいゲームと反対に、囲碁では終盤にそれほどの時間は必要としない。
例えば2時間以内で終わらせたい試合なら持ち時間を50分、1手当たり3秒の追加と設定すると300手の碁なら115分以内で終わる。350手の超長手数局になっても2時間はかからない。また1手打つごとに3秒追加されればギリギリまで時間を使っても時間切れの心配はないし、終盤はほとんど1秒で打てるとすると1手打つごとに2秒ずつ持ち時間が増えるので、それをためておけばどこかで手所が生じたときに考えることができる。3秒という設定が短すぎるなら45分―5秒でもいいだろう。
チェスの終盤に必要な一手あたりの最低の考慮時間は将棋と碁の中間くらいであるが、それでもフィッシャーモードが主流(早指戦が中心であるが)になってきた。囲碁は上記のようにチェス以上にフィッシャーモードに向いており是非採用してほしいものである。
また世界アマ方式とかいうクラシカルチェス(早指しでないチェス)のルールをわけもわからないまま採用した最悪の持ち時間システムはもういい加減にしてもらいたい。
なおチェスでは序盤は定跡通りに指して時間をためておいて中盤〜終盤に勝負という考え方から30秒−30秒といったフィシャーモードの設定の試合もよく行なわれている。
フィッシャーモードを採用するにあたってはそのモードをソフトに入れた時計が必要であるが、まだ日本で発売されている時計では対応している機種は少ないようである。現在のデジタル式手合い時計のソフトを少し組みなおすだけであるから、ほとんどコストアップにはならないのでぜひメーカーの努力に期待したいものである。
|
|
|
|
コメント(8)
先日はじめてフィッシャーモードの時計で対局する機会があった。
実に快適である。
45分−5秒の設定だったので、250手の局なら110分程度、300手で115分程度、350手でも120分以内には必ず終了する。
アマチュアの試合は通常一人1時間前後だから、この時間設定なら試合時間が延びることがなく主催者側にとっては好適である。これが持ち時間45分・秒読み30秒の通常の?設定だと、もし100手目でお互いに秒読みになり350手まで一杯に考えると3時間半ほどかかってしまい主催者にとっては悪夢である。
また選手にとっても時間をギリギリまで使ってしまっても、終盤は最低でも5秒考えられるのだから、安心して勝負所で時間を使うことが出来る。また途中で時間がほとんどなくなっても簡単なところでノータイム着手を続ければまた時間をためておくこともできる。
チェスでは20分―30秒といった設定でどちらかというと手数に比例した持ち時間を与えるという発想らしく、これは将棋と違って終盤戦が長い局(ポーンレースが延々と続く)と短い局(駒損すれば実質的にジエンドなので終盤らしきものはない)の差が極端であるためと思われる。このために何手以内に何分というルールが主流であったが、現在はフィッシャーモードに駆逐されつつあるようだ。
これに比べると囲碁は終盤の性格が全く違うので、追加時間を短くすることにより試合時間の均一化ができるという更なるメリットがある。
まさにフィッシャーモードというのは、一日に何局も打つアマチュアの囲碁大会にぴったりであり、ぜひ普及してもらいたいものである。
なおその時計はフィッシャーモード以外にも、切れ負け、秒読み、秒読み+考慮時間数回、何手以内に何分とあらゆる方式に対応していたが、通常のデジタル時計にソフトが少し加えられているだけであるから、コストアップの要素はどこにもない。値段を聞いてみるとネットを通じて輸入して5000円程度とのこと。
これが普及すれば、時計をめぐるトラブルや不満はほとんど解消されるであろう。
実に快適である。
45分−5秒の設定だったので、250手の局なら110分程度、300手で115分程度、350手でも120分以内には必ず終了する。
アマチュアの試合は通常一人1時間前後だから、この時間設定なら試合時間が延びることがなく主催者側にとっては好適である。これが持ち時間45分・秒読み30秒の通常の?設定だと、もし100手目でお互いに秒読みになり350手まで一杯に考えると3時間半ほどかかってしまい主催者にとっては悪夢である。
また選手にとっても時間をギリギリまで使ってしまっても、終盤は最低でも5秒考えられるのだから、安心して勝負所で時間を使うことが出来る。また途中で時間がほとんどなくなっても簡単なところでノータイム着手を続ければまた時間をためておくこともできる。
チェスでは20分―30秒といった設定でどちらかというと手数に比例した持ち時間を与えるという発想らしく、これは将棋と違って終盤戦が長い局(ポーンレースが延々と続く)と短い局(駒損すれば実質的にジエンドなので終盤らしきものはない)の差が極端であるためと思われる。このために何手以内に何分というルールが主流であったが、現在はフィッシャーモードに駆逐されつつあるようだ。
これに比べると囲碁は終盤の性格が全く違うので、追加時間を短くすることにより試合時間の均一化ができるという更なるメリットがある。
まさにフィッシャーモードというのは、一日に何局も打つアマチュアの囲碁大会にぴったりであり、ぜひ普及してもらいたいものである。
なおその時計はフィッシャーモード以外にも、切れ負け、秒読み、秒読み+考慮時間数回、何手以内に何分とあらゆる方式に対応していたが、通常のデジタル時計にソフトが少し加えられているだけであるから、コストアップの要素はどこにもない。値段を聞いてみるとネットを通じて輸入して5000円程度とのこと。
これが普及すれば、時計をめぐるトラブルや不満はほとんど解消されるであろう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
囲碁 更新情報
-
最新のアンケート