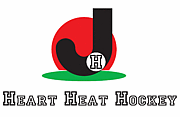スピード&パッション!ホッケーワールドへようこそ。
初めてホッケーという競技を目にされる人は、その溢れんばかりのスピード感と、一瞬で攻守が入れ替わる展開の早さ、なにより35分間ハーフを全力で駆け抜ける選手達のアスリートぶりに度肝を抜かれるのではないだろうか。
瞬時の判断が要求される素早いパス回しや、高度なスティックワークが繰り広げる激しいつばぜり合い。中でも最大の見どころは、シュートサークル内で放たれる球速200kmにも及ぶというシュートの迫力だ。
硬質なボールが、目にも止まらぬ早さでゴールに吸い込まれたその時、きっとあなたは歓声をあげていることだろう。
ペナルティコーナーという独特のセットプレーも見逃せない。緻密に作り込んだフォーメーションによって得点ができるこのシステムがあることによって、総合力で劣るチームがゲームを通じた戦術によって、強者を倒すアップセットを演じることが可能なのも魅力だ。
練り込まれた戦術によって強者を倒す、まさに競技スポーツの醍醐味がここにある。
このホッケーという競技の歴史は驚くほど長い。
いにしえには紀元前2500年の古代エジプトの壁画にもその原型が描かれ、我が国でも2006年に、日本最初のホッケー倶楽部(慶應義塾倶楽部)の発会式から、100周年の節目を迎た歴史と伝統ある球技スポーツなのである。
いまの近代ホッケーの原型は、19世紀の半ば頃にイギリスで生まれた。以来、英国生まれのロイヤルスポーツとして世界中で広く親しまれ、英国とゆかりの深い国々が、現在でも世界ランキングに名を馳せていることからも、そのルーツがうかがい知れよう。
日本においても、1926年に皇室vs陸軍戸山学校の親善試合が行われたことが記録に残っており、日本陸上連盟、日本水泳連盟、日本サッカー協会、全日本スキー連盟、日本庭球協会、日本漕艇協会とともに、日本体育協会の加盟第一期生として、日本スポーツ史の黎明期からその名を刻んでいる。
日本でのホッケーの普及は、1946年に始まった第一回国民体育大会からの種目参加が、その牽引車となってきた。各都道府県が持ち回りで、年に一度開催されるこの全国大会は、地元開催県にホッケーチームの結成と強化を促し、地域に根付く礎を確実に育んできた。
2005年よりトップリーグ機構の仲間入りを果たしたホッケー日本リーグ。このリーグに参戦する飯能市ホッケークラブ(埼玉)、Selrio島根クラブ(島根)や、南都銀行(奈良)、グラクソ・スミスクライン(栃木)などは、まさにそのような経緯を経て誕生した地域に根付く社会人チームである。
1908年の第4回ロンドン大会よりオリンピック競技として採用され、世界スポーツ史の中でも、長い歴史を持つホッケーだが、競技のルールそのものは進取の気性に富んでいる。
現代ホッケーを劇的に変えた要因の一つが、人工芝の採用だ。
以前は天然芝のグラウンドで行われてきたホッケーだが、1976年のカナダ・モントリオール五輪の際に、天然芝球技場の確保が困難となり、初めて人工芝が採用された。当時は賛否両論あったが、このことが契機となって国際ホッケー連盟(FIH)が人工芝の導入を本格的に検討、1984年より主要な国際大会をすべて人工芝のフィールドで行うことを決定した。
これは、競技ファンダメンタルにとって革命的な出来事であった。
それまでの天然芝や土のグラウンドでは、スティックワークを中心とした個人技こそが、チーム力の要となってきたが、人工芝によるフラットなフィールドの採用で、より素早いパスワークと練り上げた組織プレーが、大きく勝敗を左右するようになってきた。
さらに、ホッケー界は他の球技スポーツがなし得なかった大胆なルール改革を1996年に行う。すなわち「オフサイドの廃止」である。
この改革によって、反則による試合中断が格段に減り、先述の人工芝の採用と併せて、試合展開はよりスピード感溢れるスリリングなものとなった。もちろんチーム戦術面での劇的な変化はいうまでもないだろう。ルール改革からまだ9年。現代ホッケーの戦術は進化を続けている真っ最中でもある。
これほどまでに、競技として誇りある悠久の歴史を持ち、それに甘んじることなく常に斬新な改革を行い、競技そのものも見る者の引きつけて放さない魅力あるホッケーが、国内ではなぜ爆発的な人気種目として認知されないのであろうか。
原因として考えられるのが、ある意味で競技環境に恵まれ過ぎていることにあろう。
国体競技として、毎年のように地域のホッケー球技場を育む一連の流れは、地元密着型スポーツとして多くの種を蒔き、学生、社会人クラブを含め、多くの強豪チームがいわゆるホームグラウンドを持っている。これほど試合会場に恵まれているアマチュア競技もごくまれな存在であろう。
しかしその反面、多くの試合会場が交通不便な地方都市の山中にあり、一般のスポーツファンからは目の届かないところで数多くの大会が行われている。
さらにホームグラウンドという会場の利点は、有料開催試合という現在では、アマチュアスポーツ界でもごく当たり前の運営マネジメントへの移行を大幅に遅らせてきた。
「無料だから」という無意識の甘えの構造が、選手や運営関係者、強いては観戦者にも生まれ、「ゲームデイ」という「特別な日」の付加価値の向上を阻んできたのだ。
そういう意味で、関西のメインスタジアムである大阪市長居球技場で、有料開催試合を実施する全日本大学王座決定戦の開催コンセプトは、日本のホッケー界にとって大変意義深い。
この長居球技場は、かつての2008年大阪五輪招致活動に向けて本格整備された国際的なホッケースタジアムである。世界でも超一流のフィールドで行われる大学ホッケーの頂点を極めるこの大会で、熱い戦いを目撃した人は、明日からホッケーフリークとなることは、間違いないであろう。
初めてホッケーという競技を目にされる人は、その溢れんばかりのスピード感と、一瞬で攻守が入れ替わる展開の早さ、なにより35分間ハーフを全力で駆け抜ける選手達のアスリートぶりに度肝を抜かれるのではないだろうか。
瞬時の判断が要求される素早いパス回しや、高度なスティックワークが繰り広げる激しいつばぜり合い。中でも最大の見どころは、シュートサークル内で放たれる球速200kmにも及ぶというシュートの迫力だ。
硬質なボールが、目にも止まらぬ早さでゴールに吸い込まれたその時、きっとあなたは歓声をあげていることだろう。
ペナルティコーナーという独特のセットプレーも見逃せない。緻密に作り込んだフォーメーションによって得点ができるこのシステムがあることによって、総合力で劣るチームがゲームを通じた戦術によって、強者を倒すアップセットを演じることが可能なのも魅力だ。
練り込まれた戦術によって強者を倒す、まさに競技スポーツの醍醐味がここにある。
このホッケーという競技の歴史は驚くほど長い。
いにしえには紀元前2500年の古代エジプトの壁画にもその原型が描かれ、我が国でも2006年に、日本最初のホッケー倶楽部(慶應義塾倶楽部)の発会式から、100周年の節目を迎た歴史と伝統ある球技スポーツなのである。
いまの近代ホッケーの原型は、19世紀の半ば頃にイギリスで生まれた。以来、英国生まれのロイヤルスポーツとして世界中で広く親しまれ、英国とゆかりの深い国々が、現在でも世界ランキングに名を馳せていることからも、そのルーツがうかがい知れよう。
日本においても、1926年に皇室vs陸軍戸山学校の親善試合が行われたことが記録に残っており、日本陸上連盟、日本水泳連盟、日本サッカー協会、全日本スキー連盟、日本庭球協会、日本漕艇協会とともに、日本体育協会の加盟第一期生として、日本スポーツ史の黎明期からその名を刻んでいる。
日本でのホッケーの普及は、1946年に始まった第一回国民体育大会からの種目参加が、その牽引車となってきた。各都道府県が持ち回りで、年に一度開催されるこの全国大会は、地元開催県にホッケーチームの結成と強化を促し、地域に根付く礎を確実に育んできた。
2005年よりトップリーグ機構の仲間入りを果たしたホッケー日本リーグ。このリーグに参戦する飯能市ホッケークラブ(埼玉)、Selrio島根クラブ(島根)や、南都銀行(奈良)、グラクソ・スミスクライン(栃木)などは、まさにそのような経緯を経て誕生した地域に根付く社会人チームである。
1908年の第4回ロンドン大会よりオリンピック競技として採用され、世界スポーツ史の中でも、長い歴史を持つホッケーだが、競技のルールそのものは進取の気性に富んでいる。
現代ホッケーを劇的に変えた要因の一つが、人工芝の採用だ。
以前は天然芝のグラウンドで行われてきたホッケーだが、1976年のカナダ・モントリオール五輪の際に、天然芝球技場の確保が困難となり、初めて人工芝が採用された。当時は賛否両論あったが、このことが契機となって国際ホッケー連盟(FIH)が人工芝の導入を本格的に検討、1984年より主要な国際大会をすべて人工芝のフィールドで行うことを決定した。
これは、競技ファンダメンタルにとって革命的な出来事であった。
それまでの天然芝や土のグラウンドでは、スティックワークを中心とした個人技こそが、チーム力の要となってきたが、人工芝によるフラットなフィールドの採用で、より素早いパスワークと練り上げた組織プレーが、大きく勝敗を左右するようになってきた。
さらに、ホッケー界は他の球技スポーツがなし得なかった大胆なルール改革を1996年に行う。すなわち「オフサイドの廃止」である。
この改革によって、反則による試合中断が格段に減り、先述の人工芝の採用と併せて、試合展開はよりスピード感溢れるスリリングなものとなった。もちろんチーム戦術面での劇的な変化はいうまでもないだろう。ルール改革からまだ9年。現代ホッケーの戦術は進化を続けている真っ最中でもある。
これほどまでに、競技として誇りある悠久の歴史を持ち、それに甘んじることなく常に斬新な改革を行い、競技そのものも見る者の引きつけて放さない魅力あるホッケーが、国内ではなぜ爆発的な人気種目として認知されないのであろうか。
原因として考えられるのが、ある意味で競技環境に恵まれ過ぎていることにあろう。
国体競技として、毎年のように地域のホッケー球技場を育む一連の流れは、地元密着型スポーツとして多くの種を蒔き、学生、社会人クラブを含め、多くの強豪チームがいわゆるホームグラウンドを持っている。これほど試合会場に恵まれているアマチュア競技もごくまれな存在であろう。
しかしその反面、多くの試合会場が交通不便な地方都市の山中にあり、一般のスポーツファンからは目の届かないところで数多くの大会が行われている。
さらにホームグラウンドという会場の利点は、有料開催試合という現在では、アマチュアスポーツ界でもごく当たり前の運営マネジメントへの移行を大幅に遅らせてきた。
「無料だから」という無意識の甘えの構造が、選手や運営関係者、強いては観戦者にも生まれ、「ゲームデイ」という「特別な日」の付加価値の向上を阻んできたのだ。
そういう意味で、関西のメインスタジアムである大阪市長居球技場で、有料開催試合を実施する全日本大学王座決定戦の開催コンセプトは、日本のホッケー界にとって大変意義深い。
この長居球技場は、かつての2008年大阪五輪招致活動に向けて本格整備された国際的なホッケースタジアムである。世界でも超一流のフィールドで行われる大学ホッケーの頂点を極めるこの大会で、熱い戦いを目撃した人は、明日からホッケーフリークとなることは、間違いないであろう。
|
|
|
|
|
|
|
|
全日本大学ホッケー王座決定戦 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
全日本大学ホッケー王座決定戦のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90004人
- 3位
- 酒好き
- 170654人