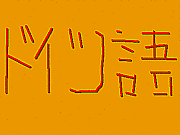日本人にはどうしても、南ドイツ、オーストリアがなじみ深いせいか、ここでは北ドイツ情報が少なくなりがちなので、救済(?)せねばと一念発起した次第です。
大まかに北ドイツと言うだけでも、非常に広いのですが、あえて幅広い情報を期待し、これ以上は限定しないようにしたいと思います。
発音や語彙、言い回しや果ては文法等、 Hochdeutsch と異なる点をご存じ、あるいは気づかれた方、情報を提供いただければ幸いです。
Plattdeutsch はもちろんのこと、低地ゲルマン語であるオランダ語やフラマン語等、さらに脈略上関連があれば、ノルド系の例えばフェロー語等の情報も大歓迎です。
さて、私が住むキールの話ですが、最近は使用範囲が南進しているらしい、典型的な 'moin' はさておき、市民自身は Hochdeutsch を話しているつもりでいて、決してそうとは思えない側面を、やはり垣間見せる事があります。
一例として、語彙面では sprechen や reden に代わり schnacken 「シュナゲン」を多用。anschnacken, beschnacken のように派生していきます。ちなみにノルウェー語やデンマーク語も sprechen に対応するのは、やはり起源を一とする snakke で、楽しくなります。
発音では、音節末の -ag, -ug, -og の g の部分が、[k]ではなく[x]音(「ク」ではなく「フ」)になります。結果として、Flugzeug の発音が「フルーフツォイヒ」のように。
あと、本来無声の[s]で発音されるべき、-ss- が有声音[z]になります。Kassette や Diskussion は、「カゼテ」、「ディスクズィオーン」。
同様に、[k]や[t]も有声化して、それぞれ[g]や[d]に。leckerは「レガー」、Partyは「パーディ」です。r 音の母音化も含めて、パーティの告知ポスターに Sportler Paadi と、当地での発音に忠実に、おもしろおかしく書かれているものすらありました(携帯で撮影したのですが、先日故障し、現在取り出せません…)。
(以上、本来、発音のカナ振りは、およそ学術的とは言えませんが、理解補助のためとご容赦下さい)
さらに、これは方言とは言えないでしょうが、南よりは明らかに過去時制の使用頻度が高い点も特徴です。Ich habe gedacht, ...や ..., habe ich gedacht. よりも、ich dachte, ... や ..., dachte ich. が好まれます。
それのみが原因ではないでしょうが、あくまで印象として、せっかちに響きます。東京の Goethe-Institut で私が師事した、Bayern 出身の講師が、やはり同じ感想を述べていました。
文法的な事では、かつて話されていた Plattdeutsch の影響で、Dativ (3格) と Akkusativ (4格)を間違える、戸惑い悩む、ケースによってはわからないという人すらいます。外国人を、ちょっとホッとさせる一コマです。
最後に Plattdeutsch の辞書に関してです。Langenscheidt 社から、Plattdeutschwörterbuch が刊行されています。400頁弱、5?×5? 程度、収録語彙4500の、かわいらしい超ミニ辞典で、値段は当時 DM 5.00でした(ISBN 3-468-20037-4)。
大まかに北ドイツと言うだけでも、非常に広いのですが、あえて幅広い情報を期待し、これ以上は限定しないようにしたいと思います。
発音や語彙、言い回しや果ては文法等、 Hochdeutsch と異なる点をご存じ、あるいは気づかれた方、情報を提供いただければ幸いです。
Plattdeutsch はもちろんのこと、低地ゲルマン語であるオランダ語やフラマン語等、さらに脈略上関連があれば、ノルド系の例えばフェロー語等の情報も大歓迎です。
さて、私が住むキールの話ですが、最近は使用範囲が南進しているらしい、典型的な 'moin' はさておき、市民自身は Hochdeutsch を話しているつもりでいて、決してそうとは思えない側面を、やはり垣間見せる事があります。
一例として、語彙面では sprechen や reden に代わり schnacken 「シュナゲン」を多用。anschnacken, beschnacken のように派生していきます。ちなみにノルウェー語やデンマーク語も sprechen に対応するのは、やはり起源を一とする snakke で、楽しくなります。
発音では、音節末の -ag, -ug, -og の g の部分が、[k]ではなく[x]音(「ク」ではなく「フ」)になります。結果として、Flugzeug の発音が「フルーフツォイヒ」のように。
あと、本来無声の[s]で発音されるべき、-ss- が有声音[z]になります。Kassette や Diskussion は、「カゼテ」、「ディスクズィオーン」。
同様に、[k]や[t]も有声化して、それぞれ[g]や[d]に。leckerは「レガー」、Partyは「パーディ」です。r 音の母音化も含めて、パーティの告知ポスターに Sportler Paadi と、当地での発音に忠実に、おもしろおかしく書かれているものすらありました(携帯で撮影したのですが、先日故障し、現在取り出せません…)。
(以上、本来、発音のカナ振りは、およそ学術的とは言えませんが、理解補助のためとご容赦下さい)
さらに、これは方言とは言えないでしょうが、南よりは明らかに過去時制の使用頻度が高い点も特徴です。Ich habe gedacht, ...や ..., habe ich gedacht. よりも、ich dachte, ... や ..., dachte ich. が好まれます。
それのみが原因ではないでしょうが、あくまで印象として、せっかちに響きます。東京の Goethe-Institut で私が師事した、Bayern 出身の講師が、やはり同じ感想を述べていました。
文法的な事では、かつて話されていた Plattdeutsch の影響で、Dativ (3格) と Akkusativ (4格)を間違える、戸惑い悩む、ケースによってはわからないという人すらいます。外国人を、ちょっとホッとさせる一コマです。
最後に Plattdeutsch の辞書に関してです。Langenscheidt 社から、Plattdeutschwörterbuch が刊行されています。400頁弱、5?×5? 程度、収録語彙4500の、かわいらしい超ミニ辞典で、値段は当時 DM 5.00でした(ISBN 3-468-20037-4)。
|
|
|
|
コメント(52)
再び、トピ立て人です。正直これだけ、コメントして下さる方がいらっしゃると思いませんでした。ひとえに感謝です。
? ja, jo :母音の長さもですが、イントネーションが大きく関係あるかもしれませんね。
私個人も「ヨッ」が大好きで、多用します。一気に相手との心理的距離が近づく感があります。この「ヨッ」に、江戸っ子の気っぷの良さに似たものを感じるのは、私だけでしょうか。
? Anne さん、お待ちしていました(クシャミしてなかった?)。ベルリンは、立派に北ドイツです。
ik は、第二次子音推移が及ばなかった、低地ドイツ語全般に見られる形ですね。
(kap は hap のタイプミスだと思いますが…、違う??)一人称単数の語尾 e が脱落し、hab や hap のようになるのは、キール、ハンブルク等でも同様で、日常会話では、専らこの形を耳にします。
ein → een、やはり単母音ですね。「せっかちな」キール市民の場合、ein → 'n で母音そのものが脱落してしまいます。でもこれは、ここ特有ではなく、南でも見られる現象のようです
例)so ein Buch → so 'n Buch (件のバイエルン出身講師の発音より)
ge → je は、既出ですが、kaufen → koofen なんですね。またしても、単母音。
<ここで、私が書いた前回のコメント内で、不用意な発言をした事に気がつきました。
単母音「化」と書くと、あたかも複母音から単母音に、歴史的に変化したような印象を与える恐れがありますね。
でも高地ドイツ語の方で、複母音化が起こった可能性もありますよね。現在、詳細がわからないので、一旦保留にさせて下さい。恐縮です。この点、ご存じの方は、ご教示願えると非常にありがたく思います。>
閑話休題。Nö は大人気(笑)で、再登場ですね。nicht wahr? ですが、キールには、やっぱりせっかちなのか、ne wa? 「ヌ・ヴァ」と言う人すら居ますが、でもこれを聞くのは男性のみですね。
? Niedersachsen からの情報、ありがとうございます。Neinというのがまどろっこしいのか、確かに ne(e)! は良く聞きます。
Moin に関して:当の北ドイツ人でも勘違いしている人の方が多いのですが、moin は語源的に、ドイツ語の Morgen とは一切関係ないんですよ。
つまり、決して北ドイツ人の時間感覚がおかしいのではありません。彼らの名誉のために、下記のサイトをご覧下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Moin
このフリジア語 moin は、やはりオランダ語や Plattdeutschで「美しい」を意味する mooi と語源が一緒です。
IYAさん、彼に教えてあげると、きっと喜ぶと思いますよ。ドイツ語で同様の説明がなされているのは、以下です
http://de.wikipedia.org/wiki/Moin
? ja, jo :母音の長さもですが、イントネーションが大きく関係あるかもしれませんね。
私個人も「ヨッ」が大好きで、多用します。一気に相手との心理的距離が近づく感があります。この「ヨッ」に、江戸っ子の気っぷの良さに似たものを感じるのは、私だけでしょうか。
? Anne さん、お待ちしていました(クシャミしてなかった?)。ベルリンは、立派に北ドイツです。
ik は、第二次子音推移が及ばなかった、低地ドイツ語全般に見られる形ですね。
(kap は hap のタイプミスだと思いますが…、違う??)一人称単数の語尾 e が脱落し、hab や hap のようになるのは、キール、ハンブルク等でも同様で、日常会話では、専らこの形を耳にします。
ein → een、やはり単母音ですね。「せっかちな」キール市民の場合、ein → 'n で母音そのものが脱落してしまいます。でもこれは、ここ特有ではなく、南でも見られる現象のようです
例)so ein Buch → so 'n Buch (件のバイエルン出身講師の発音より)
ge → je は、既出ですが、kaufen → koofen なんですね。またしても、単母音。
<ここで、私が書いた前回のコメント内で、不用意な発言をした事に気がつきました。
単母音「化」と書くと、あたかも複母音から単母音に、歴史的に変化したような印象を与える恐れがありますね。
でも高地ドイツ語の方で、複母音化が起こった可能性もありますよね。現在、詳細がわからないので、一旦保留にさせて下さい。恐縮です。この点、ご存じの方は、ご教示願えると非常にありがたく思います。>
閑話休題。Nö は大人気(笑)で、再登場ですね。nicht wahr? ですが、キールには、やっぱりせっかちなのか、ne wa? 「ヌ・ヴァ」と言う人すら居ますが、でもこれを聞くのは男性のみですね。
? Niedersachsen からの情報、ありがとうございます。Neinというのがまどろっこしいのか、確かに ne(e)! は良く聞きます。
Moin に関して:当の北ドイツ人でも勘違いしている人の方が多いのですが、moin は語源的に、ドイツ語の Morgen とは一切関係ないんですよ。
つまり、決して北ドイツ人の時間感覚がおかしいのではありません。彼らの名誉のために、下記のサイトをご覧下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Moin
このフリジア語 moin は、やはりオランダ語や Plattdeutschで「美しい」を意味する mooi と語源が一緒です。
IYAさん、彼に教えてあげると、きっと喜ぶと思いますよ。ドイツ語で同様の説明がなされているのは、以下です
http://de.wikipedia.org/wiki/Moin
再びトピ立て人です。
Kayo さん、鋭い観察による貴重な情報の数々、ありがとうございます。
? nech は、 nicht wahr から ne にいたる短縮変化の過程における、中間段階に当たるのでしょうか。やはり語尾の t 脱落が起こっていますね。
母音を e で書かれたの、良く理解できます。北ドイツ人の [i]音(長母音[i:]ではなく、短母音の方)は、南に比べると、そもそも緊張が少なく口の開きが大きいので、日本語母語話者には確かに、ほとんど「エ」のように聞こえますものね。
キールでも bitte における /i/ と /e/ の二つの母音、両者もうほとんど同じで、「ベデ」のように聞こえます。
? Na で催促を表す用法は、実は初めて聞きました。ハンブルク特有なのでしょうか。とても興味深く思います。
? フレンスブルク弁の「野性味あふれる(笑)」 -r 音は、確かに特徴的ですね。知り合いにキール出身のドイツ語講師がいますが、フレンスブルク弁の説明で、furchtbar を *fuächtbar のようにやはり ä を用いて、説明していました。
デンマーク国境のすぐ近くに位置するフレンスブルクは、デンマーク語とのバイリンガルも多く、初等教育でデンマーク語が必修(現在もそうかな?)という町。ビールの Flensburger でも、お馴染みですね。
Kayo さん、鋭い観察による貴重な情報の数々、ありがとうございます。
? nech は、 nicht wahr から ne にいたる短縮変化の過程における、中間段階に当たるのでしょうか。やはり語尾の t 脱落が起こっていますね。
母音を e で書かれたの、良く理解できます。北ドイツ人の [i]音(長母音[i:]ではなく、短母音の方)は、南に比べると、そもそも緊張が少なく口の開きが大きいので、日本語母語話者には確かに、ほとんど「エ」のように聞こえますものね。
キールでも bitte における /i/ と /e/ の二つの母音、両者もうほとんど同じで、「ベデ」のように聞こえます。
? Na で催促を表す用法は、実は初めて聞きました。ハンブルク特有なのでしょうか。とても興味深く思います。
? フレンスブルク弁の「野性味あふれる(笑)」 -r 音は、確かに特徴的ですね。知り合いにキール出身のドイツ語講師がいますが、フレンスブルク弁の説明で、furchtbar を *fuächtbar のようにやはり ä を用いて、説明していました。
デンマーク国境のすぐ近くに位置するフレンスブルクは、デンマーク語とのバイリンガルも多く、初等教育でデンマーク語が必修(現在もそうかな?)という町。ビールの Flensburger でも、お馴染みですね。
またもや貴重な情報の数々、ありちゅんさん、ありがとうございます。
? sp-, st-
st-, sp- が「シュ」ではなく「ス」というのは、北ドイツでは、どうも結構広く行われているようですね。キールは違いますが、前述したように「生粋の」ハンブルク弁でも、やはり「ス」音との事です。
Hochdeutsch を除き、これを「シュ」と発音する他のゲルマン系言語が他には、ほとんど見あたらない(ノルウェー語のほんの一部の方言にはある)ので、この「シュ」は、もしかしたら元来、高地ドイツ語から、時間をかけて北進してきたのかもしれませんね。そして、それが及ばなかった地域があると。
少々脱線しますが、この st-, sp- は、他のいくつかの言語でもおもしろい現象が見られます。スペイン語では、これらがそのままでは発音しにくかったのか、その前に e- が現れます。「学生」は、estudiante です。フランス語では、その形 est- がまどろっこしかったのか、さらに -s- が脱落し、現代フランス語では étudiant になっています。
? ja (jo)
性別にかかわらず、吸気で発音される事があるんですね。
私的な話で恐縮ですが、この現象に初めて出会ったのは、ドイツに来る前、スウェーデンのVesterås(ヴェステロース)へスウェーデン語短期留学に行った際の事でした。授業中、年配の女性講師がこれを行った時、私も、同意を意図しているがわからず、最初は戸惑いました。
その際、これを行うのは女性のみだと説明を受けたものですから、それが完全に刷り込まれていました。認識を新たにせねば。
? g → j
デュッセルドルフでも聞かれるんですね。低地ドイツ語は、その特徴から東と西の二つのグループに大まかに分けることができるようです。あの辺りは当然、ここキール等と同じ西低地ドイツ語に属するはずなのに、東低地ドイツ語である、ベルリン方言と同じ発音とは。これに関しては、東西は関係ないのかな?
? sp-, st-
st-, sp- が「シュ」ではなく「ス」というのは、北ドイツでは、どうも結構広く行われているようですね。キールは違いますが、前述したように「生粋の」ハンブルク弁でも、やはり「ス」音との事です。
Hochdeutsch を除き、これを「シュ」と発音する他のゲルマン系言語が他には、ほとんど見あたらない(ノルウェー語のほんの一部の方言にはある)ので、この「シュ」は、もしかしたら元来、高地ドイツ語から、時間をかけて北進してきたのかもしれませんね。そして、それが及ばなかった地域があると。
少々脱線しますが、この st-, sp- は、他のいくつかの言語でもおもしろい現象が見られます。スペイン語では、これらがそのままでは発音しにくかったのか、その前に e- が現れます。「学生」は、estudiante です。フランス語では、その形 est- がまどろっこしかったのか、さらに -s- が脱落し、現代フランス語では étudiant になっています。
? ja (jo)
性別にかかわらず、吸気で発音される事があるんですね。
私的な話で恐縮ですが、この現象に初めて出会ったのは、ドイツに来る前、スウェーデンのVesterås(ヴェステロース)へスウェーデン語短期留学に行った際の事でした。授業中、年配の女性講師がこれを行った時、私も、同意を意図しているがわからず、最初は戸惑いました。
その際、これを行うのは女性のみだと説明を受けたものですから、それが完全に刷り込まれていました。認識を新たにせねば。
? g → j
デュッセルドルフでも聞かれるんですね。低地ドイツ語は、その特徴から東と西の二つのグループに大まかに分けることができるようです。あの辺りは当然、ここキール等と同じ西低地ドイツ語に属するはずなのに、東低地ドイツ語である、ベルリン方言と同じ発音とは。これに関しては、東西は関係ないのかな?
このトピ とても興味深いです!
Na はOstwestfalen出身の彼とその家族が頻繁に使います。
例: Na? Wie geht es Dir?
Na? Wie heisst das nochmal(思い出せないときに)
na,was soll das (かたいネジが回らないときとか)
あと、文末の nicht wahr については、ザウアーランド出身の知り合い(女性)がいつも 「ヴぉ」 というように発音します。前出の「ノヴぁ」に近いですが、「ノ」もなしです。
印象として北出身の人は、どなたかおっしゃっていたように江戸っ子に通じる活気のよさみたいなものがかんじられます。
Na はOstwestfalen出身の彼とその家族が頻繁に使います。
例: Na? Wie geht es Dir?
Na? Wie heisst das nochmal(思い出せないときに)
na,was soll das (かたいネジが回らないときとか)
あと、文末の nicht wahr については、ザウアーランド出身の知り合い(女性)がいつも 「ヴぉ」 というように発音します。前出の「ノヴぁ」に近いですが、「ノ」もなしです。
印象として北出身の人は、どなたかおっしゃっていたように江戸っ子に通じる活気のよさみたいなものがかんじられます。
こんにちは、トピ立て人です。
Dee さん、Halle 情報、ありがとうございます。方言区分的にはすでに低地ドイツ語(Niederdeutsch)ではなく、中部ドイツ語(Mitteldeutsch)に属するであろう地域でも、na? は使われるんですね。
Alsterwasser 、キールでは'Radler' ですが、キールはそもそも地ビールもなく、市民は他の町に比べて、その類よりもウォッカや Korn 等の火酒を好むという土地柄ゆえ、参考にならないと思い、コメントを差し控えていました。gespritz や Schorle も含め、補足していただける方がいらっしゃれば、それは大歓迎です!
Giraffe さん、気に入っていただけて、こちらも非常に嬉しく思います。
Na?:稚訳ですが、2番目の文は「え〜っと、ほら、なんだっけ…」、3番目のは「おいおい〜」といったニュアンスでしょうか。共に感情がこもった、生き生きとした文になりますね。
Sauerland の辺りも、もはや低地ではなく、(西)中部ドイツ語圏かと思いますが、-r 音が「オ」に近くなるんですね。面白い。 「ネ?」 は nicht wahr の前半部分が残り、「ヴォ?」は逆に後半部分が残っている究極形でしょうね。
そして江戸っ子説、支持していただき、ありがとうございます:)
Dee さん、Halle 情報、ありがとうございます。方言区分的にはすでに低地ドイツ語(Niederdeutsch)ではなく、中部ドイツ語(Mitteldeutsch)に属するであろう地域でも、na? は使われるんですね。
Alsterwasser 、キールでは'Radler' ですが、キールはそもそも地ビールもなく、市民は他の町に比べて、その類よりもウォッカや Korn 等の火酒を好むという土地柄ゆえ、参考にならないと思い、コメントを差し控えていました。gespritz や Schorle も含め、補足していただける方がいらっしゃれば、それは大歓迎です!
Giraffe さん、気に入っていただけて、こちらも非常に嬉しく思います。
Na?:稚訳ですが、2番目の文は「え〜っと、ほら、なんだっけ…」、3番目のは「おいおい〜」といったニュアンスでしょうか。共に感情がこもった、生き生きとした文になりますね。
Sauerland の辺りも、もはや低地ではなく、(西)中部ドイツ語圏かと思いますが、-r 音が「オ」に近くなるんですね。面白い。 「ネ?」 は nicht wahr の前半部分が残り、「ヴォ?」は逆に後半部分が残っている究極形でしょうね。
そして江戸っ子説、支持していただき、ありがとうございます:)
再びトピ立て人です。
Anne さん、Assimilation (同化)で合っていますよ。
この現象や術語、私が説明するよりも、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E5%8C%96_(%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E5%AD%A6)
をご覧になっていただいた方が、わかりやすいと思います。
この場合は、直前の単語の語尾 k に同化しているので、順行同化ですね。
Na の、尻上がりイントネーションは、特に大切ですね。こういった、テキストの中で文字が通常表わさない、表せない要素を、言語学では、suprasegmental・超分節的要素と呼んでいますが、見落とされがちです。このように指摘、補足していただけると、本当に助かります。ありがとう。
ところで、先日触れた'Sportler Paadi'、今年もポスターが出ていたので、今日撮影してきました。
今年は残念ながら(?)、綴りが Paadi ではなく、ほんのちょっとだけ正書法に近い Paady になっていました。
Anne さん、Assimilation (同化)で合っていますよ。
この現象や術語、私が説明するよりも、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E5%8C%96_(%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E5%AD%A6)
をご覧になっていただいた方が、わかりやすいと思います。
この場合は、直前の単語の語尾 k に同化しているので、順行同化ですね。
Na の、尻上がりイントネーションは、特に大切ですね。こういった、テキストの中で文字が通常表わさない、表せない要素を、言語学では、suprasegmental・超分節的要素と呼んでいますが、見落とされがちです。このように指摘、補足していただけると、本当に助かります。ありがとう。
ところで、先日触れた'Sportler Paadi'、今年もポスターが出ていたので、今日撮影してきました。
今年は残念ながら(?)、綴りが Paadi ではなく、ほんのちょっとだけ正書法に近い Paady になっていました。
Akkochan さん、こんにちは。
? g- の無声化現象ですね。確かに kucken と発音されてます(この単語のみならず、Glocke の発音も *Klocke のように聞こえます)。日常、誰かの注意を引く時の、Kuck ma! (ma は、「ちょっと」を意味する'einmal'が縮まった形)は、本当によく耳にします。
キールに限って言えば、友人からの砕けた文体のメールを含め、語頭が k- で書かれたのを目にすることは、ありませんでした。でも、Spiegel はその書き方に「お墨付き」を与えていますね 笑
ちなみに kucken、オランダ語でも kijken だったはずで、やはり低地ドイツ語との連続性を示しています。
? そして巷で話題の図書、紹介していただき、ありがとうございます。
Genitiv(2格)の使用頻度は、下がる一方ですね。日常会話で
wegen des schlechten Wetters という人は、まずいませんしね。ほとんどが Dativ(3格)を用いた wegen dem schlechten Wetter
さらに現在、初等教育の場で、Marias Buch ではなく das/ein Buch von Maria という言い方を教えているといいますから、この傾向に拍車が掛かるのは当然でしょうね。
あるGoethe-Institut講師(件のバイエルン出身者とは別人)曰く、Genitiv が会話で用いられるのは、一人あたり年間10回に満たないのでは、との話でした。
あと、以下、かつて(日本の大学で)ドイツ語を習ったオーストリア人講師の個人的意見(しかも言語学ではなく、哲学専攻の方でした)で、かなり主観が入ってますが、あくまで参考にと挙げておきます。
彼は、des Mann(e)s や des Buch(e)s 等、男性あるいは中性単数の場合、語尾が連続で -s で終わるのが、母語話者にとって耳障りで、ästhetisch ではない(美しくない)とし、会話での使用が避けられる原因として挙げていました。
? g- の無声化現象ですね。確かに kucken と発音されてます(この単語のみならず、Glocke の発音も *Klocke のように聞こえます)。日常、誰かの注意を引く時の、Kuck ma! (ma は、「ちょっと」を意味する'einmal'が縮まった形)は、本当によく耳にします。
キールに限って言えば、友人からの砕けた文体のメールを含め、語頭が k- で書かれたのを目にすることは、ありませんでした。でも、Spiegel はその書き方に「お墨付き」を与えていますね 笑
ちなみに kucken、オランダ語でも kijken だったはずで、やはり低地ドイツ語との連続性を示しています。
? そして巷で話題の図書、紹介していただき、ありがとうございます。
Genitiv(2格)の使用頻度は、下がる一方ですね。日常会話で
wegen des schlechten Wetters という人は、まずいませんしね。ほとんどが Dativ(3格)を用いた wegen dem schlechten Wetter
さらに現在、初等教育の場で、Marias Buch ではなく das/ein Buch von Maria という言い方を教えているといいますから、この傾向に拍車が掛かるのは当然でしょうね。
あるGoethe-Institut講師(件のバイエルン出身者とは別人)曰く、Genitiv が会話で用いられるのは、一人あたり年間10回に満たないのでは、との話でした。
あと、以下、かつて(日本の大学で)ドイツ語を習ったオーストリア人講師の個人的意見(しかも言語学ではなく、哲学専攻の方でした)で、かなり主観が入ってますが、あくまで参考にと挙げておきます。
彼は、des Mann(e)s や des Buch(e)s 等、男性あるいは中性単数の場合、語尾が連続で -s で終わるのが、母語話者にとって耳障りで、ästhetisch ではない(美しくない)とし、会話での使用が避けられる原因として挙げていました。
こんにちは。
Oga(-chan)さんの北ドイツ方言のお話を聞いていると、どうも北部では無声子音が有声化して、、逆に南部では有声子音が無声化する場合が多い、ということになるのでしょうか。私が昔日本に居た頃に習っていたミュンヘン出身の先生も“sie”を“スィー”と発音していましたし(これについては別トピに書いていた人がいましたね)。
あと、g → jはベルリンだけではなくて、私の本拠地ケルンの方言Kölschでもそう発音されていますよ。とにかくドイツ語の場合、この発音はこの地方でだけ使われている、というのではなく、意外と似たような発音が全然違うほかの地域で使われていたりもして、いろんな方言があちこちに混在してその発音の仕方の地域分布も複雑になっている、という印象があります。
歴史的に見ると、オランダ語というのはもともとドイツ語の一方言であったものがその後独立した言語になったという経緯があったそうですね。なぜオランダ語だけが独立したのかは私にはわかりませんが、それだけオランダ語が他の北部ドイツ語とはかけ離れていたからのか、それともオランダ人という民族がドイツとは何か決定的に違うものだったからなのかもしれませんが・・・。
ノルウェー語の話がちょっと出ていたので、私も去年ノルウェー語を習い始めたので少し知っていますが、“rs”や“sl”という綴りの場合には基本的に“シュ”という発音になります。世界中の多くの国で“オスロ”と呼ばれているノルウェーの首都は実は本国では“ウシュル”に近い感じで発音されています。が、一部の地域ではそう発音しないで“ス”と言う所もあるようです。そもそもノルウェー語には標準語というものが存在しないので、放送局のアナウンサーなどもみんなそれぞれの地方言葉で話しているみたいです。
一方ドイツ語には標準語と呼ばれる言葉が一応あって、ハノーファー界隈の言葉がそれに近いというのはご周知だと思いますが、でもかといってドイツ北部のあの地方がみんな標準語を話すわけでもない、ということを考えるとちょっと不思議ですよね。なんだか言語地理学的な話になってしまいましたけど(笑)。
Oga(-chan)さんの北ドイツ方言のお話を聞いていると、どうも北部では無声子音が有声化して、、逆に南部では有声子音が無声化する場合が多い、ということになるのでしょうか。私が昔日本に居た頃に習っていたミュンヘン出身の先生も“sie”を“スィー”と発音していましたし(これについては別トピに書いていた人がいましたね)。
あと、g → jはベルリンだけではなくて、私の本拠地ケルンの方言Kölschでもそう発音されていますよ。とにかくドイツ語の場合、この発音はこの地方でだけ使われている、というのではなく、意外と似たような発音が全然違うほかの地域で使われていたりもして、いろんな方言があちこちに混在してその発音の仕方の地域分布も複雑になっている、という印象があります。
歴史的に見ると、オランダ語というのはもともとドイツ語の一方言であったものがその後独立した言語になったという経緯があったそうですね。なぜオランダ語だけが独立したのかは私にはわかりませんが、それだけオランダ語が他の北部ドイツ語とはかけ離れていたからのか、それともオランダ人という民族がドイツとは何か決定的に違うものだったからなのかもしれませんが・・・。
ノルウェー語の話がちょっと出ていたので、私も去年ノルウェー語を習い始めたので少し知っていますが、“rs”や“sl”という綴りの場合には基本的に“シュ”という発音になります。世界中の多くの国で“オスロ”と呼ばれているノルウェーの首都は実は本国では“ウシュル”に近い感じで発音されています。が、一部の地域ではそう発音しないで“ス”と言う所もあるようです。そもそもノルウェー語には標準語というものが存在しないので、放送局のアナウンサーなどもみんなそれぞれの地方言葉で話しているみたいです。
一方ドイツ語には標準語と呼ばれる言葉が一応あって、ハノーファー界隈の言葉がそれに近いというのはご周知だと思いますが、でもかといってドイツ北部のあの地方がみんな標準語を話すわけでもない、ということを考えるとちょっと不思議ですよね。なんだか言語地理学的な話になってしまいましたけど(笑)。
T.M.さん、ようこそいらっしゃいました。
件の「熱い」トピ、ドイツ語の便利・不便では、色々と生意気な口をきいて恐縮です。
ところで、このトピは本来、いわば息抜きでして、肩の力を抜き、皆さんが気楽に書き込めるよう、原則的には、あまり学術的で堅苦しくならないよう、心がけています。でも、こういった真に言語学的な観察も、大歓迎ですよ。
? s 音の無声化は、高地ゲルマン語の特徴ですね。低地のゲルマン語の一派であるオランダ語では、有声音[z]で発音されるだけで書く際も z の文字を用います。独 sein 蘭 zijn のように。
南(高地)で発生し、それが歴史的に北進してきた第二次子音推移(※1)とも、何らかの関係があるかもしれませんが、私にはわかりません。
※1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%AD%90%E9%9F%B3%E6%8E%A8%E7%A7%BB
? g → j は、まさにT.M.さんの仰るとおりだと思います。どうも、行われている地域が、とびとび、まばらにある可能性がありますね。
? オランダ語の「独立」に関してですが、長くなりそうなので、この後改めてコメントさせていただきます。
? ノルウェー語
実は私が研究するノルド語言語学で、第二言語として学んでいまして、事情は存じておりますし、Bokmål, nynorsk (大まかに言っても、公用語としてのノルウェー語自体に、二種類あるという複雑なお国柄)等も絡め、本当はコメントしたいのですが、本筋から逸れるので差し控えます。これはここまでにしておきましょう。
? 標準ドイツ語(Hochdeutsch)
仰るとおり、ハノーファー弁が最もそれに「近い」というだけで、厳密には、Hochdeutsch が話されている地域はないという点、これはある種人工言語(笑)ですね。
件の「熱い」トピ、ドイツ語の便利・不便では、色々と生意気な口をきいて恐縮です。
ところで、このトピは本来、いわば息抜きでして、肩の力を抜き、皆さんが気楽に書き込めるよう、原則的には、あまり学術的で堅苦しくならないよう、心がけています。でも、こういった真に言語学的な観察も、大歓迎ですよ。
? s 音の無声化は、高地ゲルマン語の特徴ですね。低地のゲルマン語の一派であるオランダ語では、有声音[z]で発音されるだけで書く際も z の文字を用います。独 sein 蘭 zijn のように。
南(高地)で発生し、それが歴史的に北進してきた第二次子音推移(※1)とも、何らかの関係があるかもしれませんが、私にはわかりません。
※1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%AD%90%E9%9F%B3%E6%8E%A8%E7%A7%BB
? g → j は、まさにT.M.さんの仰るとおりだと思います。どうも、行われている地域が、とびとび、まばらにある可能性がありますね。
? オランダ語の「独立」に関してですが、長くなりそうなので、この後改めてコメントさせていただきます。
? ノルウェー語
実は私が研究するノルド語言語学で、第二言語として学んでいまして、事情は存じておりますし、Bokmål, nynorsk (大まかに言っても、公用語としてのノルウェー語自体に、二種類あるという複雑なお国柄)等も絡め、本当はコメントしたいのですが、本筋から逸れるので差し控えます。これはここまでにしておきましょう。
? 標準ドイツ語(Hochdeutsch)
仰るとおり、ハノーファー弁が最もそれに「近い」というだけで、厳密には、Hochdeutsch が話されている地域はないという点、これはある種人工言語(笑)ですね。
再びトピ立て者です。
さて、オランダ語の「独立」に関してですが、まず政治的境界(国境等)と言語学的境界の相違について、考えてみてましょう。掘り下げてみると、色々と面白いです。
日本のように、海洋等の地理的境界と国境が割合一致していて、比較的明確な国に生まれるとイメージしにくいですが…、頑張って以下に例を挙げますね。
言語学的に、ドイツ語(特に北ドイツ方言 Plattdeutsch)とオランダ語の差異は、日本語の東京方言(いわば共通語)と沖縄の琉球方言との差異よりも小さい側面があります。
「コテコテ」の北ドイツ方言 (Plattdeutsch) 話者とオランダ人は、それぞれの母語を話しても、意思の疎通がかなりスムーズにできますが、東京に生まれ育った人には、「コテコテ」の琉球方言は、普通、ほとんど理解できないはずです。
かといって、沖縄ネーティブの言葉を「琉球語」と、独立した言語として普通は扱いませんよね。沖縄は日本の領土だからです。これは、ひとえに政治的な背景によるものです。
(ただ、もしも沖縄の言葉が、日本の共通語と、全く系統が違う、つまり琉球人が、本土人…あまり好きな表現ではないけど…と別の民族なら、きっと「琉球語」と呼ばれるでしょうが、実際の所、両者は同系統です。ちなみにアイヌは別の民族なので、アイヌ語と呼ばれていますね)
オランダ語と低ドイツ諸語(北ドイツ)は、以下のサイトでの説明のように、共に低地フランコニア諸語に属します。オランダ語は、前も書きましたが、Plattdeutsch(北ドイツ方言)と双子に近い兄弟です(オランダ語情報も、このトピであえて募集したのは、以上の経緯からです)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%B3%E8%AA%9E%E6%B4%BE
むしろ高地ドイツ語である、南のバイエルン方言等の方が、これらからはかなり遠い親戚で、「コテコテ」の北ドイツ語と、例えば「コテコテ」のバイエルン方言とでは、意思の疎通が非常に困難です。
こちらの方は政治に関係なく、言語学的な分類ですね。国境はこの際、全く意味をなしません。
ここで指摘して恐縮なのですが、「オランダ人」は、ドイツ人と異なる「民族」(言語学的分類)なのではありません。別の「国民」(政治的分類)なだけです(ここを混同してしまうと、ややこしくなります)。ご存じのように、オランダ人とドイツ人等は共に「ゲルマン民族」に属します。
民族が同じというのは、言葉が同じか、あるいは非常に似ていると言うことです。先ほど述べたように、オランダ人、オランダ語は、特に北ドイツ人やその言葉と、決定的な相違はありません。ドイツ人と同じ民族でありながら、政治的に独立した故に、現在「オランダ語」と独立した呼称を持つにすぎないのです。
同様に、もしも件の沖縄(沖縄出身の方、恐縮です 汗)が、政治的に日本から独立したら、彼らは自分たちの言葉を「琉球語」のように称するのではないでしょうか。
(オランダはたしか、ハプスブルクから独立したので、厳密には「ドイツから」とは言えません、歴史に興味がある方は「大ドイツ主義」「小ドイツ主義」等、検索してみてください)
そして仮にオランダが、いまだにオーストリアでもドイツでもとにかく、ドイツ語を公用語とする国の領土のままだったら、オランダ語もドイツ語の一方言、Plattdeutsch の一派と、きっと分類されるでしょう。
さて、では何が、オランダ語のドイツ語からの独立性を、保証しているのでしょう?言い方を変えれば、ドイツ人と一緒にされたくないオランダ人は、差異を強調する為に、何をするでしょう?非常に似た言葉を話す同じ民族ゆえに、独立性を維持するのは難しいですよね…
手段は色々あると思いますが、正書法を違えるのが、割と手っ取り早いんです。Sand と書いて[zant]と読むドイツ語(これは標準発音に関してで、南はもちろん例外)と、同じ発音ながら、zand と綴るのを標準にしたオランダ語。字面が違うと、かなり別の言語としての様相が漂いますね。
こういった事が「オランダ」の政治的な独立、そしてドイツ語からの「オランダ語」の独立を、より確実にするための大きな助けになっていますが、そのために、低地ドイツ語との近似性や連続性を、見落としてもしまいがちです。
さて、オランダ語の「独立」に関してですが、まず政治的境界(国境等)と言語学的境界の相違について、考えてみてましょう。掘り下げてみると、色々と面白いです。
日本のように、海洋等の地理的境界と国境が割合一致していて、比較的明確な国に生まれるとイメージしにくいですが…、頑張って以下に例を挙げますね。
言語学的に、ドイツ語(特に北ドイツ方言 Plattdeutsch)とオランダ語の差異は、日本語の東京方言(いわば共通語)と沖縄の琉球方言との差異よりも小さい側面があります。
「コテコテ」の北ドイツ方言 (Plattdeutsch) 話者とオランダ人は、それぞれの母語を話しても、意思の疎通がかなりスムーズにできますが、東京に生まれ育った人には、「コテコテ」の琉球方言は、普通、ほとんど理解できないはずです。
かといって、沖縄ネーティブの言葉を「琉球語」と、独立した言語として普通は扱いませんよね。沖縄は日本の領土だからです。これは、ひとえに政治的な背景によるものです。
(ただ、もしも沖縄の言葉が、日本の共通語と、全く系統が違う、つまり琉球人が、本土人…あまり好きな表現ではないけど…と別の民族なら、きっと「琉球語」と呼ばれるでしょうが、実際の所、両者は同系統です。ちなみにアイヌは別の民族なので、アイヌ語と呼ばれていますね)
オランダ語と低ドイツ諸語(北ドイツ)は、以下のサイトでの説明のように、共に低地フランコニア諸語に属します。オランダ語は、前も書きましたが、Plattdeutsch(北ドイツ方言)と双子に近い兄弟です(オランダ語情報も、このトピであえて募集したのは、以上の経緯からです)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%B3%E8%AA%9E%E6%B4%BE
むしろ高地ドイツ語である、南のバイエルン方言等の方が、これらからはかなり遠い親戚で、「コテコテ」の北ドイツ語と、例えば「コテコテ」のバイエルン方言とでは、意思の疎通が非常に困難です。
こちらの方は政治に関係なく、言語学的な分類ですね。国境はこの際、全く意味をなしません。
ここで指摘して恐縮なのですが、「オランダ人」は、ドイツ人と異なる「民族」(言語学的分類)なのではありません。別の「国民」(政治的分類)なだけです(ここを混同してしまうと、ややこしくなります)。ご存じのように、オランダ人とドイツ人等は共に「ゲルマン民族」に属します。
民族が同じというのは、言葉が同じか、あるいは非常に似ていると言うことです。先ほど述べたように、オランダ人、オランダ語は、特に北ドイツ人やその言葉と、決定的な相違はありません。ドイツ人と同じ民族でありながら、政治的に独立した故に、現在「オランダ語」と独立した呼称を持つにすぎないのです。
同様に、もしも件の沖縄(沖縄出身の方、恐縮です 汗)が、政治的に日本から独立したら、彼らは自分たちの言葉を「琉球語」のように称するのではないでしょうか。
(オランダはたしか、ハプスブルクから独立したので、厳密には「ドイツから」とは言えません、歴史に興味がある方は「大ドイツ主義」「小ドイツ主義」等、検索してみてください)
そして仮にオランダが、いまだにオーストリアでもドイツでもとにかく、ドイツ語を公用語とする国の領土のままだったら、オランダ語もドイツ語の一方言、Plattdeutsch の一派と、きっと分類されるでしょう。
さて、では何が、オランダ語のドイツ語からの独立性を、保証しているのでしょう?言い方を変えれば、ドイツ人と一緒にされたくないオランダ人は、差異を強調する為に、何をするでしょう?非常に似た言葉を話す同じ民族ゆえに、独立性を維持するのは難しいですよね…
手段は色々あると思いますが、正書法を違えるのが、割と手っ取り早いんです。Sand と書いて[zant]と読むドイツ語(これは標準発音に関してで、南はもちろん例外)と、同じ発音ながら、zand と綴るのを標準にしたオランダ語。字面が違うと、かなり別の言語としての様相が漂いますね。
こういった事が「オランダ」の政治的な独立、そしてドイツ語からの「オランダ語」の独立を、より確実にするための大きな助けになっていますが、そのために、低地ドイツ語との近似性や連続性を、見落としてもしまいがちです。
さて流れを、気楽な方向に戻しましょうか。
なんとオンライン Plattdeutsch 辞典がありました。日本でたとえると、東北弁辞典のようなものですね。
http://deutsch-plattdeutsch.de/wsuchen.php
まず Hochdeutsch の sprechen を引いてみると、当地では良く耳にする s(ch)nacken 以外にも küren だの、praten (確かに耳にしますが、てっきり Hochdeutschだと…)やそのバリエーションが、出てきました。
皆さんのお住まい、あるいはご存じの地方では、どの形が使われているでしょうか。
更に lesen を引くとs(ch)mökern とあります。
友人で Plattdeutsch 準ネーティブの Sabrina がかつて、s(ch)mökern は、単に「読む」というよりも、ここにあるように、「本に没頭する(して読む)」 sich in ein Buch vertiefen というニュアンスが強いと説明してくれたのを思い出します。
この単語、会話であまり耳にしないのは、「本に没頭する」機会が少ない、つまり単に使われるシチュエーションがあまりないからかな…。
もしこの単語が、標準ドイツ語の lesen のように、一般的に「本を読む」という意味で、日常的に、高い頻度で用いられる地方をご存じ、あるいはお住まいの方、どうかご一報いただけると、非常に嬉しく思います。どうか、よろしくお願いいたします。
なんとオンライン Plattdeutsch 辞典がありました。日本でたとえると、東北弁辞典のようなものですね。
http://deutsch-plattdeutsch.de/wsuchen.php
まず Hochdeutsch の sprechen を引いてみると、当地では良く耳にする s(ch)nacken 以外にも küren だの、praten (確かに耳にしますが、てっきり Hochdeutschだと…)やそのバリエーションが、出てきました。
皆さんのお住まい、あるいはご存じの地方では、どの形が使われているでしょうか。
更に lesen を引くとs(ch)mökern とあります。
友人で Plattdeutsch 準ネーティブの Sabrina がかつて、s(ch)mökern は、単に「読む」というよりも、ここにあるように、「本に没頭する(して読む)」 sich in ein Buch vertiefen というニュアンスが強いと説明してくれたのを思い出します。
この単語、会話であまり耳にしないのは、「本に没頭する」機会が少ない、つまり単に使われるシチュエーションがあまりないからかな…。
もしこの単語が、標準ドイツ語の lesen のように、一般的に「本を読む」という意味で、日常的に、高い頻度で用いられる地方をご存じ、あるいはお住まいの方、どうかご一報いただけると、非常に嬉しく思います。どうか、よろしくお願いいたします。
トピ立て人です。これまで徒然なるままに、思いついた単語、表現を挙げきて恐縮です。
しかも、今回は Schimpfwort・ののしり言葉で、さらに気が引けるのですが、キールでは、S○○eiße! の代わりに、Schitte! が使われ事があります。
思いっきり、英語と似てますね。ある年配の女性曰く、S○○eiße! は、彼女たちの年代には憚られるけれど、Schitte! は、どうもそれよりはマイルド(笑)に響くようで、使用にさほど抵抗がないようです。
他の地方で、Schitte! をお聞きになった(そんなにしょっちゅうは、耳にしないでしょうけど…汗)方、いらっしゃいましたら、どうかご一報下さい。
しかも、今回は Schimpfwort・ののしり言葉で、さらに気が引けるのですが、キールでは、S○○eiße! の代わりに、Schitte! が使われ事があります。
思いっきり、英語と似てますね。ある年配の女性曰く、S○○eiße! は、彼女たちの年代には憚られるけれど、Schitte! は、どうもそれよりはマイルド(笑)に響くようで、使用にさほど抵抗がないようです。
他の地方で、Schitte! をお聞きになった(そんなにしょっちゅうは、耳にしないでしょうけど…汗)方、いらっしゃいましたら、どうかご一報下さい。
土曜日、友人に呼ばれて Laboe (潜水艦博物館等で有名な観光地)へ向かう途中、間違ったバス停で下車してしまいました。
しかし、怪我の功名か、その近くで Amtliche Bekanntmachungen (村の公式掲示板)で、Plattdeutsch で書かれたポスターを発見し、興味深かったのでご紹介いたします。
タイトルにある、形容詞「ハイケンドルフの」が heikendörper と、すでに「訛っちゃって」ますね。Hochdeutsch では heikendorfer でしょう。
De Fohrt na Norden は 当然 Die Fahrt nach Norden. ein が een になってますし、 buttjes は、butt + je + s で、オランダ語の縮小辞と全く同形の -je- と、複数語尾 -s が現れています。曜日の綴りも、面白いですね。
Karten gifft dat in't ... は、Karten gibt es im ... なのでしょう。in't は in dat の短縮で、Hochdeutsch では Dativ (3格)を取るところですが、やはり Akkusativ (4格)との混濁が見られるようです。
月曜日、Plattdeutsch 準ネイティブの友人に会うので、Hochdeutsch に訳すのを手伝ってもらうことにします。
しかし、怪我の功名か、その近くで Amtliche Bekanntmachungen (村の公式掲示板)で、Plattdeutsch で書かれたポスターを発見し、興味深かったのでご紹介いたします。
タイトルにある、形容詞「ハイケンドルフの」が heikendörper と、すでに「訛っちゃって」ますね。Hochdeutsch では heikendorfer でしょう。
De Fohrt na Norden は 当然 Die Fahrt nach Norden. ein が een になってますし、 buttjes は、butt + je + s で、オランダ語の縮小辞と全く同形の -je- と、複数語尾 -s が現れています。曜日の綴りも、面白いですね。
Karten gifft dat in't ... は、Karten gibt es im ... なのでしょう。in't は in dat の短縮で、Hochdeutsch では Dativ (3格)を取るところですが、やはり Akkusativ (4格)との混濁が見られるようです。
月曜日、Plattdeutsch 準ネイティブの友人に会うので、Hochdeutsch に訳すのを手伝ってもらうことにします。
nombu さん、こんにちは。トピ立て人です。ようこそ、いらっしゃいました。
Spargel は、北ドイツ本来の言い方では、Spars になるようです。でも都市部だと、Hochdeutsch (標準ドイツ語)に近い言葉が話され、あまり訛ってない(platt ではない)と思います。私も、Kiel では耳にしたことがありません。田舎、特にお年寄りにそういった方言話者が多いのは、各国共通ですね。
(訂正)
47.の私の投稿内、ポスターの表記が、Karten だと思って書いたのですが、どうも Korten のようですね。a → o は、ja → *jo , nicht wahr → *wohrに見られるように、北ドイツに特徴的と言えそうです。ノルド系の、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン語でも、カードは kort で、非常に良く似ています。
準ネイティブの友人、Sabrina は忙しそうだったので(今週、友人の結婚式のため日本に行く)、標準語訳は聞けそうにありませんでした。他を当たってみます。
Spargel は、北ドイツ本来の言い方では、Spars になるようです。でも都市部だと、Hochdeutsch (標準ドイツ語)に近い言葉が話され、あまり訛ってない(platt ではない)と思います。私も、Kiel では耳にしたことがありません。田舎、特にお年寄りにそういった方言話者が多いのは、各国共通ですね。
(訂正)
47.の私の投稿内、ポスターの表記が、Karten だと思って書いたのですが、どうも Korten のようですね。a → o は、ja → *jo , nicht wahr → *wohrに見られるように、北ドイツに特徴的と言えそうです。ノルド系の、デンマーク・ノルウェー・スウェーデン語でも、カードは kort で、非常に良く似ています。
準ネイティブの友人、Sabrina は忙しそうだったので(今週、友人の結婚式のため日本に行く)、標準語訳は聞けそうにありませんでした。他を当たってみます。
こんにちは、トピ立て人です。
47.の標準語訳を、私が属するコーラス団のメンバー(71歳)がやってくれたので、ご紹介します。
De Fohrt na Norden
Die Fahrt nach Norden
Een Singspeel in dree Törns vun "De Brummelbuttjes"
Ein Singspiel in 3 Akten von "den Brummjungs"
In de Aula vun de Grund- un Hauptschool an'n Schulredder
In der Aula der Grund- und Hauptschule am Schulredder
(Im Stundenplan)
Freedag, Sunnavend, Sünndag
Freitag, Sonnabend, Sonntag
Premiere
Premiere
Vörstellung
Vorstellung
mit Koffie & Kooken
mit Kaffee und Kuchen
Korten gifft dat in't Pressezentrum Heikendorf. Dorfstraße 8 oder ünner 0431....
Karten gibt es im Pressezentrum Heikendorf, Dorfstraße 8 oder unter 0431....
un ... un in't Internet ünner www....
und... und im Internet unter www...
とのことです。'buttje' という単語に関しては、NDR1(ラジオ)の Plattdeutsch 講座・初級編に解説がありました。この後すぐ、紹介させていただきます。
47.の標準語訳を、私が属するコーラス団のメンバー(71歳)がやってくれたので、ご紹介します。
De Fohrt na Norden
Die Fahrt nach Norden
Een Singspeel in dree Törns vun "De Brummelbuttjes"
Ein Singspiel in 3 Akten von "den Brummjungs"
In de Aula vun de Grund- un Hauptschool an'n Schulredder
In der Aula der Grund- und Hauptschule am Schulredder
(Im Stundenplan)
Freedag, Sunnavend, Sünndag
Freitag, Sonnabend, Sonntag
Premiere
Premiere
Vörstellung
Vorstellung
mit Koffie & Kooken
mit Kaffee und Kuchen
Korten gifft dat in't Pressezentrum Heikendorf. Dorfstraße 8 oder ünner 0431....
Karten gibt es im Pressezentrum Heikendorf, Dorfstraße 8 oder unter 0431....
un ... un in't Internet ünner www....
und... und im Internet unter www...
とのことです。'buttje' という単語に関しては、NDR1(ラジオ)の Plattdeutsch 講座・初級編に解説がありました。この後すぐ、紹介させていただきます。
Platt für Anfänger vom NDR1: - Buttje
Lea: Du sag mal, Gerd, was ist eigentlich ein Buttje?
Gerd: Das ist ein Junge, früher vor allem ein frecher, dreister Junge, der keine Manieren hatte. Butt heißt ja auch grob, plump und roh. Du büst een groden Buttje, een Rümdriever, Bummler, Slüngel, een Vagabunden. Die Buttjes, die buttjerten denn herum und machten die Gegend unsicher. Nee, auf Buttjes war man früher nicht gut zu sprechen.
Lea: Du sagst früher - und heute?
Gerd: Bei uns zuhause waren alle lütten Jungs Buttjes - und das war immer nett gemeint. Unsere Nachbarin nannte sogar ihren Mann Buttje und bei meiner Oma hieß der Wellensittich mal nicht Hansi sondern auch Buttje. So Lea, nu weeßt Bescheed.
Lea: Jo, nu weet ick Bescheed.
孫と思われるLeaが、Gerdに、buttje とは何か聞き、Gerdが説明してくれてます。
「若者」を意味するこの言葉、かつてはあまりポジティブなニュアンスで使われなかったようですが、どうも今は、逆のようです。
この会話自体、最初こそ標準語だったんですが、
nu weeßt bescheed (nun weißt du Bescheid)
Jo, nu weet ick Bescheed. (Ja, nun weiß ich Bescheid.)
と、最後は二人とも platt になっちゃってますね。楽しい。
Lea: Du sag mal, Gerd, was ist eigentlich ein Buttje?
Gerd: Das ist ein Junge, früher vor allem ein frecher, dreister Junge, der keine Manieren hatte. Butt heißt ja auch grob, plump und roh. Du büst een groden Buttje, een Rümdriever, Bummler, Slüngel, een Vagabunden. Die Buttjes, die buttjerten denn herum und machten die Gegend unsicher. Nee, auf Buttjes war man früher nicht gut zu sprechen.
Lea: Du sagst früher - und heute?
Gerd: Bei uns zuhause waren alle lütten Jungs Buttjes - und das war immer nett gemeint. Unsere Nachbarin nannte sogar ihren Mann Buttje und bei meiner Oma hieß der Wellensittich mal nicht Hansi sondern auch Buttje. So Lea, nu weeßt Bescheed.
Lea: Jo, nu weet ick Bescheed.
孫と思われるLeaが、Gerdに、buttje とは何か聞き、Gerdが説明してくれてます。
「若者」を意味するこの言葉、かつてはあまりポジティブなニュアンスで使われなかったようですが、どうも今は、逆のようです。
この会話自体、最初こそ標準語だったんですが、
nu weeßt bescheed (nun weißt du Bescheid)
Jo, nu weet ick Bescheed. (Ja, nun weiß ich Bescheid.)
と、最後は二人とも platt になっちゃってますね。楽しい。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
ドイツ語 更新情報
-
最新のアンケート