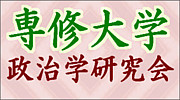12月17日 18:00〜20:00
▼テーマ
在日外国人への教育政策
▼協賛
駒澤大学政治学研究会
専修大学政治学研究会SCOP
▼参考文献
なし
▼参加者(敬称略)
内田、江尻、楠浦、佐野、津田、中橋、二瓶、福田、丸山、八坂、山本
▼まとめ
【1】担当者
佐野
・担当者はレジュメ持参。
【2】議論の流れ
論点:外国人に義務教育を受けさせるべきか。
二瓶:反対である。外国人労働者が来るのは都会である。都会ではすでに教室の空きが問題になっているのに、外国人を受け入れた場合にはさらにそうした問題が懸念されるのではないか。
江尻:日本は中国と様々な問題を抱えている。韓国もそうである。そうした人々と同じ教室で授業を受けるということに違和感がある。そのことについて賛成の人たちはどう思っているのか。
佐野:財源の問題を出されると言い返せないところがある。
楠浦:逆に外国人を育てて日本で働かせれば所得税や法人税を払ってもらえればいい、という考えもある。
佐野:そういう面はこれから勉強しないと答えきれないところがある。
楠浦:この論点は子供に対するというより、親が子供に義務教育を受けさせることを制度化する、ということですよね。すなわち親にそうした制約を課すことによって、子供に教育を受ける機会が与えられ、日本の義務教育においても国際化が進む。
佐野:国際的な問題、宗教間での問題、歴史的な問題などは、日本から積極的なアクションを起こさなければいけない時になってきている。尖閣諸島の問題が出たり、朝鮮との間で反日だとか、反韓だとかが表面化されて、その表面化されて右翼だとか左翼だとかいうような分け方がされるような世の中になってしまったというところでは、やはり子供のような歴史的な背景を知らない人たちに正しい教育を受けさせることが必要だ。そうしたことから、日本の教育をもっとオープンにするべきである。またその場合教育者の質が重要である。宗教や歴史的な観点で偏った人にしてしまうと、正しい教育は受けさせることができない。
江尻:インターナショナルスクールでは、小学校、中学校で自国の文化を学びながら、日本の文化を少しずつ学ぶ。それから初めて日本人と向き合う。そうした方法の方が日本人との摩擦が少なくてよい。それでもやはり小学校、中学校から義務教育をするべきだと思うか。
二瓶:6歳から15歳はよく喧嘩をする歳である。そうしたときに外国人と喧嘩をしてしまうと、大人になったときにその記憶によって外国人と仲が悪くなるということがありうる。
佐野:現在、国境のボーダレス化が進められている。そうした中でアイデンティティの確立が問題になっている。自国のアイデンティティは自国の政治であったり、経済であったり、また歴史によって確立するものである。その一方で他国のアイデンティティには寛容になるべきなのだろうか。またそうするべきならどこまで寛容になるべきか。
江尻:それは一番、言語が重要である。言語が違ってしまうと、かなり限定的なコミュニケーションしかできない。そうすると完全に受け入れるということはできない。そうした意味でもインターナショナルスクールでの教育が重要だ。
丸山:日本の企業の中でもとなりの席が外国人という国際化の現状が進んでいる。そうしたことから、日本でも幼い時から外国人になれることが重要になってきている。外国人のアイデンティティの受容も幼い時から慣れておかないとできない。
津田:小さいときは純真無垢から、そうした時から外国人と触れ合って協調性を高めるということ重要だ。大人になると異なるものを受け入れなくなってしまう。
八坂:インターナショナルスクールで教育してからでも遅くないのではないか。
楠浦:論点の義務教育という点が不明確である。義務教育といった場合、インターナショナルスクールへ行くという選択もありうる。だからもし義務教育を制度化した場合、実際は教育を受けていない外国人に教育を受けさせるということが目的になる。そこを中心に議論するべきだ。
福田:つまり外国人の貧困家庭にどうやって教育を受けさせることができるか、が論点である。
江尻:どのような学校に入学させるかが問題だ。
佐野:外国人で教育を受けていな人々は、いわゆるニューカマーといわれる人たちである。彼らは彼らの母国語しか話せないことが多い。そうするとその子供も親の言語しか話せず、日本に馴染めなくなることが多い。そうした人たちのために義務教育の制度をつくって、日本語を教えるべきである。
中橋:日本人の場合、義務教育費が払えない家庭はどうなっているのか。
佐野:日本人に対しては補償金があったり、教育費が免除されたりしている。
山本:結局、論点が2つある。1つは外国人に日本の義務教育を受けさせるべきか。もう1つは外国人の貧困家庭にどうやって教育をうけさせるか。
中橋:もっと現実的にいうとどうやって貧困家庭に教育費の補償金を払うかという論点になる。
佐野:私としては後者の論点について話し合いたい。
江尻:そうした問題は結局NPOなどに頼らざるをえない。
福田:NPOはこうした場合どのようなアプローチをするのか。
佐野:私が早稲田大学で参加しているNPOでは語学や歴史などアイデンティティに関わることは教えないで、もっと基本的な教養だけを教える。ただ理想的には日本語も教えていきたい。
楠浦:ベトナムのニューカマーの子供たちに教えているNPOもある。そこでは漢字と算数を教えて、日本社会に適応できるようにしている。
楠浦:都会と地方で事情が違う。都会では早稲田大学のサークルのような自主的に行動してくれる団体がある。しかし、地方ではそうした団体がないので、どうやって資金や人材を確保するかという問題がある。しかも文科省に申請してもなかなか補償金がもらえないという現実がある。
福田:そうした面で外国人の基本的人権は尊重されていない。
山本:この論点は制度面について議論しているのか。それとも金銭面で議論しているのか。
佐野:金銭面の話になると複雑になるので、制度面について話したい。
中橋:制度面で話しても、結局金銭的な問題になるのではないか。
福田:制度面の話とは、現状の義務教育制度の中でどのように外国人を受け入れるかという話だ。
楠浦:外国人の人たちをどうやったら日本人の教育環境に馴染ませるかを中心に議論した方がよい。ただ外国人といっても様々である。先ほどインターナショナルスクールの話がでたが、イギリスのそれと朝鮮のそれとは全然違う。だからまずどういった外国人を焦点にしてぎろんしているかを明確にしたい。
佐野:ニューカマーを中心に議論したい。ニューカマーとは中東アジアや南米の人たちのことをいい、何かしらの理由で日本に来て、そのまま日本で労働をした人たちの子供のことをいう。
楠浦:その人たちを教育面でどのように保障するかが論点だ。NPOで聞いた話では、そうした人たちは漢字がわららなくて学校を辞めてしまうケースが多いようだ。そして、そうした人たちはうまく就労につけず、肉体労働につくパターンが多い。そうした職業にも就けない人たちは犯罪に走ってしまう。
山本:もう1つ確認があって、ニューカマーは新しく日本に就労に来た人たちはいれないのか。
佐野:ニューカマーの定義ではそうした人たちは入らない。
楠浦:これまででニューカマーとの一緒に教育を受けた経験はなかったのか。
佐野:空手をやっているときに友達になったブラジル人の子がそうだった。彼はずっと日本の義務教育を受けていた。そこで感じたのは彼が「日本の教育を受けている」ということを自覚していなかったことだ。もしそうした教育を素直に受けることができるなら、日本の文化に馴染んでいくことができるのではないか。
山本:言葉の壁はそれほど問題ではなかったのか。
佐野:大丈夫だったようだ。
楠浦:実際の問題は日本人と外国人との間でコミュニケーションをとる機会がないということが、文化的な対立になってしまうことが多いようだ。たとえば日本人はきれい好きだが、ブラジル人は外にゴミを捨てることが少なくない。日本人はそれを見てブラジル人を嫌いになったりする。だからいかに社会全体で共存するかが重要である。
山本:義務教育の点だけでいうならば、教育費を免除することや、学校の資料を外国語することによって対応できるのではないか。
中橋:しかし、そうしたことに社会の合意が得られるのか。もっといえばその分だけ自分たちが多く税金を払えるかどうかという問題になる。
楠浦:ただ憲法上、外国人の社会権は保障されるということになっている。
江尻:憲法で保障されているといっても、実際に日本人がそれを受け入れるかという点では難しいところがある。
福田:たとえば朝鮮学校は特殊で一つのコミュニティとして感じがある。だから日本人にとっても受け入れが難しい。そうした状況でどのようにしたら日本のコミュニティに受け入れることができるか。そこでの教育の意義は何か。
中橋:自分は外国人の子供をそのまま義務教育に入学させればいいと思う。子供はそれぐらいの適応力はある。
福田:外国人に対するいじめはどのような対策をしても起こりうる。それならば早い段階から日本の義務教育を受けさせて、外国人が当たり前にいる状況を作り出すことが必要だ。
二瓶:自分も外国人が日本のコミュニティに入るという観点では早い段階での義務教育に賛成である。その方が外国人の存在を当たり前のように感じるようになり、彼らへの偏見も無くなると思う。
津田:小さいときは純粋だから外国人を受け入れやすい。大人になると偏見が入ってしまう。
内田:私の出身は群馬県でベトナム人が多かった。彼らは学校に来なくなってしまったり、ベトナム人の間だけで遊んだりしていた。しかも彼らへのいじめもあった。グローバル化が進む中で、日本人はこうした問題に無頓着である。学校の教育でしっかりとこうした問題に取り組むべき。
八坂:義務化した方がいい。その方が日本人にとっても外国人にとってもメリットがある。
丸山:やはり言語の面で問題がある。そうした問題がある以上、外国人が孤立してしまうことがある。それならばインターナショナルスクールである程度日本語を勉強してからの方がいいのではないか。
山本:ニューカマーとしては義務教育を受ける権利があっていいと思う。しかし、インターナショナルスクールに通う場合、補償金は一切出ないということでいい。その中で日本の文化に合うような教育をしていけばいい。
江尻:外国人を義務教育のなかに急に入れるということは反対である。なぜなら日本人の方で外国人を受け入れる準備ができていないからだ。だからもっと外国人が日本の文化に慣れてから受け入れていくべきである。
楠浦:政治は多数派の意見が尊重されるが、今回の問題は外国人という少数派の問題だった。だから今回の問題はどうやって実現させるのかが難しかった。今後も考えていきたい。
佐野:ニューカマーの問題に限るなら、やはり日本のコミュニティに馴染めないというのは問題だから、義務教育する必要があると思う。それから学校側が言語の面や文化の面で親をフォローしなければいけない。そうしたところから日本の国際化につながっていくのではないか。
(敬称略)
▼テーマ
在日外国人への教育政策
▼協賛
駒澤大学政治学研究会
専修大学政治学研究会SCOP
▼参考文献
なし
▼参加者(敬称略)
内田、江尻、楠浦、佐野、津田、中橋、二瓶、福田、丸山、八坂、山本
▼まとめ
【1】担当者
佐野
・担当者はレジュメ持参。
【2】議論の流れ
論点:外国人に義務教育を受けさせるべきか。
二瓶:反対である。外国人労働者が来るのは都会である。都会ではすでに教室の空きが問題になっているのに、外国人を受け入れた場合にはさらにそうした問題が懸念されるのではないか。
江尻:日本は中国と様々な問題を抱えている。韓国もそうである。そうした人々と同じ教室で授業を受けるということに違和感がある。そのことについて賛成の人たちはどう思っているのか。
佐野:財源の問題を出されると言い返せないところがある。
楠浦:逆に外国人を育てて日本で働かせれば所得税や法人税を払ってもらえればいい、という考えもある。
佐野:そういう面はこれから勉強しないと答えきれないところがある。
楠浦:この論点は子供に対するというより、親が子供に義務教育を受けさせることを制度化する、ということですよね。すなわち親にそうした制約を課すことによって、子供に教育を受ける機会が与えられ、日本の義務教育においても国際化が進む。
佐野:国際的な問題、宗教間での問題、歴史的な問題などは、日本から積極的なアクションを起こさなければいけない時になってきている。尖閣諸島の問題が出たり、朝鮮との間で反日だとか、反韓だとかが表面化されて、その表面化されて右翼だとか左翼だとかいうような分け方がされるような世の中になってしまったというところでは、やはり子供のような歴史的な背景を知らない人たちに正しい教育を受けさせることが必要だ。そうしたことから、日本の教育をもっとオープンにするべきである。またその場合教育者の質が重要である。宗教や歴史的な観点で偏った人にしてしまうと、正しい教育は受けさせることができない。
江尻:インターナショナルスクールでは、小学校、中学校で自国の文化を学びながら、日本の文化を少しずつ学ぶ。それから初めて日本人と向き合う。そうした方法の方が日本人との摩擦が少なくてよい。それでもやはり小学校、中学校から義務教育をするべきだと思うか。
二瓶:6歳から15歳はよく喧嘩をする歳である。そうしたときに外国人と喧嘩をしてしまうと、大人になったときにその記憶によって外国人と仲が悪くなるということがありうる。
佐野:現在、国境のボーダレス化が進められている。そうした中でアイデンティティの確立が問題になっている。自国のアイデンティティは自国の政治であったり、経済であったり、また歴史によって確立するものである。その一方で他国のアイデンティティには寛容になるべきなのだろうか。またそうするべきならどこまで寛容になるべきか。
江尻:それは一番、言語が重要である。言語が違ってしまうと、かなり限定的なコミュニケーションしかできない。そうすると完全に受け入れるということはできない。そうした意味でもインターナショナルスクールでの教育が重要だ。
丸山:日本の企業の中でもとなりの席が外国人という国際化の現状が進んでいる。そうしたことから、日本でも幼い時から外国人になれることが重要になってきている。外国人のアイデンティティの受容も幼い時から慣れておかないとできない。
津田:小さいときは純真無垢から、そうした時から外国人と触れ合って協調性を高めるということ重要だ。大人になると異なるものを受け入れなくなってしまう。
八坂:インターナショナルスクールで教育してからでも遅くないのではないか。
楠浦:論点の義務教育という点が不明確である。義務教育といった場合、インターナショナルスクールへ行くという選択もありうる。だからもし義務教育を制度化した場合、実際は教育を受けていない外国人に教育を受けさせるということが目的になる。そこを中心に議論するべきだ。
福田:つまり外国人の貧困家庭にどうやって教育を受けさせることができるか、が論点である。
江尻:どのような学校に入学させるかが問題だ。
佐野:外国人で教育を受けていな人々は、いわゆるニューカマーといわれる人たちである。彼らは彼らの母国語しか話せないことが多い。そうするとその子供も親の言語しか話せず、日本に馴染めなくなることが多い。そうした人たちのために義務教育の制度をつくって、日本語を教えるべきである。
中橋:日本人の場合、義務教育費が払えない家庭はどうなっているのか。
佐野:日本人に対しては補償金があったり、教育費が免除されたりしている。
山本:結局、論点が2つある。1つは外国人に日本の義務教育を受けさせるべきか。もう1つは外国人の貧困家庭にどうやって教育をうけさせるか。
中橋:もっと現実的にいうとどうやって貧困家庭に教育費の補償金を払うかという論点になる。
佐野:私としては後者の論点について話し合いたい。
江尻:そうした問題は結局NPOなどに頼らざるをえない。
福田:NPOはこうした場合どのようなアプローチをするのか。
佐野:私が早稲田大学で参加しているNPOでは語学や歴史などアイデンティティに関わることは教えないで、もっと基本的な教養だけを教える。ただ理想的には日本語も教えていきたい。
楠浦:ベトナムのニューカマーの子供たちに教えているNPOもある。そこでは漢字と算数を教えて、日本社会に適応できるようにしている。
楠浦:都会と地方で事情が違う。都会では早稲田大学のサークルのような自主的に行動してくれる団体がある。しかし、地方ではそうした団体がないので、どうやって資金や人材を確保するかという問題がある。しかも文科省に申請してもなかなか補償金がもらえないという現実がある。
福田:そうした面で外国人の基本的人権は尊重されていない。
山本:この論点は制度面について議論しているのか。それとも金銭面で議論しているのか。
佐野:金銭面の話になると複雑になるので、制度面について話したい。
中橋:制度面で話しても、結局金銭的な問題になるのではないか。
福田:制度面の話とは、現状の義務教育制度の中でどのように外国人を受け入れるかという話だ。
楠浦:外国人の人たちをどうやったら日本人の教育環境に馴染ませるかを中心に議論した方がよい。ただ外国人といっても様々である。先ほどインターナショナルスクールの話がでたが、イギリスのそれと朝鮮のそれとは全然違う。だからまずどういった外国人を焦点にしてぎろんしているかを明確にしたい。
佐野:ニューカマーを中心に議論したい。ニューカマーとは中東アジアや南米の人たちのことをいい、何かしらの理由で日本に来て、そのまま日本で労働をした人たちの子供のことをいう。
楠浦:その人たちを教育面でどのように保障するかが論点だ。NPOで聞いた話では、そうした人たちは漢字がわららなくて学校を辞めてしまうケースが多いようだ。そして、そうした人たちはうまく就労につけず、肉体労働につくパターンが多い。そうした職業にも就けない人たちは犯罪に走ってしまう。
山本:もう1つ確認があって、ニューカマーは新しく日本に就労に来た人たちはいれないのか。
佐野:ニューカマーの定義ではそうした人たちは入らない。
楠浦:これまででニューカマーとの一緒に教育を受けた経験はなかったのか。
佐野:空手をやっているときに友達になったブラジル人の子がそうだった。彼はずっと日本の義務教育を受けていた。そこで感じたのは彼が「日本の教育を受けている」ということを自覚していなかったことだ。もしそうした教育を素直に受けることができるなら、日本の文化に馴染んでいくことができるのではないか。
山本:言葉の壁はそれほど問題ではなかったのか。
佐野:大丈夫だったようだ。
楠浦:実際の問題は日本人と外国人との間でコミュニケーションをとる機会がないということが、文化的な対立になってしまうことが多いようだ。たとえば日本人はきれい好きだが、ブラジル人は外にゴミを捨てることが少なくない。日本人はそれを見てブラジル人を嫌いになったりする。だからいかに社会全体で共存するかが重要である。
山本:義務教育の点だけでいうならば、教育費を免除することや、学校の資料を外国語することによって対応できるのではないか。
中橋:しかし、そうしたことに社会の合意が得られるのか。もっといえばその分だけ自分たちが多く税金を払えるかどうかという問題になる。
楠浦:ただ憲法上、外国人の社会権は保障されるということになっている。
江尻:憲法で保障されているといっても、実際に日本人がそれを受け入れるかという点では難しいところがある。
福田:たとえば朝鮮学校は特殊で一つのコミュニティとして感じがある。だから日本人にとっても受け入れが難しい。そうした状況でどのようにしたら日本のコミュニティに受け入れることができるか。そこでの教育の意義は何か。
中橋:自分は外国人の子供をそのまま義務教育に入学させればいいと思う。子供はそれぐらいの適応力はある。
福田:外国人に対するいじめはどのような対策をしても起こりうる。それならば早い段階から日本の義務教育を受けさせて、外国人が当たり前にいる状況を作り出すことが必要だ。
二瓶:自分も外国人が日本のコミュニティに入るという観点では早い段階での義務教育に賛成である。その方が外国人の存在を当たり前のように感じるようになり、彼らへの偏見も無くなると思う。
津田:小さいときは純粋だから外国人を受け入れやすい。大人になると偏見が入ってしまう。
内田:私の出身は群馬県でベトナム人が多かった。彼らは学校に来なくなってしまったり、ベトナム人の間だけで遊んだりしていた。しかも彼らへのいじめもあった。グローバル化が進む中で、日本人はこうした問題に無頓着である。学校の教育でしっかりとこうした問題に取り組むべき。
八坂:義務化した方がいい。その方が日本人にとっても外国人にとってもメリットがある。
丸山:やはり言語の面で問題がある。そうした問題がある以上、外国人が孤立してしまうことがある。それならばインターナショナルスクールである程度日本語を勉強してからの方がいいのではないか。
山本:ニューカマーとしては義務教育を受ける権利があっていいと思う。しかし、インターナショナルスクールに通う場合、補償金は一切出ないということでいい。その中で日本の文化に合うような教育をしていけばいい。
江尻:外国人を義務教育のなかに急に入れるということは反対である。なぜなら日本人の方で外国人を受け入れる準備ができていないからだ。だからもっと外国人が日本の文化に慣れてから受け入れていくべきである。
楠浦:政治は多数派の意見が尊重されるが、今回の問題は外国人という少数派の問題だった。だから今回の問題はどうやって実現させるのかが難しかった。今後も考えていきたい。
佐野:ニューカマーの問題に限るなら、やはり日本のコミュニティに馴染めないというのは問題だから、義務教育する必要があると思う。それから学校側が言語の面や文化の面で親をフォローしなければいけない。そうしたところから日本の国際化につながっていくのではないか。
(敬称略)
|
|
|
|
|
|
|
|
専修大学政治学研究会SCOP 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
専修大学政治学研究会SCOPのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人