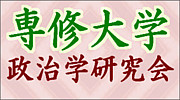12月12日にに行われました〈戦争および平和を考えるシンポジウムー非対称戦争化におけるアメリカの戦略を中心にー〉のレヴューです。
講演会には、SCOPからは10名、駒沢大政治学研究会さんから1名、ゲスト3名の計14名が参加し、『戦争形態の変化と米国の国防政策からみた今後の世界』という内容で講演会をしていただきました。以下は講演会レヴューです。
○モノゴト=多様な見方がある。
二つの生き方
客観的な生き型=リスクを考える。
↕
カッコいい生き方=リスク考えない。
⇒客観的なモノの見方、考え方とは何か。
EX:〈左翼〉平和を守れ!人の命を守れ!!
〈右翼〉全体の利益を守れ!!
↓BUT
前提条件がないため、そもそも両者を比較できない。
どういう判断基準なのか、何を優先させるのかを考える。
1、戦略構造の変化。
○戦争と国際政治がどう変わってきたのか。
その中でアメリカはどういった情勢分析をするのか。
戦争で人が死ぬようになったのは現代
EX:中世のある戦争
→2000対2000の戦い。死者は2名(原因は日射病)
∵大半が傭兵。金儲けが目的。
↓
国民国家の形成により大衆が従軍。
・鉄道・電信の発展→運搬・情報交換のが迅速になる。
・大衆の戦争導引→女性の地位向上と福祉の進展。
↓
現代の戦争=「いかに殺すのか」という戦争概念が変化。
∵テレビ報道の導入、少子化による子供の死への接し方が変化。
・紛争の潮流の変化
紛争は減っている!!(CF:ウプサー大学の調査)。
テロもピークは90年代後半だった。
↓
戦闘空間が人道的に。
⇒「相手も、自分も死なない戦争」がやりたい。
∴サイバー空間の戦争利用。
E=ルトワック「戦争は平和を生み、平和は戦争を生む」。
⇒戦争は放置すべき!!
CF:話し合いで終結した戦争の再発率=30%
殺し合いで終結した戦争の再発率=15%
EX:スリランカ紛争
→ノルウェーの介入により一時的には停戦も、再発。
C=クラウゼヴィッツ 「相手を無力化しないと終わらない」
田中明彦 「戦争の中世化」
結局は、いかに自分にとって都合の良い戦争をするのか。
◎AかBかという問題ではない。一つの見方として考えなければならない。
1−2、戦略構造の変化。
・北東アジア
〈従来〉日本・中国・アメリカの三国間関係。
↓BUT
近年のロシアの台頭と北方領土問題以外での日・ロ関係の緊密化。
◎一つのシナリオとして
日本・中国・アメリカ・ロシアの四国間関係を考える必要性。
2、米国国防政策
・「調達の休日」の終わり。
・ラムズフェルドの遺産
→疲弊した組織:新兵器の過剰購入。
政軍関係:軍人の制止にも関わらず、ラムズフェルドが強行。
ソフトパワー
・ゲーツ
NSS(国家安全保障戦略・大統領)
QDR(四年ごとの国防計画見直し・国防総省)
NMD(ミサイル防衛・軍人)
などのバランス。
・課題
帝国防衛:
→植民地保有時のイギリス・・・速くて遠くまでいける装備へ。
政軍関係
拡大抑止
3、今後の情勢
・アフガニスタン
プラスの変化:タリバンから離脱する部族が出現。
マイナスの面:タリバンは、冬にはパキスタンへ。
↓
オバマ大統領の方針:アフガン内の幹線道路を中心に駐軍。
but 幹線道路から離れた地帯ではタリバンが潜伏。
・日米同盟→政策的反発へ。
アメリカ:日米同盟は不要。
↓
日米間に感覚の齟齬。
日米同盟にはまだまだ軍事的分野以外の部分でやれることがある。
一方で、アメリカが方針転換すれば、日本独自の防衛政策が求められる。
尚、当日の様子は、写真をすでにアップしておりますのでそちらをご参照ください。
参加者の皆様、ご来場ありがとうございました。また、関係者の皆様、大変お疲れ様でした。
今後とも宜しくお願いいたします。
講演会には、SCOPからは10名、駒沢大政治学研究会さんから1名、ゲスト3名の計14名が参加し、『戦争形態の変化と米国の国防政策からみた今後の世界』という内容で講演会をしていただきました。以下は講演会レヴューです。
○モノゴト=多様な見方がある。
二つの生き方
客観的な生き型=リスクを考える。
↕
カッコいい生き方=リスク考えない。
⇒客観的なモノの見方、考え方とは何か。
EX:〈左翼〉平和を守れ!人の命を守れ!!
〈右翼〉全体の利益を守れ!!
↓BUT
前提条件がないため、そもそも両者を比較できない。
どういう判断基準なのか、何を優先させるのかを考える。
1、戦略構造の変化。
○戦争と国際政治がどう変わってきたのか。
その中でアメリカはどういった情勢分析をするのか。
戦争で人が死ぬようになったのは現代
EX:中世のある戦争
→2000対2000の戦い。死者は2名(原因は日射病)
∵大半が傭兵。金儲けが目的。
↓
国民国家の形成により大衆が従軍。
・鉄道・電信の発展→運搬・情報交換のが迅速になる。
・大衆の戦争導引→女性の地位向上と福祉の進展。
↓
現代の戦争=「いかに殺すのか」という戦争概念が変化。
∵テレビ報道の導入、少子化による子供の死への接し方が変化。
・紛争の潮流の変化
紛争は減っている!!(CF:ウプサー大学の調査)。
テロもピークは90年代後半だった。
↓
戦闘空間が人道的に。
⇒「相手も、自分も死なない戦争」がやりたい。
∴サイバー空間の戦争利用。
E=ルトワック「戦争は平和を生み、平和は戦争を生む」。
⇒戦争は放置すべき!!
CF:話し合いで終結した戦争の再発率=30%
殺し合いで終結した戦争の再発率=15%
EX:スリランカ紛争
→ノルウェーの介入により一時的には停戦も、再発。
C=クラウゼヴィッツ 「相手を無力化しないと終わらない」
田中明彦 「戦争の中世化」
結局は、いかに自分にとって都合の良い戦争をするのか。
◎AかBかという問題ではない。一つの見方として考えなければならない。
1−2、戦略構造の変化。
・北東アジア
〈従来〉日本・中国・アメリカの三国間関係。
↓BUT
近年のロシアの台頭と北方領土問題以外での日・ロ関係の緊密化。
◎一つのシナリオとして
日本・中国・アメリカ・ロシアの四国間関係を考える必要性。
2、米国国防政策
・「調達の休日」の終わり。
・ラムズフェルドの遺産
→疲弊した組織:新兵器の過剰購入。
政軍関係:軍人の制止にも関わらず、ラムズフェルドが強行。
ソフトパワー
・ゲーツ
NSS(国家安全保障戦略・大統領)
QDR(四年ごとの国防計画見直し・国防総省)
NMD(ミサイル防衛・軍人)
などのバランス。
・課題
帝国防衛:
→植民地保有時のイギリス・・・速くて遠くまでいける装備へ。
政軍関係
拡大抑止
3、今後の情勢
・アフガニスタン
プラスの変化:タリバンから離脱する部族が出現。
マイナスの面:タリバンは、冬にはパキスタンへ。
↓
オバマ大統領の方針:アフガン内の幹線道路を中心に駐軍。
but 幹線道路から離れた地帯ではタリバンが潜伏。
・日米同盟→政策的反発へ。
アメリカ:日米同盟は不要。
↓
日米間に感覚の齟齬。
日米同盟にはまだまだ軍事的分野以外の部分でやれることがある。
一方で、アメリカが方針転換すれば、日本独自の防衛政策が求められる。
尚、当日の様子は、写真をすでにアップしておりますのでそちらをご参照ください。
参加者の皆様、ご来場ありがとうございました。また、関係者の皆様、大変お疲れ様でした。
今後とも宜しくお願いいたします。
|
|
|
|
|
|
|
|
専修大学政治学研究会SCOP 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
専修大学政治学研究会SCOPのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人