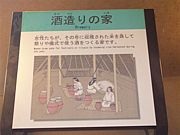1、現在の日本酒のマーケット
現在の日本酒の出荷量は2011年現在で60万1807KLで最盛期167万5000KL(1975年)の約36%の出荷量です。そのうち特定名称酒の出荷量が約25%と言われています。
海外への輸出量は約1万4000KL(2011年)で日本酒出荷量の約2.3%で、毎年少しずつではありますが、輸出量が増えてきています。
2、日本酒の国内での消費量の内訳
日本酒の消費量のうち約70%が家庭での消費で、そのうち約83%が50歳以上の世代の方が消費されていて、20歳代での消費量が約2.7%、30歳代での消費量が約4.9%と言われています。(日本政策投資銀行新潟支店2010年のレポートより)
3、日本酒の飲用アルコール度数は、他の醸造酒や蒸留酒と比較しても高い方である
日本酒の通常商品のアルコール度数はほとんどが15%~16%で、原酒となると主に18~19%となっています。ビール、酎ハイのアルコール度数が約4~5%、ワインのアルコール度数が約13%、焼酎が25%~35%でほとんどが6:4か5:5で消費されるので25%で15%又は、12.5%で消費され、ウィスキーになると40%の商品をハイボールを1:4にすると8%のアルコール度数となります。他にもスピリッツ系などがあり、ストレートで飲むことがありますが、ストレートで飲む場合と割って飲む場合では飲み方が違うので酔う速度が違いますし、チビチビ飲むのが普通です。
食事に合わせて普通に飲む分には日本酒のアルコール度数というのは他の酒類に比較して高いと思うので、あまりアルコール慣れしていない若年層からは飲みにくい商材となっていると考えられます。
4、飲酒の強要と日本酒
最近では、少なくなっていると思いますが、会社や大学のサークルに入った際の飲み会で飲酒を強要されその時に飲んだ日本酒が美味しくなくて、日本酒が嫌いになったという話を一世代前までの話の中でよく聞きました。ここで日本酒嫌いになる理由としては、?アルコールにあまり慣れていない上に日本酒自体のアルコール度数が高い、?ここで強要されて飲まされている日本酒自体がほとんど特定名称酒ではなく、三増酒であった。?日本酒というのは単独で飲むのではなく、食べ物と合わせてこそ本来の美味しさを味わうことができる。以上の3つの主な理由が挙げられると思います。
5、現在の日本酒には2種類の日本酒がある
1つ目が主に普通酒として生産されている増醸酒で、2つ目が純米酒、吟醸酒に代表される特定名称酒である。1つ目の増醸酒というのは元々、昭和初期の戦時中に米と酒不足から合成酒の技術をもとに満州で確立された第1次増産酒、第2次増産酒の技術を基に戦中の昭和19年に三増酒が技術的に確立され、戦後の米不足の時代に本格的に三増酒が生産され、平成18年に醪に対して添加されるアルコールの量が規制されて現在は二増酒として生産されています。満州で第1次増産酒、第2次増産酒が技術的に確立された際には増産酒を日本酒と呼ぶことに対して疑問視されていました。ただ、戦後になって米不足や戦争で技術が失われたこともあり増醸酒は日本酒の普通酒として定着し、この三増酒の市場のパイを巡って大手と中堅の酒蔵が争ってきた結果、現在の日本酒離れを招いた経緯があります。
2つ目の特定名称酒に関しては1992年に級別制度が廃止された以降に日本酒の造りを元に日本酒に対して付けられるようになった名称で、米だけで造ったお酒に対して純米酒、特別純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒、一部アルコールを添加した酒に対して、本醸造酒、特別本醸造酒、吟醸酒、大吟醸酒の8つのカテゴリーが確立されて現在に至っています。
この特定名称酒に関しては、現在ある醸造酒の中で世界一技術的に生産するのが難しい酒だと言われていて、食中酒として料理と一緒に食べて本来の能力をすべて発揮するというのが特定名称酒で、ゼロ戦と同じように飲み手に対してもある程度の技術を要求する部分があり、若い方々には中々日本酒の良さを理解してもらうのが難しい部分があります。
ただし、特定名称酒の持つ本来の良さが分かれば、他の酒類とは比較出来ない位いいものであるのも事実なのです。
6、急性アルコール中毒による年間の搬送者数
東京消防庁の平成18年のデータによれば、東京だけで年間13,397人の方が急性アルコール中毒により病院に搬送されています。そのうち、未成年者が810人約6%、20代以下が7,077人(未成年を含む)約53%と全体の半分以上を占めています。この急性アルコール中毒に関して言えば、日本酒だけが原因ではありませんが、日本人が全体としてアルコールを安全に飲むことをあまり理解していないことが原因にあげられると思われます。
7、急性アルコール中毒による実際の死亡事例
平成24年5月に北海道の小樽商科大学のアメリカンフットボール部のバーベキューパーティーで上級生から下級生に対する飲酒の強要が行われ、9名が急性アルコール中毒で搬送され(うち未成年が7名)、その中の一年生部員が急性アルコール中毒で心肺停止を起こし死亡しています。
ここで問題なのは、アルコールの強要が行われたことと、9名もの急性アルコール中毒での搬送者を出している事であります。
病院側から見れば急性アルコール中毒の患者は暴れたりして、非常に手がかかるので迷惑な存在であり、昨今の医師や看護士の不足を考えると単に急性アルコール中毒で体調を崩しただけでは済まない話になってきています。
8、酔いのメカニズムを血中アルコール濃度から考えてみる
?血中アルコール濃度0.05%以下
ほろ酔い一歩手前前期と呼ばれ、アルコールは血液の中に速やかに移行し、大脳の新皮質の機能を軽く抑制麻痺する。
?血中アルコール濃度0.05〜0.15%
ほろ酔い期と呼ばれ、理性的な知的活動を担っている新皮質と本能や情動を支配する大脳辺縁系の働きが歪んできて、本能的行動が一部無修正に表面に出てしまう。
?血中アルコール濃度0.15〜0.25%
酩酊期と呼ばれ、ほろ酔い状態から更にアルコールの量が増えてくると新皮質の働きはすっかり鈍り、大脳辺縁系の働きが独壇場と化して、大声を出したり、笑ったり、泣いたり、怒ったりする。
?血中アルコール濃度0.25〜0.35%
短期の記憶を担っている海馬にまで作用してくる。その時点の記憶がなくなってしまう。(ブラックアウト)俗に言う全く覚えていない状態である。
?血中アルコール濃度0.35〜0.50%
昏睡期と呼ばれ、これ以上の飲み、アルコールの作用が延髄まで及ぶと基本的な生命活動が鈍り、呼吸中枢が麻痺し、昏睡状態に陥り、死に至ることがある。
非常に短時間に大量に飲んだ場合、脳全体がアルコール漬けとなり、いきなり昏睡状態になることもある。
一気飲みなどせずにゆっくりと飲まなければ自身の酔い具合が分からないので、急に飲んだりすればいきなり昏睡状態になることもある。
9、やはりアルコールにかかわる人間が一番アルコールの恐ろしさを認識すべき
利き酒師、ソムリエ、酒類販売取扱責任者等といったアルコールの専門家は、アルコールの恐ろしさを人一倍認識し、一般の人間に指導できるだけの能力を備えないことには、国内のアルコール市場はますます低迷する。
日本国内では、フグなどの毒性を持った魚や食材を専門に扱う料理店も複数存在しますが、そこで一般の消費者が安心して食事ができるのは、調理師や店の責任者がフグの危険性をしっかりと理解し、安全に食材を提供しているから一般の消費者の支持を受けているわけである。
翻ってアルコールに関する危険性を販売する側は理解したうえで販売しているかを考えると、非常に怪しいと思いますし、アルコールの危険性を理解できないまま販売している人間も多いことに一般の消費者も気づきはじめている。
最近の若い世代がだんだんアルコールを避けるようになっている理由にアルコールの危険性を認識しないまま、販売している人間が多いこともあげられると思います。
ましてや、ソムリエや利き酒師がアルコールの危険性を理解していない店に行きたいか?って言われれば、絶対行きたくないと答える消費者がほとんどだと思います。
10、飲酒運転の十年間での減少を我々酒類販売する人間も見習うべきだろう
平成11年11月28日の東名高速で飲酒運転のトラックに追突された会社員の車の中で女児2名が死亡し、その時に飲酒運転に関する法律の不備が明らかになり、飲酒運転事故の被害者遺族や警察、法務関係者により、金、労力、時間が使われ飲酒運転に関する法律が改正され、10年で飲酒運転や事故が約2割まで減少しました。
しかし、急性アルコール中毒に関する搬送車の数については、5年で1割しか減少していません。
やはり、利き酒師やソムリエ等をはじめとして販売する側がアルコールの恐ろしさを理解できていないことや一般の方々に関する日本における飲酒教育の不足が急性アルコール患者の搬送者の数や急性アルコール中毒の死者となって表れているように思われますし、醸造酒の中で最もアルコール度数の高い日本酒離れの一因となっているように思われます。
今こそ、飲酒運転事故の減少に携わった飲酒運転事故の関係者の努力に見習い、我々酒類関係者は酒類の安全な飲酒をするにはどうすればいいかを真剣に考える時期に来ていると思います。
現在の日本酒の出荷量は2011年現在で60万1807KLで最盛期167万5000KL(1975年)の約36%の出荷量です。そのうち特定名称酒の出荷量が約25%と言われています。
海外への輸出量は約1万4000KL(2011年)で日本酒出荷量の約2.3%で、毎年少しずつではありますが、輸出量が増えてきています。
2、日本酒の国内での消費量の内訳
日本酒の消費量のうち約70%が家庭での消費で、そのうち約83%が50歳以上の世代の方が消費されていて、20歳代での消費量が約2.7%、30歳代での消費量が約4.9%と言われています。(日本政策投資銀行新潟支店2010年のレポートより)
3、日本酒の飲用アルコール度数は、他の醸造酒や蒸留酒と比較しても高い方である
日本酒の通常商品のアルコール度数はほとんどが15%~16%で、原酒となると主に18~19%となっています。ビール、酎ハイのアルコール度数が約4~5%、ワインのアルコール度数が約13%、焼酎が25%~35%でほとんどが6:4か5:5で消費されるので25%で15%又は、12.5%で消費され、ウィスキーになると40%の商品をハイボールを1:4にすると8%のアルコール度数となります。他にもスピリッツ系などがあり、ストレートで飲むことがありますが、ストレートで飲む場合と割って飲む場合では飲み方が違うので酔う速度が違いますし、チビチビ飲むのが普通です。
食事に合わせて普通に飲む分には日本酒のアルコール度数というのは他の酒類に比較して高いと思うので、あまりアルコール慣れしていない若年層からは飲みにくい商材となっていると考えられます。
4、飲酒の強要と日本酒
最近では、少なくなっていると思いますが、会社や大学のサークルに入った際の飲み会で飲酒を強要されその時に飲んだ日本酒が美味しくなくて、日本酒が嫌いになったという話を一世代前までの話の中でよく聞きました。ここで日本酒嫌いになる理由としては、?アルコールにあまり慣れていない上に日本酒自体のアルコール度数が高い、?ここで強要されて飲まされている日本酒自体がほとんど特定名称酒ではなく、三増酒であった。?日本酒というのは単独で飲むのではなく、食べ物と合わせてこそ本来の美味しさを味わうことができる。以上の3つの主な理由が挙げられると思います。
5、現在の日本酒には2種類の日本酒がある
1つ目が主に普通酒として生産されている増醸酒で、2つ目が純米酒、吟醸酒に代表される特定名称酒である。1つ目の増醸酒というのは元々、昭和初期の戦時中に米と酒不足から合成酒の技術をもとに満州で確立された第1次増産酒、第2次増産酒の技術を基に戦中の昭和19年に三増酒が技術的に確立され、戦後の米不足の時代に本格的に三増酒が生産され、平成18年に醪に対して添加されるアルコールの量が規制されて現在は二増酒として生産されています。満州で第1次増産酒、第2次増産酒が技術的に確立された際には増産酒を日本酒と呼ぶことに対して疑問視されていました。ただ、戦後になって米不足や戦争で技術が失われたこともあり増醸酒は日本酒の普通酒として定着し、この三増酒の市場のパイを巡って大手と中堅の酒蔵が争ってきた結果、現在の日本酒離れを招いた経緯があります。
2つ目の特定名称酒に関しては1992年に級別制度が廃止された以降に日本酒の造りを元に日本酒に対して付けられるようになった名称で、米だけで造ったお酒に対して純米酒、特別純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒、一部アルコールを添加した酒に対して、本醸造酒、特別本醸造酒、吟醸酒、大吟醸酒の8つのカテゴリーが確立されて現在に至っています。
この特定名称酒に関しては、現在ある醸造酒の中で世界一技術的に生産するのが難しい酒だと言われていて、食中酒として料理と一緒に食べて本来の能力をすべて発揮するというのが特定名称酒で、ゼロ戦と同じように飲み手に対してもある程度の技術を要求する部分があり、若い方々には中々日本酒の良さを理解してもらうのが難しい部分があります。
ただし、特定名称酒の持つ本来の良さが分かれば、他の酒類とは比較出来ない位いいものであるのも事実なのです。
6、急性アルコール中毒による年間の搬送者数
東京消防庁の平成18年のデータによれば、東京だけで年間13,397人の方が急性アルコール中毒により病院に搬送されています。そのうち、未成年者が810人約6%、20代以下が7,077人(未成年を含む)約53%と全体の半分以上を占めています。この急性アルコール中毒に関して言えば、日本酒だけが原因ではありませんが、日本人が全体としてアルコールを安全に飲むことをあまり理解していないことが原因にあげられると思われます。
7、急性アルコール中毒による実際の死亡事例
平成24年5月に北海道の小樽商科大学のアメリカンフットボール部のバーベキューパーティーで上級生から下級生に対する飲酒の強要が行われ、9名が急性アルコール中毒で搬送され(うち未成年が7名)、その中の一年生部員が急性アルコール中毒で心肺停止を起こし死亡しています。
ここで問題なのは、アルコールの強要が行われたことと、9名もの急性アルコール中毒での搬送者を出している事であります。
病院側から見れば急性アルコール中毒の患者は暴れたりして、非常に手がかかるので迷惑な存在であり、昨今の医師や看護士の不足を考えると単に急性アルコール中毒で体調を崩しただけでは済まない話になってきています。
8、酔いのメカニズムを血中アルコール濃度から考えてみる
?血中アルコール濃度0.05%以下
ほろ酔い一歩手前前期と呼ばれ、アルコールは血液の中に速やかに移行し、大脳の新皮質の機能を軽く抑制麻痺する。
?血中アルコール濃度0.05〜0.15%
ほろ酔い期と呼ばれ、理性的な知的活動を担っている新皮質と本能や情動を支配する大脳辺縁系の働きが歪んできて、本能的行動が一部無修正に表面に出てしまう。
?血中アルコール濃度0.15〜0.25%
酩酊期と呼ばれ、ほろ酔い状態から更にアルコールの量が増えてくると新皮質の働きはすっかり鈍り、大脳辺縁系の働きが独壇場と化して、大声を出したり、笑ったり、泣いたり、怒ったりする。
?血中アルコール濃度0.25〜0.35%
短期の記憶を担っている海馬にまで作用してくる。その時点の記憶がなくなってしまう。(ブラックアウト)俗に言う全く覚えていない状態である。
?血中アルコール濃度0.35〜0.50%
昏睡期と呼ばれ、これ以上の飲み、アルコールの作用が延髄まで及ぶと基本的な生命活動が鈍り、呼吸中枢が麻痺し、昏睡状態に陥り、死に至ることがある。
非常に短時間に大量に飲んだ場合、脳全体がアルコール漬けとなり、いきなり昏睡状態になることもある。
一気飲みなどせずにゆっくりと飲まなければ自身の酔い具合が分からないので、急に飲んだりすればいきなり昏睡状態になることもある。
9、やはりアルコールにかかわる人間が一番アルコールの恐ろしさを認識すべき
利き酒師、ソムリエ、酒類販売取扱責任者等といったアルコールの専門家は、アルコールの恐ろしさを人一倍認識し、一般の人間に指導できるだけの能力を備えないことには、国内のアルコール市場はますます低迷する。
日本国内では、フグなどの毒性を持った魚や食材を専門に扱う料理店も複数存在しますが、そこで一般の消費者が安心して食事ができるのは、調理師や店の責任者がフグの危険性をしっかりと理解し、安全に食材を提供しているから一般の消費者の支持を受けているわけである。
翻ってアルコールに関する危険性を販売する側は理解したうえで販売しているかを考えると、非常に怪しいと思いますし、アルコールの危険性を理解できないまま販売している人間も多いことに一般の消費者も気づきはじめている。
最近の若い世代がだんだんアルコールを避けるようになっている理由にアルコールの危険性を認識しないまま、販売している人間が多いこともあげられると思います。
ましてや、ソムリエや利き酒師がアルコールの危険性を理解していない店に行きたいか?って言われれば、絶対行きたくないと答える消費者がほとんどだと思います。
10、飲酒運転の十年間での減少を我々酒類販売する人間も見習うべきだろう
平成11年11月28日の東名高速で飲酒運転のトラックに追突された会社員の車の中で女児2名が死亡し、その時に飲酒運転に関する法律の不備が明らかになり、飲酒運転事故の被害者遺族や警察、法務関係者により、金、労力、時間が使われ飲酒運転に関する法律が改正され、10年で飲酒運転や事故が約2割まで減少しました。
しかし、急性アルコール中毒に関する搬送車の数については、5年で1割しか減少していません。
やはり、利き酒師やソムリエ等をはじめとして販売する側がアルコールの恐ろしさを理解できていないことや一般の方々に関する日本における飲酒教育の不足が急性アルコール患者の搬送者の数や急性アルコール中毒の死者となって表れているように思われますし、醸造酒の中で最もアルコール度数の高い日本酒離れの一因となっているように思われます。
今こそ、飲酒運転事故の減少に携わった飲酒運転事故の関係者の努力に見習い、我々酒類関係者は酒類の安全な飲酒をするにはどうすればいいかを真剣に考える時期に来ていると思います。
|
|
|
|
|
|
|
|
酒仙境心の景色 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
酒仙境心の景色のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75479人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6433人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208284人