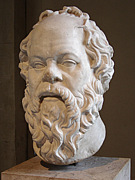要するにただいま申し上げた二つの入り乱れたる経路、すなわちできるだけ労力を節約したいと云う願望から出て来る種々の発明とか器械力とか云う方面と、できるだけ気儘(きまま)に勢力を費したいと云う娯楽の方面、これが経となり緯となり千変万化錯綜(さくそう)して現今のように混乱した開化と云う不可思議な現象ができるのであります。
そこでそう云うものを開化とすると、ここに一種妙なパラドックスとでも云いましょうか、ちょっと聞くとおかしいが、実は誰しも認めなければならない現象が起ります。元来なぜ人間が開化の流れに沿うて、以上二種の活力を発現しつつ今日に及んだかと云えば生れながらそう云う傾向をもっていると答えるよりほかに仕方がない。これを逆に申せば吾人の今日あるは全くこの本来の傾向あるがためにほかならんのであります。なお進んで云うと元(もと)のままで懐手(ふところで)をしていては生存上どうしてもやり切れぬから、それからそれへと順々に押され押されてかく発展を遂げたと言わなければならないのです。してみれば古来何千年の労力と歳月を挙(あ)げてようやくの事現代の位置まで進んで来たのであるからして、いやしくもこの二種類の活力が上代から今に至る長い時間に工夫し得た結果として昔よりも生活が楽になっていなければならないはずであります。けれども実際はどうか? 打明けて申せば御互の生活ははなはだ苦しい。昔の人に対して一歩も譲らざる苦痛の下に生活しているのだと云う自覚が御互にある。否開化が進めば進むほど競争がますます劇(はげ)しくなって生活はいよいよ困難になるような気がする。なるほど以上二種の活力の猛烈な奮闘で開化は贏(か)ち得たに相違ない。しかしこの開化は一般に生活の程度が高くなったという意味で、生存の苦痛が比較的柔げられたという訳ではありません。ちょうど小学校の生徒が学問の競争で苦しいのと、大学の学生が学問の競争で苦しいのと、その程度は違うが、比例に至っては同じことであるごとく、昔の人間と今の人間がどのくらい幸福の程度において違っているかと云えば――あるいは不幸の程度において違っているかと云えば――活力消耗活力節約の両工夫において大差はあるかも知れないが、生存競争から生ずる不安や努力に至ってはけっして昔より楽になっていない。否昔よりかえって苦しくなっているかも知れない。昔は死ぬか生きるかのために争ったものである。それだけの努力をあえてしなければ死んでしまう。やむをえないからやる。のみならず道楽の念はとにかく道楽の途(みち)はまだ開けていなかったから、こうしたい、ああしたいと云う方角も程度も至って微弱なもので、たまに足を伸したり手を休めたりして、満足していたくらいのものだろうと思われる。今日は死ぬか生きるかの問題は大分超越している。それが変化してむしろ生きるか生きるかと云う競争になってしまったのであります。生きるか生きるかと云うのはおかしゅうございますが、Aの状態で生きるかBの状態で生きるかの問題に腐心しなければならないという意味であります。活力節減の方で例を引いてお話をしますと、人力車を挽(ひ)いて渡世(とせい)にするか、または自動車のハンドルを握って暮すかの競争になったのであります。どっちを家業にしたって命に別条はないにきまっているが、どっちへ行っても労力は同じだとは云われません。人力車を挽く方が汗がよほど多分に出るでしょう。自動車の御者(ぎょしゃ)になってお客を乗せれば――もっとも自動車をもつくらいならお客を乗せる必要もないが――短い時間で長い所が走れる。糞力(くそぢから)はちっとも出さないですむ。活力節約の結果楽に仕事ができる。されば自動車のない昔はいざ知らず、いやしくも発明される以上人力車は自動車に負けなければならない。負ければ追つかなければならない。と云う訳で、少しでも労力を節減し得て優勢なるものが地平線上に現われてここに一つの波瀾(はらん)を誘うと、ちょうど一種の低気圧と同じ現象が開化の中に起って、各部の比例がとれ平均が回復されるまでは動揺してやめられないのが人間の本来であります。積極的活力の発現の方から見てもこの波動は同じことで、早い話が今までは敷島(しきしま)か何か吹かして我慢しておったのに、隣りの男が旨(うま)そうに埃及煙草(エジプトたばこ)を喫(の)んでいるとやっぱりそっちが喫みたくなる。また喫んで見ればその方が旨(うま)いに違ない。しまいには敷島などを吹かすものは人間の数へ入らないような気がして、どうしても埃及へ喫み移らなければならぬと云う競争が起って来る。通俗の言葉で云えば人間が贅沢(ぜいたく)になる。道学者は倫理的の立場から始終(しじゅう)奢侈(しゃし)を戒(いま)しめている。結構には違ないが自然の大勢に反した訓戒であるからいつでも駄目に終るという事は昔から今日(こんにち)まで人間がどのくらい贅沢になったか考えて見れば分る話である。かく積極消極両方面の競争が激しくなるのが開化の趨勢(すうせい)だとすれば、吾々は長い時日のうちに種々様々の工夫を凝(こら)し智慧(ちえ)を絞(しぼ)ってようやく今日まで発展して来たようなものの、生活の吾人の内生に与える心理的苦痛から論ずれば今も五十年前もまたは百年前も、苦しさ加減の程度は別に変りはないかも知れないと思うのです。それだからしてこのくらい労力を節減する器械が整った今日でも、また活力を自由に使い得る娯楽の途(みち)が備った今日でも生存の苦痛は存外切(せつ)なものであるいは非常という形容詞を冠らしてもしかるべき程度かも知れない。これほど労力を節減できる時代に生れてもその忝(かたじ)けなさが頭に応(こた)えなかったり、これほど娯楽の種類や範囲が拡大されても全くそのありがたみが分らなかったりする以上は苦痛の上に非常という字を附加しても好いかも知れません。これが開化の産んだ一大パラドックスだと私は考えるのであります。
これから日本の開化に移るのですが、はたして一般的の開化がそんなものであるならば、日本の開化も開化の一種だからそれでよかろうじゃないかでこの講演は済んでしまう訳であります。がそこに一種特別な事情があって、日本の開化はそういかない。なぜそうは行かないか。それを説明するのが今日の講演の主眼である。と申すと玄関を上ってようやく茶の間あたりへ来たくらいの気がして驚くでしょう。しかしそう長くはありません、奥行は存外短かい講演です。やってる方だって長いのは疲れますからできるだけ労力節約の法則に従って早く切り上げるつもりですから、もう少し辛抱して聴いて下さい。
それで現代の日本の開化は前に述べた一般の開化とどこが違うかと云うのが問題です。もし一言にしてこの問題を決しようとするならば私はこう断じたい、西洋の開化(すなわち一般の開化)は内発的であって、日本の現代の開化は外発的である。ここに内発的と云うのは内から自然に出て発展するという意味でちょうど花が開くようにおのずから蕾(つぼみ)が破れて花弁が外に向うのを云い、また外発的とは外からおっかぶさった他の力でやむをえず一種の形式を取るのを指したつもりなのです。もう一口説明しますと、西洋の開化は行雲流水のごとく自然に働いているが、御維新後外国と交渉をつけた以後の日本の開化は大分勝手が違います。もちろんどこの国だって隣づき合がある以上はその影響を受けるのがもちろんの事だから吾(わが)日本といえども昔からそう超然としてただ自分だけの活力で発展した訳ではない。ある時は三韓また或時は支那という風に大分外国の文化にかぶれた時代もあるでしょうが、長い月日を前後ぶっ通しに計算して大体の上から一瞥(いちべつ)して見るとまあ比較的内発的の開化で進んで来たと云えましょう。少なくとも鎖港排外の空気で二百年も麻酔したあげく突然西洋文化の刺戟(しげき)に跳(は)ね上ったぐらい強烈な影響は有史以来まだ受けていなかったと云うのが適当でしょう。日本の開化はあの時から急劇に曲折し始めたのであります。また曲折しなければならないほどの衝動を受けたのであります。これを前の言葉で表現しますと、今まで内発的に展開して来たのが、急に自己本位の能力を失って外から無理押しに押されて否応(いやおう)なしにその云う通りにしなければ立ち行かないという有様になったのであります。それが一時ではない。四五十年前に一押し押されたなりじっと持ち応(こた)えているなんて楽(らく)な刺戟(しげき)ではない。時々に押され刻々に押されて今日に至ったばかりでなく向後何年の間か、またはおそらく永久に今日のごとく押されて行かなければ日本が日本として存在できないのだから外発的というよりほかに仕方がない。その理由は無論明白な話で、前(ぜん)詳(くわ)しく申上げた開化の定義に立戻って述べるならば、吾々が四五十年間始めてぶつかった、また今でも接触を避ける訳に行かないかの西洋の開化というものは我々よりも数十倍労力節約の機関を有する開化で、また我々よりも数十倍娯楽道楽の方面に積極的に活力を使用し得る方法を具備した開化である。粗末な説明ではあるが、つまり我々が内発的に展開して十の複雑の程度に開化を漕ぎつけた折も折、図(はか)らざる天の一方から急に二十三十の複雑の程度に進んだ開化が現われて俄然(がぜん)として我らに打ってかかったのである。この圧迫によって吾人はやむをえず不自然な発展を余儀なくされるのであるから、今の日本の開化は地道にのそりのそりと歩くのでなくって、やッと気合を懸けてはぴょいぴょいと飛んで行くのである。開化のあらゆる階段を順々に踏んで通る余裕をもたないから、できるだけ大きな針(はり)でぼつぼつ縫って過ぎるのである。足の地面に触れる所は十尺を通過するうちにわずか一尺ぐらいなもので、他の九尺は通らないのと一般である。私の外発的という意味はこれでほぼ御了解になったろうと思います。
そういう外発的の開化が心理的にどんな影響を吾人に与うるかと云うとちょっと変なものになります。心理学の講筵(こうえん)でもないのにむずかしい事を申上げるのもいかがと存じますが、必要の個所だけをごく簡易に述べて再び本題に戻るつもりでありますから、しばらく御辛抱(ごしんぼう)を願います。我々の心は絶間なく動いている。あなた方は今私の講演を聴いておいでになる、私は今あなた方を前に置いて何か言っている、双方共にこういう自覚がある。それに御互の心は動いている。働いている。これを意識と云うのであります。この意識の一部分、時に積れば一分間ぐらいのところを絶間なく動いている大きな意識から切り取って調べてみるとやはり動いている。その動き方は別に私が発明した訳でも何でもない、ただ西洋の学者が書物に書いた通りをもっともと思うから紹介するだけでありますが、すべて一分間の意識にせよ三十秒間の意識にせよその内容が明暸(めいりょう)に心に映ずる点から云えば、のべつ同程度の強さを有して時間の経過に頓着(とんじゃく)なくあたかも一つ所にこびりついたように固定したものではない。必ず動く。動くにつれて明かな点と暗い点ができる。その高低を線で示せば平たい直線では無理なので、やはり幾分か勾配(こうばい)のついた弧線すなわち弓形(ゆみがた)の曲線で示さなければならなくなる。こんなに説明するとかえって込み入ってむずかしくなるかも知れませんが、学者は分った事を分りにくく言うもので、素人(しろうと)は分らない事を分ったように呑込(のみこ)んだ顔をするものだから非難は五分五分である。今云った弧線とか曲線とかいう事をそっと砕いてお話をすると、物をちょっと見るのにも、見てこれが何であるかと云うことがハッキリ分るには或る時間を要するので、すなわち意識が下の方から一定の時間を経て頂点へ上って来てハッキリして、ああこれだなと思う時がくる。それをなお見つめていると今度は視覚が鈍くなって多少ぼんやりし始めるのだからいったん上の方へ向いた意識の方向がまた下を向いて暗くなりかける。これは実験して御覧になると分る。実験と云っても機械などは要(い)らない。頭の中がそうなっているのだからただ試(ため)しさえすれば気がつくのです。本を読むにしてもAと云う言葉とBと云う言葉とそれからCという言葉が順々に並んでいればこの三つの言葉を順々に理解して行くのが当り前だからAが明かに頭に映る時はBはまだ意識に上らない。Bが意識の舞台に上り始める時にはもうAの方は薄ぼんやりしてだんだん識域(しきいき)の方に近づいてくる。BからCへ移るときはこれと同じ所作(しょさ)を繰返(くりかえ)すに過ぎないのだから、いくら例を長くしても同じ事であります。これは極(きわ)めて短時間の意識を学者が解剖して吾々に示したものでありますが、この解剖は個人の一分間の意識のみならず、一般社会の集合意識にも、それからまた一日一月もしくは一年乃至(ないし)十年の間の意識にも応用の利(き)く解剖で、その特色は多人数になったって、長時間に亘(わた)ったって、いっこう変りはない事と私は信じているのであります。例えて見ればあなた方という多人数の団体が今ここで私の講演を聴いておいでになる。聴いていない方もあるかも知れないが、まア聴いているとする。そうするとその個人でない集合体のあなた方の意識の上には今私の講演の内容が明かに入る。と同時に、この講演に来る前あなた方が経験された事、すなわち途中で雨が降り出して着物が濡(ぬ)れたとか、また蒸(む)し暑くて途中が難儀であったとかいう意識は講演の方が心を奪うにつれて、だんだん不明暸(ふめいりょう)不確実になってくる。またこの講演が終って場外に出て涼しい風に吹かれでもすれば、ああ好い心持だという意識に心を専領されてしまって講演の方はピッタリ忘れてしまう。私から云えば全くありがたくない話だが事実だからやむをえないのである。
そこでそう云うものを開化とすると、ここに一種妙なパラドックスとでも云いましょうか、ちょっと聞くとおかしいが、実は誰しも認めなければならない現象が起ります。元来なぜ人間が開化の流れに沿うて、以上二種の活力を発現しつつ今日に及んだかと云えば生れながらそう云う傾向をもっていると答えるよりほかに仕方がない。これを逆に申せば吾人の今日あるは全くこの本来の傾向あるがためにほかならんのであります。なお進んで云うと元(もと)のままで懐手(ふところで)をしていては生存上どうしてもやり切れぬから、それからそれへと順々に押され押されてかく発展を遂げたと言わなければならないのです。してみれば古来何千年の労力と歳月を挙(あ)げてようやくの事現代の位置まで進んで来たのであるからして、いやしくもこの二種類の活力が上代から今に至る長い時間に工夫し得た結果として昔よりも生活が楽になっていなければならないはずであります。けれども実際はどうか? 打明けて申せば御互の生活ははなはだ苦しい。昔の人に対して一歩も譲らざる苦痛の下に生活しているのだと云う自覚が御互にある。否開化が進めば進むほど競争がますます劇(はげ)しくなって生活はいよいよ困難になるような気がする。なるほど以上二種の活力の猛烈な奮闘で開化は贏(か)ち得たに相違ない。しかしこの開化は一般に生活の程度が高くなったという意味で、生存の苦痛が比較的柔げられたという訳ではありません。ちょうど小学校の生徒が学問の競争で苦しいのと、大学の学生が学問の競争で苦しいのと、その程度は違うが、比例に至っては同じことであるごとく、昔の人間と今の人間がどのくらい幸福の程度において違っているかと云えば――あるいは不幸の程度において違っているかと云えば――活力消耗活力節約の両工夫において大差はあるかも知れないが、生存競争から生ずる不安や努力に至ってはけっして昔より楽になっていない。否昔よりかえって苦しくなっているかも知れない。昔は死ぬか生きるかのために争ったものである。それだけの努力をあえてしなければ死んでしまう。やむをえないからやる。のみならず道楽の念はとにかく道楽の途(みち)はまだ開けていなかったから、こうしたい、ああしたいと云う方角も程度も至って微弱なもので、たまに足を伸したり手を休めたりして、満足していたくらいのものだろうと思われる。今日は死ぬか生きるかの問題は大分超越している。それが変化してむしろ生きるか生きるかと云う競争になってしまったのであります。生きるか生きるかと云うのはおかしゅうございますが、Aの状態で生きるかBの状態で生きるかの問題に腐心しなければならないという意味であります。活力節減の方で例を引いてお話をしますと、人力車を挽(ひ)いて渡世(とせい)にするか、または自動車のハンドルを握って暮すかの競争になったのであります。どっちを家業にしたって命に別条はないにきまっているが、どっちへ行っても労力は同じだとは云われません。人力車を挽く方が汗がよほど多分に出るでしょう。自動車の御者(ぎょしゃ)になってお客を乗せれば――もっとも自動車をもつくらいならお客を乗せる必要もないが――短い時間で長い所が走れる。糞力(くそぢから)はちっとも出さないですむ。活力節約の結果楽に仕事ができる。されば自動車のない昔はいざ知らず、いやしくも発明される以上人力車は自動車に負けなければならない。負ければ追つかなければならない。と云う訳で、少しでも労力を節減し得て優勢なるものが地平線上に現われてここに一つの波瀾(はらん)を誘うと、ちょうど一種の低気圧と同じ現象が開化の中に起って、各部の比例がとれ平均が回復されるまでは動揺してやめられないのが人間の本来であります。積極的活力の発現の方から見てもこの波動は同じことで、早い話が今までは敷島(しきしま)か何か吹かして我慢しておったのに、隣りの男が旨(うま)そうに埃及煙草(エジプトたばこ)を喫(の)んでいるとやっぱりそっちが喫みたくなる。また喫んで見ればその方が旨(うま)いに違ない。しまいには敷島などを吹かすものは人間の数へ入らないような気がして、どうしても埃及へ喫み移らなければならぬと云う競争が起って来る。通俗の言葉で云えば人間が贅沢(ぜいたく)になる。道学者は倫理的の立場から始終(しじゅう)奢侈(しゃし)を戒(いま)しめている。結構には違ないが自然の大勢に反した訓戒であるからいつでも駄目に終るという事は昔から今日(こんにち)まで人間がどのくらい贅沢になったか考えて見れば分る話である。かく積極消極両方面の競争が激しくなるのが開化の趨勢(すうせい)だとすれば、吾々は長い時日のうちに種々様々の工夫を凝(こら)し智慧(ちえ)を絞(しぼ)ってようやく今日まで発展して来たようなものの、生活の吾人の内生に与える心理的苦痛から論ずれば今も五十年前もまたは百年前も、苦しさ加減の程度は別に変りはないかも知れないと思うのです。それだからしてこのくらい労力を節減する器械が整った今日でも、また活力を自由に使い得る娯楽の途(みち)が備った今日でも生存の苦痛は存外切(せつ)なものであるいは非常という形容詞を冠らしてもしかるべき程度かも知れない。これほど労力を節減できる時代に生れてもその忝(かたじ)けなさが頭に応(こた)えなかったり、これほど娯楽の種類や範囲が拡大されても全くそのありがたみが分らなかったりする以上は苦痛の上に非常という字を附加しても好いかも知れません。これが開化の産んだ一大パラドックスだと私は考えるのであります。
これから日本の開化に移るのですが、はたして一般的の開化がそんなものであるならば、日本の開化も開化の一種だからそれでよかろうじゃないかでこの講演は済んでしまう訳であります。がそこに一種特別な事情があって、日本の開化はそういかない。なぜそうは行かないか。それを説明するのが今日の講演の主眼である。と申すと玄関を上ってようやく茶の間あたりへ来たくらいの気がして驚くでしょう。しかしそう長くはありません、奥行は存外短かい講演です。やってる方だって長いのは疲れますからできるだけ労力節約の法則に従って早く切り上げるつもりですから、もう少し辛抱して聴いて下さい。
それで現代の日本の開化は前に述べた一般の開化とどこが違うかと云うのが問題です。もし一言にしてこの問題を決しようとするならば私はこう断じたい、西洋の開化(すなわち一般の開化)は内発的であって、日本の現代の開化は外発的である。ここに内発的と云うのは内から自然に出て発展するという意味でちょうど花が開くようにおのずから蕾(つぼみ)が破れて花弁が外に向うのを云い、また外発的とは外からおっかぶさった他の力でやむをえず一種の形式を取るのを指したつもりなのです。もう一口説明しますと、西洋の開化は行雲流水のごとく自然に働いているが、御維新後外国と交渉をつけた以後の日本の開化は大分勝手が違います。もちろんどこの国だって隣づき合がある以上はその影響を受けるのがもちろんの事だから吾(わが)日本といえども昔からそう超然としてただ自分だけの活力で発展した訳ではない。ある時は三韓また或時は支那という風に大分外国の文化にかぶれた時代もあるでしょうが、長い月日を前後ぶっ通しに計算して大体の上から一瞥(いちべつ)して見るとまあ比較的内発的の開化で進んで来たと云えましょう。少なくとも鎖港排外の空気で二百年も麻酔したあげく突然西洋文化の刺戟(しげき)に跳(は)ね上ったぐらい強烈な影響は有史以来まだ受けていなかったと云うのが適当でしょう。日本の開化はあの時から急劇に曲折し始めたのであります。また曲折しなければならないほどの衝動を受けたのであります。これを前の言葉で表現しますと、今まで内発的に展開して来たのが、急に自己本位の能力を失って外から無理押しに押されて否応(いやおう)なしにその云う通りにしなければ立ち行かないという有様になったのであります。それが一時ではない。四五十年前に一押し押されたなりじっと持ち応(こた)えているなんて楽(らく)な刺戟(しげき)ではない。時々に押され刻々に押されて今日に至ったばかりでなく向後何年の間か、またはおそらく永久に今日のごとく押されて行かなければ日本が日本として存在できないのだから外発的というよりほかに仕方がない。その理由は無論明白な話で、前(ぜん)詳(くわ)しく申上げた開化の定義に立戻って述べるならば、吾々が四五十年間始めてぶつかった、また今でも接触を避ける訳に行かないかの西洋の開化というものは我々よりも数十倍労力節約の機関を有する開化で、また我々よりも数十倍娯楽道楽の方面に積極的に活力を使用し得る方法を具備した開化である。粗末な説明ではあるが、つまり我々が内発的に展開して十の複雑の程度に開化を漕ぎつけた折も折、図(はか)らざる天の一方から急に二十三十の複雑の程度に進んだ開化が現われて俄然(がぜん)として我らに打ってかかったのである。この圧迫によって吾人はやむをえず不自然な発展を余儀なくされるのであるから、今の日本の開化は地道にのそりのそりと歩くのでなくって、やッと気合を懸けてはぴょいぴょいと飛んで行くのである。開化のあらゆる階段を順々に踏んで通る余裕をもたないから、できるだけ大きな針(はり)でぼつぼつ縫って過ぎるのである。足の地面に触れる所は十尺を通過するうちにわずか一尺ぐらいなもので、他の九尺は通らないのと一般である。私の外発的という意味はこれでほぼ御了解になったろうと思います。
そういう外発的の開化が心理的にどんな影響を吾人に与うるかと云うとちょっと変なものになります。心理学の講筵(こうえん)でもないのにむずかしい事を申上げるのもいかがと存じますが、必要の個所だけをごく簡易に述べて再び本題に戻るつもりでありますから、しばらく御辛抱(ごしんぼう)を願います。我々の心は絶間なく動いている。あなた方は今私の講演を聴いておいでになる、私は今あなた方を前に置いて何か言っている、双方共にこういう自覚がある。それに御互の心は動いている。働いている。これを意識と云うのであります。この意識の一部分、時に積れば一分間ぐらいのところを絶間なく動いている大きな意識から切り取って調べてみるとやはり動いている。その動き方は別に私が発明した訳でも何でもない、ただ西洋の学者が書物に書いた通りをもっともと思うから紹介するだけでありますが、すべて一分間の意識にせよ三十秒間の意識にせよその内容が明暸(めいりょう)に心に映ずる点から云えば、のべつ同程度の強さを有して時間の経過に頓着(とんじゃく)なくあたかも一つ所にこびりついたように固定したものではない。必ず動く。動くにつれて明かな点と暗い点ができる。その高低を線で示せば平たい直線では無理なので、やはり幾分か勾配(こうばい)のついた弧線すなわち弓形(ゆみがた)の曲線で示さなければならなくなる。こんなに説明するとかえって込み入ってむずかしくなるかも知れませんが、学者は分った事を分りにくく言うもので、素人(しろうと)は分らない事を分ったように呑込(のみこ)んだ顔をするものだから非難は五分五分である。今云った弧線とか曲線とかいう事をそっと砕いてお話をすると、物をちょっと見るのにも、見てこれが何であるかと云うことがハッキリ分るには或る時間を要するので、すなわち意識が下の方から一定の時間を経て頂点へ上って来てハッキリして、ああこれだなと思う時がくる。それをなお見つめていると今度は視覚が鈍くなって多少ぼんやりし始めるのだからいったん上の方へ向いた意識の方向がまた下を向いて暗くなりかける。これは実験して御覧になると分る。実験と云っても機械などは要(い)らない。頭の中がそうなっているのだからただ試(ため)しさえすれば気がつくのです。本を読むにしてもAと云う言葉とBと云う言葉とそれからCという言葉が順々に並んでいればこの三つの言葉を順々に理解して行くのが当り前だからAが明かに頭に映る時はBはまだ意識に上らない。Bが意識の舞台に上り始める時にはもうAの方は薄ぼんやりしてだんだん識域(しきいき)の方に近づいてくる。BからCへ移るときはこれと同じ所作(しょさ)を繰返(くりかえ)すに過ぎないのだから、いくら例を長くしても同じ事であります。これは極(きわ)めて短時間の意識を学者が解剖して吾々に示したものでありますが、この解剖は個人の一分間の意識のみならず、一般社会の集合意識にも、それからまた一日一月もしくは一年乃至(ないし)十年の間の意識にも応用の利(き)く解剖で、その特色は多人数になったって、長時間に亘(わた)ったって、いっこう変りはない事と私は信じているのであります。例えて見ればあなた方という多人数の団体が今ここで私の講演を聴いておいでになる。聴いていない方もあるかも知れないが、まア聴いているとする。そうするとその個人でない集合体のあなた方の意識の上には今私の講演の内容が明かに入る。と同時に、この講演に来る前あなた方が経験された事、すなわち途中で雨が降り出して着物が濡(ぬ)れたとか、また蒸(む)し暑くて途中が難儀であったとかいう意識は講演の方が心を奪うにつれて、だんだん不明暸(ふめいりょう)不確実になってくる。またこの講演が終って場外に出て涼しい風に吹かれでもすれば、ああ好い心持だという意識に心を専領されてしまって講演の方はピッタリ忘れてしまう。私から云えば全くありがたくない話だが事実だからやむをえないのである。
|
|
|
|
|
|
|
|
池田晶子の哲学エツセイを継ぐ 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-