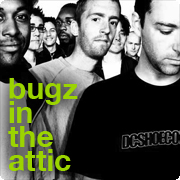ウェブでナイスな記事を見つけたので転載します。
日記には載せたんですが、改めて日本語訳したんでお楽しみ下さい。
ブロークンビートって何?って聴かれたらこれをプリントアウトして渡しましょう!ちなみにこれは2001年7月に書かれたものなのでその辺の時差にご注意を。
********************************************************
Broken/not broken
broken beatにとって退屈は発明の母
Amanda Nowinski 著
Kay Suzuki訳
ハウスミュージックはクラブシーンの『安全食』である(便利な音楽という意味)。
古き良き時代のスタイルにソリッドな四つ打ち、そしてお馴染みのゴスペル風やソウルフルな女性ボーカルの甘酸っぱいメロディの端々。フロアや車、ヘッドホンを通してハウスはあなたをインテリジェントに興奮させてくれる。。。
そしてふと気づいてあなたの家へ。
現実にもどってみて、まだ『それ』はあなたをまだ行った事が無いような場所に連れて行ってくれるだろうか?
ブロークンビートは西ロンドンから発せられた新しい音楽で、ダンスミュージックの『退屈さ』に対する解毒剤と言えば分かりやすいかもしれない。
問題はブロークンビートと呼ばれるジャンルは実はジャンルという訳ではまったく無いという事だ。
一番結びつけられる音楽的要素はインストのライブジャズだが、特に決まった型や、ビートの構造があるわけでもないし、決まったベースの音量、メロディやボーカルで分かりやすいフックがあるわけでもない。ビートは四つ打ちでもなければ純粋なブレイクスでもなく、分離された飛び跳ねたようなサウンドで、とても落ち着いて座っていられるような音ではない。ダウンテンポのものでも思わず頭が揺られてしまう。
その無制限な音楽の特徴は、それぞれのアーティストが独特の個性で特筆するクオリティがあるという事だろう。
I.G. Cultureのアフロリズム、Seijiのフリージャズのようなダークなエレクトリックサウンド、Nubian Mindのつんざくようなテクノサウンド、レアグルーブやソウルの影響があるAfronaught(Orin Walters)のサウンド。
そして、ほとんどの場合、この音楽を先導しているのは成熟したアーティスト達である。IG CultureやReinforced(レーベル)のDego (4 Hero)は彼等が聞いてきて愛してきた音楽をランダムに反映させている。 ブロークンビートはポスト・ハウスであり、ポスト・テクノであり、ポスト・アンビエントであり、ポスト・ジャングルでもあり、またそれら全てをひっくるめたものでもある。
あえてこれを定義するならその『姿勢』ではないだろうか。
Brokenbeatsのシーンを引率する集団、Bugz in the atticは西ロンドンでハウスからドラムンベースまで全てをプロデュースをしてきたOrin Walters(Afonaught)によって結成された。
若手メンバーで24歳(当時、今は28歳)のPaul"Seiji"Dolby(またの名をOpaque、Homecookin')の最新作を聴いているみると『混合』という言葉が浮かんでくる。
彼が西ロンドンの自宅から電話越しに言う、
「西ロンドン系の音はとにかくフュージョン(融合)なんだ。別に俺達は一つの型にこだわってる訳じゃない。心配なのはみんながブロークンビートってタグが付いてる音楽を聴いて『そっか、これがブロークンビートって音なんだ』ってシーンを判断しちゃう事なんだ。俺達は同じ音楽を作ってる訳じゃないし、たとえ、同じ西ロンドンのプロデューサーでもみんな様々な違うスタイルがあってやってる事が違うんだ。俺はエレクトリックで、DOMUはテクニカルでドラムンベースみたいにハードだったり、Restless Soul(Phil Asher)みたいにソウルフルだったりするしさ。ホント、幅広く色んなスタイルがあるんだよ。」
ブロークンビートのムーブメントはIG CultureとDegoが始めたスタイルが中心になっている。DegoはSeijiがドラムンベースを作り始めた時のレーベル『Rainforced』のオーナーで、彼のもう一つのレーベル『2000Black』から最近リリースしたコンピレーション『Good Good Compilation』はこの手の音を紹介するに最適だったのではないだろうか。奇しくもちょうどこの頃、アメリカ・デトロイト出身のテクノプロデューサー・Carl Craigの有するレーベル『Planet E』から彼自身のフリージャズとテクノが融合したプロジェクト『Innerzone Orchestra』の輸入版が発売され、ブロークンビートスタイルがアメリカとリンクした。
広いシーンで考えると、西ロンドンのプロデューサー達のやっている事は、ドイツのTruby Trio, Jazzanova, Beanfield, Fauna Flashなどの他の『Compost』レーベルのアーティスト達や、日本のKyoto Jazz Massive、イタリアのVolcovらが始めたエレクトリックなジャズフュージョンとまったく違うわけではない。
「ブロークンビートってのは広い意味でのFuture Jazzの一種だよね。でもアシッドジャズと誤解しちゃいかんよ」と語るのは『XLR8R』というエレクトリックミュージック雑誌の編集人、Tomas Palermo。彼は地元(この記事でアメリカで書かれてます)でレーベル『Ubiquity Records』のJonah SharpやAndrew Jervisらと共にクラブ・Emotoでブロークンビートを毎月プレイしている。
サンフランシスコ生まれの『Ubiquity Records』はFuture Jazzを何年も支持しているレーベルで、Beatless (Alex AttiasとPaul Martin)等の西ロンドンのアーティストから、P'TaahとWamdue ProjectをやっているChris Brannアメリカ人も参加。
Chris Brannのアルバム『De'Compressed』はOpaque moniker名義のSeijiとNubian Mindsのブロークンビートリミックスも収録し、Sun RaやRahsaan Roland Kirk等の往年の前衛ジャズにも迫るスタイルで、ビートをひねってカットアップし、その音は昔のアシッドジャズのようなダンスフロアに優しい音ではなく、ほとんどの音はシンプルなファンクやジャズのフレーズをヒップホップのブレイクスのテンポに落とし込んである。
西ロンドンシーンの強力な『核』は共感するアーティストの密なネットワークとそれを支えるレーベル、『people』・Bugz in the atticの『Bitasweet』・IG Cultureの『Main Squeeze』・『Laws of Motion』、そしてクラブナイトでもある『CO-OP』で発展してきた。
「Bugz in the atticはみんなとやりとりしてるよ」こう語るのは111Minna Stでブロークンビートとフューチャージャズのイベントを毎月主催する『Ubiquity』のJervisだ。
「みんながお互いの生活を支え合ってるよ、確かにそういった輪の中でやりとりしてるのは効果あるよね」
様々なバックグラウンドを限りなく融合して行って《まぁ、トランスやメインストリームのゴミハウスは別として》それでいて、どのスタイルにも留まっていない。
Jervisが加える「つまんなくなったり、飽和したりして死んでいく代わりにメインのプロデューサー達は更に幅広いスタイルに発展させつづけてるよ。AfronaughtのアルバムはIG Cultureのアルバムとは違うサウンドだし、BeatlessのアルバムはtNeon Phusionのアルバムとはまったく違ったサウンドなんだ」
ブロークンビートはロンドンから生まれた最も新しいジャズの動きでありながら、プレスの注目はもう一つのジャンル『2ステップ』に独占した。
2ステップと違ってブロークンビートは特別なガイドもなく、結果的に一つの音楽スタイルをコマーシャルなモノに発展させる、狂信的なジャンルマーケティングの手法にアピールする事は無かった。これはヘソ曲がりなブロークンビート-フューチャージャズ・プロデューサーの意識的なメインストリーム・ダンスミュージックへの反抗なのか、もしくは同じく西ロンドンのプロデューサーで2ステップの大物『MJ Cole』がスポットライトを独占したやり方への批判なのか。
2ステップからの影響も受けていると語るSeijiは"No"と応えた。「ブロークンビートは他のシーンからの影響ってのは特に無いんだ。何に対してもレスポンスはしてないよ。誰も椅子に座って考えて『よし、やろう!俺達でシーンを作ろう!』なんてやってないんだ。ただ、純粋に何か違う、新しい音楽をやろうとしてる奴等が居て、他にも同じ様にやってる奴が居るのに気が付いて、たまたま一緒になって小さいコミュニティを作る事が出来たんだ。どんどん広がって行ってはいるけどね」
それでもSeijiはブロークンビートが稼げる音楽ではないと認める。ヨーロッパのどのメジャー雑誌もIG CultureやDegoのアルバムカバーを出して大々的に取り上げた事はない。このシーンのどのアーティストも広告代理店みたいなものは持ってなさそうだし、CD店で彼等の音楽を見つけるのはある意味チャレンジである。
要するにこの音楽は疎外された位置にあって、コマーシャルマーケットから拒絶されているのだ。
そして、ブラックミュージックでありながら白人のMJ ColeやArtful Dodgerが活躍している、(メディアの大好きな)2ステップと違って、メディアによる西ロンドンのおおざっぱな認識はIG CultureとDegoという黒人だ。よって、ブロークンビートやフューチャージャズは多国籍な性格を持っていても、黒人音楽としてのアイデンティティーを保っているわけだ。
『2000 Black』レーベルは元より、Nubian MindsやAfronaughtというネーミングはその音楽が影響されているルーツが明らかなのは間違いない。
チェロ弾きだったSeijiは(Afronaughtのアルバムでもチェロで参加)、スターダムや金を求めて、こじゃれたシャンペンを飲むようなタイプ(一般的な2ステップのイメージがこれ)というよりはスタジオ・オタクだ。確かにアブストラクトなビートが魅惑的な現金を生むのは想像出来ないだろう。
彼が曲作りについて話す時に頻繁に使われる単語が『science=科学』だ。彼のテクニカルなドラムンベースを聞くと納得する。
Seiji曰く「ドラムンベースは生なグルーヴを生むっていうより、テクノロジーを駆使して音の科学を追求するって感じだよ。当時ドラムンベースがエキサイティングだった時は、とにかくいかにブレイクビートをこねくり回してどれだけ違うモノにできるか、っていう『ビートサイエンス』が全てだったね。」
彼が現在音楽を作り続けているのも同じ科学的アプローチだ。
ただもう彼はジャンルという枠に囚われる罠には落ちない。
「俺のプログラミングのスタイルはドラムンベースから来てるよ。なにか科学的な事をやろうとしている。ハウスビートの四つ打ちってずっと聴いてるとつまらなくなるんだ。それに誰にでも出来る決まったビートを作るってのも飽きるんだよね。だから俺達はちょっと違う事をやろうとしたんだよ。要するに俺達は退屈してたんだ」
そして退屈さはジャンルの壁を打ち破るほどの必然的なシーンの発展をさせた。
ダンスミュージック産業の狂信的なまでのカテゴリー分けに対する執拗は、反逆者であるブロークンビートシーンのアーティストに大々的なマーケティングプランを与えず、商業的なイベントでのライブも与えず、おそらく広告代理店も、そして間違いなく大きなレコード契約も与えないのだ。 普通の人が簡単にアクセス出来るような手段もないまま、アーティスト達は批評家達に敵対するようなリスクを負っているのだ。
ブロークンビートは共感出来る人のあいだの小さなネットワークかもしれない。それでも<ジャンルや決まりきった型からの解放>というメッセージは発信されて間違いなく広がって行くだろう。
********************************************************
ディスカッション大募集。
みなさんの考えも聞かせてくださいね。
個人的に思うに、この音楽は何十年も築き上げれたSoul/Funk/Jazzが現代のテクノロジーによってHip-Hop/Techno/Houseによって再生されて、今、更にそれら全ての集大成として生まれた『ムーブメント=シーン』だと思ってます。作る人のバックグラウンド・趣味によってテンポもビートのスタイルも多様なこの音楽は上記の音楽を通過してない人にとってはちょっと取っ付きにくいかもしれません。でも今この地球上で一番ホットで新鮮で『音楽的な』エッセンスが一番詰まってるのはこのシーンでしょう!
英語版はともかく、俺の訳の無断転記はどんどんやってくれぃ!ただし本編の人と俺の名前は載っけてね。
英語の本文まで載せると長いので英語の分かる方は僕の日記までどーぞ。
日記には載せたんですが、改めて日本語訳したんでお楽しみ下さい。
ブロークンビートって何?って聴かれたらこれをプリントアウトして渡しましょう!ちなみにこれは2001年7月に書かれたものなのでその辺の時差にご注意を。
********************************************************
Broken/not broken
broken beatにとって退屈は発明の母
Amanda Nowinski 著
Kay Suzuki訳
ハウスミュージックはクラブシーンの『安全食』である(便利な音楽という意味)。
古き良き時代のスタイルにソリッドな四つ打ち、そしてお馴染みのゴスペル風やソウルフルな女性ボーカルの甘酸っぱいメロディの端々。フロアや車、ヘッドホンを通してハウスはあなたをインテリジェントに興奮させてくれる。。。
そしてふと気づいてあなたの家へ。
現実にもどってみて、まだ『それ』はあなたをまだ行った事が無いような場所に連れて行ってくれるだろうか?
ブロークンビートは西ロンドンから発せられた新しい音楽で、ダンスミュージックの『退屈さ』に対する解毒剤と言えば分かりやすいかもしれない。
問題はブロークンビートと呼ばれるジャンルは実はジャンルという訳ではまったく無いという事だ。
一番結びつけられる音楽的要素はインストのライブジャズだが、特に決まった型や、ビートの構造があるわけでもないし、決まったベースの音量、メロディやボーカルで分かりやすいフックがあるわけでもない。ビートは四つ打ちでもなければ純粋なブレイクスでもなく、分離された飛び跳ねたようなサウンドで、とても落ち着いて座っていられるような音ではない。ダウンテンポのものでも思わず頭が揺られてしまう。
その無制限な音楽の特徴は、それぞれのアーティストが独特の個性で特筆するクオリティがあるという事だろう。
I.G. Cultureのアフロリズム、Seijiのフリージャズのようなダークなエレクトリックサウンド、Nubian Mindのつんざくようなテクノサウンド、レアグルーブやソウルの影響があるAfronaught(Orin Walters)のサウンド。
そして、ほとんどの場合、この音楽を先導しているのは成熟したアーティスト達である。IG CultureやReinforced(レーベル)のDego (4 Hero)は彼等が聞いてきて愛してきた音楽をランダムに反映させている。 ブロークンビートはポスト・ハウスであり、ポスト・テクノであり、ポスト・アンビエントであり、ポスト・ジャングルでもあり、またそれら全てをひっくるめたものでもある。
あえてこれを定義するならその『姿勢』ではないだろうか。
Brokenbeatsのシーンを引率する集団、Bugz in the atticは西ロンドンでハウスからドラムンベースまで全てをプロデュースをしてきたOrin Walters(Afonaught)によって結成された。
若手メンバーで24歳(当時、今は28歳)のPaul"Seiji"Dolby(またの名をOpaque、Homecookin')の最新作を聴いているみると『混合』という言葉が浮かんでくる。
彼が西ロンドンの自宅から電話越しに言う、
「西ロンドン系の音はとにかくフュージョン(融合)なんだ。別に俺達は一つの型にこだわってる訳じゃない。心配なのはみんながブロークンビートってタグが付いてる音楽を聴いて『そっか、これがブロークンビートって音なんだ』ってシーンを判断しちゃう事なんだ。俺達は同じ音楽を作ってる訳じゃないし、たとえ、同じ西ロンドンのプロデューサーでもみんな様々な違うスタイルがあってやってる事が違うんだ。俺はエレクトリックで、DOMUはテクニカルでドラムンベースみたいにハードだったり、Restless Soul(Phil Asher)みたいにソウルフルだったりするしさ。ホント、幅広く色んなスタイルがあるんだよ。」
ブロークンビートのムーブメントはIG CultureとDegoが始めたスタイルが中心になっている。DegoはSeijiがドラムンベースを作り始めた時のレーベル『Rainforced』のオーナーで、彼のもう一つのレーベル『2000Black』から最近リリースしたコンピレーション『Good Good Compilation』はこの手の音を紹介するに最適だったのではないだろうか。奇しくもちょうどこの頃、アメリカ・デトロイト出身のテクノプロデューサー・Carl Craigの有するレーベル『Planet E』から彼自身のフリージャズとテクノが融合したプロジェクト『Innerzone Orchestra』の輸入版が発売され、ブロークンビートスタイルがアメリカとリンクした。
広いシーンで考えると、西ロンドンのプロデューサー達のやっている事は、ドイツのTruby Trio, Jazzanova, Beanfield, Fauna Flashなどの他の『Compost』レーベルのアーティスト達や、日本のKyoto Jazz Massive、イタリアのVolcovらが始めたエレクトリックなジャズフュージョンとまったく違うわけではない。
「ブロークンビートってのは広い意味でのFuture Jazzの一種だよね。でもアシッドジャズと誤解しちゃいかんよ」と語るのは『XLR8R』というエレクトリックミュージック雑誌の編集人、Tomas Palermo。彼は地元(この記事でアメリカで書かれてます)でレーベル『Ubiquity Records』のJonah SharpやAndrew Jervisらと共にクラブ・Emotoでブロークンビートを毎月プレイしている。
サンフランシスコ生まれの『Ubiquity Records』はFuture Jazzを何年も支持しているレーベルで、Beatless (Alex AttiasとPaul Martin)等の西ロンドンのアーティストから、P'TaahとWamdue ProjectをやっているChris Brannアメリカ人も参加。
Chris Brannのアルバム『De'Compressed』はOpaque moniker名義のSeijiとNubian Mindsのブロークンビートリミックスも収録し、Sun RaやRahsaan Roland Kirk等の往年の前衛ジャズにも迫るスタイルで、ビートをひねってカットアップし、その音は昔のアシッドジャズのようなダンスフロアに優しい音ではなく、ほとんどの音はシンプルなファンクやジャズのフレーズをヒップホップのブレイクスのテンポに落とし込んである。
西ロンドンシーンの強力な『核』は共感するアーティストの密なネットワークとそれを支えるレーベル、『people』・Bugz in the atticの『Bitasweet』・IG Cultureの『Main Squeeze』・『Laws of Motion』、そしてクラブナイトでもある『CO-OP』で発展してきた。
「Bugz in the atticはみんなとやりとりしてるよ」こう語るのは111Minna Stでブロークンビートとフューチャージャズのイベントを毎月主催する『Ubiquity』のJervisだ。
「みんながお互いの生活を支え合ってるよ、確かにそういった輪の中でやりとりしてるのは効果あるよね」
様々なバックグラウンドを限りなく融合して行って《まぁ、トランスやメインストリームのゴミハウスは別として》それでいて、どのスタイルにも留まっていない。
Jervisが加える「つまんなくなったり、飽和したりして死んでいく代わりにメインのプロデューサー達は更に幅広いスタイルに発展させつづけてるよ。AfronaughtのアルバムはIG Cultureのアルバムとは違うサウンドだし、BeatlessのアルバムはtNeon Phusionのアルバムとはまったく違ったサウンドなんだ」
ブロークンビートはロンドンから生まれた最も新しいジャズの動きでありながら、プレスの注目はもう一つのジャンル『2ステップ』に独占した。
2ステップと違ってブロークンビートは特別なガイドもなく、結果的に一つの音楽スタイルをコマーシャルなモノに発展させる、狂信的なジャンルマーケティングの手法にアピールする事は無かった。これはヘソ曲がりなブロークンビート-フューチャージャズ・プロデューサーの意識的なメインストリーム・ダンスミュージックへの反抗なのか、もしくは同じく西ロンドンのプロデューサーで2ステップの大物『MJ Cole』がスポットライトを独占したやり方への批判なのか。
2ステップからの影響も受けていると語るSeijiは"No"と応えた。「ブロークンビートは他のシーンからの影響ってのは特に無いんだ。何に対してもレスポンスはしてないよ。誰も椅子に座って考えて『よし、やろう!俺達でシーンを作ろう!』なんてやってないんだ。ただ、純粋に何か違う、新しい音楽をやろうとしてる奴等が居て、他にも同じ様にやってる奴が居るのに気が付いて、たまたま一緒になって小さいコミュニティを作る事が出来たんだ。どんどん広がって行ってはいるけどね」
それでもSeijiはブロークンビートが稼げる音楽ではないと認める。ヨーロッパのどのメジャー雑誌もIG CultureやDegoのアルバムカバーを出して大々的に取り上げた事はない。このシーンのどのアーティストも広告代理店みたいなものは持ってなさそうだし、CD店で彼等の音楽を見つけるのはある意味チャレンジである。
要するにこの音楽は疎外された位置にあって、コマーシャルマーケットから拒絶されているのだ。
そして、ブラックミュージックでありながら白人のMJ ColeやArtful Dodgerが活躍している、(メディアの大好きな)2ステップと違って、メディアによる西ロンドンのおおざっぱな認識はIG CultureとDegoという黒人だ。よって、ブロークンビートやフューチャージャズは多国籍な性格を持っていても、黒人音楽としてのアイデンティティーを保っているわけだ。
『2000 Black』レーベルは元より、Nubian MindsやAfronaughtというネーミングはその音楽が影響されているルーツが明らかなのは間違いない。
チェロ弾きだったSeijiは(Afronaughtのアルバムでもチェロで参加)、スターダムや金を求めて、こじゃれたシャンペンを飲むようなタイプ(一般的な2ステップのイメージがこれ)というよりはスタジオ・オタクだ。確かにアブストラクトなビートが魅惑的な現金を生むのは想像出来ないだろう。
彼が曲作りについて話す時に頻繁に使われる単語が『science=科学』だ。彼のテクニカルなドラムンベースを聞くと納得する。
Seiji曰く「ドラムンベースは生なグルーヴを生むっていうより、テクノロジーを駆使して音の科学を追求するって感じだよ。当時ドラムンベースがエキサイティングだった時は、とにかくいかにブレイクビートをこねくり回してどれだけ違うモノにできるか、っていう『ビートサイエンス』が全てだったね。」
彼が現在音楽を作り続けているのも同じ科学的アプローチだ。
ただもう彼はジャンルという枠に囚われる罠には落ちない。
「俺のプログラミングのスタイルはドラムンベースから来てるよ。なにか科学的な事をやろうとしている。ハウスビートの四つ打ちってずっと聴いてるとつまらなくなるんだ。それに誰にでも出来る決まったビートを作るってのも飽きるんだよね。だから俺達はちょっと違う事をやろうとしたんだよ。要するに俺達は退屈してたんだ」
そして退屈さはジャンルの壁を打ち破るほどの必然的なシーンの発展をさせた。
ダンスミュージック産業の狂信的なまでのカテゴリー分けに対する執拗は、反逆者であるブロークンビートシーンのアーティストに大々的なマーケティングプランを与えず、商業的なイベントでのライブも与えず、おそらく広告代理店も、そして間違いなく大きなレコード契約も与えないのだ。 普通の人が簡単にアクセス出来るような手段もないまま、アーティスト達は批評家達に敵対するようなリスクを負っているのだ。
ブロークンビートは共感出来る人のあいだの小さなネットワークかもしれない。それでも<ジャンルや決まりきった型からの解放>というメッセージは発信されて間違いなく広がって行くだろう。
********************************************************
ディスカッション大募集。
みなさんの考えも聞かせてくださいね。
個人的に思うに、この音楽は何十年も築き上げれたSoul/Funk/Jazzが現代のテクノロジーによってHip-Hop/Techno/Houseによって再生されて、今、更にそれら全ての集大成として生まれた『ムーブメント=シーン』だと思ってます。作る人のバックグラウンド・趣味によってテンポもビートのスタイルも多様なこの音楽は上記の音楽を通過してない人にとってはちょっと取っ付きにくいかもしれません。でも今この地球上で一番ホットで新鮮で『音楽的な』エッセンスが一番詰まってるのはこのシーンでしょう!
英語版はともかく、俺の訳の無断転記はどんどんやってくれぃ!ただし本編の人と俺の名前は載っけてね。
英語の本文まで載せると長いので英語の分かる方は僕の日記までどーぞ。
|
|
|
|
コメント(5)
>コバヤシさん
いいですよね。ビートサイエンス。
GilesのWorld wideの冒頭でも入ってますよね。
「どうやってこの曲をもっとかっこよくするの?」
「なぁ、俺達は音の科学者だぜ!(We are scientist of Sound!)数学的に音を置くだけだ」
って。カッコイイ〜!
>瀬尾リンタロウさん
どもー!始めまして!
うん、うん。超納得で賛成です。俺も客層がBrokenな客じゃない時はVoモノのブロークンとハウスを交互に混ぜたりしつつ徐々にBrokenのアンセムをかけて客を扇動したりしてます。
そうそう、あのWildな音がファンクを感じますよね。
中学生の時にSly&The Family Stoneを聴いて興奮した感じがBugzを聴いた時によみがえりました!
こ綺麗なジャズハウスからの流れじゃなく、やっぱりHIP-HOP的なブラックネスを感じて欲しいもんです。HIP-HOP客を取り込むにはどうしたらいいですかね?
いいですよね。ビートサイエンス。
GilesのWorld wideの冒頭でも入ってますよね。
「どうやってこの曲をもっとかっこよくするの?」
「なぁ、俺達は音の科学者だぜ!(We are scientist of Sound!)数学的に音を置くだけだ」
って。カッコイイ〜!
>瀬尾リンタロウさん
どもー!始めまして!
うん、うん。超納得で賛成です。俺も客層がBrokenな客じゃない時はVoモノのブロークンとハウスを交互に混ぜたりしつつ徐々にBrokenのアンセムをかけて客を扇動したりしてます。
そうそう、あのWildな音がファンクを感じますよね。
中学生の時にSly&The Family Stoneを聴いて興奮した感じがBugzを聴いた時によみがえりました!
こ綺麗なジャズハウスからの流れじゃなく、やっぱりHIP-HOP的なブラックネスを感じて欲しいもんです。HIP-HOP客を取り込むにはどうしたらいいですかね?
>kay Suzuki
>こ綺麗なジャズハウスからの流れじゃなく、やっぱりHIP-HOP的なブラックネスを感じて欲しいもんです。HIP-HOP客を取り込むにはどうしたらいいですかね?
俺もそこかなり感じます。
hiphhop客をノセるにはどうすればいいか。
なんで、abstractあたりから持っていったり、future jazzのhiphopくさい感じ(最近ではAlex atiasのhelp meなんか)などからcapital Aなんて
やったりしてますが、なかなか難しい。。。
まぁ調子よければのってくれますが。。
そこからbrokenにいって、生jazzあたりでもおどらせきれたら最高なんですが。
やっぱりhiphop層は難しい!!
一般の方々はむずかしいですね。
もっと展開に腕を磨かなければ!
>こ綺麗なジャズハウスからの流れじゃなく、やっぱりHIP-HOP的なブラックネスを感じて欲しいもんです。HIP-HOP客を取り込むにはどうしたらいいですかね?
俺もそこかなり感じます。
hiphhop客をノセるにはどうすればいいか。
なんで、abstractあたりから持っていったり、future jazzのhiphopくさい感じ(最近ではAlex atiasのhelp meなんか)などからcapital Aなんて
やったりしてますが、なかなか難しい。。。
まぁ調子よければのってくれますが。。
そこからbrokenにいって、生jazzあたりでもおどらせきれたら最高なんですが。
やっぱりhiphop層は難しい!!
一般の方々はむずかしいですね。
もっと展開に腕を磨かなければ!
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
bugz in the attic 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
bugz in the atticのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90051人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人