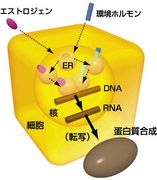http://
はじめに
人間は一生に70トン(たとえば米6トン、小麦2.6トン、野菜7.5トン、乳3.4トン、魚3トンなど)という膨大な食品を摂取し、生命を維持している。しかし、毎日摂取するこの食品の種類や量が、時代とともに大きく変化している。
図1.植物性食品の摂取量の年次推移 図2 動物性食品の摂取量の年次推移
(厚生労働省「国民栄養調査成績」)
たとえばこの50年の統計では、植物性食品の摂取量(g/日)は雑穀が大きく減少しているが、それ以外の物は大きく変化していない(図1)。しかし、動物性の食品では1950年から立ち上がった乳・乳製品の摂取量は飛躍的に上昇している(図2)。肉類、卵類も上昇傾向にある。このような食品摂取の変化は、我々の健康に大きな影響を与えた。すなわち、この変化により、植物性食品と動物性食品のバランスは理想的なものとなり、いわゆる日本型食生活を生み、世界で最高の長寿をもたらした。この食生活が、脳卒中など循環系の疾病や結核を中心とした感染症を大きく減少させた結果と考えられる。
しかしながら一方では、我々の身の回りでは生活習慣病、そしてこれから述べるアレルギーなど免疫系の疾患が増加しつつある。これも摂取する食品が変化しつつあることと関係がある。われわれはその原因を解明し、対策を考えなければならない。
さて、多少の不安はあるにしても、わが国は超高齢化社会を迎えようとしているのも事実である。高齢化によってさまざまな生理機能が低下し、特に免疫機能の低下は顕著となる。高齢者にはガンや感染症が多い。一方、高齢者だけでなくて、若年層においても免疫機能に変化が見られる。たとえば、食の欧風化、そして工業化による大気汚染、さらに微生物による感染の状況も変化し、アレルギーが増加している。
そこで、以下に免疫やアレルギーとはなにかについて述べ、さらにこれらと食や食生活との関係について述べたい。
免疫系は危険なものと安全なものとを見分ける
私たちの身のまわりには、食品から腸内細菌まで平和的に共存する安全なものや、病原細菌や病原性ウイルス、がん細胞などのように危険なものがいる。
免疫系とは、この安全なものは排除せずに、体に傷害を与える危険なものだけと戦って排除するという合理的で賢い仕組みである。
免疫系は病原菌に対して抗体というたんぱく質を、病原ウイルスに対してはキラーT細胞という細胞を使って攻撃・排除する。
また、体内で発生したがん細胞に対してはNK(ナチュラルキラー)細胞などを動員して、これを攻撃・排除する。
しかしこの免疫の働きが低下すると、身近なところでは風邪や感染症、時にはがんや心臓病などを発症する。また、何らかの原因で免疫の機能を担っている細胞の数や質のバランスが崩れるとアレルギー、自己免疫疾患などの病気になる。
このような免疫の機能は、栄養不足や栄養の偏り、高齢化、ストレスの増加などによって低下する。
また、免疫バランスの異常は、食生活のレベルダウン、ストレスの増加、精神的なバランスの崩れなどによって起こる。
腸管免疫系は病原細菌のみを排除する
腸管免疫系は最も大きな免疫系である。すなわち、免疫系全体の60%の細胞や抗体から構成されている。この腸管免疫系には大きな特徴がある。すでに触れたように、食品のように安全なものと、病原細菌のように病原性のあるものを識別していることである。われわれは、生命を維持するため必要なものを受諾して分解し、体内に取り込んでいかなければならない。病原細菌も体内に入ると生命を危険にさらされる。しかしこの病原細菌も、食品と同様にたんぱく質、炭水化物、脂質からつくられているのである。これを食品などと判別し、排除している。
たとえば、腸管免疫系により病原性の細菌と認識されると、IgAが産生され、防御反応が起こる。
図3 食品アレルギーと腸管免疫
腸管免疫系の特異的な免疫抑制機構(経口免疫寛容)は食品アレルギー反応の抑制に関与している。また病原菌が侵入した場合にはIgAが産生され、防御する。
逆に、食品など安全なものが認識された場合は、経口免疫寛容という免疫抑制作用が働く。なぜなら経口的に投与される莫大な量の物質が、すべて抗原として作用すると、免疫過敏状態たとえばアレルギーを発症してしまう。そこでそれを防ぐために、この経口免疫寛容現象が機能するのである。この関係を図3にまとめた。
腸管免疫系は複数の器官の集合体である
以上のような機能を担っている腸管の免疫器官について述べる。
図4 腸管付属リンパ組織の構造
腸管付属リンパ組織の主要構成組織器官は(1)バイエル板(2)小腸上皮細胞、腸管上皮間リンパ球(IEL)(3)粘膜固有層、粘膜固有層リンパ球(LPL)である。
腸管免疫系は、からだの中で最も大きな免疫装置である。そして複数の領域から構成されている。この概要を図4にまとめた。
腸管免疫系を構成しているのは、(1)パイエル板、(2)小腸上皮細胞とそこに存在する腸管固有リンパ球(ILE)、(3)粘膜固有層とそこに存在する粘膜固有リンパ球(LPL)である。IELは、上皮細胞5〜6個につき1個くらいの割合で存在しており、その数は全免疫系細胞の60%もあろうといわれている。経口的に体内に入る抗原は非常に多いため、これに対応する免疫系細胞も大量に存在する必要があるのである。
そしてこれらの組織の下には腸管膜リンパ節や,最近発見されたクリプトパッチが存在する。クリプトパッチは腸管独特のT細胞が作られる場であることが明らかとなっている。
腸管腔内に入ってきた抗原は、パイエル板のM細胞を通って体内に取り込まれ、そしてパイエル板のなかで一般的な免疫応答が起こす。また、一部の抗原は腸管上皮細胞の間隙を通って、あるいは腸管上皮細胞内に取りこまれる形で体内に入る。このような抗原が腸管免疫系と接すると、IgAが産生され、または経口免疫寛容が誘導される。
子供の1割が食品アレルギーである
アレルギーは免疫反応が過敏になったときに起きる疾病である。このアレルギーの発症頻度は、1965年において学童の調査で約1%くらいと報告されている。
ところが1992年にこのアレルギー疾患の調査を行ったところ、子供の場合は40%近く罹患しており、都市部では50%というような驚異的な数字が報告された。成人でも30%と報告されている。アレルギー患者は急激に増加しているのである。
それではなぜこのように増えたのであろうか。アレルギーというのは本来遺伝的な影響を受ける疾病である。したがって、両親がアレルギーの場合、子供は80%はアレルギーを発症してしまう。しかしながら、その発症には遺伝以外にも食生活の洋風化、都市環境の変化、大気汚染、ストレスの増加など、われわれの身の周りの変化もアレルギー増加の大きな原因といわれている。したがって、現在の予測ではアレルギーはますます増えこそすれ、減る可能性は非常に少ないと考えられる。
また最近、アレルギー患者の増加については新しい説が出されている。すなわち感染症とアレルギーは逆の関係があるのではないか、すなわち結核菌感染がアレルギーを抑えていたのではないかと考えられはじめている。これを衛生学説と呼んでいる。 このようなアレルギーの中で、食品の摂取によって発症するものを食品アレルギーという。最近の厚生労働省の調査ではだいたい8.6%くらいの子供が罹患している。
食品アレルギーの大きな特色は、子供の時に非常に多いということである。特にゼロ歳から二歳の間に多い。この後、ある年齢に達するとダニを中心としたアレルギー、さらに花粉を中心としたアレルギーになる。
図5 食品アレルゲンの出現頻度(厚生労働省)
いろいろな食品でアレルギーは起こる。しかし、ある特定な食品でアレルギーを起こす人が多い(5)。卵、魚、ミルク、エビ、カニなどでアレルギーを起こす人が多い。数年前までは、卵や大豆などが主要なアレルギー原因物質であったが、カニによるアレルギー患者が非常な勢いで増えている。
以上、このような食品のいずれも動物性食品である。栄養価が高いため、特に子供の栄養を考えた場合、大きな問題となっている。
外国では、アメリカではピーナッツや卵、ミルクが多い。スウェーデンではヘーゼルナッツアレルギーが多く、ノルウェーやスウェーデンではタラのアレルギーが非常に多いなど、やはりそれぞれの国の食生活を反映していると考えられる。
このような食品アレルギーの発症には、腸管免疫の働きや後で述べる腸内細菌の種類などが大きく関係している。
免疫の働きを高める食品
免疫の働きを高めるには一般的には十分な量のたんぱく質と、必要量のミネラル、ビタミンを与えることが必要である。また大豆中にあるフラボノイド、含硫性の低分子化合物、難消化性の多糖類、体の中で起こる活性化酸素を除去する成分など、非栄養素系といわれる食品成分が免疫系の働きを高める。微量栄養素ではビタミンE, A, C、セレン、亜鉛が免疫の働きの低下を防ぐ働きがある。たとえばビタミンやミネラルを継続的に補給したグループとそうでないグループについて調査を行い、菌に感染した場合どの程度の期間で治るかということを比べた結果がある。その結果、普通の食事以外にビタミンとかミネラルをサプリメントとして与えた場合には、そうでない場合に比べて短期間で感染症が治癒することが確認されている。
つぎに、ビタミンE、亜鉛、セレン個々について、その作用を述べる。
食品をからだの中で燃やすには酸素が必要である。通常の酸素とは少し性状の異なる活性酸素と呼ばれる物質もからだの中に存在する。活性酸素は基本的には生命の維持に必要な生理作用をもつが、過剰になるとからだに多くの傷害を与え免疫細胞を壊してしまい、リウマチ、アレルギー、がん、動脈硬化といったような病気を発症させる。ビタミンEはこのような活性酸素が大量に発生させないはたらきがある。また高齢になるとプロスタグランジンE2といったような物質が体の中に出てきて免疫系を弱めてしまう。ビタミンEはこれができるのも防ぎ、免疫系のはたらきを高める。
亜鉛はわれわれのからだの中で不足しがちなミネラルである。亜鉛はもともと免疫細胞の生成に役立っている。さらにスーパーオキサイドジスムターゼという活性酸素を除去する酵素の構成成分であり、この酵素の働きにとって必須な成分である。亜鉛を不足するとこの酵素は働かない。したがって、亜鉛の摂取は免疫機能の維持に必須である。
セレンも亜鉛と同様の働きをしている。
以上のように免疫の働きを維持し高めるには栄養価の高いタンパク質、そしてこれまで述べたビタミンやミネラルを摂ることが重要である。しかし脂肪は、一般には免疫系を抑えるような方向に働いていて、あまり摂りすぎると免疫の働きを弱めてしまうことになる。したがって、脂肪の取り方は注意しなければならない。
過敏な免疫反応-アレルギーを抑制する食品もある
食品のなかで、免疫の機能を高める食品がある一方で、免疫のバランスが崩れた結果発症するアレルギーを抑える食品もある。たとえば腸管免疫の特性を利用した経口免疫寛容やプロバイオテックス、プレバイオティクス、そしてヌクレオチド、ω-3系の脂肪酸などが最近になって報告されている。これらのなかで、経口免疫寛容そしてプロバイオティクスは最近注目を集めている。ここでは、まず経口免疫寛容について、次いでプロバイオティクスと密接に関係する腸内細菌、この腸内細菌とすでに述べた腸管免疫との関係、そしてそのアレルギー抑制への適用に話を進めたい。
経口免疫寛容は食品アレルギーを抑えるしくみである
われわれはふつうはアレルギーの原因になるようなものを食べてもアレルギーを発症するわけではない。アレルギー原因物質が大量に体内に入ってきても過敏な免疫現象が起こるのを抑える命令が出されるからである。これが経口免疫寛容という免疫現象であることは既に述べた。この現象を積極的に利用して、アレルギーを治す試みがこの20年くらい行われている。中国の古書には「子供のうちに漆を食べさせるとかぶれ(おそらくアレルギー)が起こらない。からだの変調が起こらない」ということが記載されているので、この現象は2000年くらい前から観察されていたことになる。
しかし、つい最近までこれが免疫反応の一種であるのか明らかでなかったが、免疫学の発展とともにこれが本格的免疫現象であることが明白になった。たとえば花粉アレルギーを治そうと思ったら花粉を食べさせればいい。あまりきれいな話ではないかもしれないが、ダニアレルギーを直すためにはダニを食べさせればいいようなことが実際に研究として行われた。
その例として、スギ花粉症について行った動物実験を紹介したい。スギ花粉症は日本の代表的なアレルギー疾患の一つで、最近も被害に遭われた方が多いのではないかと思う。花粉の中のタンパク質の中でアレルギーを起こすのはCry-j1、Cry-j2である。動物モデルでは、マウスにこれを食べさせると明らかにアレルギー発症に関係するIgEという抗体の量が減少する。したがって経口免疫寛容が誘導されアレルギーを抑えられた可能性が示された。
これ以外に経口免疫寛容によるアレルギー抑制は、シラカバ、トウモロコシの花粉、ダニなどで試みられている。まだ臨床応用で確立された治療法ではないが、今後の発展を期待したい。
腸内細菌と免疫・アレルギーには密接な関係がある
腸管には1014個位の微生物が生息している。そしてその重量は1kgに達する。これら微生物群は腸管免疫系を刺激し、その免疫的環境を左右する。
最近になり、腸内細菌が免疫系におよぼす影響について多くのことが明らかになりつつある。たとえば腸内細菌の生息しない無菌マウスでは、IgAの産生が低い。また同様に無菌マウスでは経口免疫寛容が誘導されない、すなわち腸内細菌は、このような腸内免疫系の重要な2つの特徴的な機能にとって必須である。
さらに、免疫遺伝子の個人のタイプ(主要組織適合複合体のタイプ)と腸内細菌のタイプが関係する。そして逆に、腸内細菌のタイプが特定のタイプの抗体産生に影響を与えるといわれている。
また、細菌、抗原の種類によって誘導されるT細胞の種類が異なることが明らかとなっている。T細胞はTh1型およびTh2型の2種類があり、このTh1とTh2のバランスがとれている場合には免疫系は正常であるが、Th2へとバランスが傾くとアレルギー、Th1へ傾くと自己免疫疾患になりやすい。免疫系を完全に保つにはTh2/Th1バランスが良好である必要がある。
図6 Th1あるいはTh2型T細胞を誘導する抗原
グラム陽性菌の代表的なものとして有用乳酸菌(ビフィズス菌など)、グラム陰性菌の代表的なものとして大腸菌や腸内に生息するバクテロイデス、病原菌としては結核菌が知られている。
一般にラクトバチルス菌
( http://
やビフィズス菌などのグラム陽性菌は、T細胞をTh1へと導く。この関係を図6にまとめた。
なぜグラム陽性菌がTh1を誘導するかについて、現在その機構が急速に明らかになりつつある。すなわち、抗原提示細胞にToll様受容体が存在して、これがTh1, Th2を決めていることが明らかになりつつある。Toll様受容体のなかで、TLR2, TLR4と呼ばれているものが特に関与している。
たとえばグラム陽性菌が侵入すると、細胞壁のペプチドグリカン、リポタイコ酸などを抗原提示細胞上のTLR2やTLR4がそれを認識し、抗原提示細胞はIL-12などのサイトカインを産生する。そしてこのIL-12は、T細胞をTh1型に誘導する。またアレルギーについては、1999 年には
Bi嗅sten
らによって、腸内フローラにラクトバチルス菌が多い子供にはアレルギーが少ないことが報告され、腸内細菌パターンがアレルギーの発症に関係するとの可能性が強く主張されている。
その理由は、腸内細菌においてグラム陽性菌のラクトバチルス菌はTh1を誘導し、これがアレルギー反応を抑制した結果であろうと考えられている。今後、徹底したその作用機構の解明が必要であろうが、極めて興味ある現象である。
プロバイオティクスは免疫に影響を与える
プロバイオティクスとはわれわれの腸内フローラを改善してその健康の維持に貢献する微生物群のことである。腸内フローラは健常な状態であれば、菌の構成もバランスがとれ生体に良い影響を与える菌が充分に生息している。しかしさまざまな要因によりバランスが崩れると生体に悪い影響を与える菌が優性となり、健康の維持に好ましくない。特に腸内フローラの構成と腸内免疫、全身免疫には大きな関係があることは良く知られている。プロバイオティクスはさまざまな要因で変化しがちな腸内フローラを健常な状態に保つために投与される。
プロバイオティクスとして用いられる各種菌株についてそのパイエル板や脾臓細胞に対する免疫賦活作用を調べると、多くの菌体に賦活作用があることを認めた。
さらに、著者らはプロバイオティクスの免疫調節作用について研究を行った。すなわち、腸内フローラより採取したラクトバチルスカゼイ菌(Lactobacillus casei)免疫応答に与える影響を、マウス実験系を用いて調べた。
その結果、この菌はアレルギー発症の原因となる免疫グロブリンEの産生を抑制することや、アレルギー反応によって起こるアナフィラキシーショックを抑制することを見出した。その機構を調べると、この菌の投与によってインターロイキン-4は減少し、γ-インターフェロンが増加することが観察された。すなわちこのマウスのTh2/Th1に傾いたことを示している。また実際にラクトバチルス菌を経口投与することにより、アレルギーの発症を抑制したとの報告も出されており、プロバイオティクスの重要性は確認されている。
おわりに
これまで食と免疫・アレルギーについて述べてきた。この問題から派生して、最後にわれわれが食品や食生活の未来を考える場合、真剣に取り組む必要のある課題について述べる。
それはゲノムと食品ということである。ごく最近、人間の全染色体の遺伝子の構造が解明されたと報告された。遺伝子の全解読は医療の問題、それ以外の倫理的な問題も含めて大きなインパクトを与えつつある。このゲノム解読は毎日摂っている食品と遺伝子、体質の問題に重要な影響を与えると考えられる。なぜなら、どういう遺伝子をもっている人がどういうものを食べた場合にもっとも病気になりにくいかという情報が確実に得られるのである。
人間には染色体があり、この染色体の遺伝子の塩基配列が分かりつつある。それと同時に、どういう遺伝子がどういう病気と関係するか、たとえばどういう遺伝子がアレルギーやがんなどと、さらに自己免疫疾患に関係するのか明らかになるであろう。
そして最近では、個人における遺伝子の特徴を簡便に推測できるようになっている。これを用いれば個人のDNAを採取するとどういう病気になりやすいか、アレルギーになりやすいかという体質判定ができる。予防のための食品と食生活を工夫する。そしてそれによってある程度予防が可能だろうと考えられる。いわゆる、オーダーメイド食品も将来出現することは疑いのない事実である。われわれはこのような生命科学の大いなる発表を食生活に取り入れ健康な生命を全う出来るよう努力が必要である。
はじめに
人間は一生に70トン(たとえば米6トン、小麦2.6トン、野菜7.5トン、乳3.4トン、魚3トンなど)という膨大な食品を摂取し、生命を維持している。しかし、毎日摂取するこの食品の種類や量が、時代とともに大きく変化している。
図1.植物性食品の摂取量の年次推移 図2 動物性食品の摂取量の年次推移
(厚生労働省「国民栄養調査成績」)
たとえばこの50年の統計では、植物性食品の摂取量(g/日)は雑穀が大きく減少しているが、それ以外の物は大きく変化していない(図1)。しかし、動物性の食品では1950年から立ち上がった乳・乳製品の摂取量は飛躍的に上昇している(図2)。肉類、卵類も上昇傾向にある。このような食品摂取の変化は、我々の健康に大きな影響を与えた。すなわち、この変化により、植物性食品と動物性食品のバランスは理想的なものとなり、いわゆる日本型食生活を生み、世界で最高の長寿をもたらした。この食生活が、脳卒中など循環系の疾病や結核を中心とした感染症を大きく減少させた結果と考えられる。
しかしながら一方では、我々の身の回りでは生活習慣病、そしてこれから述べるアレルギーなど免疫系の疾患が増加しつつある。これも摂取する食品が変化しつつあることと関係がある。われわれはその原因を解明し、対策を考えなければならない。
さて、多少の不安はあるにしても、わが国は超高齢化社会を迎えようとしているのも事実である。高齢化によってさまざまな生理機能が低下し、特に免疫機能の低下は顕著となる。高齢者にはガンや感染症が多い。一方、高齢者だけでなくて、若年層においても免疫機能に変化が見られる。たとえば、食の欧風化、そして工業化による大気汚染、さらに微生物による感染の状況も変化し、アレルギーが増加している。
そこで、以下に免疫やアレルギーとはなにかについて述べ、さらにこれらと食や食生活との関係について述べたい。
免疫系は危険なものと安全なものとを見分ける
私たちの身のまわりには、食品から腸内細菌まで平和的に共存する安全なものや、病原細菌や病原性ウイルス、がん細胞などのように危険なものがいる。
免疫系とは、この安全なものは排除せずに、体に傷害を与える危険なものだけと戦って排除するという合理的で賢い仕組みである。
免疫系は病原菌に対して抗体というたんぱく質を、病原ウイルスに対してはキラーT細胞という細胞を使って攻撃・排除する。
また、体内で発生したがん細胞に対してはNK(ナチュラルキラー)細胞などを動員して、これを攻撃・排除する。
しかしこの免疫の働きが低下すると、身近なところでは風邪や感染症、時にはがんや心臓病などを発症する。また、何らかの原因で免疫の機能を担っている細胞の数や質のバランスが崩れるとアレルギー、自己免疫疾患などの病気になる。
このような免疫の機能は、栄養不足や栄養の偏り、高齢化、ストレスの増加などによって低下する。
また、免疫バランスの異常は、食生活のレベルダウン、ストレスの増加、精神的なバランスの崩れなどによって起こる。
腸管免疫系は病原細菌のみを排除する
腸管免疫系は最も大きな免疫系である。すなわち、免疫系全体の60%の細胞や抗体から構成されている。この腸管免疫系には大きな特徴がある。すでに触れたように、食品のように安全なものと、病原細菌のように病原性のあるものを識別していることである。われわれは、生命を維持するため必要なものを受諾して分解し、体内に取り込んでいかなければならない。病原細菌も体内に入ると生命を危険にさらされる。しかしこの病原細菌も、食品と同様にたんぱく質、炭水化物、脂質からつくられているのである。これを食品などと判別し、排除している。
たとえば、腸管免疫系により病原性の細菌と認識されると、IgAが産生され、防御反応が起こる。
図3 食品アレルギーと腸管免疫
腸管免疫系の特異的な免疫抑制機構(経口免疫寛容)は食品アレルギー反応の抑制に関与している。また病原菌が侵入した場合にはIgAが産生され、防御する。
逆に、食品など安全なものが認識された場合は、経口免疫寛容という免疫抑制作用が働く。なぜなら経口的に投与される莫大な量の物質が、すべて抗原として作用すると、免疫過敏状態たとえばアレルギーを発症してしまう。そこでそれを防ぐために、この経口免疫寛容現象が機能するのである。この関係を図3にまとめた。
腸管免疫系は複数の器官の集合体である
以上のような機能を担っている腸管の免疫器官について述べる。
図4 腸管付属リンパ組織の構造
腸管付属リンパ組織の主要構成組織器官は(1)バイエル板(2)小腸上皮細胞、腸管上皮間リンパ球(IEL)(3)粘膜固有層、粘膜固有層リンパ球(LPL)である。
腸管免疫系は、からだの中で最も大きな免疫装置である。そして複数の領域から構成されている。この概要を図4にまとめた。
腸管免疫系を構成しているのは、(1)パイエル板、(2)小腸上皮細胞とそこに存在する腸管固有リンパ球(ILE)、(3)粘膜固有層とそこに存在する粘膜固有リンパ球(LPL)である。IELは、上皮細胞5〜6個につき1個くらいの割合で存在しており、その数は全免疫系細胞の60%もあろうといわれている。経口的に体内に入る抗原は非常に多いため、これに対応する免疫系細胞も大量に存在する必要があるのである。
そしてこれらの組織の下には腸管膜リンパ節や,最近発見されたクリプトパッチが存在する。クリプトパッチは腸管独特のT細胞が作られる場であることが明らかとなっている。
腸管腔内に入ってきた抗原は、パイエル板のM細胞を通って体内に取り込まれ、そしてパイエル板のなかで一般的な免疫応答が起こす。また、一部の抗原は腸管上皮細胞の間隙を通って、あるいは腸管上皮細胞内に取りこまれる形で体内に入る。このような抗原が腸管免疫系と接すると、IgAが産生され、または経口免疫寛容が誘導される。
子供の1割が食品アレルギーである
アレルギーは免疫反応が過敏になったときに起きる疾病である。このアレルギーの発症頻度は、1965年において学童の調査で約1%くらいと報告されている。
ところが1992年にこのアレルギー疾患の調査を行ったところ、子供の場合は40%近く罹患しており、都市部では50%というような驚異的な数字が報告された。成人でも30%と報告されている。アレルギー患者は急激に増加しているのである。
それではなぜこのように増えたのであろうか。アレルギーというのは本来遺伝的な影響を受ける疾病である。したがって、両親がアレルギーの場合、子供は80%はアレルギーを発症してしまう。しかしながら、その発症には遺伝以外にも食生活の洋風化、都市環境の変化、大気汚染、ストレスの増加など、われわれの身の周りの変化もアレルギー増加の大きな原因といわれている。したがって、現在の予測ではアレルギーはますます増えこそすれ、減る可能性は非常に少ないと考えられる。
また最近、アレルギー患者の増加については新しい説が出されている。すなわち感染症とアレルギーは逆の関係があるのではないか、すなわち結核菌感染がアレルギーを抑えていたのではないかと考えられはじめている。これを衛生学説と呼んでいる。 このようなアレルギーの中で、食品の摂取によって発症するものを食品アレルギーという。最近の厚生労働省の調査ではだいたい8.6%くらいの子供が罹患している。
食品アレルギーの大きな特色は、子供の時に非常に多いということである。特にゼロ歳から二歳の間に多い。この後、ある年齢に達するとダニを中心としたアレルギー、さらに花粉を中心としたアレルギーになる。
図5 食品アレルゲンの出現頻度(厚生労働省)
いろいろな食品でアレルギーは起こる。しかし、ある特定な食品でアレルギーを起こす人が多い(5)。卵、魚、ミルク、エビ、カニなどでアレルギーを起こす人が多い。数年前までは、卵や大豆などが主要なアレルギー原因物質であったが、カニによるアレルギー患者が非常な勢いで増えている。
以上、このような食品のいずれも動物性食品である。栄養価が高いため、特に子供の栄養を考えた場合、大きな問題となっている。
外国では、アメリカではピーナッツや卵、ミルクが多い。スウェーデンではヘーゼルナッツアレルギーが多く、ノルウェーやスウェーデンではタラのアレルギーが非常に多いなど、やはりそれぞれの国の食生活を反映していると考えられる。
このような食品アレルギーの発症には、腸管免疫の働きや後で述べる腸内細菌の種類などが大きく関係している。
免疫の働きを高める食品
免疫の働きを高めるには一般的には十分な量のたんぱく質と、必要量のミネラル、ビタミンを与えることが必要である。また大豆中にあるフラボノイド、含硫性の低分子化合物、難消化性の多糖類、体の中で起こる活性化酸素を除去する成分など、非栄養素系といわれる食品成分が免疫系の働きを高める。微量栄養素ではビタミンE, A, C、セレン、亜鉛が免疫の働きの低下を防ぐ働きがある。たとえばビタミンやミネラルを継続的に補給したグループとそうでないグループについて調査を行い、菌に感染した場合どの程度の期間で治るかということを比べた結果がある。その結果、普通の食事以外にビタミンとかミネラルをサプリメントとして与えた場合には、そうでない場合に比べて短期間で感染症が治癒することが確認されている。
つぎに、ビタミンE、亜鉛、セレン個々について、その作用を述べる。
食品をからだの中で燃やすには酸素が必要である。通常の酸素とは少し性状の異なる活性酸素と呼ばれる物質もからだの中に存在する。活性酸素は基本的には生命の維持に必要な生理作用をもつが、過剰になるとからだに多くの傷害を与え免疫細胞を壊してしまい、リウマチ、アレルギー、がん、動脈硬化といったような病気を発症させる。ビタミンEはこのような活性酸素が大量に発生させないはたらきがある。また高齢になるとプロスタグランジンE2といったような物質が体の中に出てきて免疫系を弱めてしまう。ビタミンEはこれができるのも防ぎ、免疫系のはたらきを高める。
亜鉛はわれわれのからだの中で不足しがちなミネラルである。亜鉛はもともと免疫細胞の生成に役立っている。さらにスーパーオキサイドジスムターゼという活性酸素を除去する酵素の構成成分であり、この酵素の働きにとって必須な成分である。亜鉛を不足するとこの酵素は働かない。したがって、亜鉛の摂取は免疫機能の維持に必須である。
セレンも亜鉛と同様の働きをしている。
以上のように免疫の働きを維持し高めるには栄養価の高いタンパク質、そしてこれまで述べたビタミンやミネラルを摂ることが重要である。しかし脂肪は、一般には免疫系を抑えるような方向に働いていて、あまり摂りすぎると免疫の働きを弱めてしまうことになる。したがって、脂肪の取り方は注意しなければならない。
過敏な免疫反応-アレルギーを抑制する食品もある
食品のなかで、免疫の機能を高める食品がある一方で、免疫のバランスが崩れた結果発症するアレルギーを抑える食品もある。たとえば腸管免疫の特性を利用した経口免疫寛容やプロバイオテックス、プレバイオティクス、そしてヌクレオチド、ω-3系の脂肪酸などが最近になって報告されている。これらのなかで、経口免疫寛容そしてプロバイオティクスは最近注目を集めている。ここでは、まず経口免疫寛容について、次いでプロバイオティクスと密接に関係する腸内細菌、この腸内細菌とすでに述べた腸管免疫との関係、そしてそのアレルギー抑制への適用に話を進めたい。
経口免疫寛容は食品アレルギーを抑えるしくみである
われわれはふつうはアレルギーの原因になるようなものを食べてもアレルギーを発症するわけではない。アレルギー原因物質が大量に体内に入ってきても過敏な免疫現象が起こるのを抑える命令が出されるからである。これが経口免疫寛容という免疫現象であることは既に述べた。この現象を積極的に利用して、アレルギーを治す試みがこの20年くらい行われている。中国の古書には「子供のうちに漆を食べさせるとかぶれ(おそらくアレルギー)が起こらない。からだの変調が起こらない」ということが記載されているので、この現象は2000年くらい前から観察されていたことになる。
しかし、つい最近までこれが免疫反応の一種であるのか明らかでなかったが、免疫学の発展とともにこれが本格的免疫現象であることが明白になった。たとえば花粉アレルギーを治そうと思ったら花粉を食べさせればいい。あまりきれいな話ではないかもしれないが、ダニアレルギーを直すためにはダニを食べさせればいいようなことが実際に研究として行われた。
その例として、スギ花粉症について行った動物実験を紹介したい。スギ花粉症は日本の代表的なアレルギー疾患の一つで、最近も被害に遭われた方が多いのではないかと思う。花粉の中のタンパク質の中でアレルギーを起こすのはCry-j1、Cry-j2である。動物モデルでは、マウスにこれを食べさせると明らかにアレルギー発症に関係するIgEという抗体の量が減少する。したがって経口免疫寛容が誘導されアレルギーを抑えられた可能性が示された。
これ以外に経口免疫寛容によるアレルギー抑制は、シラカバ、トウモロコシの花粉、ダニなどで試みられている。まだ臨床応用で確立された治療法ではないが、今後の発展を期待したい。
腸内細菌と免疫・アレルギーには密接な関係がある
腸管には1014個位の微生物が生息している。そしてその重量は1kgに達する。これら微生物群は腸管免疫系を刺激し、その免疫的環境を左右する。
最近になり、腸内細菌が免疫系におよぼす影響について多くのことが明らかになりつつある。たとえば腸内細菌の生息しない無菌マウスでは、IgAの産生が低い。また同様に無菌マウスでは経口免疫寛容が誘導されない、すなわち腸内細菌は、このような腸内免疫系の重要な2つの特徴的な機能にとって必須である。
さらに、免疫遺伝子の個人のタイプ(主要組織適合複合体のタイプ)と腸内細菌のタイプが関係する。そして逆に、腸内細菌のタイプが特定のタイプの抗体産生に影響を与えるといわれている。
また、細菌、抗原の種類によって誘導されるT細胞の種類が異なることが明らかとなっている。T細胞はTh1型およびTh2型の2種類があり、このTh1とTh2のバランスがとれている場合には免疫系は正常であるが、Th2へとバランスが傾くとアレルギー、Th1へ傾くと自己免疫疾患になりやすい。免疫系を完全に保つにはTh2/Th1バランスが良好である必要がある。
図6 Th1あるいはTh2型T細胞を誘導する抗原
グラム陽性菌の代表的なものとして有用乳酸菌(ビフィズス菌など)、グラム陰性菌の代表的なものとして大腸菌や腸内に生息するバクテロイデス、病原菌としては結核菌が知られている。
一般にラクトバチルス菌
( http://
やビフィズス菌などのグラム陽性菌は、T細胞をTh1へと導く。この関係を図6にまとめた。
なぜグラム陽性菌がTh1を誘導するかについて、現在その機構が急速に明らかになりつつある。すなわち、抗原提示細胞にToll様受容体が存在して、これがTh1, Th2を決めていることが明らかになりつつある。Toll様受容体のなかで、TLR2, TLR4と呼ばれているものが特に関与している。
たとえばグラム陽性菌が侵入すると、細胞壁のペプチドグリカン、リポタイコ酸などを抗原提示細胞上のTLR2やTLR4がそれを認識し、抗原提示細胞はIL-12などのサイトカインを産生する。そしてこのIL-12は、T細胞をTh1型に誘導する。またアレルギーについては、1999 年には
Bi嗅sten
らによって、腸内フローラにラクトバチルス菌が多い子供にはアレルギーが少ないことが報告され、腸内細菌パターンがアレルギーの発症に関係するとの可能性が強く主張されている。
その理由は、腸内細菌においてグラム陽性菌のラクトバチルス菌はTh1を誘導し、これがアレルギー反応を抑制した結果であろうと考えられている。今後、徹底したその作用機構の解明が必要であろうが、極めて興味ある現象である。
プロバイオティクスは免疫に影響を与える
プロバイオティクスとはわれわれの腸内フローラを改善してその健康の維持に貢献する微生物群のことである。腸内フローラは健常な状態であれば、菌の構成もバランスがとれ生体に良い影響を与える菌が充分に生息している。しかしさまざまな要因によりバランスが崩れると生体に悪い影響を与える菌が優性となり、健康の維持に好ましくない。特に腸内フローラの構成と腸内免疫、全身免疫には大きな関係があることは良く知られている。プロバイオティクスはさまざまな要因で変化しがちな腸内フローラを健常な状態に保つために投与される。
プロバイオティクスとして用いられる各種菌株についてそのパイエル板や脾臓細胞に対する免疫賦活作用を調べると、多くの菌体に賦活作用があることを認めた。
さらに、著者らはプロバイオティクスの免疫調節作用について研究を行った。すなわち、腸内フローラより採取したラクトバチルスカゼイ菌(Lactobacillus casei)免疫応答に与える影響を、マウス実験系を用いて調べた。
その結果、この菌はアレルギー発症の原因となる免疫グロブリンEの産生を抑制することや、アレルギー反応によって起こるアナフィラキシーショックを抑制することを見出した。その機構を調べると、この菌の投与によってインターロイキン-4は減少し、γ-インターフェロンが増加することが観察された。すなわちこのマウスのTh2/Th1に傾いたことを示している。また実際にラクトバチルス菌を経口投与することにより、アレルギーの発症を抑制したとの報告も出されており、プロバイオティクスの重要性は確認されている。
おわりに
これまで食と免疫・アレルギーについて述べてきた。この問題から派生して、最後にわれわれが食品や食生活の未来を考える場合、真剣に取り組む必要のある課題について述べる。
それはゲノムと食品ということである。ごく最近、人間の全染色体の遺伝子の構造が解明されたと報告された。遺伝子の全解読は医療の問題、それ以外の倫理的な問題も含めて大きなインパクトを与えつつある。このゲノム解読は毎日摂っている食品と遺伝子、体質の問題に重要な影響を与えると考えられる。なぜなら、どういう遺伝子をもっている人がどういうものを食べた場合にもっとも病気になりにくいかという情報が確実に得られるのである。
人間には染色体があり、この染色体の遺伝子の塩基配列が分かりつつある。それと同時に、どういう遺伝子がどういう病気と関係するか、たとえばどういう遺伝子がアレルギーやがんなどと、さらに自己免疫疾患に関係するのか明らかになるであろう。
そして最近では、個人における遺伝子の特徴を簡便に推測できるようになっている。これを用いれば個人のDNAを採取するとどういう病気になりやすいか、アレルギーになりやすいかという体質判定ができる。予防のための食品と食生活を工夫する。そしてそれによってある程度予防が可能だろうと考えられる。いわゆる、オーダーメイド食品も将来出現することは疑いのない事実である。われわれはこのような生命科学の大いなる発表を食生活に取り入れ健康な生命を全う出来るよう努力が必要である。
|
|
|
|
|
|
|
|
☻人体生命科学と薬理学 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
☻人体生命科学と薬理学のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37847人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人