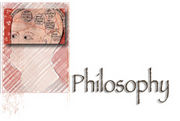私の学んだことを少し書き込んで見ます。
1.はじめに「心の哲学」を学ぼうとした理由
現代哲学の最先端の一つに「心の哲学」があるということを知ったのは、信原幸弘著の『心の現代哲学』1999年6月発行をある先生に紹介されてからである。それまでは、「心の哲学」というテーマをうかつにも聞きもらしていたので、あらためて「心の哲学」があることを知った。私は、現代哲学の問題を、科学技術の発達の結果から生じる脳死判定問題や臓器移植、遺伝子操作、生命倫理や環境問題など、おもに倫理面で捉えていた。しかし、それよりはるかに複雑で未解決な問題の多い、人間の「心」を対象とした哲学があることを知って驚いた。この問題に無知であった私のこの驚きが、この「心の哲学」を学ぼうとした一つの理由である。
中世のスコラ学はアリストテレス的世界観であったが、デカルトの心身二元論によって近代の科学的世界観へと転回し、カントの認識論では人の心や感情は哲学の対象からいったん離れた観がある。それが「心身問題」として、今日再び時代の脚光をあびることになってきた。新しい時代の脚光を浴びている「心の哲学」という現代哲学のテーマに関心をよせたのは、やはり、人間の心を合理的に理解し全体像を把握したいからにほかならない。これが「心の哲学」を学ぶもう一つの理由である。
1.はじめに「心の哲学」を学ぼうとした理由
現代哲学の最先端の一つに「心の哲学」があるということを知ったのは、信原幸弘著の『心の現代哲学』1999年6月発行をある先生に紹介されてからである。それまでは、「心の哲学」というテーマをうかつにも聞きもらしていたので、あらためて「心の哲学」があることを知った。私は、現代哲学の問題を、科学技術の発達の結果から生じる脳死判定問題や臓器移植、遺伝子操作、生命倫理や環境問題など、おもに倫理面で捉えていた。しかし、それよりはるかに複雑で未解決な問題の多い、人間の「心」を対象とした哲学があることを知って驚いた。この問題に無知であった私のこの驚きが、この「心の哲学」を学ぼうとした一つの理由である。
中世のスコラ学はアリストテレス的世界観であったが、デカルトの心身二元論によって近代の科学的世界観へと転回し、カントの認識論では人の心や感情は哲学の対象からいったん離れた観がある。それが「心身問題」として、今日再び時代の脚光をあびることになってきた。新しい時代の脚光を浴びている「心の哲学」という現代哲学のテーマに関心をよせたのは、やはり、人間の心を合理的に理解し全体像を把握したいからにほかならない。これが「心の哲学」を学ぶもう一つの理由である。
|
|
|
|
コメント(19)
2.心の哲学とはなにか
20世紀後半になって現代科学哲学のなかで注目を浴びるようになった心の哲学(Philosophy of Mind)は、21世紀にはいって今なおホットな研究途上の学問である。『岩波 哲学思想事典』岩波書店(1998年3月「心の哲学」519Lページ)によれば、次のように解説されている。「心の本性をめぐる問題は、特に近世に入ってデカルトが物心二元論を唱えて以来、哲学の中心問題として大きく浮上した。デカルトは心と物を異なる実体としたために、両者間の相互作用をいかにして説明しうるかという難問を抱え込むこととなった。デカルト以降、この問題に対処するために機会原因論や並行論のようなさまざまな説が唱えられたが、いずれも満足のいくものではなく、そのため二元論を放棄して、唯心論や唯物論のような一元論が提起されもしたが、それらもまたあまり満足のいくものではなかった。こうして心の本性を問う問題、特に心と物ないし身体の関係を問う「心身問題」は、現在でもなお哲学の中心的な難問でありつづけている。」
また、2000年4月に発行された、笠松幸一、和田和行編の『21世紀の哲学』 八千代出版社 (25ページ)の中で大沢秀介は、次のように述べている。「『心の哲学』とは何であろうか。最近出現したインターネットの哲学事典の定義によれば、心という現象一般の本質、とくに意識、感覚、知覚、概念、行為、推論、意図、信念、記憶などの役割に関心をもつ哲学の分野であり、そこでの主要問題は、自由意志、人格の同一性、心身問題、他者の心、計算主義などである。」また、これは、1970年代の半ばまで英米分析哲学の主流を占めていた「言語哲学」に代わって登場した、心の本性を対象とする哲学であり、上記にみられるような心の現象全般の本質を認識することをその分野としている、としている。
心の哲学は現代哲学の最前線であることに加えて、さらに研究の対象が人の「心」であり、これにかかわる複数の学問体系が絡み合っており、哲学としての研究だけでは解明できない面が多い。他の学問の研究結果も総合して検討する必要のある極めて学際的な分野である。
20世紀後半になって現代科学哲学のなかで注目を浴びるようになった心の哲学(Philosophy of Mind)は、21世紀にはいって今なおホットな研究途上の学問である。『岩波 哲学思想事典』岩波書店(1998年3月「心の哲学」519Lページ)によれば、次のように解説されている。「心の本性をめぐる問題は、特に近世に入ってデカルトが物心二元論を唱えて以来、哲学の中心問題として大きく浮上した。デカルトは心と物を異なる実体としたために、両者間の相互作用をいかにして説明しうるかという難問を抱え込むこととなった。デカルト以降、この問題に対処するために機会原因論や並行論のようなさまざまな説が唱えられたが、いずれも満足のいくものではなく、そのため二元論を放棄して、唯心論や唯物論のような一元論が提起されもしたが、それらもまたあまり満足のいくものではなかった。こうして心の本性を問う問題、特に心と物ないし身体の関係を問う「心身問題」は、現在でもなお哲学の中心的な難問でありつづけている。」
また、2000年4月に発行された、笠松幸一、和田和行編の『21世紀の哲学』 八千代出版社 (25ページ)の中で大沢秀介は、次のように述べている。「『心の哲学』とは何であろうか。最近出現したインターネットの哲学事典の定義によれば、心という現象一般の本質、とくに意識、感覚、知覚、概念、行為、推論、意図、信念、記憶などの役割に関心をもつ哲学の分野であり、そこでの主要問題は、自由意志、人格の同一性、心身問題、他者の心、計算主義などである。」また、これは、1970年代の半ばまで英米分析哲学の主流を占めていた「言語哲学」に代わって登場した、心の本性を対象とする哲学であり、上記にみられるような心の現象全般の本質を認識することをその分野としている、としている。
心の哲学は現代哲学の最前線であることに加えて、さらに研究の対象が人の「心」であり、これにかかわる複数の学問体系が絡み合っており、哲学としての研究だけでは解明できない面が多い。他の学問の研究結果も総合して検討する必要のある極めて学際的な分野である。
3. 20世紀後半の変遷
英米の論理実証主義と同時代の心理学は行動主義であった。それは、非科学的な論証の排除を目的としていた。そして、それはまた、行動傾向を指示する語彙を優先して、心的なものの言及を制限しようとする心理学上の方法論であった。行動主義が哲学へ影響し、心身問題や他者の心の哲学問題の無意味性を主張、戦後、クワイン(1908-2000)やライル(1900−1976)の著作に影響を与えた。行動主義の影響は1950年代に終わった。その理由は「行動主義」者の方法の厳格性にあった。それはまた科学的に不毛であると考えた。批判は言語学者のチョムスキー(1928-)によるもので、彼は生成変形文法の言語学を創始した。これは反行動主義的心理学の認知心理学、ひいては認知科学の誕生をもたらした。(参考前掲 『21世紀の哲学』 大沢秀介「心の哲学」 26ページ)
「ここ半世紀の心の哲学の大きな特徴は、自然科学の発展を受けて、物的一元論を目指す試みが支配的となったことである。この傾向は特に英語圏の哲学において顕著であり、心身問題は主として、自然科学の描く物理的世界像のうちにいかにして心を位置づけることができるか、という形で問われるようになった。」(参考前掲 『岩波 哲学・思想事典』「心の哲学」の項、519Lページ)
英米の論理実証主義と同時代の心理学は行動主義であった。それは、非科学的な論証の排除を目的としていた。そして、それはまた、行動傾向を指示する語彙を優先して、心的なものの言及を制限しようとする心理学上の方法論であった。行動主義が哲学へ影響し、心身問題や他者の心の哲学問題の無意味性を主張、戦後、クワイン(1908-2000)やライル(1900−1976)の著作に影響を与えた。行動主義の影響は1950年代に終わった。その理由は「行動主義」者の方法の厳格性にあった。それはまた科学的に不毛であると考えた。批判は言語学者のチョムスキー(1928-)によるもので、彼は生成変形文法の言語学を創始した。これは反行動主義的心理学の認知心理学、ひいては認知科学の誕生をもたらした。(参考前掲 『21世紀の哲学』 大沢秀介「心の哲学」 26ページ)
「ここ半世紀の心の哲学の大きな特徴は、自然科学の発展を受けて、物的一元論を目指す試みが支配的となったことである。この傾向は特に英語圏の哲学において顕著であり、心身問題は主として、自然科学の描く物理的世界像のうちにいかにして心を位置づけることができるか、という形で問われるようになった。」(参考前掲 『岩波 哲学・思想事典』「心の哲学」の項、519Lページ)
4. 行動主義
ギルバート・ライル(1900−1976)は、物的一元論の流れの口火を切った主著『心の概念』1949において、心的状態は心の中で生じる出来事ではなく、行動への傾向性にほかならないと主張した。彼はデカルトの神話、すなわち「私は考える精神であり、私の身体は広がりを持つ物体である。」との心身二元論を「機械の中の幽霊」として、心と身体の二重性は根本的なカテゴリー・ミステイクであるとした。それは、デカルトが「人間には心(精神)がある」と語ることも、「人間には身体がある」と語ることも適切であるが、心と身体とを対等に並べて語ることはその両者が本来同じタイプのものではないので適切ではないとした。(参考『岩波 哲学・思想事典』「心の概念」の項 518Rページ)
しかし、行為の概念を用いて心の概念を分析しても、行為の概念そのものに心的要素が入り、心的概念に痛みの概念が入り哲学的な分析とはならず、次の心脳同一説や機能主義に移ることになった。
ギルバート・ライル(1900−1976)は、物的一元論の流れの口火を切った主著『心の概念』1949において、心的状態は心の中で生じる出来事ではなく、行動への傾向性にほかならないと主張した。彼はデカルトの神話、すなわち「私は考える精神であり、私の身体は広がりを持つ物体である。」との心身二元論を「機械の中の幽霊」として、心と身体の二重性は根本的なカテゴリー・ミステイクであるとした。それは、デカルトが「人間には心(精神)がある」と語ることも、「人間には身体がある」と語ることも適切であるが、心と身体とを対等に並べて語ることはその両者が本来同じタイプのものではないので適切ではないとした。(参考『岩波 哲学・思想事典』「心の概念」の項 518Rページ)
しかし、行為の概念を用いて心の概念を分析しても、行為の概念そのものに心的要素が入り、心的概念に痛みの概念が入り哲学的な分析とはならず、次の心脳同一説や機能主義に移ることになった。
5.心脳同一説
1950年代に入ると、行動主義に代わって、J.C.C.スマート(1920−)等による、心脳同一説が提唱された。この説は心的状態を脳状態と同一とみるもので、次のような特徴を持っている。(a)物理学的な原子・分子・電磁場などを究極的な実在としたこと。(b)心的事象を刺激と反応の関数として捉える、行動主義から出発していること。(c)20世紀中葉の大脳生理学の興隆を背景とし心的事象と同一視すべき身体的過程を大脳過程に局限したこと。(d)論理実証主義、分析哲学の伝統に立ち、心的事象と大脳過程の関係をつとめて言語どうしの関係として捉えたことである。(参考 前掲『岩波 哲学・思想事典』「心脳同一説」の項 836Rページ19)
この心脳同一説についてスマートは、「明けの明星と宵の明星とは同一の星(金星)を指している」というフレーゲ(1848-1925)の例えを引いて説明した。彼は「感覚言明が『何ものか』を報告しているとすれば、その『何ものか』は事実上脳過程である」と述べて、これを心脳同一説の基本テーゼとした。(参考『科学哲学=現代哲学の転回』 坂本百大「科学的人間像」73ページ)
「心脳同一説には、二つの立場がある。その一つは、心脳同一性は心的状態と脳神経状態の双方が持ちうるすべての属性に及ぶと考える<タイプ同一説>であり、もう一つは単にそれらの属性を持つ出来事のレベルでの同一性しか認めない<トークン同一説>である。タイプとトークンという言葉遣いはアメリカの哲学者パース(1839-1914)に由来するが、要するに時空の一部分を区切る<出来事>を基本的存在者として、その集合を<種>と認めた場合、その<種>がタイプであり、その種に属する<出来事>がトークンである。たとえば、100円という金銭単位はタイプであり、100円硬貨はそのトークンである。」(参考『21世紀の哲学』大沢秀介「心の哲学」29ページ)
1950年代に入ると、行動主義に代わって、J.C.C.スマート(1920−)等による、心脳同一説が提唱された。この説は心的状態を脳状態と同一とみるもので、次のような特徴を持っている。(a)物理学的な原子・分子・電磁場などを究極的な実在としたこと。(b)心的事象を刺激と反応の関数として捉える、行動主義から出発していること。(c)20世紀中葉の大脳生理学の興隆を背景とし心的事象と同一視すべき身体的過程を大脳過程に局限したこと。(d)論理実証主義、分析哲学の伝統に立ち、心的事象と大脳過程の関係をつとめて言語どうしの関係として捉えたことである。(参考 前掲『岩波 哲学・思想事典』「心脳同一説」の項 836Rページ19)
この心脳同一説についてスマートは、「明けの明星と宵の明星とは同一の星(金星)を指している」というフレーゲ(1848-1925)の例えを引いて説明した。彼は「感覚言明が『何ものか』を報告しているとすれば、その『何ものか』は事実上脳過程である」と述べて、これを心脳同一説の基本テーゼとした。(参考『科学哲学=現代哲学の転回』 坂本百大「科学的人間像」73ページ)
「心脳同一説には、二つの立場がある。その一つは、心脳同一性は心的状態と脳神経状態の双方が持ちうるすべての属性に及ぶと考える<タイプ同一説>であり、もう一つは単にそれらの属性を持つ出来事のレベルでの同一性しか認めない<トークン同一説>である。タイプとトークンという言葉遣いはアメリカの哲学者パース(1839-1914)に由来するが、要するに時空の一部分を区切る<出来事>を基本的存在者として、その集合を<種>と認めた場合、その<種>がタイプであり、その種に属する<出来事>がトークンである。たとえば、100円という金銭単位はタイプであり、100円硬貨はそのトークンである。」(参考『21世紀の哲学』大沢秀介「心の哲学」29ページ)
6. 非法則的一元論、トークン同一説
D.デイヴィドソン(1917−)による非法則論的一元論は、存在論のテーゼで、「信念や知覚や行為といった心理的(志向的)現象は厳格な法則的説明を受け付けないという考えと、宇宙に存在するものは最終的には物質的なものだけだという考えを同時に主張しようとするとき、この立場が出てくる。それによれば、心的なものと物的なものとは同一だが、その同一なものの心的な捉え方は非法則的である」とした(『21世紀の哲学』 大沢秀介「非法則的一元論」の項 1326Rページ)。さらに、「行動の理由として帰属させられる心的状態はその行動の原因でもあるという考えから、心的状態を行動の原因となる実在的な出来事とみなし、脳状態による心的状態の裏打ちを積極的に認める」ものであった。
1960年代になると、心と脳の関係をコンピュータにおけるプログラムとハードウェアの関係と類比的に捉え、心的状態をその機能によって定義しようとする機能主義が唱えられるようになった。
D.デイヴィドソン(1917−)による非法則論的一元論は、存在論のテーゼで、「信念や知覚や行為といった心理的(志向的)現象は厳格な法則的説明を受け付けないという考えと、宇宙に存在するものは最終的には物質的なものだけだという考えを同時に主張しようとするとき、この立場が出てくる。それによれば、心的なものと物的なものとは同一だが、その同一なものの心的な捉え方は非法則的である」とした(『21世紀の哲学』 大沢秀介「非法則的一元論」の項 1326Rページ)。さらに、「行動の理由として帰属させられる心的状態はその行動の原因でもあるという考えから、心的状態を行動の原因となる実在的な出来事とみなし、脳状態による心的状態の裏打ちを積極的に認める」ものであった。
1960年代になると、心と脳の関係をコンピュータにおけるプログラムとハードウェアの関係と類比的に捉え、心的状態をその機能によって定義しようとする機能主義が唱えられるようになった。
7. 機能主義 ファンクショナリズム
機能主義はヒラリー・パトナム(1926-)によって初めて提唱された。認知科学の領域における心的な状態を、それを担う脳の物理的な状態の機能によって定義する立場である。彼は、これを同一説に代わるものとして、心的状態をチューリング・マシンの状態になぞらえた。これは、A・チューリング(1912-1954)が1936年に考案した仮想計算機で、これによってアルゴリズムに厳密な数学的定義を与えることができる。
「機能主義によれば、心的状態は他の心的諸状態や知覚入力、行動出力とともに複雑な因果連関を構成しており、この因果的機能を果たしている。このような機能によって心的状態を定義すれば、心的状態はそれの機能を担うさまざまなタイプの物的状態によって実現可能となる。機能主義では、この多重実現可能性により、人造繊維を移植された人にも痛みが認められ、またさらにわれわれ人間とはまったく異なる素材から成るロボットのような存在者にも心が認められる可能性が出てくる。」(『哲学・思想事典』「機能主義」の項、319Rページ)
機能主義はヒラリー・パトナム(1926-)によって初めて提唱された。認知科学の領域における心的な状態を、それを担う脳の物理的な状態の機能によって定義する立場である。彼は、これを同一説に代わるものとして、心的状態をチューリング・マシンの状態になぞらえた。これは、A・チューリング(1912-1954)が1936年に考案した仮想計算機で、これによってアルゴリズムに厳密な数学的定義を与えることができる。
「機能主義によれば、心的状態は他の心的諸状態や知覚入力、行動出力とともに複雑な因果連関を構成しており、この因果的機能を果たしている。このような機能によって心的状態を定義すれば、心的状態はそれの機能を担うさまざまなタイプの物的状態によって実現可能となる。機能主義では、この多重実現可能性により、人造繊維を移植された人にも痛みが認められ、またさらにわれわれ人間とはまったく異なる素材から成るロボットのような存在者にも心が認められる可能性が出てくる。」(『哲学・思想事典』「機能主義」の項、319Rページ)
8. 計算主義 コンピューティショナリズム(または古典的計算主義)
計算主義とは、「認知(認識)は一種の計算にほかならない、とする認知科学、人工知能(AI)研究における主流的発想」である。これによると、「知識を要素とその組み合わせからなる記号で表現し、それらを操作するアルゴリズムを定義する、という手法をとることから、「記号計算主義」とも呼ばれる。最終的には、万能チューリング・マシンに還元されるような計算として知識を考える立場とも言える。フレーゲ(前述)、ヒルベルト(1862-1943)、チューリング(前述)、フォン・ノイマン(1903-1957)らによって、今日の計算主義は確立した。1980年代における記号計算主義の行き詰まりに対して、コネクショニズムにおける概念の分散表現など、あらたな手法が模索されるようになってきた。」(『哲学・思想事典』「計算主義」の項、406Rページ)
計算主義とは、「認知(認識)は一種の計算にほかならない、とする認知科学、人工知能(AI)研究における主流的発想」である。これによると、「知識を要素とその組み合わせからなる記号で表現し、それらを操作するアルゴリズムを定義する、という手法をとることから、「記号計算主義」とも呼ばれる。最終的には、万能チューリング・マシンに還元されるような計算として知識を考える立場とも言える。フレーゲ(前述)、ヒルベルト(1862-1943)、チューリング(前述)、フォン・ノイマン(1903-1957)らによって、今日の計算主義は確立した。1980年代における記号計算主義の行き詰まりに対して、コネクショニズムにおける概念の分散表現など、あらたな手法が模索されるようになってきた。」(『哲学・思想事典』「計算主義」の項、406Rページ)
9. コネクショニズム
「人工知能(AI)研究の分野において、記号計算主義と並ぶ立場の一つ。神経回路網の基本構造にヒントを得、単純なユニットのネットワーク的結合によって、認知システムをモデル化しようとする試み」である。ところで、人間の脳は膨大なニューロン(神経細胞)が、巨大なネットワークを織りなしている。ニューロンのこのような脳のニューラルネットワークを参考にして考案された認知モデルがコネクショニズムである。
最近のコネクショニズムの脳モデルによると、多数のシナプス(神経伝達物質を詰めた小袋:シナプス小胞)が示すその結合強度の全体的配置のうちに膨大な数の知識が蓄えられており、そのよう知識を個別に脳の異なる状態に対応させることはできない。(『哲学・思想事典』「コネクショニズム」の項、540Rページ)
「人工知能(AI)研究の分野において、記号計算主義と並ぶ立場の一つ。神経回路網の基本構造にヒントを得、単純なユニットのネットワーク的結合によって、認知システムをモデル化しようとする試み」である。ところで、人間の脳は膨大なニューロン(神経細胞)が、巨大なネットワークを織りなしている。ニューロンのこのような脳のニューラルネットワークを参考にして考案された認知モデルがコネクショニズムである。
最近のコネクショニズムの脳モデルによると、多数のシナプス(神経伝達物質を詰めた小袋:シナプス小胞)が示すその結合強度の全体的配置のうちに膨大な数の知識が蓄えられており、そのよう知識を個別に脳の異なる状態に対応させることはできない。(『哲学・思想事典』「コネクショニズム」の項、540Rページ)
10. 意識に関する研究――特に脳科学
現代は、脳科学の進歩により、物理学的な手法が高度に開発されているので、「磁気刺激実験で意識に迫れるか」などの測定などの結果が報じられている。「脳の研究者たちは、昔ペンフィールド(1891-1976)がやったように、いろんな人の脳を開いて、自由にいろいろな部位を刺激して、いかなる意識変化が起きたかを聞けたら、どんなに脳と意識の研究が進むだろうと考えたものでしたが、磁気刺激によって、脳を開かずに類似したことができるようになったわけです。脳の研究は、高次機能といっても、これなど、知覚、記憶、言語といった領域に初歩的にしか迫ることができませんでしたが、今後はこの武器をうまく使って、感情、目的意識、人格といった、より複雑で高次の機能に迫っていくことがわれわれの夢です」(立花 隆 『脳を極める――脳研究最前線』 朝日新聞社 1996年 杉下守弘「磁気刺激実験で意識に迫れるか」 163ページ)。
今や、意識の研究は心理学だけの課題ではなくなったといえる。
以上、20世紀後半の「心の哲学」の歴史のハイライトを眺望した。これは、留まることなく、ますます新しい研究成果からの提言がなされている。
なお、「心の哲学」の本格的な手ほどきが頂ければありがたい。さらに機会があれば、「意識について」書きたいと思う。
参考文献
1.信原幸弘著 『心の現代哲学』 勁草書房 1999年6月
2.カント著、三井善正訳 『人間学・教育学』玉川大学出版部1986年5月
3.廣松渉他編 『岩波 哲学・思想事典』 岩波書店 1998年3月
4.笠松孝一・和田和行編 『21世紀の哲学』 八千代出版社 2000年4月
5.坂本百大、野本和幸編著『科学哲学=現代哲学の転回』北樹出版2002年5月
6.山本光雄訳 『アリストテレス全集6、霊魂論』 岩波書店 1968年10月
7.『新共同訳聖書』日本聖書協会1987年
8.エティエンヌ・ジルソンとフィロテウス・ベーナー著、服部英次郎・藤本雄三訳『アウグスティヌスとトマス・アクィナス』みすず書房 1998年6月(新装1版)
9.乾 孝・中川作一・亀谷純雄共著 『心理学』博文堂1989年2月
10.立花 隆 『脳を極める――脳研究最前線』 朝日新聞社 1996年 杉下守弘「磁気刺激実験で意識に迫れるか」
11.宮城音弥編 『岩波小辞典 心理学』岩波書店 1956年9月
12.デイヴィット・J・チャーマーズ著、林一訳 『意識する心』白揚社 2001年12月
13.大江精一『科学哲学』 日本大学通信教育部教科書
14.野田又夫著 『デカルト』 岩波新書
15.デカルト著 『方法序説(第4部)』中央公論社
16.P・フルキエ著、中村雄二郎他訳、『哲学講義1,2』ちくま書房
17.河合隼雄著 『宗教と科学の接点』 岩波書店 1986年5月
18.井筒俊彦 『意識と本質―精神的東洋を求めて』 岩波書店 1983年1月
現代は、脳科学の進歩により、物理学的な手法が高度に開発されているので、「磁気刺激実験で意識に迫れるか」などの測定などの結果が報じられている。「脳の研究者たちは、昔ペンフィールド(1891-1976)がやったように、いろんな人の脳を開いて、自由にいろいろな部位を刺激して、いかなる意識変化が起きたかを聞けたら、どんなに脳と意識の研究が進むだろうと考えたものでしたが、磁気刺激によって、脳を開かずに類似したことができるようになったわけです。脳の研究は、高次機能といっても、これなど、知覚、記憶、言語といった領域に初歩的にしか迫ることができませんでしたが、今後はこの武器をうまく使って、感情、目的意識、人格といった、より複雑で高次の機能に迫っていくことがわれわれの夢です」(立花 隆 『脳を極める――脳研究最前線』 朝日新聞社 1996年 杉下守弘「磁気刺激実験で意識に迫れるか」 163ページ)。
今や、意識の研究は心理学だけの課題ではなくなったといえる。
以上、20世紀後半の「心の哲学」の歴史のハイライトを眺望した。これは、留まることなく、ますます新しい研究成果からの提言がなされている。
なお、「心の哲学」の本格的な手ほどきが頂ければありがたい。さらに機会があれば、「意識について」書きたいと思う。
参考文献
1.信原幸弘著 『心の現代哲学』 勁草書房 1999年6月
2.カント著、三井善正訳 『人間学・教育学』玉川大学出版部1986年5月
3.廣松渉他編 『岩波 哲学・思想事典』 岩波書店 1998年3月
4.笠松孝一・和田和行編 『21世紀の哲学』 八千代出版社 2000年4月
5.坂本百大、野本和幸編著『科学哲学=現代哲学の転回』北樹出版2002年5月
6.山本光雄訳 『アリストテレス全集6、霊魂論』 岩波書店 1968年10月
7.『新共同訳聖書』日本聖書協会1987年
8.エティエンヌ・ジルソンとフィロテウス・ベーナー著、服部英次郎・藤本雄三訳『アウグスティヌスとトマス・アクィナス』みすず書房 1998年6月(新装1版)
9.乾 孝・中川作一・亀谷純雄共著 『心理学』博文堂1989年2月
10.立花 隆 『脳を極める――脳研究最前線』 朝日新聞社 1996年 杉下守弘「磁気刺激実験で意識に迫れるか」
11.宮城音弥編 『岩波小辞典 心理学』岩波書店 1956年9月
12.デイヴィット・J・チャーマーズ著、林一訳 『意識する心』白揚社 2001年12月
13.大江精一『科学哲学』 日本大学通信教育部教科書
14.野田又夫著 『デカルト』 岩波新書
15.デカルト著 『方法序説(第4部)』中央公論社
16.P・フルキエ著、中村雄二郎他訳、『哲学講義1,2』ちくま書房
17.河合隼雄著 『宗教と科学の接点』 岩波書店 1986年5月
18.井筒俊彦 『意識と本質―精神的東洋を求めて』 岩波書店 1983年1月
「心の哲学」に於ける主に心身問題(及び心脳問題)のに絞った哲学史的な解説、ご苦労様でした。老婆心ながら、それに対するコメントを付け加えさせていただきます。
ご存じの様に「心の哲学」は、心についての存在論的な問いである心身問題(及び心脳問題)の分野が中心になっているとは言え、その他にも心の哲学の分野があります。心についての認識論(知識論)的な問いとしては、志向性(命題的態度)とその表象の問題や、意識(の性質と機能)の問題、人格(自我)としての自己同一性及び他我についての知識の問題と言った各分野があります。心身問題(心脳問題)としての存在論的な問いとこれらの認識論(知識論)的な問いとはその内容を異にしますが、勿論のこと両者は無関係でなく相互に関連します。それは、心を持つ人格の実践的側面としての(行為論に関係する)行為者の問題と言えるものかも知れません。そして更に、認知科学等の「心の科学」をそこでの経験的究明に即してそれを哲学的に基礎づけようと試みるところの認知哲学と称される分野もあります。
ところで、心とは何かと言う問いは(認知)心理学の問いでもあります。「心の哲学」が(認知)心理学の問いと区別されるのは、そのアプローチの仕方の違いであり、それらが取り扱う問いの内容によってではありません。哲学の問いは科学の用いる概念や方法について論じるものであって、それは経験的探究に裏打ちされているとは言え、それ自体は経験的探究ではなく、科学的説明に用いられる諸概念を分析することです。当然ながら、「心の哲学」は思考、意志、意識、信念、感覚等々の心的現象を表す諸概念の分析を通して、心とは何かを明らかにしようとするものであります。その意味では「心の哲学」は「心理学の哲学」とは同じではないと言えます。しかしながら、心的現象の概念を分析するには、それらについての(認知)心理学等の経験的知識が必要で、分析対象としての概念が如何なる事実についての説明であるかを知ることなしに、それら概念を分析する事はできない。事実「心の哲学」は、認知科学の発展と共に形成されてきた。したがって、「心の哲学」は、「心理学の哲学」や「心の科学」との混同を注意深く避けつつも、それらについて強い関心を持ち続けなければ言えます。
ご存じの様に「心の哲学」は、心についての存在論的な問いである心身問題(及び心脳問題)の分野が中心になっているとは言え、その他にも心の哲学の分野があります。心についての認識論(知識論)的な問いとしては、志向性(命題的態度)とその表象の問題や、意識(の性質と機能)の問題、人格(自我)としての自己同一性及び他我についての知識の問題と言った各分野があります。心身問題(心脳問題)としての存在論的な問いとこれらの認識論(知識論)的な問いとはその内容を異にしますが、勿論のこと両者は無関係でなく相互に関連します。それは、心を持つ人格の実践的側面としての(行為論に関係する)行為者の問題と言えるものかも知れません。そして更に、認知科学等の「心の科学」をそこでの経験的究明に即してそれを哲学的に基礎づけようと試みるところの認知哲学と称される分野もあります。
ところで、心とは何かと言う問いは(認知)心理学の問いでもあります。「心の哲学」が(認知)心理学の問いと区別されるのは、そのアプローチの仕方の違いであり、それらが取り扱う問いの内容によってではありません。哲学の問いは科学の用いる概念や方法について論じるものであって、それは経験的探究に裏打ちされているとは言え、それ自体は経験的探究ではなく、科学的説明に用いられる諸概念を分析することです。当然ながら、「心の哲学」は思考、意志、意識、信念、感覚等々の心的現象を表す諸概念の分析を通して、心とは何かを明らかにしようとするものであります。その意味では「心の哲学」は「心理学の哲学」とは同じではないと言えます。しかしながら、心的現象の概念を分析するには、それらについての(認知)心理学等の経験的知識が必要で、分析対象としての概念が如何なる事実についての説明であるかを知ることなしに、それら概念を分析する事はできない。事実「心の哲学」は、認知科学の発展と共に形成されてきた。したがって、「心の哲学」は、「心理学の哲学」や「心の科学」との混同を注意深く避けつつも、それらについて強い関心を持ち続けなければ言えます。
はじめまして。。。
専門分野とはかけ離れているものの、ある事情から「情の哲学」なるものってないのか?という疑問から、「こころ」というものを考えてきました。
チャマーズは多世界解釈に批判的なので(というか、受け入れがたいと表明しているので)個人的に好きではないです(笑)。
「こころ」というものは、
1.機能としての核は自己認識(自己参照)系があり、
2.認識側からみると、認識対象としては、(周囲との関連性を完全には断ち切ることができないので)自身を含む全体となるために、
3.存在として「全体」にならざるをえないと思っております。
2’.存在側からみると、(動的に変容するという境界の曖昧性故に)全体から切り離せない部分としてあり、
3’.認識しようとすれば、仮想点(ないし、各機能レベル)にまで退縮してしまうように感じられるものだと思っています。
ようするに、認識側からと存在側からの交錯する「あたり」がこころとして漠然と捉えられているのだろうと思っています。
以上は、脳内部に「こころ」を閉じこめようとしても、どうしても生じる問題になろうかと思っています。
例えば、「○○に感動した」といったとき、「感動した」という主体を持ってして「こころ」と言おうとするならば、「○○に」という対象との間で切断が生じますが、脳内では「○○に」という対象のイメージ(像)が存在する訳であり、「感動した」という部分を切り出そうとしたとたん、脳内のこころの分断を生み出すわけです。
。。。といったことなどを、稚拙のブログで考え続けています。
専門分野とはかけ離れているものの、ある事情から「情の哲学」なるものってないのか?という疑問から、「こころ」というものを考えてきました。
チャマーズは多世界解釈に批判的なので(というか、受け入れがたいと表明しているので)個人的に好きではないです(笑)。
「こころ」というものは、
1.機能としての核は自己認識(自己参照)系があり、
2.認識側からみると、認識対象としては、(周囲との関連性を完全には断ち切ることができないので)自身を含む全体となるために、
3.存在として「全体」にならざるをえないと思っております。
2’.存在側からみると、(動的に変容するという境界の曖昧性故に)全体から切り離せない部分としてあり、
3’.認識しようとすれば、仮想点(ないし、各機能レベル)にまで退縮してしまうように感じられるものだと思っています。
ようするに、認識側からと存在側からの交錯する「あたり」がこころとして漠然と捉えられているのだろうと思っています。
以上は、脳内部に「こころ」を閉じこめようとしても、どうしても生じる問題になろうかと思っています。
例えば、「○○に感動した」といったとき、「感動した」という主体を持ってして「こころ」と言おうとするならば、「○○に」という対象との間で切断が生じますが、脳内では「○○に」という対象のイメージ(像)が存在する訳であり、「感動した」という部分を切り出そうとしたとたん、脳内のこころの分断を生み出すわけです。
。。。といったことなどを、稚拙のブログで考え続けています。
きすぎじねん さんへ
「心の哲」(あるいは「情の哲学」)ではないのですが、脳科学の分野でSomatic Marker hypothesisを唱えているアントニオ・R・ダマジオの著作「生存する脳 心と脳と身体の神秘」(講談社)、「無意識の脳 自己意識の脳 身体と情動と感情の神秘」(講談社)、「」感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ」(ダイヤモンド社)が参考になるのでは?
それに、意外と思われるかもしれませんが、松本元編集「情と意の脳科学―人とは何か」(培風館)、ジョセフ・ルドゥー著「エモーショナル・ブレイン 情動の脳科学」(東大出版会)や菅野重樹・尾形哲也「"情"が作る真のコミニケーション」(日経サイエンス2004年1月号掲載)、土井利忠編集「脳・身体性・ロボット インテリジェンス・ダイナミクス」(シュプリンガー・フェアラーク東京)等々に見られる様に、情動(及び感情)ならびに身体性については、脳神経科学にとどまらずロボット工学にても、かなり研究されています。
「心の哲」(あるいは「情の哲学」)ではないのですが、脳科学の分野でSomatic Marker hypothesisを唱えているアントニオ・R・ダマジオの著作「生存する脳 心と脳と身体の神秘」(講談社)、「無意識の脳 自己意識の脳 身体と情動と感情の神秘」(講談社)、「」感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ」(ダイヤモンド社)が参考になるのでは?
それに、意外と思われるかもしれませんが、松本元編集「情と意の脳科学―人とは何か」(培風館)、ジョセフ・ルドゥー著「エモーショナル・ブレイン 情動の脳科学」(東大出版会)や菅野重樹・尾形哲也「"情"が作る真のコミニケーション」(日経サイエンス2004年1月号掲載)、土井利忠編集「脳・身体性・ロボット インテリジェンス・ダイナミクス」(シュプリンガー・フェアラーク東京)等々に見られる様に、情動(及び感情)ならびに身体性については、脳神経科学にとどまらずロボット工学にても、かなり研究されています。
慧遠(EON)様
詳しい情報ありがとうございます。いろいろと読んでみたく存じます。
あと、ロボット工学に応用されている分には、特に「意外」とは思っていないといえば、語弊があるかもしれませんが、そのように思っております。
というのは、センサー関連を含めて、工学的に感覚系から判断系(たとえばニューラルネットなど)を使った情動のシミュレーションは、ネット上でもよく見かけますし、画像関連の並列処理プログラム開発に関わったこともありますので、情動が発生する機構や制御、および脳神経系との関連は現代科学の領域では「分かっている」といって過言ではない状況になっていると思っています。
問題なのは、「心・情」の機構が「分かった」ということと「心・情」の本質とは?という疑問とが完全に一致するとは思えない(という主観)が払拭できないところにあります。
心の科学としては問題ないでしょうが、哲学としては、この「主観」を外すことができないという問題が永遠に残るので、個人的な趣味(?)として、綴っていくことになろうかと思っています。
メモ:昨晩から、エキサイトブログへのアクセスができにくくなっているようです(新機能を搭載した直後のようで、サーバー側の問題?)
詳しい情報ありがとうございます。いろいろと読んでみたく存じます。
あと、ロボット工学に応用されている分には、特に「意外」とは思っていないといえば、語弊があるかもしれませんが、そのように思っております。
というのは、センサー関連を含めて、工学的に感覚系から判断系(たとえばニューラルネットなど)を使った情動のシミュレーションは、ネット上でもよく見かけますし、画像関連の並列処理プログラム開発に関わったこともありますので、情動が発生する機構や制御、および脳神経系との関連は現代科学の領域では「分かっている」といって過言ではない状況になっていると思っています。
問題なのは、「心・情」の機構が「分かった」ということと「心・情」の本質とは?という疑問とが完全に一致するとは思えない(という主観)が払拭できないところにあります。
心の科学としては問題ないでしょうが、哲学としては、この「主観」を外すことができないという問題が永遠に残るので、個人的な趣味(?)として、綴っていくことになろうかと思っています。
メモ:昨晩から、エキサイトブログへのアクセスができにくくなっているようです(新機能を搭載した直後のようで、サーバー側の問題?)
きすぎじねん さんへの問題提議とはかけ離れた「感情」理解かもしれませんが、戸田正直著『感情-人を動かしている適応プログラム (認知科学選書24)』東京大学出版会の「感情」分析を紹介します。
戸田正直氏はこの本で、「感情」というものを人間が野生時代に進化的に獲得した「状況対応行動」の選択システムとして理解し、すなわち感情には目的行動的な合理性が無いにしても、必ずしも非合理的とは言えない環境状況に適応的な対処行動を選択するプログラムとしてのシステム性(これを著者は「アージ・システムの野生合理性」と名付け、思考回路を通さずに個体を環境に適応させるために進化したとしています)をもつものと考えて、その「野生合理性を持つアージ・システム」に於いての「非自覚的な」結果合理性を持つ状況対応行動的な適応プログラムと考えています。--と。
そして以前に、私はあるところでこの本の紹介に関連して次のような感想を書いたことがあります。
感情というものがマックス・シェーラーが言うようにそれ自体で評価価値(ムード等)を伴う(対象への後行的関係づけの)志向的内容をもつ態度であり、そしてまたジェームズが示唆したように感情的な経験が感情的な状態を代表する身体の変更の単に経験であったとしても、その感情に関する文化規範の社会化として「感情の語彙」とそれを社会的場面と対応させる感情の使用規則とを習得することで人間は感情を社会的な規約と解釈とに基づいても経験すると言えるのであれば、そうした感情とは説明概念としての「本能」や「衝動」というレベルでの欲動の先行的充足目標に関しての快/不快体験と言う非融通的なもの(遺伝形態的クレオド)でなく、場合によっては経験学習的であったり持続待機的であったりすることもある柔軟な社会使用規則的かつ個人心理的な調節システム(局所チャート的行動クレオド)ではないかと、私は思っています。
よって、以上のような考え方から「感情」と「合理的知性」とは、*常に*必ずしも対立するとは限らないと思えますが、設定状況における行動の最適値と実際の情動反応の結果のズレが、合理性を欠くように見えるのは、戸田正直氏が言うように感情システムの進化が文明環境への環境変化に対応することが遅れてそのある部分が合理性を欠くことになってあたかも感情と言うものの多様な機能全体が非合理的と見なされているとしても、ある問題解決過程には知的推論だけでなく感情的な情意も少なからず働いており、その意味では合理的知性と感情とは常に排反的対立関係にあるのではなく往々にして共立的な関係にもあるのではと考えられます。
なを、進化論的感情階層仮説を神経生理学の立場から説明する、福田正治著『感情を知る 感情学入門』ナカニシヤ出版刊もありますが、存念ながら私はこの本をまだ読んではいません。また、進化心理学からの説明した菅原和孝著「感情の猿=人(エンジン)」弘文堂も同様にまだj読んでいません。
戸田正直氏はこの本で、「感情」というものを人間が野生時代に進化的に獲得した「状況対応行動」の選択システムとして理解し、すなわち感情には目的行動的な合理性が無いにしても、必ずしも非合理的とは言えない環境状況に適応的な対処行動を選択するプログラムとしてのシステム性(これを著者は「アージ・システムの野生合理性」と名付け、思考回路を通さずに個体を環境に適応させるために進化したとしています)をもつものと考えて、その「野生合理性を持つアージ・システム」に於いての「非自覚的な」結果合理性を持つ状況対応行動的な適応プログラムと考えています。--と。
そして以前に、私はあるところでこの本の紹介に関連して次のような感想を書いたことがあります。
感情というものがマックス・シェーラーが言うようにそれ自体で評価価値(ムード等)を伴う(対象への後行的関係づけの)志向的内容をもつ態度であり、そしてまたジェームズが示唆したように感情的な経験が感情的な状態を代表する身体の変更の単に経験であったとしても、その感情に関する文化規範の社会化として「感情の語彙」とそれを社会的場面と対応させる感情の使用規則とを習得することで人間は感情を社会的な規約と解釈とに基づいても経験すると言えるのであれば、そうした感情とは説明概念としての「本能」や「衝動」というレベルでの欲動の先行的充足目標に関しての快/不快体験と言う非融通的なもの(遺伝形態的クレオド)でなく、場合によっては経験学習的であったり持続待機的であったりすることもある柔軟な社会使用規則的かつ個人心理的な調節システム(局所チャート的行動クレオド)ではないかと、私は思っています。
よって、以上のような考え方から「感情」と「合理的知性」とは、*常に*必ずしも対立するとは限らないと思えますが、設定状況における行動の最適値と実際の情動反応の結果のズレが、合理性を欠くように見えるのは、戸田正直氏が言うように感情システムの進化が文明環境への環境変化に対応することが遅れてそのある部分が合理性を欠くことになってあたかも感情と言うものの多様な機能全体が非合理的と見なされているとしても、ある問題解決過程には知的推論だけでなく感情的な情意も少なからず働いており、その意味では合理的知性と感情とは常に排反的対立関係にあるのではなく往々にして共立的な関係にもあるのではと考えられます。
なを、進化論的感情階層仮説を神経生理学の立場から説明する、福田正治著『感情を知る 感情学入門』ナカニシヤ出版刊もありますが、存念ながら私はこの本をまだ読んではいません。また、進化心理学からの説明した菅原和孝著「感情の猿=人(エンジン)」弘文堂も同様にまだj読んでいません。
脳科学では、少なくとも、原始的な情動をつかさどる辺縁系と、知能の首座であるところの大脳皮質とがあり、さらに、大脳皮質内においても情動が生み出されるというのが通説となっているようです。
であれば、(脳が心を作り出すとしても、)知と情は「同じところから発生する」のではなく、「中心がずれた場所から発生する」としなければなりません。
また、脳の機能局在も定説に近く、そうであれば、(各機能毎に)「心の中心」が存在することを意味します。
ただし、通常「私の心」というとき、「私」という中心があり、(脳科学的には)統合する場所もあるわけです。
このように、(辺縁系を含めた)機能局在と「私という統合」(機能)とがあるということは、知と情とは「私という統合」に対して、時には対立し、時には矛盾し、時には協力しながら、すなわち相互に関連しあいながら「私の(心の)一部」を構成していることは、至極当然のことになろうかと思います。
したがって、脳の一部(特に「知」、あるいは「統合する領域」)を取り出して「これが私だ」なんていうのが馬鹿げているのは誰しも分かるわけです。
(それゆえ、人工「知」能≠「心」といえると思います。)
http://jinen.exblog.jp/1011324/
では、脳を取り出して「これが私だ」という問題はどうか?というのが水槽脳の問題として古くから考え続けられているのでしょう。
http://jinen.exblog.jp/3890034/
少なくとも、「私・心」の背後に「知・情(そして意など)の統合」があるのなら、そういった対象を「論理的に」(すなわち知的に)扱いうる範疇においては、「知」を越えることは出来ないわけです。更に言えば、「情」にしても、知的(論理的・記号論的)に扱いうるのは「知的認識されうる範疇」、すなわち、情を成立させている「もの」の1断面(私の造語では「知的切断面」)でしか過ぎないと思うわけです。
であれば、(脳が心を作り出すとしても、)知と情は「同じところから発生する」のではなく、「中心がずれた場所から発生する」としなければなりません。
また、脳の機能局在も定説に近く、そうであれば、(各機能毎に)「心の中心」が存在することを意味します。
ただし、通常「私の心」というとき、「私」という中心があり、(脳科学的には)統合する場所もあるわけです。
このように、(辺縁系を含めた)機能局在と「私という統合」(機能)とがあるということは、知と情とは「私という統合」に対して、時には対立し、時には矛盾し、時には協力しながら、すなわち相互に関連しあいながら「私の(心の)一部」を構成していることは、至極当然のことになろうかと思います。
したがって、脳の一部(特に「知」、あるいは「統合する領域」)を取り出して「これが私だ」なんていうのが馬鹿げているのは誰しも分かるわけです。
(それゆえ、人工「知」能≠「心」といえると思います。)
http://jinen.exblog.jp/1011324/
では、脳を取り出して「これが私だ」という問題はどうか?というのが水槽脳の問題として古くから考え続けられているのでしょう。
http://jinen.exblog.jp/3890034/
少なくとも、「私・心」の背後に「知・情(そして意など)の統合」があるのなら、そういった対象を「論理的に」(すなわち知的に)扱いうる範疇においては、「知」を越えることは出来ないわけです。更に言えば、「情」にしても、知的(論理的・記号論的)に扱いうるのは「知的認識されうる範疇」、すなわち、情を成立させている「もの」の1断面(私の造語では「知的切断面」)でしか過ぎないと思うわけです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
Philosophy of Mind(心の哲学) 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
Philosophy of Mind(心の哲学)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90059人
- 2位
- 酒好き
- 170694人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208291人