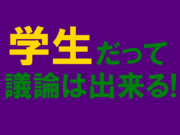地球温暖化という言葉は良く聞かれる言葉ですが、
具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。
そもそも地球温暖化とはどのような現象の指すのでしょうか。
大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスの増加が
温暖化に大きく関わっていると言われています。
しかし、実際にそれらの影響がどれくらい深刻なのでしょうか。
温暖化だと叫ぶだけでは意味が無く、
どれくらい深刻なのか、どのような対処法が考えられ、どれが効果的なのか。
また、
温暖化は深刻な問題だと言われていますが、
地球温暖化は英語では"Global Warming"となります。
Warmは温かいという意味で、
地球が暖かくなると聞いただけでは全く危機感が生じません。
この言葉は、ある意味その深刻さに目をつぶるために
このような呼び方をしているとも考えられます。
このトピックはかなり科学的な知識が関わっており、
なかなか一様な議論が出来ないとは思いますが、社会学的な
アプローチ(簡単に言えば文系的なアプローチと言った方が分かりやすいでしょうか。)
でも科学的なアプローチでも構いません。
具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。
そもそも地球温暖化とはどのような現象の指すのでしょうか。
大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスの増加が
温暖化に大きく関わっていると言われています。
しかし、実際にそれらの影響がどれくらい深刻なのでしょうか。
温暖化だと叫ぶだけでは意味が無く、
どれくらい深刻なのか、どのような対処法が考えられ、どれが効果的なのか。
また、
温暖化は深刻な問題だと言われていますが、
地球温暖化は英語では"Global Warming"となります。
Warmは温かいという意味で、
地球が暖かくなると聞いただけでは全く危機感が生じません。
この言葉は、ある意味その深刻さに目をつぶるために
このような呼び方をしているとも考えられます。
このトピックはかなり科学的な知識が関わっており、
なかなか一様な議論が出来ないとは思いますが、社会学的な
アプローチ(簡単に言えば文系的なアプローチと言った方が分かりやすいでしょうか。)
でも科学的なアプローチでも構いません。
|
|
|
|
コメント(12)
温暖化が無いって話は初耳なんで後ほど詳しく伺いたいですが、とりあえず今言われてるバイオエタノールについては無意味と思われます。
まず、海外からの輸入がガソリン以上のコストがかかると聞いてます。
材料である小麦やトウモロコシ栽培拡張の為に、広葉樹のみかん畑等を伐採したり新たに森を畑に作り変えてると・・小麦等が栽培され成長するのに二酸化炭素を吸収して+-0との触れ込みですが、栽培期間と広葉樹の落葉までの期間の違いがはっきり数値化されてないので信頼おけないとこですね。
個人的には(あくまで個人的ですが)、アメリカの押し付け貿易対象になってるのかと。私にはアメリカは本腰入れて温暖化対策してるようには見えず、ブラジルでは何年か前より普通車をアルコールのみで走らす者が多く、わざわざバイオエタノールを使ってると聞いたことがないからです。(情報不足かもしれませんが)
今の車社会の台数を減らすことは難しいので、アイドリングや発進時にガソリンを多く使うのなら首都高などをフリーウェイにして流れをスムーズにしてみたらどうなるのかと考えたりしています。。一番いいのは全てを電動自動車に変えるのが早いと思いますが、石油メーカーの反発も考えられ無理でしょう。
まず、海外からの輸入がガソリン以上のコストがかかると聞いてます。
材料である小麦やトウモロコシ栽培拡張の為に、広葉樹のみかん畑等を伐採したり新たに森を畑に作り変えてると・・小麦等が栽培され成長するのに二酸化炭素を吸収して+-0との触れ込みですが、栽培期間と広葉樹の落葉までの期間の違いがはっきり数値化されてないので信頼おけないとこですね。
個人的には(あくまで個人的ですが)、アメリカの押し付け貿易対象になってるのかと。私にはアメリカは本腰入れて温暖化対策してるようには見えず、ブラジルでは何年か前より普通車をアルコールのみで走らす者が多く、わざわざバイオエタノールを使ってると聞いたことがないからです。(情報不足かもしれませんが)
今の車社会の台数を減らすことは難しいので、アイドリングや発進時にガソリンを多く使うのなら首都高などをフリーウェイにして流れをスムーズにしてみたらどうなるのかと考えたりしています。。一番いいのは全てを電動自動車に変えるのが早いと思いますが、石油メーカーの反発も考えられ無理でしょう。
シズクさん
温暖化についての定義によっては
もしかすると温暖化という言葉自体が今の現象に適していないのかも
しれないですね。それについては僕もどういう意味で温暖化が無いのか
聞いてみたい気がします。
まず補足すると、バイオエタノールとは
サトウキビやトウモロコシなどの穀物からエタノールを作り出すことで、
それにより作り出されたエタノールが石油の代替エネルギーになるのでは
ないかと叫ばれている次代の燃料候補の一つです。
バイオエタノールはご指摘のようにアメリカ先導のもので、
二酸化炭素削減などの環境対策をまともに出来ないので、それでも環境問題に対して
積極的に行動しているとアピールするための、言わば隠れ蓑のようなものだと
思われます。
クーリエジャポンの6月号に取り上げられているエコノミストやインティペンデントの
バイオエタノールに関する議論の大まかな部分をピックアップしてみます。
エコノミストは結構環境問題でもそうなのですが、一般に叫ばれている意見に
「いや、ちょっと待って」という疑問を投げかけることが多いです。
論点はエタノール生産におけるマイナス面が強調されています。
まず第一にバイオエタノールを作るためにはサトウキビかトウモロコシが必要と
されるのですが、例えばエタノール生産の先進国であるブラジルではその生産の
ためにサトウキビ畑が増やし、その為に熱帯雨林が破壊され、二酸化炭素の排出量が
以前として高いのです。
またアメリカではバイオエタノールの産出に主にトウモロコシが使われ、
その為にトウモロコシの値段が高騰し、それを飼料としていた牛の値段も上がるという
悪循環に陥っているようです。またトウモロコシによるバイオエタノール生成には
それで得られるエネルギーと同量のエネルギーがかかるということが指摘されているようです。
つまりトウモロコシ由来のバイオエタノールは効率性が非常に低いのです。
またトウモロコシなどの「食糧」をエタノールにするというのは
今後深刻になるであろう食糧問題にも悪影響を及ぼすのではないのかということが
言われています。
まずは燃料をどうするかではなく、
消費燃料を減らすような政策あるいはライフスタイルの転換が求められています。
温暖化についての定義によっては
もしかすると温暖化という言葉自体が今の現象に適していないのかも
しれないですね。それについては僕もどういう意味で温暖化が無いのか
聞いてみたい気がします。
まず補足すると、バイオエタノールとは
サトウキビやトウモロコシなどの穀物からエタノールを作り出すことで、
それにより作り出されたエタノールが石油の代替エネルギーになるのでは
ないかと叫ばれている次代の燃料候補の一つです。
バイオエタノールはご指摘のようにアメリカ先導のもので、
二酸化炭素削減などの環境対策をまともに出来ないので、それでも環境問題に対して
積極的に行動しているとアピールするための、言わば隠れ蓑のようなものだと
思われます。
クーリエジャポンの6月号に取り上げられているエコノミストやインティペンデントの
バイオエタノールに関する議論の大まかな部分をピックアップしてみます。
エコノミストは結構環境問題でもそうなのですが、一般に叫ばれている意見に
「いや、ちょっと待って」という疑問を投げかけることが多いです。
論点はエタノール生産におけるマイナス面が強調されています。
まず第一にバイオエタノールを作るためにはサトウキビかトウモロコシが必要と
されるのですが、例えばエタノール生産の先進国であるブラジルではその生産の
ためにサトウキビ畑が増やし、その為に熱帯雨林が破壊され、二酸化炭素の排出量が
以前として高いのです。
またアメリカではバイオエタノールの産出に主にトウモロコシが使われ、
その為にトウモロコシの値段が高騰し、それを飼料としていた牛の値段も上がるという
悪循環に陥っているようです。またトウモロコシによるバイオエタノール生成には
それで得られるエネルギーと同量のエネルギーがかかるということが指摘されているようです。
つまりトウモロコシ由来のバイオエタノールは効率性が非常に低いのです。
またトウモロコシなどの「食糧」をエタノールにするというのは
今後深刻になるであろう食糧問題にも悪影響を及ぼすのではないのかということが
言われています。
まずは燃料をどうするかではなく、
消費燃料を減らすような政策あるいはライフスタイルの転換が求められています。
地球温暖化と言いますが、実際何処までが本当かわかりませんね。
ついこの前、ノーベル平和賞を受賞したアル・ゴアの"The Inconvenient Truth"という映画だって間違えだらけだったらしいじゃないですか。
それが理由でオスカーが起訴してますしね。
地球温暖化と言いますが、実際気温は前回の氷河期が終わった時点から上昇しているのでそういう意味では自然に起きていたのです。
実際、現在の気温の上昇が急になっただけでなのです。
ですから、地球温暖化という名前は間違っているのです。
たしかにwarmingと聞いて危機感は感じませんね。
地球温暖化の信憑性が疑われる理由はおそらく政治家たちが口にするからだと思います。
プロパガンダだと思われてしまうんでしょうね。
科学者たちだけが口にすれば、みんな信じているかもしれないってやつですよ。
実際悪影響があるかわからないものに対策を打ったり、政府にお金を使ってほしくないですね。
最悪の事態で海水の温度が上昇し、海流が変わり、その影響で北半球の気温が変わることです。
[The day after tomorrow]で起きる現象は科学的な根拠があるそうです。
しかしありえないという理由でフィクションですがね。
地球温暖化より化石燃料が尽きることによって生じるエネルギー不足の方が深刻な予感がしますがね。
そういう意味では地球温暖化の対策は一石二鳥ですね。
ついこの前、ノーベル平和賞を受賞したアル・ゴアの"The Inconvenient Truth"という映画だって間違えだらけだったらしいじゃないですか。
それが理由でオスカーが起訴してますしね。
地球温暖化と言いますが、実際気温は前回の氷河期が終わった時点から上昇しているのでそういう意味では自然に起きていたのです。
実際、現在の気温の上昇が急になっただけでなのです。
ですから、地球温暖化という名前は間違っているのです。
たしかにwarmingと聞いて危機感は感じませんね。
地球温暖化の信憑性が疑われる理由はおそらく政治家たちが口にするからだと思います。
プロパガンダだと思われてしまうんでしょうね。
科学者たちだけが口にすれば、みんな信じているかもしれないってやつですよ。
実際悪影響があるかわからないものに対策を打ったり、政府にお金を使ってほしくないですね。
最悪の事態で海水の温度が上昇し、海流が変わり、その影響で北半球の気温が変わることです。
[The day after tomorrow]で起きる現象は科学的な根拠があるそうです。
しかしありえないという理由でフィクションですがね。
地球温暖化より化石燃料が尽きることによって生じるエネルギー不足の方が深刻な予感がしますがね。
そういう意味では地球温暖化の対策は一石二鳥ですね。
「不都合な真実」は授業の一環で英語版のみを観たので、
そこまで詳しく内容は覚えていないのですが、アル・ゴア氏が使った
科学的なデータが間違っているというのは聞いたがありません。
批判の根拠があれば助かります。
しかし、たとえその科学的なデータが正しかったとしても、
そのデータの解釈の仕方で結論が変わると言うのは大いにあり得ると思います。
気温の変化については、映画の中では
大気中の二酸化炭素の上昇を過去の氷河期を含む推移で見て、
これまでの二酸化炭素量を上回っており、また、二酸化炭素の大気中量と
気温の変化に直接の関連性があると見て、このまま二酸化炭素量が上昇し続けると、
気温も過去に見ない上昇を見せるであろうと予測しているのです。
この議論の欠点は、二酸化炭素の大気中の量と気温の関係性が一対一で対応しているように
簡略化して捉えていることです。実際には大気のシステムはより複雑であり、
二酸化炭素量の上昇がそのままストレートに気温上昇に現れるとは言えないことです。
しかしT2 the Kさんが指摘されるような急激な上昇があるとすれば、
その上昇が何によってもたらされているかを分析する必要があると思います。
また、もしそのような(急激な)上昇が過去の気温の変化と一致している(波のパターンが一定)
のであれば、地球は温暖化しているのではなく、季節の変化による気温変化と同様の意味しか
持たなくなるとも考えられます。
確かにお二人が言っているように、
温暖化という言葉ではなく、
地球の環境の変化が何が原因で、どの程度のもので、どのような対策が求められているのか
を考えるのがより重要なのかもしれません。
また、二酸化炭素の排出は、地球のシステムで
問題なく吸収できる量に抑えられることが求められますが、
それ以前に、温暖化よりもまず最初に取り組むべき、プライオリティの高い
問題があるのかというところから議論をすべきでしょう。
ちなみにメタンガスという、二酸化炭素よりも更に温室効果の高い気体があり、
永久凍土や海底にあるそれらが大気中に放出されることが懸念されているという
議論があります。
そして、それに関連付けられて
気温上昇によりそれらの放出が増え、さらにそれが気温上昇をもたらすという
サイクル(正のフィードバック、あるいはpositive feedback)が起こると、
気温上昇に歯止めが効かなくなるという主張もされているようです。
メタンガスに関する記事として参考にリンクを張っておきます。
http://wiredvision.jp/archives/200405/2004052802.html
そこまで詳しく内容は覚えていないのですが、アル・ゴア氏が使った
科学的なデータが間違っているというのは聞いたがありません。
批判の根拠があれば助かります。
しかし、たとえその科学的なデータが正しかったとしても、
そのデータの解釈の仕方で結論が変わると言うのは大いにあり得ると思います。
気温の変化については、映画の中では
大気中の二酸化炭素の上昇を過去の氷河期を含む推移で見て、
これまでの二酸化炭素量を上回っており、また、二酸化炭素の大気中量と
気温の変化に直接の関連性があると見て、このまま二酸化炭素量が上昇し続けると、
気温も過去に見ない上昇を見せるであろうと予測しているのです。
この議論の欠点は、二酸化炭素の大気中の量と気温の関係性が一対一で対応しているように
簡略化して捉えていることです。実際には大気のシステムはより複雑であり、
二酸化炭素量の上昇がそのままストレートに気温上昇に現れるとは言えないことです。
しかしT2 the Kさんが指摘されるような急激な上昇があるとすれば、
その上昇が何によってもたらされているかを分析する必要があると思います。
また、もしそのような(急激な)上昇が過去の気温の変化と一致している(波のパターンが一定)
のであれば、地球は温暖化しているのではなく、季節の変化による気温変化と同様の意味しか
持たなくなるとも考えられます。
確かにお二人が言っているように、
温暖化という言葉ではなく、
地球の環境の変化が何が原因で、どの程度のもので、どのような対策が求められているのか
を考えるのがより重要なのかもしれません。
また、二酸化炭素の排出は、地球のシステムで
問題なく吸収できる量に抑えられることが求められますが、
それ以前に、温暖化よりもまず最初に取り組むべき、プライオリティの高い
問題があるのかというところから議論をすべきでしょう。
ちなみにメタンガスという、二酸化炭素よりも更に温室効果の高い気体があり、
永久凍土や海底にあるそれらが大気中に放出されることが懸念されているという
議論があります。
そして、それに関連付けられて
気温上昇によりそれらの放出が増え、さらにそれが気温上昇をもたらすという
サイクル(正のフィードバック、あるいはpositive feedback)が起こると、
気温上昇に歯止めが効かなくなるという主張もされているようです。
メタンガスに関する記事として参考にリンクを張っておきます。
http://wiredvision.jp/archives/200405/2004052802.html
みなさん、はじめまして、ぬりといいます。
まず、
◆温暖化があるかないかについて
多くの観測データが、この100年で0.8度ほど上昇している事を示していますが、それに反論する人も未だに多くいます。時代が進むにつれて、地球平均温度を計る為の温度計の設置箇所が都市化していっている為、ヒートアイランドの効果が大きいというもの。自然が沢山残っているところにいけばいくほど、温度が変化していない、または下がっているという地域が多く見つかっているからです。
地球全体を観測衛星を使って気温を計ることもなされていますが、一年の平均温度の変化が0.1度にも満たないし、一年の間、一日の間の温度変化は激しいので、衛星から高い精度で平均気温の推移を追いかけるのは難しいようです。
それでも、世界の気温はどうやら上がっているらしいという事は、かなり多くの科学者が認める所のようです。ヒートアイランドの問題も当然考慮して計られていますからね。
◆人為説について
温暖化という傾向自体が事実だと広く認められているとして、その原因が問題なわけですが、温暖化の科学的な論争はむしろこちらにウェイトがあります。
つまり、人間の活動によるCO2排出によって気温変化が起きているのか、それとも別の原因で温度が上がっているのか。因果関係が争われているわけです。IPCCの第4次報告書では、人為的な原因の可能性がかなり高いという結論なわけですが、今も太陽黒点説や、ミランコビッチサイクルだと主張している人など、多くの反対論者がいます。
IPCCの主張が正しいとしても、人為的に温暖化を止める事は不可能という事を言っている人もいます。この議論は、とてもここに書ききれませんので、機会があったらお話します。
◆不都合な真実について
話題になった、イギリスの法廷が指摘したアルゴアの9つの間違いについて。コピペです。
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/corporate_law/article2633838.ece
1.この映画の核となる主張には同意するが、近未来に海水面が上昇するというのは極端な主張である。
2.温暖化が原因で太平洋に浮かぶ孤島が沈んでいるという主張は証拠による裏付けがない。
3.「メキシコ湾流が停止し、それによって西欧が氷河期を迎える」と述べているが、この内容に対して科学者は同意していない。
4.「過去65万年の二酸化炭素と地球規模の気温の変化」を示すとするグラフの信憑性に疑いがある。
5.チャド湖の枯渇が温暖化によるものだとしているが、他の可能性の方が高い。
6.アフリカ最高峰のキリマンジャロの雪が後退しているのが温暖化によるものであるという主張の信憑性に疑いがある。
7.アメリカで起きたハリケーン・カトリーナが温暖化の影響によるものとの主張に疑いがある。
8.北極海の熊が温暖化が原因でおぼれ死んでいるという主張は事実ではない。
9.珊瑚礁の損傷の原因はもっと複雑であり、温暖化によるものという主張には疑いがある。
私も、極端な仮定の話が多いなと思っていました。危機感を煽るには、これくらいむちゃしないと効果が薄いんでしょうけど。
◆バイオ燃料について
エタノール生産は元々ブラジル主導であって、歴史も長いです。アメリカは別の意図があって、今年の年頭に目標値を掲げたので話題になったのだと思います。
バイオエタノールのエネルギー評価は大変難しい問題で、仮定によって大きく評価が変わってしまいますが、概ねガソリンよりも意味が無いというのは言い過ぎかと思います。CO2排出削減やエネルギー問題に対するインパクトはあまり無い、むしろ悪影響ということはありますが。
◆地球温暖化という言葉について
すでに、広く使われている言葉なので、適当であるか否かのここでの議論は不毛ではないでしょうか。中国をシナと呼ぶべきだと言っているようなものです。伝わる事が最も大切です。
☆
ええと、温暖化自体の是非について、ここで情報交換をしてもよいのですが、我々は科学者ではありませんし、未来予想は楽しいけれど不毛な一面もあります。
差し当たって迫ってくる、排出権取引について焦点をあててみてはいかがでしょうか。
これでけは避けられそうにありませんので。
まず、
◆温暖化があるかないかについて
多くの観測データが、この100年で0.8度ほど上昇している事を示していますが、それに反論する人も未だに多くいます。時代が進むにつれて、地球平均温度を計る為の温度計の設置箇所が都市化していっている為、ヒートアイランドの効果が大きいというもの。自然が沢山残っているところにいけばいくほど、温度が変化していない、または下がっているという地域が多く見つかっているからです。
地球全体を観測衛星を使って気温を計ることもなされていますが、一年の平均温度の変化が0.1度にも満たないし、一年の間、一日の間の温度変化は激しいので、衛星から高い精度で平均気温の推移を追いかけるのは難しいようです。
それでも、世界の気温はどうやら上がっているらしいという事は、かなり多くの科学者が認める所のようです。ヒートアイランドの問題も当然考慮して計られていますからね。
◆人為説について
温暖化という傾向自体が事実だと広く認められているとして、その原因が問題なわけですが、温暖化の科学的な論争はむしろこちらにウェイトがあります。
つまり、人間の活動によるCO2排出によって気温変化が起きているのか、それとも別の原因で温度が上がっているのか。因果関係が争われているわけです。IPCCの第4次報告書では、人為的な原因の可能性がかなり高いという結論なわけですが、今も太陽黒点説や、ミランコビッチサイクルだと主張している人など、多くの反対論者がいます。
IPCCの主張が正しいとしても、人為的に温暖化を止める事は不可能という事を言っている人もいます。この議論は、とてもここに書ききれませんので、機会があったらお話します。
◆不都合な真実について
話題になった、イギリスの法廷が指摘したアルゴアの9つの間違いについて。コピペです。
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/corporate_law/article2633838.ece
1.この映画の核となる主張には同意するが、近未来に海水面が上昇するというのは極端な主張である。
2.温暖化が原因で太平洋に浮かぶ孤島が沈んでいるという主張は証拠による裏付けがない。
3.「メキシコ湾流が停止し、それによって西欧が氷河期を迎える」と述べているが、この内容に対して科学者は同意していない。
4.「過去65万年の二酸化炭素と地球規模の気温の変化」を示すとするグラフの信憑性に疑いがある。
5.チャド湖の枯渇が温暖化によるものだとしているが、他の可能性の方が高い。
6.アフリカ最高峰のキリマンジャロの雪が後退しているのが温暖化によるものであるという主張の信憑性に疑いがある。
7.アメリカで起きたハリケーン・カトリーナが温暖化の影響によるものとの主張に疑いがある。
8.北極海の熊が温暖化が原因でおぼれ死んでいるという主張は事実ではない。
9.珊瑚礁の損傷の原因はもっと複雑であり、温暖化によるものという主張には疑いがある。
私も、極端な仮定の話が多いなと思っていました。危機感を煽るには、これくらいむちゃしないと効果が薄いんでしょうけど。
◆バイオ燃料について
エタノール生産は元々ブラジル主導であって、歴史も長いです。アメリカは別の意図があって、今年の年頭に目標値を掲げたので話題になったのだと思います。
バイオエタノールのエネルギー評価は大変難しい問題で、仮定によって大きく評価が変わってしまいますが、概ねガソリンよりも意味が無いというのは言い過ぎかと思います。CO2排出削減やエネルギー問題に対するインパクトはあまり無い、むしろ悪影響ということはありますが。
◆地球温暖化という言葉について
すでに、広く使われている言葉なので、適当であるか否かのここでの議論は不毛ではないでしょうか。中国をシナと呼ぶべきだと言っているようなものです。伝わる事が最も大切です。
☆
ええと、温暖化自体の是非について、ここで情報交換をしてもよいのですが、我々は科学者ではありませんし、未来予想は楽しいけれど不毛な一面もあります。
差し当たって迫ってくる、排出権取引について焦点をあててみてはいかがでしょうか。
これでけは避けられそうにありませんので。
ぬりさん
議論の整理ありがとうございます。
科学的なアプローチ、とても参考になりました。
温暖化の問題については、
みなさんも関心のあることだと思うので、
一度は触れてみる必要があると思いました。
実際に話し合ってみる中で、それぞれの問題に対する捉え方が
違っていたので、それを確認することが出来ただけでも有意義だったのでは
ないかと思っています。
また、温暖化の議論が政治的な面で少々先走っているというような
印象も受けました。しかし、科学的な面で捉えることも重要であるというのが
今回の教訓ですね。僕自身、哲学の授業の一環で「不都合な真実」を観たり
環境問題について考えたこともあって、科学的なアプローチが欠けていると
思いました。
排出権についてはまた別のトピックを使って話し合えたら面白いと思います。
今回の議論について、
みなさんはどう思われたでしょうか。
ちょっとした感想や疑問でも良いので書きこんでみてください。
どうぞよろしくお願いします。
議論の整理ありがとうございます。
科学的なアプローチ、とても参考になりました。
温暖化の問題については、
みなさんも関心のあることだと思うので、
一度は触れてみる必要があると思いました。
実際に話し合ってみる中で、それぞれの問題に対する捉え方が
違っていたので、それを確認することが出来ただけでも有意義だったのでは
ないかと思っています。
また、温暖化の議論が政治的な面で少々先走っているというような
印象も受けました。しかし、科学的な面で捉えることも重要であるというのが
今回の教訓ですね。僕自身、哲学の授業の一環で「不都合な真実」を観たり
環境問題について考えたこともあって、科学的なアプローチが欠けていると
思いました。
排出権についてはまた別のトピックを使って話し合えたら面白いと思います。
今回の議論について、
みなさんはどう思われたでしょうか。
ちょっとした感想や疑問でも良いので書きこんでみてください。
どうぞよろしくお願いします。
二酸化炭素と気温だけの一対一の関係で考えているのは、マスコミだけで科学者はそのようなことをしません。ただ結果を見てみると二酸化炭素の量を考えることが一番大きな影響があるという結論なのです。あと皆さんご存知かもしれませんが、地球上の温室効果ガスの99パーセントが水H2Oです。しかもCO2の100倍ぐらい強力です。僕もはじめは、地球温度上昇が、砂漠地域やツンドラ気候や極地であまり変化していないこと、気温が上昇するから二酸化炭素が上昇するのでは…ということから、懐疑していた時期もありましたが、よく勉強してみると僕の考えていたことの10倍以上IPCCの科学者は考えていました。
つまり、メタンガスやフロンガスや二酸化炭素だけでなくエアロゾルや反射率など僕たちの考えることはすべて考慮されてます。日経サイエンス(最近かな…)などを見てみたら分かりやすく書いてありましたよ。シュミレーションが正しくできないといえば確かにそうかもしれませんが、完全に将来予測をすることはあまり意味がないと僕は思っています。
ある程度大げさな部分はあるかもしれませんが、地球温暖化は事実だと思います。
ただGDPを成長しながら対応できるというのはかなり楽観的だと思います。というか50年後の技術革新を予想することは誰もできません。
あと政治的な要因が先走っているのは確かだと思います。過剰に市場に介入することは、旧ソ連のように技術革新で後れを取りかねません。日本の鉄鋼業界は本当に可愛そうです…
つまり、メタンガスやフロンガスや二酸化炭素だけでなくエアロゾルや反射率など僕たちの考えることはすべて考慮されてます。日経サイエンス(最近かな…)などを見てみたら分かりやすく書いてありましたよ。シュミレーションが正しくできないといえば確かにそうかもしれませんが、完全に将来予測をすることはあまり意味がないと僕は思っています。
ある程度大げさな部分はあるかもしれませんが、地球温暖化は事実だと思います。
ただGDPを成長しながら対応できるというのはかなり楽観的だと思います。というか50年後の技術革新を予想することは誰もできません。
あと政治的な要因が先走っているのは確かだと思います。過剰に市場に介入することは、旧ソ連のように技術革新で後れを取りかねません。日本の鉄鋼業界は本当に可愛そうです…
Jackさん
温暖化の問題は、おっしゃるように様々な「顔」がありますので、切り口をそろえてみたり、多角的な視野で捉えるだけでは、その本質に迫ることはできません。
いろいろな思惑の人たちが、違った視点で集まっているので、問題をややこしくしているんですね。
科学的なアプローチ・・・。(自分のコミュでも書いたのですが)たとえば、
http://www.inspiringgreenleadership.com/blog/aangel
↑
こういう視点。
つまり、ピークオイルと、ピークコール(石炭)によって、地球温暖化に対する取り組みは、自動的に達成されるかもしれない、ということ。次(第5次報告書)には盛り込まれる可能性が高いと書いてありますね。IPCCでは、経済成長が前提になっていますから。
画像は、IPCCの想定している40のシナリオと、そのどれよりも(一番理想的なケースよりも)CO2排出量が少なくなるピークオイルのシナリオ。カルフォルニア工科大学のRutledge教授による。
http://rutledge.caltech.edu/
レイさん
水の温室効果の大きさについては知らない人も多いですよね。でもIPCCは全ての懐疑的な批判に対する考察を包括的に行っています。あとは、モデルと仮定(政治的、経済的、鉱物的な意味で)の不確実性、シミュレーションの問題(逐次計算など)だけなのかもしれません。
温暖化の問題は、おっしゃるように様々な「顔」がありますので、切り口をそろえてみたり、多角的な視野で捉えるだけでは、その本質に迫ることはできません。
いろいろな思惑の人たちが、違った視点で集まっているので、問題をややこしくしているんですね。
科学的なアプローチ・・・。(自分のコミュでも書いたのですが)たとえば、
http://www.inspiringgreenleadership.com/blog/aangel
↑
こういう視点。
つまり、ピークオイルと、ピークコール(石炭)によって、地球温暖化に対する取り組みは、自動的に達成されるかもしれない、ということ。次(第5次報告書)には盛り込まれる可能性が高いと書いてありますね。IPCCでは、経済成長が前提になっていますから。
画像は、IPCCの想定している40のシナリオと、そのどれよりも(一番理想的なケースよりも)CO2排出量が少なくなるピークオイルのシナリオ。カルフォルニア工科大学のRutledge教授による。
http://rutledge.caltech.edu/
レイさん
水の温室効果の大きさについては知らない人も多いですよね。でもIPCCは全ての懐疑的な批判に対する考察を包括的に行っています。あとは、モデルと仮定(政治的、経済的、鉱物的な意味で)の不確実性、シミュレーションの問題(逐次計算など)だけなのかもしれません。
一応、メディアと環境問題として、面白かったのを。
池田信夫さんのブログより。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/f4ebd3172c222e69bc9916e4a87701e8
この方は科学者ではないのですが、言ってることは興味深いと思います。
また、温暖化を考えるための道筋として、
第一に、温暖化は進んでいるのか、
そしてもし進んでいるとして、その温暖化は人為的なものなのか、
その温暖化が人為的なもので有る無しに関わらず、人間が対処出来る問題なのか、
と言う風に考えてゆけると思います。
ここで最も重要な疑問にたどり着きます。
温暖化は深刻であるのかどうか
ということです。
温暖化は、最も一般の人々にアピールしやすく、
二酸化炭素の排出という、あまりどれか一つの産業に原因を求められない、
つまり排出を抑えるということを反対する利益団体が少ないというのが考えられるのかも
しれません。
また、この問題を大々的に人々に訴え危機感を与え、その問題に積極的に取り組もうとしているのは
なんといっても先進国です。そこには後進国の口を挟む立場は少なく、温暖化問題解決という
形で、後進国の産業への口出しが出来るというメリットもあるともいえるのではないでしょうか。
またぬりさんの言うように、
他の問題に対処することが、温暖化問題対策にもつながるということもあるでしょう。
例えば大気汚染や砂漠化に対する対策など。あるいは逆に、温暖化対策が
他の多くの問題を解決に導くことになるのかもしれません。これは推測になってしまいますが。
最初に紹介したブログの中では、IPCCの第四次レポートの温度上昇予想の幅が狭くなり、
実際には前回のレポートよりも深刻では無くなっていると言っています。
デンマークの環境保護主義者のロンボルグという方が
「The Skeptical Environmentalist」という本で一部の環境問題は、十分な科学的なデータ
によって論じられていないという主張をしています。
彼のコメントはこちらから見ることが出来ます。
http://commentisfree.guardian.co.uk/bjrn_lomborg/2007/02/climate_hysteria.html
英語ですので、一応ざっと要約すると、今回のIPCCによる第四次報告に関して、
前回の報告より事態は深刻でないとした上で、アル・ゴア氏は科学的だデータに十分に基づいた
主張を行っておらず、彼の主張の一部はこの報告により否定されたと言っています。
そしてメディアは、気候変動について、深刻な変化が実は起こらないというような報道は出来ず、
今回のレポートで、〜がこれこれ深刻になっていたという形でしか報道しようとしないという風に
指摘しています。
また、最後には他にもエイズや貧困国の栄養不足の解消など地球のために出来る他の、あるいは
より重要なことがあるのではないかという彼の持論を展開しています。
※IPCCとは、Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)
の略で、気候変動に関するレポートを数年おきに発表し(現在までに4回)、2007年には
アル・ゴア前副大統領と共に、ノーベル平和賞を受賞しています。
池田信夫さんのブログより。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/f4ebd3172c222e69bc9916e4a87701e8
この方は科学者ではないのですが、言ってることは興味深いと思います。
また、温暖化を考えるための道筋として、
第一に、温暖化は進んでいるのか、
そしてもし進んでいるとして、その温暖化は人為的なものなのか、
その温暖化が人為的なもので有る無しに関わらず、人間が対処出来る問題なのか、
と言う風に考えてゆけると思います。
ここで最も重要な疑問にたどり着きます。
温暖化は深刻であるのかどうか
ということです。
温暖化は、最も一般の人々にアピールしやすく、
二酸化炭素の排出という、あまりどれか一つの産業に原因を求められない、
つまり排出を抑えるということを反対する利益団体が少ないというのが考えられるのかも
しれません。
また、この問題を大々的に人々に訴え危機感を与え、その問題に積極的に取り組もうとしているのは
なんといっても先進国です。そこには後進国の口を挟む立場は少なく、温暖化問題解決という
形で、後進国の産業への口出しが出来るというメリットもあるともいえるのではないでしょうか。
またぬりさんの言うように、
他の問題に対処することが、温暖化問題対策にもつながるということもあるでしょう。
例えば大気汚染や砂漠化に対する対策など。あるいは逆に、温暖化対策が
他の多くの問題を解決に導くことになるのかもしれません。これは推測になってしまいますが。
最初に紹介したブログの中では、IPCCの第四次レポートの温度上昇予想の幅が狭くなり、
実際には前回のレポートよりも深刻では無くなっていると言っています。
デンマークの環境保護主義者のロンボルグという方が
「The Skeptical Environmentalist」という本で一部の環境問題は、十分な科学的なデータ
によって論じられていないという主張をしています。
彼のコメントはこちらから見ることが出来ます。
http://commentisfree.guardian.co.uk/bjrn_lomborg/2007/02/climate_hysteria.html
英語ですので、一応ざっと要約すると、今回のIPCCによる第四次報告に関して、
前回の報告より事態は深刻でないとした上で、アル・ゴア氏は科学的だデータに十分に基づいた
主張を行っておらず、彼の主張の一部はこの報告により否定されたと言っています。
そしてメディアは、気候変動について、深刻な変化が実は起こらないというような報道は出来ず、
今回のレポートで、〜がこれこれ深刻になっていたという形でしか報道しようとしないという風に
指摘しています。
また、最後には他にもエイズや貧困国の栄養不足の解消など地球のために出来る他の、あるいは
より重要なことがあるのではないかという彼の持論を展開しています。
※IPCCとは、Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)
の略で、気候変動に関するレポートを数年おきに発表し(現在までに4回)、2007年には
アル・ゴア前副大統領と共に、ノーベル平和賞を受賞しています。
ちょっと面白かった記事を再び。
「 ペットボトルリサイクルは資源のムダ?」
http://promotion.yahoo.co.jp/charger/200710/contents07/theme07.php
武田邦彦氏に対するインタビューです。
『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』
という著作で有名だということですが、
僕はまだこの本を読んでいません。
しかしペットボトルリサイクルの実態については
ほとんどリサイクルがどこまでされているのかや、
効率はどうかなど気にかけておらず盲点でした。
どうなんでしょうね。
若干丁寧さに欠けるインタビュー記事ではありますが、
是非読んでみてください。
「 ペットボトルリサイクルは資源のムダ?」
http://promotion.yahoo.co.jp/charger/200710/contents07/theme07.php
武田邦彦氏に対するインタビューです。
『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』
という著作で有名だということですが、
僕はまだこの本を読んでいません。
しかしペットボトルリサイクルの実態については
ほとんどリサイクルがどこまでされているのかや、
効率はどうかなど気にかけておらず盲点でした。
どうなんでしょうね。
若干丁寧さに欠けるインタビュー記事ではありますが、
是非読んでみてください。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
学生だって議論は出来る! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-