歌舞伎座さよなら公演
御名残三月大歌舞伎
3月2日(火)初日 28日(日)千穐楽
第一部(午前11時開演)
一、菅原伝授手習鑑 加茂堤 一幕
桜丸 梅玉
斎世親王 友右衛門
苅屋姫 孝太郎
八重 時蔵
二、楼門五三桐 一幕
石川五右衛門 吉右衛門
右忠太 歌六
左忠太 歌昇
真柴久吉 菊五郎
三、女暫 一幕
大薩摩連中
巴御前 玉三郎
蒲冠者範頼 我當
轟坊震斎 松緑
女鯰若菜 菊之助
猪俣平六 團蔵
武蔵九郎 権十郎
江田源三 彌十郎
東条八郎 市蔵
紅梅姫 梅枝
木曽太郎 松江
手塚太郎 進之介
清水冠者義高 錦之助
成田五郎 左團次
舞台番辰次 吉右衛門
第二部(午後2時30分開演)
一、菅原伝授手習鑑 筆法伝授 一幕
菅原館奥殿の場
同 学問所の場
同 門外の場
菅丞相 仁左衛門
園生の前 魁春
戸浪 芝雀
梅王丸 歌昇
左中弁希世 東蔵
武部源蔵 梅玉
河竹黙阿弥 作
二、弁天娘女男白浪 二幕
浜松屋見世先の場
稲瀬川勢揃いの場
弁天小僧菊之助 菊五郎
南郷力丸 吉右衛門
忠信利平 左團次
伜宗之助 菊之助
鳶頭清次 團蔵
浜松屋幸兵衛 東蔵
赤星十三郎 梅玉
日本駄右衛門 幸四郎
第三部(午後6時開演)
十三代目片岡仁左衛門十七回忌
十四代目守田勘弥三十七回忌
追善狂言
一、菅原伝授手習鑑 道明寺 一幕
菅丞相 仁左衛門
覚寿 玉三郎
奴宅内 錦之助
苅屋姫 孝太郎
贋迎い弥藤次 市蔵
宿禰太郎 彌十郎
土師兵衛 歌六
立田の前 秀太郎
判官代輝国 我當
文殊菩薩花石橋
二、石橋 長唄囃子連中
獅子の精 富十郎
文殊菩薩 鷹之資
男某 松緑
修験者 錦之助
寂昭法師 幸四郎
御名残三月大歌舞伎
3月2日(火)初日 28日(日)千穐楽
第一部(午前11時開演)
一、菅原伝授手習鑑 加茂堤 一幕
桜丸 梅玉
斎世親王 友右衛門
苅屋姫 孝太郎
八重 時蔵
二、楼門五三桐 一幕
石川五右衛門 吉右衛門
右忠太 歌六
左忠太 歌昇
真柴久吉 菊五郎
三、女暫 一幕
大薩摩連中
巴御前 玉三郎
蒲冠者範頼 我當
轟坊震斎 松緑
女鯰若菜 菊之助
猪俣平六 團蔵
武蔵九郎 権十郎
江田源三 彌十郎
東条八郎 市蔵
紅梅姫 梅枝
木曽太郎 松江
手塚太郎 進之介
清水冠者義高 錦之助
成田五郎 左團次
舞台番辰次 吉右衛門
第二部(午後2時30分開演)
一、菅原伝授手習鑑 筆法伝授 一幕
菅原館奥殿の場
同 学問所の場
同 門外の場
菅丞相 仁左衛門
園生の前 魁春
戸浪 芝雀
梅王丸 歌昇
左中弁希世 東蔵
武部源蔵 梅玉
河竹黙阿弥 作
二、弁天娘女男白浪 二幕
浜松屋見世先の場
稲瀬川勢揃いの場
弁天小僧菊之助 菊五郎
南郷力丸 吉右衛門
忠信利平 左團次
伜宗之助 菊之助
鳶頭清次 團蔵
浜松屋幸兵衛 東蔵
赤星十三郎 梅玉
日本駄右衛門 幸四郎
第三部(午後6時開演)
十三代目片岡仁左衛門十七回忌
十四代目守田勘弥三十七回忌
追善狂言
一、菅原伝授手習鑑 道明寺 一幕
菅丞相 仁左衛門
覚寿 玉三郎
奴宅内 錦之助
苅屋姫 孝太郎
贋迎い弥藤次 市蔵
宿禰太郎 彌十郎
土師兵衛 歌六
立田の前 秀太郎
判官代輝国 我當
文殊菩薩花石橋
二、石橋 長唄囃子連中
獅子の精 富十郎
文殊菩薩 鷹之資
男某 松緑
修験者 錦之助
寂昭法師 幸四郎
|
|
|
|
コメント(11)
《菅原伝授手習鑑 加茂堤 賀の祝》
初見は平成20年6月の博多座だったのですが、
桜丸・八重・三善清行が同じ役者さんでした。
梅玉丈の桜丸は、パッと見は二枚目ですが、
三枚目で鷹揚な雰囲気もあります。
下人とは言え、気品にあふれ、斎世親王と苅屋姫を案じる
緊迫感の中に、犯しがたい美しさもかいま見えます。
その一瞬の美は、悲劇の序曲を十分過ぎるほど表しています。
時蔵丈の八重は、愛らしさが全身からあふれています。
斎世親王・苅屋姫への気づかい、
桜丸への愛情がほのぼのと伝わってきます。
仕丁との立ち廻りや御所車を引く場面でも、あまり勇ましくならず、
どこまでも柔らかさが漂っています。
孝太郎丈の苅屋姫は、深窓の令嬢という感じで、
言葉がなくても、斎世親王のそばにいることができる喜びが伝わってきます。
おきゃんな娘役から奥ゆかしさのあるお姫様まで、
役どころの幅が更に広まっていると思います。
秀調丈の三善清行は、悪役ながらも、
三枚目と上品さをきっちり出しています。
やはり、家老や高貴な後家が似合うだけあって、安定しています。
権力の風向きを見るのがうまいヤツ、と思わずニヤリとさせられます。
《楼門五三桐》
たった15分にかける舞台装置、衣裳、大物役者と、贅沢さ満開です。
吉右衛門丈の石川五右衛門は
太っ腹な天下の大盗賊らしい見栄えです。
立ち廻りにも、さほどの見せ場はありませんが、
「絶景かな、絶景かな…」の台詞には、
役者としての大きさを感じました。
菊五郎丈の真柴久吉は、実に美しい巡礼姿でした。
セリとともに上がってくると、水色の衣裳がまぶしく、
気品の中に凛々しさも見えます。
「石川や…」の涼やかな口跡にも、音羽屋らしさを聞かせてくれます。
《女暫》
『暫』も『女暫』も、内容自体はどうというものではないのですが、
様々な役柄がそろい、様式美を楽しめる演目です。
玉三郎丈の巴御前は、可愛らしさと、
キリっとした女武者としての美しさが際立っていました。
玉三郎丈で好きなのは、時代物のお姫様・世話物の花魁・舞踊物です。
どれも、恋に生き、恋に死ぬ女性であり、強さと弱さの両面を見せる
ところは、巴御前にも、他の役にも通じるのではないでしょうか。
今までに見た『暫』『女暫』で、いいなあと思っていた
松緑丈の震斎と菊之助丈の若菜のコンビを
見ることができたのはラッキーでした。
菊之助丈と玉三郎丈の
「大和屋のねえさん」「音羽屋のお菊ちゃん」はお約束ですが、
『二人道成寺』で舞台をともにすることが多いお二人なので、
芝居を越えたほのぼのとしたものを感じました。
我當丈の範頼は、どっしりとした悪の大物ぶりと口跡が冴えていました。
足を悪くして痛々しい姿が最近多いのですが、
まだまだ活躍していただきたいものです。
成田五郎は、赤っ面の筆頭なわけですが、憎々しさの中に、
ユーモラスを漂わせてくれるのは、左團次丈ならではでしょう。
善人方で光っていたのは、梅枝丈の紅梅姫です。
あまり台詞はなくても、可哀そうなお姫様のオーラが突出し、
将来の大物ぶりに期待してしまいます。
初見は平成20年6月の博多座だったのですが、
桜丸・八重・三善清行が同じ役者さんでした。
梅玉丈の桜丸は、パッと見は二枚目ですが、
三枚目で鷹揚な雰囲気もあります。
下人とは言え、気品にあふれ、斎世親王と苅屋姫を案じる
緊迫感の中に、犯しがたい美しさもかいま見えます。
その一瞬の美は、悲劇の序曲を十分過ぎるほど表しています。
時蔵丈の八重は、愛らしさが全身からあふれています。
斎世親王・苅屋姫への気づかい、
桜丸への愛情がほのぼのと伝わってきます。
仕丁との立ち廻りや御所車を引く場面でも、あまり勇ましくならず、
どこまでも柔らかさが漂っています。
孝太郎丈の苅屋姫は、深窓の令嬢という感じで、
言葉がなくても、斎世親王のそばにいることができる喜びが伝わってきます。
おきゃんな娘役から奥ゆかしさのあるお姫様まで、
役どころの幅が更に広まっていると思います。
秀調丈の三善清行は、悪役ながらも、
三枚目と上品さをきっちり出しています。
やはり、家老や高貴な後家が似合うだけあって、安定しています。
権力の風向きを見るのがうまいヤツ、と思わずニヤリとさせられます。
《楼門五三桐》
たった15分にかける舞台装置、衣裳、大物役者と、贅沢さ満開です。
吉右衛門丈の石川五右衛門は
太っ腹な天下の大盗賊らしい見栄えです。
立ち廻りにも、さほどの見せ場はありませんが、
「絶景かな、絶景かな…」の台詞には、
役者としての大きさを感じました。
菊五郎丈の真柴久吉は、実に美しい巡礼姿でした。
セリとともに上がってくると、水色の衣裳がまぶしく、
気品の中に凛々しさも見えます。
「石川や…」の涼やかな口跡にも、音羽屋らしさを聞かせてくれます。
《女暫》
『暫』も『女暫』も、内容自体はどうというものではないのですが、
様々な役柄がそろい、様式美を楽しめる演目です。
玉三郎丈の巴御前は、可愛らしさと、
キリっとした女武者としての美しさが際立っていました。
玉三郎丈で好きなのは、時代物のお姫様・世話物の花魁・舞踊物です。
どれも、恋に生き、恋に死ぬ女性であり、強さと弱さの両面を見せる
ところは、巴御前にも、他の役にも通じるのではないでしょうか。
今までに見た『暫』『女暫』で、いいなあと思っていた
松緑丈の震斎と菊之助丈の若菜のコンビを
見ることができたのはラッキーでした。
菊之助丈と玉三郎丈の
「大和屋のねえさん」「音羽屋のお菊ちゃん」はお約束ですが、
『二人道成寺』で舞台をともにすることが多いお二人なので、
芝居を越えたほのぼのとしたものを感じました。
我當丈の範頼は、どっしりとした悪の大物ぶりと口跡が冴えていました。
足を悪くして痛々しい姿が最近多いのですが、
まだまだ活躍していただきたいものです。
成田五郎は、赤っ面の筆頭なわけですが、憎々しさの中に、
ユーモラスを漂わせてくれるのは、左團次丈ならではでしょう。
善人方で光っていたのは、梅枝丈の紅梅姫です。
あまり台詞はなくても、可哀そうなお姫様のオーラが突出し、
将来の大物ぶりに期待してしまいます。
《菅原伝授手習鑑 筆法伝授》
初めて見ました。
今回は変則的とは言え、通し上演でなければ、
なかなかお目にかかれない演目です。
率直な感想を述べますと、菅原館奥殿の場はやや退屈で、
菅原館学問所の場で、菅丞相が登場するあたりから面白くなりました。
主従・夫婦・親子の愛と絆が静かに深く描かれ、
『寺子屋』の世界が一層色濃く感じられるのではないでしょうか。
仁左衛門丈の菅丞相が、実に神々しく、まさに天神様そのものです。
殆ど座ったままで動きのない役にもかかわらず、
口跡には右大臣としての重みがあり、
指の添え方ひとつとってみても、絶品です。
宮中に出向くため、冠装束に着替えた丞相の冠が落ちるくだりは、
分かっていてもドキっとする絶妙のタイミングで、
その後の悲劇を見事に象徴していました。
梅玉丈の武部源蔵は、『寺子屋』で何度か見ているのですが、
ここでは、若くて、まっすぐな気性で、
菅丞相への忠誠心は揺るがない男です。
特に「伝授は伝授、勘当は勘当」と丞相に言い渡され、
男泣きする場面では、哀れさと純粋さを感じました。
菅原館門外の場では、時平の手下を相手に立ち廻るのですが、
「おお!源蔵って、文武に優れた人なんだ!!」
と妙に感動してしまいました。
源蔵夫婦が丞相の若君・菅秀才を背負って花道を行く姿からは、
命に代えても若君を守る気迫が感じられました。
魁春丈の園生の前は、菅丞相の奥方である気品と、
源蔵夫婦に対するさりげない思いやりが、
舞台に自然と溶け込んでいました。
芝雀丈の戸浪は、平成17年10月の古典芸能鑑賞会(NHKホール)の
『寺子屋』で見たのですが、その時も、夫・源蔵は梅玉丈でした。
この頃から、芝雀丈が演じる人妻に、
ものすごい色気を感じるようになったのですが、
今回も、その泣き出しそうな瞳に、くらくらしました。
園生の前と再会する場面では、
夫を思う気持ちと菅原家への変わらぬ忠誠心が見て取れ、
夫婦・主従の結び付きをより強調するものとなりました。
東蔵丈の左中弁希世は、秀調丈の三善清行と似たような役柄ですが、
高貴な中のいやらしさ、悪役の中の三枚目を見事に表しています。
特に、腰元・勝野を口説くあたりなどは、
権力を笠に着たイヤなヤツという反面、
「うん。あんな可愛い腰元なら口説きたくなるよな」
と同調させてしまうおかしさもありました。
歌昇丈の梅王丸は、忠誠心と力強さにあふれていました。
歌昇丈の梅王丸、歌六丈の松王丸(or時平)で、
『車引』を見たいなあと、ふと思いました。
初めて見ました。
今回は変則的とは言え、通し上演でなければ、
なかなかお目にかかれない演目です。
率直な感想を述べますと、菅原館奥殿の場はやや退屈で、
菅原館学問所の場で、菅丞相が登場するあたりから面白くなりました。
主従・夫婦・親子の愛と絆が静かに深く描かれ、
『寺子屋』の世界が一層色濃く感じられるのではないでしょうか。
仁左衛門丈の菅丞相が、実に神々しく、まさに天神様そのものです。
殆ど座ったままで動きのない役にもかかわらず、
口跡には右大臣としての重みがあり、
指の添え方ひとつとってみても、絶品です。
宮中に出向くため、冠装束に着替えた丞相の冠が落ちるくだりは、
分かっていてもドキっとする絶妙のタイミングで、
その後の悲劇を見事に象徴していました。
梅玉丈の武部源蔵は、『寺子屋』で何度か見ているのですが、
ここでは、若くて、まっすぐな気性で、
菅丞相への忠誠心は揺るがない男です。
特に「伝授は伝授、勘当は勘当」と丞相に言い渡され、
男泣きする場面では、哀れさと純粋さを感じました。
菅原館門外の場では、時平の手下を相手に立ち廻るのですが、
「おお!源蔵って、文武に優れた人なんだ!!」
と妙に感動してしまいました。
源蔵夫婦が丞相の若君・菅秀才を背負って花道を行く姿からは、
命に代えても若君を守る気迫が感じられました。
魁春丈の園生の前は、菅丞相の奥方である気品と、
源蔵夫婦に対するさりげない思いやりが、
舞台に自然と溶け込んでいました。
芝雀丈の戸浪は、平成17年10月の古典芸能鑑賞会(NHKホール)の
『寺子屋』で見たのですが、その時も、夫・源蔵は梅玉丈でした。
この頃から、芝雀丈が演じる人妻に、
ものすごい色気を感じるようになったのですが、
今回も、その泣き出しそうな瞳に、くらくらしました。
園生の前と再会する場面では、
夫を思う気持ちと菅原家への変わらぬ忠誠心が見て取れ、
夫婦・主従の結び付きをより強調するものとなりました。
東蔵丈の左中弁希世は、秀調丈の三善清行と似たような役柄ですが、
高貴な中のいやらしさ、悪役の中の三枚目を見事に表しています。
特に、腰元・勝野を口説くあたりなどは、
権力を笠に着たイヤなヤツという反面、
「うん。あんな可愛い腰元なら口説きたくなるよな」
と同調させてしまうおかしさもありました。
歌昇丈の梅王丸は、忠誠心と力強さにあふれていました。
歌昇丈の梅王丸、歌六丈の松王丸(or時平)で、
『車引』を見たいなあと、ふと思いました。
《弁天娘女男白浪》
「菊五郎丈の弁天小僧と出会うために、
歌舞伎に引き寄せられたのではないか?」
突然、何を言いだしやがるっと思われるでしょうが、
終演後、まず、頭に浮かんだのは、そんなことでした。
武家娘の花道の入りでは、写真でしか見たことがない20〜30歳代の
ような瑞々しさはないのですが、一つ一つの動き、口跡から柔らかさ、
可愛らしさが伝わってきます。
浜松屋見世先でも、品々を選ぶ姿には恥じらいが感じられ、
婚礼前の嬉しさをかみしめている感じです。
ところが、正体を見破られる場面では、
スパンっと気持ちの良い啖呵の中に、
男でもあり、女でもある両性具有的な倒錯美が見てとれます。
お馴染みの「知らざぁ言って聞かせやしょう」をよく聞いてみると、
転落また転落の大変な人生です。
しかし、『弁天小僧』が初演された幕末同様、混沌とした現代では、
正義の味方ではない、しかし、
単純な悪役でもない弁天小僧に、退廃美的で、
更に、禁断の木の実のような、ぬめっとした美味しさを堪能できます。
南郷力丸との花道の引っ込みは、お金の山分け、坊主持ちと
お約束のコント(?)ですが、どこか即興劇っぽくて面白かったです。
ここでは、弁天小僧に、
「男にもなれる、女にもなれる。しかも、どちらも愛せる」
というバイセクシャル(両性愛)のようなものまで感じます。
しかし、それは肉体的なものではなく、
精神的なものであるような気がします。
やはり、兼ル役者である菊五郎丈に、ぴったりの役です。
菊五郎丈の弁天と吉右衛門丈の南郷というコンビは、
本公演では過去2回しかなく、
「もう永遠に見られないのでは」と思っていました。
いつも、文句ばかり言っていますが、この配役にはお礼を言います。
「松竹株式会社さん、ありがとう」
時代物を得意とする吉右衛門丈だけあって、
武家に奉公する若党・南郷力丸は、
武士らしい品性と有無を言わさぬ威圧感を見せてくれました。
その端々には、漁師出身という荒々しさも、かいま見え、
素晴らしい、『弁天の兄貴分』でした。
菊之助丈の浜松屋伜・宗之助は、大店の若旦那にピッタリでした。
出の場面では、決して騒がず、うろたえず、目と指先で、
ちょっと制する姿が美しいです。
どこか鷹揚でありながら、いざとなるとビシっと決めてくれる、
こんな若旦那なら、浜松屋は安泰だなと思わせてくれます。
東蔵丈の浜松屋幸兵衛は、大店の主人らしい安定感です。
團蔵丈の鳶頭・清次は、喧嘩っ早い江戸っ子の香りが漂っています。
菊十郎丈の狼の悪次郎は、冒頭、見世先に登場するだけですが、
鋭い目つきに加え、全身から研ぎ澄まされた殺気が漂い、
「この役者さんでなければ」と感じます。
橘太郎丈の番頭・与九郎は、音羽屋さんの『弁天小僧』に
なくてはならない一員になりつつあります。
この番頭は、小心者なのに、いばるの大好き、
というイヤな上司の典型でしょうか。
番頭が、武家娘に、好きな歌舞伎役者を尋ねるのは、お約束ですが、
今回は、こんなやり取りがありました。
番頭「お嬢様の好きな役者は、中村吉右衛門でございましょう」
娘「あいなぁ」
若党「あのような役者は大嫌いでござる。
時に番頭さん、芝居好きと見えるな。
好きな役者がいるだろう?」
番頭「ちょっと小粒のいい役者・坂東橘太郎が贔屓でございます」
このあたりを、また変えて楽しませてくれるのでしょうか。
稲瀬川勢揃いだけの登場ですが、
梅玉丈の赤星十三郎は、元は小姓という色気があり、
やっぱり、前髪が似合うなあと思いました。
左團次には、南郷力丸か日本駄右衛門というイメージがあるので、
忠信利平もやるんだあ、と思い、
もっと調べたら、鳶頭や宗之助もやっていました。
「菊五郎丈の弁天小僧と出会うために、
歌舞伎に引き寄せられたのではないか?」
突然、何を言いだしやがるっと思われるでしょうが、
終演後、まず、頭に浮かんだのは、そんなことでした。
武家娘の花道の入りでは、写真でしか見たことがない20〜30歳代の
ような瑞々しさはないのですが、一つ一つの動き、口跡から柔らかさ、
可愛らしさが伝わってきます。
浜松屋見世先でも、品々を選ぶ姿には恥じらいが感じられ、
婚礼前の嬉しさをかみしめている感じです。
ところが、正体を見破られる場面では、
スパンっと気持ちの良い啖呵の中に、
男でもあり、女でもある両性具有的な倒錯美が見てとれます。
お馴染みの「知らざぁ言って聞かせやしょう」をよく聞いてみると、
転落また転落の大変な人生です。
しかし、『弁天小僧』が初演された幕末同様、混沌とした現代では、
正義の味方ではない、しかし、
単純な悪役でもない弁天小僧に、退廃美的で、
更に、禁断の木の実のような、ぬめっとした美味しさを堪能できます。
南郷力丸との花道の引っ込みは、お金の山分け、坊主持ちと
お約束のコント(?)ですが、どこか即興劇っぽくて面白かったです。
ここでは、弁天小僧に、
「男にもなれる、女にもなれる。しかも、どちらも愛せる」
というバイセクシャル(両性愛)のようなものまで感じます。
しかし、それは肉体的なものではなく、
精神的なものであるような気がします。
やはり、兼ル役者である菊五郎丈に、ぴったりの役です。
菊五郎丈の弁天と吉右衛門丈の南郷というコンビは、
本公演では過去2回しかなく、
「もう永遠に見られないのでは」と思っていました。
いつも、文句ばかり言っていますが、この配役にはお礼を言います。
「松竹株式会社さん、ありがとう」
時代物を得意とする吉右衛門丈だけあって、
武家に奉公する若党・南郷力丸は、
武士らしい品性と有無を言わさぬ威圧感を見せてくれました。
その端々には、漁師出身という荒々しさも、かいま見え、
素晴らしい、『弁天の兄貴分』でした。
菊之助丈の浜松屋伜・宗之助は、大店の若旦那にピッタリでした。
出の場面では、決して騒がず、うろたえず、目と指先で、
ちょっと制する姿が美しいです。
どこか鷹揚でありながら、いざとなるとビシっと決めてくれる、
こんな若旦那なら、浜松屋は安泰だなと思わせてくれます。
東蔵丈の浜松屋幸兵衛は、大店の主人らしい安定感です。
團蔵丈の鳶頭・清次は、喧嘩っ早い江戸っ子の香りが漂っています。
菊十郎丈の狼の悪次郎は、冒頭、見世先に登場するだけですが、
鋭い目つきに加え、全身から研ぎ澄まされた殺気が漂い、
「この役者さんでなければ」と感じます。
橘太郎丈の番頭・与九郎は、音羽屋さんの『弁天小僧』に
なくてはならない一員になりつつあります。
この番頭は、小心者なのに、いばるの大好き、
というイヤな上司の典型でしょうか。
番頭が、武家娘に、好きな歌舞伎役者を尋ねるのは、お約束ですが、
今回は、こんなやり取りがありました。
番頭「お嬢様の好きな役者は、中村吉右衛門でございましょう」
娘「あいなぁ」
若党「あのような役者は大嫌いでござる。
時に番頭さん、芝居好きと見えるな。
好きな役者がいるだろう?」
番頭「ちょっと小粒のいい役者・坂東橘太郎が贔屓でございます」
このあたりを、また変えて楽しませてくれるのでしょうか。
稲瀬川勢揃いだけの登場ですが、
梅玉丈の赤星十三郎は、元は小姓という色気があり、
やっぱり、前髪が似合うなあと思いました。
左團次には、南郷力丸か日本駄右衛門というイメージがあるので、
忠信利平もやるんだあ、と思い、
もっと調べたら、鳶頭や宗之助もやっていました。
《菅原伝授手習鑑 道明寺》
十三代目仁左衛門十七回忌、十四代目勘弥三十七回忌の追善狂言です。
残念ながら、私は両人とも、画像・写真で拝見するばかりです。
『道明寺』は、4年前に一度見たきりで、
木像と本物の菅丞相の演じ分けが、印象に残っているだけでした。
今回は、『筆法伝授』を見ているので、
物語の背景や人物のつながりが分かり、
少しばかり理解が深まったかもしれません。
仁左衛門丈の菅丞相は、ここでも神々しさを見せてくれました。
木像の丞相は、操り人形のような動きの中に、神が命を吹き込んだ荘厳さと
けがれのない天真爛漫さ感じました。
本物の丞相は、ここでも、動きや台詞は少ないのですが、
苅屋姫との別れの場面は、
遠くを見るような目が、感動的な台詞の何倍も物語っていました。
玉三郎丈の覚寿は、高貴な身分の女性の品格に加え、
いざとなったら、男に代わり家を守る覚悟が見て取れ、
カッコいい老け役でした。
二人の娘を折檻する場面でも、
義理・愛情など様々な思いが複雑にからんだ心情を表現していました。
秀太郎丈の立田の前は、悲劇のヒロインですが、
自分のことよりも、人への思いやりが先に立つという優しさが
にじみ出ています。
特に、苅屋姫とのやり取りから、その人柄が浮かびあがってきます。
なぜ、立田の前が、強欲非道な宿禰太郎の奥方なのか疑問でした。
「夫のことを世間は悪く言うけど、本当はいい人なのよ」と、
あくまでプラス面を見ようとする優しさだったのかな、
と思うようになりました。
我當丈の判官代輝国は、厳格な役人という風貌の中に、
正義と思いやりが感じられ、
その場を引きしめる役もこなしていました。
孝太郎丈の苅屋姫は、自分のせいで、丞相が罪に陥れられたことに
対する申し訳なさに押しつぶされそうな気持を、よく表していました。
最後に、丞相の袖にすがりついて別れを悲しむ場面では、
このまま失神して倒れてしまうのでは、
と思わせるほどの息使いまで聞こえてきそうでした。
《石橋》
富十郎丈の口跡は、いつもながら朗々と響き渡り、
獅子の精の姿も様になっていました。
毛ぶりはなく、地味な舞踊物だなあと思いましたが、
優しさと厳しさの混じった目は、まさに子(鷹之資)を
守っている獅子そのものでした。
何度も言うように、私は日本舞踊の心得はありません。
しかし、藤間流の家元である松緑丈と、
舞踊の名人・富十郎丈の弟子である錦之助丈の二人が舞台に立ち、
ちょっとした動きをするだけでも、見とれてしまいます。
舞踊というものを通して美しさを見せることを、
よく分かっている役者さんと思いました。
十三代目仁左衛門十七回忌、十四代目勘弥三十七回忌の追善狂言です。
残念ながら、私は両人とも、画像・写真で拝見するばかりです。
『道明寺』は、4年前に一度見たきりで、
木像と本物の菅丞相の演じ分けが、印象に残っているだけでした。
今回は、『筆法伝授』を見ているので、
物語の背景や人物のつながりが分かり、
少しばかり理解が深まったかもしれません。
仁左衛門丈の菅丞相は、ここでも神々しさを見せてくれました。
木像の丞相は、操り人形のような動きの中に、神が命を吹き込んだ荘厳さと
けがれのない天真爛漫さ感じました。
本物の丞相は、ここでも、動きや台詞は少ないのですが、
苅屋姫との別れの場面は、
遠くを見るような目が、感動的な台詞の何倍も物語っていました。
玉三郎丈の覚寿は、高貴な身分の女性の品格に加え、
いざとなったら、男に代わり家を守る覚悟が見て取れ、
カッコいい老け役でした。
二人の娘を折檻する場面でも、
義理・愛情など様々な思いが複雑にからんだ心情を表現していました。
秀太郎丈の立田の前は、悲劇のヒロインですが、
自分のことよりも、人への思いやりが先に立つという優しさが
にじみ出ています。
特に、苅屋姫とのやり取りから、その人柄が浮かびあがってきます。
なぜ、立田の前が、強欲非道な宿禰太郎の奥方なのか疑問でした。
「夫のことを世間は悪く言うけど、本当はいい人なのよ」と、
あくまでプラス面を見ようとする優しさだったのかな、
と思うようになりました。
我當丈の判官代輝国は、厳格な役人という風貌の中に、
正義と思いやりが感じられ、
その場を引きしめる役もこなしていました。
孝太郎丈の苅屋姫は、自分のせいで、丞相が罪に陥れられたことに
対する申し訳なさに押しつぶされそうな気持を、よく表していました。
最後に、丞相の袖にすがりついて別れを悲しむ場面では、
このまま失神して倒れてしまうのでは、
と思わせるほどの息使いまで聞こえてきそうでした。
《石橋》
富十郎丈の口跡は、いつもながら朗々と響き渡り、
獅子の精の姿も様になっていました。
毛ぶりはなく、地味な舞踊物だなあと思いましたが、
優しさと厳しさの混じった目は、まさに子(鷹之資)を
守っている獅子そのものでした。
何度も言うように、私は日本舞踊の心得はありません。
しかし、藤間流の家元である松緑丈と、
舞踊の名人・富十郎丈の弟子である錦之助丈の二人が舞台に立ち、
ちょっとした動きをするだけでも、見とれてしまいます。
舞踊というものを通して美しさを見せることを、
よく分かっている役者さんと思いました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
歌舞伎愛好会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
歌舞伎愛好会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90017人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208279人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 75471人
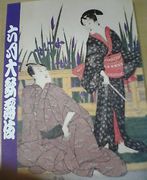





![[dir] 日本の伝統芸能](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/58/266758_56s.jpg)

![[dir] 邦楽](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/61/266761_218s.jpg)















