新春浅草歌舞伎
2008年1月2日(水)〜27日(日)
第1部(午後11時開演)
お年玉〈年始ご挨拶〉
一、傾城反魂香
土佐将監閑居の場
浮世又平 中村勘太郎
狩野雅楽之助 片岡愛之助
土佐将監 市川男女蔵
女房おとく 市川亀治郎
二、弁天娘女男白浪
浜松屋店先より
稲瀬川勢揃いまで
弁天小僧菊之助 中村七之助
南郷力丸 中村獅 童
赤星十三郎 中村勘太郎
鳶頭清次 中村亀 鶴
忠信利平 市川亀治郎
日本駄右衛門 片岡愛之助
第2部(午後3時開演)
お年玉〈年始ご挨拶〉
一、祗園祭礼信仰記
金閣寺
雪姫 市川亀治郎
此下東吉 中村勘太郎
狩野之介直信 中村七之助
慶寿院尼 中村亀 鶴
佐藤正清 市川男女蔵
松永大膳 中村獅 童
二、与話情浮名横櫛
木更津海岸見染の場
源氏店の場
与三郎 片岡愛之助
お富 中村七之助
蝙蝠安 中村亀 鶴
鳶頭金五郎 中村獅 童
和泉屋多左衛門 市川男女蔵
2008年1月2日(水)〜27日(日)
第1部(午後11時開演)
お年玉〈年始ご挨拶〉
一、傾城反魂香
土佐将監閑居の場
浮世又平 中村勘太郎
狩野雅楽之助 片岡愛之助
土佐将監 市川男女蔵
女房おとく 市川亀治郎
二、弁天娘女男白浪
浜松屋店先より
稲瀬川勢揃いまで
弁天小僧菊之助 中村七之助
南郷力丸 中村獅 童
赤星十三郎 中村勘太郎
鳶頭清次 中村亀 鶴
忠信利平 市川亀治郎
日本駄右衛門 片岡愛之助
第2部(午後3時開演)
お年玉〈年始ご挨拶〉
一、祗園祭礼信仰記
金閣寺
雪姫 市川亀治郎
此下東吉 中村勘太郎
狩野之介直信 中村七之助
慶寿院尼 中村亀 鶴
佐藤正清 市川男女蔵
松永大膳 中村獅 童
二、与話情浮名横櫛
木更津海岸見染の場
源氏店の場
与三郎 片岡愛之助
お富 中村七之助
蝙蝠安 中村亀 鶴
鳶頭金五郎 中村獅 童
和泉屋多左衛門 市川男女蔵
|
|
|
|
コメント(7)
新春浅草歌舞伎(第二部)
《祗園祭礼信仰記 金閣寺》
雀右衛門丈が指導したそうですが、亀治郎丈は、見事に、それに答えていました。
大膳の要求を拒絶する場面で、少し斜め上を見上げるような表情が、
とても印象に残りました。
更に、桜吹雪の中で、縛られながらも、爪先で鼠を描く見せ場は、
とても初役とは思えません。
私は、雀右衛門丈の雪姫は、写真でしか、観たことがありません。
亀治郎丈の雪姫は、一瞬、一瞬の動きの中で、
「雀右衛門丈は、こう演じたのだろう」と思わせるものがありました。
勘太郎丈の此下東吉の、碁盤の見得は、実に美しく決まりました。
どこかひょうひょうとしながらも、知性あふれる武将を見せてくれました。
様々な場面で、得意な舞踊が生かされ、
『勘太郎丈の型』を確立しつつあるように見えました。
亀鶴丈の慶寿院は、出番は少なく、地味かもしれませんが、重要な役どころです。
尼僧としての気品と、将軍の母としての威厳を、備えていたと思います。
「この方を、大膳も簡単に殺せないし、東吉も自然に平伏するよなあ」、
という感じでしょうか。
獅童丈の大膳は、恰幅がよく、錦絵から飛び出したような悪玉ぶりでした。
口跡も良く、イイ出来だったと思うのですが、
天下を狙う大悪人としての懐の深さまで、あと一歩という感じでした。
《与話情浮名横櫛》
おじの仁左衛門丈に習ったという、愛之助丈の与三郎です。
木更津海岸見染の場では、放蕩三昧を続ける大店の息子、
という雰囲気が、出ていたと思います。
実は、子細あっての放蕩か?と思わせるしぐさや目付きも、なかなかのものでした。
さすがに、“羽織落し”は、難しそうでした。
源氏店の場では、まだまだ凄味と色気が、足りなく見えましたが、
あと10年後、20年後が楽しみです。
七之助丈のお富は、玉三郎丈に習ったのでしょうか?
美しくまとまっていましたが、特に、源氏店の場では、身のこなしや口跡が、
玉三郎丈のコピーを思わせるものがありました。
しかし、大先輩のモノを貪欲に吸収しようとする意識も感じられ、
ラクには、新たな、お富ができるのでは?と期待できます。
この演目でも、亀鶴丈が、イイ味を出してくれました。
猫なで声を出したかと思えば、怒鳴り上げる、という蝙蝠安は、
強請りのプロ(?)でしょう。
そのくせ、本当に強い者には、からっきし弱いというヤツを、
亀鶴丈は、楽しんで演じているようです。
しかも、決して、主役の与三郎とお富を食うことなく、
一歩下がって、盛り立てています。
地味な役どころでも、きっちりツボを押さえています。
片岡一門のベテラン脇役の松之助丈が、手代・藤八で、楽しませてくれました。
時には敵役、時には三枚目と、幅の広い役者さんです。
《祗園祭礼信仰記 金閣寺》
雀右衛門丈が指導したそうですが、亀治郎丈は、見事に、それに答えていました。
大膳の要求を拒絶する場面で、少し斜め上を見上げるような表情が、
とても印象に残りました。
更に、桜吹雪の中で、縛られながらも、爪先で鼠を描く見せ場は、
とても初役とは思えません。
私は、雀右衛門丈の雪姫は、写真でしか、観たことがありません。
亀治郎丈の雪姫は、一瞬、一瞬の動きの中で、
「雀右衛門丈は、こう演じたのだろう」と思わせるものがありました。
勘太郎丈の此下東吉の、碁盤の見得は、実に美しく決まりました。
どこかひょうひょうとしながらも、知性あふれる武将を見せてくれました。
様々な場面で、得意な舞踊が生かされ、
『勘太郎丈の型』を確立しつつあるように見えました。
亀鶴丈の慶寿院は、出番は少なく、地味かもしれませんが、重要な役どころです。
尼僧としての気品と、将軍の母としての威厳を、備えていたと思います。
「この方を、大膳も簡単に殺せないし、東吉も自然に平伏するよなあ」、
という感じでしょうか。
獅童丈の大膳は、恰幅がよく、錦絵から飛び出したような悪玉ぶりでした。
口跡も良く、イイ出来だったと思うのですが、
天下を狙う大悪人としての懐の深さまで、あと一歩という感じでした。
《与話情浮名横櫛》
おじの仁左衛門丈に習ったという、愛之助丈の与三郎です。
木更津海岸見染の場では、放蕩三昧を続ける大店の息子、
という雰囲気が、出ていたと思います。
実は、子細あっての放蕩か?と思わせるしぐさや目付きも、なかなかのものでした。
さすがに、“羽織落し”は、難しそうでした。
源氏店の場では、まだまだ凄味と色気が、足りなく見えましたが、
あと10年後、20年後が楽しみです。
七之助丈のお富は、玉三郎丈に習ったのでしょうか?
美しくまとまっていましたが、特に、源氏店の場では、身のこなしや口跡が、
玉三郎丈のコピーを思わせるものがありました。
しかし、大先輩のモノを貪欲に吸収しようとする意識も感じられ、
ラクには、新たな、お富ができるのでは?と期待できます。
この演目でも、亀鶴丈が、イイ味を出してくれました。
猫なで声を出したかと思えば、怒鳴り上げる、という蝙蝠安は、
強請りのプロ(?)でしょう。
そのくせ、本当に強い者には、からっきし弱いというヤツを、
亀鶴丈は、楽しんで演じているようです。
しかも、決して、主役の与三郎とお富を食うことなく、
一歩下がって、盛り立てています。
地味な役どころでも、きっちりツボを押さえています。
片岡一門のベテラン脇役の松之助丈が、手代・藤八で、楽しませてくれました。
時には敵役、時には三枚目と、幅の広い役者さんです。
新春浅草歌舞伎(第一部)
昨日(6日)の第二部が「着物で歌舞伎の日」だったせいか、
第一部も着物姿の人が目立ちました。
年始ご挨拶は、獅童丈。第一部の演目の解説をしていました。
『傾城反魂香』の解説の中で、
「夫婦愛の物語です」と言ったところで、客席から笑いが‥‥。
「何で、ここで笑うんですか?
私に夫婦愛は似合わない、ってことですかねー!」
と言う獅童丈の自虐ネタに、場内は大爆笑。
パンフレットを見たら、獅童丈の年始ご挨拶は、第一部ばかりでした。
このネタで、ずっと行くのでしょうか?
どなたか、レポートをお願いします。
《傾城反魂香》
亀治郎丈のおとくが、冴えていました。
又平に代わり、長々と話す“しゃべり”では、
どことなく、『十二夜』の麻阿を思わせる雰囲気でした。
しかし、又平との二人だけの場面になると、一転、
又平を温かく包み込む優しさが、伝わってきました。
こちらも、雀右衛門丈の指導なのでしょうか?
勘太郎丈の又平は、純粋な人柄は伝わりますが、やや物足りなく感じました。
でも、難しい役を、よく勤めたと思います。
最後に、衣裳を改め、大頭の舞を舞う場面では、
豪快で、気持ちよく決めてくれました。
愛之助丈の雅楽之助は、注進に駆けつけ、主君・狩野元信の危機を知らせます。
剣の腕も立ち、二枚目という雰囲気が、よく出ていました。
主家の危機を、舞いながら語って聞かす場面では、
完全に、舞台を独り占めしていました。
《弁天娘女男白浪》
2003年(平成15)10月、平成中村座で観た、七之助丈の弁天小僧は、
「知らざぁ言って聞かせやしょう」の名台詞が、
平坦で、少しがっかりした記憶があります。
しかし、今回は、「ああ、素敵だなあ」と思わせてくれました。
武家娘は、女形の本領発揮で、そそとした美しさと恥らう様子が、絶品でした。
盗賊の本性を顕す場面では、顔つきも口跡も、ぐっと来るものがありました。
今後、悪のすご味や色気が、もっと加われば、
更に、“弁天小僧七之助”に磨きがかかるのではないでしょうか。
愛之助丈の日本駄右衛門は、2004年(平成16)、三越劇場で観た時より、
ますます、深みを増していました。
当時は、おじの仁左衛門丈に、そっくりという印象しかありませんでしたが、
自分なりに、いろいろ工夫をしてきているのでしょう。
特に、浜松屋の場面では、思慮深くて、
子細工などは看破してしまうような表情でした。
「おぬし、なかなかの者じゃのぉ〜」と肩をたたきたくなる、お武家様です。
獅童丈の南郷は、見ばえも、口跡も、良いと思うのです。
しかし、浜松屋の場面では、武家に仕える若党というより、
町内の兄貴に見えてしまいました。
南郷は、浜育ちで、武家ではないから、これで、いいのかもしれませんが‥‥。
稲瀬川の勢揃いは、錦絵を見ているようで、私が大好きな場面です。
演歌歌手も真っ青の、ド派手な衣裳が、歌舞伎らしくて、最高です。
亀治郎丈の忠信利平は、この場面だけの登場ですが、
名乗りも、見得も、迫力があり、ここも、私の目に、はっきりと焼付けられました。
昨日(6日)の第二部が「着物で歌舞伎の日」だったせいか、
第一部も着物姿の人が目立ちました。
年始ご挨拶は、獅童丈。第一部の演目の解説をしていました。
『傾城反魂香』の解説の中で、
「夫婦愛の物語です」と言ったところで、客席から笑いが‥‥。
「何で、ここで笑うんですか?
私に夫婦愛は似合わない、ってことですかねー!」
と言う獅童丈の自虐ネタに、場内は大爆笑。
パンフレットを見たら、獅童丈の年始ご挨拶は、第一部ばかりでした。
このネタで、ずっと行くのでしょうか?
どなたか、レポートをお願いします。
《傾城反魂香》
亀治郎丈のおとくが、冴えていました。
又平に代わり、長々と話す“しゃべり”では、
どことなく、『十二夜』の麻阿を思わせる雰囲気でした。
しかし、又平との二人だけの場面になると、一転、
又平を温かく包み込む優しさが、伝わってきました。
こちらも、雀右衛門丈の指導なのでしょうか?
勘太郎丈の又平は、純粋な人柄は伝わりますが、やや物足りなく感じました。
でも、難しい役を、よく勤めたと思います。
最後に、衣裳を改め、大頭の舞を舞う場面では、
豪快で、気持ちよく決めてくれました。
愛之助丈の雅楽之助は、注進に駆けつけ、主君・狩野元信の危機を知らせます。
剣の腕も立ち、二枚目という雰囲気が、よく出ていました。
主家の危機を、舞いながら語って聞かす場面では、
完全に、舞台を独り占めしていました。
《弁天娘女男白浪》
2003年(平成15)10月、平成中村座で観た、七之助丈の弁天小僧は、
「知らざぁ言って聞かせやしょう」の名台詞が、
平坦で、少しがっかりした記憶があります。
しかし、今回は、「ああ、素敵だなあ」と思わせてくれました。
武家娘は、女形の本領発揮で、そそとした美しさと恥らう様子が、絶品でした。
盗賊の本性を顕す場面では、顔つきも口跡も、ぐっと来るものがありました。
今後、悪のすご味や色気が、もっと加われば、
更に、“弁天小僧七之助”に磨きがかかるのではないでしょうか。
愛之助丈の日本駄右衛門は、2004年(平成16)、三越劇場で観た時より、
ますます、深みを増していました。
当時は、おじの仁左衛門丈に、そっくりという印象しかありませんでしたが、
自分なりに、いろいろ工夫をしてきているのでしょう。
特に、浜松屋の場面では、思慮深くて、
子細工などは看破してしまうような表情でした。
「おぬし、なかなかの者じゃのぉ〜」と肩をたたきたくなる、お武家様です。
獅童丈の南郷は、見ばえも、口跡も、良いと思うのです。
しかし、浜松屋の場面では、武家に仕える若党というより、
町内の兄貴に見えてしまいました。
南郷は、浜育ちで、武家ではないから、これで、いいのかもしれませんが‥‥。
稲瀬川の勢揃いは、錦絵を見ているようで、私が大好きな場面です。
演歌歌手も真っ青の、ド派手な衣裳が、歌舞伎らしくて、最高です。
亀治郎丈の忠信利平は、この場面だけの登場ですが、
名乗りも、見得も、迫力があり、ここも、私の目に、はっきりと焼付けられました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
歌舞伎愛好会 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
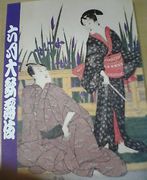





![[dir] 日本の伝統芸能](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/58/266758_56s.jpg)

![[dir] 邦楽](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/67/61/266761_218s.jpg)














