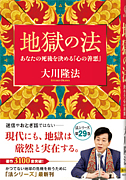四国霊場、八十八ヶ所を紹介します。
言うまでもなく、当会とはとても関係が深いですが、詳しい事は良く分らない・・・。
と言われる方に、八十八ヶ所の歴史を紐解いていきたいと思います。
実は、四国は意外な事に、聖地だったんです。
まず、仏教を日本へ布教させた聖徳太子。
奈良の大仏を建てた行基菩薩。
中国から5度の渡来に失敗し、失明をしたにもかかわらず6度目で日本へ来て、お寺を建てた鑑真。
香川県善通寺に生まれ、中国へ渡り、恵果和尚から密教の全てを託され、真言宗の開祖となった、弘法大師空海。
この方々が、実は四国八十八ヶ所、巡礼の基礎となるお寺を建てたり、仏像を彫ったりした事を、ご存じでしょうか?
空海は約半分の四十ヶ所のお寺を建てましたが、最後に八十八ヶ所のまとめ役として、この世に生を受けたとも言われております。
この八十八ヶ所の意味はなんであるか?と言いますと、実は地図を見てもらえると解りやすいのですが、四国をぐるっと一周しています。
これは結界を意味し、邪霊、悪霊の侵入を防ぐ為、と言われております。
では何の為の結界か?と言いますと、2500〜2600年前に、インドのお釈迦様が、「我、東の国にて再誕す」と予言を残されたのですが、それが日本の四国なのだそうです。
空海没1200年経ち、一周1200キロのこの四国八十八ヶ所も空海の「四国に鉄の橋が架かる時、私の使命も終わるであろう。」と予言を残し、四国に三つの橋が架かったため、この結界の役目は終わりを告げました。
前置きが長くなりましたが、この神秘の四国について、色々語りたいと思いますので、皆様よろしくお願いしたいと思います。
※主な登場人物。
弘法大師空海、行基菩薩、鑑真和上、聖徳太子、役行者小角、松法師、真念僧正、宥応法印、月峰上人、正澄上人、明神右京・隼人、恵明上人、真野長者、越智守興、日証上人、和気道善、和気道隆、義渕僧正、恵果和上、一遍上人、行教上人、智法大師、藤原不比等、運慶、湛慶、海覚、山本玄峰、義渕僧正、恵雲師、聖武天皇、光明皇后、嵯峨天皇、天武天皇、垣武天皇、平城天皇、後鳥羽天皇、後醍醐天皇、用命天皇、村山天皇、欽明天皇、孝謙天皇、淳和天皇、天智天皇、文徳天皇、高倉天皇、須徳天皇、、崇徳天皇、景行天皇、後白河法皇、考霊天皇、推古天皇、天正天皇、蜂須賀家政、蜂須賀光隆、源義経、武蔵坊弁慶、山内一豊、山内忠義、伊達宗利、浅野内匠頭、伊達若狭守、円手院正澄、法華仙人、尭音、伊予守玉興、恵心僧都、熊野大権現、越智宿称玉純、越智宿称実勝、松平隠岐守、覚栄法印、覚深法親王、藤堂高虎、小早川隆影、頼富美毅師、松平頼重、朝祐法師、生駒一正。
ダークサイド。(笑)
悪蛇、長曽我部元親。
関連トピック。
四国八十八箇所遍路。
http://
映画「仏陀再誕」
http://
救世の法
http://
言うまでもなく、当会とはとても関係が深いですが、詳しい事は良く分らない・・・。
と言われる方に、八十八ヶ所の歴史を紐解いていきたいと思います。
実は、四国は意外な事に、聖地だったんです。
まず、仏教を日本へ布教させた聖徳太子。
奈良の大仏を建てた行基菩薩。
中国から5度の渡来に失敗し、失明をしたにもかかわらず6度目で日本へ来て、お寺を建てた鑑真。
香川県善通寺に生まれ、中国へ渡り、恵果和尚から密教の全てを託され、真言宗の開祖となった、弘法大師空海。
この方々が、実は四国八十八ヶ所、巡礼の基礎となるお寺を建てたり、仏像を彫ったりした事を、ご存じでしょうか?
空海は約半分の四十ヶ所のお寺を建てましたが、最後に八十八ヶ所のまとめ役として、この世に生を受けたとも言われております。
この八十八ヶ所の意味はなんであるか?と言いますと、実は地図を見てもらえると解りやすいのですが、四国をぐるっと一周しています。
これは結界を意味し、邪霊、悪霊の侵入を防ぐ為、と言われております。
では何の為の結界か?と言いますと、2500〜2600年前に、インドのお釈迦様が、「我、東の国にて再誕す」と予言を残されたのですが、それが日本の四国なのだそうです。
空海没1200年経ち、一周1200キロのこの四国八十八ヶ所も空海の「四国に鉄の橋が架かる時、私の使命も終わるであろう。」と予言を残し、四国に三つの橋が架かったため、この結界の役目は終わりを告げました。
前置きが長くなりましたが、この神秘の四国について、色々語りたいと思いますので、皆様よろしくお願いしたいと思います。
※主な登場人物。
弘法大師空海、行基菩薩、鑑真和上、聖徳太子、役行者小角、松法師、真念僧正、宥応法印、月峰上人、正澄上人、明神右京・隼人、恵明上人、真野長者、越智守興、日証上人、和気道善、和気道隆、義渕僧正、恵果和上、一遍上人、行教上人、智法大師、藤原不比等、運慶、湛慶、海覚、山本玄峰、義渕僧正、恵雲師、聖武天皇、光明皇后、嵯峨天皇、天武天皇、垣武天皇、平城天皇、後鳥羽天皇、後醍醐天皇、用命天皇、村山天皇、欽明天皇、孝謙天皇、淳和天皇、天智天皇、文徳天皇、高倉天皇、須徳天皇、、崇徳天皇、景行天皇、後白河法皇、考霊天皇、推古天皇、天正天皇、蜂須賀家政、蜂須賀光隆、源義経、武蔵坊弁慶、山内一豊、山内忠義、伊達宗利、浅野内匠頭、伊達若狭守、円手院正澄、法華仙人、尭音、伊予守玉興、恵心僧都、熊野大権現、越智宿称玉純、越智宿称実勝、松平隠岐守、覚栄法印、覚深法親王、藤堂高虎、小早川隆影、頼富美毅師、松平頼重、朝祐法師、生駒一正。
ダークサイド。(笑)
悪蛇、長曽我部元親。
関連トピック。
四国八十八箇所遍路。
http://
映画「仏陀再誕」
http://
救世の法
http://
|
|
|
|
コメント(109)
第六十九番・七宝山・「観音寺」
本尊・聖観世音菩薩
開基・日証上人
宗派・真言宗大覚寺派
住所・香川県観音寺市八幡町一丁目1の7
略縁起
大宝年間、日証上人によって開創された当時は神宮寺と号していた。
大同二年、留錫した弘法大師が聖観世音菩薩を刻み、安置する堂宇を琴弾山の中腹に建立し、その周辺に四十七基の仏塔を建て、七種の珍宝を埋めて地鎮したことにちなんで、それまでの山号を七宝山と改号した。と、共に当寺の第七世住職となられた大師は、南都興福寺にならって七堂伽藍を建立し、先に刻んだ聖観世音菩薩を本尊として中金堂に安置し、それまでの神宮寺の寺号を現在の観音寺と改号され、第六十九番札所と定められた。
また、右の由来を奉聞された朝廷は垣武、平城、亀山と代々にわたっての勅願所と定められたし、各武将たちからも厚い信仰を受けた。観音寺にある国宝は琴弾山絵縁起(絵という字は中がエの当て字です)があり涅槃、不動尊などの、諸仏もある。
明治の神仏分離令により、六十八番の本地仏を観音寺の西金堂に請来したことにより、一境内に二札所となった。
詠歌
かんおんの、だいひのちから、つよければ、おもきつみをも、ひきあげてたべ。
寛永通宝の銭形
裏山の琴弾山頂から見下せば、海辺に寛永通宝の銭形が見える。直径は120メートルと92メートルと、見下して丁度円形に見えるように、なかなかの工夫をしている。
弘法大師が杖で画かれたという時代の合わない話は別として、領内巡視の丸亀藩主京極高俊のために一夜のうちにつくりあげたものという。
本尊・聖観世音菩薩
開基・日証上人
宗派・真言宗大覚寺派
住所・香川県観音寺市八幡町一丁目1の7
略縁起
大宝年間、日証上人によって開創された当時は神宮寺と号していた。
大同二年、留錫した弘法大師が聖観世音菩薩を刻み、安置する堂宇を琴弾山の中腹に建立し、その周辺に四十七基の仏塔を建て、七種の珍宝を埋めて地鎮したことにちなんで、それまでの山号を七宝山と改号した。と、共に当寺の第七世住職となられた大師は、南都興福寺にならって七堂伽藍を建立し、先に刻んだ聖観世音菩薩を本尊として中金堂に安置し、それまでの神宮寺の寺号を現在の観音寺と改号され、第六十九番札所と定められた。
また、右の由来を奉聞された朝廷は垣武、平城、亀山と代々にわたっての勅願所と定められたし、各武将たちからも厚い信仰を受けた。観音寺にある国宝は琴弾山絵縁起(絵という字は中がエの当て字です)があり涅槃、不動尊などの、諸仏もある。
明治の神仏分離令により、六十八番の本地仏を観音寺の西金堂に請来したことにより、一境内に二札所となった。
詠歌
かんおんの、だいひのちから、つよければ、おもきつみをも、ひきあげてたべ。
寛永通宝の銭形
裏山の琴弾山頂から見下せば、海辺に寛永通宝の銭形が見える。直径は120メートルと92メートルと、見下して丁度円形に見えるように、なかなかの工夫をしている。
弘法大師が杖で画かれたという時代の合わない話は別として、領内巡視の丸亀藩主京極高俊のために一夜のうちにつくりあげたものという。
第七十番・七宝山・「本山寺」・持宝院
本尊・馬頭観世音菩薩(国宝・伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗高野派
住所・香川県三豊中町本山甲1445
略縁起
大同二年、(807)平城天皇の勅願により、国家鎮護を祈願した弘法大師が、一夜のうちに堂宇を建立し本尊として馬頭観世音菩薩を刻んで安置したのがはじまりであり、本尊彫刻と同時に刻んだ阿弥陀、薬師の両如来とも国宝である。
本山寺は珍しいことに、戦国の兵火や火災などはまぬがれている。ために久安三年建立の仁王門、大同四年建立の五重塔などは往古の姿そのままで残されている。
本堂は正安二年(1300)の建築で七間四面の堂宇は県内寺院では唯一の国宝建造物の指定をうけている。
前記の大同四年(809)弘法大師が建立したと伝えられている五重塔は、長い年月を経るにつれ内外部ともに損傷が激しく、見る影もない様となった。
原形復が悲願であった前住職・頼富美毅師が明治四十三年にようやく再建した。
詠歌
もとやまに、だれかうえける、はなれや、春こそたおれ、たむけにぞなる。
太刀受けの仏
天正年間、長曽我部元親が讃岐に進め入って来た時、ここに陣を構えようとした。断った時の住職に斬りつけたが、倒れたその僧には傷も付かず、御堂の中に入ると阿弥陀如来の腕から血が流れていたので、さすがの荒武者達も驚き恐れて退いたという。かくて、この寺は、戦火にかからなかった数少ない寺の一つとなった。
本尊・馬頭観世音菩薩(国宝・伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗高野派
住所・香川県三豊中町本山甲1445
略縁起
大同二年、(807)平城天皇の勅願により、国家鎮護を祈願した弘法大師が、一夜のうちに堂宇を建立し本尊として馬頭観世音菩薩を刻んで安置したのがはじまりであり、本尊彫刻と同時に刻んだ阿弥陀、薬師の両如来とも国宝である。
本山寺は珍しいことに、戦国の兵火や火災などはまぬがれている。ために久安三年建立の仁王門、大同四年建立の五重塔などは往古の姿そのままで残されている。
本堂は正安二年(1300)の建築で七間四面の堂宇は県内寺院では唯一の国宝建造物の指定をうけている。
前記の大同四年(809)弘法大師が建立したと伝えられている五重塔は、長い年月を経るにつれ内外部ともに損傷が激しく、見る影もない様となった。
原形復が悲願であった前住職・頼富美毅師が明治四十三年にようやく再建した。
詠歌
もとやまに、だれかうえける、はなれや、春こそたおれ、たむけにぞなる。
太刀受けの仏
天正年間、長曽我部元親が讃岐に進め入って来た時、ここに陣を構えようとした。断った時の住職に斬りつけたが、倒れたその僧には傷も付かず、御堂の中に入ると阿弥陀如来の腕から血が流れていたので、さすがの荒武者達も驚き恐れて退いたという。かくて、この寺は、戦火にかからなかった数少ない寺の一つとなった。
第七十一番・剣五山・「弥谷寺」・千手院
本尊・千手観世音菩薩(伝・弘法大師作)
開基・行基菩薩
宗派・真言宗善通寺派
住所・香川県三豊郡三野町大字見乙70
略縁起
天平年間、聖武天皇の勅願により行基菩薩が開創。
当山より八国が眺望できることにちなみ蓮華山・八国寺と号していた。
その頃、大師は真魚と呼ばれていたが、この岩窟で勉学されている。さらに延暦二十三年に入唐した大師は真言密教を受法。
帰国後の大同二年再度登山修行中、空中から五柄の剣が降る霊を感じたことにより剣五山と改号し、本尊を刻んで安置、弥谷寺と改号し七十一番札所と定められた。その後の天平年間、天霧城主、香川家没落の際全山焼失したが慶長年間、生駒讃岐守が再興している。
弥谷寺は岩盤の中に堂宇があり、四国霊場唯一の摩崖仏(岩盤に刻まれた阿弥陀三尊)、大師堂背後の奥の院聞持窟、洞の地蔵尊、大師瑜加護摩修行窟、大師加持水などがあり、さらには阿弥陀三尊の岩盤に大師が彫りつけられた弥陀宝号、梵字などがあり、さらに大師が唐の国から請来したという金銅五鈷鈴がある。
詠歌
悪人と、ゆきづれなんも、いやだにじ、ただかりそめも、良き友ぞよき。
八万四千体の石仏
死者の霊を背負ってこの山に登る風習がある。
「その数をかぞへつくすべからず」(本居宣長)とある山内の石仏群は、その風習の象徴だろうか。そしてそれは「往古の人、至而貴人にあらずんば別に墳墓をばきづく事なし、唯此のごとく自然の石へおもふままに彫付しもと見へたり」(讃岐廻遊記)と言うことだろうか。
本尊・千手観世音菩薩(伝・弘法大師作)
開基・行基菩薩
宗派・真言宗善通寺派
住所・香川県三豊郡三野町大字見乙70
略縁起
天平年間、聖武天皇の勅願により行基菩薩が開創。
当山より八国が眺望できることにちなみ蓮華山・八国寺と号していた。
その頃、大師は真魚と呼ばれていたが、この岩窟で勉学されている。さらに延暦二十三年に入唐した大師は真言密教を受法。
帰国後の大同二年再度登山修行中、空中から五柄の剣が降る霊を感じたことにより剣五山と改号し、本尊を刻んで安置、弥谷寺と改号し七十一番札所と定められた。その後の天平年間、天霧城主、香川家没落の際全山焼失したが慶長年間、生駒讃岐守が再興している。
弥谷寺は岩盤の中に堂宇があり、四国霊場唯一の摩崖仏(岩盤に刻まれた阿弥陀三尊)、大師堂背後の奥の院聞持窟、洞の地蔵尊、大師瑜加護摩修行窟、大師加持水などがあり、さらには阿弥陀三尊の岩盤に大師が彫りつけられた弥陀宝号、梵字などがあり、さらに大師が唐の国から請来したという金銅五鈷鈴がある。
詠歌
悪人と、ゆきづれなんも、いやだにじ、ただかりそめも、良き友ぞよき。
八万四千体の石仏
死者の霊を背負ってこの山に登る風習がある。
「その数をかぞへつくすべからず」(本居宣長)とある山内の石仏群は、その風習の象徴だろうか。そしてそれは「往古の人、至而貴人にあらずんば別に墳墓をばきづく事なし、唯此のごとく自然の石へおもふままに彫付しもと見へたり」(讃岐廻遊記)と言うことだろうか。
第七十二番・我拝師山・「曼荼羅寺」・延命院
本尊・大日如来(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗善通寺派
住所・香川県善通寺市吉原町1380-1
略縁起
弘法大師の一族である佐伯家の氏寺として推古四年(596)の建立であり、当時は世坂寺と号していた。
大同二年(807)唐より帰国した大師が母御の菩提を祈らんがため、唐の青竜寺に模した堂塔を建立し、本尊として大日如来を勧請、御請来の金剛界、胎蔵界の両界曼荼羅を安置し奉ったことにちなみ、それまでの寺号を、現在のそれに改称され七十二番札所と定められた。
曼荼羅寺の境内には県指定の不老松(通称・笠松)がある。樹高四メートル、円形状に広がった枝葉は二百平方メートルの地上を覆っている。
この松は大師が曼荼羅寺と改称された記念にお手植えされたもの。
また、この寺の近辺には「四国のかたへまかりける 同行の・・・。」云々という同行の者を懐かしんで詠んだ西行法師の仮住居・水茎庵がある。
詠歌
わずかにも、まんだらおがむ人はただ、ふたたび、みたび、かえらざらまし。
遍路が寄進した茶堂
山門を入り、堀にかかった石橋を渡ると、右側に茶堂がある。
これは、兵庫県から遍路に出て、昭和七年までの五十年間に貯めた一万円を全てこの寺に寄進し、そのうちの二千円で茶堂を建て、そこで死んだ信部長蔵という人のものである。今も本堂前にその寄進を記した石が立っている。
本尊・大日如来(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗善通寺派
住所・香川県善通寺市吉原町1380-1
略縁起
弘法大師の一族である佐伯家の氏寺として推古四年(596)の建立であり、当時は世坂寺と号していた。
大同二年(807)唐より帰国した大師が母御の菩提を祈らんがため、唐の青竜寺に模した堂塔を建立し、本尊として大日如来を勧請、御請来の金剛界、胎蔵界の両界曼荼羅を安置し奉ったことにちなみ、それまでの寺号を、現在のそれに改称され七十二番札所と定められた。
曼荼羅寺の境内には県指定の不老松(通称・笠松)がある。樹高四メートル、円形状に広がった枝葉は二百平方メートルの地上を覆っている。
この松は大師が曼荼羅寺と改称された記念にお手植えされたもの。
また、この寺の近辺には「四国のかたへまかりける 同行の・・・。」云々という同行の者を懐かしんで詠んだ西行法師の仮住居・水茎庵がある。
詠歌
わずかにも、まんだらおがむ人はただ、ふたたび、みたび、かえらざらまし。
遍路が寄進した茶堂
山門を入り、堀にかかった石橋を渡ると、右側に茶堂がある。
これは、兵庫県から遍路に出て、昭和七年までの五十年間に貯めた一万円を全てこの寺に寄進し、そのうちの二千円で茶堂を建て、そこで死んだ信部長蔵という人のものである。今も本堂前にその寄進を記した石が立っている。
第七十三番・我拝師山・「出釈迦寺」・求聞持院
本尊・釈迦如来(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗御室派
住所・香川県善通寺市吉原町1091
略縁起
弘法大師七歳の時、仏道にはいる証しを得ようとして、四八一メートルの倭斯濃山(わしのざん)の頂きに立ち「仏道に入り、衆生を救わんとするわが願い、成就するものならば霊験を、さもなくば、賭したこの身を諸仏に奉げる。」と念じて截りたつ断崖から身を躍らせた。と、落下する大師の下方に紫雲がたなびき、蓮華の花に座した釈迦如来が出現「一生成仏」の宣を授け、大師の願いは叶えられたという。
そこで大師は、出現した釈迦如来の尊像を刻んで本尊とし、出釈迦寺と命名の寺をその麓に創建すると共に、得た霊験から山号を我拝師山と改称せられた。
大師が命をかけた霊蹟は捨身ヶ嶽禅定(しゃしんがけぜんじょう)といい、寺より一・八キロほど登った山の断崖に奥の院としてあり、麓の寺と共に衆生済度発願の根本道場として残っている。
詠歌
まよいぬる、とくどぅ衆生、すくわんと、とうとき山に、いずるしゃかでら。
西行法師の山里庵
仁安三年(1168)西行法師がここ讃岐の国へ下って来た。それは一つには歌の道の友であった崇徳上皇の陵(山峰)に詣でることであり、今一つは僧となった身として、弘法大師の遺跡を訪うことであった。
この寺の裏山に山里庵という庵を結んでいたことが、その歌集「山家集」に書かれている。
本尊・釈迦如来(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗御室派
住所・香川県善通寺市吉原町1091
略縁起
弘法大師七歳の時、仏道にはいる証しを得ようとして、四八一メートルの倭斯濃山(わしのざん)の頂きに立ち「仏道に入り、衆生を救わんとするわが願い、成就するものならば霊験を、さもなくば、賭したこの身を諸仏に奉げる。」と念じて截りたつ断崖から身を躍らせた。と、落下する大師の下方に紫雲がたなびき、蓮華の花に座した釈迦如来が出現「一生成仏」の宣を授け、大師の願いは叶えられたという。
そこで大師は、出現した釈迦如来の尊像を刻んで本尊とし、出釈迦寺と命名の寺をその麓に創建すると共に、得た霊験から山号を我拝師山と改称せられた。
大師が命をかけた霊蹟は捨身ヶ嶽禅定(しゃしんがけぜんじょう)といい、寺より一・八キロほど登った山の断崖に奥の院としてあり、麓の寺と共に衆生済度発願の根本道場として残っている。
詠歌
まよいぬる、とくどぅ衆生、すくわんと、とうとき山に、いずるしゃかでら。
西行法師の山里庵
仁安三年(1168)西行法師がここ讃岐の国へ下って来た。それは一つには歌の道の友であった崇徳上皇の陵(山峰)に詣でることであり、今一つは僧となった身として、弘法大師の遺跡を訪うことであった。
この寺の裏山に山里庵という庵を結んでいたことが、その歌集「山家集」に書かれている。
第七十四番・医王山・「甲山寺」・多宝院
本尊・薬師如来(座像二寸五尺)(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗善通寺派
住所・香川県善通寺市弘田町1765
略縁起
弘法大師は、善通寺と曼荼羅寺との間に伽藍を建立せんとして霊地を求め探していた時、この山麓の岩窟から一人の老翁が現れ「ここが探し求めている霊地なり。一寺を建立せよ」との霊示を受けた。
大師は早速、石を割って毘沙門天を刻んで安置したのがはじまりだと伝えられる。
そののち弘仁十二年。嵯峨天皇より満濃池の修築を下命された大師は、その年の五月に下向し、当寺で工事の完成祈願の秘法を修し、さらに成功を願って座像二尺五寸の薬師如来像を刻んで安置した。
黒四ダム七分の一の貯水量を誇る満濃池は、弘仁九年に大決壊、朝廷が派遣した築池使の手には負えなかった。
大師が監督するや、あれ程手を焼いた難工事も僅か三ヶ月で完成。
大師はこれ偏に薬師如来の加護であるとし、勅賜金の一部で堂塔を建立、先の薬師如来を本尊として祀り医王山と命名した。
寺号は山の形が毘沙門天の甲ににていることから甲山寺と号したという。
詠歌
十二神、みかたにもてる、いくさには、おのれとこころ、かぶとやまかな。
大師のままごと遊びの遺跡
大師は、多度郡の郡司であった父、佐伯直田公(善通)と、母、阿刀氏(玉依姫)の三男として宝亀五年(774)六月十五日、この地に誕生した。
幼名を真魚と言い、小さい時から土で仏を作って祀るという遊びをよくした。その遊び場はこの寺の東の辺りで、仙遊が原と言い、地蔵堂やその飼犬を埋めたという犬塚などがある。
本尊・薬師如来(座像二寸五尺)(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗善通寺派
住所・香川県善通寺市弘田町1765
略縁起
弘法大師は、善通寺と曼荼羅寺との間に伽藍を建立せんとして霊地を求め探していた時、この山麓の岩窟から一人の老翁が現れ「ここが探し求めている霊地なり。一寺を建立せよ」との霊示を受けた。
大師は早速、石を割って毘沙門天を刻んで安置したのがはじまりだと伝えられる。
そののち弘仁十二年。嵯峨天皇より満濃池の修築を下命された大師は、その年の五月に下向し、当寺で工事の完成祈願の秘法を修し、さらに成功を願って座像二尺五寸の薬師如来像を刻んで安置した。
黒四ダム七分の一の貯水量を誇る満濃池は、弘仁九年に大決壊、朝廷が派遣した築池使の手には負えなかった。
大師が監督するや、あれ程手を焼いた難工事も僅か三ヶ月で完成。
大師はこれ偏に薬師如来の加護であるとし、勅賜金の一部で堂塔を建立、先の薬師如来を本尊として祀り医王山と命名した。
寺号は山の形が毘沙門天の甲ににていることから甲山寺と号したという。
詠歌
十二神、みかたにもてる、いくさには、おのれとこころ、かぶとやまかな。
大師のままごと遊びの遺跡
大師は、多度郡の郡司であった父、佐伯直田公(善通)と、母、阿刀氏(玉依姫)の三男として宝亀五年(774)六月十五日、この地に誕生した。
幼名を真魚と言い、小さい時から土で仏を作って祀るという遊びをよくした。その遊び場はこの寺の東の辺りで、仙遊が原と言い、地蔵堂やその飼犬を埋めたという犬塚などがある。
第七十五番・五岳山・「善通寺」・誕生院
本尊・薬師如来(座像一丈六尺)
開基・弘法大師
宗派・真言宗善通寺派総本山
住所・香川県善通寺市善通寺町3〜3〜1
略縁起
弘法大師ご誕生の霊蹟である。
寺は屏風ヶ浦五岳山誕生院・総本山善通寺と号し、真言宗善通寺派の総本山である。
唐から帰朝した大師は大同二年(807)先祖の氏寺を建立せんとして、父善通郷から寺領として荘園四町余を拝受し、そこにかつて学んだ唐の青竜寺に模した堂宇を建てた。
寺号は父の名をとって、善通寺と命名。山号は背後の五つの山にちなんで五岳山と号し、院号は大師誕生せしところより誕生院と名づけられたという。
境内にはご両親及び稚児大師木像、産湯の井戸、御影池、瞬目大師、二十日橋、後嵯峨、亀山、後宇多の三帝御廊、大樟、法然上人逆修塔、足利尊氏利生塔仙遊ヶ原、西行庵と久之松、旅大師、雲気、大麻など五大明神があり、国宝に行基菩薩作地蔵尊、大師作吉祥天、大師母公筆の法華経序品一巻や三国伝来の金銅錫杖がある。
広大な境内に建つ五重の塔はときとして目も覚めるような黄金色に包まれて映える事がある。
詠歌
われすまば、よもきえはてじ、善通寺、ふかきちかいの、のりのともしび。
八十九メートルの戒壇めぐり
仁王門をくぐれば、西院坊の御影堂に進む。その地下に、能満所願の本尊をお祀りした戒壇めぐりがある。
真っ暗な中を、左手で壁をなでながら89メートルを行く。
だんだん怖くなり「南無大師遍照金剛」が自然に口に出る。中程の、大師がお生まれになった下の所に祭壇が設けられてあり、その御灯明の明るさでほっとする。
本尊・薬師如来(座像一丈六尺)
開基・弘法大師
宗派・真言宗善通寺派総本山
住所・香川県善通寺市善通寺町3〜3〜1
略縁起
弘法大師ご誕生の霊蹟である。
寺は屏風ヶ浦五岳山誕生院・総本山善通寺と号し、真言宗善通寺派の総本山である。
唐から帰朝した大師は大同二年(807)先祖の氏寺を建立せんとして、父善通郷から寺領として荘園四町余を拝受し、そこにかつて学んだ唐の青竜寺に模した堂宇を建てた。
寺号は父の名をとって、善通寺と命名。山号は背後の五つの山にちなんで五岳山と号し、院号は大師誕生せしところより誕生院と名づけられたという。
境内にはご両親及び稚児大師木像、産湯の井戸、御影池、瞬目大師、二十日橋、後嵯峨、亀山、後宇多の三帝御廊、大樟、法然上人逆修塔、足利尊氏利生塔仙遊ヶ原、西行庵と久之松、旅大師、雲気、大麻など五大明神があり、国宝に行基菩薩作地蔵尊、大師作吉祥天、大師母公筆の法華経序品一巻や三国伝来の金銅錫杖がある。
広大な境内に建つ五重の塔はときとして目も覚めるような黄金色に包まれて映える事がある。
詠歌
われすまば、よもきえはてじ、善通寺、ふかきちかいの、のりのともしび。
八十九メートルの戒壇めぐり
仁王門をくぐれば、西院坊の御影堂に進む。その地下に、能満所願の本尊をお祀りした戒壇めぐりがある。
真っ暗な中を、左手で壁をなでながら89メートルを行く。
だんだん怖くなり「南無大師遍照金剛」が自然に口に出る。中程の、大師がお生まれになった下の所に祭壇が設けられてあり、その御灯明の明るさでほっとする。
第七十六番・鶏足山・「金倉寺」(こんぞうじ)・宝幢院(ほうどういん)
本尊・薬師如来(伝・智証大師作)
開基・和気道善
宗派・天台寺門宗
住所・香川県善通寺市金蔵寺町1160
略縁起
宝亀五年(774)長者和気道善の開基で当時は道善寺と号した。
もともと当山は弘法大師の甥で、のち延暦寺五代座主となり三井園城寺を賜った智証大師のご生誕地である。
のち唐から帰朝した大師が、先祖の菩提の為に伽藍を造営し、薬師如来を刻み、本尊として安置した。
金倉寺と改称したのは延長六年(928)醍醐天皇の勅命によるものであり、この地の郷の名をとって命名、山号は迦葉尊者の入定地にあやかってである。
その後、広大な寺領や百三十二坊、数十の神仏閣堂宇は建武の争乱、さらに、永正、天文と続いた兵火に遭ってことごとく焼失した。
以来、境内の一隅に小庵を建て、そこに本尊を安置して法灯を守りつづけた。
再興となったのは、寛永年間の末期頃のことであり、讃岐の大守・松平頼重公によってである。
寺宝に金胎両部曼荼羅大般若経、十六善神像、絹本着色智証大師御自像があり、境内には乃木将軍妻返しの松がある。
詠歌
まことにも、神仏僧を、ひらくれば、しんごんかんじの、ふしぎなりけり。
讃岐の五大師
貞観八年(866)最澄に伝教大師という大師号が贈られてから、明治になるまでに、十七人の大師が生まれている。
そのうち、この寺から出た、智証、「大師は弘法」の弘法、空海と同じ佐伯氏出身の道興、空海の俗弟子法光、修験の理源と、五人が讃岐出身であり、世にこれを「讃岐の五大師」と呼ぶ。
本尊・薬師如来(伝・智証大師作)
開基・和気道善
宗派・天台寺門宗
住所・香川県善通寺市金蔵寺町1160
略縁起
宝亀五年(774)長者和気道善の開基で当時は道善寺と号した。
もともと当山は弘法大師の甥で、のち延暦寺五代座主となり三井園城寺を賜った智証大師のご生誕地である。
のち唐から帰朝した大師が、先祖の菩提の為に伽藍を造営し、薬師如来を刻み、本尊として安置した。
金倉寺と改称したのは延長六年(928)醍醐天皇の勅命によるものであり、この地の郷の名をとって命名、山号は迦葉尊者の入定地にあやかってである。
その後、広大な寺領や百三十二坊、数十の神仏閣堂宇は建武の争乱、さらに、永正、天文と続いた兵火に遭ってことごとく焼失した。
以来、境内の一隅に小庵を建て、そこに本尊を安置して法灯を守りつづけた。
再興となったのは、寛永年間の末期頃のことであり、讃岐の大守・松平頼重公によってである。
寺宝に金胎両部曼荼羅大般若経、十六善神像、絹本着色智証大師御自像があり、境内には乃木将軍妻返しの松がある。
詠歌
まことにも、神仏僧を、ひらくれば、しんごんかんじの、ふしぎなりけり。
讃岐の五大師
貞観八年(866)最澄に伝教大師という大師号が贈られてから、明治になるまでに、十七人の大師が生まれている。
そのうち、この寺から出た、智証、「大師は弘法」の弘法、空海と同じ佐伯氏出身の道興、空海の俗弟子法光、修験の理源と、五人が讃岐出身であり、世にこれを「讃岐の五大師」と呼ぶ。
第七十七番・桑多山・「道隆寺」(どうりゅうじ)・明王院
本尊・薬師如来(立像二尺五寸)(伝・弘法大師作)
開基・和気道隆
宗派・真言宗醍醐派
住所・香川県多度津郡多度津町北鴨一丁目
略縁起
当寺領はもと和気道隆公の荘園であった。
この荘園内の桑畑で天平勝宝元年(749)のある夜、怪光が起きた。
道隆公は怪光を退治したが、そのとき誤って乳母を射殺。道隆公は乳母の供養を願い、桑の木で薬師如来像を刻み、それを安置するための堂宇を建立したのがはじまりである。
その後、第二代住職・朝祐法師が七堂伽藍を建立し、寺号を開祖の名をとって道隆寺と名づけたという。
のち、諸国を行脚中の弘法大師が当寺に留錫され、二尺五寸立像の薬師如来を刻み、道隆公の掘った小像を胎内に納めて本尊とし、四国第七十七番札所と定められた。
開創者、和気道隆公の廟は本坊に祀ってあり、また観音堂には理源大師作の観世音菩薩が、さらに持仏堂には智証大師作の大日如来が安置されている。
ちなみに、境内には百観音像がある。
詠歌
ねがいをば、ぶつどうりゅうに、入りはてて、ぼだいの月を、見ましほしさに。
多宝塔の建立
四国札所には現在五重塔が三塔ある。70番本山寺、75番善通寺、86番志度寺で、全部香川県であることも面白い。
この寺にも、かつて五重塔が建っていたが、天正三年(1574)長曽我部元親によって焼かれた。
今、その跡に、昭和五十五年春完成した二層の多宝塔がある。
本尊・薬師如来(立像二尺五寸)(伝・弘法大師作)
開基・和気道隆
宗派・真言宗醍醐派
住所・香川県多度津郡多度津町北鴨一丁目
略縁起
当寺領はもと和気道隆公の荘園であった。
この荘園内の桑畑で天平勝宝元年(749)のある夜、怪光が起きた。
道隆公は怪光を退治したが、そのとき誤って乳母を射殺。道隆公は乳母の供養を願い、桑の木で薬師如来像を刻み、それを安置するための堂宇を建立したのがはじまりである。
その後、第二代住職・朝祐法師が七堂伽藍を建立し、寺号を開祖の名をとって道隆寺と名づけたという。
のち、諸国を行脚中の弘法大師が当寺に留錫され、二尺五寸立像の薬師如来を刻み、道隆公の掘った小像を胎内に納めて本尊とし、四国第七十七番札所と定められた。
開創者、和気道隆公の廟は本坊に祀ってあり、また観音堂には理源大師作の観世音菩薩が、さらに持仏堂には智証大師作の大日如来が安置されている。
ちなみに、境内には百観音像がある。
詠歌
ねがいをば、ぶつどうりゅうに、入りはてて、ぼだいの月を、見ましほしさに。
多宝塔の建立
四国札所には現在五重塔が三塔ある。70番本山寺、75番善通寺、86番志度寺で、全部香川県であることも面白い。
この寺にも、かつて五重塔が建っていたが、天正三年(1574)長曽我部元親によって焼かれた。
今、その跡に、昭和五十五年春完成した二層の多宝塔がある。
第七十八番・仏光山・「郷照寺」・広徳院
本尊・阿弥陀如来(座像一尺八寸)
開基・行基菩薩
宗派・時宗
住所・香川県綾歌郡宇多津町1435
略縁起
神亀二年(725)行基菩薩が開創し、一尺八寸の阿弥陀如来を刻んで本尊として安置、仏光山・道場寺と命名した。
その後の大同二年(807)来錫した弘法大師は、当寺領に端霊を感得、真言密教有縁の地なりとて当寺を四国第七十八番札所と定められた。
さらに正応元年(1288)来錫した一遍上人は、一遍流の法門による光明を大衆に与えたことにより踊り念仏する念仏道場になった。と、共にそれまでの真言宗を一遍上人の時宗に改宗した。なお、このとき、寺号が七十七番の道隆寺と誤りやすいため、郷照寺と改号されている。
郷照寺も天正の兵火にあって堂塔は焼失したが、ときの住職の努力によって文禄二年に再興している。
ちなみに、この時宗なる宗派は四国霊場中唯一のものである。
なお、現在は厄除けの寺として知られる。
詠歌
おどりはね、ねんぶつ申す、道場寺、ひょうしをそろへ、かねをうつなり。
札所と宗派
弘法大師との結びつきが強く、またそれが特色ともなっているので、四国霊場の札所は全て真言宗と思っている人も多いが、そうではない。
江戸時代には神社までが札所であったし、現在でも天台宗が四ヶ寺、(43・76・82・87)、禅宗が三ヶ寺(11・15・87)、時宗が一ヶ寺(この寺)となっている。
本尊・阿弥陀如来(座像一尺八寸)
開基・行基菩薩
宗派・時宗
住所・香川県綾歌郡宇多津町1435
略縁起
神亀二年(725)行基菩薩が開創し、一尺八寸の阿弥陀如来を刻んで本尊として安置、仏光山・道場寺と命名した。
その後の大同二年(807)来錫した弘法大師は、当寺領に端霊を感得、真言密教有縁の地なりとて当寺を四国第七十八番札所と定められた。
さらに正応元年(1288)来錫した一遍上人は、一遍流の法門による光明を大衆に与えたことにより踊り念仏する念仏道場になった。と、共にそれまでの真言宗を一遍上人の時宗に改宗した。なお、このとき、寺号が七十七番の道隆寺と誤りやすいため、郷照寺と改号されている。
郷照寺も天正の兵火にあって堂塔は焼失したが、ときの住職の努力によって文禄二年に再興している。
ちなみに、この時宗なる宗派は四国霊場中唯一のものである。
なお、現在は厄除けの寺として知られる。
詠歌
おどりはね、ねんぶつ申す、道場寺、ひょうしをそろへ、かねをうつなり。
札所と宗派
弘法大師との結びつきが強く、またそれが特色ともなっているので、四国霊場の札所は全て真言宗と思っている人も多いが、そうではない。
江戸時代には神社までが札所であったし、現在でも天台宗が四ヶ寺、(43・76・82・87)、禅宗が三ヶ寺(11・15・87)、時宗が一ヶ寺(この寺)となっている。
第七十九番・金華山・「天皇寺」・高照院
本尊・十一面観世音菩薩(立像・二尺三寸)(弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗御室派
住所・香川県坂出市西庄町字天皇1713の2
略縁起
弘仁年間、この地に来錫した弘法大師は空中より霊妙の声を訊いた。
大師は早速、八十八の霊泉で得た霊木で十一面観世音菩薩、愛染明王、阿弥陀如来の三尊像を刻み、堂宇を建立して金華山・摩尼珠院・妙成就寺と名づけて四国第七十九番札所と定められた。
その後、保元の乱で敗れ、讃岐の地に流され鼓ヶ岡で崩御された崇徳上皇。その死を京の都へ奉聞するあいだ天皇の柩を安置したのがこの寺であり、そのことから寺号を天皇寺と改号した。ちなみに、崩御した崇徳天皇を祀ってあるのは八十一番・白峰寺である。
この寺も天正の長曽我部の兵火にかかって全山焼失したが、天和二年二月に再興した。
さらに明治初年の神仏分離令によって一時廃寺となっていたが、末寺の高照院を合併して再興をはかり以後、高照院と改号した。
詠歌
十らくの、浮きよの中を、たずぬべし、天皇さえも、さすらいぞある。
やそばの清水
景行天皇の御代、讃留霊王は瀬戸内海を荒らしていた悪魚を退治した。
その時八十八人の兵士と共にその毒気に当たって気を失ったが、童子の捧げたこの地の泉の水によって皆蘇生した。
以来この泉を八十八の水、弥蘇場の水と呼ぶ。
一時はこの水を売って歩く商売さえあったし、現在はこの泉に冷やされた心太(ところてん)が有名である。
本尊・十一面観世音菩薩(立像・二尺三寸)(弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗御室派
住所・香川県坂出市西庄町字天皇1713の2
略縁起
弘仁年間、この地に来錫した弘法大師は空中より霊妙の声を訊いた。
大師は早速、八十八の霊泉で得た霊木で十一面観世音菩薩、愛染明王、阿弥陀如来の三尊像を刻み、堂宇を建立して金華山・摩尼珠院・妙成就寺と名づけて四国第七十九番札所と定められた。
その後、保元の乱で敗れ、讃岐の地に流され鼓ヶ岡で崩御された崇徳上皇。その死を京の都へ奉聞するあいだ天皇の柩を安置したのがこの寺であり、そのことから寺号を天皇寺と改号した。ちなみに、崩御した崇徳天皇を祀ってあるのは八十一番・白峰寺である。
この寺も天正の長曽我部の兵火にかかって全山焼失したが、天和二年二月に再興した。
さらに明治初年の神仏分離令によって一時廃寺となっていたが、末寺の高照院を合併して再興をはかり以後、高照院と改号した。
詠歌
十らくの、浮きよの中を、たずぬべし、天皇さえも、さすらいぞある。
やそばの清水
景行天皇の御代、讃留霊王は瀬戸内海を荒らしていた悪魚を退治した。
その時八十八人の兵士と共にその毒気に当たって気を失ったが、童子の捧げたこの地の泉の水によって皆蘇生した。
以来この泉を八十八の水、弥蘇場の水と呼ぶ。
一時はこの水を売って歩く商売さえあったし、現在はこの泉に冷やされた心太(ところてん)が有名である。
第八十番・白牛山・「國分寺」・千手院
本尊・千手観音菩薩(立像一尺六寸)(行基菩薩)
開基・行基菩薩
宗派・真言宗御室派
住所・香川県綾歌郡国分寺町国分
略縁起
天平十三年(741)聖武天皇は各国に国分寺を建立せよと宣を賜れた。
この寺はその勅命により、行基菩薩が建てた讃岐の国分寺である。
この開創から時代が降った弘仁年間、四国を巡錫中の弘法大師が当寺に久しく留錫され、行基作の五・三メートルの大立像(本尊)の損傷個所を補修、そして四国第八十番札所と定められた。
それから時代が推移した天正年間長曽我部の兵火にあって堂塔の殆どは焼失したが、本堂と鐘楼だけは難を逃れた。
本尊は明治三十四年に国宝に指定。
鎌倉中期建立の本堂は同三十六年に国宝指定。
また、高松藩主・生駒一正公と因縁浅からぬ鐘は、昭和十六年に国宝指定。
さらに特別史蹟に指定されている境内には、往時、建立されていた七重大塔の塔跡に礎石が十四個、金堂跡に三十三個の礎石が遺されていて、往古の姿を偲ばせている。
詠歌
国をわけ、野山をしのぎ、てらでらに、まいれる人を、たすけましませ。
鐘の返却証文
この寺の鐘は、もと香川郡塩江町安原の鮎滝の渕に住む大蛇がかぶっていたものと言う。
その音色が素晴らしいので、藩主生駒一正が時報に使おうと、田、二ヘクタールと交換に城へ持ち帰った。ところがさっぱり鳴らず、遂には「もとの国分寺へいぬー」と鳴った。
殿様が鐘を返した時の証文が今に遺っている。
本尊・千手観音菩薩(立像一尺六寸)(行基菩薩)
開基・行基菩薩
宗派・真言宗御室派
住所・香川県綾歌郡国分寺町国分
略縁起
天平十三年(741)聖武天皇は各国に国分寺を建立せよと宣を賜れた。
この寺はその勅命により、行基菩薩が建てた讃岐の国分寺である。
この開創から時代が降った弘仁年間、四国を巡錫中の弘法大師が当寺に久しく留錫され、行基作の五・三メートルの大立像(本尊)の損傷個所を補修、そして四国第八十番札所と定められた。
それから時代が推移した天正年間長曽我部の兵火にあって堂塔の殆どは焼失したが、本堂と鐘楼だけは難を逃れた。
本尊は明治三十四年に国宝に指定。
鎌倉中期建立の本堂は同三十六年に国宝指定。
また、高松藩主・生駒一正公と因縁浅からぬ鐘は、昭和十六年に国宝指定。
さらに特別史蹟に指定されている境内には、往時、建立されていた七重大塔の塔跡に礎石が十四個、金堂跡に三十三個の礎石が遺されていて、往古の姿を偲ばせている。
詠歌
国をわけ、野山をしのぎ、てらでらに、まいれる人を、たすけましませ。
鐘の返却証文
この寺の鐘は、もと香川郡塩江町安原の鮎滝の渕に住む大蛇がかぶっていたものと言う。
その音色が素晴らしいので、藩主生駒一正が時報に使おうと、田、二ヘクタールと交換に城へ持ち帰った。ところがさっぱり鳴らず、遂には「もとの国分寺へいぬー」と鳴った。
殿様が鐘を返した時の証文が今に遺っている。
第八十一番・綾松山(りょうしょうざん)・「白峰寺」・洞林院
本尊・千手観世音菩薩(立像三尺三寸)(智証大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗御室派
住所・香川県坂出市青海町2635
略縁起
弘仁六年(815)白峰山に登られた弘法大師は山頂に如意宝珠埋め、閼伽井を掘って衆生済度を祈願された。
ついで、貞観二年(860)十月に来錫した智証大師は、白峰大権現の「海上にまで届く異光あり、その霊木で本尊を刻むべし」とのご神託を受け、早速その霊木で千手観音菩薩を刻んで本尊とした。
この寺も盛衰の歴史を繰り返していて、本堂は慶長四年、高松藩主・生駒家が再建したものであり、大師堂は文化八年、松平頼儀公が老臣佐藤掃部と共に再建している。
また、保元の乱で讃岐に配流、崩御された崇徳上皇の御陵、その菩提をとむらう頓証寺殿がある。
宝物館には国宝の後小松天皇の宸筆下賜された「頓証寺」の扁額、上皇宸筆六字名号掛軸、光明皇后御筆法華経、大師御筆地蔵尊、智証大師御自筆の画像などが保管されている。
詠歌
しもさむく、つゆしろたえの、てらのうち、みなをとなふる、のりのこえごえ。
ほととぎすの落とし文
勅願門前の欅(けやき)の木を、玉章の木といい、その巻いた落ち葉を「ほととぎすの落とし文」という。
昔、この国に流された崇徳上皇が都恋しさに、啼ばきく聞けば都ぞ慕はるる此里過ぎよ山杜鵑(ほととぎす)
と歌われたので、杜鵑がこの木の葉をくちばしに巻いて、つまり鳴き声を出さず、しかし訪れた印にこれを落としたということからの名である。
本尊・千手観世音菩薩(立像三尺三寸)(智証大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗御室派
住所・香川県坂出市青海町2635
略縁起
弘仁六年(815)白峰山に登られた弘法大師は山頂に如意宝珠埋め、閼伽井を掘って衆生済度を祈願された。
ついで、貞観二年(860)十月に来錫した智証大師は、白峰大権現の「海上にまで届く異光あり、その霊木で本尊を刻むべし」とのご神託を受け、早速その霊木で千手観音菩薩を刻んで本尊とした。
この寺も盛衰の歴史を繰り返していて、本堂は慶長四年、高松藩主・生駒家が再建したものであり、大師堂は文化八年、松平頼儀公が老臣佐藤掃部と共に再建している。
また、保元の乱で讃岐に配流、崩御された崇徳上皇の御陵、その菩提をとむらう頓証寺殿がある。
宝物館には国宝の後小松天皇の宸筆下賜された「頓証寺」の扁額、上皇宸筆六字名号掛軸、光明皇后御筆法華経、大師御筆地蔵尊、智証大師御自筆の画像などが保管されている。
詠歌
しもさむく、つゆしろたえの、てらのうち、みなをとなふる、のりのこえごえ。
ほととぎすの落とし文
勅願門前の欅(けやき)の木を、玉章の木といい、その巻いた落ち葉を「ほととぎすの落とし文」という。
昔、この国に流された崇徳上皇が都恋しさに、啼ばきく聞けば都ぞ慕はるる此里過ぎよ山杜鵑(ほととぎす)
と歌われたので、杜鵑がこの木の葉をくちばしに巻いて、つまり鳴き声を出さず、しかし訪れた印にこれを落としたということからの名である。
第八十二番・青峰山「根香寺」(ねごろじ)・千手院
本尊・千手観音菩薩(座像三尺八寸)(伝・智証大師作)
開基・弘法大師
宗派・単立
住所・香川県高松市中山1506
略縁起
弘仁年間、巡錫中の弘法大師は当地で金剛界曼荼羅の五智如来を感得した。
大師はその事にちなんでこの山を青峰、赤嶺、黒峰、黄色峰、白峰と命名され、その中の青峰に花蔵院を創建し、五大明王を祀られた。
その後の天長九年(832)智証大師が来錫したとき市之瀬明神が現れ「この地は霊地なり」との信託があった。
よって智証大師は蓮華谷の香木で千手観音を刻み、千手院を創建して安置した。
この両大師の創建した花蔵院、千手院の二院を総称したものが寺号となった。
また、一説によると、千手観音を刻んだ香木の根株が永いあいだ香気を発散させていたことから根香寺と名づけられたともいう。
根香寺は後白河法皇の勅願所となり寺領を下賜されたが、その後の度重なる兵火で堂宇は荒れ寺運は衰退していたが、高松藩主・松平頼重公によって再興された。
秘仏の本尊は三十三年目に一度の開扉。
詠歌
よいのまの、たえふるしもの、消えぬれば、あとこそかねの、ごんぎょうのこえ。
牛鬼と山田蔵人
昔この山に、牛鬼と呼ばれる怪物が住んで人々を困らせていたので、殿様は香川郡安原の弓の名人山田蔵人高清に命じて退治させた。
高清は、その褒美に頂いた、米六石と共にこの牛鬼の角(長さ36センチ)を当寺に納めた。
当寺には、今もその角と文化三年(1806)に石虎という人が描いた牛鬼の軸とが伝わっている。
本尊・千手観音菩薩(座像三尺八寸)(伝・智証大師作)
開基・弘法大師
宗派・単立
住所・香川県高松市中山1506
略縁起
弘仁年間、巡錫中の弘法大師は当地で金剛界曼荼羅の五智如来を感得した。
大師はその事にちなんでこの山を青峰、赤嶺、黒峰、黄色峰、白峰と命名され、その中の青峰に花蔵院を創建し、五大明王を祀られた。
その後の天長九年(832)智証大師が来錫したとき市之瀬明神が現れ「この地は霊地なり」との信託があった。
よって智証大師は蓮華谷の香木で千手観音を刻み、千手院を創建して安置した。
この両大師の創建した花蔵院、千手院の二院を総称したものが寺号となった。
また、一説によると、千手観音を刻んだ香木の根株が永いあいだ香気を発散させていたことから根香寺と名づけられたともいう。
根香寺は後白河法皇の勅願所となり寺領を下賜されたが、その後の度重なる兵火で堂宇は荒れ寺運は衰退していたが、高松藩主・松平頼重公によって再興された。
秘仏の本尊は三十三年目に一度の開扉。
詠歌
よいのまの、たえふるしもの、消えぬれば、あとこそかねの、ごんぎょうのこえ。
牛鬼と山田蔵人
昔この山に、牛鬼と呼ばれる怪物が住んで人々を困らせていたので、殿様は香川郡安原の弓の名人山田蔵人高清に命じて退治させた。
高清は、その褒美に頂いた、米六石と共にこの牛鬼の角(長さ36センチ)を当寺に納めた。
当寺には、今もその角と文化三年(1806)に石虎という人が描いた牛鬼の軸とが伝わっている。
第八十三番・神毫山・「一宮寺」・大宝院
本尊・聖観世音菩薩(立像・三尺五寸)(伝・弘法大師作)
開基・義渕僧正
宗派・真言宗御室派
住所・香川県高松市一宮町607
略縁起
大宝年間(八世紀の初)義渕僧正によって創建された頃は大宝寺と号していた。
その後、田村神社を一国に一社建立せよとの勅命により、行基菩薩が創建したのが讃岐一宮の田村神社であり、寺はその別当寺となって神毫山一宮寺と改号した。
さらに大同年間(806〜810)弘法大師が来錫して、三尺五寸の立像の聖観世音菩薩を刻んで本尊として安置し、前記の行基菩薩が建立した堂塔を補修、伽藍を再興、そして、四国八十三番札所と定められた。が、これらの堂塔も天正年間、長曽我部の兵火にあって灰燼に帰している。再興は宥勢大徳によってである。
延宝七年(1679)高松藩主・松平頼重公によって別当職を解かれ、つまり神仏が分けられて独立寺となった。
境内には考霊天皇、百襲姫、吉備津彦命などの宝塔がある。
詠歌
さぬき一宮の、御前に、あふぎきて、神の心を、だれかしらゆふ。
地獄の釜首と一宮御陵
本堂前に薬師如来を祀る小さな石の祠がある。この中へ首を突っ込むと地獄の釜の音が聞こえると言われ、罪の深い人は、その石の扉が閉まって首が抜けなくなると言うから怖い。
その横に一宮御陵と呼ばれる三基の石塔があり、百襲姫等を祀る。
隣の田村神社が百襲姫を祀っており、神仏合祀の名残であろう。
本尊・聖観世音菩薩(立像・三尺五寸)(伝・弘法大師作)
開基・義渕僧正
宗派・真言宗御室派
住所・香川県高松市一宮町607
略縁起
大宝年間(八世紀の初)義渕僧正によって創建された頃は大宝寺と号していた。
その後、田村神社を一国に一社建立せよとの勅命により、行基菩薩が創建したのが讃岐一宮の田村神社であり、寺はその別当寺となって神毫山一宮寺と改号した。
さらに大同年間(806〜810)弘法大師が来錫して、三尺五寸の立像の聖観世音菩薩を刻んで本尊として安置し、前記の行基菩薩が建立した堂塔を補修、伽藍を再興、そして、四国八十三番札所と定められた。が、これらの堂塔も天正年間、長曽我部の兵火にあって灰燼に帰している。再興は宥勢大徳によってである。
延宝七年(1679)高松藩主・松平頼重公によって別当職を解かれ、つまり神仏が分けられて独立寺となった。
境内には考霊天皇、百襲姫、吉備津彦命などの宝塔がある。
詠歌
さぬき一宮の、御前に、あふぎきて、神の心を、だれかしらゆふ。
地獄の釜首と一宮御陵
本堂前に薬師如来を祀る小さな石の祠がある。この中へ首を突っ込むと地獄の釜の音が聞こえると言われ、罪の深い人は、その石の扉が閉まって首が抜けなくなると言うから怖い。
その横に一宮御陵と呼ばれる三基の石塔があり、百襲姫等を祀る。
隣の田村神社が百襲姫を祀っており、神仏合祀の名残であろう。
第八十四番・南面山・「屋島寺」・千光院
本尊・十一面千手観音菩薩(伝・弘法大師作)
開基・鑑真和上
宗派・真言宗御室派
住所・香川県高松市屋島東町
略縁起
天平勝宝六年、唐の国より正式に和国に迎えられた鑑真和上が来朝の際、おとずれたのが屋島山上。和上は山上の北嶺こそ伽藍建立の霊地なりとて念誦、開基した。
その後、和上の弟子の恵雲師が登攀し、和上の開創した霊地に堂宇を建立したのがはじまりである。恵雲師は第一代目の住職となった。
弘仁六年(815)には、嵯峨天皇の勅願を奉じて来錫弘法大師が、それまで北嶺にあった伽藍を現在の南嶺に移すとともに十一面観世音菩薩を刻んで本尊として安置、而して四国第八十四番札所と定められた。
寺運は平安期から天暦、藤原、鎌倉時代と隆盛を見たが、以後は盛衰の歴史を繰り返している。
寺宝に平重盛寄進の鉄灯籠、土佐光信筆源平合戦図、悪七兵衛景清の守本尊である千手観世音菩薩などがある。
詠歌
あずさ弓、屋島の宮にもうでつつ、いのりをかけて、いさむますらお。
狸の蓑山大明神
この山の狸太三郎は、佐渡の三郎狸、淡路の芝衛独と共に日本三名狸と言われる。
屋島住職の代がわりの時は、屋島合戦の模様を鳴り物入りで実演してみせたりしたと言うが、日清、日露戦争に多くの乾分を連れて出征して大いに働いた後、死んだという。
今、本殿横に祀られ、水商売の神となっている。
本尊・十一面千手観音菩薩(伝・弘法大師作)
開基・鑑真和上
宗派・真言宗御室派
住所・香川県高松市屋島東町
略縁起
天平勝宝六年、唐の国より正式に和国に迎えられた鑑真和上が来朝の際、おとずれたのが屋島山上。和上は山上の北嶺こそ伽藍建立の霊地なりとて念誦、開基した。
その後、和上の弟子の恵雲師が登攀し、和上の開創した霊地に堂宇を建立したのがはじまりである。恵雲師は第一代目の住職となった。
弘仁六年(815)には、嵯峨天皇の勅願を奉じて来錫弘法大師が、それまで北嶺にあった伽藍を現在の南嶺に移すとともに十一面観世音菩薩を刻んで本尊として安置、而して四国第八十四番札所と定められた。
寺運は平安期から天暦、藤原、鎌倉時代と隆盛を見たが、以後は盛衰の歴史を繰り返している。
寺宝に平重盛寄進の鉄灯籠、土佐光信筆源平合戦図、悪七兵衛景清の守本尊である千手観世音菩薩などがある。
詠歌
あずさ弓、屋島の宮にもうでつつ、いのりをかけて、いさむますらお。
狸の蓑山大明神
この山の狸太三郎は、佐渡の三郎狸、淡路の芝衛独と共に日本三名狸と言われる。
屋島住職の代がわりの時は、屋島合戦の模様を鳴り物入りで実演してみせたりしたと言うが、日清、日露戦争に多くの乾分を連れて出征して大いに働いた後、死んだという。
今、本殿横に祀られ、水商売の神となっている。
第八十五番・五剣山・「八栗寺」(やくりじ)・観自在院
本尊・正観世音菩薩(座像四尺)(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗大覚寺派
住所・香川県木田郡牟礼町
略縁起
天長六年(827)弘法大師がこの山に登って求聞持の法を修されその満願日に空中より五柄の利剣が降り、金剛蔵王が示現、山の鎮護を告げられた。
大師はその剣を山の中腹に埋め、岩盤に毘廬遮那の像を刻みしかるのち千手観音菩薩像を刻んで堂宇を建立、当山を五剣山と号した。
大師はさらに入唐に際し求法の前効を試み八個の焼栗を埋められたが、帰朝後立ち寄ってみると八本とも生長繁茂していたという因縁から、現在の寺号になったといわれる。
その後、天正年間に長曽我部の兵火にあって堂宇はことごとく焼失したが、文禄年間になって無辺上人が一部を復興さらに寛永十九年に高松藩主・松平頼重公が本堂を再建した際、それまでの本尊が小さいということで現在の本堂を寄進している。
延宝五年、木食上人が勧請した歓喜天は黄金五寸像で、その霊験あらたかであるという。
詠歌
ぼんのうを、胸の智火にて、八栗をば、修行者ならで、誰が知るべき。
下駄を穿く天狗
本堂と歓喜天を祀った聖天堂との間の、両側に赤い千人札が林立している石段を登って行くと、中将坊という堂がある。
この山の守護神、天狗様が祀られている。
ここに新しい下駄を奉納して、翌日行ってみると天狗様が加護のために働いて下さった証拠に、必ずその下駄の歯が汚れているという。
本尊・正観世音菩薩(座像四尺)(伝・弘法大師作)
開基・弘法大師
宗派・真言宗大覚寺派
住所・香川県木田郡牟礼町
略縁起
天長六年(827)弘法大師がこの山に登って求聞持の法を修されその満願日に空中より五柄の利剣が降り、金剛蔵王が示現、山の鎮護を告げられた。
大師はその剣を山の中腹に埋め、岩盤に毘廬遮那の像を刻みしかるのち千手観音菩薩像を刻んで堂宇を建立、当山を五剣山と号した。
大師はさらに入唐に際し求法の前効を試み八個の焼栗を埋められたが、帰朝後立ち寄ってみると八本とも生長繁茂していたという因縁から、現在の寺号になったといわれる。
その後、天正年間に長曽我部の兵火にあって堂宇はことごとく焼失したが、文禄年間になって無辺上人が一部を復興さらに寛永十九年に高松藩主・松平頼重公が本堂を再建した際、それまでの本尊が小さいということで現在の本堂を寄進している。
延宝五年、木食上人が勧請した歓喜天は黄金五寸像で、その霊験あらたかであるという。
詠歌
ぼんのうを、胸の智火にて、八栗をば、修行者ならで、誰が知るべき。
下駄を穿く天狗
本堂と歓喜天を祀った聖天堂との間の、両側に赤い千人札が林立している石段を登って行くと、中将坊という堂がある。
この山の守護神、天狗様が祀られている。
ここに新しい下駄を奉納して、翌日行ってみると天狗様が加護のために働いて下さった証拠に、必ずその下駄の歯が汚れているという。
第八十六番・補陀落山(ふだらくさん)・「志度寺」
本尊・十一面観世音菩薩(立像五尺二寸)(国宝)
開基・藤原不比等
宗派・真言宗善通寺派
住所・香川県大川郡志度町志度
略縁起
推古天皇の御代園の子尼は漂着した霊木で十一面観音像を刻まんと腐心していると、仏師姿の男が現れ単日に等身大の像を彫りあげ、「われは補陀落の観音なり」と告げて去って行った。
また、堂宇建立の際も閻魔王の出現があったという不思議な縁起を秘めた寺であり、事を奉聞された推古天皇は当寺を勅願所に定めたという。
後、藤原不比等が唐の皇帝の妃となっている妹から賜れた、釈迦三尊彫刻の上下表裏なき面向不背の宝珠が、ここ志度浦の龍神に奪われたのを取り返すため当地へ来て、房前の漁師の娘と夫婦となり、その妻が命と引き換えに宝珠を取り戻したことが物語として残されている。
不比等は妻の菩提をとむらおうと五間四面の堂宇を建て、志度道場と命名。現在の寺号に改号したのは、その後訪れた行基菩薩である。
奪い返した宝珠は奈良興福寺の本尊・釈迦如来の眉間に納まっているという。
また、寛文七年に松平頼重公が建てた仁王門は三つ棟木という珍しい工法を用いている。
詠歌
いざさらば、こよいはここに、志度の寺、いのりの声を、耳にふれつつ。
仏罰で大蛇になった当願という狩人
この寺で有難い説教を聞きながら、猟に出かけた弟暮当のことばかりを考えていた兄の当願は、仏罰が当たって大蛇に変身させられた。
悲しみながらも、自らの目玉を瓶に入れて酒を醸るよう弟に言い残し、満濃池に入り、後には瀬戸内海の底に入った。
今でも樽に酒を入れて海に流すと大雨を降らせてくれると言う。
本尊・十一面観世音菩薩(立像五尺二寸)(国宝)
開基・藤原不比等
宗派・真言宗善通寺派
住所・香川県大川郡志度町志度
略縁起
推古天皇の御代園の子尼は漂着した霊木で十一面観音像を刻まんと腐心していると、仏師姿の男が現れ単日に等身大の像を彫りあげ、「われは補陀落の観音なり」と告げて去って行った。
また、堂宇建立の際も閻魔王の出現があったという不思議な縁起を秘めた寺であり、事を奉聞された推古天皇は当寺を勅願所に定めたという。
後、藤原不比等が唐の皇帝の妃となっている妹から賜れた、釈迦三尊彫刻の上下表裏なき面向不背の宝珠が、ここ志度浦の龍神に奪われたのを取り返すため当地へ来て、房前の漁師の娘と夫婦となり、その妻が命と引き換えに宝珠を取り戻したことが物語として残されている。
不比等は妻の菩提をとむらおうと五間四面の堂宇を建て、志度道場と命名。現在の寺号に改号したのは、その後訪れた行基菩薩である。
奪い返した宝珠は奈良興福寺の本尊・釈迦如来の眉間に納まっているという。
また、寛文七年に松平頼重公が建てた仁王門は三つ棟木という珍しい工法を用いている。
詠歌
いざさらば、こよいはここに、志度の寺、いのりの声を、耳にふれつつ。
仏罰で大蛇になった当願という狩人
この寺で有難い説教を聞きながら、猟に出かけた弟暮当のことばかりを考えていた兄の当願は、仏罰が当たって大蛇に変身させられた。
悲しみながらも、自らの目玉を瓶に入れて酒を醸るよう弟に言い残し、満濃池に入り、後には瀬戸内海の底に入った。
今でも樽に酒を入れて海に流すと大雨を降らせてくれると言う。
第八十七番・補陀落山・「長尾寺」・観音院
本尊・聖観世音菩薩(立像三尺二寸)(伝・行基菩薩作)
開基・行基菩薩
宗派・天台宗
住所・香川県大川郡長尾町西
略縁起
聖徳太子の開創と伝えられている。
後、天平十一年(739)この地に来錫した行基菩薩は霊夢を感じ、道端の楊柳で聖観世音菩薩像を刻むと、小堂を建てて安置したことがはじまりだという。
その後、唐の国へ渡られる前、当寺を訪れた弘法大師は求法を祈願、帰朝後は堂宇を建て、大日教を一石に一字ずつ書き写して万霊の供養塔を建立し、年頭七夜の護摩秘宝を厳修され、その祈り札を衆生に与えたといわれている。
天和元年(1681)松平頼重公は堂塔を建立、田畑を寄進し讃岐七観音の一つに定めると共に天台宗に改宗させている。
この寺の仁王門に立つ仁王像は、大阪で造られ船で志度浦へ到着。志度から長尾まで陸路を運ぶ者がなかった。
そこで当時、長尾寺の住職だった名僧桂同法印が、仁王さんに向って心の中で念じた。仁王像は法印の命ずるまま長尾寺まで歩いたという伝説を持っている。
詠歌
あしびきの、山鳥の尾の、長尾寺、秋の夜すがら、み名をとなえよ。
静御前得度の寺
源義経没後、その愛妾であった静御前は、母磯禅尼の出身地(大内郡小磯)ということで讃岐にやって来て、この長尾寺で得度し、「宥心」という尼になった。
その遺跡として剃髪塚、化粧の井戸、義経を忘れようとその形見の鼓「初音」を静めた鼓が渕、住んでいた庵跡の静薬師などがある。
本尊・聖観世音菩薩(立像三尺二寸)(伝・行基菩薩作)
開基・行基菩薩
宗派・天台宗
住所・香川県大川郡長尾町西
略縁起
聖徳太子の開創と伝えられている。
後、天平十一年(739)この地に来錫した行基菩薩は霊夢を感じ、道端の楊柳で聖観世音菩薩像を刻むと、小堂を建てて安置したことがはじまりだという。
その後、唐の国へ渡られる前、当寺を訪れた弘法大師は求法を祈願、帰朝後は堂宇を建て、大日教を一石に一字ずつ書き写して万霊の供養塔を建立し、年頭七夜の護摩秘宝を厳修され、その祈り札を衆生に与えたといわれている。
天和元年(1681)松平頼重公は堂塔を建立、田畑を寄進し讃岐七観音の一つに定めると共に天台宗に改宗させている。
この寺の仁王門に立つ仁王像は、大阪で造られ船で志度浦へ到着。志度から長尾まで陸路を運ぶ者がなかった。
そこで当時、長尾寺の住職だった名僧桂同法印が、仁王さんに向って心の中で念じた。仁王像は法印の命ずるまま長尾寺まで歩いたという伝説を持っている。
詠歌
あしびきの、山鳥の尾の、長尾寺、秋の夜すがら、み名をとなえよ。
静御前得度の寺
源義経没後、その愛妾であった静御前は、母磯禅尼の出身地(大内郡小磯)ということで讃岐にやって来て、この長尾寺で得度し、「宥心」という尼になった。
その遺跡として剃髪塚、化粧の井戸、義経を忘れようとその形見の鼓「初音」を静めた鼓が渕、住んでいた庵跡の静薬師などがある。
第八十八番・医王山・「大窪寺」・遍照光院
本尊・薬師如来(座像三尺)(伝・弘法大師作)
開基・行基菩薩
宗派・真言宗大覚寺派
住所・香川県大川郡長尾町多和96
略縁起
天正天皇勅願寺天皇の御代、当地へ来錫した行基菩薩は霊感を得、持念された。
その後、唐より帰朝された弘法大師は奥の院で求聞持の秘法を修せられた。
その場所は窟胎蔵ヶ峰、あるいは胎蔵峯寺という。
大師はさらに大きな窪の側に堂宇を建立、自ら座像等身大の薬師如来像を刻んで本堂として安置。
そして、四国霊場ご開創のあいだ所持された三国伝来の錫杖を納めて、当寺を四国霊場八十八番札所と定め、結願寺と定められた。
大師が錫杖を納められたのが、本堂前の宝杖堂と伝えられている。
詠歌
なむやくし、諸病なかれと、願いつつ、まいれる人は、おおくぼの寺。
結願所の話。
長尾寺の東に、真言宗西教寺という寺があり、そこに俗称穴薬師と呼ばれる奥の院がある。
かつて大師はここを結願所にしたいと思い、一夜のうちに本尊を刻もうと発願された。
ところが、例の天の邪鬼が、鶏の鳴き声をつくって朝を告げたので、大師は自らの力不足を恥じて諦めたという。
今も彫りかけの摩崖仏が残っている。
お名残りや、これが札所の打ち納め、またのご縁を結びたまえ。
本尊・薬師如来(座像三尺)(伝・弘法大師作)
開基・行基菩薩
宗派・真言宗大覚寺派
住所・香川県大川郡長尾町多和96
略縁起
天正天皇勅願寺天皇の御代、当地へ来錫した行基菩薩は霊感を得、持念された。
その後、唐より帰朝された弘法大師は奥の院で求聞持の秘法を修せられた。
その場所は窟胎蔵ヶ峰、あるいは胎蔵峯寺という。
大師はさらに大きな窪の側に堂宇を建立、自ら座像等身大の薬師如来像を刻んで本堂として安置。
そして、四国霊場ご開創のあいだ所持された三国伝来の錫杖を納めて、当寺を四国霊場八十八番札所と定め、結願寺と定められた。
大師が錫杖を納められたのが、本堂前の宝杖堂と伝えられている。
詠歌
なむやくし、諸病なかれと、願いつつ、まいれる人は、おおくぼの寺。
結願所の話。
長尾寺の東に、真言宗西教寺という寺があり、そこに俗称穴薬師と呼ばれる奥の院がある。
かつて大師はここを結願所にしたいと思い、一夜のうちに本尊を刻もうと発願された。
ところが、例の天の邪鬼が、鶏の鳴き声をつくって朝を告げたので、大師は自らの力不足を恥じて諦めたという。
今も彫りかけの摩崖仏が残っている。
お名残りや、これが札所の打ち納め、またのご縁を結びたまえ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%98%E7%9B%A7%E9%81%AE%E9%82%A3%E4%BB%8F
毘盧遮那仏
毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)は、大乗仏教における仏の1つ。
概要
毘盧遮那とはサンスクリット語のVairocana「ヴァイローチャナ」の音訳で「光明遍照」(こうみょうへんじょう)を意味する。「毘盧舎那仏」とも表記される。略して盧遮那仏(るしゃなぶつ)、遮那仏(しゃなぶつ)とも表される。
史実の人物としてのゴータマ・シッダールタを超えた宇宙仏(法身仏)。宇宙の真理を全ての人に照らし、悟りに導く仏。毘盧遮那仏については、華厳経に詳しく説かれている。
密教
真言宗などの密教における「摩訶毘盧遮那仏」(大毘盧遮那仏、Mahāvairocana(マハー・ヴァイローチャナ))は、大日如来と呼ばれ、成立の起源を、ゾロアスター教の善の最高神アフラ・マズダーに求める学説がある。仏像では、聖武天皇の発願により造られた東大寺盧舎那仏像(奈良の大仏、東大寺大仏)が有名。同様に、鑑真が開創した唐招提寺金堂の中尊も、天平時代の脱乾漆像として有名であり、鑑真が中国からもたらした盛唐様式の作風を伝える彫刻[1]として貴重な存在である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E5%A6%82%E6%9D%A5
大日如来
大日如来(だいにちにょらい)、梵名 マハー・ヴァイローチャナ (महावैरोचन [mahaavairocana])は、密教において宇宙そのものと一体と考えられる汎神論的な如来(法身仏)の一尊。その光明が遍く照らすところから遍照、または大日という。
三昧耶形は、金剛界曼荼羅では宝塔、胎蔵曼荼羅では五輪塔。種子(種字)は金剛界曼荼羅ではバン(vaM)、胎蔵曼荼羅ではアーク(aaH)またはア(a)
概要
大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)の教主であり、大日経の説く胎蔵曼荼羅中台八葉院九尊の主である。また金剛頂経の説く金剛界曼荼羅五智如来の中心。空海の開いた真言宗において、究極的には修行者自身と一体化すべきものとして最も重要な仏陀である。不動明王は、密教の根本尊である大日如来の化身、あるいはその内証(内心の決意)を表現したものであると見なされている。
後期密教を大幅に取り入れたチベット仏教でも、大日如来は金剛界五仏(五智如来)の中心として尊崇される。チベット仏教では、宝飾品を身に纏わずに通常の如来の姿で表現されたり、あるいは多面仏として描かれることもある。
像形は、宝冠をはじめ瓔珞などの豪華な装身具を身に着けた、菩薩のような姿の坐像として表現される。これは古代インドの王族の姿を模したものである。一般に如来は装身具を一切身に着けない薄衣の姿で表現されるが、大日如来は宇宙そのもの存在を装身具の如く身にまとった者として、特に王者の姿で表されるのである。 印相は、金剛界大日如来は智拳印を、胎蔵界大日如来は法界定印を結ぶ。
毘盧遮那仏
毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)は、大乗仏教における仏の1つ。
概要
毘盧遮那とはサンスクリット語のVairocana「ヴァイローチャナ」の音訳で「光明遍照」(こうみょうへんじょう)を意味する。「毘盧舎那仏」とも表記される。略して盧遮那仏(るしゃなぶつ)、遮那仏(しゃなぶつ)とも表される。
史実の人物としてのゴータマ・シッダールタを超えた宇宙仏(法身仏)。宇宙の真理を全ての人に照らし、悟りに導く仏。毘盧遮那仏については、華厳経に詳しく説かれている。
密教
真言宗などの密教における「摩訶毘盧遮那仏」(大毘盧遮那仏、Mahāvairocana(マハー・ヴァイローチャナ))は、大日如来と呼ばれ、成立の起源を、ゾロアスター教の善の最高神アフラ・マズダーに求める学説がある。仏像では、聖武天皇の発願により造られた東大寺盧舎那仏像(奈良の大仏、東大寺大仏)が有名。同様に、鑑真が開創した唐招提寺金堂の中尊も、天平時代の脱乾漆像として有名であり、鑑真が中国からもたらした盛唐様式の作風を伝える彫刻[1]として貴重な存在である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E5%A6%82%E6%9D%A5
大日如来
大日如来(だいにちにょらい)、梵名 マハー・ヴァイローチャナ (महावैरोचन [mahaavairocana])は、密教において宇宙そのものと一体と考えられる汎神論的な如来(法身仏)の一尊。その光明が遍く照らすところから遍照、または大日という。
三昧耶形は、金剛界曼荼羅では宝塔、胎蔵曼荼羅では五輪塔。種子(種字)は金剛界曼荼羅ではバン(vaM)、胎蔵曼荼羅ではアーク(aaH)またはア(a)
概要
大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)の教主であり、大日経の説く胎蔵曼荼羅中台八葉院九尊の主である。また金剛頂経の説く金剛界曼荼羅五智如来の中心。空海の開いた真言宗において、究極的には修行者自身と一体化すべきものとして最も重要な仏陀である。不動明王は、密教の根本尊である大日如来の化身、あるいはその内証(内心の決意)を表現したものであると見なされている。
後期密教を大幅に取り入れたチベット仏教でも、大日如来は金剛界五仏(五智如来)の中心として尊崇される。チベット仏教では、宝飾品を身に纏わずに通常の如来の姿で表現されたり、あるいは多面仏として描かれることもある。
像形は、宝冠をはじめ瓔珞などの豪華な装身具を身に着けた、菩薩のような姿の坐像として表現される。これは古代インドの王族の姿を模したものである。一般に如来は装身具を一切身に着けない薄衣の姿で表現されるが、大日如来は宇宙そのもの存在を装身具の如く身にまとった者として、特に王者の姿で表されるのである。 印相は、金剛界大日如来は智拳印を、胎蔵界大日如来は法界定印を結ぶ。
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2013/04/2013_13654719073111.html
螺髪、吉野川市で出土 仏像の頭髪部分
2013/4/9 10:44
吉野川市川島町川島の民有地で、奈良〜平安時代のものとみられる土作りの仏像の頭髪部分「螺髪(らほつ)」が9個出土した。市教委や四国各県の埋蔵文化財センターなどによると、古代の螺髪が複数見つかったのは四国初。当時の神社仏閣の屋根に装飾として使われていた「鬼瓦(おにがわら)」と「鴟尾(しび)」も同時に発掘されており、市教委は県内最古の寺の一つで、川島町にあったとされる大日寺の存在を裏付ける物証になるとして、現地をさらに詳しく調べる。
見つかった螺髪は高さ、底径が各約2センチ。螺髪の寸法から、仏像は比較的小さく座像なら高さ1・2メートル、立像なら2・4メートルほどだったと推定される。
螺髪は全国各地の遺跡などで出土しており、四国では今年1月、香川県東かがわ市で1個見つかったが、9個も発見されたのは初めて。
螺髪とともに発見された鬼瓦は縦26センチ、横23センチ、厚さ3センチ。板状の土台に目や鼻などを後付けしている特徴から、市教委は奈良〜平安時代のものと判断した。一部が欠けているものの表情はしっかり残っており、これほど保存状態の良いのは珍しいという。鴟尾は縦12センチ、横6・5センチの断片で、魚のヒレのような模様が刻まれている。
ほかにも、寺院の土台部分に使われる凝灰(ぎょうかい)岩や、石を敷き詰めて屋根からの雨粒を受けていたとみられる礫敷(れきじき)など、寺の存在に結びつく遺構が一緒に見つかった。
出土現場周辺は古文書の記録などで大日寺があったとされるが、裏付けとなる出土品は公的な調査で発見されていなかった。市教委は「出土した鬼瓦や鴟尾は立派な作品。かつて川島が栄えていたことを示す史料だ」と話している。
現場が遺物出土の可能性がある文化財保護法の包蔵地に該当するため、建設工事を計画していた土地の所有者が市教委に工事を届け出た。これを受けて市教委が昨年10月から試掘調査を行い、螺髪や鬼瓦を見つけた。
【写真説明】[右]吉野川市の民有地から出土した螺髪[左]寺の屋根部分に使われていたとみられる鬼瓦=いずれも吉野川市役所
螺髪、吉野川市で出土 仏像の頭髪部分
2013/4/9 10:44
吉野川市川島町川島の民有地で、奈良〜平安時代のものとみられる土作りの仏像の頭髪部分「螺髪(らほつ)」が9個出土した。市教委や四国各県の埋蔵文化財センターなどによると、古代の螺髪が複数見つかったのは四国初。当時の神社仏閣の屋根に装飾として使われていた「鬼瓦(おにがわら)」と「鴟尾(しび)」も同時に発掘されており、市教委は県内最古の寺の一つで、川島町にあったとされる大日寺の存在を裏付ける物証になるとして、現地をさらに詳しく調べる。
見つかった螺髪は高さ、底径が各約2センチ。螺髪の寸法から、仏像は比較的小さく座像なら高さ1・2メートル、立像なら2・4メートルほどだったと推定される。
螺髪は全国各地の遺跡などで出土しており、四国では今年1月、香川県東かがわ市で1個見つかったが、9個も発見されたのは初めて。
螺髪とともに発見された鬼瓦は縦26センチ、横23センチ、厚さ3センチ。板状の土台に目や鼻などを後付けしている特徴から、市教委は奈良〜平安時代のものと判断した。一部が欠けているものの表情はしっかり残っており、これほど保存状態の良いのは珍しいという。鴟尾は縦12センチ、横6・5センチの断片で、魚のヒレのような模様が刻まれている。
ほかにも、寺院の土台部分に使われる凝灰(ぎょうかい)岩や、石を敷き詰めて屋根からの雨粒を受けていたとみられる礫敷(れきじき)など、寺の存在に結びつく遺構が一緒に見つかった。
出土現場周辺は古文書の記録などで大日寺があったとされるが、裏付けとなる出土品は公的な調査で発見されていなかった。市教委は「出土した鬼瓦や鴟尾は立派な作品。かつて川島が栄えていたことを示す史料だ」と話している。
現場が遺物出土の可能性がある文化財保護法の包蔵地に該当するため、建設工事を計画していた土地の所有者が市教委に工事を届け出た。これを受けて市教委が昨年10月から試掘調査を行い、螺髪や鬼瓦を見つけた。
【写真説明】[右]吉野川市の民有地から出土した螺髪[左]寺の屋根部分に使われていたとみられる鬼瓦=いずれも吉野川市役所
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=5854
徳島・川島町「聖地」の証明 - 大川隆法・幸福の科学総裁の生誕地で「大日寺」の遺跡発見
2013.04.09
徳島・川島町「聖地」の証明
大川隆法・幸福の科学総裁の生誕地で「大日寺」の遺跡発見
大川隆法・幸福の科学総裁の生誕地である徳島県吉野川市川島町で昨年秋から年始にかけて行われた発掘調査で、奈良時代前後に建てられたと考えられている「大日寺」に関する重要な遺跡が見つかった。9日付徳島新聞が伝えている。発見場所は、JR阿波川島駅前の幸福の科学の施設建設予定地で、幸福の科学川島特別支部の隣に位置する。幸福の科学は発掘調査に協力するため建設計画を見送る予定で、今後は県による調査が続けられる。
(写真1)「礫敷(れきじき)」。礫敷は建物を中心としてロの字型に配置されるため、今後発掘が進めば、残りも見つかる可能性があるという。(以下、画像はクリックすると大きくなります)
(写真2)本堂の屋根にあったと考えられる「鬼瓦(おにがわら)」。写真の鬼瓦は、これまでに日本国内で発掘された鬼瓦と比較しても、かなりよい状態で見つかっている。
(写真3)本堂の屋根の両側に据える瓦の「鴟尾(しび)」の一部である鴟尾片。
(写真4)仏像の頭部の「螺髪(らはつ)」。発見場所に本殿が位置し、大日如来像が安置されていたことが予想される。
貴重な遺跡が次々発見 「国指定」の可能性も
この地域一帯は大日寺の敷地であったことが古文書で伝えられており、「文化財保護法の埋蔵文化財包蔵地」に指定されている。2006年以降、埋蔵文化財包蔵地内で建設工事を行う場合には発掘調査を行う必要が出てきた。これまで近隣の川島城本丸跡には大日寺の塔の礎石とされる石やJR阿波川島駅に大日寺跡石碑があるほか、住宅建築の際などに瓦が多数発見されてはいたが、今回初めて、幸福の科学聖地川島特別支部の境内地から、古代寺院大日寺の存在を確証しうる大量の出土品が発見された。
発見されたのは、屋根からの雨粒を受けていたとみられる「礫敷(れきじき)」と、建物土台部分にあたる「凝灰岩(ぎょうかいがん)」だ(写真1)。礫敷は建物を中心としてロの字型に配置されるため、今後発掘が進めば、残りも見つかる可能性があるという。
また、金堂の屋根にあったと考えられる「鬼瓦(おにがわら)」(写真2)が見つかった。その中には、これまでに日本国内で発掘された鬼瓦と比較しても、かなりよい状態で見つかっているものがある。
さらには、金堂の屋根の両側に据える瓦の「鴟尾(しび)」の一部である鴟尾片が見つかっている(写真3)。
そして、仏像の頭部の「螺髪(らほつ)」も9点見つかった(写真4)。9個も発見されたのも四国初である。これによって、発見された場所に金堂が位置し、大日如来像が安置されていたことが裏付けされる。さらに、当時の伽藍配置から、金堂の横に何層かの仏塔が位置し現在の聖地川島特別支部の辺りにあったとも推定される。
徳島県内では、これまでにも同様の古代寺院跡が見つかっている。石井町の「阿波国分尼寺跡」と美馬市の「郡里廃寺跡」があり、いずれも「国指定史跡」となっている。大日寺について発見されたものは、「県指定史跡」に匹敵するもので、今後の発掘によっては、「国指定史跡」になる可能性もあるという。
つづく。
徳島・川島町「聖地」の証明 - 大川隆法・幸福の科学総裁の生誕地で「大日寺」の遺跡発見
2013.04.09
徳島・川島町「聖地」の証明
大川隆法・幸福の科学総裁の生誕地で「大日寺」の遺跡発見
大川隆法・幸福の科学総裁の生誕地である徳島県吉野川市川島町で昨年秋から年始にかけて行われた発掘調査で、奈良時代前後に建てられたと考えられている「大日寺」に関する重要な遺跡が見つかった。9日付徳島新聞が伝えている。発見場所は、JR阿波川島駅前の幸福の科学の施設建設予定地で、幸福の科学川島特別支部の隣に位置する。幸福の科学は発掘調査に協力するため建設計画を見送る予定で、今後は県による調査が続けられる。
(写真1)「礫敷(れきじき)」。礫敷は建物を中心としてロの字型に配置されるため、今後発掘が進めば、残りも見つかる可能性があるという。(以下、画像はクリックすると大きくなります)
(写真2)本堂の屋根にあったと考えられる「鬼瓦(おにがわら)」。写真の鬼瓦は、これまでに日本国内で発掘された鬼瓦と比較しても、かなりよい状態で見つかっている。
(写真3)本堂の屋根の両側に据える瓦の「鴟尾(しび)」の一部である鴟尾片。
(写真4)仏像の頭部の「螺髪(らはつ)」。発見場所に本殿が位置し、大日如来像が安置されていたことが予想される。
貴重な遺跡が次々発見 「国指定」の可能性も
この地域一帯は大日寺の敷地であったことが古文書で伝えられており、「文化財保護法の埋蔵文化財包蔵地」に指定されている。2006年以降、埋蔵文化財包蔵地内で建設工事を行う場合には発掘調査を行う必要が出てきた。これまで近隣の川島城本丸跡には大日寺の塔の礎石とされる石やJR阿波川島駅に大日寺跡石碑があるほか、住宅建築の際などに瓦が多数発見されてはいたが、今回初めて、幸福の科学聖地川島特別支部の境内地から、古代寺院大日寺の存在を確証しうる大量の出土品が発見された。
発見されたのは、屋根からの雨粒を受けていたとみられる「礫敷(れきじき)」と、建物土台部分にあたる「凝灰岩(ぎょうかいがん)」だ(写真1)。礫敷は建物を中心としてロの字型に配置されるため、今後発掘が進めば、残りも見つかる可能性があるという。
また、金堂の屋根にあったと考えられる「鬼瓦(おにがわら)」(写真2)が見つかった。その中には、これまでに日本国内で発掘された鬼瓦と比較しても、かなりよい状態で見つかっているものがある。
さらには、金堂の屋根の両側に据える瓦の「鴟尾(しび)」の一部である鴟尾片が見つかっている(写真3)。
そして、仏像の頭部の「螺髪(らほつ)」も9点見つかった(写真4)。9個も発見されたのも四国初である。これによって、発見された場所に金堂が位置し、大日如来像が安置されていたことが裏付けされる。さらに、当時の伽藍配置から、金堂の横に何層かの仏塔が位置し現在の聖地川島特別支部の辺りにあったとも推定される。
徳島県内では、これまでにも同様の古代寺院跡が見つかっている。石井町の「阿波国分尼寺跡」と美馬市の「郡里廃寺跡」があり、いずれも「国指定史跡」となっている。大日寺について発見されたものは、「県指定史跡」に匹敵するもので、今後の発掘によっては、「国指定史跡」になる可能性もあるという。
つづく。
つづき。
四国・川島町が「聖地」であることが歴史的にも証明される
歴史的にも大きな発見だが、宗教的にも発見の意義は大きい。大日如来とは、仏陀の悟りと修行、霊界の秘儀を象徴する存在であり、毘盧遮那仏とも言われる。これは、東大寺の大仏と同じであり、幸福の科学のご本尊であるエル・カンターレのことである。現地は、再誕の仏陀である大川総裁の生家とほぼ同じ場所であり、やはり生誕地という「聖地」の下地ができていたということだろう。
さらに視野を広げてみると、おもに行基菩薩や弘法大師空海が開基したとされる四国八十八ヶ所の霊場は不思議な配置になっている。実は、第一番礼所から第十までが、川島町に向かって一直線になっており、その後、第十番から第八十八番までがまるで川島町を取り囲む形で四国全体を一周するというように、結界構造になっているのだ。
さらに細かく見ていくと、川島町近隣に第十番礼所「切幡寺」があるが、その奥の院には、インドから中国を経て日本に密教を伝えた八人の祖師「八祖大師」が祀られている。その中の一人、善無畏三蔵は、東インド出身で、真言密教の根本経典である大日経を漢字に翻訳した。この善無畏三蔵は、大川総裁の父である善川三朗氏の過去世である。
また、第三十一番札所の「竹林寺」は聖武天皇の命で行基が建てたもので、文殊菩薩を本尊としており、竹林寺の庭園を造ったのは夢窓疎石だと伝えられている。聖武天皇の妻である光明皇后は大川総裁の長女として転生しており、文殊菩薩と夢窓疎石はともに大川総裁の次男の過去世である。
第二十番札所の「鶴林寺」は、桓武天皇の勅命で空海が開いたと伝えられているが、桓武天皇も大川総裁の三男として転生しているのだ。
第八十四番札所の「屋島寺」は鑑真和上が普賢菩薩像を安置して開創されたり、第七十五番札所の「善通寺」には西行法師が訪れ様々の和歌を残されており、聖徳太子が第六十一番札所の「香園寺」を開基したり第十七番札所の「井戸寺」の本尊の七仏薬師如来像を作られたとされており、過去の多くの偉人聖人が四国八十八箇所に関わりを持っている。ちなみに普賢菩薩は大川総裁の次女として転生しており、西行法師は大川総裁の長男として転生している。
このように、大川総裁の親族の過去世の偉人をはじめ多くの諸菩薩如来たちが、四国・川島町を中心とする一大霊場の建設に尽力していたのである。今も四国は全国から多数のお遍路が集まり巡礼する、日本で最も霊的な土地である。今回の「大日寺」遺跡発見で、この川島の地が、神仏への篤い信仰心により結界が作られ、本仏降臨の「聖地」として選ばれた地であるということが、ますます明らかになった。遺跡のさらなる調査・発掘が待たれることだ。
四国・川島町が「聖地」であることが歴史的にも証明される
歴史的にも大きな発見だが、宗教的にも発見の意義は大きい。大日如来とは、仏陀の悟りと修行、霊界の秘儀を象徴する存在であり、毘盧遮那仏とも言われる。これは、東大寺の大仏と同じであり、幸福の科学のご本尊であるエル・カンターレのことである。現地は、再誕の仏陀である大川総裁の生家とほぼ同じ場所であり、やはり生誕地という「聖地」の下地ができていたということだろう。
さらに視野を広げてみると、おもに行基菩薩や弘法大師空海が開基したとされる四国八十八ヶ所の霊場は不思議な配置になっている。実は、第一番礼所から第十までが、川島町に向かって一直線になっており、その後、第十番から第八十八番までがまるで川島町を取り囲む形で四国全体を一周するというように、結界構造になっているのだ。
さらに細かく見ていくと、川島町近隣に第十番礼所「切幡寺」があるが、その奥の院には、インドから中国を経て日本に密教を伝えた八人の祖師「八祖大師」が祀られている。その中の一人、善無畏三蔵は、東インド出身で、真言密教の根本経典である大日経を漢字に翻訳した。この善無畏三蔵は、大川総裁の父である善川三朗氏の過去世である。
また、第三十一番札所の「竹林寺」は聖武天皇の命で行基が建てたもので、文殊菩薩を本尊としており、竹林寺の庭園を造ったのは夢窓疎石だと伝えられている。聖武天皇の妻である光明皇后は大川総裁の長女として転生しており、文殊菩薩と夢窓疎石はともに大川総裁の次男の過去世である。
第二十番札所の「鶴林寺」は、桓武天皇の勅命で空海が開いたと伝えられているが、桓武天皇も大川総裁の三男として転生しているのだ。
第八十四番札所の「屋島寺」は鑑真和上が普賢菩薩像を安置して開創されたり、第七十五番札所の「善通寺」には西行法師が訪れ様々の和歌を残されており、聖徳太子が第六十一番札所の「香園寺」を開基したり第十七番札所の「井戸寺」の本尊の七仏薬師如来像を作られたとされており、過去の多くの偉人聖人が四国八十八箇所に関わりを持っている。ちなみに普賢菩薩は大川総裁の次女として転生しており、西行法師は大川総裁の長男として転生している。
このように、大川総裁の親族の過去世の偉人をはじめ多くの諸菩薩如来たちが、四国・川島町を中心とする一大霊場の建設に尽力していたのである。今も四国は全国から多数のお遍路が集まり巡礼する、日本で最も霊的な土地である。今回の「大日寺」遺跡発見で、この川島の地が、神仏への篤い信仰心により結界が作られ、本仏降臨の「聖地」として選ばれた地であるということが、ますます明らかになった。遺跡のさらなる調査・発掘が待たれることだ。
http://info.happy-science.jp/2013/7919/
徳島県の川島特別支部の敷地内で古代寺院の遺跡が発見されました!
2013.05.08
県内最古の大型寺院の可能性
このたび、幸福の科学 聖地・川島特別支部の敷地内において、1300年前の大型寺院・大日寺(だいにちじ)の遺跡が発見されました。
遺跡が発見された聖地・川島特別支部の境内地は、新たな施設の建設予定地でしたが、試掘によって重要な遺跡であることが判明したため、幸福の科学は吉野川市に対し、発掘調査に全面的に協力することを申し出ました。
2012年10月から行われた試掘調査の結果、出土したのは、仏像の頭髪部分である螺髪(らほつ)をはじめ、屋根の装飾である鬼瓦(おにがわら)や鴟尾(しび)などで、古文書の記録で川島町にあったとされる大日寺の存在の裏付けとなるものです。
大日寺は、約1300年前の飛鳥時代後期・白鳳時代に建立されたと考えられており、同時代に県内に建立された郡里廃寺(こうざとはいじ)と同規模で、県内最古の大型寺院であった可能性があります。
大川隆法総裁のご生誕の地
大日寺の本尊・大日如来(だいにちにょらい)は、仏陀の悟りと修行、霊界の秘儀を象徴する存在であり、東大寺の大仏でも知られる毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)でもあります。
これは、まさしく幸福の科学の本尊であるエル・カンターレのことです。
幸福の科学において、徳島県は大川隆法総裁ご生誕の「聖地」であり、その中でも、今回遺跡が発見された聖地・川島特別支部のある川島町は、大川隆法総裁のご生誕の地です。
「聖地」の名を冠する場所において、こうした新たな真実が発見されたことは、改めて「聖地」の証明であると同時に、古代よりこの地にエル・カンターレ信仰の種が蒔かれていたことの象徴であると言えるでしょう。
エル・カンターレというのは、大乗の仏陀、大毘盧遮那仏のことを言うのです。
『宗教選択の時代』 より
幸福の科学 川島特別支部の敷地内で古代寺院・大日寺の遺跡発見
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3nonqAE3WDQ
徳島県の川島特別支部の敷地内で古代寺院の遺跡が発見されました!
2013.05.08
県内最古の大型寺院の可能性
このたび、幸福の科学 聖地・川島特別支部の敷地内において、1300年前の大型寺院・大日寺(だいにちじ)の遺跡が発見されました。
遺跡が発見された聖地・川島特別支部の境内地は、新たな施設の建設予定地でしたが、試掘によって重要な遺跡であることが判明したため、幸福の科学は吉野川市に対し、発掘調査に全面的に協力することを申し出ました。
2012年10月から行われた試掘調査の結果、出土したのは、仏像の頭髪部分である螺髪(らほつ)をはじめ、屋根の装飾である鬼瓦(おにがわら)や鴟尾(しび)などで、古文書の記録で川島町にあったとされる大日寺の存在の裏付けとなるものです。
大日寺は、約1300年前の飛鳥時代後期・白鳳時代に建立されたと考えられており、同時代に県内に建立された郡里廃寺(こうざとはいじ)と同規模で、県内最古の大型寺院であった可能性があります。
大川隆法総裁のご生誕の地
大日寺の本尊・大日如来(だいにちにょらい)は、仏陀の悟りと修行、霊界の秘儀を象徴する存在であり、東大寺の大仏でも知られる毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)でもあります。
これは、まさしく幸福の科学の本尊であるエル・カンターレのことです。
幸福の科学において、徳島県は大川隆法総裁ご生誕の「聖地」であり、その中でも、今回遺跡が発見された聖地・川島特別支部のある川島町は、大川隆法総裁のご生誕の地です。
「聖地」の名を冠する場所において、こうした新たな真実が発見されたことは、改めて「聖地」の証明であると同時に、古代よりこの地にエル・カンターレ信仰の種が蒔かれていたことの象徴であると言えるでしょう。
エル・カンターレというのは、大乗の仏陀、大毘盧遮那仏のことを言うのです。
『宗教選択の時代』 より
幸福の科学 川島特別支部の敷地内で古代寺院・大日寺の遺跡発見
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3nonqAE3WDQ
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8091
大川総裁の生誕地はやはり「聖地」 吉野川市教委が川島町の大日寺遺跡の発掘を報告
2014.07.03
徳島県吉野川市の吉野川市役所で3日、同市川島町で見つかった大日寺遺跡の発掘について、市教委の生涯学習課が記者会見を行った。この遺跡は幸福の科学川島特別支部の境内地から見つかったもので、幸福の科学は発掘調査に協力するため施設建設計画を見送っている。
川島特別支部は本誌取材に対し、以下のようにコメントした。「千年以上以前の古代寺院の遺跡発掘を通して、今後、この遺跡が徳島県や吉野川市のさらなる地域の活性化や観光資源となって、地域貢献できるように全面協力をしています。この協力に対し、徳島県や吉野川市の教育委員会や地域の皆様より多くの感謝のお言葉をいただいています」
大日寺とは、大日如来を本尊とする奈良時代の古代寺院と推定される。この大日如来とは、東大寺の大仏である毘盧遮那仏とも同一視されている。大日寺が川島町に存在していたことは、江戸時代の文献『阿波志(あわし)』に記述されており、『川島町史』(昭和54年刊行)では、大日寺が塔と金堂が東西に並ぶ法起寺式伽藍配置を持つと推定されていた。
大日寺遺跡が見つかったのは2012年秋から2013年にかけて行われた市の調査による。第一次調査では、同地からは大日寺の存在を確証する材料となる大日如来像の一部と考えられる「螺髪(らほつ)」や、大日如来像が安置されていた「金堂(こんどう)」の一部と考えられる鬼瓦が多数発掘された。その後、徳島県教育委員会の指導のもと、吉野川市教育委員会が継続して調査を行ってきた。
記者会見での吉野川市の発表によれば、今年4月から進められていた第二次調査では、建物跡が金堂であることと、その位置が特定された。螺髪や鬼瓦も追加で多数発掘されており、発掘された瓦や土器の特徴からは、大日寺が奈良時代までには建立され、少なくとも平安時代まで存続していたことが分かった。
今回の発掘調査は7月末で終了し、吉野川市教育委員会は県指定文化財を目指して、今後報告書を作成する予定だ。遺跡現場は遺構や遺物を保護するために一旦埋め戻す。 今後のあり方については、 文化庁や徳島県の指導のもと、協議しながら検討していくという。
歴史的にも非常に大きな発見だが、徳島県の川島町で発掘されたことには、宗教的にも大きな意味がある。大日如来、すなわち毘盧遮那仏は、仏陀の悟りと修行、霊界の秘儀を象徴しており、幸福の科学の本尊であるエル・カンターレの一側面を表した存在だからだ。
大日寺の遺跡が発掘された場所は、再誕の仏陀である大川隆法総裁の生家にほど近い場所だ。今回の発掘で、当地には奈良時代から大日如来への信仰が集まっていたことがわかった。四国は現在でも八十八箇所の巡礼が行われている霊場である。川島町には、仏陀の再誕地という聖地としての下地ができていたと言えるだろう。遺跡発掘をきっかけに、四国の歴史的・宗教的意味にも再び注目していきたい。(晴)
【関連書籍】
幸福の科学出版 『仏陀再誕』 大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=175
幸福の科学出版 『信仰のすすめ』 大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=136
【関連記事】
Web限定記事 徳島・川島町「聖地」の証明 - 大川隆法・幸福の科学総裁の生誕地で「大日寺」の遺跡発見
http://the-liberty.com/article.php?item_id=5854
2013年6月号記事 Happy Science News The - Liberty 2013年6月号
http://the-liberty.com/article.php?item_id=5929
大川総裁の生誕地はやはり「聖地」 吉野川市教委が川島町の大日寺遺跡の発掘を報告
2014.07.03
徳島県吉野川市の吉野川市役所で3日、同市川島町で見つかった大日寺遺跡の発掘について、市教委の生涯学習課が記者会見を行った。この遺跡は幸福の科学川島特別支部の境内地から見つかったもので、幸福の科学は発掘調査に協力するため施設建設計画を見送っている。
川島特別支部は本誌取材に対し、以下のようにコメントした。「千年以上以前の古代寺院の遺跡発掘を通して、今後、この遺跡が徳島県や吉野川市のさらなる地域の活性化や観光資源となって、地域貢献できるように全面協力をしています。この協力に対し、徳島県や吉野川市の教育委員会や地域の皆様より多くの感謝のお言葉をいただいています」
大日寺とは、大日如来を本尊とする奈良時代の古代寺院と推定される。この大日如来とは、東大寺の大仏である毘盧遮那仏とも同一視されている。大日寺が川島町に存在していたことは、江戸時代の文献『阿波志(あわし)』に記述されており、『川島町史』(昭和54年刊行)では、大日寺が塔と金堂が東西に並ぶ法起寺式伽藍配置を持つと推定されていた。
大日寺遺跡が見つかったのは2012年秋から2013年にかけて行われた市の調査による。第一次調査では、同地からは大日寺の存在を確証する材料となる大日如来像の一部と考えられる「螺髪(らほつ)」や、大日如来像が安置されていた「金堂(こんどう)」の一部と考えられる鬼瓦が多数発掘された。その後、徳島県教育委員会の指導のもと、吉野川市教育委員会が継続して調査を行ってきた。
記者会見での吉野川市の発表によれば、今年4月から進められていた第二次調査では、建物跡が金堂であることと、その位置が特定された。螺髪や鬼瓦も追加で多数発掘されており、発掘された瓦や土器の特徴からは、大日寺が奈良時代までには建立され、少なくとも平安時代まで存続していたことが分かった。
今回の発掘調査は7月末で終了し、吉野川市教育委員会は県指定文化財を目指して、今後報告書を作成する予定だ。遺跡現場は遺構や遺物を保護するために一旦埋め戻す。 今後のあり方については、 文化庁や徳島県の指導のもと、協議しながら検討していくという。
歴史的にも非常に大きな発見だが、徳島県の川島町で発掘されたことには、宗教的にも大きな意味がある。大日如来、すなわち毘盧遮那仏は、仏陀の悟りと修行、霊界の秘儀を象徴しており、幸福の科学の本尊であるエル・カンターレの一側面を表した存在だからだ。
大日寺の遺跡が発掘された場所は、再誕の仏陀である大川隆法総裁の生家にほど近い場所だ。今回の発掘で、当地には奈良時代から大日如来への信仰が集まっていたことがわかった。四国は現在でも八十八箇所の巡礼が行われている霊場である。川島町には、仏陀の再誕地という聖地としての下地ができていたと言えるだろう。遺跡発掘をきっかけに、四国の歴史的・宗教的意味にも再び注目していきたい。(晴)
【関連書籍】
幸福の科学出版 『仏陀再誕』 大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=175
幸福の科学出版 『信仰のすすめ』 大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=136
【関連記事】
Web限定記事 徳島・川島町「聖地」の証明 - 大川隆法・幸福の科学総裁の生誕地で「大日寺」の遺跡発見
http://the-liberty.com/article.php?item_id=5854
2013年6月号記事 Happy Science News The - Liberty 2013年6月号
http://the-liberty.com/article.php?item_id=5929
http://news.biglobe.ne.jp/trend/0925/sgk_140925_5240992016.html
四国お遍路 各県の基本と難所・見所を専門家がレクチャー
NEWSポストセブン9月25日(木)16時0分
今年で開創1200年となる「四国遍路」。最近はバスや車で巡る観光客も増えており、気軽に楽しめるようになっているという。そこで、八十八ヶ所の寺院を気軽に巡りたいという初心者に、お遍路のプロである四国八十八ヶ所霊場会公認権大先達の横地稔さんと中大先達の貞美さんご夫妻が、エリアごとに基本を伝授する。
まずは徳島県。徳島県の札所は23か所。1番札所霊山寺を擁し、ここから全長約1400km、歩きなら40〜60日はかかる遍路道が始まる。
「徳島県はお遍路の始まりの土地のため、『発心(ほっしん)の道場』と呼ばれています。10番(切幡寺)くらいまでは比較的歩きやすいですが、11番(藤井寺)あたりから“遍路ころがし”と呼ばれる難所も始まり、徐々にきつい旅路になります」(横地さんご夫妻、以下「」同)
続く高知県の札所は16か所と4県でもっとも少ないが、お寺からお寺への距離が長く、歩き遍路ではまさに修行の場所。
「23番札所(徳島の薬王寺)と24番札所(高知の最御崎寺)は約75km離れており、歩くと3日はかかります。これを越えても、変化の少ない海辺の道が延々と続くため、高知は、自分と向かい合うための修行の場所とされています。とはいえ、室戸岬、足摺岬では絶景も楽しめます」
愛媛県の札所は26か所ともっとも多い。宇和海沿岸の穏やかな道が続くかと思えば、険しい山道に入っていく…。めまぐるしく変わる景色の中を進むのが特徴。
「厳しい環境が続いた高知の札所を歩ききると、体も鍛えられ、愛媛は比較的楽に越えられます。景色も変化に富み、名湯・道後温泉などの観光スポットもあるため、心の余裕も生まれるでしょう。とはいえ、43〜44番札所(明石寺〜大寶寺)までは約75km離れており、さらに46番札所(浄瑠璃寺)までは、険しい山道を行く難所が続きますので、まだまだ慢心はできません」
香川県の札所は全部で23か所。長かったお遍路の旅も、88か所を巡り終える“結願”(けちがん)へ向けて、クライマックスを迎える場所だ。
「香川の札所を『涅槃の道場』と呼びます。長く苦しい旅の末、煩悩を断ち、結願で悟りの境地を開くことに重ねて、こう呼ぶようです。88番(大窪寺)まで巡拝を終えたら、1番札所にお礼参りをし、高野山奥の院か、京都の東寺を訪れるまでが本来のお遍路になります」
※女性セブン2014年10月9日号
四国お遍路 各県の基本と難所・見所を専門家がレクチャー
NEWSポストセブン9月25日(木)16時0分
今年で開創1200年となる「四国遍路」。最近はバスや車で巡る観光客も増えており、気軽に楽しめるようになっているという。そこで、八十八ヶ所の寺院を気軽に巡りたいという初心者に、お遍路のプロである四国八十八ヶ所霊場会公認権大先達の横地稔さんと中大先達の貞美さんご夫妻が、エリアごとに基本を伝授する。
まずは徳島県。徳島県の札所は23か所。1番札所霊山寺を擁し、ここから全長約1400km、歩きなら40〜60日はかかる遍路道が始まる。
「徳島県はお遍路の始まりの土地のため、『発心(ほっしん)の道場』と呼ばれています。10番(切幡寺)くらいまでは比較的歩きやすいですが、11番(藤井寺)あたりから“遍路ころがし”と呼ばれる難所も始まり、徐々にきつい旅路になります」(横地さんご夫妻、以下「」同)
続く高知県の札所は16か所と4県でもっとも少ないが、お寺からお寺への距離が長く、歩き遍路ではまさに修行の場所。
「23番札所(徳島の薬王寺)と24番札所(高知の最御崎寺)は約75km離れており、歩くと3日はかかります。これを越えても、変化の少ない海辺の道が延々と続くため、高知は、自分と向かい合うための修行の場所とされています。とはいえ、室戸岬、足摺岬では絶景も楽しめます」
愛媛県の札所は26か所ともっとも多い。宇和海沿岸の穏やかな道が続くかと思えば、険しい山道に入っていく…。めまぐるしく変わる景色の中を進むのが特徴。
「厳しい環境が続いた高知の札所を歩ききると、体も鍛えられ、愛媛は比較的楽に越えられます。景色も変化に富み、名湯・道後温泉などの観光スポットもあるため、心の余裕も生まれるでしょう。とはいえ、43〜44番札所(明石寺〜大寶寺)までは約75km離れており、さらに46番札所(浄瑠璃寺)までは、険しい山道を行く難所が続きますので、まだまだ慢心はできません」
香川県の札所は全部で23か所。長かったお遍路の旅も、88か所を巡り終える“結願”(けちがん)へ向けて、クライマックスを迎える場所だ。
「香川の札所を『涅槃の道場』と呼びます。長く苦しい旅の末、煩悩を断ち、結願で悟りの境地を開くことに重ねて、こう呼ぶようです。88番(大窪寺)まで巡拝を終えたら、1番札所にお礼参りをし、高野山奥の院か、京都の東寺を訪れるまでが本来のお遍路になります」
※女性セブン2014年10月9日号
◆東大寺の大仏建立 なぜ民衆からお金を集めたの?【3分で学ぶ世界の教養】
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9215
「日本が、アジアで最も栄えた仏教国の一つだった」ことを象徴するのが、奈良県・東大寺にある毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)像、いわゆる奈良の大仏です。
この大仏は、仏教伝来(552年)から、ちょうと200年目の節目に合わせて、752年に開眼されました。
この大仏建立事業を、日本文化の精華として評価する声もあれば、為政者が民を苦しめた例として批判する声もあります。
当時の聖武天皇は、なぜこうした事業を行ったのでしょうか。大仏建立の背景にあった宗教的思想について、仏教の経典や聖武天皇の詔(みことのり)などから見ていきます。
「三宝の威力で天地を安泰に」
大仏開眼の20年前である732年には、全国で干ばつ、飢饉、地震、台風が相次いで発生しました。
その翌年にも大地震が起き、各地で山が崩れ、土砂で川がせき止められ、地割れが起き、多数の死者が出ました。さらにその翌年には疫病も流行しました。
当時、こうした天災は「政治家が深い信仰心を持つことで防ぐべき」という思想がありました。いわゆる「鎮護国家」思想です。 この教えが説かれているのが『金光明最勝王経(こんこうみょうさいしょうおうきょう)』。
聖武天皇の5代前の天武天皇が日本の政治の中心に位置づけた経文です。そこには、「為政者が仏法を尊重すれば、四天王が国を守護し、あらゆる災難から国を護ってくれる。
逆に為政者が仏法を軽んじれば、自然災害や疫病などが頻発する」といった内容が記されています。
いわば、仏教版「帝王学」です。 聖武天皇は、この「鎮護国家」を目指し、信仰心を示すために、大仏建立を決めたのです。天皇は「大仏造顕の詔」で、「仏法の恩徳が、国土すべてにいきわたってはいない。
三宝の威力によって天地を安泰にする」
と述べています。 ちなみに、東大寺の正式名称は、「金光明四天王護国之寺」。「『金光明最勝王経』の教えに基づき、四天王の力で国を護る」という理念が込められています。
あくまで信仰心で寄進する
大仏建立の事業で特徴的なのが「資金や労役を、民からの自主的な寄進で集めた」という点です。聖武天皇は詔で以下のように述べています。
「そもそも天下の富と勢いを所持しているのは私である。
その富と勢いで、この尊い像をつくるのは簡単だが、それでは像をつくる真意は果たされない」「もし一枝の草、一把の土という、わずかなものであっても、進んで造像事業に参加しようとする者があれば皆許そう」「役人たちは、この事業を理由として民の財産を侵害し、租税を収奪してはならない」 実際に材木、労働、金銭などを自主的に寄進した人は、合わせて260万3638人だったという記録が残っています。
これは、当時の人口の半分にあたります。もちろん、貧乏な農民も多い時代。
2文(現在の100円)という小額の寄進も、しっかり木簡に残されています。
聖武天皇は、なぜこうした事業形態をとったのでしょうか。
詔ではこう述べています。 「この大事業を広く呼びかけ、その趣旨に賛同する者を私の友として、最後
には皆とともに仏の利益を受け、悟りの境地に到達したい」 なけなしのお金の寄進でも、事業に自主的に参加する民衆は自分の信仰心を高め、功徳を積むことができます。
それにより、国の大半の民が救われ、国が平らかになる――。
それが大仏建立事業の大きな目的だったのです。
この考えが、単に「お金を集める口実」でないことが分かるのが、詔の次の言葉です。
「この事業を行う上で恐れるべきは、民に苦労をかけるだけで、その聖なる心を分からせることができないこと。
誹謗中傷の心を起こさせて、かえって罪に陥る者が出てくる。
そこで、造像に参加するものは、誠に至誠の心をもってこれに当たり、大いなる幸せを招きいれ、日に三回、心の中の盧遮那仏を拝むといい」 単に寄進が進み大仏が建つことではなく、仏への信仰心を動機とした寄進で大仏が建てられることが大前提でした。
天皇のみならず、多くの人々が信仰心を深める機会を持つことが、国の繁栄につながる――。
これが大仏建立の思想であり、大仏は「為政者や人々の信仰の象徴」なのです。
東大寺盧舎那仏像
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E7%9B%A7%E8%88%8E%E9%82%A3%E4%BB%8F%E5%83%8F
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9215
「日本が、アジアで最も栄えた仏教国の一つだった」ことを象徴するのが、奈良県・東大寺にある毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)像、いわゆる奈良の大仏です。
この大仏は、仏教伝来(552年)から、ちょうと200年目の節目に合わせて、752年に開眼されました。
この大仏建立事業を、日本文化の精華として評価する声もあれば、為政者が民を苦しめた例として批判する声もあります。
当時の聖武天皇は、なぜこうした事業を行ったのでしょうか。大仏建立の背景にあった宗教的思想について、仏教の経典や聖武天皇の詔(みことのり)などから見ていきます。
「三宝の威力で天地を安泰に」
大仏開眼の20年前である732年には、全国で干ばつ、飢饉、地震、台風が相次いで発生しました。
その翌年にも大地震が起き、各地で山が崩れ、土砂で川がせき止められ、地割れが起き、多数の死者が出ました。さらにその翌年には疫病も流行しました。
当時、こうした天災は「政治家が深い信仰心を持つことで防ぐべき」という思想がありました。いわゆる「鎮護国家」思想です。 この教えが説かれているのが『金光明最勝王経(こんこうみょうさいしょうおうきょう)』。
聖武天皇の5代前の天武天皇が日本の政治の中心に位置づけた経文です。そこには、「為政者が仏法を尊重すれば、四天王が国を守護し、あらゆる災難から国を護ってくれる。
逆に為政者が仏法を軽んじれば、自然災害や疫病などが頻発する」といった内容が記されています。
いわば、仏教版「帝王学」です。 聖武天皇は、この「鎮護国家」を目指し、信仰心を示すために、大仏建立を決めたのです。天皇は「大仏造顕の詔」で、「仏法の恩徳が、国土すべてにいきわたってはいない。
三宝の威力によって天地を安泰にする」
と述べています。 ちなみに、東大寺の正式名称は、「金光明四天王護国之寺」。「『金光明最勝王経』の教えに基づき、四天王の力で国を護る」という理念が込められています。
あくまで信仰心で寄進する
大仏建立の事業で特徴的なのが「資金や労役を、民からの自主的な寄進で集めた」という点です。聖武天皇は詔で以下のように述べています。
「そもそも天下の富と勢いを所持しているのは私である。
その富と勢いで、この尊い像をつくるのは簡単だが、それでは像をつくる真意は果たされない」「もし一枝の草、一把の土という、わずかなものであっても、進んで造像事業に参加しようとする者があれば皆許そう」「役人たちは、この事業を理由として民の財産を侵害し、租税を収奪してはならない」 実際に材木、労働、金銭などを自主的に寄進した人は、合わせて260万3638人だったという記録が残っています。
これは、当時の人口の半分にあたります。もちろん、貧乏な農民も多い時代。
2文(現在の100円)という小額の寄進も、しっかり木簡に残されています。
聖武天皇は、なぜこうした事業形態をとったのでしょうか。
詔ではこう述べています。 「この大事業を広く呼びかけ、その趣旨に賛同する者を私の友として、最後
には皆とともに仏の利益を受け、悟りの境地に到達したい」 なけなしのお金の寄進でも、事業に自主的に参加する民衆は自分の信仰心を高め、功徳を積むことができます。
それにより、国の大半の民が救われ、国が平らかになる――。
それが大仏建立事業の大きな目的だったのです。
この考えが、単に「お金を集める口実」でないことが分かるのが、詔の次の言葉です。
「この事業を行う上で恐れるべきは、民に苦労をかけるだけで、その聖なる心を分からせることができないこと。
誹謗中傷の心を起こさせて、かえって罪に陥る者が出てくる。
そこで、造像に参加するものは、誠に至誠の心をもってこれに当たり、大いなる幸せを招きいれ、日に三回、心の中の盧遮那仏を拝むといい」 単に寄進が進み大仏が建つことではなく、仏への信仰心を動機とした寄進で大仏が建てられることが大前提でした。
天皇のみならず、多くの人々が信仰心を深める機会を持つことが、国の繁栄につながる――。
これが大仏建立の思想であり、大仏は「為政者や人々の信仰の象徴」なのです。
東大寺盧舎那仏像
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E7%9B%A7%E8%88%8E%E9%82%A3%E4%BB%8F%E5%83%8F
◆高野山の開創1200周年大法会 空海の「鎮護国家」の精神に思いをはせる
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9389
弘法大師・空海が開いた高野山(和歌山県高野町)は、開創1200周年を迎えるにあたり、4月2日から5月21日まで、一般の人も参加できる大法会(ほうえ)を開く。期間中に最大30万人の人出があると予想され、参道などの整備が進んでいる。1843年に火災で焼失した檀上伽藍の中門が170年ぶりに再建されたほか、秘仏や秘宝の公開なども予定されている。21日付産経などが報じた。
空海は平安時代に唐へ渡り、恵果和尚から密教の正統を継ぐ地位を与えられ、教法を伝授された。このとき、現地に1000人はいた弟子たちをごぼう抜きにしての伝授だったという。帰国後は高野山を「最も禅の修行の道場にかなった地」であるとして金剛峰寺を建てた。唐から持ち帰ったお経の中には建築技術なども含まれており、ため池である満膿池の修築などでも知られている。
歴代天皇の信任の厚かった空海は、疫病が流行した時などにたびたび天皇の相談を受け、政治に関しても発言している。
空海は若い頃に四国や近畿で山林修行をしており、四国八十八カ所のお遍路は、空海の弟子・真済が、空海の遺蹟をたどったことが起源だとされている。真言宗系の信徒は現在、約920万人といわれ、空海は、1200年が経っても信仰を集め続けている(「宗教年鑑」平成24年版)。
宗教と政治の両方に才能があった空海は、現代の日本に対してどのような意見を持っているのだろうか。大川隆法・幸福の科学総裁は2011年、菅直人首相(当時)が、退任後にお遍路に行きたいと発言していたころに空海の霊言を収録している(幸福の科学出版刊『もし空海が民主党政権を見たら何というか』所収、下記関連書籍参照)。
空海の霊は、自身が密教を国教とすることによって「鎮護国家」を目指していたことや、当時の政治家が宗教家に頼り、その法力で国を守ろうとしていたことなどに触れながら、宗教と政治の本来あるべき関係について語った。
高野山や四国八十八カ所のような、境内があり、本尊が安置されるなど、宗教的な磁場のあるお寺や神社は、霊界とつながっている場所でもある。
かつて空海は「すべての人を救いたい」と誓願し、政治にも助言をしていた。しかし、現代において、政治にはウソやごまかしがつきものというイメージがある。高野山開創1200年を機に、空海に思いをはせ、政治のあるべき姿を描いてみてはいかがだろうか。(居)
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9389
弘法大師・空海が開いた高野山(和歌山県高野町)は、開創1200周年を迎えるにあたり、4月2日から5月21日まで、一般の人も参加できる大法会(ほうえ)を開く。期間中に最大30万人の人出があると予想され、参道などの整備が進んでいる。1843年に火災で焼失した檀上伽藍の中門が170年ぶりに再建されたほか、秘仏や秘宝の公開なども予定されている。21日付産経などが報じた。
空海は平安時代に唐へ渡り、恵果和尚から密教の正統を継ぐ地位を与えられ、教法を伝授された。このとき、現地に1000人はいた弟子たちをごぼう抜きにしての伝授だったという。帰国後は高野山を「最も禅の修行の道場にかなった地」であるとして金剛峰寺を建てた。唐から持ち帰ったお経の中には建築技術なども含まれており、ため池である満膿池の修築などでも知られている。
歴代天皇の信任の厚かった空海は、疫病が流行した時などにたびたび天皇の相談を受け、政治に関しても発言している。
空海は若い頃に四国や近畿で山林修行をしており、四国八十八カ所のお遍路は、空海の弟子・真済が、空海の遺蹟をたどったことが起源だとされている。真言宗系の信徒は現在、約920万人といわれ、空海は、1200年が経っても信仰を集め続けている(「宗教年鑑」平成24年版)。
宗教と政治の両方に才能があった空海は、現代の日本に対してどのような意見を持っているのだろうか。大川隆法・幸福の科学総裁は2011年、菅直人首相(当時)が、退任後にお遍路に行きたいと発言していたころに空海の霊言を収録している(幸福の科学出版刊『もし空海が民主党政権を見たら何というか』所収、下記関連書籍参照)。
空海の霊は、自身が密教を国教とすることによって「鎮護国家」を目指していたことや、当時の政治家が宗教家に頼り、その法力で国を守ろうとしていたことなどに触れながら、宗教と政治の本来あるべき関係について語った。
高野山や四国八十八カ所のような、境内があり、本尊が安置されるなど、宗教的な磁場のあるお寺や神社は、霊界とつながっている場所でもある。
かつて空海は「すべての人を救いたい」と誓願し、政治にも助言をしていた。しかし、現代において、政治にはウソやごまかしがつきものというイメージがある。高野山開創1200年を機に、空海に思いをはせ、政治のあるべき姿を描いてみてはいかがだろうか。(居)
11月27日。
知り合いの方からメールが来た。
それが以下の書籍の紹介。
空海の思想について (講談社学術文庫) | 梅原 猛 |本 | 通販 | Amazon
https://www.amazon.co.jp/%E7%A9%BA%E6%B5%B7%E3%81%AE%E6%80%9D%E6%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E5%AD%A6%E8%A1%93%E6%96%87%E5%BA%AB-%E6%A2%85%E5%8E%9F-%E7%8C%9B/dp/406158460X?SubscriptionId=AKIAI7F5LWAIHOKT3ILA&tag=pnecmd-22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=406158460X
以下、文章を転載します。
「たぶん、来年あたりから、
四国のほうだと関係あるかもしれないので、念のためご紹介します。
内容自体は題名通りですが、
珍しく著者の認識力や主観などの問題で変な劣化などが少ないのでオススメします。
主に『空海の密教』の『思想』と『仏教哲理』についての仏教的な『解説』です。
しっかり『大日如来』や『未来仏』とかにも触れられているので、
『当会的にもオススメ』だったりします。
内容が『内容』なので、ちゃんと『理解できる』推奨の認識力が7次元の中以上になるんで、
予めご了承ください。
ただ、空海と仏教の教学が充分なら、“なんとなく”までならいけるかも。
必要なら、支部なりの蔵書にもどうぞ。」
と、言う訳でご参考にしてください。<m(__)m>
尚、「来年」と言えば「信仰の法」でしたよね・・・。
「信仰の法」
地球神エル・カンターレとは
・著者 大川隆法
・定価 2,160 円(税込)
・四六判 309頁
・発刊元 幸福の科学出版
・ISBN 978-4-86395-957-6
・発刊日 2017-12-04
人種、文化、政治、そして宗教――
さまざまな価値観の違いを超えて、
この地球は“ひとつ”になれる。
人類が求めてきた
「永遠の疑問」に対する
「答え」が、この一冊に。
あなたが抱える
どんな悩みも苦しみも、
この世界の争いや
憎しみの連鎖さえも。
「信じる力」によって、
超えていける――。
【著作2300書突破!
世界100ヵ国以上
(29言語)に
愛読者を持つ
著者渾身の一書!】
まえがき
第1章 信じる力
──人生と世界の新しい現実を創り出す
第2章 愛から始まる
──「人生の問題集」を解き、「人生学のプロ」になる
第3章 未来への扉
──人生三万日を世界のために使って生きる
第4章 「日本発世界宗教」が地球を救う
──この星から紛争をなくすための国造りを
第5章 地球神への信仰とは何か
──新しい地球創世記の時代を生きる
第6章 人類の選択
──地球神の下に自由と民主主義を掲げよ
あとがき
知り合いの方からメールが来た。
それが以下の書籍の紹介。
空海の思想について (講談社学術文庫) | 梅原 猛 |本 | 通販 | Amazon
https://www.amazon.co.jp/%E7%A9%BA%E6%B5%B7%E3%81%AE%E6%80%9D%E6%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E5%AD%A6%E8%A1%93%E6%96%87%E5%BA%AB-%E6%A2%85%E5%8E%9F-%E7%8C%9B/dp/406158460X?SubscriptionId=AKIAI7F5LWAIHOKT3ILA&tag=pnecmd-22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=406158460X
以下、文章を転載します。
「たぶん、来年あたりから、
四国のほうだと関係あるかもしれないので、念のためご紹介します。
内容自体は題名通りですが、
珍しく著者の認識力や主観などの問題で変な劣化などが少ないのでオススメします。
主に『空海の密教』の『思想』と『仏教哲理』についての仏教的な『解説』です。
しっかり『大日如来』や『未来仏』とかにも触れられているので、
『当会的にもオススメ』だったりします。
内容が『内容』なので、ちゃんと『理解できる』推奨の認識力が7次元の中以上になるんで、
予めご了承ください。
ただ、空海と仏教の教学が充分なら、“なんとなく”までならいけるかも。
必要なら、支部なりの蔵書にもどうぞ。」
と、言う訳でご参考にしてください。<m(__)m>
尚、「来年」と言えば「信仰の法」でしたよね・・・。
「信仰の法」
地球神エル・カンターレとは
・著者 大川隆法
・定価 2,160 円(税込)
・四六判 309頁
・発刊元 幸福の科学出版
・ISBN 978-4-86395-957-6
・発刊日 2017-12-04
人種、文化、政治、そして宗教――
さまざまな価値観の違いを超えて、
この地球は“ひとつ”になれる。
人類が求めてきた
「永遠の疑問」に対する
「答え」が、この一冊に。
あなたが抱える
どんな悩みも苦しみも、
この世界の争いや
憎しみの連鎖さえも。
「信じる力」によって、
超えていける――。
【著作2300書突破!
世界100ヵ国以上
(29言語)に
愛読者を持つ
著者渾身の一書!】
まえがき
第1章 信じる力
──人生と世界の新しい現実を創り出す
第2章 愛から始まる
──「人生の問題集」を解き、「人生学のプロ」になる
第3章 未来への扉
──人生三万日を世界のために使って生きる
第4章 「日本発世界宗教」が地球を救う
──この星から紛争をなくすための国造りを
第5章 地球神への信仰とは何か
──新しい地球創世記の時代を生きる
第6章 人類の選択
──地球神の下に自由と民主主義を掲げよ
あとがき
https://the-liberty.com/article.php?item_id=14196
映画公開で話題の空海 「天才」の湯川秀樹が「超人」と評価した人物だった
2018.03.03
《本記事のポイント》
映画「空海」で描かれた「中国から密教を"持ち去った"」謎
湯川秀樹「アリストテレス、レオナルド・ダ・ヴィンチより万能」
ヘーゲルに比肩される思想家
日中合作映画「空海―KU-KAI―美しき王妃の謎」の公開に伴い、弘法大師・空海にスポットライトが当たっている。
映画の宣伝も兼ねてだろうが、テレビ番組や各メディアでも、空海に関するものが数多く放送されている。
中国から密教を"持ち去った"
映画では、空海が唐の長安を訪ね、密教の後継者となった"秘密"が描かれている。
当時の唐において、中国仏教は最盛期を迎えていた。空海が訪ねた恵果和尚は、密教の正当な継承者であり、玄宗をはじめとする三代の皇帝にも頼りにされた、長安で最も有名な僧だ。
空海は恵果を訪れ、密教の全てを伝授された。そして、1000人の弟子をごぼう抜きにし、正統な継承者に指名された。唐の人々からすれば、"後進国"の若い留学生に文化の中心部分を丸ごと"持ち去られた"ようなものだ。
映画におけるその経緯の描かれ方はエンターテイメント化されすぎているきらいがある。空海の思想の深遠さを知る人は納得がいかないかもしれない。「仏教映画だと思って見るとがっかりする」という声もある。
とはいえ、空海が世界史に残る"離れ業"をやってのけたことは紛れもない史実だ。今回の映画は、日本人がその天才性を再確認する機会にはなるかもしれない。
天才・湯川秀樹が「超人」と評価
日本人初のノーベル賞受賞者であり、この国の「代表的天才」である湯川秀樹博士は、空海をこう評している。
「世界的スケールで見ても、アリストテレスとか、レオナルド・ダ・ヴィンチとかいうような人よりも、むしろ幅が広い。宗教、文芸、美術、学問、技術、社会事業の各方面にわたる活動を通観すると、超人的というほかない」
空海はこの言葉の通り、万能の天才だった。
空海が、嵯峨天皇、橘逸勢と並び「三筆」と呼ばれた書の達人だったことは有名だ。入唐した際も、天皇の国書を持っていなかったため、入国が認められないというトラブルに見舞われた。そこでも空海は、見事な内容と筆で嘆願書を作成した。すると「これほどの文章をつくれる人物が、怪しい人物であるはずがない」と入国が認められたのだ。他にも、平仮名の「ん」を発明するなど、文芸の第一人者でもあった。
また美術の面でも、曼荼羅の絵を自分で描くことができ、仏像も自分で彫れたという説もある。さらに讃岐の満濃池の修復を監督するなど、一流の技術を持っていたことがうかがえる。
映画公開で話題の空海 「天才」の湯川秀樹が「超人」と評価した人物だった
2018.03.03
《本記事のポイント》
映画「空海」で描かれた「中国から密教を"持ち去った"」謎
湯川秀樹「アリストテレス、レオナルド・ダ・ヴィンチより万能」
ヘーゲルに比肩される思想家
日中合作映画「空海―KU-KAI―美しき王妃の謎」の公開に伴い、弘法大師・空海にスポットライトが当たっている。
映画の宣伝も兼ねてだろうが、テレビ番組や各メディアでも、空海に関するものが数多く放送されている。
中国から密教を"持ち去った"
映画では、空海が唐の長安を訪ね、密教の後継者となった"秘密"が描かれている。
当時の唐において、中国仏教は最盛期を迎えていた。空海が訪ねた恵果和尚は、密教の正当な継承者であり、玄宗をはじめとする三代の皇帝にも頼りにされた、長安で最も有名な僧だ。
空海は恵果を訪れ、密教の全てを伝授された。そして、1000人の弟子をごぼう抜きにし、正統な継承者に指名された。唐の人々からすれば、"後進国"の若い留学生に文化の中心部分を丸ごと"持ち去られた"ようなものだ。
映画におけるその経緯の描かれ方はエンターテイメント化されすぎているきらいがある。空海の思想の深遠さを知る人は納得がいかないかもしれない。「仏教映画だと思って見るとがっかりする」という声もある。
とはいえ、空海が世界史に残る"離れ業"をやってのけたことは紛れもない史実だ。今回の映画は、日本人がその天才性を再確認する機会にはなるかもしれない。
天才・湯川秀樹が「超人」と評価
日本人初のノーベル賞受賞者であり、この国の「代表的天才」である湯川秀樹博士は、空海をこう評している。
「世界的スケールで見ても、アリストテレスとか、レオナルド・ダ・ヴィンチとかいうような人よりも、むしろ幅が広い。宗教、文芸、美術、学問、技術、社会事業の各方面にわたる活動を通観すると、超人的というほかない」
空海はこの言葉の通り、万能の天才だった。
空海が、嵯峨天皇、橘逸勢と並び「三筆」と呼ばれた書の達人だったことは有名だ。入唐した際も、天皇の国書を持っていなかったため、入国が認められないというトラブルに見舞われた。そこでも空海は、見事な内容と筆で嘆願書を作成した。すると「これほどの文章をつくれる人物が、怪しい人物であるはずがない」と入国が認められたのだ。他にも、平仮名の「ん」を発明するなど、文芸の第一人者でもあった。
また美術の面でも、曼荼羅の絵を自分で描くことができ、仏像も自分で彫れたという説もある。さらに讃岐の満濃池の修復を監督するなど、一流の技術を持っていたことがうかがえる。
ヘーゲルに比肩される思想家
とはいえ、やはり空海のすごいところは、その思想だ。湯川博士はこう述べている。
「もうひとつ特筆すべきは、おそらく空海は独自の思想体系を構築した最初の日本人だったろうことである。当時の日本と中国の間の思想・文化の落差が、非常に大きかったことを考え合わせると、これまた奇蹟的である」
著名な哲学者である梅原猛氏も、空海とヘーゲルの思想展開が似ていることを次のように指摘している。
「私もカント、ヒィフテ、ヘーゲルなんていうのを、学生時代に難解な辞書を読んだわけですね。そういうのを読んで、日本の思想の研究などに入ったんですけど、ヘーゲルを読んだ人間として、『十住心論』を読んだ時に、『これヘーゲルじゃないか』と(思った)」(1998年6月14日のNHK教育テレビ「こころの時代」より)
実際に、ヘーゲルの『精神現象学』といった思想と、空海の思想を比較する研究などもある。空海が活躍したのは、ヘーゲルの時代から十世紀も前のことだ。
本誌2012年8月号記事においても、評論家の黄文雄氏はこう評している。
「空海が『十住心論』の中で、原始的な煩悩の心、儒教的な道徳心、老荘思想と段階を踏んで、その上に小乗仏教、大乗仏教の宗派の心を置いて、いちばん上に自分の真言密教の境地を位置づけた。これはヘーゲル哲学を上回ると私は思うんです」
また、作家の司馬遼太郎も、著作『空海の風景』で、その思想の普遍性についてこう評している。
「空海はすでに、人間とか人類というものに共通する原理を知った。空海が会得した原理には、王も民もなく、さらにはかれは長安で人類というものは多くの民族にわかれているということを目で見て知ったが、仏教もしくは大日如来の密教はそれをも超越したもの(中略)日本の歴史上の人物としての空海の印象の特異さは、このあたりにあるかもしれない。言いかえれば、空海だけが日本の歴史のなかで民族社会的な存在でなく、人類的な存在だったということがいえるのではないか」
ヘーゲルやカントといった一流の思想家が、ドイツという国の地位を押し上げている面は大きい。空海という天才を生んだ日本も、もっと空海の天才性を誇り、世界に打ち出していく必要があるのではないか。
(馬場光太郎)
【関連記事】
2015年3月21日付本欄 高野山の開創1200周年大法会 空海の「鎮護国家」の精神に思いをはせる
https://the-liberty.com/article.php?item_id=9389
とはいえ、やはり空海のすごいところは、その思想だ。湯川博士はこう述べている。
「もうひとつ特筆すべきは、おそらく空海は独自の思想体系を構築した最初の日本人だったろうことである。当時の日本と中国の間の思想・文化の落差が、非常に大きかったことを考え合わせると、これまた奇蹟的である」
著名な哲学者である梅原猛氏も、空海とヘーゲルの思想展開が似ていることを次のように指摘している。
「私もカント、ヒィフテ、ヘーゲルなんていうのを、学生時代に難解な辞書を読んだわけですね。そういうのを読んで、日本の思想の研究などに入ったんですけど、ヘーゲルを読んだ人間として、『十住心論』を読んだ時に、『これヘーゲルじゃないか』と(思った)」(1998年6月14日のNHK教育テレビ「こころの時代」より)
実際に、ヘーゲルの『精神現象学』といった思想と、空海の思想を比較する研究などもある。空海が活躍したのは、ヘーゲルの時代から十世紀も前のことだ。
本誌2012年8月号記事においても、評論家の黄文雄氏はこう評している。
「空海が『十住心論』の中で、原始的な煩悩の心、儒教的な道徳心、老荘思想と段階を踏んで、その上に小乗仏教、大乗仏教の宗派の心を置いて、いちばん上に自分の真言密教の境地を位置づけた。これはヘーゲル哲学を上回ると私は思うんです」
また、作家の司馬遼太郎も、著作『空海の風景』で、その思想の普遍性についてこう評している。
「空海はすでに、人間とか人類というものに共通する原理を知った。空海が会得した原理には、王も民もなく、さらにはかれは長安で人類というものは多くの民族にわかれているということを目で見て知ったが、仏教もしくは大日如来の密教はそれをも超越したもの(中略)日本の歴史上の人物としての空海の印象の特異さは、このあたりにあるかもしれない。言いかえれば、空海だけが日本の歴史のなかで民族社会的な存在でなく、人類的な存在だったということがいえるのではないか」
ヘーゲルやカントといった一流の思想家が、ドイツという国の地位を押し上げている面は大きい。空海という天才を生んだ日本も、もっと空海の天才性を誇り、世界に打ち出していく必要があるのではないか。
(馬場光太郎)
【関連記事】
2015年3月21日付本欄 高野山の開創1200周年大法会 空海の「鎮護国家」の精神に思いをはせる
https://the-liberty.com/article.php?item_id=9389
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
死後の世界は存在します。 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
死後の世界は存在します。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90011人
- 2位
- 酒好き
- 170663人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人