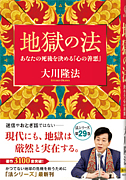サブタイトル 「人は死んだらどうなるか」
目次
永遠の生命の世界
第一章 死の下の平等
1 なぜ宗教という分野の仕事があるか
宗教家は死の専門家でなければいけない
「生老病死」は宗教の根本問題
現代の科学は生命が理解できていない
2 目に見える世界以外の力が働いている
科学による第一原因論は迷信に聞こえる
光の粒子が持つ機能
動植物に見る「生命を育んでいる力」
3 「人は必ず死ぬものだ」という覚悟を
人生は一枚の葉っぱのようなもの
死は突然にやってくる
4 霊界での新しい経験
あの世にも子育てがある
天使の予備軍は、死んだ人を導く仕事をする
死を自覚させるための、さまざまな方便
霊界での経験値を増やしていく
唯物論的な人を説得するのは難しい
“思想犯”は「無間地獄」に隔離される
5 死後、あの世での行き先が決まるまで
自分の死を信じない人もたくさんいる
儀式としての「三途の川」
三途の川を渡らない場合
過去を写す「照魔の鏡」
守護霊は“生前ビデオ”を撮っている
誰からも見られてもいいような人生を
第二章 死後の魂について(質疑応答)
1 死期が近づいた人間の魂の様相
死の一年ぐらい前から、さまざまな準備が始まる
2 死後、人間の魂はどうなるか
魂が肉体から離れるまでの状況
地上を去り、死後の世界へ
3 死後の世界での年齢について
死後三年ぐらいで、自分が望む年齢の姿になれる
子供の魂は天上界で大人にしていく
4 自殺した人の霊はどうなるか
自殺霊は自縛霊になることが多い
自殺霊が天国に行くための条件
5 戦争や震災による不成仏霊たちの供養
多くの人を供養するには、かなりのエネルギーが要る
不慮の死で天上界に還った人は生まれ変わりが早い
地域浄化のための供養は三年目ぐらいまで
6 あの世を信じていない人への伝道の意義
あの世の知識があると、死後気づくのが早い
まずは知識を入れ、さらに信仰を持つ
7 脳死についての考え方
「霊子線」の切れたときが死である
内臓には意識がある
脳の機能が止まった段階で臓器を取られたら痛い
第三章 脳死と臓器移植の問題点
1 真実を知る宗教家として、正論を述べる
2 ほんとうの死とは何か
「唯脳論」は新しい唯物論
魂こそが人間の本体である
脳死状態では魂はまだ生きようとしている
臓器移植に伴う憑依現象
臓器提供者は、あの世でどうなるか
「霊肉二元」(れいにくにげん)ではなく「色心不二」(しきしんふに)が正しい
死とは肉体から魂が離脱すること
3 現代の医学は、まだまだ未開の状態にある
人工流産は霊界の混乱を引き起こしている
心臓移植は古代の宗教儀式の復活
第四章 先祖供養の真実
1 先祖供養の意義
宗教の第一使命とは
先祖供養―――過去に生きた人に対する救済
2 先祖供養における注意点
「奪う愛」へのすり替え
供養の原点―――自分自身が光を発する
供養大祭の霊的意味
3 死はあの世への旅立ち
「諸行無常」としての死
死は永遠の別れではない
4 救済の前段階―――責任の自覚
5 晩年を生きる心構え
この世への執着を断つ
発展がもたらす世代間の断絶
「滅びの美学」を持って生きる
第五章 永遠の生命の世界
1 この世は、かりそめの世界
この世が仮の世であることの証拠
人生における、さまざまな苦悩
2 魂を鍛え、光らせるために
3 真実の価値観に基づいた仏国土を
幸福の科学出版。
http://
amazon.co.jp。
http://
幸福の科学関連書籍トピック。
http://
目次
永遠の生命の世界
第一章 死の下の平等
1 なぜ宗教という分野の仕事があるか
宗教家は死の専門家でなければいけない
「生老病死」は宗教の根本問題
現代の科学は生命が理解できていない
2 目に見える世界以外の力が働いている
科学による第一原因論は迷信に聞こえる
光の粒子が持つ機能
動植物に見る「生命を育んでいる力」
3 「人は必ず死ぬものだ」という覚悟を
人生は一枚の葉っぱのようなもの
死は突然にやってくる
4 霊界での新しい経験
あの世にも子育てがある
天使の予備軍は、死んだ人を導く仕事をする
死を自覚させるための、さまざまな方便
霊界での経験値を増やしていく
唯物論的な人を説得するのは難しい
“思想犯”は「無間地獄」に隔離される
5 死後、あの世での行き先が決まるまで
自分の死を信じない人もたくさんいる
儀式としての「三途の川」
三途の川を渡らない場合
過去を写す「照魔の鏡」
守護霊は“生前ビデオ”を撮っている
誰からも見られてもいいような人生を
第二章 死後の魂について(質疑応答)
1 死期が近づいた人間の魂の様相
死の一年ぐらい前から、さまざまな準備が始まる
2 死後、人間の魂はどうなるか
魂が肉体から離れるまでの状況
地上を去り、死後の世界へ
3 死後の世界での年齢について
死後三年ぐらいで、自分が望む年齢の姿になれる
子供の魂は天上界で大人にしていく
4 自殺した人の霊はどうなるか
自殺霊は自縛霊になることが多い
自殺霊が天国に行くための条件
5 戦争や震災による不成仏霊たちの供養
多くの人を供養するには、かなりのエネルギーが要る
不慮の死で天上界に還った人は生まれ変わりが早い
地域浄化のための供養は三年目ぐらいまで
6 あの世を信じていない人への伝道の意義
あの世の知識があると、死後気づくのが早い
まずは知識を入れ、さらに信仰を持つ
7 脳死についての考え方
「霊子線」の切れたときが死である
内臓には意識がある
脳の機能が止まった段階で臓器を取られたら痛い
第三章 脳死と臓器移植の問題点
1 真実を知る宗教家として、正論を述べる
2 ほんとうの死とは何か
「唯脳論」は新しい唯物論
魂こそが人間の本体である
脳死状態では魂はまだ生きようとしている
臓器移植に伴う憑依現象
臓器提供者は、あの世でどうなるか
「霊肉二元」(れいにくにげん)ではなく「色心不二」(しきしんふに)が正しい
死とは肉体から魂が離脱すること
3 現代の医学は、まだまだ未開の状態にある
人工流産は霊界の混乱を引き起こしている
心臓移植は古代の宗教儀式の復活
第四章 先祖供養の真実
1 先祖供養の意義
宗教の第一使命とは
先祖供養―――過去に生きた人に対する救済
2 先祖供養における注意点
「奪う愛」へのすり替え
供養の原点―――自分自身が光を発する
供養大祭の霊的意味
3 死はあの世への旅立ち
「諸行無常」としての死
死は永遠の別れではない
4 救済の前段階―――責任の自覚
5 晩年を生きる心構え
この世への執着を断つ
発展がもたらす世代間の断絶
「滅びの美学」を持って生きる
第五章 永遠の生命の世界
1 この世は、かりそめの世界
この世が仮の世であることの証拠
人生における、さまざまな苦悩
2 魂を鍛え、光らせるために
3 真実の価値観に基づいた仏国土を
幸福の科学出版。
http://
amazon.co.jp。
http://
幸福の科学関連書籍トピック。
http://
|
|
|
|
コメント(12)
まえがき
今から二千五百数十年前、北インドの釈迦族の王子ゴータマ・シッダールタ(釈尊)は、人間にはなぜ「生」「老」「病」「死」の四苦の苦しみがあるのか、その問への答えを求めて出家した。そして「真理」とは何か、「善」とは何かを巡って「悟り」を目指した。
本書が、釈尊の疑問への答えである。迷える宗教家への導きであると同時に、無明に生きる現代の医者や科学者への厳しい警鐘ともなっている。
最初に真理を発見し、確信するのは、いつの時代もただ一人である。そしてその真理を伝えんとする情熱が、人の心から心へと伝わり、時代を経て、多くの人々に覚醒をもたらす。
本書は真実の世界の秘密を知る宗教家としての、私の使命をかけた一書であり、必ず後世に遺さなければならない真理でもある。
2004年 春
幸福の科学総裁 大川隆法
今から二千五百数十年前、北インドの釈迦族の王子ゴータマ・シッダールタ(釈尊)は、人間にはなぜ「生」「老」「病」「死」の四苦の苦しみがあるのか、その問への答えを求めて出家した。そして「真理」とは何か、「善」とは何かを巡って「悟り」を目指した。
本書が、釈尊の疑問への答えである。迷える宗教家への導きであると同時に、無明に生きる現代の医者や科学者への厳しい警鐘ともなっている。
最初に真理を発見し、確信するのは、いつの時代もただ一人である。そしてその真理を伝えんとする情熱が、人の心から心へと伝わり、時代を経て、多くの人々に覚醒をもたらす。
本書は真実の世界の秘密を知る宗教家としての、私の使命をかけた一書であり、必ず後世に遺さなければならない真理でもある。
2004年 春
幸福の科学総裁 大川隆法
あとがき
本書中に出てくる霊子線「シルバー・コード」については、旧約聖書の中の『伝道者の書』第十二章で「こうしてついに、銀のひもは切れ、金の器は打ち砕かれ・・・」とのべられている『銀のひも』であり、早くから知られているが、現代のキリスト教会も人間の死については正しく理解していないだろう。
脳死状態での臓器移植の問題点は、第一に、本人の魂がまだ自分の死を認めていないことによる恐怖の苦しみ、第二に、脳死者の魂が被移植者に憑依して死後の世界への移行が妨げられると同時に、相手の人格変化や家族への障りを起こすことである。
仏教的に正しい布施として成り立つためには、布施する主体(施者)、布施する相手(受者)、布施する物品(施持――この場合、臓器)に汚れがないこと、執着がないことが必要である(三輪清浄)。つまり、臓器提供者が仏法真理を学び愛の心で与えたいと思うこと、受者も深く真理を理解しつつ、感謝すること、臓器取引に違法性や金銭対価を伴わないこと、などを前提として正しい布施が成り立つ。この点、死ねば何もかも終わりだと唯物論的に考え、臓器ビジネスの一翼を担うようでは、霊界の混乱には拍車がかかり、死者も浮かばれない。
一方、宗教界に目を転ずれば、すべての不幸を先祖の不成仏霊との合作による悲喜劇としての先祖供養がまかり通っている。悟りは個人に属するものだという原点を忘れてはならない。正しい先祖供養あり方を学んでいただきたい。先祖を供養しているつもりで、他の悪霊たちにとりつかれている家庭も多いのだ。
この仏法真理が、一人でも多くの人の知識となることを心から希望している。
2004年 春
幸福の科学総裁 大川隆法
本書中に出てくる霊子線「シルバー・コード」については、旧約聖書の中の『伝道者の書』第十二章で「こうしてついに、銀のひもは切れ、金の器は打ち砕かれ・・・」とのべられている『銀のひも』であり、早くから知られているが、現代のキリスト教会も人間の死については正しく理解していないだろう。
脳死状態での臓器移植の問題点は、第一に、本人の魂がまだ自分の死を認めていないことによる恐怖の苦しみ、第二に、脳死者の魂が被移植者に憑依して死後の世界への移行が妨げられると同時に、相手の人格変化や家族への障りを起こすことである。
仏教的に正しい布施として成り立つためには、布施する主体(施者)、布施する相手(受者)、布施する物品(施持――この場合、臓器)に汚れがないこと、執着がないことが必要である(三輪清浄)。つまり、臓器提供者が仏法真理を学び愛の心で与えたいと思うこと、受者も深く真理を理解しつつ、感謝すること、臓器取引に違法性や金銭対価を伴わないこと、などを前提として正しい布施が成り立つ。この点、死ねば何もかも終わりだと唯物論的に考え、臓器ビジネスの一翼を担うようでは、霊界の混乱には拍車がかかり、死者も浮かばれない。
一方、宗教界に目を転ずれば、すべての不幸を先祖の不成仏霊との合作による悲喜劇としての先祖供養がまかり通っている。悟りは個人に属するものだという原点を忘れてはならない。正しい先祖供養あり方を学んでいただきたい。先祖を供養しているつもりで、他の悪霊たちにとりつかれている家庭も多いのだ。
この仏法真理が、一人でも多くの人の知識となることを心から希望している。
2004年 春
幸福の科学総裁 大川隆法
http://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e9%81%ba%e6%97%8f%e3%81%8c%e7%b5%8c%e9%a8%93%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bd%a2311%e5%be%8c%e3%81%ae%e9%9c%8a%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bd%a3%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%8b-%e4%ba%a1%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ab%ef%bd%a4%e3%81%8a%e5%88%a5%e3%82%8c%e3%81%ae%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4%e3%81%ab/ar-AAnM7V6?ocid=spartandhp
遺族が経験した「3.11後の霊体験」とは何か 亡くなった時間に、お別れのあいさつに
東洋経済オンライン
 東洋経済オンライン 被災者が体験した「亡き人との再会」とは(写真 : Fast&Slow / PIXTA)
東洋経済オンライン 被災者が体験した「亡き人との再会」とは(写真 : Fast&Slow / PIXTA)
あの日から、もうすぐ6年の月日が経とうとしているが、今だに震災について語るべき言葉を持っていない。身の回りで大きな被害があったわけでもない。知人や親戚が被災地にいたわけでもない。ボランティア活動に参加したこともない。
そんな自分が何を語ろうとしても、言葉が軽くなってしまう。同じようなためらいを感じている方は、案外多いのかもしれない。しかし本書『魂でもいいから、そばにいて』は、意外な切り口からそのような壁を取り払ってくれ、最も大切な姿勢が何かを教えてくれた。
数年前から被災地で、まことしやかに囁かれてきた不思議な体験の数々。多くの人にとってかけがえのないものでありながら、「誰も信じてくれないから」と胸に秘められてきたのは、大切な「亡き人との再会」ともいえる体験談であった。偶然の一言では片付けられない話ばかりが、次々と飛び出してくる。
被災地で囁かれてきた不思議な体験の数々
中でも圧倒的に多いのは、亡くなった家族が夢に現れるという現象である。夢とは思えないほどリアリティに溢れ、当人と言葉を交わすようなケースも多い。その次に多いのが、「お知らせ」というものだ。亡くなった時間に、お別れの挨拶に来たという証言する人は少なくない。また、携帯電話を通しての不思議な現象も散見された。
このような霊的体験は、阪神・淡路大震災の時にはほとんど見られなかったという。オガミサマと呼ばれるイタコのような風習が古くから生活の一部になっていたように、東北には土着の宗教心が今も潜在意識の中でしっかり流れている。それが霊を見たり、感じさせたりということにつながっていくのだろうか。
被災で亡くなった人と残された人。その差に、何か明白な原因があったわけではない。あまりにも理不尽な分断が、ある日突然起こった。だからこそ両者は、その分断を目には見えない何かで埋めようとするのかもしれない。
あの悲劇を一刻も早く忘れたい、でも大切な人のことを忘れたくない。そんな忘却へのジレンマが、その人固有の物語を生み出していく。本書は、そんな人々の物語だ。
“私は眠ったら妻や娘に逢えると思うから、自分自身が死んだつもりになって寝るんです。(亀井繁さん)”
妻と娘を喪った、亀井繁さん。遺体が見つかり、火葬を終えた日の夜中のこと、二人が自分に向かって手を振っている姿を目の当たりにする。「ああ逢いに来てくれたんだ」と手を伸ばしたその時、目が醒めたという。繁さんはその後も何度か同じような経験をし、こうした出来事を大学ノートに記録するようになった。
夢のようなひと時を、夢の中で過ごす。ある時は「私がいないとつまんない?」と妻から尋ねられ、ある時は「どこにも行かないよ」と声を掛けられた。むろん夢から醒めてしまえば、想像を絶する地獄が待っている。だが、夢の中だけでもあの頃に戻れるのであれば、たしかな希望を感じることができるそうだ。
遺族が経験した「3.11後の霊体験」とは何か 亡くなった時間に、お別れのあいさつに
東洋経済オンライン
あの日から、もうすぐ6年の月日が経とうとしているが、今だに震災について語るべき言葉を持っていない。身の回りで大きな被害があったわけでもない。知人や親戚が被災地にいたわけでもない。ボランティア活動に参加したこともない。
そんな自分が何を語ろうとしても、言葉が軽くなってしまう。同じようなためらいを感じている方は、案外多いのかもしれない。しかし本書『魂でもいいから、そばにいて』は、意外な切り口からそのような壁を取り払ってくれ、最も大切な姿勢が何かを教えてくれた。
数年前から被災地で、まことしやかに囁かれてきた不思議な体験の数々。多くの人にとってかけがえのないものでありながら、「誰も信じてくれないから」と胸に秘められてきたのは、大切な「亡き人との再会」ともいえる体験談であった。偶然の一言では片付けられない話ばかりが、次々と飛び出してくる。
被災地で囁かれてきた不思議な体験の数々
中でも圧倒的に多いのは、亡くなった家族が夢に現れるという現象である。夢とは思えないほどリアリティに溢れ、当人と言葉を交わすようなケースも多い。その次に多いのが、「お知らせ」というものだ。亡くなった時間に、お別れの挨拶に来たという証言する人は少なくない。また、携帯電話を通しての不思議な現象も散見された。
このような霊的体験は、阪神・淡路大震災の時にはほとんど見られなかったという。オガミサマと呼ばれるイタコのような風習が古くから生活の一部になっていたように、東北には土着の宗教心が今も潜在意識の中でしっかり流れている。それが霊を見たり、感じさせたりということにつながっていくのだろうか。
被災で亡くなった人と残された人。その差に、何か明白な原因があったわけではない。あまりにも理不尽な分断が、ある日突然起こった。だからこそ両者は、その分断を目には見えない何かで埋めようとするのかもしれない。
あの悲劇を一刻も早く忘れたい、でも大切な人のことを忘れたくない。そんな忘却へのジレンマが、その人固有の物語を生み出していく。本書は、そんな人々の物語だ。
“私は眠ったら妻や娘に逢えると思うから、自分自身が死んだつもりになって寝るんです。(亀井繁さん)”
妻と娘を喪った、亀井繁さん。遺体が見つかり、火葬を終えた日の夜中のこと、二人が自分に向かって手を振っている姿を目の当たりにする。「ああ逢いに来てくれたんだ」と手を伸ばしたその時、目が醒めたという。繁さんはその後も何度か同じような経験をし、こうした出来事を大学ノートに記録するようになった。
夢のようなひと時を、夢の中で過ごす。ある時は「私がいないとつまんない?」と妻から尋ねられ、ある時は「どこにも行かないよ」と声を掛けられた。むろん夢から醒めてしまえば、想像を絶する地獄が待っている。だが、夢の中だけでもあの頃に戻れるのであれば、たしかな希望を感じることができるそうだ。
その霊も誰かの大切な家族だった
“他人の霊を見たら怖いでしょうね。でも私は見方が変わりました。その霊も誰かの大切な家族だったんだと思えば、ちっとも怖くないと思えるようになったんです(永沼恵子さん)”
当時8歳だった息子の琴君を喪った、永沼恵子さん。何気なく携帯の写メで家の写真を撮ったら、なんと窓に琴君の顔が写っていたのだという。それを皮切りに、次々と不思議なことが起こっていく。風邪もなく窓も閉めきっているのに、ティッシュが激しく揺れたり、どたんと大きな音がしたり、天井や壁を走り回る音がしたり。
琴くんの足音が聞こえてくるーーそう思えるだけでも亡くなった我が子の気遣いとして感じられ、頑張っている姿を見せなければと前を向けるのだという。子供を喪うことは、未来を奪われることにも等しい。それでも子供との思い出が、確かに未来を創っているのだ。
“夢の中でお父さんにぐっと手を握られたりハグされたりするでしょ? お父さんの手は大きくて温かいんですよ(菅野佳代子さん)”
市役所勤務の夫を喪った、菅野佳代子さん。仮設住宅に移った2013年くらいから夢に旦那さんが出てくるようになった。鮮明な映像で音も大きく、現実と錯覚するほどのリアリティであったという。
生きている「死者」を抱きしめるような感覚が、生活を穏やかに包み込んでくれる。だから現実にはいないはずの仮設住宅でも、旦那さんと二人っきりで生活している気がするそうだ。
生きる力を取り戻し、少しずつ心の復興が進んでいる
在りし日の思い出、亡くなった悲しみ、夢で再会できた喜び。それらがシームレスにつながり、一つの物語が形成されていく。その過程において、著者は同じ人に最低3回は話を聞いたそうだ。その物語も、決して不変なものばかりではなかった。他者に語ることで語り手が少しずつ変化を加えつつ、自らが納得できる物語として完成したのである。
それは事実と言えるものなのか。そう指摘することは容易い。しかしその物語で、遺された人たちが生きる力を取り戻し、少しずつ心の復興が進んでいることは、紛れもない「事実」である。
被災者たちを襲ったのは、津波だけではなかった。時を追うごとに、さまざまな困難が襲いかかってくる。一番キツいのは、「あの時もし、こうしていたら、家族は助かったのかもしれない」と、自分で自分を攻め続けてしまうことだ。その悩みは内省的なものであるがゆえに、表面化しづらく根も深い。だが、当人たちそれぞれの不思議な物語が、彼らを罪の意識から解放してくれるのだ。
「生者が死者を記憶に刻み続けることで、死者は生き続ける。私は、その記憶を刻む器なのだ」と、著者は語る。それぞれの話が共鳴することによって生まれる、新たな共同体感覚。それがさらに、誰かを孤独から救い出すことへつながっていくのかもしれない。第三者に出来る唯一にして最大のことは、ただひたすら器に描かれた物語を記憶に刻んでいくことだけだろう。
幸せと絶望があまりにも理不尽に分断されたことで、現実と虚構が入れ替わっていく。だが一体、何が現実で、何が虚構なのか。常識や思い込みといったものこそ、虚構に過ぎないのかもしれない。我々にそれを決めることなど、決して出来はしないはずだ。
“他人の霊を見たら怖いでしょうね。でも私は見方が変わりました。その霊も誰かの大切な家族だったんだと思えば、ちっとも怖くないと思えるようになったんです(永沼恵子さん)”
当時8歳だった息子の琴君を喪った、永沼恵子さん。何気なく携帯の写メで家の写真を撮ったら、なんと窓に琴君の顔が写っていたのだという。それを皮切りに、次々と不思議なことが起こっていく。風邪もなく窓も閉めきっているのに、ティッシュが激しく揺れたり、どたんと大きな音がしたり、天井や壁を走り回る音がしたり。
琴くんの足音が聞こえてくるーーそう思えるだけでも亡くなった我が子の気遣いとして感じられ、頑張っている姿を見せなければと前を向けるのだという。子供を喪うことは、未来を奪われることにも等しい。それでも子供との思い出が、確かに未来を創っているのだ。
“夢の中でお父さんにぐっと手を握られたりハグされたりするでしょ? お父さんの手は大きくて温かいんですよ(菅野佳代子さん)”
市役所勤務の夫を喪った、菅野佳代子さん。仮設住宅に移った2013年くらいから夢に旦那さんが出てくるようになった。鮮明な映像で音も大きく、現実と錯覚するほどのリアリティであったという。
生きている「死者」を抱きしめるような感覚が、生活を穏やかに包み込んでくれる。だから現実にはいないはずの仮設住宅でも、旦那さんと二人っきりで生活している気がするそうだ。
生きる力を取り戻し、少しずつ心の復興が進んでいる
在りし日の思い出、亡くなった悲しみ、夢で再会できた喜び。それらがシームレスにつながり、一つの物語が形成されていく。その過程において、著者は同じ人に最低3回は話を聞いたそうだ。その物語も、決して不変なものばかりではなかった。他者に語ることで語り手が少しずつ変化を加えつつ、自らが納得できる物語として完成したのである。
それは事実と言えるものなのか。そう指摘することは容易い。しかしその物語で、遺された人たちが生きる力を取り戻し、少しずつ心の復興が進んでいることは、紛れもない「事実」である。
被災者たちを襲ったのは、津波だけではなかった。時を追うごとに、さまざまな困難が襲いかかってくる。一番キツいのは、「あの時もし、こうしていたら、家族は助かったのかもしれない」と、自分で自分を攻め続けてしまうことだ。その悩みは内省的なものであるがゆえに、表面化しづらく根も深い。だが、当人たちそれぞれの不思議な物語が、彼らを罪の意識から解放してくれるのだ。
「生者が死者を記憶に刻み続けることで、死者は生き続ける。私は、その記憶を刻む器なのだ」と、著者は語る。それぞれの話が共鳴することによって生まれる、新たな共同体感覚。それがさらに、誰かを孤独から救い出すことへつながっていくのかもしれない。第三者に出来る唯一にして最大のことは、ただひたすら器に描かれた物語を記憶に刻んでいくことだけだろう。
幸せと絶望があまりにも理不尽に分断されたことで、現実と虚構が入れ替わっていく。だが一体、何が現実で、何が虚構なのか。常識や思い込みといったものこそ、虚構に過ぎないのかもしれない。我々にそれを決めることなど、決して出来はしないはずだ。
http://tocana.jp/2015/03/post_5942_entry.html
【3.11震災から4年】被災地で幽霊目撃談が多い本当の理由
2015.03.11
M9.0の巨大地震と、それに伴う大津波によって、15,800人以上の犠牲者を出すという未曾有の大災害からちょうど4年が過ぎた。震災直後から、被災各地で囁かれていたのが「幽霊が出る」という類の噂である。当然、このような幽霊話は多くの犠牲者に対して不謹慎とされ、避難所などではタブーとして扱われてきたようだが、そこに「癒し」を見出す人々も少なくないという。果たして、震災に際して幽霊話が本当に「不謹慎」なのかどうかを考えてみることにしたい。
なお、筆者は超常現象研究家として40年以上にわたって心霊現象などを研究してきたが、今回の記事は3.11にまつわる幽霊話の真偽を確かめるものではなく、そのような話には人々にとってプラスとなる要素があるかどうかを探求するものである。幽霊話の真偽についての考察は、また別の機会に譲ることにしたい。
■数々の幽霊話、真剣に報じるマスコミ
さて、3.11から1年ほどが過ぎた頃から、避難所やネット上では様々な幽霊話が語られるようになっていた。多くの死者が出た大震災の後では、このような幽霊話はつきものだが、3.11の場合、いつになく多いようなのだ。以下は、その一例だ。
・ 夜になると大勢の人たちが走る足音が聞こえる
・ 津波で瓦礫となった車の中を、1台ずつ覗いていく子連れの女性がいる
・ 行方不明者の家族の枕元で、「見つけてほしい、埋葬してほしい」と声が聞こえた
・ 仮設住宅で、夜な夜な「寒い」といった呻き声が聞こえる
・ 夜中に停車しているタクシーに近寄ってきて、「自分は生きているのか死んだのかわからない、乗せてもらえないか」と語りかける女性がいる。乗せると、いつの間にか後部座席から消えている
また震災の翌年3月には、AFP通信が「東日本大震災から1年、石巻で語られる『幽霊』の噂」という記事を掲載している。それによると、宮城県石巻市では、さまよう霊たちのせいで修復工事が中断してしまった現場さえあるという。
このような噂を無視できないと思ったのか、なんとNHKまでも、2013年8月23日に「亡き人との“再会”〜被災地 三度目の夏に〜」という番組で、“震災幽霊”の話を真剣に取り上げた。それは、故人と「再会」したという4人の人物の不思議な体験を紹介するというものだった。津波で3歳の息子と死に別れた母親の場合、子どもが遊ぶ気配を感じると、アンパンマンの乗り物のオモチャのスイッチが勝手に入ったのだという。これまで、超常現象や心霊ものを退けてきたNHKとしては考えられないような番組である。
【3.11震災から4年】被災地で幽霊目撃談が多い本当の理由
2015.03.11
M9.0の巨大地震と、それに伴う大津波によって、15,800人以上の犠牲者を出すという未曾有の大災害からちょうど4年が過ぎた。震災直後から、被災各地で囁かれていたのが「幽霊が出る」という類の噂である。当然、このような幽霊話は多くの犠牲者に対して不謹慎とされ、避難所などではタブーとして扱われてきたようだが、そこに「癒し」を見出す人々も少なくないという。果たして、震災に際して幽霊話が本当に「不謹慎」なのかどうかを考えてみることにしたい。
なお、筆者は超常現象研究家として40年以上にわたって心霊現象などを研究してきたが、今回の記事は3.11にまつわる幽霊話の真偽を確かめるものではなく、そのような話には人々にとってプラスとなる要素があるかどうかを探求するものである。幽霊話の真偽についての考察は、また別の機会に譲ることにしたい。
■数々の幽霊話、真剣に報じるマスコミ
さて、3.11から1年ほどが過ぎた頃から、避難所やネット上では様々な幽霊話が語られるようになっていた。多くの死者が出た大震災の後では、このような幽霊話はつきものだが、3.11の場合、いつになく多いようなのだ。以下は、その一例だ。
・ 夜になると大勢の人たちが走る足音が聞こえる
・ 津波で瓦礫となった車の中を、1台ずつ覗いていく子連れの女性がいる
・ 行方不明者の家族の枕元で、「見つけてほしい、埋葬してほしい」と声が聞こえた
・ 仮設住宅で、夜な夜な「寒い」といった呻き声が聞こえる
・ 夜中に停車しているタクシーに近寄ってきて、「自分は生きているのか死んだのかわからない、乗せてもらえないか」と語りかける女性がいる。乗せると、いつの間にか後部座席から消えている
また震災の翌年3月には、AFP通信が「東日本大震災から1年、石巻で語られる『幽霊』の噂」という記事を掲載している。それによると、宮城県石巻市では、さまよう霊たちのせいで修復工事が中断してしまった現場さえあるという。
このような噂を無視できないと思ったのか、なんとNHKまでも、2013年8月23日に「亡き人との“再会”〜被災地 三度目の夏に〜」という番組で、“震災幽霊”の話を真剣に取り上げた。それは、故人と「再会」したという4人の人物の不思議な体験を紹介するというものだった。津波で3歳の息子と死に別れた母親の場合、子どもが遊ぶ気配を感じると、アンパンマンの乗り物のオモチャのスイッチが勝手に入ったのだという。これまで、超常現象や心霊ものを退けてきたNHKとしては考えられないような番組である。
■幽霊話が生まれる本当の意味
このように幽霊話がメディアで取り上げられるようになったのは、大震災から時が経つにつれ、タブー視されていたものを語ってもよいのではないかという雰囲気が少しずつ生まれてきたという背景もあるようだ。さらに、カウンセラーや学者たちによると、大災害や悲劇的事件の後の幽霊話は、日本では一般的なものであって、それが社会的な「癒しのプロセス」にもなるのだという。
前述のAFP通信の記事で、文化人類学者の船曳建夫氏は、人間は本来、突然の死を受け容れられないものだとして、「その社会で納得できなくてたまっているものがどう表現されるかというと、噂話であったり、まつりの中で供養するなどということになります。社会的に共有できるものに変えるということがポイントです」(AFPBB News、2012年3月3日)と語っている。このことは、科学技術が発達した現代の日本でも、そう変わらないようなのだ。この説に合致すると思しき実例を、以下に紹介しよう。
・ にこやかな母の表情に救われ……
仙台市の地方紙・河北新報が、2015年2月26日の記事で紹介している岩手県山田町の公務員・長根勝さんは、大震災で母を亡くした。ある日、その母がニコニコした表情で18歳の娘の夢に現れた。娘が「なぜ津波で逃げなかったの」と聞くと、困ったような顔をしたという。その後、勝さん自身も夢の中で、台所で家事をする母を見た。にこやかな表情だったので救われた思いになったという。勝さんは、その体験を経て「怒りのような感情が薄らいでいった」と語っている。
・ 体験者は幽霊を怖がらない
河北新報の2015年2月27日の記事が紹介しているのは、浄土真宗本願寺派の僧侶・金沢豊さんだ。金沢さんは、毎月のように京都から岩手の被災地へと赴き、これまで200軒の被災者を訪ねているが、超自然的な話や幽霊話を聞くことも多いという。「金縛りになって誰かの顔が見えた」、「津波で亡くなった妹に見られている」といった具合だ。しかし、そのような話をしてくれる人々の顔は、恐怖ではなく慈しむような表情であるという。
・ 見守られている感覚が、生きる希望に
同じく河北新報の2015年1月4日の記事で紹介されているジャーナリストの奥野修司さんは、被災地を回り、犠牲者の霊を見たという家族や知人からの聞き取りを進めている。そのきっかけは、医師への取材で、死者の「お迎え」の重要性に気づいたからだという。その医師によれば、いまわの際に、亡くなった両親や親類の姿を見る患者の死に方は穏やかだという。最愛の夫を亡くしたある女性は、自暴自棄に陥り、死にたいと思う日々を送っていたが、ある時、夫の霊に会い、見守られている感覚が芽生えて「お父ちゃんと一緒に生きよう」と思い直したそうだ。
確かに、被災地で幽霊を見たという話の中には、単なる興味本位の怪談で終わっているものもある。しかし、こうして見てきたように、特に亡くした肉親や友人との「再会」を果たしたというケースでは、恐怖よりも感動の方が先立つことが非常に多いようだ。「日本人の約2人に1人が幽霊の存在を信じている」という調査報告もあるようだが、震災で大切な人を失った被災者にとって、「たとえこの世にいなくても、あの世で生きている」と考えることが、明日へ一歩を踏み出すための大きな力になっている可能性がある。
多くの死者が出た大災害で、幽霊の話をすることは「不謹慎」に感じられる気持ちも理解できる。しかしそれ以上に、犠牲者の肉親や知人など、残された人々にとっての救いに繋がる面もあることを理解しようとする姿勢が大切ではないだろうか。
百瀬直也(ももせ・なおや)
超常現象研究家、地震前兆研究家、ライター。25年のソフトウエア開発歴を生かしIT技術やデータ重視の調査研究が得意。ブログ:『探求三昧』、Web:『沙龍家』、Twitter:@noya_momose
※百瀬氏が企画・執筆したコンビニムック『2015予言 戦慄の未来記』(ダイアプレス)、大好評発売中!
このように幽霊話がメディアで取り上げられるようになったのは、大震災から時が経つにつれ、タブー視されていたものを語ってもよいのではないかという雰囲気が少しずつ生まれてきたという背景もあるようだ。さらに、カウンセラーや学者たちによると、大災害や悲劇的事件の後の幽霊話は、日本では一般的なものであって、それが社会的な「癒しのプロセス」にもなるのだという。
前述のAFP通信の記事で、文化人類学者の船曳建夫氏は、人間は本来、突然の死を受け容れられないものだとして、「その社会で納得できなくてたまっているものがどう表現されるかというと、噂話であったり、まつりの中で供養するなどということになります。社会的に共有できるものに変えるということがポイントです」(AFPBB News、2012年3月3日)と語っている。このことは、科学技術が発達した現代の日本でも、そう変わらないようなのだ。この説に合致すると思しき実例を、以下に紹介しよう。
・ にこやかな母の表情に救われ……
仙台市の地方紙・河北新報が、2015年2月26日の記事で紹介している岩手県山田町の公務員・長根勝さんは、大震災で母を亡くした。ある日、その母がニコニコした表情で18歳の娘の夢に現れた。娘が「なぜ津波で逃げなかったの」と聞くと、困ったような顔をしたという。その後、勝さん自身も夢の中で、台所で家事をする母を見た。にこやかな表情だったので救われた思いになったという。勝さんは、その体験を経て「怒りのような感情が薄らいでいった」と語っている。
・ 体験者は幽霊を怖がらない
河北新報の2015年2月27日の記事が紹介しているのは、浄土真宗本願寺派の僧侶・金沢豊さんだ。金沢さんは、毎月のように京都から岩手の被災地へと赴き、これまで200軒の被災者を訪ねているが、超自然的な話や幽霊話を聞くことも多いという。「金縛りになって誰かの顔が見えた」、「津波で亡くなった妹に見られている」といった具合だ。しかし、そのような話をしてくれる人々の顔は、恐怖ではなく慈しむような表情であるという。
・ 見守られている感覚が、生きる希望に
同じく河北新報の2015年1月4日の記事で紹介されているジャーナリストの奥野修司さんは、被災地を回り、犠牲者の霊を見たという家族や知人からの聞き取りを進めている。そのきっかけは、医師への取材で、死者の「お迎え」の重要性に気づいたからだという。その医師によれば、いまわの際に、亡くなった両親や親類の姿を見る患者の死に方は穏やかだという。最愛の夫を亡くしたある女性は、自暴自棄に陥り、死にたいと思う日々を送っていたが、ある時、夫の霊に会い、見守られている感覚が芽生えて「お父ちゃんと一緒に生きよう」と思い直したそうだ。
確かに、被災地で幽霊を見たという話の中には、単なる興味本位の怪談で終わっているものもある。しかし、こうして見てきたように、特に亡くした肉親や友人との「再会」を果たしたというケースでは、恐怖よりも感動の方が先立つことが非常に多いようだ。「日本人の約2人に1人が幽霊の存在を信じている」という調査報告もあるようだが、震災で大切な人を失った被災者にとって、「たとえこの世にいなくても、あの世で生きている」と考えることが、明日へ一歩を踏み出すための大きな力になっている可能性がある。
多くの死者が出た大災害で、幽霊の話をすることは「不謹慎」に感じられる気持ちも理解できる。しかしそれ以上に、犠牲者の肉親や知人など、残された人々にとっての救いに繋がる面もあることを理解しようとする姿勢が大切ではないだろうか。
百瀬直也(ももせ・なおや)
超常現象研究家、地震前兆研究家、ライター。25年のソフトウエア開発歴を生かしIT技術やデータ重視の調査研究が得意。ブログ:『探求三昧』、Web:『沙龍家』、Twitter:@noya_momose
※百瀬氏が企画・執筆したコンビニムック『2015予言 戦慄の未来記』(ダイアプレス)、大好評発売中!
http://the-liberty.com/article.php?item_id=12699
3.11東日本大震災から6年 もう一度会いたい幽霊の話
2017.03.10
《本記事のポイント》
東日本大震災の後、霊体験をする人がたくさんいた。
本誌2016年9月号でも「もう一度会いたい幽霊の話」を特集した。
この世に生きる人が正しい生き方をすることで、迷える霊を救うことができる。
2011年3月11日の東日本大震災から、11日で丸6年が経つ。この大震災によって亡くなった方は、1万5893人、行方不明者は2554人にのぼる(3月1日時点)。
ダイヤモンドオンライン(10日付)には、被災地で聞いた霊体験を集めた書籍『魂でもいいから、そばにいて――3.11の霊体験を聞く』の紹介記事が掲載された。記事では、極めてリアルな亡くなった家族の夢を見る人の話や、何気なく撮った自宅の写真に亡くなった息子が映っていたりといった体験談が紹介されている。
こうした体験によって、遺された人たちの「心の復興」が進んでいることや、「あの時もし、こうしていたら、家族は助かったのかもしれない」という罪の意識から解放されることを指摘している。霊体験が救いになっていることが、この記事からは読み取れる。
亡くなったあの人を感じた霊体験
本誌でも、2016年9月号で、「もう一度会いたい幽霊の話」という特集を組んだ。幽霊というと、普通は「あまり会いたくない」ものだが、「また会いたい」と思うような心温まる霊体験を集めたものだ。供養の思いを持つにあたって、ここで一部紹介したい。
東日本大震災の津波でお兄さんが行方不明になったという宮城県気仙沼市のタクシードライバーの男性は、震災後何度もお兄さんの霊の存在を感じたという。「庭の砂利の上や廊下を歩く足音を月に1回ほど聞くんです。確認しても誰もいません。聞こえるのは家族で私だけ。兄の家は、今誰もいないので、私のところに遊びにきているのでしょうか」。
東日本大震災に限らず、霊体験は多く寄せられた。
北海道のある女性は、当時33歳だったご主人を突然の事故で亡くした。娘が生まれてから19日後の悲劇だったが、実は娘の本来の出産予定日は、ご主人が亡くなった次の日だった。なぜか「早く生みたい」という気持ちに駆られていたこと、なぜかひどかった娘の夜泣きがピタリと止まったことなど、まるで、ご主人が「娘を少しでも多く抱けるように」と仕組まれていたかのように不思議な出来事があったという。
葬儀の2週間後のある日、すぐそばにご主人の存在を感じ、「○○(女性の名前)には悪いけど、天国ってほんっとうに良いところだよ」というご主人の声が心に響いてきた。その言い方がとても彼らしく、心がじんと温かくなったという。
東京・渋谷で街頭インタビューを行ったところ、次のような霊体験を聞くことができた。「最近亡くなった母が、夢に出てきました。ニコニコしてて、幸せそうな世界にいる感じだったので、安心しました」(20代・女性)、「死んだ祖父が夢に出てきました。私が野菜嫌いなので、『野菜を食べろ!』と言って冷蔵庫に野菜をたくさん入れていきました」(10代・女性)。
3.11東日本大震災から6年 もう一度会いたい幽霊の話
2017.03.10
《本記事のポイント》
東日本大震災の後、霊体験をする人がたくさんいた。
本誌2016年9月号でも「もう一度会いたい幽霊の話」を特集した。
この世に生きる人が正しい生き方をすることで、迷える霊を救うことができる。
2011年3月11日の東日本大震災から、11日で丸6年が経つ。この大震災によって亡くなった方は、1万5893人、行方不明者は2554人にのぼる(3月1日時点)。
ダイヤモンドオンライン(10日付)には、被災地で聞いた霊体験を集めた書籍『魂でもいいから、そばにいて――3.11の霊体験を聞く』の紹介記事が掲載された。記事では、極めてリアルな亡くなった家族の夢を見る人の話や、何気なく撮った自宅の写真に亡くなった息子が映っていたりといった体験談が紹介されている。
こうした体験によって、遺された人たちの「心の復興」が進んでいることや、「あの時もし、こうしていたら、家族は助かったのかもしれない」という罪の意識から解放されることを指摘している。霊体験が救いになっていることが、この記事からは読み取れる。
亡くなったあの人を感じた霊体験
本誌でも、2016年9月号で、「もう一度会いたい幽霊の話」という特集を組んだ。幽霊というと、普通は「あまり会いたくない」ものだが、「また会いたい」と思うような心温まる霊体験を集めたものだ。供養の思いを持つにあたって、ここで一部紹介したい。
東日本大震災の津波でお兄さんが行方不明になったという宮城県気仙沼市のタクシードライバーの男性は、震災後何度もお兄さんの霊の存在を感じたという。「庭の砂利の上や廊下を歩く足音を月に1回ほど聞くんです。確認しても誰もいません。聞こえるのは家族で私だけ。兄の家は、今誰もいないので、私のところに遊びにきているのでしょうか」。
東日本大震災に限らず、霊体験は多く寄せられた。
北海道のある女性は、当時33歳だったご主人を突然の事故で亡くした。娘が生まれてから19日後の悲劇だったが、実は娘の本来の出産予定日は、ご主人が亡くなった次の日だった。なぜか「早く生みたい」という気持ちに駆られていたこと、なぜかひどかった娘の夜泣きがピタリと止まったことなど、まるで、ご主人が「娘を少しでも多く抱けるように」と仕組まれていたかのように不思議な出来事があったという。
葬儀の2週間後のある日、すぐそばにご主人の存在を感じ、「○○(女性の名前)には悪いけど、天国ってほんっとうに良いところだよ」というご主人の声が心に響いてきた。その言い方がとても彼らしく、心がじんと温かくなったという。
東京・渋谷で街頭インタビューを行ったところ、次のような霊体験を聞くことができた。「最近亡くなった母が、夢に出てきました。ニコニコしてて、幸せそうな世界にいる感じだったので、安心しました」(20代・女性)、「死んだ祖父が夢に出てきました。私が野菜嫌いなので、『野菜を食べろ!』と言って冷蔵庫に野菜をたくさん入れていきました」(10代・女性)。
正しい生き方をすることが、迷える霊たちを救う
古今東西、こうした霊体験の報告は山のようにある。それは、遺された人が「心の復興」をするためでも、罪の意識から逃れるためでもなく、本当に霊が存在するからだ。人間は肉体が死んでも魂は死なず、魂として生き続ける。
大川隆法・幸福の科学総裁は著書『正しい供養 まちがった供養』の中で、この世に生きる人が亡くなった人に手向けるべき供養について、次のように述べている。
「来世では、反省さえきちんとすれば、みな天国に還れます。自分自身の心の針の方向を変えて、思いを入れ替えれば天国に還れるのです。しかし、亡くなったご先祖には、そういうことが分からないので、生きている子孫のほうが実践してみせるのです。
先祖はいつも家族のほうを見ているので、子孫が実践してみせると、『ああ、こういうふうにするのだな。ああいう考え方をするのだな。人に愛を与え、それを手柄にしない。人に優しく生きていく。そういう生き方を私の子孫はしているようだ。なるほど、自分はそういう生き方をしなかったな。これが間違いなのだな』と気づいていただけます」
地上で迷っている霊や地獄に行ってしまった霊にとっては、家族の姿が頼りだ。遺された家族一人一人が愛を与えて生きていれば、その姿を見ている。人として正しく生きることが、愛する人を天国に導くことにつながっていく。
霊体験に救われるのではなく、この世に生きる人が、霊たちの救いになることができるのだ。
(山本泉)
【関連書籍】
幸福の科学出版 『正しい供養 まちがった供養』 大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1811
【関連記事】
2016年9月号 もう一度会いたい幽霊の話 死は永遠の別れではない
http://the-liberty.com/article.php?item_id=11680
古今東西、こうした霊体験の報告は山のようにある。それは、遺された人が「心の復興」をするためでも、罪の意識から逃れるためでもなく、本当に霊が存在するからだ。人間は肉体が死んでも魂は死なず、魂として生き続ける。
大川隆法・幸福の科学総裁は著書『正しい供養 まちがった供養』の中で、この世に生きる人が亡くなった人に手向けるべき供養について、次のように述べている。
「来世では、反省さえきちんとすれば、みな天国に還れます。自分自身の心の針の方向を変えて、思いを入れ替えれば天国に還れるのです。しかし、亡くなったご先祖には、そういうことが分からないので、生きている子孫のほうが実践してみせるのです。
先祖はいつも家族のほうを見ているので、子孫が実践してみせると、『ああ、こういうふうにするのだな。ああいう考え方をするのだな。人に愛を与え、それを手柄にしない。人に優しく生きていく。そういう生き方を私の子孫はしているようだ。なるほど、自分はそういう生き方をしなかったな。これが間違いなのだな』と気づいていただけます」
地上で迷っている霊や地獄に行ってしまった霊にとっては、家族の姿が頼りだ。遺された家族一人一人が愛を与えて生きていれば、その姿を見ている。人として正しく生きることが、愛する人を天国に導くことにつながっていく。
霊体験に救われるのではなく、この世に生きる人が、霊たちの救いになることができるのだ。
(山本泉)
【関連書籍】
幸福の科学出版 『正しい供養 まちがった供養』 大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1811
【関連記事】
2016年9月号 もう一度会いたい幽霊の話 死は永遠の別れではない
http://the-liberty.com/article.php?item_id=11680
http://the-liberty.com/article.php?item_id=12720
2017年、春のお彼岸入りへ――「間違った供養」をしていませんか?
2017.03.16
《本記事のポイント》
不幸を先祖のせいにする"供養宗教"にご注意
天国にいそうな先祖、地獄にいそうな先祖で、対応は変わる
供養は「自分の死後」を考える機会でもある
正しい供養 まちがった供養
愛するひとを天国に導く方法
大川隆法著
幸福の科学出版
昼と夜の長さが同じになる3月下旬の春分、9月下旬の秋分のころを、「彼岸」と言います。
お彼岸時には、親族が実家に集まり、先祖を「供養」するためにお坊さんを呼んでお経をあげてもらったり、お墓参りをしたりしますが、意外と「供養の意味」についてはよく分からないという方が多いのではないでしょうか。
「供養」というと、「あなたが不幸なのは、浮かばれていないご先祖様のせいです」という"先祖供養宗教"が思い浮かぶ人もいるかもしれません。
この先祖供養宗教について、幸福の科学・大川隆法総裁は、著書『正しい供養 間違った供養』でこのように述べています。
「たいていの場合、四代以上前の先祖が浮かばれていないと言われます。そして、『それが原因で不幸が起きているのだから、先祖供養をしっかりやれば運がよくなる』と言われるのです。これは、先祖供養型の宗教を生業とする人の常套手段だと言ってもよいでしょう」
「先祖が浮かばれているかどうかは、相談者には分かりません。したがって、何代か前の先祖のせいにしておけば、それで見料をもらえるのです。このような"商売"が日本各地でどれだけ行われているかを考えたとき、私は愕然とせざるをえません。なかには、本当に浮かばれずに迷っている先祖がいる場合もありますが、その場合でも、積極的に子孫を害してやろうと思っている先祖は、基本的にはいないのです」
"先祖供養ビジネス"の間違いが喝破されていますが、では、「正しい供養」とはいったい何なのでしょうか。同著から、供養のあり方について見てみましょう。
あの世の存在を知る
供養を語る前には、「死後の世界を知る」ことが必要です。これは、亡くなった人にとっても、生きている人にとっても、死後さまよわないために重要なことです。
「そんなものはインチキだ」「自分の目で見たものしか信じない」と、死後の世界を否定する人もいます。もちろん、死後の世界がなければ問題はありませんが、実際に「死んだ後の世界」があった時に困ってしまうのは本人です。
大川総裁の霊査によって、生前に「死ねばすべて終わりだ」と考えていた人々が、死後もなお「自分はまだ生きている」と主張し、地上でさまよい苦しんでいるという事実が分かっています。
供養をするに当たっては、まず、このような霊的真実を知る必要があります。
供養に大切な「感謝」と「導き」
では、霊的真実を知った上で、どのような思いで先祖供養をすれば良いのでしょうか。成仏している先祖と、成仏できていない先祖、両方に子孫からできることがあります。
天国にいる先祖は、救済は求めてはいませんが、子孫が年に1、2回思い出して感謝の思いを向けてくれるとうれしく思います。
これに対して、救済を必要としているのが、地獄に行ってしまった先祖です。彼らは、子孫が「あなたの間違っている点はここですよ。それを反省しましょう。私自身も努力して生き方を変えていきますから、あなたも修行しましょう」という思いで、日々精進し徳を積むことによって、次第に浄化され救われるのです。迷っている先祖にとって、子孫が日々を正しく生きることが、「導き」となります。
子孫が徳を積み、自らの人生を輝かせることで救われるのであって、戒名や御札によって救われるわけではないのです。
2017年、春のお彼岸入りへ――「間違った供養」をしていませんか?
2017.03.16
《本記事のポイント》
不幸を先祖のせいにする"供養宗教"にご注意
天国にいそうな先祖、地獄にいそうな先祖で、対応は変わる
供養は「自分の死後」を考える機会でもある
正しい供養 まちがった供養
愛するひとを天国に導く方法
大川隆法著
幸福の科学出版
昼と夜の長さが同じになる3月下旬の春分、9月下旬の秋分のころを、「彼岸」と言います。
お彼岸時には、親族が実家に集まり、先祖を「供養」するためにお坊さんを呼んでお経をあげてもらったり、お墓参りをしたりしますが、意外と「供養の意味」についてはよく分からないという方が多いのではないでしょうか。
「供養」というと、「あなたが不幸なのは、浮かばれていないご先祖様のせいです」という"先祖供養宗教"が思い浮かぶ人もいるかもしれません。
この先祖供養宗教について、幸福の科学・大川隆法総裁は、著書『正しい供養 間違った供養』でこのように述べています。
「たいていの場合、四代以上前の先祖が浮かばれていないと言われます。そして、『それが原因で不幸が起きているのだから、先祖供養をしっかりやれば運がよくなる』と言われるのです。これは、先祖供養型の宗教を生業とする人の常套手段だと言ってもよいでしょう」
「先祖が浮かばれているかどうかは、相談者には分かりません。したがって、何代か前の先祖のせいにしておけば、それで見料をもらえるのです。このような"商売"が日本各地でどれだけ行われているかを考えたとき、私は愕然とせざるをえません。なかには、本当に浮かばれずに迷っている先祖がいる場合もありますが、その場合でも、積極的に子孫を害してやろうと思っている先祖は、基本的にはいないのです」
"先祖供養ビジネス"の間違いが喝破されていますが、では、「正しい供養」とはいったい何なのでしょうか。同著から、供養のあり方について見てみましょう。
あの世の存在を知る
供養を語る前には、「死後の世界を知る」ことが必要です。これは、亡くなった人にとっても、生きている人にとっても、死後さまよわないために重要なことです。
「そんなものはインチキだ」「自分の目で見たものしか信じない」と、死後の世界を否定する人もいます。もちろん、死後の世界がなければ問題はありませんが、実際に「死んだ後の世界」があった時に困ってしまうのは本人です。
大川総裁の霊査によって、生前に「死ねばすべて終わりだ」と考えていた人々が、死後もなお「自分はまだ生きている」と主張し、地上でさまよい苦しんでいるという事実が分かっています。
供養をするに当たっては、まず、このような霊的真実を知る必要があります。
供養に大切な「感謝」と「導き」
では、霊的真実を知った上で、どのような思いで先祖供養をすれば良いのでしょうか。成仏している先祖と、成仏できていない先祖、両方に子孫からできることがあります。
天国にいる先祖は、救済は求めてはいませんが、子孫が年に1、2回思い出して感謝の思いを向けてくれるとうれしく思います。
これに対して、救済を必要としているのが、地獄に行ってしまった先祖です。彼らは、子孫が「あなたの間違っている点はここですよ。それを反省しましょう。私自身も努力して生き方を変えていきますから、あなたも修行しましょう」という思いで、日々精進し徳を積むことによって、次第に浄化され救われるのです。迷っている先祖にとって、子孫が日々を正しく生きることが、「導き」となります。
子孫が徳を積み、自らの人生を輝かせることで救われるのであって、戒名や御札によって救われるわけではないのです。
「死」について考える
『正しい供養 間違った供養』には、上記の他にも、自殺者や水子の供養、晩年を生きる心構えなどが分かりやすく説明してあります。
死は誰にでも訪れるものでありながら、誰もがその実体を理解しているわけではありません。だからこそ、生きているうちに、死について正しい認識を持つことが大切です。
17日は彼岸入りです。「正しい供養」について考えることで、自分自身も死後迷わないための"予防策"になるかもしれません。
【関連書籍】
幸福の科学出版 『正しい供養 間違った供養』 大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1811
【関連記事】
2017年3月10日付本欄 3.11東日本大震災から6年 もう一度会いたい幽霊の話
http://the-liberty.com/article.php?item_id=12699
2015年10月8日付本欄 お坊さんブーム でもお寺は消えていく? 現代の宗教に求められる霊的な教え
http://the-liberty.com/article.php?item_id=10284
『正しい供養 間違った供養』には、上記の他にも、自殺者や水子の供養、晩年を生きる心構えなどが分かりやすく説明してあります。
死は誰にでも訪れるものでありながら、誰もがその実体を理解しているわけではありません。だからこそ、生きているうちに、死について正しい認識を持つことが大切です。
17日は彼岸入りです。「正しい供養」について考えることで、自分自身も死後迷わないための"予防策"になるかもしれません。
【関連書籍】
幸福の科学出版 『正しい供養 間違った供養』 大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1811
【関連記事】
2017年3月10日付本欄 3.11東日本大震災から6年 もう一度会いたい幽霊の話
http://the-liberty.com/article.php?item_id=12699
2015年10月8日付本欄 お坊さんブーム でもお寺は消えていく? 現代の宗教に求められる霊的な教え
http://the-liberty.com/article.php?item_id=10284
正しい供養 まちがった供養
愛するひとを天国に導く方法
・著者 大川隆法
・定価 1,620 円(税込)
・四六判 173頁
・発刊元 幸福の科学出版
・ISBN 978-4-86395-874-6
・発刊日 2017-02-09
※全国書店は、発刊日より順次発売です
死は永遠の別れでは
ありません。
「死の意味」から「葬儀の意義」、
そして「霊界の真実」まで。
亡くなった人が天国に導かれる
供養の「心がけ」と「注意点」とは。
自分が死んだあとに困らない
「生き方」と「心のあり方」とは。
供養の「常識」をくつがえす一冊。
■その読経は効果がない!?
■自然葬が実はよくない理由!?
■あの世の霊には戒名が通じない!?
■あの世を信じない人は死後どうなる?
■先祖供養型の宗教の危険性とは?
■先祖の「障り」の具体例と対処法
故人と子孫が幸せになる供養を、わかりやすく解説。
まえがき
プロローグ 死は永遠の別れではない
第1章 あの世への旅立ち
第2章 こんな間違った先祖供養をしていませんか
第3章 正しい供養で故人も遺族も幸福になる
第4章 晩年を生きる心構え
エピローグ まず、一人を救え
あとがき
愛するひとを天国に導く方法
・著者 大川隆法
・定価 1,620 円(税込)
・四六判 173頁
・発刊元 幸福の科学出版
・ISBN 978-4-86395-874-6
・発刊日 2017-02-09
※全国書店は、発刊日より順次発売です
死は永遠の別れでは
ありません。
「死の意味」から「葬儀の意義」、
そして「霊界の真実」まで。
亡くなった人が天国に導かれる
供養の「心がけ」と「注意点」とは。
自分が死んだあとに困らない
「生き方」と「心のあり方」とは。
供養の「常識」をくつがえす一冊。
■その読経は効果がない!?
■自然葬が実はよくない理由!?
■あの世の霊には戒名が通じない!?
■あの世を信じない人は死後どうなる?
■先祖供養型の宗教の危険性とは?
■先祖の「障り」の具体例と対処法
故人と子孫が幸せになる供養を、わかりやすく解説。
まえがき
プロローグ 死は永遠の別れではない
第1章 あの世への旅立ち
第2章 こんな間違った先祖供養をしていませんか
第3章 正しい供養で故人も遺族も幸福になる
第4章 晩年を生きる心構え
エピローグ まず、一人を救え
あとがき
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
死後の世界は存在します。 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
死後の世界は存在します。のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90014人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37150人