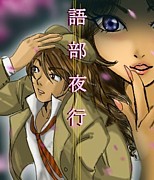※注意※
この話は、キート⇔ゼトワール さんとの合作の【前篇】になります。
急げ。
急げ。
日が暮れる。
光は消え去り、闇が満ちる。
人が文明を以って専横を振るう時間はもうおしまい。
さぁこれよりは。
人に非ずモノが、人を外れたモノが、人であったかもしれないモノ達が。
気ままにそぞろ歩く時。
目を瞑れ。
耳を塞げ。
口を閉じよ。
まだ人で在りたいのなら。
見てはいけない。
聞いてはならない。
応えるなど以ての外。
急げ。
急げ。
日が落ちる
陽は消え去り、陰が満ちる。
目を瞑れ。
耳を塞げ。
口を閉じよ。
一番鶏を信じるな。
ただひたすらに朝を待て。
暇だな。
そう湊が呟くと、圭一はマジありえねぇと呟き返した。
「だって暗いし、雨降ってるし」
「そりゃそうでしょうけど」
この日、二人は怪談のネタ探しに廃墟巡りに行っていた。
しかし昭和初期に建てられた観光ホテルも、深刻な問題(経営難)で閉鎖された病院も、バブル期の負の遺産というべきテーマパークもどれも残念な事になっていた。
更地になってたり、土砂崩れで埋まってたり、黒服の怖いお兄さんがタムロってたりで近寄る事すらできなかった。
何かもう散々だった。
今日はもう帰ろうと車を走らせる山の中、湊が突然止めろと叫んだ。
山芋を見つけたと言い、山の中にガサガサと入って行き、トランクから持ち出したバールで穴を掘りだした。
『山、芋?』
『長芋とは違うのだよ長芋とは!味も粘りも濃度が段違いだ。デパ地下で買おうと思ったら一本一万超えるぞ』
『この枯れた蔓の下を掘ればいいんですね!?』
『山芋は折れやすいから気をつけろ。あ、むかごも採っといて』
『えっ?この灰色の歪なツブツブ食えるの!?』
『ご飯と炊きこむとうまい』
そんなこんなで掘り出した山芋を笹で包んで葛で縛り、掘った穴を埋め戻した頃、陽はすっかり傾いていた。
『えっと……私らどっちから来たっけ?』
『あああ遭難フラグーーーー!?』
携帯が圏内だったのは不幸中の幸いだった。
『思ってたより人里に近かったんだな』
『湊さん、地図アプリはね、獣道は表示してくれないんですよ』
紆余曲折の末、細い県道に全身枯葉塗れで転がり出た頃には、だいぶ暗くなっていた。
夕空は黒く厚い雲に覆われ、細く僅かな切れ間から血の滴るような赤を覗かせている。
『おお!道だ!アスファルトだ!人間社会だ文明万歳!!』
『あ、キイチゴみっけ』
『湊さんちょっとは懲りて!!』
このまま県道に沿って歩けば20分くらいで車を停めた場所に戻れそうだ。
そう思っていた矢先、ポツリと水滴が落ちた。
水滴は息を吸って吐く間に数と勢いを増して土砂降りの雨になった。
『傘は?』
『車の中!』
『畜生!走れ!!』
『間に合わないよ!!』
『……あっ』
『今度は何すか!!』
『そこ、消防小屋がある!』
湊が指差す先に、古びたコンクリートの建物があった。
**村消防団詰所と書かれた字はかなり掠れていた。
車庫に毛が生えた程度の大きさで、苔に塗れた丸い赤色灯に灯りは着いてなかったが、シャッターを閉めようとしている男がいた。
スーツ姿の中年で、二人と目が合うとギョッとしてシャッターを下ろそうとした。
『ちょっ…待っ』
『走れぇぇぇぇぇぇぇぇっ!』
山芋を抱えたままダッシュする湊。
つられて走り出す圭一。
『ファイトーーーーーー!』
『いっぱあぁぁぁぁぁつ!』
閉じる寸前のシャッターにスライディングで滑り込んだ為、結局二人ともずぶ濡れになった。
『何なんだあんたらは!?出ていけ!早く!!』
『変な入り方してすみません!でも雨が上がるまでは……』
『いいから出ていけ!』
『……本当に出ていいんですかね?』
凄い剣幕で怒鳴る男に対して圭一は妙に冷静だった。
『それ、霊能者の○○先生の書いたお札ですよね』
小屋の内部を見渡して、少し嫌味っぽくそう言うと、男はギクリと顔を強張らせた。
『ホントだ。何か貼ってあるや』
この消防小屋はかなり前に放棄されていたのか、消防車もホースの類もなく、床には埃塗れの古新聞の束と破れたブルーシートがあるだけだった。
そして四方の壁と明り取りの窓、それからシャッターの内側に、湊には読めない文字と複雑な図形のような物が掛かれたお札が貼ってあった。
『そのお札の形式からして効果は結界。一度閉じたら外にいるモノは何であれ入って来れない』
『お前……わかるのか』
男の怒気が幾分引いて、畏怖のような物が混じる。
脇で見ている湊には、圭一の“口先の魔術師”がONになっている事だけはわかった。
『陽は没し、時はすでに逢魔が刻……さて俺達は外に出る為、このシャッターを、開けて、良いのですかねぇ?』
『待て!シャッターに触れるんじゃない!』
『先にいた人に出ていけと言われちゃったら仕方ないデスヨネー』
『おいコラ待て!』
『あ、湊さんそっち持って』
『おし、せーの!』
『やめてください。お願いですここにいてください』
『いやー仕方ないなぁもう』
圭一はにこやかに笑って肩をすくめて見せた。
その後も口先の魔術師モードは続行され、男は何故自分がここにいるのか喋らされた。
『実は性質の悪い女につきまとわれて……』
男は3年前から女ストーカーに粘着されていたと言う。
最近その女が姿を現さないと思っていたら、事故で死んでいたそうで。
安心したのもつかの間、悪霊となって憑りつき、今度は酷い霊障を起こすようになった。
○○という霊能者に助けを求めたが、○○氏は別件が立て込んでいてすぐには動けなかった。
その代りにと結界のお札を渡され、これで侵入を防いで時間を稼ぐようにと言われた。
悪霊が動くのは日没から夜明けまで、昼のうちに家に帰ってお札を貼って籠るつもりだったが、この県道で車が故障してしまった。
車は動かず、JAFは来ず、時はどんどん流れていく。
途方に暮れたその時、途中でこの消防小屋があった事を思い出した。
『それでここをキャンプ地としたと』
『なぁ、あんた……○○先生の事、知ってるんだよな』
『仕事の都合で、多少は』
『あんたは……』
『家が、骨董品を扱ってます。曰くつきの品物がたまに来るのでその関係で』
圭一は嘘ではないが本当でもない事を言った。
正直に記者だと言ったら無駄に警戒されると思ったのだろう。
『今日は友人の山芋掘りを手伝っていたら、この雨ですよ』
言われて湊は山芋を掲げて大漁ですよと笑って見せた。
怪談のネタ探しに廃墟巡りしてましたなんて、本当だけど胡散臭い事は言えない。
『そうか、じゃあ朝までその辺に座っててくれ』
男がそれを信じたかどうかはよくわからなかった。
そして長い夜が始まった。
濡れた身体を古新聞で無理やり拭いて、ブルーシートにくるまると寒さは少しはマシになった。
掘りたての山芋は電気もガスも水道も止まっているここでは食べられた物ではないが、湊のポケットというポケットからアケビだの柿だの木イチゴだのがボロボロ出てきた。
『……いつの間にこんな』
『特別にちょっとだけ分けてあげなくもないよ』
口ではそういいながら、惜しげもなく三等分にしていく。
そう、自分の分と圭一の分と……
『あのおっさんは……』
男は小屋の隅で耳を塞いでうずくまっていた。
ギュっと目を閉じ、歯をギリギリと食いしばり、話しかけても答えない。
周りの全てを拒んでいるようだ。
『死んだ女の訪問をお札で避ける、か……牡丹燈篭みたいだね』
『……霊能者の○○氏は、力は本物だけど、やる事が少しえげつなくて評判が悪い』
『お金積まれたらなんでもやっちゃう系?』
『これは牡丹燈篭じゃなくて、吉備津の釜かもしれない』
『あの話、どこが違うんだっけ?』
圭一はそれには答えず、眠ってはいけないとだけ小さく囁いた。
眠るなと言われたものの、実際湊に眠気が訪れる事はなかった。
廃墟巡り(悉く失敗)と山芋掘りでかなり疲れているはずなのに。
携帯の電池切れを警戒して二人とも電源を切って、小屋の中は墨を流したような真っ暗闇だというのに。
雨や風の音が神経に障るのだろうか。
いや、自分は本気で眠ければ打ち鳴らされる大太鼓の下でも眠れる奴だ。
眠ってはいけない時に眠れないのは良い事だ。
だけどいつまでこうしていれば良いのか。
今は何時で、後何時間で朝になるのか、さっぱりわからないと、こう……
「暇だな」
「マジありえねぇ」
圭一は苦虫を噛み潰したような顔をした。
「だって暗いし、雨降ってるし」
「そりゃそうでしょうけど」
「圭一は退屈じゃないのか」
「それどころじゃないっすよ……もう、外の気配がうるっさくて」
「えっ」
「えっ」
圭一には小屋の外を延々と歩き回る足音や、シャッターを叩いたり明り取りの窓をガタガタ揺さぶる音、女の啜り泣きが聞こえていた。
それも小屋に入った最初から。
「私は雨と風と時々雷の音しか聞こえないんだけど」
「そりゃ良かったですね」
悲しげな啜り泣きは鬱々とした恨み言に代わり、今は聞くに堪えない罵詈雑言になっていた。
でも湊には聞こえない。
「よくない。暇だ。ゲームするからスマホ貸して」
「電池減るからいやです」
「じゃあ何か面白い(怖い)話して」
「こんな時に」
「こんな時だから」
「なるほど……だが断るッ!」
「えー」
「今は話すより生きた人間の声が聞きたいです。お先にどうぞ」
「……ちっ」
*****
(コメントに続く)
この話は、キート⇔ゼトワール さんとの合作の【前篇】になります。
急げ。
急げ。
日が暮れる。
光は消え去り、闇が満ちる。
人が文明を以って専横を振るう時間はもうおしまい。
さぁこれよりは。
人に非ずモノが、人を外れたモノが、人であったかもしれないモノ達が。
気ままにそぞろ歩く時。
目を瞑れ。
耳を塞げ。
口を閉じよ。
まだ人で在りたいのなら。
見てはいけない。
聞いてはならない。
応えるなど以ての外。
急げ。
急げ。
日が落ちる
陽は消え去り、陰が満ちる。
目を瞑れ。
耳を塞げ。
口を閉じよ。
一番鶏を信じるな。
ただひたすらに朝を待て。
暇だな。
そう湊が呟くと、圭一はマジありえねぇと呟き返した。
「だって暗いし、雨降ってるし」
「そりゃそうでしょうけど」
この日、二人は怪談のネタ探しに廃墟巡りに行っていた。
しかし昭和初期に建てられた観光ホテルも、深刻な問題(経営難)で閉鎖された病院も、バブル期の負の遺産というべきテーマパークもどれも残念な事になっていた。
更地になってたり、土砂崩れで埋まってたり、黒服の怖いお兄さんがタムロってたりで近寄る事すらできなかった。
何かもう散々だった。
今日はもう帰ろうと車を走らせる山の中、湊が突然止めろと叫んだ。
山芋を見つけたと言い、山の中にガサガサと入って行き、トランクから持ち出したバールで穴を掘りだした。
『山、芋?』
『長芋とは違うのだよ長芋とは!味も粘りも濃度が段違いだ。デパ地下で買おうと思ったら一本一万超えるぞ』
『この枯れた蔓の下を掘ればいいんですね!?』
『山芋は折れやすいから気をつけろ。あ、むかごも採っといて』
『えっ?この灰色の歪なツブツブ食えるの!?』
『ご飯と炊きこむとうまい』
そんなこんなで掘り出した山芋を笹で包んで葛で縛り、掘った穴を埋め戻した頃、陽はすっかり傾いていた。
『えっと……私らどっちから来たっけ?』
『あああ遭難フラグーーーー!?』
携帯が圏内だったのは不幸中の幸いだった。
『思ってたより人里に近かったんだな』
『湊さん、地図アプリはね、獣道は表示してくれないんですよ』
紆余曲折の末、細い県道に全身枯葉塗れで転がり出た頃には、だいぶ暗くなっていた。
夕空は黒く厚い雲に覆われ、細く僅かな切れ間から血の滴るような赤を覗かせている。
『おお!道だ!アスファルトだ!人間社会だ文明万歳!!』
『あ、キイチゴみっけ』
『湊さんちょっとは懲りて!!』
このまま県道に沿って歩けば20分くらいで車を停めた場所に戻れそうだ。
そう思っていた矢先、ポツリと水滴が落ちた。
水滴は息を吸って吐く間に数と勢いを増して土砂降りの雨になった。
『傘は?』
『車の中!』
『畜生!走れ!!』
『間に合わないよ!!』
『……あっ』
『今度は何すか!!』
『そこ、消防小屋がある!』
湊が指差す先に、古びたコンクリートの建物があった。
**村消防団詰所と書かれた字はかなり掠れていた。
車庫に毛が生えた程度の大きさで、苔に塗れた丸い赤色灯に灯りは着いてなかったが、シャッターを閉めようとしている男がいた。
スーツ姿の中年で、二人と目が合うとギョッとしてシャッターを下ろそうとした。
『ちょっ…待っ』
『走れぇぇぇぇぇぇぇぇっ!』
山芋を抱えたままダッシュする湊。
つられて走り出す圭一。
『ファイトーーーーーー!』
『いっぱあぁぁぁぁぁつ!』
閉じる寸前のシャッターにスライディングで滑り込んだ為、結局二人ともずぶ濡れになった。
『何なんだあんたらは!?出ていけ!早く!!』
『変な入り方してすみません!でも雨が上がるまでは……』
『いいから出ていけ!』
『……本当に出ていいんですかね?』
凄い剣幕で怒鳴る男に対して圭一は妙に冷静だった。
『それ、霊能者の○○先生の書いたお札ですよね』
小屋の内部を見渡して、少し嫌味っぽくそう言うと、男はギクリと顔を強張らせた。
『ホントだ。何か貼ってあるや』
この消防小屋はかなり前に放棄されていたのか、消防車もホースの類もなく、床には埃塗れの古新聞の束と破れたブルーシートがあるだけだった。
そして四方の壁と明り取りの窓、それからシャッターの内側に、湊には読めない文字と複雑な図形のような物が掛かれたお札が貼ってあった。
『そのお札の形式からして効果は結界。一度閉じたら外にいるモノは何であれ入って来れない』
『お前……わかるのか』
男の怒気が幾分引いて、畏怖のような物が混じる。
脇で見ている湊には、圭一の“口先の魔術師”がONになっている事だけはわかった。
『陽は没し、時はすでに逢魔が刻……さて俺達は外に出る為、このシャッターを、開けて、良いのですかねぇ?』
『待て!シャッターに触れるんじゃない!』
『先にいた人に出ていけと言われちゃったら仕方ないデスヨネー』
『おいコラ待て!』
『あ、湊さんそっち持って』
『おし、せーの!』
『やめてください。お願いですここにいてください』
『いやー仕方ないなぁもう』
圭一はにこやかに笑って肩をすくめて見せた。
その後も口先の魔術師モードは続行され、男は何故自分がここにいるのか喋らされた。
『実は性質の悪い女につきまとわれて……』
男は3年前から女ストーカーに粘着されていたと言う。
最近その女が姿を現さないと思っていたら、事故で死んでいたそうで。
安心したのもつかの間、悪霊となって憑りつき、今度は酷い霊障を起こすようになった。
○○という霊能者に助けを求めたが、○○氏は別件が立て込んでいてすぐには動けなかった。
その代りにと結界のお札を渡され、これで侵入を防いで時間を稼ぐようにと言われた。
悪霊が動くのは日没から夜明けまで、昼のうちに家に帰ってお札を貼って籠るつもりだったが、この県道で車が故障してしまった。
車は動かず、JAFは来ず、時はどんどん流れていく。
途方に暮れたその時、途中でこの消防小屋があった事を思い出した。
『それでここをキャンプ地としたと』
『なぁ、あんた……○○先生の事、知ってるんだよな』
『仕事の都合で、多少は』
『あんたは……』
『家が、骨董品を扱ってます。曰くつきの品物がたまに来るのでその関係で』
圭一は嘘ではないが本当でもない事を言った。
正直に記者だと言ったら無駄に警戒されると思ったのだろう。
『今日は友人の山芋掘りを手伝っていたら、この雨ですよ』
言われて湊は山芋を掲げて大漁ですよと笑って見せた。
怪談のネタ探しに廃墟巡りしてましたなんて、本当だけど胡散臭い事は言えない。
『そうか、じゃあ朝までその辺に座っててくれ』
男がそれを信じたかどうかはよくわからなかった。
そして長い夜が始まった。
濡れた身体を古新聞で無理やり拭いて、ブルーシートにくるまると寒さは少しはマシになった。
掘りたての山芋は電気もガスも水道も止まっているここでは食べられた物ではないが、湊のポケットというポケットからアケビだの柿だの木イチゴだのがボロボロ出てきた。
『……いつの間にこんな』
『特別にちょっとだけ分けてあげなくもないよ』
口ではそういいながら、惜しげもなく三等分にしていく。
そう、自分の分と圭一の分と……
『あのおっさんは……』
男は小屋の隅で耳を塞いでうずくまっていた。
ギュっと目を閉じ、歯をギリギリと食いしばり、話しかけても答えない。
周りの全てを拒んでいるようだ。
『死んだ女の訪問をお札で避ける、か……牡丹燈篭みたいだね』
『……霊能者の○○氏は、力は本物だけど、やる事が少しえげつなくて評判が悪い』
『お金積まれたらなんでもやっちゃう系?』
『これは牡丹燈篭じゃなくて、吉備津の釜かもしれない』
『あの話、どこが違うんだっけ?』
圭一はそれには答えず、眠ってはいけないとだけ小さく囁いた。
眠るなと言われたものの、実際湊に眠気が訪れる事はなかった。
廃墟巡り(悉く失敗)と山芋掘りでかなり疲れているはずなのに。
携帯の電池切れを警戒して二人とも電源を切って、小屋の中は墨を流したような真っ暗闇だというのに。
雨や風の音が神経に障るのだろうか。
いや、自分は本気で眠ければ打ち鳴らされる大太鼓の下でも眠れる奴だ。
眠ってはいけない時に眠れないのは良い事だ。
だけどいつまでこうしていれば良いのか。
今は何時で、後何時間で朝になるのか、さっぱりわからないと、こう……
「暇だな」
「マジありえねぇ」
圭一は苦虫を噛み潰したような顔をした。
「だって暗いし、雨降ってるし」
「そりゃそうでしょうけど」
「圭一は退屈じゃないのか」
「それどころじゃないっすよ……もう、外の気配がうるっさくて」
「えっ」
「えっ」
圭一には小屋の外を延々と歩き回る足音や、シャッターを叩いたり明り取りの窓をガタガタ揺さぶる音、女の啜り泣きが聞こえていた。
それも小屋に入った最初から。
「私は雨と風と時々雷の音しか聞こえないんだけど」
「そりゃ良かったですね」
悲しげな啜り泣きは鬱々とした恨み言に代わり、今は聞くに堪えない罵詈雑言になっていた。
でも湊には聞こえない。
「よくない。暇だ。ゲームするからスマホ貸して」
「電池減るからいやです」
「じゃあ何か面白い(怖い)話して」
「こんな時に」
「こんな時だから」
「なるほど……だが断るッ!」
「えー」
「今は話すより生きた人間の声が聞きたいです。お先にどうぞ」
「……ちっ」
*****
(コメントに続く)
|
|
|
|
コメント(4)
【しあわせのあおいとり】
青い鳥って知ってるよね。
そう、メーテルリンクの童話劇。
幸せの青い鳥を探す兄妹の物語。
でも何で幸せをもたらす鳥の色が『青』なのだろうね。
幸せって言うなら、ピンクとか黄色とかのがそれっぽいない?
ほら『薔薇色の人生』とか『幸せの黄色いハンカチ』とかさ。
それでも幸せをもたらす鳥の色は『青』
憂鬱とか、元気ないとかそういう意味になる『青』
実は幸せの青い鳥には、モデルとなった鳥がいるんだ。
『セネガンビアアオツグミ』
大航海時代にポルトガルの船乗りが西アフリカから持ち帰った鳥で、ツグミとついてるけど実際はツグミより一回り大きい別種の鳥らしい。
19世紀初頭に絶滅してるからよくわからない事が多いんだけどね。
わかっているのは、嘴から足の爪まで全身全てが明るい空色をした非常に美しい鳥だという事。
それで貴族がこぞって飼いたがってんだけど、巣引き(繁殖)に成功できたのはごく一部の修道院だけでね、セネガンビアアオツグミ……面倒だから青い鳥って言うね。
その青い鳥を入手できた人は凄い幸運の持ち主だと言われるようになった。
幸せの青い鳥……この時はそういう意味でそう呼ばれていた。
この時はね。
やがてある商人が巣引きのやり方をすっぱ抜いて、貴族だけでなく裕福なら誰でも青い鳥を飼えるようになった。
商人は青い鳥を幸せをもたらす鳥だと言って売りつけた。
壺とか判子とかの霊感商法なアレのノリで。
実際、青い鳥の飼い主達は『自分達は幸せだ』と言った。
青い鳥を飼ったその日に、むかし失くした指輪を見つけた。
鼻のイボが取れた。
嫁が元気な男の子を産んだ。
馬の糞を踏まずに過ごせた。
姑がちょっと優しくなった。
その他色々、なんとも細やかな幸せだった。
だけど皆、青い鳥のおかげだと言った。
確かに青い鳥は幸せの鳥だったのだろう。
この頃も。
青い鳥って知ってるよね。
そう、メーテルリンクの童話劇。
幸せの青い鳥を探す兄妹の物語。
でも何で幸せをもたらす鳥の色が『青』なのだろうね。
幸せって言うなら、ピンクとか黄色とかのがそれっぽいない?
ほら『薔薇色の人生』とか『幸せの黄色いハンカチ』とかさ。
それでも幸せをもたらす鳥の色は『青』
憂鬱とか、元気ないとかそういう意味になる『青』
実は幸せの青い鳥には、モデルとなった鳥がいるんだ。
『セネガンビアアオツグミ』
大航海時代にポルトガルの船乗りが西アフリカから持ち帰った鳥で、ツグミとついてるけど実際はツグミより一回り大きい別種の鳥らしい。
19世紀初頭に絶滅してるからよくわからない事が多いんだけどね。
わかっているのは、嘴から足の爪まで全身全てが明るい空色をした非常に美しい鳥だという事。
それで貴族がこぞって飼いたがってんだけど、巣引き(繁殖)に成功できたのはごく一部の修道院だけでね、セネガンビアアオツグミ……面倒だから青い鳥って言うね。
その青い鳥を入手できた人は凄い幸運の持ち主だと言われるようになった。
幸せの青い鳥……この時はそういう意味でそう呼ばれていた。
この時はね。
やがてある商人が巣引きのやり方をすっぱ抜いて、貴族だけでなく裕福なら誰でも青い鳥を飼えるようになった。
商人は青い鳥を幸せをもたらす鳥だと言って売りつけた。
壺とか判子とかの霊感商法なアレのノリで。
実際、青い鳥の飼い主達は『自分達は幸せだ』と言った。
青い鳥を飼ったその日に、むかし失くした指輪を見つけた。
鼻のイボが取れた。
嫁が元気な男の子を産んだ。
馬の糞を踏まずに過ごせた。
姑がちょっと優しくなった。
その他色々、なんとも細やかな幸せだった。
だけど皆、青い鳥のおかげだと言った。
確かに青い鳥は幸せの鳥だったのだろう。
この頃も。
ある年、流行り病が国を覆った。
医療といえば、腕の血管切って血を抜くような時代の事だ。
たくさんの人が死んだ。
わずかな生き残りに青い鳥の飼い主がいた。
彼らは言った『青い鳥』のおかげだと。
もちろん青い鳥ごと全滅した家はいくつもあったよ。
でも残った彼らは幸せそうに笑っていた。
そこにちょっとした変化があるのに気付いた者がいた。
街で大量の死体を片付けた修道士は、飼い主によって青い鳥の色合いが違っていると思った。
家族の誰も死ななかった家の青い鳥はそのままだけど、家族の誰かが死んでる家の青い鳥は、その羽の青がより深く鮮やかなものになっていた。
それも、前から寝たきりだった老爺が死んだ家より、幼子を失った母親とか、一人しか残らなかった家の方が変化の度合いは強く、青い鳥はより青くなっていた。
そう、不幸の度合いが大きいほど、青い鳥は青くなり、青い鳥が青いほど悲嘆にくれるはずの飼い主に笑顔があった。
その不思議な変化を修道士は『悲しみに打ちひしがれるだろう彼らを慰める為に、主が奇跡を起こして下さったのだろう』と解釈した。
その話を聞いたある貴族は、ふと思った事を試す事にした。
使用人に青い鳥を預け、その上で酷い仕打ちをした。
些細な事で怒り、言われのない罪を着せ、家財を没収し、大勢の前で鞭打った。
使用人は全身血塗れになりながら笑い声をあげた。
狂ったような……ではなく、穏やかな優しい笑顔だった。
そして明るい空色だった青い鳥は一回り大きくなり、サファイアから削り出したように深く鮮やかな輝きを放っていた。
貴族は確信した。
青い鳥は人の不幸を喰らって肥え太り、より青く美しくなると。
それから酷く悪い趣味が流行るようになった。
お茶会やパーティに、金の鳥籠に入れた青い鳥を持ち寄って、その青さを自慢し合う。
金と暇を持て余した連中のする事だから、ねぇ?
飼い主が不幸になればなるほど青く美しくなる鳥。
どうやって青くしたかも、自慢のタネ。
決して逆らえない立場にいる者を飼い主として青い鳥の世話をさせ、ありとあらゆる苦痛を味あわせた。
身なりのいい紳士淑女のみなさんが、毒を盛っただの、冤罪をかけただの、破産させただの、妻子を慰み者にしてやっただの、笑いながら話す。
青い鳥の飼い主も鳥籠を抱えて笑う。
自分が受けた仕打ちを聞きながら、それでも幸せそうに笑う。
不幸を、悲しみを、憤怒を、青い鳥に全て喰い尽くされて、シアワセしか残っていなかったから。
その有様すら物笑いのタネにされた。
青い鳥がより青くなるようにと。
医療といえば、腕の血管切って血を抜くような時代の事だ。
たくさんの人が死んだ。
わずかな生き残りに青い鳥の飼い主がいた。
彼らは言った『青い鳥』のおかげだと。
もちろん青い鳥ごと全滅した家はいくつもあったよ。
でも残った彼らは幸せそうに笑っていた。
そこにちょっとした変化があるのに気付いた者がいた。
街で大量の死体を片付けた修道士は、飼い主によって青い鳥の色合いが違っていると思った。
家族の誰も死ななかった家の青い鳥はそのままだけど、家族の誰かが死んでる家の青い鳥は、その羽の青がより深く鮮やかなものになっていた。
それも、前から寝たきりだった老爺が死んだ家より、幼子を失った母親とか、一人しか残らなかった家の方が変化の度合いは強く、青い鳥はより青くなっていた。
そう、不幸の度合いが大きいほど、青い鳥は青くなり、青い鳥が青いほど悲嘆にくれるはずの飼い主に笑顔があった。
その不思議な変化を修道士は『悲しみに打ちひしがれるだろう彼らを慰める為に、主が奇跡を起こして下さったのだろう』と解釈した。
その話を聞いたある貴族は、ふと思った事を試す事にした。
使用人に青い鳥を預け、その上で酷い仕打ちをした。
些細な事で怒り、言われのない罪を着せ、家財を没収し、大勢の前で鞭打った。
使用人は全身血塗れになりながら笑い声をあげた。
狂ったような……ではなく、穏やかな優しい笑顔だった。
そして明るい空色だった青い鳥は一回り大きくなり、サファイアから削り出したように深く鮮やかな輝きを放っていた。
貴族は確信した。
青い鳥は人の不幸を喰らって肥え太り、より青く美しくなると。
それから酷く悪い趣味が流行るようになった。
お茶会やパーティに、金の鳥籠に入れた青い鳥を持ち寄って、その青さを自慢し合う。
金と暇を持て余した連中のする事だから、ねぇ?
飼い主が不幸になればなるほど青く美しくなる鳥。
どうやって青くしたかも、自慢のタネ。
決して逆らえない立場にいる者を飼い主として青い鳥の世話をさせ、ありとあらゆる苦痛を味あわせた。
身なりのいい紳士淑女のみなさんが、毒を盛っただの、冤罪をかけただの、破産させただの、妻子を慰み者にしてやっただの、笑いながら話す。
青い鳥の飼い主も鳥籠を抱えて笑う。
自分が受けた仕打ちを聞きながら、それでも幸せそうに笑う。
不幸を、悲しみを、憤怒を、青い鳥に全て喰い尽くされて、シアワセしか残っていなかったから。
その有様すら物笑いのタネにされた。
青い鳥がより青くなるようにと。
この流行は、ある日突然に廃れた。
それは寒い寒い冬の夜の事だった。
ある貴族の館で、豪華な夜会と青い鳥の品評会が行われた。
国中の青い鳥愛好家が集まった。
雪降る路上で凍える貧民をよそに、煌びやかな馬車が何台も通り過ぎていく。
大理石の大広間、天井にはシャンデリアと共に、無数の鳥籠がぶら下げられる。
精巧な細工を施した鳥籠の一つ一つに青い鳥が一羽ずつ。
南の海の透き通るような青。
砂漠の空の目の眩むような青。
矢車菊の清々しい青。
ラピスラズリの深く鮮やかな青。
様々な青がそこにあり、誰もがそれを眺めて幸せそうに笑っていた。
……みんな笑ってたそうなんだ。
……生きてる間はね。
その日はとても寒い雪の夜だった。
大きな暖炉に薪ががんがん焚かれていた。
その日の雪は酷い吹雪で、通気口を塞いだ。
それで、一酸化中毒が起きたのではないかと言われている。
(本当はどうだかわからないよ)
新しい料理と酒を持った給仕が大広間の扉を開けると、中で全員死んでいたんだ。
金時計を持った紳士も、最新流行のドレスを纏った淑女も、彼らに酒を注いでいた給仕達もみんな、死んでいた。
酷く長い苦しみを味わい尽くしたような凄い形相で。
大広間の隅に集められていた飼い主達も死んでいた。
幸せそうな笑顔も苦悶もない、まっさらな無表情で眠るように。
青い鳥も死んでいた。
……たぶん死んでる。
まるで内側から破裂したみたいになっていた。
血と臓物のわずかな赤を、飛び散った青い羽毛が覆い隠した。
(不幸を喰い過ぎちまったんじゃないかなぁ?)
鳥籠からこぼれた羽根は青い雪のように美しかったというよ。
それで青い鳥愛好家は激減した。
みんな何か思うところがあったんだろうね。
でも不思議な事に誰も青い鳥の事を、不幸の鳥と呼ぶ人はいなかった。
国内に残った青い鳥は、助かる見込みのない病人の枕元に置かれたり、そのまま放されたりした。
元はアフリカのジャングルに住む鳥だ。
冬のある大陸では野生に帰る事はできなかったろう。
最後の一羽をみた少年が、後に劇作家になって、この鳥をネタに可愛らしい戯曲を書いたかもしれないね。
****
生きた人間の声が、耳に心地よい事を紡ぐとは限らないわけで。
「どーよ。聞くのは足りたか?」
「はは…」
【後編に続く】
それは寒い寒い冬の夜の事だった。
ある貴族の館で、豪華な夜会と青い鳥の品評会が行われた。
国中の青い鳥愛好家が集まった。
雪降る路上で凍える貧民をよそに、煌びやかな馬車が何台も通り過ぎていく。
大理石の大広間、天井にはシャンデリアと共に、無数の鳥籠がぶら下げられる。
精巧な細工を施した鳥籠の一つ一つに青い鳥が一羽ずつ。
南の海の透き通るような青。
砂漠の空の目の眩むような青。
矢車菊の清々しい青。
ラピスラズリの深く鮮やかな青。
様々な青がそこにあり、誰もがそれを眺めて幸せそうに笑っていた。
……みんな笑ってたそうなんだ。
……生きてる間はね。
その日はとても寒い雪の夜だった。
大きな暖炉に薪ががんがん焚かれていた。
その日の雪は酷い吹雪で、通気口を塞いだ。
それで、一酸化中毒が起きたのではないかと言われている。
(本当はどうだかわからないよ)
新しい料理と酒を持った給仕が大広間の扉を開けると、中で全員死んでいたんだ。
金時計を持った紳士も、最新流行のドレスを纏った淑女も、彼らに酒を注いでいた給仕達もみんな、死んでいた。
酷く長い苦しみを味わい尽くしたような凄い形相で。
大広間の隅に集められていた飼い主達も死んでいた。
幸せそうな笑顔も苦悶もない、まっさらな無表情で眠るように。
青い鳥も死んでいた。
……たぶん死んでる。
まるで内側から破裂したみたいになっていた。
血と臓物のわずかな赤を、飛び散った青い羽毛が覆い隠した。
(不幸を喰い過ぎちまったんじゃないかなぁ?)
鳥籠からこぼれた羽根は青い雪のように美しかったというよ。
それで青い鳥愛好家は激減した。
みんな何か思うところがあったんだろうね。
でも不思議な事に誰も青い鳥の事を、不幸の鳥と呼ぶ人はいなかった。
国内に残った青い鳥は、助かる見込みのない病人の枕元に置かれたり、そのまま放されたりした。
元はアフリカのジャングルに住む鳥だ。
冬のある大陸では野生に帰る事はできなかったろう。
最後の一羽をみた少年が、後に劇作家になって、この鳥をネタに可愛らしい戯曲を書いたかもしれないね。
****
生きた人間の声が、耳に心地よい事を紡ぐとは限らないわけで。
「どーよ。聞くのは足りたか?」
「はは…」
【後編に続く】
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
語部夜行 〜カタリベヤコウ〜 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
語部夜行 〜カタリベヤコウ〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 75494人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208297人
- 3位
- 音楽が無いと生きていけない
- 196028人