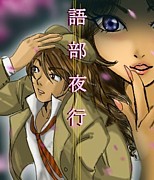この話は『蜃』http://
雨音は再び激しく、だけど遠くに響いていた。
「さっきまで晴れてたのに……」
シダの葉陰に膝をついた湊は、ふと頭上を見上げた。
時計の針こそ午前九時を指していたが、厚い雨雲と生い茂る木々が天蓋となってそこは黄昏時の暗さを保っていた。
ここは、語部館の庭園の隅に設えてある温室。
温室なので、湊は雨に濡れる事はないが、視界の悪さと生暖かい湿気でベトナムの密林にでも放り出されたような錯覚を感じる。
「こちら湊。所定の場所についた」
『こちら夜子。奇門遁甲の陣の発動にはあと小一時間ばかりかかるそうよ』
無線に囁きかけると、思ったよりも大きくはっきりした応答が帰ってきた。
骨伝導スピーカーの調子は良好なようだ。
「えー。それならもうちょいそっちでまったりしてれば良かった」
『先んじれば人を制すというものよ』
「奇襲は好きだけど、こういうのは趣味じゃない」
『でしょうね。だけど今は力を温存しておいてもらえる?』
「了解」
湊は背後のトックリヤシの幹に背中を預けて、編み上げの軍用ブーツに包まれた脚を軽く伸ばした。
森林迷彩の野戦服に、肩にかかるアサルトライフル。
腰のベルトに弾倉がいくつもねじ込まれ、どこのコマンドーかという有様だが、頭にかぶっているのはバンダナでも鉄のヘルメットではなく、牙を剥く鬼の面だった。
――二時間前。
「話は聞かせてもらったぜー!」
朝日を背に、騒がしく登場した湊と……和服姿の清楚な女性。
「湊さん、その人は……」
「姉さん何故ここにっ!?」
「姉ぇぇぇーーーーーーーーーーーッ!?」
「どうも、愚弟がいつもお世話になってます」
和服美人――三堂 咲はにっこり笑って一礼し、菓子折りを夜子に渡した。
「へぇ、双子のお姉さんなんだ」
「二卵性だから、あまり似てないでしょう?」
「いや、目元とか鼻筋のあたりに面影が……」
「でも、圭一さんがお姉さんにそっくりなら、すごいイケメンになってるはずじゃん」
お茶とお菓子でテーブル席の会話が弾む一方。
「湊さん……姉さんとはどういう知り合いで?」
壁際で魂魄の抜けかかった圭一が、湊に問うていた。
「ああ、三堂さんとは……」
「語部館に行く途中、偶々知り合ったんですよね?ね?湊さんてば誰にでもなれなれしいゲフン誰とでも友達になれるタイプだからと」
「うんにゃ。仕事上の付き合い」
「社会人方面!?」
湊の勤める清掃会社には、特殊な清掃を請け負う部署があり、その業務の過程で『持ち主のない家財』が発生し、その処理をそのまま任される事が少なくない。
それらは、あるものはリサイクル業者に送られ、あるものはゴミとして廃棄される。
「そんで時には、曰くつきのモノってのが出てきてね」
例えば、髪の伸びる人形のような可愛いものから、人の指が入った寄木細工の箱といった洒落にならないものまで。
「虫籠事件の後、そういうモノの鑑定や処理を、専門の業者に任せようって事になって、うちの社長が依頼したのが三堂本舗って骨董品店でね」
骨董品店の主人というから、社員全員が老仙じいちゃんみたいなの想像してて、なのに若い美人が来たから驚くやらはしゃぐやらで大変だったという。
「全然知らなかった……」
「私も、三堂本舗さんの噂の弟が圭一だとか初めて知ったよ」
「え?噂って……」
『ちょっと待たんかい!』
圭一の言葉を遮って怒鳴ったのは鬼の面だった。
『お前ら何か忘れておらんか?忘れておるだろう?なぁ!』
「そ……ソンナコトナイヨ。鬼面の嫁さんが、ヒトガタに寝取られて駆け落ちして逃げたんだろ」
「湊さん違ッ!大体合ってるけど違ッ!」
鬼の面は湊の頭に噛みついた。
「痛たたたたたたっ!?暴力反対っ!」
『黙れ!人間如きに何がわかるっ!!』
「こーいうのは殴ったら負けなんだってば!間男と汚嫁はわざと泳がせて、裁判に有利な証拠を探偵に集めさせて両方から慰謝料がっぽり搾り取れってパートのおばちゃんがッ!!」
『おたふくはそんな女ではないわーーーーーー!!』
鬼面は血の涙を流しながら、湊の頭をギリギリ噛みしめた。
「湊さん、おたふくさんは鬼面さんをかばって連れ去られたんですよー」
『そうじゃ!おたふくは情の深い優しい女じゃあ、貴様の下劣な想像で汚すでないわー!』
その時ギラリと湊の目が光った。
「信じてるなら、さっさと助けに行けよこのヘタレッ!!」
『おぶっ!?』
湊は片手で鬼面をむしり取って、床に叩きつけた。
床に毛足の長いふかふか絨毯が敷いてなかったら、木端微塵になっていたかもしれない。
「黙って聞いてりゃ、てめぇの嫁が拉致られたってのに一晩中めそめそ泣いてるだけで……情けない」
『お……おおお』
「だから男なんてピンポン玉とか言われるんだよ」
湊のわけのわからない罵倒に小刻みに震える鬼面を、白魚のような手が拾った。
「言ったでしょう、話は聞かせてもらったと」
咲の細い指先が鬼面の血涙をそっと拭う。
「愚弟の犯した不始末は、姉の私がすすぎましょう」
その微笑みは清雅で、だけどどこか底冷えのするものだった。
作戦そのものは非常に単純だ。
語部館の敷地内をうろうろしているヒトガタを、一か所に追い込み、叩いて、おたふくの面を引き剥がして回収する。
「三堂さん、語部館って、見た目よりかなり広いんだけど……」
「あら葦谷さん、仕事じゃないんだから名前で良くてよ。それに三堂が二人もいたらややこしいでしょう」
「そんじゃ自分の事も湊で……それより、ここは庭も含めると捜索範囲がかなりとんでもない事になるのですよ」
「大丈夫よ。圭一がいるから」
「そうか、頑張れよ」
「え?それで会話終了!?」
ぽむっと湊は圭一の肩に手を置いた。
「自分一人であのヒトガタを追いかけろと!?」
「馬鹿ね、奇門遁甲の陣を敷くの」
奇門遁甲は中国の占術の一種で、その歴史は古く、戦で布陣や策略にも利用されていたという。
「これを使えば、ヒトガタをこちらの意図する場所に誘導できるわ。簡単なものなら、二人がかりでやれば短時間で作れるはずよ」
「でも姉さん、アレは計算がすっごく面倒で……」
しかもちょっとでもミスがあれば大変な事になると躊躇う圭一に、姉はにこやかに言った。
「仕方ないわね、私一人で作った不完全な陣でも、ヒトガタの爆発と外への流出は防げるわ……でもね」
捕まえない限りヒトガタは永遠に語部館敷地内を彷徨い続ける。
おたふくの面をかぶったまま。
そして、ヒトガタとおたふくの面は互いに影響し合い、変異していくだろう。
あたかも芋虫が蛹になり、蛹の内側でドロドロに溶けて、蝶というそれまでと全く違った生き物に再構成されるように。
「何が出来上がるか、興味深くはあるわね」
『さらりと恐ろしい事を言うでないわ!』
鬼面が悲鳴じみた声で叫んだ。
「可哀そうな鬼面さん。変成したおたふくさんだったものは、鬼面さんの事を何一つ覚えていないんだわ」
『おおおおっおたふくぅーーーー!?』
「嗚呼、なんという悲劇なんでしょう……誰かがヒトガタを語部館に入れさえしなければこんな事は」
咲は、はらはらと涙を流した。
「わかったよ、わかりましたよ!計算頑張るから!遁甲陣敷くからっ!」
奇門遁甲の陣による最終追い込み地点は、裏庭の温室に決まった。
おたふく奪還の大任を背負うのは、半身たる鬼面と、その依り坐。
「責任重大よ。頑張ってね、湊さん!」
「えええええっ!?」
――そして今に至る。
『何もお前が無理する事はないと思うんじゃがの』
湊の頭の上で鬼面はカタカタと喋った。
「確かに、咲さんがあんたをかぶって薙刀もったら凄く萌えると思うよ」
『そうではない。ヒトガタを引き込んだのはあの男ならば、わしの依り坐はあの男がやれば良いではないか』
「それを防ぎたかったんだよ、あの人は」
妙なモノに好かれやすく、憑かれやすい圭一。
彼の依り坐としての資質は群を抜いたもので、姉の咲はいつもそれを心配している。
「咲さん曰く、私とあんたの相性が100点中80とするなら、圭一とあんたは256くらいあるらしいから」
一度憑いたら最後、互いの意志があっても離れられないだろうと。
それに、おたふくの面に取り返しのつかない事が起こったら、原因となった圭一を鬼面は決して許さないだろう。
「全てはそれを防ぐ為。私を駒にしてまで……怖い人だよ」
『お前は、大人しゅう駒に甘んじる人間に見えんがな』
「……一週間前、遺品整理の現場に駆り出されてさ」
そこで湊は茶碗を一つ落として割った。
「とろけるような青い色をした茶碗で、100円ショップで同じようなの探して弁償すればいいと思ったんだけど……」
その日の事を思い出した湊の顔色が青ざめる。
「誰も思わないよ……孤独死した老人の、ゴミ屋敷の中に宋代の青磁があるとかっ」
しかもそれが皇帝御用達の窯で焼かれたものだとか、世界でも70個前後しか残ってないとか、製法が失われているので国宝どころかオーパーツ同然だとか。
「ゴミ屋敷の権利書はヤクザが持っていて……もしもあの時、あの人がいなかったら、私は内臓売る羽目になってたんだよ」
その日その時その場所で何が起こったか、湊はそれ以上詳しく語る事はなかった。
『わしが思うに、あの男の姉の恩は、内臓よりも汝窯の青磁よりも高くつくのではないか?』
「……なぁ、やめよう?この話は」
『そうじゃな』
鬼面と人間が口をつぐむと、静かになった分、雨音がやけに大きく聞こえた。
『やれうるさいの』
「……」
『おたふくはまだかの』
「……」
『陣はまだできんのか』
「あんたのがうるせぇよ!」
『暇なんじゃ!何か話をせい!』
「そっちこそ何かネタはないのか?元は蜃気楼の蛤だったんだろ」
『ふん、いい男は過去にこだわらんのじゃ』
「……そうか、それじゃあ浪の底の都の事は知らないのか」
『浪の底?』
「平家物語って知ってる?」
『そのくらい知っておるわ。源平合戦じゃろ』
度重なる敗戦で、都を追われた平家一門。
壇ノ浦で追い詰められ、ついに入水自殺する時、二位の尼は孫でもある幼い安徳天皇に『浪の底にも都はありますよ』と言ったのだった。
「それで、海底に本当に都があるのか、あんた知ってるかなと思って」
『さすがに嘘じゃろぅ……幼子をなぐさめる為の悲しく優しい嘘じゃあ』
「ところで、平家物語といえば耳なし芳一だよね」
『切り替え方がかなり強引じゃが、その話はもう知っておるぞ』
『耳なし芳一』は小泉八雲の代表作『怪談』の中の一編だ。
平家の怨霊にとり憑かれた琵琶法師が、全身に経文を書いて姿を隠して難を逃れようとするが……衝撃的な結末を迎える恐ろしい話だ。
「だけど、この話には古来から類話がいくつかあるらくてね」
例えば江戸時代の書物では舞台が尼寺だったり、主人公が芳一ではなく、うん市って座頭だったりと、設定に差異があるが同系の話があるという。
「私が聞いたのは……あれは、類話っていうより後日談って奴かな」
++++++++++
|
|
|
|
コメント(11)
「ご心配なく。聴こえておりますよ」
僧形の青年は、直平と同い年くらいで、だけど刃物で削いだように痩せていた。
両目は固く閉ざされ、やや顎をつきだすようにしているが顔つきそのものは平凡で、せいぜい剃り上げた頭の形が良いくらい。
それゆえに、彼の異形が際立っていた。
顔の横にあるはずの、左右の耳がない。
彼は、僧は僧でも当道座の琵琶法師。
三年前、その類稀な腕前ゆえに、平家の怨霊に魅入られ、墓の前で平曲を弾じるのを強いられた挙句の果てに両の耳をむしり取られたという噂がある。
噂の通り、彼には確かに耳が無くそれで直平はつい言ってしまったのだ。
――目だけでなく耳まで失うとは哀れだな。
――音が聞こえないのに、琵琶が弾けるのか?
耳がないから、聴力もないと思い込んだ直平は当の琵琶法師の目の前で、そんな心無い事を言った。
そして嘲られた琵琶法師は、顔色一つ変えず答えたのだった。
直平は貴族の子弟で、家は没落しつつあったが、闘茶(注:茶の銘柄を当てる賭博)で財を成した。
その金を元手に土蔵(注:金貸し)を始め、近隣の守護や商人と親交を深め、今回、堺の豪商摩周屋に陀厳(だごん)寺での茶寄合に招かれた。
集まった名士や遊女達と共に、風呂で汗を流し、茶の湯を愉しみ、宴会で大騒ぎするという遊興性の高い淋汗茶湯だ。
その宴席で当代随一と名高い琵琶法師の平曲(平家物語)を鑑賞するという趣向になっていた。
庭園を散策していた直平は、道に迷う内に噂の琵琶法師と出会ったのだった。
「こっ……これは、、知らなかったとはいえ無礼な物言いをいたしました」
「お気になさらず。よく言われる事なのです」
怨霊に力任せに引きちぎられたというその耳は、思ったよりも滑らかな傷痕で耳孔を囲んでいた。
「耳の穴の奥には膜があって、それが無事なら音は聞こえるのですよ」
「それは良かった」
「ですが……」
聴力そのものは失せてはいないが、外耳部がなくなった事で、聞こえ辛くはあるという。
特に音の聞こえる方向がわからなくなった。
「最近では、聞こえるはずのない音まで聞こえるようになりました」
琵琶法師はその手に抱いた琵琶を爪弾いた。
“ビィン”
平曲に用いる平家琵琶は、雅楽の琵琶より小ぶりで音も小さい。
携帯しやすくする為と語りを妨げない為だ。
「聞こえるはずのない音とは?」
「浪の……いいえ、あれは水の音」
例えば澱んだ水に飛び込んで、その底まで潜った時の、耳の中で響くころころとした低く濁った音にとてもよく似た、名状しがたい何かの音。
その音がふとした拍子に、どこからか何度でも鳴り響くのだと。
「ここは山寺なのに?風の音ではありませんか」
「いいえ、水です。水の中の音です」
“ビィン”“ビィン”“ビィン”
無意識だろうか、爪弾く間隔が短く、激しいものになっていく。
「直平様、私は思うのです。三年前のあの日、平家の怨霊が耳を引き千切り……果てしてそれで終わっだろうか」
――自分は本当に難を逃れる事ができたのか?
「平家の怨霊は言いました『耳だけでも連れて行く』と。連れて行かれた拙僧の耳は、壇ノ浦の水底にあり、水の音と亡霊達の声を聴き続けているのではないかと?」
――嗚呼、そもそもあれは本当に平家の怨霊だったのか?
「法師殿、その音は……」
今この時も聞こえているのかと、直平は聞こうとしてやめた。
彼が琵琶を爪弾いているのは、直平には聞こえないその音を掻き消そうとしているのに他ならない。
「法師殿、私はこれにて。今宵の平曲楽しみにしております」
気味が悪い。
そう思った直平は、そそくさと部屋を出た。
無駄に大きな石灯籠に持たれて一息ついていると、簡素な水干を着た少年がこちらへ駆け寄ってきた。
直平が連れてきた供の一人だ。
「頭、探しましたぜ」
「今は直平だ。頭はよせ」
直平はニヤリと笑う少年の頬をつまんで力いっぱい捻った。
「いひゃひゃひゃ!?」
「お貴族サマの侍童が、山賊の下っ端みてーな喋りしてんじゃねぇよ」
直平……直平に化けた山賊の頭目は、他に人の気配がない事を確認してから、気が済むまで部下の少年を抓った。
捨て子から山賊の頭目に成り上がったこの男に名前は無く。その時々の気分で適当に名前を変えたり、奪っていた。
直平もその一つで、この陀厳寺に入る為に直平の名前と身分が必要だったので、ここに来る途中を襲って奪った。
本物の直平は今頃、生まれたままの姿になって山の獣に功徳を施している事だろう。
陀厳寺は度重なる戦乱で所持していた荘園を失い、寂れる一方だったが最近、摩周屋から多額の寄進を受けた。
それで雨漏りのする本堂を建て替え、さらに書院だ茶室だと庭園だと増改築を重ねた。
今では、麓の村の寂れっぷりと裏腹に、花の御所もかくやといった贅沢な寺院になっている。
ならば宝物庫に貯めこんだお宝も結構なモノだろう。
よしそれをいただこう。
そう思った山賊の頭目は、直平になって寺に入り込んだ。
迷ったフリして間取りを調べ、宝物庫の位置と鍵を押さえて、内側から門を開けて血に飢えた子分共を中に引き込みヒャッハー!……というのが大まかな計画だった。
そんな雑な計画がここまでまかり通ってしまったのは、頭目のこの男が水も滴る美丈夫だったからだ。
男は自分を捨てた両親を恨んではいたが、山賊とはとても思えない気品のある整った顔に産んでくれた事は感謝していた。
この顔は人を誑かし易いのだ。
女は自分から股を開くし、男はこちらを弱いと思い込んで油断してくれるし、年寄は我が子に面影を重ねる。
ただ盲目の琵琶法師には通じないだろうと思っていたが、何故か聞かれもしないのに不気味な悩みを語りだした。
「それで、かし……直平様、首尾は?」
「ほらよ」
頭目は袂から紙片を取り出し、少年に渡した。
紙片には陀厳寺の間取りが記されていた。
「これで後は、頭の合図待ちっすね」
頭目は無言で少年のつま先を踏んで、捻じった。
「いぃぃぃぃっ……オユルシクダサイ直平様」
「口のきき方に気をつけろよ、演技指導的な意味で」
「すいません。間取りもらったから俺もう行っていいですか?」
元よりこの後、何かしら理由をつけて少年を不自然なく外へ遣り、山中に待機している仲間にこれを渡す手はずになっているのだが。
少年は一刻も早くここを離れたいと言った。
「なんつーか、ここってすげぇヤな感じするんすよ」
「陸にいるのに水に潜った時の音でもするのか」
頭目は琵琶法師を思い出して、冗談を言ったつもりだったが。
「いや、音までしないけど、なんか生臭いしょっぱい匂いしません?海みたいな」
「ここは山の中だぞ」
「だから気味が悪いんじゃないすか」
頭目も本当は潮の香りを感じていた。
だがそれは錯覚だと思っていた。
この贅を尽くした造りの寺院の、どの部屋の襖絵も海や川を描いたものばかりで、天井に鯛やヒラメといった魚介類や見たこともないような生き物が精密な筆致で描かれていた。
門や回廊、欄間にも柱に細かに波や流水を思わせる彫刻が施され、どこにいても海の中にいるような気がする。
それこそ、潮の香りがしそうな程に。
……いや、潮の香りがするような錯覚を『錯覚させられていた』としたら?
少年はお供という設定で、用もないのに奥まで入らないし、琵琶法師は陀厳寺の内装を知りようがない。
「わけわからん。だからなんだってんだ」
「このヤマはなんかヤバいから止め……」
「眠たい事言ってると、本当に眠らずぞ?」
「ひぃっ!」
頭目が、気前はいいが屈強な野武士も幼い赤子も分け隔てなく殺せる人間だと知ってる少年は、彼の冷たい眼差しに腰を抜かして怯えた。
「まぁいい、さっさとそれを持って行け。全て整ったら指笛を吹くから……後はわかるな」
「全員でブっこんで、金目の物をいただいて、火をつけてずらかる。邪魔する奴らは皆殺しっすね!」
ぱぁっと目を輝かせて少年は走り去った。
身が軽いから、塀をこえていくだろう。
頭目はふと目を閉じて、耳を澄ませた。
風の音と、摩周屋が連れてきた遊女の笑い声が聞こえた。
それから幽かな琵琶の音が。
水っぽい音は聞こえなかったけれど、生臭い海の匂いを確かに感じた。
広間には様々な音と匂いに溢れていた。
酒の匂い、茶の匂い、珍味佳肴の匂い、女の肌の甘い匂い、寺稚児の青臭い匂い。
武士の武勇伝、食器の触れる音、商人の苦労話のふりした自慢話、笑い声、公卿の噂話、嬌声。
一度気になると、とことん気に障るものなのか。
頭目の耳と鼻は、あるはずのない海の気配を探し続けていた。
すでに、廚に忍び込み水瓶に眠り薬を放り込んでおり、警備の僧兵は眠り始めているだろう。
適当な理由をつけてこの場を離れ、門を開けて仲間を引き込まなければならないのに、頭目はいまだ宴席に留まっていた。
「直平様、お楽しみいただけておりますかな」
顔色の悪い男がにたにた笑いながら、頭目に酒を注いだ。
「これは摩周屋殿」
堺の豪商・摩周屋。
陀厳寺に莫大な寄進をした男。琵琶法師の怪我を治し、陀厳寺での静養を勧めたのもこの男だ。
彼は商人とは思えぬ大きな体躯を丸め、ぺこぺこと頭を下げた。
直平と摩周屋は書簡でのやりとりが主で、実際に顔を合わせるのはこれが初めてらしい。
具合が悪いのか、摩周屋はぬめぬめとした汗をかき、それでも愛想をふりまく。
その姿は醜悪だと頭目は思った。
摩周屋の顔はぎょろりとした目が左右離れ、口が大きく、それがへの字に曲げられていて、まるで……
『魚か蛙のようだ』
もちろん口には出さず、穏やかに微笑んでみせた。
「どうも御気分がすぐれないように見受けましたが?」
「いやはや酒が過ぎたようだ」
酔い覚ましに夜風にあたってくると、立ち上がりかけた所を摩周屋に引き止められる。
「どうぞ、茶は百薬の長ですぞ」
押し付けられた唐物の茶碗にの底に、松葉色の抹茶がとろりと溜まっていた。
香り高く滋味深いはずのそれが、水藻の塊に思えて飲み干すのを躊躇わせた。
「直平様、いかがなさいましたか?」
「いや、なんでもない」
頭目が化けている『直平』は闘茶の強さで有名な男だ。この場で出された茶を断るのはまずい。
――どうする?『手が滑った』とか言って茶碗を落とすか?
――駄目だ。闘茶で名を上げた人間のする動作じゃない。
その時、広間のざわめきが一瞬大きくなった後、しんと静まり返った。
大柄な僧兵が、痩せた盲目の僧の手を引いて入ってくる。
盲僧は残った片手に琵琶をしっかりと抱きしめていた。
「おお、琵琶法師だ」
「あれが噂の……」
「まぁ、本当に耳がないわ。かわいそうに」
白々しい囁き声の中、琵琶法師は席についた。
その表情は、昼間と打って変わって晴れやかだった。
「結構なお点前で」
頭目は涼しい顔で空の茶碗を摩周屋に返した。
「あ……」
「このような席です、堅苦しいのは無しでしょう」
全員の視線が琵琶法師に集中した隙に、頭目は自分の着物の端を千切り、丸めて口に含んだ。
そして茶を飲んだようにみせかけ、実際は口の中の端切れに茶を吸わせた。
飲み込みこそしないものの、口内に茶の味が広がる。
茶の味と、緑に澱んだ沼の水のような味が。
吐きそうになるのをぐっとこらえて笑ってみせた。
「なら、御代わりはいかがですか」
「………」
頭目が外で待機してる仲間の事を忘れて、こいつらこの場で皆殺しにしようと意志を固めかけた時、美しい琵琶の音と、力強い声が響いた。
『祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き有り、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理を表す』
平曲が始まっていた。
あのやつれた身体のどこからと、驚くほどの声量だ。
「今宵の演目は?」
平曲は200曲以上あるので、人気のあるものを幾つか選んで弾き語るのが通例となっている。
「予定では祇園精舎と……敦盛最期と那須与一、先帝御入水となっておりますが、頼めば好きな曲を何でも弾いてくれるそうです」
『去るほどに一の谷の戦破れにしかば、武蔵の国の住人熊谷の次郎直実は……』
胸を掻き毟るような切々とした琵琶の音。
張りのある朗々とした声が、栄華を極めた一門が滅びる様を謳いあげるのを頭目は聞き入った。
そして当初の目的を忘れかけてるのに気付いて、内心慌てた。
「直平様、そんなにそわそわなされて……平家の亡霊を信じておいでですかな」
摩周屋はなおもしつこく引き止める。
「いえ、ちょっと厠に」
「大丈夫、恐れる事などありません……法師様も何やら悩んでおいでのようでしたが」
「摩周屋、お前も知っていたのか」
「直平様、盲人が最も恐れるのは何だと思いますかな?」
頭目は少し考えて『見える者の悪意』と答えた。
目の見える者は、見えない者をどうとでも欺ける。騙すも殺すも思いのままだ。
「ああ、それもありますね。私はですね『正体のわからない音』だと思うのです」
盲人は見えるものより、聴覚が鋭い。
視覚という光りでは得られない情報を、そのほかの全てを使って得ようとするからだ。
中には常人には聞こえぬ音を聞き取る者もいるだろう。
だからこそ、何だかわからない音はなおさら恐ろしいはずだ。
「だから私は法師様に音の正体を教えて差し上げました」
摩周屋のまん丸く濁った目が恍惚と輝き、口の端から涎がだらだらと垂れる。
「そしてそれが聞けるというのは、選ばれた者に与えられた僥倖だと」
「僥倖?どこがだよ!?」
「拒むから恐ろしく思えるのです。それは受け入れさえすればいい……法師様はわかってくださいました」
素に戻った頭目が問い詰めようとした時、それは起こった。
「ぐげええええええっ!」
遊女を膝に乗せて戯れていた武士が、くぐもった悲鳴を上げた。
武士の顔貌が、メキメキと音を立てながら変わっていく。
大きく見開かれた目が左右に離れ、鼻が縮み、口は横に広がり、顎は突き出て……まるで、魚のように。
「キャーーーーーーッ!」
それを目の当たりにした遊女の絹を裂くような悲鳴も、途中で濁り、武士と同じような変貌が始まる。
「ゲゲッ…げぼがぼっ……」
「いぎぎぎぎっ……グギャッ」
「助げで、ぐるじぃ。だずげべべべべ」
変貌は、広間のそこら中で起こっていた。
何万貫もの金を指先一つで動かす商人も、典雅な歌人も、才覚に溢れた能楽者も、妖艶な寺稚児も、皆、魚のような顔になっていく。
背は曲がり、脚も曲がり、指先には鉤爪が伸び、指の間には水掻きができた。
『……二位殿やがて抱き参らせて、浪の底にも都の侍ふぞと慰め参らせて千尋の底にぞ沈給ふ……』
狂乱の中、琵琶法師の平曲だけがそのまま朗々と響いていた。
それにカッとなった頭目は、床に転がる刀を拾い琵琶法師を斬り捨てようとしたが、摩周屋が間に割って入った。
頭目はそのまま摩周屋を斬った。
肩から腹にかけて刀をめりこませた摩周屋はごぼごぼと笑った。
『祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響き有り、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理を表す』
平曲が始まっていた。
あのやつれた身体のどこからと、驚くほどの声量だ。
「今宵の演目は?」
平曲は200曲以上あるので、人気のあるものを幾つか選んで弾き語るのが通例となっている。
「予定では祇園精舎と……敦盛最期と那須与一、先帝御入水となっておりますが、頼めば好きな曲を何でも弾いてくれるそうです」
『去るほどに一の谷の戦破れにしかば、武蔵の国の住人熊谷の次郎直実は……』
胸を掻き毟るような切々とした琵琶の音。
張りのある朗々とした声が、栄華を極めた一門が滅びる様を謳いあげるのを頭目は聞き入った。
そして当初の目的を忘れかけてるのに気付いて、内心慌てた。
「直平様、そんなにそわそわなされて……平家の亡霊を信じておいでですかな」
摩周屋はなおもしつこく引き止める。
「いえ、ちょっと厠に」
「大丈夫、恐れる事などありません……法師様も何やら悩んでおいでのようでしたが」
「摩周屋、お前も知っていたのか」
「直平様、盲人が最も恐れるのは何だと思いますかな?」
頭目は少し考えて『見える者の悪意』と答えた。
目の見える者は、見えない者をどうとでも欺ける。騙すも殺すも思いのままだ。
「ああ、それもありますね。私はですね『正体のわからない音』だと思うのです」
盲人は見えるものより、聴覚が鋭い。
視覚という光りでは得られない情報を、そのほかの全てを使って得ようとするからだ。
中には常人には聞こえぬ音を聞き取る者もいるだろう。
だからこそ、何だかわからない音はなおさら恐ろしいはずだ。
「だから私は法師様に音の正体を教えて差し上げました」
摩周屋のまん丸く濁った目が恍惚と輝き、口の端から涎がだらだらと垂れる。
「そしてそれが聞けるというのは、選ばれた者に与えられた僥倖だと」
「僥倖?どこがだよ!?」
「拒むから恐ろしく思えるのです。それは受け入れさえすればいい……法師様はわかってくださいました」
素に戻った頭目が問い詰めようとした時、それは起こった。
「ぐげええええええっ!」
遊女を膝に乗せて戯れていた武士が、くぐもった悲鳴を上げた。
武士の顔貌が、メキメキと音を立てながら変わっていく。
大きく見開かれた目が左右に離れ、鼻が縮み、口は横に広がり、顎は突き出て……まるで、魚のように。
「キャーーーーーーッ!」
それを目の当たりにした遊女の絹を裂くような悲鳴も、途中で濁り、武士と同じような変貌が始まる。
「ゲゲッ…げぼがぼっ……」
「いぎぎぎぎっ……グギャッ」
「助げで、ぐるじぃ。だずげべべべべ」
変貌は、広間のそこら中で起こっていた。
何万貫もの金を指先一つで動かす商人も、典雅な歌人も、才覚に溢れた能楽者も、妖艶な寺稚児も、皆、魚のような顔になっていく。
背は曲がり、脚も曲がり、指先には鉤爪が伸び、指の間には水掻きができた。
『……二位殿やがて抱き参らせて、浪の底にも都の侍ふぞと慰め参らせて千尋の底にぞ沈給ふ……』
狂乱の中、琵琶法師の平曲だけがそのまま朗々と響いていた。
それにカッとなった頭目は、床に転がる刀を拾い琵琶法師を斬り捨てようとしたが、摩周屋が間に割って入った。
頭目はそのまま摩周屋を斬った。
肩から腹にかけて刀をめりこませた摩周屋はごぼごぼと笑った。
「浪の底には都がある。都には神がおられる。法師様は神の声を聴く巫であられた!」
「全部てめぇの差し金かよっ!」
「この寺は巫たる法師様の為に、眷族の血を引く者を集めたこの宴は眠れる神の為に、この謳も楽も全てが神託!さぁ目覚めるがいい眷族よ同胞よ!」
八百万の神より旧い神、その眷族の血を引く摩周屋は己の財力を全てつかって、同じ血をわずかでも持つ者を探し、集め、無理やりにでも覚醒させようとしたのだった。
人間らしい部分が失せると、変貌した人々は苦しむのをやめて、てんでばらばらに歩き回った。
ぴょんぴょんと蛙のように跳ねながら。
歪んだ身体に絡みつく着物が、彼らが元は人間であった事をわずかに指示していた。
そして魚顔達は、変貌の度合いが薄いものや、人間のままでいる者を探して襲い掛かった。
魚顔に変貌したのは全体の三割程度だったが、魚顔は見た目が人間離れしている分、体力や腕力も人間離れしているのだろう、人間の五体をたやすく引き裂き、食い千切った。
「……ちっ!」
頭目は摩周屋を蹴り飛ばして刀を抜くと、広間を飛び出した。
琵琶法師を改めて斬ろうとも思ったが、魚顔がたくさん集まっていて近づけなかった。
――とにかく逃げろ!……違う、続行するんだ。
陀厳寺の境内は、地獄絵図が繰り広げられていた。
魚顔が人間に飛びかかり、噛みつき、引き裂き、食いちぎる。
中には太刀を振り回して、逆に魚顔を殺す者もいたが、ごく少数だった。
そしてどこにいても琵琶の音と、琵琶法師の声が聞こえた。
彼はもう、平曲を弾き語ってはいなかった。
浪の底の都にある、自分の耳を通して聞こえる唸りとも声明ともつかないモノを謳っていた。
“ふんぐるい むぐるうなふ くとぅるふ るるいえ うが=なぐる ふたぐん”
どうにか門に辿り着くと、屈強な僧兵が何人も横たわっていて、それに魚顔が群がっている。
僧兵達は、ほぼ無抵抗で食い殺されていた。
「糞っ!役立たず共が……って俺のせいか」
事前に眠り薬を盛ったのが完全に裏目に出たようだった。
だが、魚顔達は哀れな獲物を貪るのに夢中でこちらに気づいていなかった。
流れ作業のように魚顔の首を落とし、頭目は門の閂を外して開けた。
「こいつら皆殺しにして、跡形もなく焼き払ってやる」
頭目は合図の指笛を吹いて、仲間の山賊を陀厳寺に呼び込んだ。
――そしてその事を頭目は酷く後悔した。
「全部てめぇの差し金かよっ!」
「この寺は巫たる法師様の為に、眷族の血を引く者を集めたこの宴は眠れる神の為に、この謳も楽も全てが神託!さぁ目覚めるがいい眷族よ同胞よ!」
八百万の神より旧い神、その眷族の血を引く摩周屋は己の財力を全てつかって、同じ血をわずかでも持つ者を探し、集め、無理やりにでも覚醒させようとしたのだった。
人間らしい部分が失せると、変貌した人々は苦しむのをやめて、てんでばらばらに歩き回った。
ぴょんぴょんと蛙のように跳ねながら。
歪んだ身体に絡みつく着物が、彼らが元は人間であった事をわずかに指示していた。
そして魚顔達は、変貌の度合いが薄いものや、人間のままでいる者を探して襲い掛かった。
魚顔に変貌したのは全体の三割程度だったが、魚顔は見た目が人間離れしている分、体力や腕力も人間離れしているのだろう、人間の五体をたやすく引き裂き、食い千切った。
「……ちっ!」
頭目は摩周屋を蹴り飛ばして刀を抜くと、広間を飛び出した。
琵琶法師を改めて斬ろうとも思ったが、魚顔がたくさん集まっていて近づけなかった。
――とにかく逃げろ!……違う、続行するんだ。
陀厳寺の境内は、地獄絵図が繰り広げられていた。
魚顔が人間に飛びかかり、噛みつき、引き裂き、食いちぎる。
中には太刀を振り回して、逆に魚顔を殺す者もいたが、ごく少数だった。
そしてどこにいても琵琶の音と、琵琶法師の声が聞こえた。
彼はもう、平曲を弾き語ってはいなかった。
浪の底の都にある、自分の耳を通して聞こえる唸りとも声明ともつかないモノを謳っていた。
“ふんぐるい むぐるうなふ くとぅるふ るるいえ うが=なぐる ふたぐん”
どうにか門に辿り着くと、屈強な僧兵が何人も横たわっていて、それに魚顔が群がっている。
僧兵達は、ほぼ無抵抗で食い殺されていた。
「糞っ!役立たず共が……って俺のせいか」
事前に眠り薬を盛ったのが完全に裏目に出たようだった。
だが、魚顔達は哀れな獲物を貪るのに夢中でこちらに気づいていなかった。
流れ作業のように魚顔の首を落とし、頭目は門の閂を外して開けた。
「こいつら皆殺しにして、跡形もなく焼き払ってやる」
頭目は合図の指笛を吹いて、仲間の山賊を陀厳寺に呼び込んだ。
――そしてその事を頭目は酷く後悔した。
++++++++++
『何で後悔したんじゃ?』
鬼面はカタカタ言いながら続きを促した。
物語への貪欲さは、語部館の住人も人外も変わらないのだなと湊は思った。
『……ああそうか、山賊は魚顔に返り討ちにされてもうたんか』
「いいや、もっと酷い事さ』
陀厳寺になだれ込んだ山賊達は、そこで例の琵琶と琵琶法師の声を聴き、その半数が魚顔になってしまった。
壮絶な同士討ちが起こって、もう略奪どころではなくなったという。
「それでも頭目は執念で陀厳寺を燃やしたらしいよ」
『琵琶法師はどうなった?』
「陀厳寺の焼け跡から、それらしき死体はでてこなかったそうだよ……ただ」
『もったいぶるな。早よぅ言え』
「その地域の記録によると、陀厳寺が焼けた数年後、補陀落渡海があったらしい」
補陀落渡海は仏教の捨身行の形態の一つで、小船に僧を入れた箱を乗せて、西方浄土を目指して沖まで流す。
小船に櫂や櫓の類はなく、箱も出入り口はなく、中の僧は死んでもそのまま漂流し続ける。
「即身仏の海バージョンって奴」
『乱暴すぎる説明じゃのぅ……して、その箱から琵琶の音でもしておったか』
「海のモノは海に返すのが妥当って判断されたみたいだね。どこまでホントか知らないけど」
『嘘でも真でもかまわんから、山賊の頭目がどうなったのかも話さんかい』
「半年後に自殺したらしい」
『自殺とな、意外と繊細じゃったんだのぅ』
己が率いていた山賊団が、あんな形で壊滅したのは確かにショックだっただろう。
だが、倭寇や水軍ほど結束の強い集まりではなかったので、残念とは思っても死ぬほど悲しみはしない。
彼は、、風のない静かな朝に池の畔で死んでいた。
木の枝で両耳の鼓膜を破り、短刀で、自分の顔をズタズタに引き裂いて。
「彼を死に至らしめたのは、悲しみじゃない……恐怖だ」
『くくっ……顔が変わっていったかよぅ。目が離れ口が大きくなったかのぅ。魚みたいに』
「琵琶の音も聞こえていたかもしれないな」
『耳を潰し、顔を刻み、それで死ねたから良いものの、もし生きながらえたら哀れよなぁ』
医学が今ほど進んでおらんで良かったのぅと鬼面は笑った。
もし現代の日本なら、すぐさま病院に連れて行かれ緊急手術を受け、一命をとりとめてしまった挙句、全て失ったまま傷だらけの顔で生きていかなければならないだろう。
『もしそうなったら、ぬしは何とする?』
「そうだな……」
湊は少し考え込み、やがて顔を上げてこう言った。
「あいつのマネでもするかな」
視線の先に、おたふくの面をかぶった人形が立っていた。
『おたふくワシじゃあ!一緒に帰るぞ!!』
鬼面が呼びかけるが、おたふくはまるでただのお面のように反応がない。
湊は素早くアサルトライフルを構え、人形に狙いを定め、無警告で発砲した。
“スパパパパパッ”
銃口から香ばしく炒った大豆が飛び出す。
人形は身体を直角に曲げて、それを避けた。
湊は豆アサルトの連射を続けるが、人形はぐにゃぐにゅと身体を複雑に折り曲げて全弾回避した。
かたちは人でも骨格はそうと限らないようだ。
前衛芸術のようになった人形は、指らしき部分を湊に向けて何事か囁いた。
『湊、下がれっ!!』
「えっ?」
“ドガアアアアアアアン”
湊の足元を起点に爆発が起こった。
爆風に温室のガラスは震え、巻き起こる土煙にひしゃげた豆アサルトライフルと弾倉(豆ぎっしり)がバラバラと落ちる。
人形は形を元に戻すと、くるりと背を向けた。
その背中に何か大きなモノが飛んできてぶつかる。
“バキッ”
湊のドロップキックだった。
人形は吹っ飛んで、バナナの木に激突して止まると、ぐるりと幹に巻き付いてするすると登って逃げた。
素早く立ち上がる湊の顔には、今まで頭に乗せているだけだった鬼面が被さっていた。
『さて、鬼ごっこをはじめるかの』
自由に動く身体を手に入れた鬼面は一跳びで、椰子の木の上に上がり、二跳びで人形を追う。
『いつもはワシが逃げ、おたふくが追うて来たが』
温室のガラスをなぞるように逃げる人形。
出口を探しているのだろう。
『捕まれば袋叩きだのタコ殴りだのヒドイ目に負うたが、それでも逃げるのをやめられんかった』
人形は温室をぐるぐる回る。
この温室そのものが袋小路である事が理解できないのだろう。
『幻よりも目まぐるしく変わる外の世界が見たい。自由に動く身体が欲しい。それに何より――』
爆発がガラスの上で立て続けに起こった。
しかし三堂姉弟の作った陣は完璧で、温室に傷一つ付けられない。
『なぁ、おたふくよ。情の深いお前はいつでも誰でも優しく笑いかける。じゃが、ワシが逃げた時だけは怒り狂って、まっすぐにワシを見る』
湊に意識があれば、おたふくさん、笑顔はデフォルトなんだけど。とツッコミをいれたかもしれないが。
鬼面はガラスを叩く人形の肩を掴んで、向い合せにした。
『ほれ、捕まえた。ワシの勝……グハッ!?』
血を吐く鬼面。
人形の手に柊の枝が握られていて、それががら空きになっていた湊の胴を薙ぎ払った。
柊は魔除けの力を持ち、その鋭く尖った葉は鬼面を依り坐ごとズタズタにする。
堪えきれず腹を押さえて膝をついた。
『……お…た……ふ』
膝と地面に血がボタボタと降りかかり、鬼面が外れてからりと落ちた。
その時だった。
鬼面が呼びかけるが、おたふくはまるでただのお面のように反応がない。
湊は素早くアサルトライフルを構え、人形に狙いを定め、無警告で発砲した。
“スパパパパパッ”
銃口から香ばしく炒った大豆が飛び出す。
人形は身体を直角に曲げて、それを避けた。
湊は豆アサルトの連射を続けるが、人形はぐにゃぐにゅと身体を複雑に折り曲げて全弾回避した。
かたちは人でも骨格はそうと限らないようだ。
前衛芸術のようになった人形は、指らしき部分を湊に向けて何事か囁いた。
『湊、下がれっ!!』
「えっ?」
“ドガアアアアアアアン”
湊の足元を起点に爆発が起こった。
爆風に温室のガラスは震え、巻き起こる土煙にひしゃげた豆アサルトライフルと弾倉(豆ぎっしり)がバラバラと落ちる。
人形は形を元に戻すと、くるりと背を向けた。
その背中に何か大きなモノが飛んできてぶつかる。
“バキッ”
湊のドロップキックだった。
人形は吹っ飛んで、バナナの木に激突して止まると、ぐるりと幹に巻き付いてするすると登って逃げた。
素早く立ち上がる湊の顔には、今まで頭に乗せているだけだった鬼面が被さっていた。
『さて、鬼ごっこをはじめるかの』
自由に動く身体を手に入れた鬼面は一跳びで、椰子の木の上に上がり、二跳びで人形を追う。
『いつもはワシが逃げ、おたふくが追うて来たが』
温室のガラスをなぞるように逃げる人形。
出口を探しているのだろう。
『捕まれば袋叩きだのタコ殴りだのヒドイ目に負うたが、それでも逃げるのをやめられんかった』
人形は温室をぐるぐる回る。
この温室そのものが袋小路である事が理解できないのだろう。
『幻よりも目まぐるしく変わる外の世界が見たい。自由に動く身体が欲しい。それに何より――』
爆発がガラスの上で立て続けに起こった。
しかし三堂姉弟の作った陣は完璧で、温室に傷一つ付けられない。
『なぁ、おたふくよ。情の深いお前はいつでも誰でも優しく笑いかける。じゃが、ワシが逃げた時だけは怒り狂って、まっすぐにワシを見る』
湊に意識があれば、おたふくさん、笑顔はデフォルトなんだけど。とツッコミをいれたかもしれないが。
鬼面はガラスを叩く人形の肩を掴んで、向い合せにした。
『ほれ、捕まえた。ワシの勝……グハッ!?』
血を吐く鬼面。
人形の手に柊の枝が握られていて、それががら空きになっていた湊の胴を薙ぎ払った。
柊は魔除けの力を持ち、その鋭く尖った葉は鬼面を依り坐ごとズタズタにする。
堪えきれず腹を押さえて膝をついた。
『……お…た……ふ』
膝と地面に血がボタボタと降りかかり、鬼面が外れてからりと落ちた。
その時だった。
「えいっ!」
人形の背後に突然、咲が現れて手にした木刀を人形に振り下ろした。
“ぽこっ”
あまりにも軽い音がして、おたふくの面が人形から外れて落ちた。
「最後まで油断するな。勝利に酔いしれた瞬間にこそ最大の隙が生じるってね」
油断も何も、咲は最初からこの瞬間を狙ってこの場所に埋伏していた。
『ひぃぃぃぃぃあぁぁぁぁぁ』
顔を失った人形が悲しげな鳴き声を上げ、輪郭がおぼろげになっていく。
その中心に線香花火の球のような赤く光る点が浮かび、それがみるみる膨れ上がる。
『いけない!自爆する気だよっ!』
咲に拾われて正気に戻ったおたふくが叫ぶ。
「湊さん起きて!鬼面を拾って!」
咲が呼びかけるが、鬼面に憑かれて消耗が激しかったのかぴくりとも動かない。
そうしてるうちに、起爆点は拳大の大きさになり、まばゆい光を放ち始める。
『爆発する―――――ッ!!』
「湊さんっ!汝窯の青磁の請求書ッ!!」
咲が叫んだ瞬間、湊の目がカッと見開かれ、バネ仕掛けのように鬼面を拾って立ち上がる。
そして咲はおたふくの面の内側を、湊は鬼面の内側を互いに向け。
“ガキーーーーーン!”
人形を間に挟んで、二つの面を合わせた。
人形は消え、内側で重い地響きのような音と振動がしたが、それもやがて消えた。
「……収まった?」
「みたいね」
元は一つの貝だった二つの面は、ぴったりと合わさっていたが、面の目や鼻や口からしゅうしゅうと金色に光る靄が噴き出した。
ゆらゆらと中空に漂う靄の中に、何処かの風景が見える。
碁盤の目のように整備された古の都市だった。
煌びやかな高楼が立ち並び、雅な貴人がそぞろ歩く。
「映画村?」
「京だわ……でも」
通りにはゴミがなければ物乞いもいない。
人々はみな優しく、満ち足りて幸せそうな笑みを浮かべていた。
「綺麗すぎて、現実味がまるでないわ」
『幻だからのう』
鬼面が言う。
苦しみも悲しみもない世界など、夢幻でしか許されない。
『善でも悪でもない、何者でもないモノは、美しい幻になるのが一番だよ』
おたふくが言う。
美しいという事は、善良であり邪悪でもあるのだから。
幻の都は、消え去る瞬間まで美しかった。
【終】
人形の背後に突然、咲が現れて手にした木刀を人形に振り下ろした。
“ぽこっ”
あまりにも軽い音がして、おたふくの面が人形から外れて落ちた。
「最後まで油断するな。勝利に酔いしれた瞬間にこそ最大の隙が生じるってね」
油断も何も、咲は最初からこの瞬間を狙ってこの場所に埋伏していた。
『ひぃぃぃぃぃあぁぁぁぁぁ』
顔を失った人形が悲しげな鳴き声を上げ、輪郭がおぼろげになっていく。
その中心に線香花火の球のような赤く光る点が浮かび、それがみるみる膨れ上がる。
『いけない!自爆する気だよっ!』
咲に拾われて正気に戻ったおたふくが叫ぶ。
「湊さん起きて!鬼面を拾って!」
咲が呼びかけるが、鬼面に憑かれて消耗が激しかったのかぴくりとも動かない。
そうしてるうちに、起爆点は拳大の大きさになり、まばゆい光を放ち始める。
『爆発する―――――ッ!!』
「湊さんっ!汝窯の青磁の請求書ッ!!」
咲が叫んだ瞬間、湊の目がカッと見開かれ、バネ仕掛けのように鬼面を拾って立ち上がる。
そして咲はおたふくの面の内側を、湊は鬼面の内側を互いに向け。
“ガキーーーーーン!”
人形を間に挟んで、二つの面を合わせた。
人形は消え、内側で重い地響きのような音と振動がしたが、それもやがて消えた。
「……収まった?」
「みたいね」
元は一つの貝だった二つの面は、ぴったりと合わさっていたが、面の目や鼻や口からしゅうしゅうと金色に光る靄が噴き出した。
ゆらゆらと中空に漂う靄の中に、何処かの風景が見える。
碁盤の目のように整備された古の都市だった。
煌びやかな高楼が立ち並び、雅な貴人がそぞろ歩く。
「映画村?」
「京だわ……でも」
通りにはゴミがなければ物乞いもいない。
人々はみな優しく、満ち足りて幸せそうな笑みを浮かべていた。
「綺麗すぎて、現実味がまるでないわ」
『幻だからのう』
鬼面が言う。
苦しみも悲しみもない世界など、夢幻でしか許されない。
『善でも悪でもない、何者でもないモノは、美しい幻になるのが一番だよ』
おたふくが言う。
美しいという事は、善良であり邪悪でもあるのだから。
幻の都は、消え去る瞬間まで美しかった。
【終】
というわけで、久しぶりの怖い話はキート⇔ゼトワール さんとの合作になりました。
キャッチボールの球を釘バットでフルスイングした感が否めません。
せっかく使用解禁になった、圭一さんのお姉さんが、腹黒策士なってしまいました。
時代劇なんか二度と書くかー!と思っていたのに、出来上がったのは小泉八雲とラヴクラフトを混ぜるな危険でした。
そして恒例のおまけ
後日、語部館。
二つの面は合わさったまま箱にしまわれる事になった。
「えー、桐の箱?二度とこんな騒ぎ起こさないように、三重の鉛の箱に重石つけて海に沈めたらいいのに」
せめてこれだけでもと、箱の上に漬物石を置こうとする湊。
『おい誰かこいつの暴虐を止めんかーーー!』
箱の中から鬼面の叫び声がするが、常連はみな生暖かい笑みを浮かべるばかり。
『あんたうるさいよ!』
おたふくの怒鳴り声と、バシッと何かひっぱたく音がした。
面が何をどうやって叩いているのか、とっても謎だ。
『いい加減におし。やや(赤ん坊)が起きちまうだろ』
『おぅ、すまんすまん』
「ちょっと待てーーーーー!?」
予想の右斜め上をいく発言に、湊は思わず箱をガタガタ揺さぶった。
『やめんか、やっと寝付いたんじゃぞ!』
「やっとって、そもそもいつどこで何がどうして!?」
『いつと言われても……その、あたしらいわゆるデキ婚だからねぇ』
恥ずかしそうなおたふくの声。
ちなみに生まれたのは、人形から解放されたその日の晩だったらしい。
「何だ、このわけのわからない敗北感と置き去りにされるような寂寥感は?」
それは小学校の同級生から『私たち結婚しました☆』と書かれた写真つきのハガキが来たときのやるせなさに似て。
がっくりと膝をついた湊の肩を、美珠がよくわからないままぽふぽふと叩いた。
「お面の子供って……」
見てもいいかと聞く圭一に、鬼面はきっぱり断った『箱入り娘だから』と。
この後、意外にも鬼面の脱走は激減した。
曰く『子育ては大変なんじゃ』との事。
それこそ逃げたくなる理由のように思えるが、顔に似合わず子煩悩だったようだ。
現実は、幻のように美しくはないけれど、想像の斜め上を行くものらしいですよ。
キャッチボールの球を釘バットでフルスイングした感が否めません。
せっかく使用解禁になった、圭一さんのお姉さんが、腹黒策士なってしまいました。
時代劇なんか二度と書くかー!と思っていたのに、出来上がったのは小泉八雲とラヴクラフトを混ぜるな危険でした。
そして恒例のおまけ
後日、語部館。
二つの面は合わさったまま箱にしまわれる事になった。
「えー、桐の箱?二度とこんな騒ぎ起こさないように、三重の鉛の箱に重石つけて海に沈めたらいいのに」
せめてこれだけでもと、箱の上に漬物石を置こうとする湊。
『おい誰かこいつの暴虐を止めんかーーー!』
箱の中から鬼面の叫び声がするが、常連はみな生暖かい笑みを浮かべるばかり。
『あんたうるさいよ!』
おたふくの怒鳴り声と、バシッと何かひっぱたく音がした。
面が何をどうやって叩いているのか、とっても謎だ。
『いい加減におし。やや(赤ん坊)が起きちまうだろ』
『おぅ、すまんすまん』
「ちょっと待てーーーーー!?」
予想の右斜め上をいく発言に、湊は思わず箱をガタガタ揺さぶった。
『やめんか、やっと寝付いたんじゃぞ!』
「やっとって、そもそもいつどこで何がどうして!?」
『いつと言われても……その、あたしらいわゆるデキ婚だからねぇ』
恥ずかしそうなおたふくの声。
ちなみに生まれたのは、人形から解放されたその日の晩だったらしい。
「何だ、このわけのわからない敗北感と置き去りにされるような寂寥感は?」
それは小学校の同級生から『私たち結婚しました☆』と書かれた写真つきのハガキが来たときのやるせなさに似て。
がっくりと膝をついた湊の肩を、美珠がよくわからないままぽふぽふと叩いた。
「お面の子供って……」
見てもいいかと聞く圭一に、鬼面はきっぱり断った『箱入り娘だから』と。
この後、意外にも鬼面の脱走は激減した。
曰く『子育ては大変なんじゃ』との事。
それこそ逃げたくなる理由のように思えるが、顔に似合わず子煩悩だったようだ。
現実は、幻のように美しくはないけれど、想像の斜め上を行くものらしいですよ。
二葉さん>好き嫌いの激しそうなネタを扱ったので、楽しんでもらえてよかったです。
今回は室町時代(戦国時代よりちょっと前、一休さんがいたあたり)を舞台にしました。
お面は、前篇『蜃』に登場した駆け落ちカップルをモデルに作られたと聞いたので、それってデキ婚やんという暴論に達してああなりました。
お面の子供は元の素材が貝なので、面の内側で最初は真珠の粒のようなものが出来て、それがピンポン玉大になったあたりで、次第に童子面の形になって、百年かけて美しい能面が出来上がると勝手に想像しています。
お面の入った箱からは時々、子供の笑い声がしたり、いつか嫁ぐ日を想像した鬼面の暑苦しい泣き声や、それをたしなめるおたふくの声がすればいいと思います。
今回は室町時代(戦国時代よりちょっと前、一休さんがいたあたり)を舞台にしました。
お面は、前篇『蜃』に登場した駆け落ちカップルをモデルに作られたと聞いたので、それってデキ婚やんという暴論に達してああなりました。
お面の子供は元の素材が貝なので、面の内側で最初は真珠の粒のようなものが出来て、それがピンポン玉大になったあたりで、次第に童子面の形になって、百年かけて美しい能面が出来上がると勝手に想像しています。
お面の入った箱からは時々、子供の笑い声がしたり、いつか嫁ぐ日を想像した鬼面の暑苦しい泣き声や、それをたしなめるおたふくの声がすればいいと思います。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
語部夜行 〜カタリベヤコウ〜 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
語部夜行 〜カタリベヤコウ〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 暮らしを楽しむ
- 77420人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 209455人
- 3位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19956人